
「ちゃんと育ててるはずなのに…」が、
頭から離れなかったあなたへ
毎日、がんばってる。
でもどこかで、
「それでも足りてないのかな」と自分を責めてしまう。
- 子どもが癇癪を起こしたり、
- 切り替えがうまくいかなかったり、
- 言葉のキャッチボールがちぐはぐだったり…。
そのたびに、
「私の関わり方が悪かったのかな」とココロがザワついてしまう。
でも本当は、
「うちの子、ちょっとだけ特別なのかも」という違和感を
ずっと感じてきました。
- 「ちゃんと知りたい」
- 「間違っていたくない」
──その想いは、あなたがどれだけ子どもを大切にしてきたかの証ですよね。
この記事を読んでくださっているあなたは、
もうすでに、向き合おうとしている人です。
この記事でわかる5つのこと
- 発達障害・グレーゾーンの子に見られる「日常のサイン」
- 「わがまま」や「甘え」と誤解されやすい行動の見極め方
- 医療・診断に頼る前に、親としてできる安心の土台づくり
- 「私のせいだったの?」という自責のループから抜け出すヒント
- 子どもの特性と、安心できる親子関係のつくり方
- 「これ以上、どうすればいいの?」
- 「誰かに頼りたいけど、甘えていると思われそうで怖い」
──そんな声を、胸の奥に押し込めてきましたよね。
あなたは、
自分を責めていたんじゃなくて、
ただ「本当の安心」を探していただけなんです。
発達特性のある子どもに向き合うことは、
- 教科書にも正解にも頼れない、
- 終わりのない試行錯誤。
でも、
そこに「安心できる視点」があれば、
あなたの中にあった力を、もう一度取り戻すことができます。
そんな想いで生まれたのが、
「発達障害・育てにくさに悩む私が、『母としての安心』を取り戻す|3週間集中再安心サポート」です。
このサポートは、
子どもを「どうにかしよう」と
無理に変えようとするものではありません。
むしろ、
「何が正しいか」よりも、
「あなたが何に傷ついてきたか」を丁寧に見つめていきます。
- 「怒らないようにしよう」と決めたはずなのに、
- 「うまく関わろう」と頑張っているはずなのに、
なぜか空回りしてしまう。
──そんなとき、問題は子どもではなく、
「安心して子どもと向き合える私」でいられないことにあるはずです。
この3週間のサポートでは、
これまで誰にも言えなかった
- 「不安」
- 「怖さ」
にやさしく向き合いながら、
「母親でいることが、つらくなくなる」感覚を取り戻していきます。
あなたの子育ての奥にある
「傷ついた母の気持ち」を抱きしめ、
もう一度、
子どもとの関係を「安心の土台」から築き直すための時間です。
誰かの評価ではなく、
「これが私の家族のかたち」と言える日々へ──。
それは、
子どもの未来を信じ直すための最初の一歩でもあります。
母としての安心を、自分の手で取り戻していく──
そのための3週間を、私たちは一緒に歩んでいきます。
監修者
株式会社Osaka-Child所属 児童精神科医
- 名前: 西山遥
- 出身地: 京都府
- 最終学歴: 京都大学医学部 精神科専攻
- 専門分野: 思春期精神医学、発達障害、小児うつ病
- 職歴: 大阪市立総合医療センター精神科(児童・思春期外来)勤務(12年)
専門分野について一言: 「『わからない』と感じる思春期のこころに、安心の手が届く社会を目指しています。」
監修者
株式会社Osaka-Child所属 臨床心理専攻大学教授
- 名前: 森本哲夫
- 出身地: 奈良県
- 最終学歴: 米国ハーバード大学心理学部 博士課程修了
- 専門分野: 臨床心理学、発達心理学
- 職歴: ハーバード大学研究員(5年)、大阪大学人間科学部教授
専門分野について一言: 「心の成長とは、自己理解の旅でもあります。その旅のお手伝いができれば幸いです。」
毎日が“これでいいのかな…”の連続だった私へ
「育て方が間違ってるのかも」
そんなふうに、毎日ずっと自分を責めてきた。
でも本当は、「何が正しいか」さえわからなかった。
病院に行くべき? 支援級を選ぶべき?
わからないまま、今日も不安に飲みこまれていく。
「発達障害・育てにくさに悩む私が、『母としての安心』を取り戻す──《3週間集中再安心サポート》」は、
誰にも相談できず孤立していた母親が、
「安心して子どもと向き合える自分」を取り戻すための個別サポートです。
こんな方におすすめです
- 育てにくさの正体がわからず、日々不安に押しつぶされそう
- 「診断されたら終わり」な気がして、病院にも行けずにいる
- 子どもの困りごとに怒ってしまい、寝顔を見て後悔してばかり
- 支援情報を調べすぎて混乱し、もう何を信じたらいいのかわからない
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 7月11日(金)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと1名様限定』
※銀行振込限定・先着順
そして──
「母としての安心」を土台に、
もう一度、「私としての人生」を取り戻したいあなたへ。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
「母でも妻でもなく、『私自身』をちゃんと生きたい」
その願いを、誰にも遠慮せず実現していく3週間。
誰かの期待に応える毎日は、もう終わり。
これからは、「私が選ぶ人生」を歩いていける。
- 子育てだけでなく、自分の人生も空っぽに感じる
- 夫にも、親にも、子どもにさえ「わかってもらえない」と感じている
- もう一度、ココロから笑える「自分」で生きていきたい
このプログラムでは、
「母としての安心」のその先にある「自分としての自由」を取り戻します。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
「ちゃんとしてるのに、苦しい」
「頑張ってるのに、うまくいかない」
——そんな違和感を抱えたまま、ずっと我慢していませんか?
LINEで3分セルフ診断ができます。
あなたの“今の感覚”の正体が、見えてきます。
子どもの「育てにくさ」から始まる──それは「親のせい」じゃない
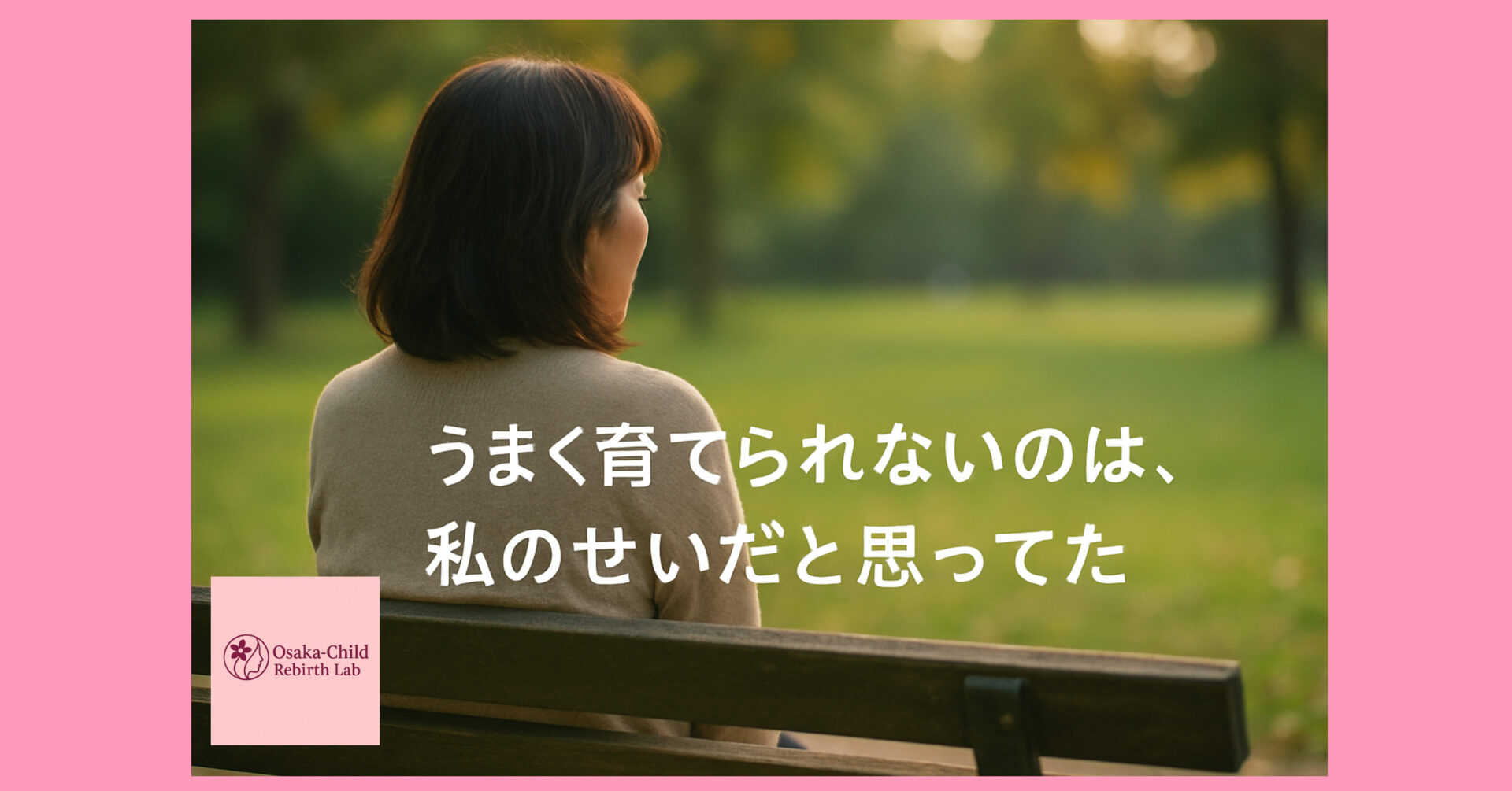
「うちの子、なんだか育てにくい気がする」
そう感じたとき、
真っ先に自分を責めてしまう母親はとても多いです。
でも、
それはあなたがちゃんと
子どもを見ようとしてきた証なんですよね。
ここではまず、
その「育てにくさ」の正体について、一緒に見ていきましょう。
「性格の問題」じゃなかった。育てにくさの正体とは?
- 「こんなに手がかかるの、うちだけ?」
- 「どうして言っても伝わらないんだろう」
そう感じながら、
ずっと頑張ってきましたよね。
まわりからは
- 「しつけが足りない」
- 「甘やかしてる」
と言われてきたのに、
あなただけは、
本当のしんどさにずっと向き合ってきた。
- 何度も注意しても同じことを繰り返す。
- スイッチが入ったように突然怒り出す。
こだわりや不器用さに、
どこか「かたさ」のような違和感がある。
それは、
性格ではなく「発達特性」という脳の傾向によるものです。
そしてこの特性は、
見えづらく、
周囲からも理解されにくいぶん、
母親が責められる構造があるという背景があります。
ここまで、
あなたはひとりで抱えてきました。
だからこそ次に、
「気づきが遅れる理由」に目を向けてみましょう。
「いい母親」ほど気づくのが遅れる理由
子どもの困りごとに気づくのは、
たいてい母親です。
でも、気づいたその直後に、
「自分のせいかもしれない」と否定してしまうことがよくあります。
- 「神経質すぎるのかも」
- 「周りの子もそうだし、もう少し様子を見よう」
- 「夫にも『気にしすぎだ』って言われたし」
そうやって、
「いい母親でいよう」とする人ほど、違和感にフタをしてしまいやすい。
でも本当はずっと、
ココロのどこかでわかっていました。
あのときの違和感は、ちゃんと意味のある感覚だったということ。
その感覚があるからこそ、
あなたは今この記事にたどり着いています。
次は、
「発達障害かも」と初めて感じたときに、どう向き合えばいいかをお伝えします。
初めて「発達障害かも」と感じたときに読む記事です
「発達障害」という言葉が頭をよぎったとき、
多くの母親がまず感じるのは
- 「不安」
- 「否定」
です。
- 「うちの子がそうだなんて、信じたくない」
- 「もし診断がついたら、なにかが決定的に変わってしまいそう」
- 「自分が受け止められるのか、自信がない…」
でも、いちばん大切なのは、
今あなたが「気づいている」ということです。
ポイント
診断や病名よりも、
「何かが違う」と感じてきたそのまなざしこそが、
子どもを守るための第一歩になります。
そして今はもう、ひとりで悩み続けなくていい時代です。
医療的な診断に進む前に、やさしく整理できる情報もあります。
- 「誰に相談すればいいの?」
- 「何を準備すればいいの?」
と迷っている方は、
以下の記事から、安心して始めてみてください。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「この子、発達障害かもしれない…」
そんな不安を感じたときに。
相談先や診断の流れを、専門家の視点からわかりやすく整理しました。
-

-
参考自分の子どもが発達障害では?と感じたときにすぐに行くべき相談先と診断内容とは
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 子どもの発達に関する不安や疑問は、親にとって深刻な課題です。発達障害の可能性を感じた ...
続きを見る
発達障害とは?|ASD・ADHD・DCD・学習障害の違いと共通点を知る
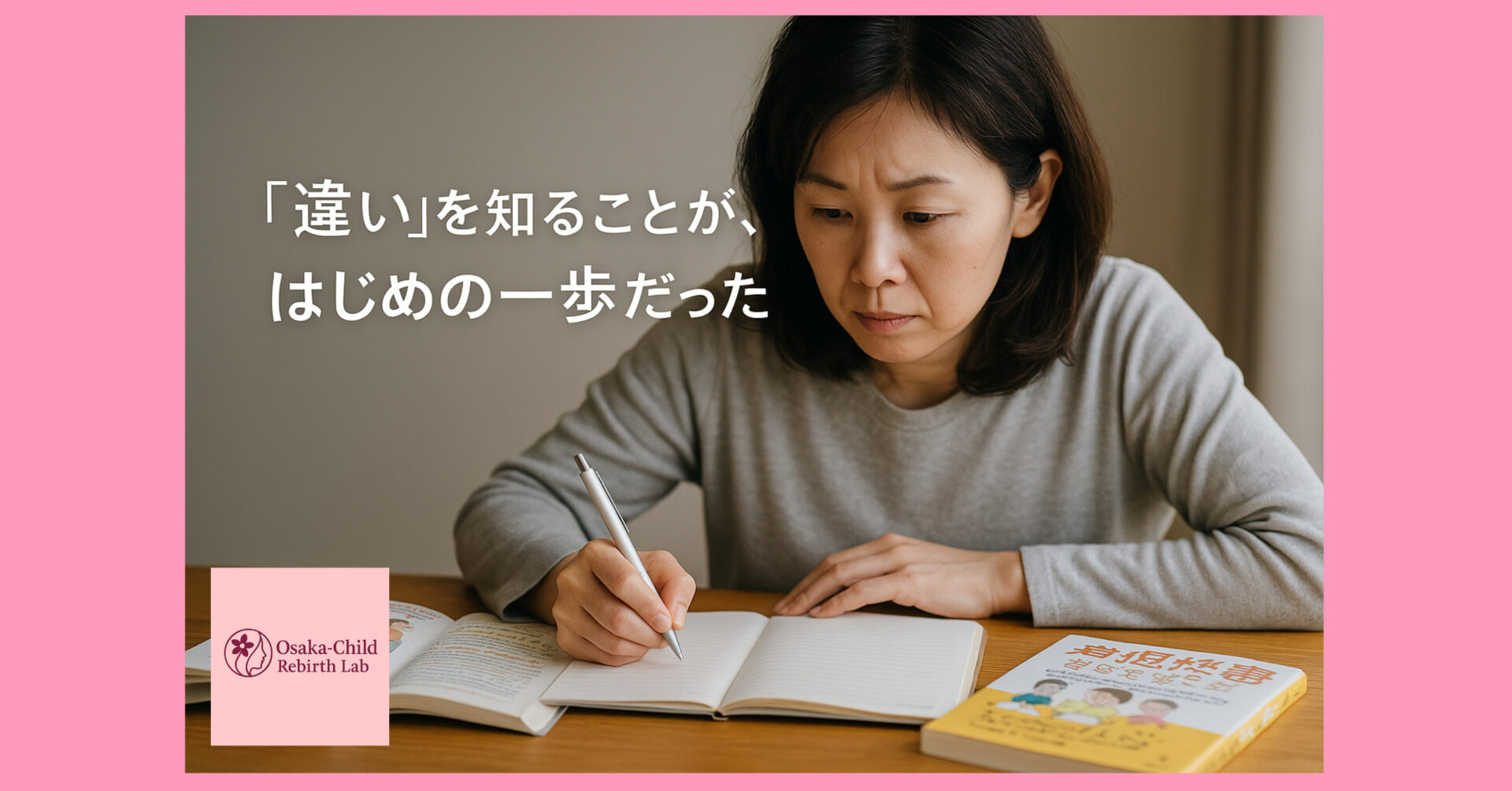
「発達障害」という言葉を聞いたとき、
- ASD
- ADHD
- DCD
- 学習障害…
いろんな略語が出てきて、
どれがどう違うのか、
わからなくなっていませんか?
- 「うちの子はどれにも当てはまらない気がする」
- 「全部がちょっとずつ当てはまる気もする…」
そんなふうに感じてしまうのも、無理はないんです。
このキャプションでは、
4つのタイプを母親目線でわかりやすく整理していきます。
ASD(自閉スペクトラム症)の特徴
ASDの子どもは、
「見た目には普通」だけど、なんだかズレている感じがすることが多いです。
- 一人遊びはずっと続けられるけど、集団に入ると混ざれない
- 言葉は話せるのに、気持ちのすれ違いが多い
- 急な予定変更やイレギュラーにパニックになってしまう
- 「自分ルール」が強くて柔軟に対応できない
最初は
- 「ちょっと頑固な子かな」
- 「マイペースなだけかな」
と思っていたけれど、
だんだんと
- 「関わりづらさ」
- 「言葉のキャッチボールのずれ」
に、疲れを感じるようになるんですよね。
でも、
ASDの子は
わざと反抗しているわけでも、無神経なわけでもないはずです。
ただ、
- 「どう伝えたらいいか」
- 「相手がどう感じるか」
が、つかみにくいだけなんです。
✅ [ASD・ADHD・DCDの違いを図解で解説(新設)]
次は、
反対に「エネルギーが外にあふれ出す」ように見えるADHDタイプを見ていきましょう。
ADHD(注意欠如・多動)の特徴と「性格との違い」
ADHDの子は、
とにかく目立ちやすい。
学校でも家庭でも、
- 「落ち着きがない」
- 「話を聞かない」
と言われがちです。
- 忘れ物が多く、集中が続かない
- 席にじっと座っていられない
- 相手の話にかぶせて話し出す
- 並ぶ、待つといった「順番」がとにかく苦手
ただ、
それは決して「わざとやっている」わけではありません。
脳の中の「ブレーキ」のかかりにくさが
あるというだけなんです。
でもそれが周りに理解されないと、
- 「だらしない」
- 「言うこと聞かない」
- 「育て方の問題」など
と決めつけられてしまう。
本人にとっては、
「気をつけてるつもりなのに止められない」という状態が、
何度も自信を失わせていく原因になります。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「怒っても全然変わらない…」
そんな子どもを前に、「性格の問題じゃなかったの?」と悩んだことはありませんか?
叱っても響かない理由と、関わり方のヒントを専門家がわかりやすく整理しています。
-

-
参考ADHDと「性格の違い」を誤解していた私へ|怒っても直らない本当の理由【児童精神科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「どうして何度言っても直らないの?」 「わざとやってるんじゃないかと思ってしまう」 ...
続きを見る
では次に、
「運動の不器用さ」に悩む子に関わるDCDの特徴を見ていきます。
これも
気づかれにくく、
誤解されやすいタイプです。
DCD(発達性協調運動障害)とは?|運動の不器用さの背景
DCDの子は、
見た目ではわかりません。
でも、
「手足がうまく使えない」ことが生活に影響している場面は、
じつはたくさんあるんです。
- 縄跳びやボール運動が極端に苦手
- 走ると左右のバランスが崩れやすい
- お箸、はさみ、鉛筆など道具の操作が難しい
- リュックの整理、服のたたみ方、ランドセルの荷物管理が混乱しやすい
こういった子に、
- 「不器用だなあ」
- 「ちゃんとやりなさい」
と言ってしまうと、
どんどんやる気を失い、
自分の身体への信頼感をなくしてしまうことがあります。
それは単なる練習不足ではなく、
脳と体の「連携のズレ」があるという背景があるからです。
少しでも当てはまると感じた方は、
以下のチェックリストで整理してみてください。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「うちの子、なんでこんなに不器用なんだろう…」
そんなふうに感じた経験がある方へ。
発達性協調運動障害(DCD)に関する具体的なチェック項目を、年齢別にわかりやすくまとめました。
-

-
参考乳幼児から大人まで発達障害協調運動障害(DCD )チェックリスト【小児科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 子どもの成長はなかなかカンタンにはいかず、一筋縄ではいかないものです。特に、ボールを ...
続きを見る
LD(学習障害)の特徴|読み書き・計算が「できない」のではなく「難しい」
無料診断|あなたの「ココロのパターン」を知る
「なぜか同じことで悩んでしまう…」
そんな方のために、LINEで「キーワード」を送るだけで診断できるサービスをご用意しました。
📩 LINEに「発達障害知りたい」と送ってください。
あなたに合った視点と診断のヒントをすぐにお届けします。
- 読みはできるのに、書くとなると極端に苦手。
- 漢字だけがどうしても覚えられない。
- 音読になると、たどたどしくなる──。
そんなわが子の様子に、
戸惑ったことはありませんか?
- 「やればできるはずなのに」
- 「ふざけてるだけ?」
──そう思ってしまったあとに、自分を責めた経験もあるはずです。
でも、
それは「やる気」や「努力」の問題じゃありません。
読み書きや計算が難しい、
という認知の特性があるという背景があります。
ポイント
LD(学習障害)は、
知的な遅れとは違って、
特定の分野だけに困難が現れやすい傾向です。
おそらく、
全体的な理解力や会話力はしっかりしているのに、
「なぜそこだけできないの?」と感じることがあったはずです。
大切なのは、
「ちゃんと教える」よりも、
「ちゃんと支える」という視点。
ひとつでも「できた!」と感じられる体験が、
子どもの中に安心と自信を育てていきます。
親が知っておくだけで変えられることは、
実はたくさんあります。
焦らなくて大丈夫。
あなたのその「気づき」が、
わが子にとって大きな味方になるはずです。
――今、できることを少しずつ整理してみませんか?
👉 「もしかしてLD?子どもの読み書き・計算の困難を見極めるチェックリスト【専門家監修】」
発達障害の「主な症状」と日常で出やすいサイン

無料診断|あなたの“心のパターン”を知る
「なぜか育てにくい」「特徴に当てはまる気がする」
そんなあなたへ。LINEで「キーワード」を送るだけで診断できるサービスをご用意しました。
📩 LINEに「発達障害知りたい」と入力して送ってください。
お子さんに必要な視点と、今できる対応のヒントが届きます。
「なんでうちの子は、こんなに大変なんだろう…」
そんなふうに感じながら、
日々必死に向き合ってきたあなたへ。
ポイント
発達障害の特性は、
医師の診断名よりも、
日常の「しんどさ」の中にこそヒントがあります。
それはテストでは測れないし、
病名だけでは見えてこないんですよね。
ここでは、
子育て中の母親が
「これって何かおかしい?」と感じやすい
「リアルなサイン」を3つの視点で整理します。
あなたがすでに気づいていた「違和感」に、
意味を与える時間になりますように。
言葉・切り替え・感覚の敏感さ|見逃しやすい初期サイン
- 「話しかけたのに返事がない」
- 「ちょっと予定が変わっただけで泣き出す」
- 「着替えのとき、タグが痛いと言って怒り出す」
こういう場面、ココロあたりがある方も多いと思います。
これは、
言葉の処理や感覚の受け取り方に特性がある子どもによく見られる反応です。
- 一度に複数の指示が入らない
- 音やにおいに対して強く反応する
- 「いつも通り」じゃないと混乱してしまう
こうした子どもは、
日常の刺激に対して「世界がちょっと強すぎる」状態で生きていると言えます。
だから、
私たちにはなんてことのない変化が、
その子にとっては「大事件」になることもあるんです。
あなたが「なんでこんなことで?」と困惑した場面こそ、
その子が「自分の感覚を守ろうとしている」合図だったのです。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「この行動、発達障害のサインだったの?」
そんな気づきを深めたい方へ。
言葉・感覚・行動面に表れる具体的な「症状」をわかりやすく整理しました。
-

-
参考発達障害の症状を40代母親に理解できるように分かりやすく解説|株式会社OsakaChild発達支援
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 子供の発達に関する不安や疑問は尽きません。特に40代の母親は、子供の行動や発達に対す ...
続きを見る
「ただのわがまま?」と誤解される行動
- 「また癇癪?」
- 「どうしてすぐ泣くの?」
──何度もそう思ってきたあなたは、
きっとそのたびに自分の対応を責めてしまったはずです。
でも実はそれ、
本人の「気持ちの整理の仕方」が周りと違っているだけなんです。
- 指示を出してもすぐ忘れる
- 自分の思い通りにならないと大声を出す
- 叱ったらパニックになって取り乱す
これらの行動は、
大人から見ると
「わがまま」に見えてしまうけれど、
内側では「混乱と不安」が渦巻いている状態なんです。
本人も、
「どうしたらいいかわからない」まま、
必死に自分を守っているんですよね。
あなたが何度も困った顔で見つめてきたその姿は、
SOSのサインを精一杯伝えている姿だったはずです。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「HSP?発達障害?どう違うの?」
そんな悩みを感じたときに。
感覚の鋭さ・こだわり・疲れやすさなど、似て見える特性の違いを整理しました。
-

-
参考HSPか発達障害かわからない…違い・共通点・選び方を整理して解説【精神科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「私ってHSPかもしれない」 そう思って調べていくうちに、 発達障害(ASDやADH ...
続きを見る
無気力・癇癪・極端なこだわりは「困りごと」のサイン
- 「何もやる気がない」
- 「すぐキレる」
- 「細かすぎて面倒くさい」
──そんなふうに感じてしまう瞬間、ありませんか?
でもその背景には、
「うまくやれない自分」を見せたくない葛藤が隠れています。
- 学校に行くのがしんどいのに理由が言えない
- 自分でも怒りたくないのに、感情が止められない
- 生活の中で「これだけは守りたい」というマイルールを手放せない
こうした行動の裏には、
自分を保つために必要な
- 「こだわり」
- 「防衛反応」
が根っこにあるという流れがあります。
本人も苦しんでいます。
でも、
その気持ちを説明する言葉を持っていないだけなんです。
だから、
- 大人に伝わらない。
- 否定されてしまう。
そうやって、
ますますココロを閉ざしていくという悪循環が起きてしまうんです。
「変わってほしい」と願う前に、
その子なりの「守り方」を理解することが、
回復のスタート地点になります。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「やる気がないだけ?」
そう見える「無気力」の裏に、発達障害によるエネルギー切れや自己否定が隠れていることもあります。
中学生のサインを、親がどう受け止めたらいいのか──
-

-
参考中学生の無気力、背後にある発達障害|発達グレーゾーン・診断つかないケースへの対応を解説【精神科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 中学生のお子さんが、最近なにもやる気を見せない。 声をかけても反応が薄くて、親のほう ...
続きを見る
診断・相談ってどうするの?|医療機関に行く前に知っておきたいこと

“診断の前に知ってほしい”安心の選択肢
「育てにくい」「もしかして発達障害?」
──そんな不安を抱えながら、ひとりで頑張り続けてきたあなたへ。
この3週間が、「母としての安心」を取り戻す第一歩になります。
発達障害・グレーゾーン・不登校傾向…
診断があってもなくても、「どう育てたらいいのかわからない」と悩む時間は、あなたの責任ではありません。
ひとりで抱え込まずに、「今できること」から一緒に整えていきませんか?
- 「病院に行ったほうがいいのかな…」
- 「でも、診断名がつくのは抵抗がある」
──そんなふうに感じながら、
ひとりで検索を繰り返している方、多いですよね。
子どもに「何かあるかも」と感じたとき、
多くのお母さんが悩むのが
- 「診断」
- 「相談」
の問題です。
でも実は、
診断よりも大切な
- 「選び方」
- 「視点」
があることを知るだけで、
ぐっと気持ちが整っていくんです。
ここでは、
診断にまつわる誤解や不安をやさしくほどきながら、
自分らしい関わり方と選択肢を取り戻すための知識を整理していきます。
診断がつく子・つかない子の違いとは
「この子は診断が必要なのか、それとも様子見でいいのか…」
そんな問いを、
ずっと胸の中で抱えてきた方もいるはずです。
発達障害の診断は、
実はとても「グレー」な側面があります。
- 小学校低学年までは判断がつきにくい
- 家では問題がなくても、学校では困りごとが出る
- 医師や施設によって診断の有無が分かれる
つまり、
- 「診断がつく=障害」
- 「つかない=正常」
といった白黒では測れないのが現実です。
大切なのは、
いまその子が「生活の中で何に困っているか」という視点です。
困りごとがあるなら、
たとえ診断名がつかなくても、
支援を受ける理由はじゅうぶんにあります。
あなたが気づいてきた違和感には、
ちゃんと意味があります。
その声を無視せずに、選択肢を広げていい。
診断は「目的」ではなく、「必要な支援を受けるためのツール」なんです。
✅新設記事④「グレーゾーンの子の特徴と支援」
焦らないで|誤診や過剰診断が起きる3つの理由
- 「間違った診断をされたらどうしよう」
- 「ほんとは違うのに、発達障害って言われたら…」
──そんな不安が、
「病院に行くなんて大げさかも…」と迷わせて、
受診をためらわせる大きな壁になってきたはずです。
実際、
現場では
- 「誤診」
- 「過剰診断」
が起こるケースもあるんです。
たとえば…
- 子どもの一時的な不調(不登校・生活リズムの乱れ)が、発達障害に「見えてしまう」
- 保護者の話だけで判断が進み、家庭環境などの背景が反映されない
- 「診断がつけば支援を受けやすくなる」仕組みによって、便宜的に診断がつく
こうしたケースでは、
診断名ばかりが一人歩きして、肝心の“関わり方”が置き去りになることがあります。
でも、あなたが戸惑っているのは当然のことです。
むしろ、慎重に選ぼうとしている姿勢が、お子さんにとっての安全基地になります。
大切なのは、
診断を受けるかどうかよりも、
日々の生活で
「どんな支援が必要か」を丁寧に見つめ直すこと。
焦らなくて大丈夫。
今の悩みは、
「親子で暮らしやすくなるヒント」の入り口なんです。
✅新設記事⑤「誤診が起きる背景」
相談先・診断の流れをわかりやすく解説
- 「じゃあ、どこに相談すればいいの?」
- 「何から始めたらいいのかわからない」
そんな状態のまま、立ち止まってしまっていませんか?
いきなり心療内科に行くのではなく、
もっと気軽に相談できる窓口が、
各自治体に用意されています。
たとえば…
- 地域の子ども家庭支援センター・発達支援センター
- 通っている保育園・学校の先生・スクールカウンセラー
- 子育て支援NPOや児童発達支援事業所
こうした窓口では、
「発達障害かどうか」だけでなく、
家庭や学校での困りごとにどう対応すればいいかを一緒に考えてもらえます。
一般的な流れとしては、
- 保育園や学校に相談
- 地域の支援センターでアセスメント
- 必要に応じて、専門医の紹介 or 連携
という順番になります。
相談=診断ではありません。
相談は
「生活のなかで必要な支援を見つけるための対話」であって、
あなたの味方を増やすプロセスでもあります。
いまの悩みを誰かと分かち合うこと。
それが、
あなたにとっても
子どもにとっても、
「家庭での第一歩」になる流れがあります。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「この子、発達障害かもしれない…」
そんな不安を感じたときに。
相談先や診断の流れを、専門家の視点からわかりやすく整理しました。
-

-
参考自分の子どもが発達障害では?と感じたときにすぐに行くべき相談先と診断内容とは
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 子どもの発達に関する不安や疑問は、親にとって深刻な課題です。発達障害の可能性を感じた ...
続きを見る
家庭でできること|子どもに「安心」を届ける関わり方

「“私のせい”って、もう思いたくなかった」
子どもに優しくしたいのに、
感情が爆発してしまう夜があった。
そのたびに、「私がダメなんだ」と自分を責めてきた。
- 「育てにくい」
- 「他の子と違う」
わかってるのに、ちゃんと受け止められなくて。
ずっと、自分が母親として失格のように感じていた。
「発達障害・育てにくさに悩む私が、『母としての安心』を取り戻す──《3週間集中再安心サポート》」は、
自分を責め続けてきたお母さんに、
「安心して子育てできる私」を取り戻してもらう3週間。
子どもの困りごとだけじゃなく、
「母である自分自身」のケアからはじめていきます。
こんな方におすすめです
- 子どもにイライラして怒ったあと、自己嫌悪が消えない
- 支援や療育のことを調べすぎて、余計に混乱している
- 病院に行くのはためらっていて、もっとやさしい支援を探している
- 子どものことを誰にも相談できず、孤独を感じている
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 7月11日(金)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと1名様限定』
※銀行振込限定・先着順
そして──
「私が悪いんじゃなかった」って、
ちゃんと自分を抱きしめられるようになったあなたへ。
次は、「母としての人生」を超えて、
「ひとりの私」としての未来を歩き出す番です。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
誰かのためではなく、自分の人生を取り戻す3週間。
ずっと後回しにしてきた「本当の私」に、
今こそ手を伸ばしてあげてください。
- 「母としての役割」ばかりを演じてきた
- 本当はもっと自分の人生を生きたかった
- これからの人生を、「私のために」立て直したい
「母である私」も、「私という人間」も、
どちらも愛して生き直す準備はできていますか?
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
- 「何をしても怒られる」
- 「ここにいると苦しい」
──子どもがそう感じてしまう家庭に、安心は育ちません。
でもきっと、
あなたも日々悩んできました。
- 叱りたくないのに叱ってしまったり、
- 「どうしてこんなに手がかかるの?」と落ち込んだり。
「安心させたい」と思っても、
どうしていいかわからなくなる日もありましたよね。
ここでは、
そんなあなたのために、
家庭のなかで今すぐできることを3つの視点で整理します。
「完璧な母親」じゃなくていい。
ただ、子どもにとっての「戻れる場所」であること。
そこから、すべては変わっていきます。
やってはいけない対応|子どもを追い詰める言葉
- 「もう何回言ったの?」
- 「甘えてるだけでしょ?」
──こう言ってしまったあと、自分を責めた経験がある方もいるはずです。
でも、責めることが目的ではありません。
ここで伝えたいのは、
「その言葉が届かない理由がある」ということです。
発達障害やグレーゾーンの子どもにとっては、
「正す言葉」よりも
「理解しようとする言葉」のほうが、
圧倒的に届きやすい構造があります。
たとえば、
- 「どうしてできないの?」→「どこで困ったのか、一緒に考えよう」
- 「さっきも言ったよね?」→「わかりづらかったら、言い方を変えるね」
このように伝え方を変えるだけで、
子どもの「自己否定」がぐっと減っていく流れがあります。
子どもは、
「怒られなかった日」よりも、
「理解されようとした日」をちゃんと覚えています。
そしてその積み重ねが、
「この家は私を守ってくれる場所」という感覚に変わっていきます。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「どんな接し方をすればいいの?」
そんなふうに悩んでいる40代母親の方へ。
日常で無意識にやってしまいがちな「NGな関わり方」とその改善法を、専門家監修でわかりやすく解説しています。
👉 子どもとの関わりでやってはいけない4つのことをチェックする
-

-
参考40代母親の発達障害の子どもを生きやすくする生き方で4つのやってはいけないこと【小児科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 多くの40代の母親にとって、発達障害を持つ子どもとの生活は日々の喜びであると同時に、 ...
続きを見る
「運動」が脳とココロに効く理由とは?
「落ち着かないから、運動は逆効果じゃないの?」
──そう思われている方も多いかもしれません。
でも実は、
「動くこと」そのものが、
発達特性のある子どものココロと脳を整える支援になるといわれています。
理由はシンプルで、
運動によって「セロトニン」などの神経伝達物質が分泌されるから。
これらは、
- 情緒の安定
- 集中力の維持
- 自己コントロール力の向上
に深く関わっています。
特に効果的なのは…
- ブランコや鉄棒などの「リズムある動き」
- トランポリンやスクーターなどの「全身運動」
- 自然のなかを走る・転がる・登るといった「自由な身体活動」
こうした運動を通じて、
脳の神経ネットワークが育ち、感情のコントロールがしやすくなる流れがあります。
「静かにさせる」ではなく、
「動いて調整する」という視点に変えるだけで、
親子の関係にも余白が生まれていきます。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「落ち着きがないから、運動は逆効果だと思ってた…」
そんなふうに感じていた方へ。
実は「運動」こそ、発達障害のある子どもの脳を育てるサポートになります。
👉 落ち着き・集中力・感情の安定に。家庭でできる運動の取り入れ方
-

-
参考発達障害の子どもの運動すると脳の育ちに良い作用を生む理由【40代母親対象 専門小児科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 多くの40代の母親たちが直面する一つの疑問は、発達障害のある子どもたちにとって、運動 ...
続きを見る
家庭内でできる「感覚の安心」の工夫
- 「服のタグを嫌がる」
- 「音が気になって外に出られない」
──こうした反応は、
「過敏な子どものこだわり」と誤解されやすいですが、
実際には感覚調整がうまくいっていないサインです。
発達特性のある子どもは、
音・におい・手ざわりなどの「感覚刺激」にとても敏感で、
それだけでストレスを感じやすい構造があります。
だからこそ、
家庭では「感覚をゆるめられる空間」が必要です。
たとえば、
- 着心地のいい素材の服を用意する
- 照明や音の刺激を落とす
- 自分だけの「こもれるスペース」をつくる(押し入れ・テントなどもOK)
こうした環境を整えるだけで、
子ども自身が
「ここでは安心してもいい」と身体で覚えていく流れがあります。
感覚が整うと、
気持ちも自然と落ち着いていきます。
それが家庭の中でしかできない、
「感覚からの安心」というケアなんですよね。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「運動が苦手で不器用すぎるのは、うちの子だけ…?」
そんなふうに感じたことがある方へ。
年長〜小学生の「発達性協調運動障害(DCD)」に気づき、支えるための視点をわかりやすく解説しています。
-

-
参考40代母親の年長の子どもの発達障害である発達障害協調運動障害(DCD)の運動スキルの伸ばし方【小児科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 極端な不器用さで日常生活にうまくいかない子どもたちがいます。これは、発達障害協調運動 ...
続きを見る
子どもの発達障害と「成長に合わせた支援」の考え方

子どもの“これから”を支えるのは、母親の“今の安心”です
「療育や支援って、いつ・なにをすればいいの?」
そんな迷いがある方にこそ、今すぐ始められる「母の安心サポート」を届けたい。
成長とともに特性が変化するからこそ、
「今、どんなまなざしで子どもと向き合うか」がカギになります。
焦らず、比べず、あなた自身が安心できる土台をつくりませんか?
- 「このまま変わらなかったら…」
- 「大人になって困るようになったら…」
──そんな不安を、ずっと抱えてきた方もいるはずです。
でも、安心してほしいんです。
発達特性は「固定された障害」ではなく、
「時間と経験と支援によって変化していくもの」です。
そして、
子どもが育つにつれて、
その時々で「必要な支え方」も、
変わっていくものなんですよね。
だからこそ、
今の状態だけを切り取って
「未来」を決めつけなくて大丈夫です。
このキャプションでは、
成長に合わせた支援の考え方と、
年齢ごとの親の関わり方のヒントを、
3つの視点からお伝えします。
ライフステージで支援の形は変わる
「療育は終わったけど、これから何をしたらいいの?」
──そんなふうに感じたこと、ありませんか?
発達特性を持つ子どもは、
年齢が上がるたびに
「困りごとの出方」も変わっていきます。
たとえば:
- 幼児期は「感覚の過敏さ」「生活習慣の安定化」が中心
- 小学校期は「集団への適応」「言葉の理解力の差」が課題に
- 中高生になると「自己肯定感」「進路選択」など心のテーマが浮上してくる
このように、
年齢とともに必要な支援は
「切り替わっていく」という構造があります。
だからこそ、
今の支援が終わった=問題解決、ではなく、
「次のステージに必要な視点は何か」を親が知っておくことが、
何よりのサポートになります。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「この子にとって、どんなサポートが最適なんだろう…?」
そんな悩みを持つお母さんへ。
年齢や発達段階に合わせた「その子らしい支援のヒント」をお届けします。
-

-
参考発達障害の子どもの人生をライフステージから考えた個人に合った最適な支援方法
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 子どもの発達障害に関する課題に直面したことがありますか? 適切な支援方法を見つけるこ ...
続きを見る
親子のすれ違いが起きやすい思春期の接し方
思春期になると、
- あんなに甘えていた我が子が急にそっけなくなったり、
- 「もうほっといて」と言ってきたり。
戸惑いますよね。
でも実はそれ、
親との関係を切るためではなく、
「守ろうとしている」行動である場合が多いんです。
発達特性のある思春期の子どもは、
- 自分の弱さを見られたくない
- 周囲と比べて劣等感を抱えやすい
- 頼りたいのに、うまく言えない
──そういった複雑な感情を、
- 「拒否」
- 「反発」
という形でしか表現できない時期が
あるという背景があります。
だからこそ大切なのは、
正論で押し返すのではなく、
「いつでも味方だよ」と態度で示し続けることです。
言葉がなくても、背中で伝わるものがある。
「距離をとらせてあげる」こともまた、
立派な支援のひとつです。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「思春期に入ってから、なんだかうまく関われない…」
そんな戸惑いを感じているお母さんへ。
反抗・無気力・親子のすれ違いを乗り越えるヒントを、思春期支援の視点からお届けします。
-

-
参考発達障害の思春期の子どもへの最適対応とは|親子関係に起こりやすいすれ違いを解く
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 思春期の発達障害を抱える子どもとの親子関係は、しばしば理解とコミュニケーションに課題 ...
続きを見る
中学生・女子の特徴と「親の支援の形」
女の子は
「きちんとして見える」ことが
多いですよね。
学校でも家でも大人しくて、
周りに合わせて、
がんばっている。
でもその「ちゃんとした姿」の奥で、
ものすごくがんばって疲れていることがよくあります。
中学生女子の発達特性は、
以下のように現れやすい特徴があります:
- 外では問題なく過ごすのに、家で情緒が崩れる
- 言葉にできないまま、体調不良や無気力で現れる
- 周囲に合わせすぎて、感情が麻痺してしまう
つまり、
「困っていることが外に見えにくい」という構造があるんです。
だからこそ親にできるのは、
「何があったの?」と問い詰めることではなく、
「何も言わなくても見ているよ」という存在であり続けること。
言葉よりも、温度で伝わる関わり。
それが、
中学生女子にとっての「信じられる支援」になります。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「思春期に入った娘との関わりが、なんだか難しい…」
そう感じるお母さんへ。
中学生女子ならではの発達特性や感情表現を踏まえた、専門家監修の関わり方ガイドをご紹介します。
-

-
参考発達障害を持つ中学生女子の特徴を医師監修で解説|最適な関わり・療育を知ろう
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 中学生の女子が発達障害を抱える場合、その特徴やニーズを理解し、最適な関わりや療育を提 ...
続きを見る
研究と環境から考える|発達障害の「原因」と可能性

「なぜこの子に、こんな生きづらさがあるの?」
──そんなふうに、ココロの奥でずっと問いかけてきたお母さんもいるはずです。
けれども、
いま世界中の研究でわかってきたのは、
発達障害の「原因」は一つではなく、
- 脳
- ホルモン
- 環境など
が複雑に影響し合っているということです。
同時に、
「何が悪かったのか」を探すよりも、
「今、何ができるか」を見つけた家庭のほうが、
子どもの変化が早く訪れているという事実も
はっきりしています。
ここでは、
科学・環境・そして親のまなざしという3つの視点から、
未来につながる「理解」と「希望」のヒントをお伝えしていきます。
オキシトシンは治療になる?最新研究からの示唆
「オキシトシン」という言葉を
聞いたことはありますか?
別名「愛情ホルモン」と呼ばれるこの物質は、
近年、
発達障害と深く関係することが研究で明らかになってきています。
たとえば、オキシトシンには…
- 不安をやわらげ、安心感を与える
- 相手の表情や気持ちを読み取る力を高める
- 対人場面での過覚醒を抑える
という働きがあることが報告されています。
ASD(自閉スペクトラム症)の子どもを対象とした複数の研究では、
オキシトシンの投与によって、
表情認知や共感性が改善された例も確認されています。
しかし、
それ以上に注目されているのが、
「家庭や人とのつながりの中でオキシトシンが自然に分泌される環境」が、
- 子どもの神経
- 情緒の安定
を助けているという報告です。
つまり、
- 「愛されている」
- 「安心してここにいていい」
と感じられる日常こそが、
脳の働きを整えていく支援になるという視点が
強調されているのです。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「薬や療育だけじゃ、限界がある気がして…」
そんな思いを抱えている方へ。
発達障害の新たな可能性として注目される「オキシトシン」について、最新の研究と専門家監修の視点からご紹介します。
👉 親として「できること」を知るために読んでおきたい内容です
-

-
参考発達障害治療に朗報!オキシトシンの効果とは?最新研究からの示唆
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 発達障害の子を持つ母親たちにとって、新しい治療法や支援方法の情報は待ち望んだ光となる ...
続きを見る
農薬・ネオニコチノイドとの関連はあるのか?
近年、
発達障害の背景に
「環境因子」が影響しているという研究も
進んでいます。
その中でも注目されているのが、
ネオニコチノイド系農薬や化学物質と子どもの神経発達への影響です。
国内外の複数の報告では、
- 胎児期・乳児期に農薬にさらされることで、脳神経の発達が阻害される
- 感覚過敏や注意力のばらつき、感情の不安定さが強まりやすくなる
という指摘があり、
特に脳の発達が活発な時期にはリスクが高くなるという流れがあります。
もちろん、
これらの物質が
「直接の原因」という単純な話ではありません。
ただ確実に言えるのは、
子どもの神経系は、
私たちの暮らしにある「見えない刺激」の影響を受けているということです。
だからこそ家庭では、
- 添加物や香料を避けた生活用品に変える
- 有機・無農薬の食材を選んでみる
- 自然の中で五感をひらく時間を増やす
──そうしたちいさな工夫が、
「感覚のストレス」を減らすことで、
子ども自身が落ち着きやすい状態に近づいていきます。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「まさか農薬が原因だったなんて…」
そんな驚きを感じた方へ。
発達障害とネオニコチノイド系農薬の関係を、小児科医監修でわかりやすく解説しています。
-

-
参考40代母親の子どもにみられる発達障害の決定的な原因は農薬にふくまれるネオニコチノイド【小児科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 多くの40代の母親たちは、子どもたちの脳や身体を自然に発達させたいと思い、安全な食生 ...
続きを見る
「原因」を追うより、「できること」に目を向けよう
「何が悪かったの?」と
自分を責め続けてしまう。
そんな声を、私たちは本当によく聞きます。
でも、はっきり言えることがあります。
「原因」を特定することと、
「子どもを支えること」は別の道筋にあるということです。
発達障害は、
「生まれつきの脳の特性」だとよく言われます。
けれど
それは、
「変わらない」という意味ではありません。
- 子どもが安心できる人間関係の中にいる
- 周囲から「否定されない経験」を積み重ねていく
- 「できないこと」ではなく、「できる形」に切り替えていく
──このような関わりによって、
発達特性の現れ方は、
環境やサポートの質によって大きく変わっていきます。
だからこそ、
もう原因探しにココロを使わなくていいんです。
「今の子ども」を、まるごと受け取ってあげること。
それが、この子の未来をひらくもっとも確かな一歩であり、
何よりもあなた自身を、ゆるめてくれます。
“診断の前に知ってほしい”安心の選択肢
「育てにくい」「もしかして発達障害?」
──そんな不安を抱えながら、ひとりで頑張り続けてきたあなたへ。
この3週間が、「母としての安心」を取り戻す第一歩になります。
発達障害・グレーゾーン・不登校傾向…
診断があってもなくても、「どう育てたらいいのかわからない」と悩む時間は、あなたの責任ではありません。
ひとりで抱え込まずに、「今できること」から一緒に整えていきませんか?
「ひとりで抱え込まない」ために──再安心プログラムのご案内

ここまで読み進めてくださったあなたは、
ずっと、
「私のせいなのかな」と
ココロのどこかで抱えながらも、
毎日、子どもの目をちゃんと見て向き合ってきたあなたです。
でも──
どれだけ情報を調べても、
誰に相談しても、
「じゃあ私はどうしたらいいの?」という答えだけが、
見つからなかった。
それは、
あなたが「逃げずに向き合ってきた証」です。
ただ
「育てにくい」だけじゃない、
「関係のしんどさ」そのものにちゃんと気づいてきましたよね。
この章では、
そんなあなたの
「つながりたいのに、うまくいかない」をほどいていく、
3週間の実践サポートをご案内します。
診断があってもなくても「育てにくさ」は確かにある
- 「発達障害かはわからないけど、なんだか育てにくい」
- 「でも、病院に行くほどじゃないのかもしれない」
──そんなふうに迷いながら、
ずっと子どものためにがんばってきたんですよね。
でも世の中には、
- 「診断がついたら支援を」
- 「グレーなら様子見」
といった「枠の中でしか考えられない」空気があります。
けれど本当は、
診断の有無よりも「親子のつながりの痛み」に光を当てるほうが大切です。
- 朝の支度で毎日イライラしてしまう
- 注意しても聞いてくれないことに、何度も傷ついてきた
- 何が正解かわからないまま、ずっとひとりで悩んできた
そんな日々には、
あなたなりの気づきと努力が積み重なっています。
- 「わがまま」
- 「しつけの問題」
では片づけられない背景が、そこにはあるんです。
「母親のまなざし」を取り戻す3週間サポート
気づけば、
「うまく育てる」ことばかりに気を取られていた。
でも本当は、
ただ「安心して見守れる関係」をつくりたかっただけ。
- 他の子と比べて落ち込む
- 周囲に理解されず、わかってもらえない孤独
- 子どもにイライラして、寝顔を見て後悔する夜
そんな日々を、
あなたはひとりで越えてきたはずです。
この3週間サポートは、
子どもにどう接するかだけではなく、
あなた自身の「安心の起点」を取り戻していくためのプログラムです。
- 「怒らないようにする」でもなく、
- 「ちゃんと育てる」でもなく、
「子どもと並んでいられる私」に戻っていくための時間です。
発達障害・育てにくさに悩む私が、「母としての安心」を取り戻す|3週間集中再安心サポート
「この子、発達障害なのかもしれない…」
でも、
病院に行っても何が正解なのかよくわからない。
かといって、
支援機関に相談しても、
マニュアル的な対応で余計に傷ついた──
そんな経験はありませんか?
この《3週間集中再安心サポート》は、
「診断名よりも、まず『母親自身の安心』を取り戻すこと」
に重きをおいた、家庭向けの心理サポートです。
【母親が変わると、子どもも変わる──その理由】
子どもの育てにくさには、
脳や感覚の特性が大きく関わっています。
でも、それと同じくらい大切なのが、
「母親の安心感」が「日常の関わり」にどう現れているかです。
たとえば──
- 子どもが怒って暴れたとき、あなたの呼吸は速くなっていませんか?
- 思い通りに動けないわが子を見て、「どうして…」と焦っていませんか?
- 「この子の将来どうなるんだろう」と、眠れない夜を過ごしていませんか?
この「見えない不安」は、
子どもにとって
- 「空気」
- 「刺激」
として伝わり、
余計に落ち着きを失わせていることがあるのです。
【この3週間で取り組むこと】
このサポートでは、
「子どもの特性理解 × 母親自身の安心回復」
を同時に進めていきます。
ステップ①|子どもの「行動の意味」を知る
- わがまま
- 反抗
- 癇癪…
その裏にある「困りごとのサイン」を一緒に読み解いていきます
「そういうことだったんだ」と気づけるだけで、
関わり方はガラッと変わっていきます。
ステップ②|「私の関わり」に優しさを取り戻す
- 「つい怒ってしまう」
- 「距離を置きたくなる」
…そんな反応にも理由があります。
過去の体験や「無意識のココロのクセ」を見つめ直し、
自分を責めずに接するための「余白」を育てていきます。
ステップ③|家庭のなかに「安心の土台」を作る
母親の呼吸が深くなると、
子どもの脳も落ち着きやすくなります。
具体的な関わり(声かけ・距離感・選択肢の渡し方など)を
実践形式でサポートしながら、
「家の中の空気」ごと変えていきます。
[/st-mybox]
【子どもに起きてくる変化】
サポートを受けた方の多くが、こんな変化を実感しています:
- 母親が落ち着いて対応できるようになると、子どもの癇癪が減っていった
- 勉強や登校しぶりがあっても、責めずに対応できるようになった
- 子どもが「話してもいいんだ」と感じて、自然に気持ちを話すようになった
- 「イライラしない私」に戻れたことで、自分にも自信が持てるようになった
【「安心」は、あなたから始まる】
- どんなに育てにくい子でも、
- どんなに他人に理解されなくても、
あなたが「私はちゃんと見ているよ」と伝えられたら、
子どもは確実に、あなたの「安心」に反応してくれます。
この3週間は、
「母親としてうまくやる」ためではなく、
「母親である私自身を整える」ための時間です。
“診断の前に知ってほしい”安心の選択肢
「育てにくい」「もしかして発達障害?」──そんな不安を抱えながら、ひとりで頑張り続けてきたあなたへ。
この3週間が、“母としての安心”を取り戻す第一歩になります。
発達障害・グレーゾーン・不登校傾向…
診断があってもなくても、「どう育てたらいいのかわからない」と悩む時間は、あなたの責任ではありません。
ひとりで抱え込まずに、“今できること”から一緒に整えていきませんか?
まとめ|「私が間違ってたわけじゃなかった」と思える場所へ
子どもを育てるって、
こんなにも苦しいことなんだなって──
気づいたときにはもう、
あなたは何年もずっとひとりで踏ん張ってきたんですよね。
- 「育てにくい」
- 「わかってあげられてないのかも」
そんなモヤモヤを抱えながらも、
どうにか日常をまわしてきた毎日。
誰かに話しても「気にしすぎじゃない?」なんて返されると、
それ以上は言えなくなってしまう。
でも本当はずっと、
「わかってほしかった」はずです。
うまく言えないけど、
「うちの子、何かが違う気がする」
──その感覚は、おそらくずっと前からあったんだと思います。
今回の内容のまとめ
- 発達障害かどうか以前に、「育てにくさ」はたしかに存在している
- 「診断がないと支援できない」わけではない
- 子どもの行動には、本人なりの「困りごと」が隠れている
- 「わがまま」や「甘え」と片づけられる行動にも、理由がある
- いちばんつらいのは、「誰にもわかってもらえないこと」
あなたの子育ては、間違ってなんかいません。
ただ、「わかりあえる場所」がなかっただけなんです。
病院に行く勇気はまだ出なくても、
いま、できることはあるはずです。
まずは、あなた自身が「安心できる時間」を持つこと。
それが、これからの選択に向き合う力になります。
「発達障害・育てにくさに悩む私が、『母としての安心』を取り戻す|3週間集中再安心サポート」を
ご用意しました。
この3週間で目指すのは、
- 「怒る前に気づける私」
- 「この子らしさを受けとめられる私」
への変化。
何から始めたらいいかわからない毎日から、
「わかってあげられる私」に戻っていくプロセスを、一緒に歩んでいきます。
「子育てが、こんなに孤独になるなんて思わなかった」
「気にしすぎじゃない?」
誰かにそう言われるたびに、
自分の感覚を信じられなくなっていった。
あの子の「育てにくさ」は、私のせいなの?
どれだけ考えても答えは出なくて、
誰にも頼れないまま、時間だけが過ぎていった。
でも──
それは「あなたが悪い」からではなく、
「支援につながっていないだけ」だったのです。
「発達障害・育てにくさに悩む私が、『母としての安心』を取り戻す|3週間集中再安心サポート」は、
病院でもなく、ママ友でもなく、
「母親の孤独に寄り添う」専門家が並走する3週間。
どんな気持ちも否定されない環境で、
あなたの中にある「母としての直感」をもう一度取り戻していく。
「答えがわからない子育て」を、たったひとりで抱え込まなくていいんです。
こんな方におすすめです
- 子どもがHSP・発達グレーかもと感じている
- でも病院に行くのはまだ早い気がしている
- 「育て方が悪い」と責められてきた
- パートナーにも理解されず、誰にも相談できない
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 7月11日(金)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと1名様限定』
※銀行振込限定・先着順
ネットバンキングのご利用で、今すぐ開始することが可能です。
そして──
子どもとの関係に、「希望の手ごたえ」を感じはじめたあなたへ。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
母として、ひとりの女性として、
「これからの人生をどう生きたいか」に向き合う3週間。
- 「子どものために生きること」に限界を感じている
- 自分自身の「ココロの満たされなさ」に気づきはじめた
- これからは「私の人生」をちゃんと歩いていきたい
子どもと向き合ったその先に、
「私自身とつながり直す」時間が待っています。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
無料LINE診断|今のあなたに必要なサポートは?
あなたが悪かったわけじゃありません。
ただ、「必要なサポート」にまだ出会っていなかっただけです。
📩 今すぐLINEで【 4 】と入力してみてください。
あなたの子育てに合ったサポートをお届けします。
株式会社OsakaChildの発達障害が簡単にわかる関連記事
発達障害とは?種類、症状、進路選択そして不登校復学支援の大切さ
不登校と発達障害の両方を抱える子どもたちへの支援策:個別のニーズに合わせたアプローチ
発達障害・グレーゾーンの子どもが不登校に|40代母親が知っておく原因、対応策、そして未来への道筋
中学生の発達障害を理解して40代母親の育てにくさ克服!勉強の遅れの最適な対応解説
中学生の発達障害の特徴とは?40代母親が子どもに合わせた最適な関わり方を理解できる
中学生の無気力、背後にある発達障害|40代母親が知るべきポイントと対策
発達障害を持つ中学生女子の特徴を医師監修で解説|最適な関わり・療育を知ろう
発達障害の思春期の子どもへの最適対応とは|親子関係に起こりやすいすれ違いを解く
発達障害の思春期の子どもへの最適対応とは|親子関係に起こりやすいすれ違いを解く
発達障害の子どもの運動すると脳の育ちに良い作用を生む理由【40代母親対象 専門小児科医監修】
発達障害を抱える女性の年齢別特徴とは|各年代で起こる生きづらさと解決法を解説
子どもの発達障害の年代別特徴を解説|乳児期・就学期・思春期に分けて考える
発達障害の中学生への復学につながる最適な学校対応とは|「合理的配慮」と現実的療育の解説
▶︎ 株式会社Osaka-Childの母親・子ども支援まとめを見る(心理・不登校・身体調整など・左の▼をクリック)
株式会社Osaka-Childの3人の子育てでストレスがたかい40代女性の心理作用をととのえるカウンセリング
子育ての真っ最中で、仕事と家庭の間で揺れ動いている女性の皆さんへ。私たちのカウンセリングサービスは、あなたのためにあります。もし心の中で悩みや生きづらさを感じている場合、それは特別な心のケアが必要な証拠です。株式会社Osaka-Childとして、日々の生活で直面している困難を理解し、その解決をサポートします。
私たちは、あなたが人生の困難に立ち向かう勇気を見つけるための安全な空間を提供します。当社のプロフェッショナルなカウンセラーは、あなたの問題や感情に深い理解を持ち、あなたを尊重します。ここでは、あなたの気持ちを自由に表現し、過去の影響から解放され、自分自身を再発見することができるでしょう。
カウンセリングは、心理システムの問題を共に解決するための有力な手段です。私たちのカウンセリングでは、まずじっくりとあなたのお話を聴きます。過去の経験やトラウマ、日常生活でのストレスなど、あなたが抱える悩みや心の中での葛藤を理解し、共感します。その後、適切なカウンセリング技法を用いて、心の中のブロックを取り除き、自分自身と向き合い、成長するためのサポートを行います。
初めての方でも、私たちのサービスを利用することはとても簡単です。当社のウェブサイト上で、カウンセリングセッションの申し込みをすることができます。また、具体的な問い合わせや不明点がある場合は、お気軽に当社までメールをお送りください。
心の中で抱える悩みや生きづらさに苦しんでいるなら、あなたは一人ではありません。株式会社Osaka-Childは、あなたが自分自身の価値を見つけ、生活の質を改善するためのサポートを提供します。カウンセリングを通じて、あなたがより健康的で充実した人生を歩む手助けをいたします。
カウンセリングのプロセスは、あなたの個別のニーズや目標に合わせてカスタマイズされます。私たちは、あなたが心地よく感じるペースでサポートを提供し、尊重と信頼の関係を築くことを大切にしています。カウンセリングを通じて、自己理解を深め、心の中の問題を克服し、より充実した人生を築いていきましょう。
あなたが心の支えを必要としているなら、ぜひ株式会社Osaka-Childのカウンセリングにお越しください。私たちがあなたの側にいて、共に問題を解決し、より健康で幸せな未来を築くお手伝いをいたします。一歩踏み出す勇気を持ってください。私たちと一緒に、新しい人生の扉を開いてみましょう。
\本気で変わりたい40代母親へ/
子どもとの関係、自分の人生、どちらもあきらめない方法があります。
33万円・50万円の本格プログラムで、臨床心理士とマンツーマンであなたの「再スタート」をサポートします。
現在【銀行振込の方限定で割引案内】をご用意しています。
🔸 本日 7月11日(金)23:59まで のご入金分までのご案内となります。
🔸 『あと1名様限定』
※銀行振込限定・先着順での受付となります。
小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援事業をする株式会社Osaka-Childとは?




【 復学率100% 】小中学生復学支援Osaka-Childの支援策とは?
こちらもCHECK
-

-
【 復学率100% 】小中学生復学支援Osaka-Childの支援策とは?
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
【堺市】不登校の子どもをサポートする!Osaka-Childのカウンセリング支援
こちらもCHECK
-

-
【堺市】不登校の子どもをサポートする!Osaka-Childのカウンセリング支援
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 Osaka-Childは、堺市にある不登校の子どもたちとその家族を支援するカウンセリ ...
続きを見る
復学支援の専門家が教える、家庭学習支援のポイントと効果的な学習方法
株式会社Osaka-Childの心理技法・心理検査一覧
株式会社Osaka-Childの障害一覧
株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:母親のメンタルサポート


支援内容
1. オキシトシン分泌促進で子どもに接する母親の専門的なカウンセリング
2. 胎児期から乳児期のオキシトシン分泌状態の再経験
3. 母親の子育ての疲れやストレスの軽減
4. 母親の胎児期・幼少期の体験のインナーチャイルドの修正
5. 母親の親子関係をカウンセリングにより気づかせる
6. カウンセリングによって母親の生き方を主体性を持たせる
7. 幼少期に得られなかった愛着の再構築
8. 個人に合った最適な心理システムの再起動
9. 母親を子どもの親から一個人としての存在の獲得
10. 愛着育成による自己肯定感の向上
11. 人生軸上でインストールした感覚ー認識の空洞化
母親のメンタルサポートの具体的なアプローチ
株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、母親のメンタルサポートを提供しています。以下に、具体的な支援内容を説明します。
- オキシトシン分泌促進で子どもに接する母親の専門的なカウンセリング オキシトシンは愛着や絆の形成に関与するホルモンであり、母親と子どもの関係を深める重要な役割を果たします。カウンセリングにおいては、母親がオキシトシン分泌を促進する方法や子どもとの関わり方について学びます。
- 胎児期から乳児期のオキシトシン分泌状態の再経験 母親が胎児期から乳児期の自身のオキシトシン分泌状態を再経験することで、子どもとの関係性や愛着形成に関する理解を深めます。これにより、母親はより適切な愛着行動を身につけ、子どもの安定した成長を支援します。
- 母親の子育ての疲れやストレスの軽減 子育てにおける疲れやストレスは母親のメンタルヘルスに大きな影響を与えます。専門的なカウンセリングにより、母親の疲れやストレスを軽減し、心の健康を保つための具体的なケア方法を提供します。
- 母親の胎児期・幼少期の体験のインナーチャイルドの修正 母親の胎児期や幼少期におけるトラウマや負の体験は、子育てに影響を及ぼすことがあります。カウンセリングにより、母親は自身のインナーチャイルド(内なる子どもの存在)の修正を通じて、子育てにおける負のパターンを変容させます。
- 母親の親子関係をカウンセリングにより気づかせる 母親の親子関係に潜むパターンや影響をカウンセリングを通じて明示し、母親自身がその関係性に気づくことを支援します。これにより、母親はより良好な親子関係を構築し、子どもの成長を促進します。
- カウンセリングによって母親の生き方を主体性を持たせる 母親が自身の生き方を主体的に選択し、子どもとの関係性をより意識的に築いていくことを支援します。母親の個別のニーズや目標を考慮し、適切なカウンセリングプランを策定します。
- 幼少期に得られなかった愛着の再構築 母親が幼少期に得られなかった愛着を再構築することで、自己肯定感や安心感を向上させます。カウンセリングにおいては、母親が自身の愛着スタイルや関わり方を理解し、健全な愛着関係の構築に向けた具体的なアプローチを身につけます。
- 個人に合った最適な心理システムの再起動 母親の心理システムの再起動により、ストレスへの対処能力や情緒調整能力を向上させます。カウンセリングにより、母親は自身の心理的な困難や制約を克服し、より健康的な心の状態を取り戻すことができます。
- 母親を子どもの親から一個人としての存在として認識 母親が自身を単に子どもの親としてではなく、個別の存在として認識することを支援します。母親の自己アイデンティティや自己実現の重要性を再確認し、自己成長とバランスの取れた生活を促進します。
- 愛着育成による自己肯定感の向上 母親が子どもとの愛着関係を育むことで、自己肯定感や自己価値感を向上させます。カウンセリングにおいては、母親が愛着行動やコミュニケーションスキルを向上させるための具体的な手法やアドバイスを受け取ります。
- 人生軸上でインストールした感覚ー認識の空洞化 母親が人生軸上で自身の感覚や認識を見つめ直し、新たな視点や意味づけを行うことを支援します。これにより、母親はよりポジティブな心理状態を持ち、子どもとの関係や子育てにおいてより健全な選択を行うことができます。
具体的な支援内容として、母親は定期的なカウンセリングセッションを通じて自身のメンタルヘルスや子育てに関する課題を共有し、カウンセラーとの対話やアドバイスを受け取ります。また、母親には日常生活におけるストレス管理や自己ケアの方法、感情の調整やコミュニケーションスキルの向上など、実践的なツールや戦略が提供されます。
大阪の不登校カウンセリング|40代の母親が必知!子供の不登校を解決する支援方法と専門家のアドバイス
こちらもCHECK
-

-
大阪の不登校カウンセリング|40代の母親が必知!子供の不登校を解決する支援方法と専門家のアドバイス
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 子供の不登校は多くの40代の母親にとって深刻な悩みです。その解決には適切な支援方法と ...
続きを見る
【40代母親からの第一歩】不登校問題解決への道と専門カウンセリングでの導き
こちらもCHECK
-

-
【40代母親からの第一歩】不登校問題解決への道と専門カウンセリングでの導き
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 40代の母親が抱える不登校問題は深刻な課題です。子どもの不登校により家庭や学校の関係 ...
続きを見る
【幸せホルモン】オキシトシンの増やし方12選|瞑想やマインドセット・身体調整が効果的
不登校の原因を知る方法!40代の母親が的確にサポートする方法とは?
中学生の不登校の原因は母親にあった!母親へのカウンセリングで復学につなげる
【40代子育ての悩み】不登校の原因を解明!不登校になる子の親の特徴と改善策
株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どものカウンセリング


支援内容
1. 不登校の子どもが抱えるココロの動きの促進
2. 幼少期の負の体験の心理システムの循環
3. 親子関係による負の自己イメージの軌道修正
4. 学校環境での存在価値の促進
5. 過去ー現在ー未来の時間軸の自然循環
6. 幼少期に遺伝的にもっているエネルギーの再生成
7. 学校環境で経験した負の要素への関わり
8. 学校環境で作られた他者との競争原理の滅尽
9. 母親では得られなかった愛着をカウンセラーとの共有で再獲得
10. 幼少期のゼロベースでの人間像への気づき
11. 負の心理システムで構成された世界観の抑制
不登校の子どものカウンセリングの具体的なアプローチ
- 不登校の子どもが抱えるココロの動きの促進 不登校の子どもは心理的な負担を抱えている場合があります。私たちは、子どものココロの動きを理解し、彼らが抱える不安やストレスを軽減するための支援を行います。具体的な方法としては、感情の表現や認識のトレーニング、リラクゼーション技法の導入などがあります。また、子どもが自己理解を深め、自己肯定感を高めるために、自己探索のプロセスにも取り組みます。
- 幼少期の負の体験の心理システムの循環 幼少期に経験した負の出来事やトラウマは、不登校の原因となることがあります。私たちは、そのような負の体験が心理システムにどのように影響を与え、循環するのかを理解し、子どもと共にその解決に向けた取り組みを行います。具体的には、トラウマ解消のための技法や自己発見のプロセスを通じて、過去の負の経験に対処し、新たな自己概念を構築するサポートを行います。
- 親子関係による負の自己イメージの軌道修正 親子関係は子どもの自己イメージに大きな影響を与えます。不登校の子どもにおいては、負の自己イメージが形成されることがあります。私たちは、子どもと親の関係を理解し、親子のコミュニケーションの改善や共感的な対話を通じて、子どもの自己イメージの軌道修正を支援します。親には、子どもの感情や困難に対して理解を示し、受け入れる姿勢を促すためのアドバイスや指導を提供します。
- 学校環境での存在価値の促進 不登校の子どもは学校環境での存在価値や自己肯定感に欠けていることがあります。私たちは、子どもが学校での存在感を取り戻すための支援を行います。具体的には、学校との連携や学校内でのサポート体制の構築を行い、子どもが自分の能力や才能を発揮できる場を提供します。また、学校生活の中での達成感や成功体験を通じて、子どもの自信を育む取り組みも行います。
- 過去ー現在ー未来の時間軸の自然循環 不登校の子どもは、過去の困難や現在の問題に囚われる傾向があります。私たちは、子どもが過去、現在、未来の時間軸を自然に循環できるように支援します。過去の出来事への執着や現在の問題に対する固執を解放し、未来に向けて前向きに取り組むことを促します。具体的な方法としては、目標設定や将来のビジョンの明確化、行動計画の策定などがあります。
- 幼少期に遺伝的に持っているエネルギーの再生成 子どもの行動や感情は、幼少期に遺伝的に受け継がれたエネルギーによって影響を受けることがあります。私たちは、子どもが遺伝的に持っているエネルギーを再生成し、ポジティブな方向へと導くための支援を行います。具体的には、子どもが自己観察や自己理解を深めるプロセスを通じて、自己変容を促すことに焦点を当てます。
- 学校環境で経験した負の要素への関わり 不登校の子どもは、学校環境での負の要素に対して適切に関わることができない場合があります。私たちは、子どもが学校環境での負の要素に対して適切に対処できるように支援します。具体的には、コミュニケーションスキルのトレーニングや問題解決能力の向上を促すプログラムを提供し、子どもが対処方法を見つけられるようにサポートします。
- 学校環境で作られた他者との競争原理の滅尽 学校環境では競争原理が存在し、不登校の子どもにとっては負の影響を与えることがあります。私たちは、他者との競争原理を滅尽し、協力や共感の文化を醸成する支援を行います。具体的には、協調性やチームワークの重要性を学ぶ活動や、他者との比較ではなく自己の成長に焦点を当てる指導を行います。
- 母親では得られなかった愛着をカウンセラーとの共有で再獲得 不登校の子どもの中には、母親からの愛着が不足している場合があります。私たちは、子どもがカウンセラーとの関係を通じて、得られなかった愛着を再獲得できるように支援します。子どもが安心感や信頼感を育み、自己価値感や自己受容感を高めるために、カウンセラーとの関係性を重視したアプローチを取ります。
- 幼少期のゼロベースでの人間像への気づき 不登校の子どもには、幼少期に根付いた人間像や自己イメージに問題がある場合があります。私たちは、子どもが自己観察や内省を通じて、幼少期のゼロベースから新たな人間像への気づきを促す支援を行います。具体的には、自己評価の見直しやポジティブな特性の発見、適応的な思考や行動パターンの構築をサポートします。
- 負の心理システムで構成された世界観の抑制 不登校の子どもは、負の心理システムで構成された世界観を持っていることがあります。私たちは、子どもがそのような負の世界観から抜け出し、ポジティブな視点や心理的な柔軟性を取り戻すための支援を行います。
具体的には、認知行動療法やポジティブ心理学の手法を用いて、子どもの思考や信念の再構築を促し、より健康的な心理システムを構築します。 株式会社Osaka-Childの臨床心理士(カウンセラー・セラピスト・不登校専門カウンセラー)として、私たちは不登校の子どもとその家族に対して、個別に適した支援を提供します。子どもの心の健康を重視し、不登校の原因や状況を的確に把握した上で、専門知識や経験に基づいたアプローチを用いてサポートを行います。私たちの目標は、子どもが健やかな学校生活を送り、自己成長や社会参加の機会を最大限に引き出すことです。
不登校カウンセリングでHSCの子どもを復学支援に|HSCの子どもを持つ40代の母親に向けて
こちらもCHECK
株式会社Osaka-Childのカウンセリング技法
カウンセリングとは?心理システムを正常化して生きづらさを克服する効果最大
-

-
参考カウンセリングとは?心理システムを正常化して生きづらさを克服する効果最大
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
来談者中心療法で心理システムを自然状態にして精神的苦しみを克服|40代女性の生きづらさ克服
-

-
参考来談者中心療法で心理システムを自然状態にして精神的苦しみを克服|40代女性の生きづらさ克服
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
トラウマインフォームドケアをカウンセリングで心理システムの最短正常化に
-

-
参考トラウマインフォームドケアをカウンセリングで心理システムの最短正常化に
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
オンラインカウンセリングのメリット・デメリットを知って手軽に心理システムを正常化する
-

-
参考オンラインカウンセリングのメリット・デメリットを知って手軽に心理システムを正常化する
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
精神分析的心理療法でカウンセリングを実施し心理システムの正常化で生きづらさ克服
株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの身体調整


支援内容
1. 子どもの姿勢コントロールの修正
2. 姿勢コントロールによる身体アライメント構築
3. 姿勢コントロールから重心作り
4. 学習に不可欠な座り姿勢での姿勢コントロールの促通
5. 姿勢に伴う手の運動構成のバランス
6. 姿勢と視覚・聴覚情報の同期
7. 全身の関節運動・筋肉の出力調整
8. 三半規管や脳神経系の出力の修正
9. ハンドリングによる触覚刺激で感覚系のコントロール
10. 皮ふ刺激によるオキシトシン分泌の促進
11. 皮ふ・筋膜・筋肉・筋肉の長さのセンサーのコントロール
12. 感覚ー認識システム促通から無の状態へのアップデート
13. 身体への関わりによる不足した愛着の向上
14. 負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化
15. 負の心理システムから身体への過剰な意識への抑制
不登校の子どもの身体調整の具体的なアプローチ
株式会社Osaka-Childでは、不登校の小中学高校生や発達障害の子どもの復学支援の一環として、身体調整の支援を行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。
- 子どもの姿勢コントロールの修正 子どもの姿勢は、身体の調整や感覚統合に重要な役割を果たします。不適切な姿勢が存在する場合、学習や集中力に悪影響を与えることがあります。私たちは、子どもの姿勢を正しい形に修正し、適切な姿勢コントロールをサポートします。具体的には、姿勢の矯正や筋力トレーニング、姿勢保持のためのエルゴノミクス指導などを行います。
- 姿勢コントロールによる身体アライメント構築 姿勢の改善は、身体のアライメントやバランスの向上につながります。私たちは、子どもの身体アライメントを構築するために、姿勢コントロールのトレーニングを行います。これには、正しい姿勢の保持や身体の軸の調整、バランス感覚の向上などが含まれます。
- 姿勢コントロールから重心作り 姿勢と重心の関係は、身体の安定性や運動の質に大きな影響を与えます。私たちは、姿勢コントロールから重心の形成に焦点を当て、子どもが適切な重心を持つことをサポートします。具体的には、姿勢トレーニングやバランスボードを使ったトレーニングなどを通じて、重心の安定化を促します。
- 学習に不可欠な座り姿勢での姿勢コントロールの促通 適切な座り姿勢は、学習において重要な要素です。不適切な座り姿勢は集中力の低下や身体の疲労を引き起こすことがあります。私たちは、子どもが学習に不可欠な座り姿勢を維持できるように、姿勢コントロールの促通を支援します。具体的には、正しい座り方やデスク環境の調整、体操やストレッチの指導などを行います。
- 姿勢に伴う手の運動構成のバランス 姿勢と手の運動は密接に関連しています。不適切な姿勢は手の運動にも影響を与えることがあります。私たちは、子どもの手の運動構成をバランス良く整えるために、姿勢と手の連動性を意識した支援を行います。具体的には、手の筋力や協調性のトレーニング、細かい手指の動作の指導などを行います。
- 姿勢と視覚・聴覚情報の同期 姿勢の調整と視覚・聴覚情報の適切な処理は、子どもの学習や集中力に影響を与えます。私たちは、子どもが姿勢と視覚・聴覚情報を適切に同期させるための支援を行います。具体的には、視覚情報や聴覚情報の統合を促すトレーニングやセンサリー処理の指導などを行います。
- 全身の関節運動・筋肉の出力調整 全身の関節運動や筋肉の出力の調整は、身体の柔軟性や運動能力に影響を与えます。私たちは、子どもの全身の関節運動や筋肉の出力を調整し、適切な身体の動きをサポートします。具体的には、関節の可動域の拡大や筋力トレーニング、コーディネーションの向上を目指したプログラムを提供します。
- 三半規管や脳神経系の出力の修正 三半規管や脳神経系の出力の調整は、バランス感覚や運動の調整に関与します。私たちは、子どもの三半規管や脳神経系の出力を修正し、バランス感覚や運動の質を改善するための支援を行います。具体的には、バランス感覚のトレーニングや目の運動の指導などを行います。
- ハンドリングによる触覚刺激で感覚系のコントロール 触覚刺激は感覚統合や身体の調整に重要な役割を果たします。私たちは、子どもの感覚系のコントロールを促すために、ハンドリングと呼ばれる触覚刺激を活用した支援を行います。具体的には、身体全体に触覚刺激を与えることで感覚統合を促し、身体の安定性や調整能力を高めます。
- 皮ふ刺激によるオキシトシン分泌の促進 皮ふ刺激はオキシトシンの分泌を促し、リラックスや安定感をもたらします。私たちは、子どもの皮ふ刺激を活用してオキシトシンの分泌を促進し、心身の安定をサポートします。具体的には、マッサージや触れ合いのアクティビティを通じて、子どもがリラックスした状態に入る機会を提供します。
- 皮ふ・筋膜・筋肉の長さのセンサーのコントロール 身体の皮ふ、筋膜、筋肉は長さの変化を感知するセンサーを持っています。私たちは、子どもの皮ふ・筋膜・筋肉の長さのセンサーをコントロールし、正常な身体の感覚を促します。具体的には、ストレッチや筋膜リリースなどの手法を用いて、身体の柔軟性や感覚統合を促進します。
- 感覚ー認識システム促通から無の状態へのアップデート 感覚と認識のシステムが促通し、無の状態にアップデートされることは、子どもの集中力や学習能力に大きな影響を与えます。私たちは、子どもの感覚と認識のシステムを促通させ、無の状態へのアップデートを支援します。具体的には、身体を使ったアクティビティやセンサリー統合の手法を用いて、感覚と認識の調整を促します。
- 身体への関わりによる不足した愛着の向上 不登校の子どもには、不足した愛着が存在する場合があります。私たちは、身体への関わりを通じて子どもの不足した愛着を向上させる支援を行います。具体的には、身体的な接触やアクティビティを通じて子どもとの関係性を構築し、安心感や信頼感を促します。
- 負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化 負の心理システムは、子どもの身体に過緊張や緊張を引き起こすことがあります。私たちは、負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化をサポートします。具体的には、筋肉の緊張を緩めるエクササイズやリラクゼーション法の指導を行い、身体の緊張を軽減します。
- 負の心理システムから身体への過剰な意識への抑制 負の心理システムから身体への過剰な意識は、子どもの集中力や学習に悪影響を与えることがあります。私たちは、負の心理システムから身体への過剰な意識を抑制する支援を行います。
株式会社Osaka-Childの身体調整とカウンセリング技法
催眠療法と心理カウンセリング併用で精神作用をリセット|40代女性の心理システムを正常化に
-

-
参考催眠療法と心理カウンセリング併用で精神作用をリセット|40代女性の心理システムを正常化に
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
自律訓練法とカウンセリングの併用で40代女性生きづらさ克服|自宅で簡単にできる
-

-
参考自律訓練法とカウンセリングの併用で40代女性生きづらさ克服|自宅で簡単にできる
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
呼吸法とカウンセリングで身体と精神をコントロールし40代女性が安定した人生を送る
-

-
参考呼吸法とカウンセリングで身体と精神をコントロールし40代女性が安定した人生を送る
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
メンタライゼーション・ベースド・セラピーで40代女性の心理システムを整える
-

-
参考メンタライゼーション・ベースド・セラピーで40代女性の心理システムを整える
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
グリーフケアカウンセリングで新しい自分で自然世界と調和した生き方を獲得する
-

-
参考グリーフケアカウンセリングで新しい自分で自然世界と調和した生き方を獲得する
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
リラクゼーション法で40代女性の生きづらさの身体症状を克服|目的・やり方・コツを解説
-

-
参考リラクゼーション法で40代女性の生きづらさの身体症状を克服|目的・やり方・コツを解説
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
具体的には、身体感覚の調整やマインドフルネスなどの技法を用いて、子どもの心身のバランスを整えます。 株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの身体の健康と調整を重視し、個別に適した身体調整の支援を提供します。子どもとその家族との協力を通じて、身体の調整や感覚統合の促進を図り、学習や社会生活の質を向上させることを目指します。
📌 あなたに必要な支援は、今すぐ手に届きます。
ここまで読んで「これ、私のことだ」と感じた方へ。
私たちが提供している再設計プログラムは、表面的なアドバイスではなく、根本から人生を整えるための実践型サポートです。
現在【銀行振込の方限定で割引案内】をご用意しています。
🔸 本日 7月11日(金)23:59まで のご入金分までのご案内となります。
🔸 『あと1名様限定』
※銀行振込限定・先着順での受付となります。
銀行振込限定で 最大5万円割引・個別相談枠の優先予約も受付中。
株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの家庭学習支援


支援内容
1. オンラインによる苦手教科の徹底的学習サポート
2. 自分に合った教材と学習法の発見と実践
3. 得意科目を地域で成績上位に入るための学習法
4. 苦手科目の時間的な関わり(量→質)
5. 予習・復習の時間共有
6. 脳内の特性に合わせた学習プログラムの実践
7. 脳内と心理システムを促通した個人に合った学習方法の習得
8. 勉強量から勉強の質への関わり
9. 不登校中の自宅でのスケジューリング
10. 勉強に対する苦手意識への心理システムの調整
11. 成績に反映する個人に合った勉強法の獲得
12. 全教科の要素分解と要素の合成への考え方の習得
13. 不登校中に偏差値を20以上向上させる学習時間と質の習得
不登校の子どもの家庭学習支援の具体的なアプローチ
株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、家庭学習の支援を行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。
- オンラインによる苦手教科の徹底的学習サポート オンラインを活用して、子どもの苦手とする教科について徹底的な学習サポートを行います。個別のオンラインチューターや学習プラットフォームを活用し、子どもが理解を深めるための指導を提供します。
- 自分に合った教材と学習法の発見と実践 子どもに合った教材や学習法を見つけ、実践するサポートを行います。子どもの学習スタイルや興味・関心に合わせて教材を選定し、効果的な学習方法を指導します。
- 得意科目を地域で成績上位に入るための学習法 子どもの得意科目を活かして、地域で成績上位に入るための学習法を指導します。具体的な学習戦略やアプローチを提供し、子どもが得意科目での自信と成果を得られるように支援します。
- 苦手科目の時間的な関わり(量→質) 苦手科目に対する学習時間を質の高いものにするための支援を行います。集中力を高めるための学習スケジュールの作成や、効果的な学習方法の指導を通じて、苦手科目への取り組みを効果的に進める方法を提供します。
- 予習・復習の時間共有 予習と復習の重要性を理解し、効果的に取り組むために、子どもと共有する時間を設けます。予習や復習の方法や具体的な計画の立て方を指導し、子どもが学習内容を定着させるサポートを行います。
- 脳内の特性に合わせた学習プログラムの実践 子どもの脳の特性に合わせた学習プログラムを実践します。例えば、視覚的な学習スタイルを持つ子どもにはマインドマップやイメージングを活用し、効果的な学習を促します。
- 脳内と心理システムを促通した個人に合った学習方法の習得 子どもの脳内の機能と心理システムを促通させ、個人に合った学習方法を習得させる支援を行います。具体的には、脳の情報処理や学習スタイルを理解し、それに基づいた学習戦略やアプローチを提案します。
- 勉強量から勉強の質への関わり 勉強の量だけでなく、質の高い学習を実現するための関わりをサポートします。集中力の向上や学習環境の整備、効果的な学習テクニックの指導などを通じて、子どもが効率的かつ効果的に学習できるように支援します。
- 不登校中の自宅でのスケジューリング 不登校中の子どもが自宅での学習をスムーズに進めるためのスケジューリングのサポートを行います。適切な時間配分やタスク管理の方法を指導し、子どもが自主的に学習を進められるように支援します。
- 勉強に対する苦手意識への心理システムの調整 勉強に対する苦手意識を持つ子どもに対して、心理システムの調整を行います。適切な支援方法や学習環境の整備、ポジティブなフィードバックの提供などを通じて、子どもの勉強への意欲や自信を高める支援を行います。
- 成績に反映する個人に合った勉強法の獲得 子どもの個別の特性や学習スタイルに合わせて、成績に反映される勉強法を獲得させる支援を行います。具体的には、学習戦略の指導や学習プランの作成、効果的な学習テクニックの習得などを通じて、子どもが効果的に学習できるようにサポートします。
- 全教科の要素分解と要素の合成への考え方の習得 全教科において、学習内容を要素分解し、それらを合成する考え方を習得させる支援を行います。具体的には、重要なキーポイントの抽出や概念の整理、総合的な学習アプローチの指導などを通じて、子どもの学習能力を向上させます。
- 不登校中に偏差値を20以上向上させる学習時間と質の習得 不登校中に子どもの学習時間と質を向上させ、偏差値を20以上上げる支援を行います。適切な学習計画の策定や時間管理の指導、効果的な学習方法の習得などを通じて、子どもの学力向上を支援します。
発達支援・発達相談をカウンセリングと療育で発達障害の子どもの機能性を120%アップ
動機づけ面接とカウンセリングの併用で40代女性の個人の人生に合った生き方を見つける
ナラティヴセラピーをカウンセリングで過去の経験値を未来軸に近づけ40代女性を自己実現に
ペアレント・トレーニングで40代母親の子育てを楽にする|子どもの育ちを大切にできる
不登校中の勉強しない・遅れる不安を解決する40代母親ができる接し方とは
中3不登校生徒で勉強してない場合の受験対策や進路の選択肢|今からでも間に合う!
【40代母親必見】不登校の子が復学後に勉強しない?その原因と解決策を詳解
中学3年間不登校だと勉強してないから高校受験は難しい?中学生の不登校の原因と親ができる対応
発達障害をカウンセリングで心理システムをスムーズにし克服へ|40代女性生きづらさ解決
学習障害(LD)をカウンセリングで最短で負担なく克服させる|生きづらさ解決に
株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの家庭学習をサポートし、個別に適した学習方法や戦略を提供します。子どもとその家族との協力を通じて、学習の成果を最大化し、不登校からの復学を支援します。
株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポート


支援内容
1. カウンセリングによる自己イメージのリセット
2. 意識と覚醒の自然現象への共有
3. 好きなこと・得意なこと・使命感への気づき
4. 未来像のマインドからの発見
5. 未来像と現実の自己へのプログラミング
6. 自己内から具体的な人生設計
7. 誕生から死への人生軸への関わりと意識の促通
8. トレンド情報に流されない個人に合った生き方の習得
9. 努力せずありのままで成果が出るキャリアとプロセスの構築
10. 学校環境での失敗体験の再現化と捨てる作業
11. 世界を構造から見つけていくトレーナーとの共有
不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポートの具体的なアプローチ
株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、進学やキャリアデザインのサポートを行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。
- カウンセリングによる自己イメージのリセット カウンセリングを通じて、子どもの自己イメージをリセットします。過去の失敗や困難な経験に縛られず、新たな可能性や自己評価を見つける支援を行います。
- 意識と覚醒の自然現象への共有 子どもに対して、意識や覚醒の自然現象について共有し、自己の内面に目覚めるきっかけを与えます。具体的には、マインドフルネスや瞑想などの方法を取り入れ、子どもが内なる気づきや成長を促します。
- 好きなこと・得意なこと・使命感への気づき 子どもが自分の好きなことや得意なこと、そして使命感を見つけるための支援を行います。興味や才能を引き出し、将来の方向性を探るための活動や自己探求のプロセスをサポートします。
- 未来像のマインドからの発見 子どもが自分自身の未来像を持つことで、目標や希望を見つける手助けをします。未来を具体的にイメージすることで、自己の成長や進学・キャリアの方向性を見出すサポートを行います。
- 未来像と現実の自己へのプログラミング 子どもが描いた未来像と現実の自己を結び付けるためのプログラミングをサポートします。具体的な目標設定や行動計画の策定、自己肯定感や自己効力感の醸成を通じて、子どもの進学やキャリアの実現を支援します。
- 自己内から具体的な人生設計 子どもが自己内に持つ資源や価値観を活かし、具体的な人生設計を立てるサポートを行います。自己の内なる声や目標に基づき、将来の進路やキャリアの方向性を考えるプロセスを共に進めます。
- 誕生から死への人生軸への関わりと意識の促通 子どもに対して、人生の意義や目的、誕生から死への人生軸について考える機会を提供します。自己の存在意義や時間の尊さを理解し、将来に向けた意識の促進を支援します。
- トレンド情報に流されない個人に合った生き方の習得 子どもがトレンド情報や社会の期待に流されず、自己に合った生き方を見つけるための支援を行います。個別の特性や価値観を尊重し、自己を大切にする生き方の習得をサポートします。
- 努力せずありのままで成果が出るキャリアとプロセスの構築 子どもが努力せずにありのままの自己で成果を出せるキャリアやプロセスの構築をサポートします。個々の能力や資質を活かし、自己の個性や魅力を最大限に生かした進学やキャリアの選択を支援します。
- 学校環境での失敗体験の再現化と捨てる作業 学校環境での失敗体験を再現し、それらを手放すプロセスを支援します。過去のネガティブな体験やトラウマからの解放を促し、自己成長と前向きな展望を持つためのサポートを提供します。
- 世界を構造から見つけていくトレーナーとの共有 子どもが世界の構造や社会の仕組みを理解し、自己の進学やキャリアの選択に生かすために、トレーナーとの共有を行います。具体的な情報や知識の提供、意義や意味の理解を通じて、子どもの進学やキャリアデザインに役立つサポートをします。
対人関係療法カウンセリングで治りにくい精神疾患を正常化する|うつ病・摂食障害に効果的
ソリューション・フォーカスト・アプローチで人生の悩みを最短解決|40代女性生きづらさ克服
キャリアカウンセリング(キャリアコンサルティング)で40代女性の人生を幸福に導く
コーチングで40代女性の子育てやキャリアアップを最速に機能させる
株式会社Osaka-Childのカウンセリング技法
【2023年最新】認知行動療法(CBT)とは?方法、効果やメリット・デメリット、療法の流れなどを解説
ストレスマネジメントとは?40代女性が子育て・キャリアアップで活かせる効果ややり方を解説
-

-
参考ストレスマネジメントとは?40代女性が子育て・キャリアアップで活かせる効果ややり方を解説
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
アサーショントレーニングとは?職場や子育てで実践する方法や自己表現タイプを解説
-

-
参考アサーショントレーニングとは?職場や子育てで実践する方法や自己表現タイプを解説
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
認知再構成法とカウンセリングで40代女性の生きづらさを生む認知のゆがみを克服
-

-
参考認知再構成法とカウンセリングで40代女性の生きづらさを生む認知のゆがみを克服
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの進学やキャリアデザインを支援し、自己の可能性や夢を追求するサポートを行います。子どもとその家族との協力を通じて、自己の価値を見出し、将来への道を切り拓くお手伝いをします。
株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの子どもの不登校復学支援内容:不登校復学後の1年間のサポート


支援内容
1. 復学後の学校との連携
2. 復学後の母親と子どものカウンセリングの実施
3. 復学後に生まれる諸問題の解決と実践
4. 復学後の生きづらさの軌道修正
5. 復学後の母親のメンタルサポートの継続
6. 復学後にぶつかる学校環境での負の体験への関わり
7. 母親に生まれる子どもへの過負荷の調整
8. 母親の人生サポートの継続による子どもの自由の解放
9. 復学後に生まれる母親と子どもへの不安の共有
不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポートの具体的なアプローチ
株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学後の1年間にわたるサポートを提供しています。以下に、具体的な支援内容を説明します。
- 復学後の学校との連携 子どもの復学後において、学校との綿密な連携を行います。学校とのコミュニケーションを円滑にし、子どもの学習状況や生活面でのサポートが必要な点を把握し、適切な支援策を立てるために協力します。
- 復学後の母親と子どものカウンセリングの実施 復学後においても母親と子どものカウンセリングを実施し、お互いの心情や課題に対して向き合います。母親の支えや理解を促し、子どもの心理的な安定と学校生活への適応をサポートします。
- 復学後に生まれる諸問題の解決と実践 復学後に生じる様々な問題や課題に対して、具体的な解決策を見つけて実践する支援を行います。学校生活や人間関係のトラブル、学習上の困難などに対して、子どもと母親の双方が適切に対処できるようにサポートします。
- 復学後の生きづらさの軌道修正 復学後に感じる生きづらさや不安に対して、子どもの心理的な軌道修正を支援します。自己肯定感の向上や適切なストレス管理の方法を教えることで、子どもが学校での生活に前向きに取り組むことを支えます。
- 復学後の母親のメンタルサポートの継続 母親のメンタルサポートを復学後も継続的に行います。母親が子どもの復学に伴うストレスや不安を抱える場合には、心理的な支えや情報提供を通じて、彼女の心の健康状態を維持し、子どもへのサポートを続けます。
- 復学後にぶつかる学校環境での負の体験への関わり 復学後に学校環境での負の体験が生じた場合には、子どもがそれに適切に関わることができるようにサポートします。適切なコーピングスキルの習得や自己肯定感の強化を通じて、子どもが学校での困難に立ち向かう力を育みます。
- 母親に生まれる子どもへの過負荷の調整 復学後において、母親が子どもに対して過度な負荷を感じる場合には、適切な調整を行います。母親の負担を軽減し、子どもとの関係性を健全に保ちながら、サポートのバランスを取ることが重要です。
- 母親の人生サポートの継続による子どもの自由の解放 母親の人生全体にわたるサポートを継続し、彼女が自己の成長と発展に集中できる環境を整えます。母親の支えが安定することで、子どもはより自由に自己を表現し、学校生活を充実させることができます。
- 復学後に生まれる母親と子どもへの不安の共有 復学後に母親と子どもが抱える不安や心配事に対して、お互いがそれを共有し、解消するための場を提供します。相互の理解を深め、不安を和らげることで、子どもの復学後の安定と成長をサポートします。
ストレスコーピングとカウンセリングの併用で40代女性のキャリア・子育てに成果
マインドフルネスとカウンセリングで効果を最大に|40代女性のキャリア・子育てに成果を出す
行動活性化療法で精神的抑うつを改善|40代女性生きづらさ克服でキャリア・育児両立に
株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの不登校復学後の1年間にわたり、学校との連携や心理的なサポートを通じて、子どもと母親の両方を支えます。子どもの安定した学校生活の確立と母親のメンタルヘルスの維持に注力し、一人ひとりのニーズに合わせたサポートを提供します。
Osaka-Childは小学生・中学生の不登校のお子さまに対して最短復学支援を提供しています

株式会社Osaka-Childの支援内容とは
- 母親のメンタルサポート
- 不登校子どものカウンセリング
- 不登校子どもの身体調整
- 不登校子どもの家庭学習支援
- 不登校子どもの進学・キャリアデザインサポート
- 不登校復学後の1年間のサポート
不登校子どものカウンセリング Osaka-Childでは、専門のカウンセラーによる個別のカウンセリングを行い、不登校の原因や問題を解決するための支援を提供しています。不登校子どもの身体調整 心身共に健康であることは、不登校克服に不可欠な要素の1つです。Osaka-Childでは、体の不調を訴える子どもに対して、運動や栄養指導などの支援を提供しています。不登校子どもの家庭学習支援 学校に行けない状況であっても、家庭学習を続けることが重要です。 Osaka-Childでは、家庭学習の計画立案や実践支援を行い、学習習慣の維持や向上に貢献しています。不登校子どもの進学・キャリアデザインサポート 不登校期間中に進路について考えることは、将来の自分自身の希望や目標を明確にするためにも重要です。 Osaka-Childでは、進路相談や進学・就職に関する情報提供など、キャリアデザインに必要な支援を提供しています。不登校復学後の1年間のサポート 不登校克服後の生活は、新たな課題やストレスを伴うことがあります。Osaka-Childでは、不登校復学後の1年間にわたって、学校生活や社会生活のサポートを行っています。
🔚 最後まで読まれたあなたへ。
もし「私は変わりたい」と思われたのなら、
それは変わる準備が、すでに整い始めている証拠です。
✅ 現在【銀行振込の方限定で割引案内・特別価格&3大特典】をご案内中です
🔸 本日 7月11日(金)23:59まで のご入金分までのご案内となります。
🔸 『あと1名様限定』
※銀行振込限定・先着順での受付となります。
33万円・50万円の再スタート支援プログラムでは、
家族関係・心理構造・生き方の再構築を、あなたのペースでじっくり支援します。
すでに診断済みの方も、そのまま詳細ページへ進めます。
あなたの心と体に合ったサポートを、今すぐ確認してみてください。


























































をカウンセリングで-最短で負担なく克服させる-〜株式会社Osaka-Childで生きづらさ解決に〜-150x150.png)
の-女性専門カウンセリング支援.png)


で-40代女性の人生を幸福に導く-〜株式会社Osaka-Childの効果的なアプローチ〜-150x150.png)






