
- ひらがなを何度教えても、また忘れている
- 算数の文章題を読んでも、どこから手をつけていいのかわからない
- ようやく書き始めても、すぐにペンが止まってしまう
そんなわが子を前に、
- 「どうしてできないの?」
- 「また忘れてるの?」
と、つい責めてしまうことがあった。
怒ったあとに、
「また言いすぎた」と落ち込む。
それでも明日はうまくやろうと決めるのに、
また同じことをくり返してしまう。
夫には相談しづらくて、
周りにも言えないまま、
ひとりでネットを検索する夜が続いていた。
――そんな毎日を、静かに耐えてきましたよね。
でももし、
「伝わらない理由」が、
本人の努力不足ではなく、
特性による「つまずき方」にあるとしたら。
そこに気づけるだけで、
見える世界は少しずつ変わっていきます。
この記事は、
国語や算数でつまずく子どもとの関わりに悩む母親が、
- 「この子に合った教え方」
- 「自分自身の安心」
を取り戻すための視点と方法を届ける内容です。
この記事で得られる5つのこと
- ノートが書けない、読み飛ばすといった「つまずきのサイン」に気づけるようになる
- 子どもの苦手が「やる気」や「性格」の問題ではないことを理解できる
- 怒らずに関われる「安心の声かけ」のコツがわかる
- 「合う教え方」とは何かを、家庭で試せる視点が得られる
- 母親自身が「私のせいじゃなかった」と感じられる安心の土台をつくれる
どう関わればいいのかわからなくて、
毎日が戦いみたいだった。
優しくしたいのに、できなかった。
わかってあげたいのに、届かなかった。
それでも、ここまで本当にがんばってきましたよね。
- できないわが子を前に、何度も怒ってしまった。
- 言いすぎたことを後悔して、眠れなかった夜もあった。
- 勉強のことになると空気が張りつめて、家庭に笑顔がなくなっていた。
それでも、ここまで本当によくがんばってきましたよね。
「国語も算数もわからない──学習障害の子に戸惑っていた私が、『安心して関われる母』に変わっていく──3週間集中再安心サポート」は、
そんな母親が、わが子に合った学び方と関わり方を見つけていく3週間です。
- 最初の週は、「つまずき方」に気づき、
- 2週目で「伝わる工夫」を試し、
- 3週目には、怒らずに関われる視点を整えていきます。
教え方を変えるのではなく、見方を変えるだけで関係は動き出していきます。
「どうしたらいいのか、わからなかった」
その気持ちに寄り添うところから始まるサポートです。
ここから少しずつ、「安心して向き合える母」として整えていきませんか?
監修者
株式会社Osaka-Child所属 小児神経科医
- 名前: 三浦あすか
- 出身地: 兵庫県西宮市
- 最終学歴: 神戸大学医学部 小児科専攻
- 専門分野: 小児神経、DCD(協調運動障害)、発達性ディスプラクシア、HSP気質の子ども支援
- 職歴: 兵庫県立こども病院 小児神経センター勤務(11年)
専門分野について一言: 「できないことの奥にある『がんばっているサイン』を、もっと社会全体で受けとめていけたらと思っています。」
監修者
株式会社Osaka-Child所属 臨床心理専攻大学教授
- 名前: 森本哲夫
- 出身地: 奈良県
- 最終学歴: 米国ハーバード大学心理学部 博士課程修了
- 専門分野: 臨床心理学、発達心理学
- 職歴: ハーバード大学研究員(5年)、大阪大学人間科学部教授
専門分野について一言: 「心の成長とは、自己理解の旅でもあります。その旅のお手伝いができれば幸いです。」
「普通に教えてるつもりなのに…」と悩んでいるあなたへ
- 「ひらがなも漢字も、何度やっても覚えない…」
- 「ノートを写すのが遅いのは、やる気の問題なの?」
──そんなふうに、毎日の勉強が「イライラの時間」になってしまうことがある。
「どうして伝わらないの?」と責めてしまうけれど、
本当は、「教え方」よりも「伝わり方」のズレに戸惑っていただけだった。
《国語も算数もわからない──学習障害の子に戸惑っていた私が、『安心して関われる母』に変わっていく──3週間集中再安心サポート》は、
子どもの「できなさ」を一緒にひもときながら、
関わり方を根本から見直すためのサポートです。
こんな方におすすめです
- 「何度教えてもダメ…」と怒ってしまい、自己嫌悪が続いている
- ノートや宿題への取り組みに、毎日疲れてしまう
- 「この子は普通じゃないのかな」と不安が膨らんでいる
- 勉強ができなかった「あの頃の自分」と重なって、つらくなる
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 2月7日(土)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと2名様限定』
※銀行振込限定・先着順
▶ 教えても伝わらなかった毎日から、「安心して関わる母」へ変わる3週間
そして──
子どもの「困りごと」と向き合ってきた時間の先に、
「わたし自身」の人生を見つめ直したくなったあなたへ。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
「母としての安心」を土台に、
「わたしとしての人生」を再設計する3週間。
自分のことを後回しにしてきた私が、
ようやく「私の人生」と向き合い直すための時間です。
- 子育てが一段落した今、自分を立て直したい
- 誰かのためではなく、「私」のために時間を使いたい
- 「このままじゃない未来」を見つけたい気持ちがある
このプログラムでは、
「役割ではない自分」に立ち返るサポートを行います。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
「ちゃんとしてるのに、苦しい」
「頑張ってるのに、うまくいかない」
——そんな違和感を抱えたまま、ずっと我慢していませんか?
LINEで3分セルフ診断ができます。
あなたの“今の感覚”の正体が、見えてきます。
「国語も算数もわからない…」と悩んだ日々
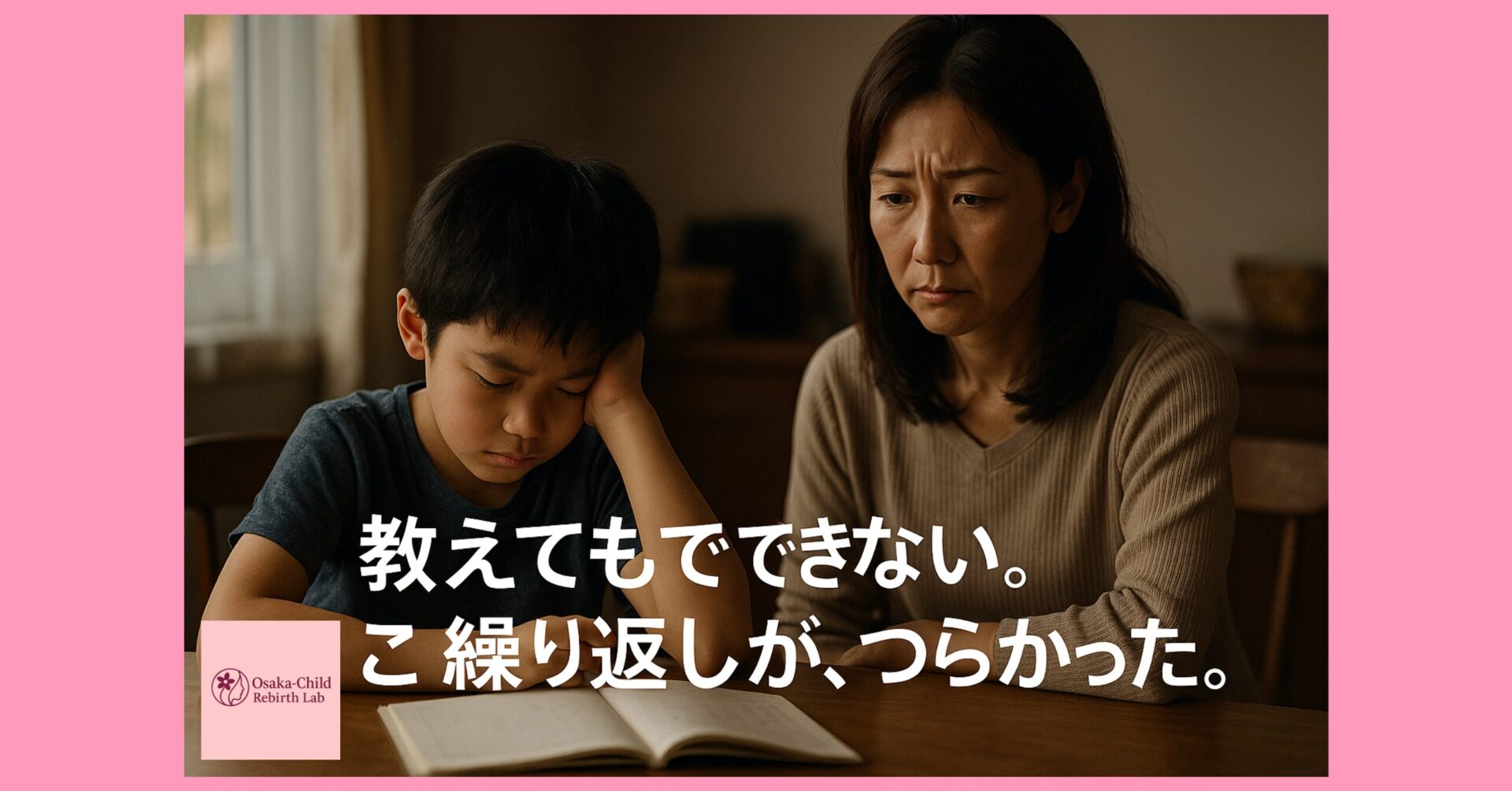
- ノートは白紙のまま
- 計算も文章も、何度教えてもつまずいてしまう
やる気がないわけじゃないとわかっていても、
どうしても責めたくなる自分がいた。
- 「私の教え方が悪いの?」
- 「この子、ほんとうに大丈夫なんだろうか」
そんな不安が、
胸の奥に居座ったまま動かなくなっていきましたよね。
「やる気の問題じゃないの?」と誰かに言われた一言が、
ずっとココロに引っかかっていた。
けれど、どこかで感じていましたよね。
──それだけじゃない気がして。
ここでは、
- 「ノートが書けない」
- 「覚えられない」
- 「宿題が進まない」
といった日常のつまずきから、
少しずつ「ほんとうの原因」を一緒にたどっていきます。
ノートが書けない/写せないのは「やる気の問題」?
- 黒板を写すのが遅い
- 何度見ても、ノートにうまく書き写せない
「ちゃんとやってよ」と言いたくなる場面が、
何度もありました。
でも実は、
学習障害(LD)や発達のグレーゾーンの子どもには、
視覚の情報処理や記憶の保持にズレが生まれます。
「見たまま」をすぐに書き写すことが、
当たり前のようにできるわけではないんです。
それでも最初は、
「やる気が足りないだけ」と感じていました。
つい厳しく言ってしまうこともありました。
でも、写せないことに困っていたのは、
他でもない「子ども自身」だったと気づいたとき、
胸がぎゅっとなったあなたがいました。
何度教えても覚えられない「国語と算数」
- ひらがなを覚えても、次の日には忘れている
- 九九がなかなか定着しない
- 計算の途中で、手が止まってしまう
そんな姿に、もどかしさを感じずにはいられませんでした。
- 「なんでできないの?」
- 「ちゃんと教えたよね?」
そう言いそうになったこと、きっと何度もありますよね。
ポイント
学習障害(LD)のある子どもは、
記憶の仕方そのものに特性があることがわかっています。
- 言葉での記憶が難しかったり、
- 順序立てて覚えるのが苦手だったりする
ことも多いです。
「教えたはずなのに、また忘れてる」
──その背景には、「伝わり方のズレ」があること。
この理由を知ったら、
あなたはどのように子どもを思いますか?
ずっと母親だけで抱えてきた子どもの生きづらさが、
「教え方の問題じゃなかったんだ」と気づけると、
ココロが軽くなってきます。
宿題が進まない/イライラして怒ってしまう私
- 宿題に向かう時間になると、部屋の空気がピリッと張りつめる。
- やりたくない気持ちがにじむ子どもの態度に、こちらも構えてしまう。
- 「またグズグズしてる」
- 「やるって言ったよね?」
そうやってイライラをぶつけたあと、
自分を責める時間がやってきます。
- 「私が怒らなければ…」
- 「もっと上手に関われたら…」
そんな後悔ばかりが、
ココロの中に積もっていくんですよね。
でも、
子どもは「わからない」を抱えたまま、
なんとかやり過ごそうとしていただけだった。
この記事を通じて、
子どもなりにがんばっていて、
がんばっているのに記憶が残らない苦しみがあること。
この事実を知ると
多くの母親は涙を流してしまうほどの強烈な気づきを得られます。
無料LINE診断|今のあなたに必要なサポートは?
「国語も算数も、どう教えればいいのかわからない…」
わかってほしいのに伝わらない、そんな日々に疲れていませんか?
「この子にはどう関わればいいのか──」
迷いながら頑張っているあなたに、
LINEで「4」と入力するだけで、
学習障害の子への関わり方が見えてくるサポート診断をご用意しています。
📩 今すぐLINEに【 4 】と送信してください。
あなたの状況に合ったサポート内容と、安心のヒントが届きます。
「教え方が間違ってたのかな?」という自責に気づいたとき
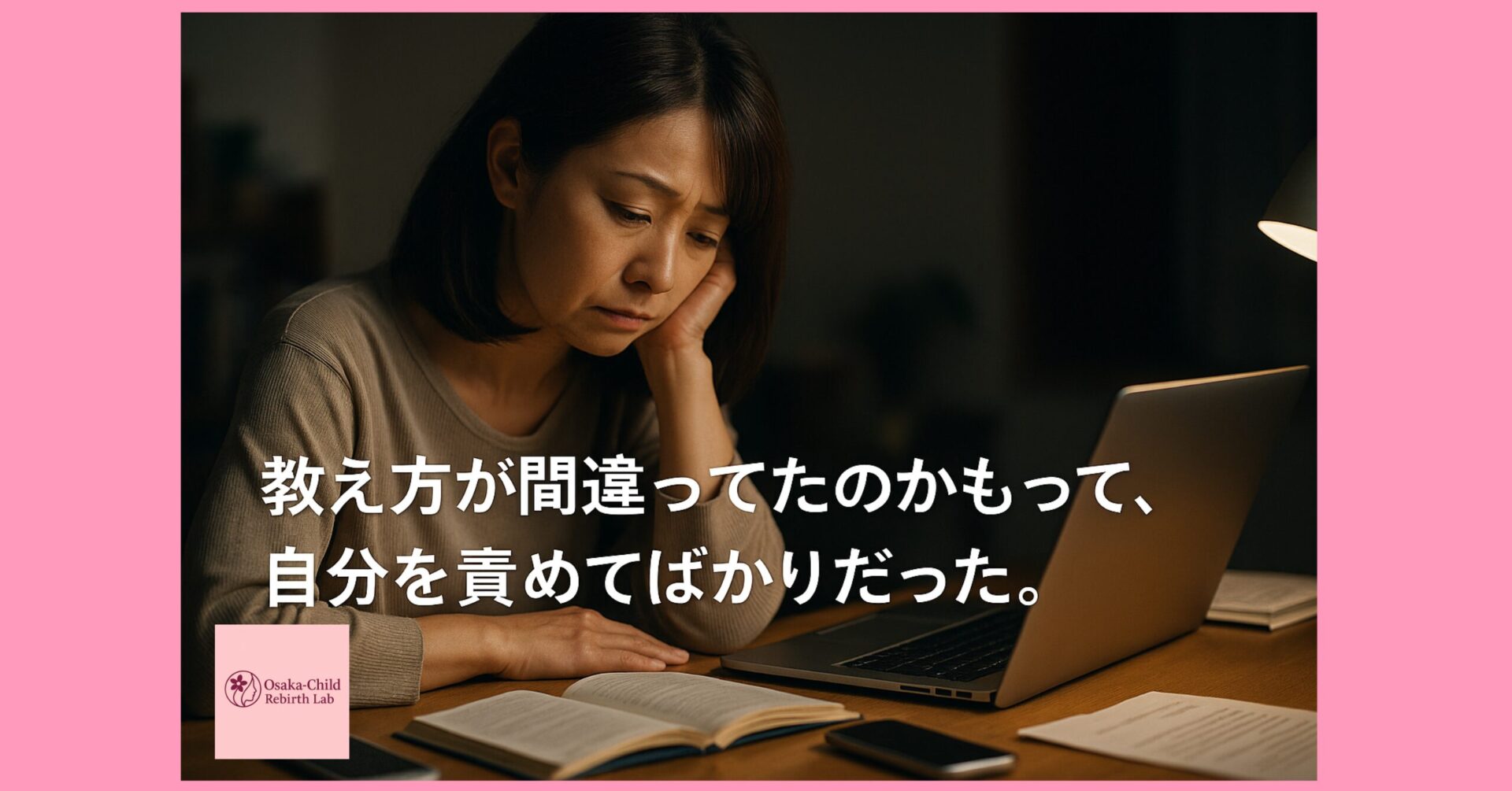
一生懸命に教えてきた。
それでもうまくいかない日々が続くと、
「やり方が悪かったのかな」と、
自分の関わりを疑う気持ちが大きくなっていった。
- 何が足りなかったんだろう。
- どうすれば伝わったんだろう。
そんなふうに、
あなたは毎日を自分のやるせなさを振り返っては
ココロが重くなっていました。
ここでは、
そんな
- 「自責の入り口」に立ったときの迷い
- 少しずつ見えてきた変化の視点
を一緒にたどっていきます。
「ちゃんと教えてるのに…」伝わらない葛藤
- 時間をかけて説明してきたつもりだった。
- 順序立てて、わかりやすい言葉を選んで、何度も同じところをくり返して。
それでも子どもが止まってしまうと、
「どうして?」という気持ちがこみ上げてくる。
がんばって教えているのに、
まったく届いていないような感覚。
あのときのむなしさは、
今でも胸に残っている。
でも、責めたかったわけじゃなかった。
ただ、
「わかってほしい」と願っていただけだった。
その思いがすれ違うたびに、
自分を責める声がどんどん強くなっていった。
あなたがこの記事で知ったのは、
学習障害(LD)や発達の特性によって、
情報の受け取り方に「見えないズレ」があること。
こちらの伝え方に問題があるというより、
子どもの理解のプロセスに違いがあるという視点でした。
「伝わらなかった」ではなく、
「伝わりにくかっただけ」。
この構造を知ってもらえると、
あなたがすべて自分で教えてあげないとという
ココロのストレスが軽くなっていきます。
グレーゾーン?発達障害?診断より先にできること
「発達障害かも」
そんな言葉が頭に浮かぶたびに、
すぐに調べようとしたけど、
どこかで止まってしまっていました。
- 診断を受けるべきか、
- それとも今は様子を見たほうがいいのか。
その間でずっと揺れていたでしょう。
誰かに相談しても、
「診断はされていますか?」と
聞かれることが不安で、
声に出せないこともありましたよね。
どこからが「グレーゾーン」なのかもよくわからず、
ただ焦りばかりがふくらんでいました。
でも本当は、
診断があるかどうかよりも、
「この子が今、何に困っているのか」を知りたかったんです。
そして、どうやって関わればいいのかを知りたかった。
その願いのほうが、
ずっと切実だった。
診断がなくても、
今の様子からできることはたくさんあります。
- 「言葉を変えてみる」
- 「タイミングをずらしてみる」
──ほんの少しの工夫でも、
空気が変わっていくことがあるんです。
名前をつけるよりも前に、
できる関わりを始めていい。
そう思えたとき、ココロの中にひとすじの光が差してきます。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「やる気がないわけじゃないと思うのに…」
そんなふうに、子どもの「できなさ」の理由が見えなくて苦しくなることはありませんか?
👉 読み書き・計算が苦手な子にある「特性」と、その対応法をくわしく見る
-

-
参考学習障害とは?読み書き・計算が「できない理由」と家庭でできる対応法【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「どうしてこんなに教えてるのに、できないんだろう」 そう思ったあとで、 つい声を荒ら ...
続きを見る
普通学級で本当に大丈夫?迷い続けた理由
学校の授業についていけていない様子を見て、
あなたは「このままでいいのかな」と
不安になってきました。
「支援級のほうがいいのかも」と思っても、
すぐに決めるのがこわくて、
ただ迷い続けていた日々もありますよね。
- 普通学級が合っているのか、
- それとも支援が必要なのか。
情報が多すぎて、
何を信じればいいのかわからなくなっていた時期もありました。
先生に相談しても、
「もう少し見ていきましょう」と言われるばかりで、
判断を任されてしまうことがつづきます。
その「はっきりしない状態」がいちばんつらくて、
立ち止まってしまいます。
でも、進む道が1つしかないわけではありません。
学習障害(LD)や発達の特性があっても、
環境を整えることで安心して学べる子も多くいます。
どのクラスにいるかよりも、
「この子が安心できる場所はどこか」を見つけることが
いちばん大切なんですよね。
- 支援級か
- 普通学級か
という
「枠」に縛られずに、
「この子がその子らしく過ごせる選択肢」を
考えられるようになったとき、
ようやく前に進めたような気がしました。
“普通の環境で頑張らせたい”と願うあなたへ
- 「この子には『まだ』普通学級でやれるかも」
- 「でも、やっぱり苦しそう…」
──そんなふうに、願いと迷いのあいだで立ち止まっているあなたへ。
「国語も算数もわからない──学習障害の子に戸惑っていた私が、『安心して関われる母』に変わっていく──3週間集中再安心サポート」は、
「どの環境が合っているか」よりも先に、
「どう関われば安心できるか」を母の視点から整えるサポートです。
「この子に合った関わり方」を、今ここから一緒に探してみませんか?
国語・算数の「つまずき」に合った教え方とは?
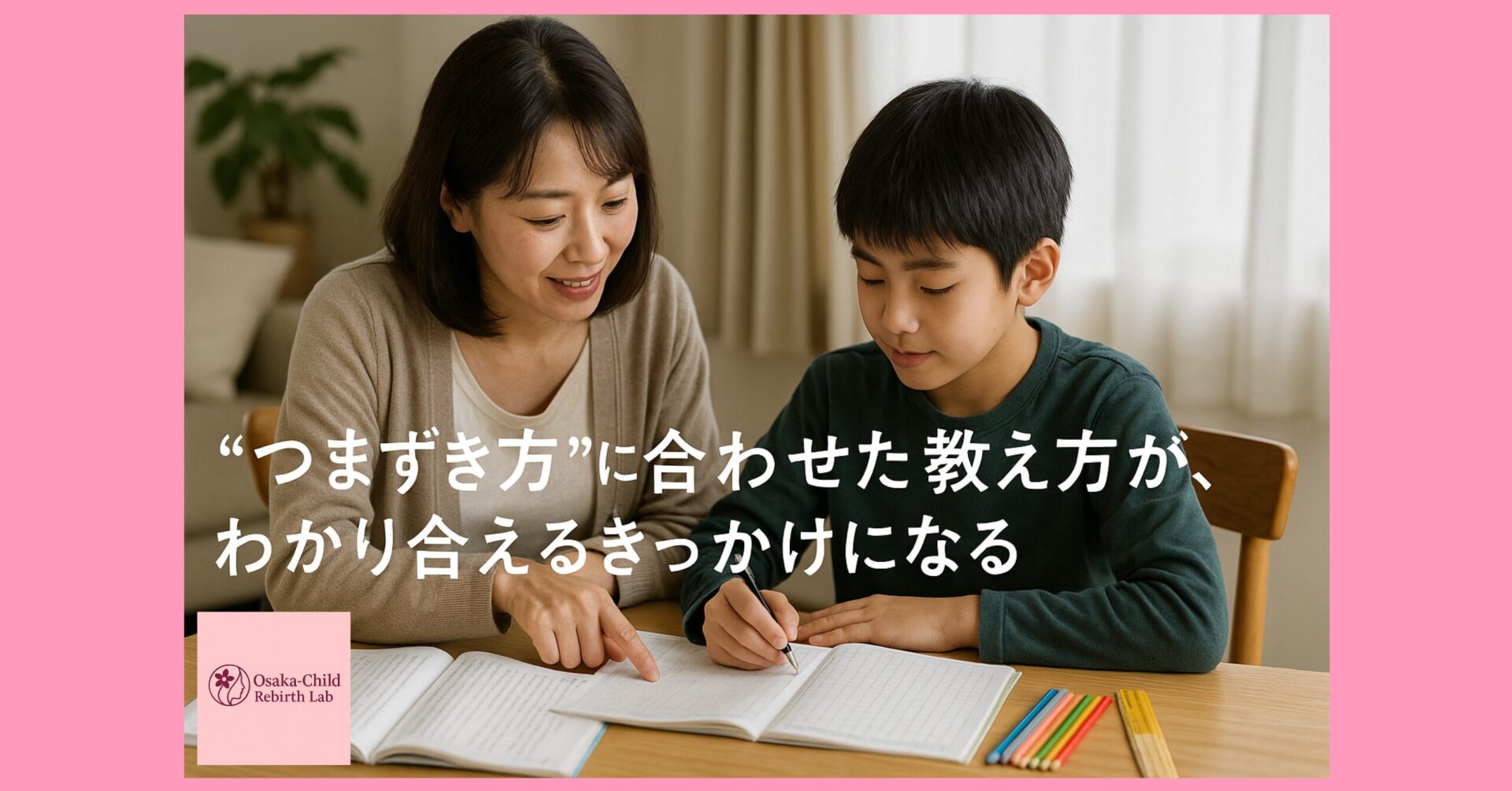
どれだけ時間をかけても、
読み書きや計算が身につかない
そのつまずきの背景には、
「学習障害(LD)」という認知の特性があります。
- 叱っても直らない
- 努力してもできない
そんな現実を前に、
どうしても親はつい感情が揺れてしまいます。
でも、
視点を変えてみたら、
ちがう関わり方が見えてきました。
このキャプションでは、
「国語・算数」のつまずきに合わせた具体的な教え方を整理していきます。
【国語】音読が苦手な子には「短く区切る」読み方から始める
「つっかえてばかり」の読みにイライラせず、
「区切る・止まる・確認する」を一緒にくり返すコツ
音読を聞いていると、
何度もつっかえる声にモヤモヤしてきました。
「ちゃんと読めてないじゃない…」と感じるたびに、
どうしていいかわからなくなっていたんです。
でも、本人はふざけていたわけではありません。
目で文字を追っても、
それを声に出すのが難しいという感覚があります。
ある日、
「ここまでで一回止まろうか」と区切って読ませてみたら、
子どもの表情が少し変わったんです。
ポイント
短く分けてあげると、
読みやすくなり、
戸惑いが減っていきます。
学習障害(LD)のある子には、
「文字を音に変える」プロセスでつまずきが出ます。
一気に読ませようとするのではなく、
「区切ってもいい」という関わり方で子どもはココロが楽になり、
もっているポテンシャルを最大に動かすことができます。
「読み」「書き」「漢字」に苦手さがある子には、「音と形」をつなぐ工夫を
- 音読が苦手
- ひらがなを何度も間違える
- 漢字が全く定着しない
国語でつまずく子どもには、
共通する「記憶のつながりにくさ」があります。
- 目で見た形
- 耳で聞いた音
- 手で書いた動作
が、
それぞれバラバラに記憶されてしまい、
うまく統合できていないのです。
そんな子どもに対しては、
ただ書かせるのではなく、
- 「声に出す」
- 「指でなぞる」
- 「リズムで覚える」など、
複数の感覚を同時に使う方法が効果的です。
たとえば──
- 読みが苦手なら、親子で交互に読む「リピート読み」
- 漢字は「へん・つくり・全体」を分けて説明し、指で空書きしながら記憶
- 見て覚えるのではなく、声に出しながら「音→形→意味」をセットで定着
記憶の整理を「外側から手伝う」意識が大切です。
子どもが
「やってみようかな」と
思える関わり方が、力になります。
【算数】文章題がわからないときは「絵や図で見える化」して伝える
言葉の理解が追いつかない子には、
「数」より先に
「場面のイメージ」を共有する工夫を
算数の文章題になると、
急に手が止まりました。
「何がわからないの?」と聞いても、
言葉が返ってこないまま時間だけが過ぎていきます。
一文ずつ読ませても、
結局どう考えればいいのかがつかめない様子で…。
でも、
それって「式が立てられない」のではなく、
場面が思い浮かばなかったんだと気づいたんです。
「3人ずつバスに乗ってるとしたら、こんな絵になるね」と
紙に描いてみたら、
スッと理解が進みます。
数字ではなく、
状況をイメージできることで、
子どもがようやく前に進めていけます。
学習障害(LD)の子には、
言語の処理よりも「具体的な場面」を先に描いてあげることが、
考える入口になることがあります。
絵や図にするだけで、
「なんとなく難しい」が
「やってみようか」に変わっていけるのです。
計算・時計・文章題につまずく子には、「順番と意味」を補う教え方を
- 数が増えると混乱する
- 文章題になると手が止まる
- 時計の読み方があやふや
こうした算数の苦手さには、
- 「順序」
- 「操作」
- 「言葉」
のつながりがうまくいかないという特徴があります。
そのため、
- 計算手順を視覚化すること
- 量や数のイメージを具体的に持たせること
がポイントになります。
具体的には──
- 計算は「左から読む」「右から書く」などのズレを補正しながら、色分けや図を活用
- 文章題は、「なにを聞かれているか」→「何がわかっているか」の順に線を引きながら分解
- 時計は、実物の時計を使い「短針は時間」「長針は分」を手で動かして体感する
ひとつひとつの手順を、
頭の中だけで処理しきれない子もいます。
だからこそ、
- 見せて
- 動かして
- 声にして教えること
が大切なのです。
【共通】ノートが書けない子には「書かせる」より「選ばせる」サポートへ
マス目・記述・まとめが苦手な子には、
「書く工程」そのものを見直して合った形を探る
「ノートに書いて」と言っても、
全然進まないままページが真っ白。
何をどう書けばいいのか、
最初からわからなくなっていたようでした。
「何か書きなさい」と言い続けていた頃は、
お互いにイライラするばかりだったと思います。
でも、あるとき
- 「ここに○つけてみて」
- 「なぞるだけでいいよ」
と声をかけてみたら、
少しずつ動けるようになっていきます。
学習障害(LD)の子にとって、
「書くこと」はアウトプットの手段である前に、
大きな「負担」になっています。
だからこそ、
「書かせる」のではなく
「選ばせる」ことで、
安心して取り組める土台が整っていくんです。
「この子なりのやり方」で取り組めると、
初めて「やってみよう」という気持ちが自然に湧きあがる反応が見えてきます。
叱らずに教えるには、「『わかった』サイン」を見逃さないことから
つまずきが重なると、
どうしてもイライラしてしまいますよね。
でも、叱ったあとで
「なんで怒ってしまったんだろう」と落ち込むことも、
何度もありました。
そんなあなたに気づいて欲しいのは
「できないこと」よりも、
「わかったときのサイン」を見逃していたことでした。
たとえば──
- ふっと表情が明るくなる
- 手が止まっていたのが動き出す
- 「あっ、そうか」と口にしたとき
この「気づきの瞬間」を受け止めることが、
子どもの意欲につながります。
一緒に喜べる関係があるからこそ、
また「やってみよう」と前を向けられるのです。
無料診断|あなたの“心のパターン”を知る
「何度言っても伝わらない…」
その苛立ちの奥に、
「伝え方」ではなく「わかり方」の特性が隠れています。
📩 LINEで「発達障害 学習障害」と送ってください。
「うちの子はどこでつまずいている?」がわかるヒントが届きます。
学習障害の子どもに「伝わる関わり方」とは

- 何度伝えても届かない。
- 一緒に向き合ってきたつもりなのに、うまく伝わらない。
そんな日が続いて、あなたの中にも疲れがたまってきていませんか?
「この子には、どう関わればよかったんだろう」
そう思って立ち止まる瞬間があったなら、
それは「まっすぐ向き合ってきた証」だったのです。
ここでは、
今のあなたが「少しラクになるための視点」をそっと差し出していきますね。
うまくいかなくて苦しいままのあなたのために。
“もう怒りたくないのに…”と悩みながら関わっているあなたへ
- 「宿題になると不機嫌になる」
- 「ノートがぐちゃぐちゃで提出できない」
──そんな日常のひとつひとつに、つい怒ってしまう。
本当はわかってる。
子どもも困ってる。
でも、どう関わればいいのかわからない。
「教える」ことに必死で、「伝わる工夫」を考える余裕がなかっただけ。
《国語も算数もわからない──学習障害の子に戸惑っていた私が、『安心して関われる母』に変わっていく──3週間集中再安心サポート》は、
宿題やノートでつまずく背景を丁寧にひもときながら、
親子の「伝わる関係」を取り戻していくサポートです。
こんな方におすすめです
- ノート・宿題のたびに怒ってしまい、自己嫌悪をくり返している
- 「教えてるのに、なぜできないの?」と戸惑っている
- 支援や診断に踏み切れず、「普通」と「特性」の間で揺れている
- 子どもと笑って過ごせる時間を、もっと増やしたい
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 2月7日(土)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと2名様限定』
※銀行振込限定・先着順
▶ ノートと宿題がつらかった日々から、「伝わる関係」を取り戻す3週間へ
そして──
子どもとの関わりに向き合ったあなたが、
今度は「わたし自身」と向き合ってみたいと思ったとき。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
「母としての安心」を出発点に、
「わたしらしい人生」を再設計する3週間。
これまで支えることを優先してきた私が、
本音で「どう生きたいか」に立ち返る時間です。
- 子育てだけではない自分の軸を見つけたい
- 「このままで終わりたくない」と感じている
- 「私のこれから」に向けて、動き出したい気持ちがある
このプログラムでは、
「誰かのため」から「私の人生」へ視点を移していく支援を行います。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
「国語」と「算数」で違う「つまずき方」を見てみる
- 国語では読み間違いが多く、
- 算数になると急に黙り込む。
教科によって違う反応に、
どう関わればいいのか混乱したことがありますよね。
「ちゃんと伝えたのに…」という無力感が、
ココロの奥に残っていたこともあると思います。
でも実際には、
それぞれの教科で「求められている力」がまったく異なります。
- 国語では、文章の意味を理解しながら記憶する力
- 算数では、順序を整理して考える力や、数のイメージを扱う力
その子にとって、
どの部分が負担になっているかは、
内容によって変わってくることもあるんです。
学習障害(LD)や発達グレーゾーンの子どもには、
このような教科ごとの「つまずきの違い」が明確に出やすいという傾向
があります。
- 「この子は『順番』を追うのが苦しかったのでは?」
- 「この言葉の意味があいまいだったのでは?」
そうやって、
あなたが「つまずきの背景」を探ろうとしていること自体が、
すでにとても尊い関わりです。
「できない」を見つけるのではなく、
「どこが難しかったのか」を見ようとするその視点が、
子どもを支える大きなかかわりになります。
ノートや宿題が進まないときにできること
宿題のページを開いたまま、
ただ時間だけが過ぎていく。
あなたはその様子を見て、
どこから声をかければいいのかわからなくなっていました。
「やる気がないわけじゃない」と感じていても、
毎日が続くと、
あなたのココロも折れそうになりますよね。
実は、
「進まない」の裏には、
「何をどうすればいいのかわからない」が隠れています。
- 最初の一文字が書けなかったり
- どの問題から取りかかればいいのかが見えなかったり
そんな状態で、
子どもはずっと止まっていたのです。
- 「ここだけ一緒にやろうか」
- 「このページまでで今日はおしまいにしよう」
あなたがそう声をかけられたなら
子どもの表情がわずかにゆるむ反応を見ることができます。
学習障害(LD)のある子どもにとって、
「何をすればいいのかが明確であること」が
ココロの安心につながります。
少しだけ見通しを示してあげること。
それが、
あなたのまなざしに込められたやさしさになり、
子どももできることに意識を向けられるようになります。
怒る前にできる「ちょっとした切り替え」
- 「また忘れてきたの?」
- 「この前も言ったよね?」
そう言いそうになって、
口を閉じたことが何度もありました。
わかっているのに感情が出てしまうことほど、
あとで自分を責めたくなりますよね。
でもそのたびに、
あなたは立ち止まろうとしていましたよね。
怒らない関わりができるなら…と、
いつも考えていたのです。
そんなとき、
ほんの少しだけ問いかけを変えてみる。
- 「どこで止まったの?」
- 「ここまではがんばってたね」
正しさではなく、「その子の歩幅」に目を向けるようにしてみる。
それだけで状況が一気に良くなるわけじゃないけれど、
あなたが怒りを抑えようとしたその瞬間にも、
ちゃんと意味があるんです。
うまくできなかった日でも、
向き合おうとした自分を、そっと認めてあげてくださいね。
少しずつ変わり始めた親子関係

いつもピリピリしていた空気が、
ふとした瞬間に
少しだけゆるんでいるように感じることはありませんか?
それは、
あなたがずっとこの子に向き合ってきた反応です。
どんなにうまくいかない日が続いても、
あなたは毎回、
立ち止まって、考えて、また向き合ってきた。
その積み重ねが、
子どもとの関係に静かににじみはじめているんです。
ここでは、
「変わった」と言いきれるものではなく、
「少しちがってきた」と感じたあなたのその感覚に、
そっと言葉を添えていきます。
怒る回数が減った・教える声がやわらかくなった
前より、怒る回数が減ってきた。
そんな実感が芽生えた瞬間はありませんか?
- 気づけば、叱る前に言葉を選んでいたり、
- 子どもが戸惑っているときに、少しだけ待てるようになっていたり。
それは、「こうしよう」と決めて実行したからではなく、
あなたがこの子に寄り添いたいと、
ずっと願っていたから生まれた変化。
学習障害(LD)や発達の特性をもつ子どもにとって、
「伝わりやすさ」よりも、
「伝えるときの空気」のほうが、プラス作用があります。
子どもに対して、
あなたの声がやわらかくなれると、
子どもの中の「構え」が、
ほんの少しずつほどけていきます。
子どもが「やってみよう」と言えた瞬間
- 「ムリ」
- 「できない」
そんな言葉ばかりだったあの子が、
ある日こうつぶやいた。
「やってみようかな」
それは、
誰にとっても見過ごしそうなひとことだった。
でも、
あなたにとっては、
あの日の空気をまるごと変えるような言葉だったのです。
きっとその背景には、
あなたが「待ってくれていた時間」があった。
- 急かさず
- 責めず
- 怒らずに、
そばにいてくれた人がいたからこそ、
出てきた言葉でした。
学習障害(LD)のある子どもにとって、
「挑戦すること」は
「傷つく覚悟」とセットです。
だからこそ、
その一言が出てきたということ自体が、
関係の中に育ってきた信頼の反応です。
「学ぶのが怖くない」と思えるようになった日
学ぶことは、
子どもにとって希望だけではありません。
- うまくいかなかった記憶
- 注意された体験
- 失敗への不安…。
そうしたものが重なって、
「勉強したくない」の言葉になって現れてきます。
けれど、
あなたが積極的に子どもを見守れるようになると、
前ほど学ぶことを怖がっていない気がする。
- 「読んでみたい」
- 「ノート開いてみようかな」
そんな小さな声が、
日常の中に混ざっていたことに。
それは、
あなたの関わりが、
成果ではなく
「存在そのもの」を認めていたからです。
学習障害(LD)のある子どもは、
「できた」よりも
「わかってもらえた」と感じた瞬間に、
前を向きはじめます。
そして
その「わかってくれる人」が、
あなただったということ。
それが、この子の学びの土台になっているです。
「わかってもらえた」が始まりだった──そう感じたあなたへ
「宿題の前に泣いていたあの子が、今日は自分からペンを持った」
──その小さな一歩に、胸がいっぱいになった。
「国語も算数もわからない──学習障害の子に戸惑っていた私が、『安心して関われる母』に変わっていく──3週間集中再安心サポート」は、
「学ぶのが怖くない」と思える関係を、
家庭の中で少しずつ育てていくサポートです。
「できる・できない」ではなく、「伝わる・伝わった」を積み重ねていきませんか?
「わからない」に戸惑っていた私が、「安心して関われる母」に変わっていくまで

あの頃、
私はずっと「どうすればいいのか」が
わからずにいました。
勉強が苦手な子どもを見るたび、
- 怒るわけでもなく笑うわけでもなく
- ただ黙り込んでしまう自分。
どう向き合えばいいのかも、
何を変えればいいのかも見えなくて。
気づけば毎日が「正解探し」になっていたのです。
「わからない」という感覚は、
思った以上に不安を引き寄せます。
- 何が足りないのか
- どこが間違っているのか
私がちゃんと教えられていないのか、
そもそもこの子に何かあるのか──
そんなふうに
答えの出ない問いに飲み込まれて、
気づけばずっと立ち止まっていました。
でも、
本当は「答え」を求めすぎていました。
正しさより、安心が必要だった。
そう思いはじめたとき、
「支える」という言葉の意味が少し変わって見えてきます。
ここでは、
あなた自身の視点が
ゆっくりと変わっていく過程と、
「関わり直す」というあたたかな始まりについて、
等身大の気づきとして記していきます。
「国語も算数もできない子」に、どう関わればいいのかわからなかった
- テストで0点を取った日も、
- ノートが真っ白だった日もありました。
ふざけているわけじゃないのに、
やればやるほどできなくなる。
その様子を見て、
最初は戸惑いながらも
あなたは「もうちょっと頑張って」と声をかけていました。
でも、
どう頑張ればいいのかがわからないまま、
空回りばかりが続いていったんです。
あるときから、
教えるのが怖くなりました。
何をどう伝えても、
またできない結果を見るのがつらくて。
- 励ます言葉も
- 叱る言葉も
どちらもこの子を傷つけてしまう気がして、
だんだんと口を閉ざすことが増えていきました。
「関わりたいのに、どう関わればいいかわからない」
そのジレンマに立ち尽くしたまま、
日々の勉強時間がどんどん苦痛になっていきました。
誰かに相談するのも、正直ためらっていました。
「親なんだから、ちゃんと教えなきゃ」
そういう無言のプレッシャーが、
ずっとココロの中に残っていたからです。
うまく言葉にできなかった「焦り」と「罪悪感」
- 周りの子はスラスラ読み書きできているのに、うちの子は音読もおぼつかない
- 計算も、ひとつひとつ順を追って教えたのに、次の日には全部忘れている
そんな姿を見るたびに、
ココロの奥がギュッと締めつけられた。
「どうしてできないの?」と聞きたいわけじゃない。
でも、
その「できなさ」を見つめ続ける自分の気持ちに、
言葉が見つかりませんでした。
イライラや焦りが募る一方で、
それを表に出せば傷つけることもわかっていて。
だからこそ、
自分の感情を押し殺していたのです。
- 「私がもっと早く気づいてあげれば…」
- 「他のやり方があったんじゃないか…」
そんなふうに、
自分を責める言葉が自然と浮かんでしまう。
本音では、
誰かに「わかるよ」って言ってほしかった。
でもそれが言えずに、
孤独なまま、
同じループの中でぐるぐると悩んでいました。
「この子に合う関わり方」を、ひとりで見つけるのは難しかった
- どんな教材がいいのか
- どんな言い方なら伝わるのか
ネットで検索して
書籍も読んで
たくさんの情報を集めました。
でも読めば読むほど、わからなくなっていったんです。
- 「このやり方が合わなかったら?」
- 「また傷つけてしまったら?」
そんな不安が頭から離れず、
実際には何も試せない日が続きました。
私自身が、
安心できていなかったのです。
「これでいい」と言える確信がないままでは、
何をやってもうまくいかない。
だからこそ、
「ひとりでなんとかしようとしない関わり方」が必要でした。
もし、
「この子に合う関わり方を一緒に探していける場所」があったなら
──そのときのあなたは、今、すがるような気持ちで手を伸ばそうとしています。
次のセクションでは、
その安心の足がかりとなるサポートについて、
くわしくご紹介していきます。
「安心して関われる母」になるための3週間集中再安心サポート
「国語も算数もわからない──学習障害の子に戸惑っていた私が、『安心して関われる母』に変わっていく──3週間集中再安心サポート」は、
母親が自分のまなざしを整えながら、
子どもの「覚えられない・できない」と向き合える関係を
築いていくための心理支援プログラムです。
誰かに教わるようなサポートではなく、
母自身が「わかってあげられる関わり方」を取り戻していく時間。
変わるのは、
子どもよりも、
母親の「ココロのまなざし」です。
Week1|がんばっていた母のココロをほどく週
- 「なぜ怒ってしまうのか」
- 「どうして余裕がなくなるのか」
──その背景には、母自身の不安や焦り、自責の思いが複雑に絡み合っています。
最初の1週間では、
その感情を安心して吐き出し、
整理していくところから始めます。
「私だけじゃなかった」と思える共感の中で、
まず母親自身が落ち着いていくことを大切にしていきます。
Week2|学習障害の特性理解と「つまずき」の整理
2週目は、
学習障害(LD)や発達グレーの子どもが
「なぜ国語や算数でつまずくのか」を
具体的に理解していく週です。
- 覚えられない
- 続かない
- 書けない…
その背景には「特性」によるつまずき方があります。
それを丁寧に言葉にしながら、
「がんばれ」で済ませず、
どう寄り添えば安心できるのかを一緒に探っていきます。
Week3|関係を整える「まなざし」を育てていく
最後の週は、
「この子らしさ」に合わせた接し方や学習環境を、
日常に落とし込んでいく時間です。
- 叱らなくても伝えられる声かけ
- 子どもが前を向けるようになる関わり方
- 宿題時間の安心のつくり方
──母親が変わることで、子どもとの関係に「待てる余裕」が育っていきます。
特別なスキルは不要です。
ただ、
あなた自身が安心して向き合える「土台」を整えることから、
すべてが始まります。
今まで見えていなかった「わが子の姿」や、
「ほんとうに届けたかった言葉」が、
少しずつ輪郭を持ちはじめる。
その瞬間に出会うための、3週間です。
“伝わらない…”と悩んでいた母へ|安心して関われる3週間サポート
「国語も算数も、どう教えたらいいかわからない」──
そんな悩みに向き合ってきたあなたへ。
「子どもに合った教え方」と、「安心して関われる私」を一緒に育てていく、
3週間集中のオンラインサポートをご用意しました。
- 発達障害
- 学習障害
- グレーゾーン…
診断の前でも後でも、「今できること」から整えていけます。
あなたとお子さんにとっての「学び直しのはじまり」として、受け取ってください。
まとめ|「ちゃんと伝わる関係」を、あきらめたくなかった
- ノートに手が進まない。
- ひらがなを忘れて、漢字を書けなくて、また怒ってしまった。
「何度言ったらできるの?」って、わかってるのに声が荒くなる。
…そうやって、自分を責める夜ばかりだった。
勉強のたびにイライラして、
宿題を前に子どもが黙り込む。
やる気がないわけじゃないと、
どこかで信じたかった。
でも、
伝わらないことに疲れてしまって
どこから向き合えばいいのか、見失っていた。
- ほんとは、変わりたかった
- もっとちゃんと、やさしく接したかった
でも、それがうまくできなかった。
――そんな日々を、誰にも言えずに、あなたは1人で抱えてきましたよね。
この記事ででお伝えしてきたことを、少しだけ整理します。
この記事のまとめ
- 学習障害(LD)には「伝わりにくさ」という特性がある
- ノートが書けないのは、やる気の問題だけではない
- つまずきが見えたときこそ、母のまなざしを整えるチャンスになる
- 叱る前に立ち止まる視点が、親子の関係を守ってくれる
- 特別な指導より、日々の関わりの中で「伝わる」経験を重ねていける
誰よりもわが子を思ってきた。
でも、その思いが届かなくて、苦しかった。
そう感じてきたなら、
まずはあなた自身の気持ちから整えていいんです。
「どうしてこんなに怒っていたのか」
──その理由が、少しだけ見えてきた気がする。
国語も算数も伝わらないことが、
いつの間にか私の焦りや不安を増幅させていた。
この関わり方じゃ、きっと苦しかった。
わが子も、
私自身も。
そんな関係に立ち止まる時間としてご用意しているのが、
「国語も算数もわからない──学習障害の子に戸惑っていた私が、『安心して関われる母』に変わっていく──3週間集中再安心サポート」です。
- ひらがな
- 文章題
- ノート指導
──「できなさ」の背景を「努力不足」ではなく、認知の特性として理解し、
その子に合った
- 「伝え方」
- 「声かけ」
を、母親のまなざしから整えていく時間です。
ひとりで背負わなくていい。ここから、関わりを見直していけます。
正解を探すんじゃなくて、
「一緒に向き合っていく関係」を育てていく──そんな3週間を届けられたらと思います。
「『教え方じゃなくて、伝え方だったんだ』──そう気づいた今だからこそ
- 「何度も言ったのに、また間違える」
- 「宿題を前に、今日も不機嫌になる」
──そんな毎日に戸惑い続けてきたけれど。
「この子のやり方」に気づけたとき、
関わりが変わり始めることがあります。
「国語も算数もわからない──学習障害の子に戸惑っていた私が、『安心して関われる母』に変わっていく──3週間集中再安心サポート」は、
「できなさ」の背景をていねいにひもときながら、
叱る前に立ち止まれる関係づくりをサポートします。
こんな方におすすめです
- 「私の教え方が悪いのかな」と責めてきた
- ノートや宿題を前に、毎日ピリピリしてしまう
- 子どもの「困りごと」に向き合いきれず、苦しくなっている
- 支援を受けるより、まず「伝え方」から整えたい
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 2月7日(土)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと2名様限定』
※銀行振込限定・先着順
ネットバンキングのご利用で、今すぐ開始することが可能です。
▶ 怒る関係から、「伝わる関係」へ切り替える3週間サポートへ
そして──
子どもの「わかってほしい」に応えてきたあなたが、
「わたしの人生」にも耳を澄ませたくなったとき。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
「母」としての歩みを力に変えて、
「わたし」としての生き方を再設計する3週間。
- 「支える日々」から少し距離をとってみたい
- 子どもと向き合う中で、自分のことも見つめ直してきた
- これからは「私の人生」にも向き合っていきたい
このプログラムでは、
「母」を土台に、「わたし自身」へと還る時間をつくっていきます。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
▶︎ 株式会社Osaka-Childの母親・子ども支援まとめを見る(心理・不登校・身体調整など・左の▼をクリック)
株式会社Osaka-Childの3人の子育てでストレスがたかい40代女性の心理作用をととのえるカウンセリング
子育ての真っ最中で、仕事と家庭の間で揺れ動いている女性の皆さんへ。私たちのカウンセリングサービスは、あなたのためにあります。もし心の中で悩みや生きづらさを感じている場合、それは特別な心のケアが必要な証拠です。株式会社Osaka-Childとして、日々の生活で直面している困難を理解し、その解決をサポートします。
私たちは、あなたが人生の困難に立ち向かう勇気を見つけるための安全な空間を提供します。当社のプロフェッショナルなカウンセラーは、あなたの問題や感情に深い理解を持ち、あなたを尊重します。ここでは、あなたの気持ちを自由に表現し、過去の影響から解放され、自分自身を再発見することができるでしょう。
カウンセリングは、心理システムの問題を共に解決するための有力な手段です。私たちのカウンセリングでは、まずじっくりとあなたのお話を聴きます。過去の経験やトラウマ、日常生活でのストレスなど、あなたが抱える悩みや心の中での葛藤を理解し、共感します。その後、適切なカウンセリング技法を用いて、心の中のブロックを取り除き、自分自身と向き合い、成長するためのサポートを行います。
初めての方でも、私たちのサービスを利用することはとても簡単です。当社のウェブサイト上で、カウンセリングセッションの申し込みをすることができます。また、具体的な問い合わせや不明点がある場合は、お気軽に当社までメールをお送りください。
心の中で抱える悩みや生きづらさに苦しんでいるなら、あなたは一人ではありません。株式会社Osaka-Childは、あなたが自分自身の価値を見つけ、生活の質を改善するためのサポートを提供します。カウンセリングを通じて、あなたがより健康的で充実した人生を歩む手助けをいたします。
カウンセリングのプロセスは、あなたの個別のニーズや目標に合わせてカスタマイズされます。私たちは、あなたが心地よく感じるペースでサポートを提供し、尊重と信頼の関係を築くことを大切にしています。カウンセリングを通じて、自己理解を深め、心の中の問題を克服し、より充実した人生を築いていきましょう。
あなたが心の支えを必要としているなら、ぜひ株式会社Osaka-Childのカウンセリングにお越しください。私たちがあなたの側にいて、共に問題を解決し、より健康で幸せな未来を築くお手伝いをいたします。一歩踏み出す勇気を持ってください。私たちと一緒に、新しい人生の扉を開いてみましょう。
\本気で変わりたい40代母親へ/
子どもとの関係、自分の人生、どちらもあきらめない方法があります。
33万円・50万円の本格プログラムで、臨床心理士とマンツーマンであなたの「再スタート」をサポートします。
現在【銀行振込の方限定で割引案内】をご用意しています。
🔸 本日 2月7日(土)23:59まで のご入金分までのご案内となります。
🔸 『あと2名様限定』
※銀行振込限定・先着順での受付となります。
小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援事業をする株式会社Osaka-Childとは?




【 復学率100% 】小中学生復学支援Osaka-Childの支援策とは?
こちらもCHECK
-

-
【 復学率100% 】小中学生復学支援Osaka-Childの支援策とは?
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
【堺市】不登校の子どもをサポートする!Osaka-Childのカウンセリング支援
こちらもCHECK
-

-
【堺市】不登校の子どもをサポートする!Osaka-Childのカウンセリング支援
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 Osaka-Childは、堺市にある不登校の子どもたちとその家族を支援するカウンセリ ...
続きを見る
復学支援の専門家が教える、家庭学習支援のポイントと効果的な学習方法
株式会社Osaka-Childの心理技法・心理検査一覧
株式会社Osaka-Childの障害一覧
株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:母親のメンタルサポート


支援内容
1. オキシトシン分泌促進で子どもに接する母親の専門的なカウンセリング
2. 胎児期から乳児期のオキシトシン分泌状態の再経験
3. 母親の子育ての疲れやストレスの軽減
4. 母親の胎児期・幼少期の体験のインナーチャイルドの修正
5. 母親の親子関係をカウンセリングにより気づかせる
6. カウンセリングによって母親の生き方を主体性を持たせる
7. 幼少期に得られなかった愛着の再構築
8. 個人に合った最適な心理システムの再起動
9. 母親を子どもの親から一個人としての存在の獲得
10. 愛着育成による自己肯定感の向上
11. 人生軸上でインストールした感覚ー認識の空洞化
母親のメンタルサポートの具体的なアプローチ
株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、母親のメンタルサポートを提供しています。以下に、具体的な支援内容を説明します。
- オキシトシン分泌促進で子どもに接する母親の専門的なカウンセリング オキシトシンは愛着や絆の形成に関与するホルモンであり、母親と子どもの関係を深める重要な役割を果たします。カウンセリングにおいては、母親がオキシトシン分泌を促進する方法や子どもとの関わり方について学びます。
- 胎児期から乳児期のオキシトシン分泌状態の再経験 母親が胎児期から乳児期の自身のオキシトシン分泌状態を再経験することで、子どもとの関係性や愛着形成に関する理解を深めます。これにより、母親はより適切な愛着行動を身につけ、子どもの安定した成長を支援します。
- 母親の子育ての疲れやストレスの軽減 子育てにおける疲れやストレスは母親のメンタルヘルスに大きな影響を与えます。専門的なカウンセリングにより、母親の疲れやストレスを軽減し、心の健康を保つための具体的なケア方法を提供します。
- 母親の胎児期・幼少期の体験のインナーチャイルドの修正 母親の胎児期や幼少期におけるトラウマや負の体験は、子育てに影響を及ぼすことがあります。カウンセリングにより、母親は自身のインナーチャイルド(内なる子どもの存在)の修正を通じて、子育てにおける負のパターンを変容させます。
- 母親の親子関係をカウンセリングにより気づかせる 母親の親子関係に潜むパターンや影響をカウンセリングを通じて明示し、母親自身がその関係性に気づくことを支援します。これにより、母親はより良好な親子関係を構築し、子どもの成長を促進します。
- カウンセリングによって母親の生き方を主体性を持たせる 母親が自身の生き方を主体的に選択し、子どもとの関係性をより意識的に築いていくことを支援します。母親の個別のニーズや目標を考慮し、適切なカウンセリングプランを策定します。
- 幼少期に得られなかった愛着の再構築 母親が幼少期に得られなかった愛着を再構築することで、自己肯定感や安心感を向上させます。カウンセリングにおいては、母親が自身の愛着スタイルや関わり方を理解し、健全な愛着関係の構築に向けた具体的なアプローチを身につけます。
- 個人に合った最適な心理システムの再起動 母親の心理システムの再起動により、ストレスへの対処能力や情緒調整能力を向上させます。カウンセリングにより、母親は自身の心理的な困難や制約を克服し、より健康的な心の状態を取り戻すことができます。
- 母親を子どもの親から一個人としての存在として認識 母親が自身を単に子どもの親としてではなく、個別の存在として認識することを支援します。母親の自己アイデンティティや自己実現の重要性を再確認し、自己成長とバランスの取れた生活を促進します。
- 愛着育成による自己肯定感の向上 母親が子どもとの愛着関係を育むことで、自己肯定感や自己価値感を向上させます。カウンセリングにおいては、母親が愛着行動やコミュニケーションスキルを向上させるための具体的な手法やアドバイスを受け取ります。
- 人生軸上でインストールした感覚ー認識の空洞化 母親が人生軸上で自身の感覚や認識を見つめ直し、新たな視点や意味づけを行うことを支援します。これにより、母親はよりポジティブな心理状態を持ち、子どもとの関係や子育てにおいてより健全な選択を行うことができます。
具体的な支援内容として、母親は定期的なカウンセリングセッションを通じて自身のメンタルヘルスや子育てに関する課題を共有し、カウンセラーとの対話やアドバイスを受け取ります。また、母親には日常生活におけるストレス管理や自己ケアの方法、感情の調整やコミュニケーションスキルの向上など、実践的なツールや戦略が提供されます。
大阪の不登校カウンセリング|40代の母親が必知!子供の不登校を解決する支援方法と専門家のアドバイス
こちらもCHECK
-

-
大阪の不登校カウンセリング|40代の母親が必知!子供の不登校を解決する支援方法と専門家のアドバイス
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 子供の不登校は多くの40代の母親にとって深刻な悩みです。その解決には適切な支援方法と ...
続きを見る
【40代母親からの第一歩】不登校問題解決への道と専門カウンセリングでの導き
こちらもCHECK
-

-
【40代母親からの第一歩】不登校問題解決への道と専門カウンセリングでの導き
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 40代の母親が抱える不登校問題は深刻な課題です。子どもの不登校により家庭や学校の関係 ...
続きを見る
【幸せホルモン】オキシトシンの増やし方12選|瞑想やマインドセット・身体調整が効果的
不登校の原因を知る方法!40代の母親が的確にサポートする方法とは?
中学生の不登校の原因は母親にあった!母親へのカウンセリングで復学につなげる
【40代子育ての悩み】不登校の原因を解明!不登校になる子の親の特徴と改善策
株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どものカウンセリング


支援内容
1. 不登校の子どもが抱えるココロの動きの促進
2. 幼少期の負の体験の心理システムの循環
3. 親子関係による負の自己イメージの軌道修正
4. 学校環境での存在価値の促進
5. 過去ー現在ー未来の時間軸の自然循環
6. 幼少期に遺伝的にもっているエネルギーの再生成
7. 学校環境で経験した負の要素への関わり
8. 学校環境で作られた他者との競争原理の滅尽
9. 母親では得られなかった愛着をカウンセラーとの共有で再獲得
10. 幼少期のゼロベースでの人間像への気づき
11. 負の心理システムで構成された世界観の抑制
不登校の子どものカウンセリングの具体的なアプローチ
- 不登校の子どもが抱えるココロの動きの促進 不登校の子どもは心理的な負担を抱えている場合があります。私たちは、子どものココロの動きを理解し、彼らが抱える不安やストレスを軽減するための支援を行います。具体的な方法としては、感情の表現や認識のトレーニング、リラクゼーション技法の導入などがあります。また、子どもが自己理解を深め、自己肯定感を高めるために、自己探索のプロセスにも取り組みます。
- 幼少期の負の体験の心理システムの循環 幼少期に経験した負の出来事やトラウマは、不登校の原因となることがあります。私たちは、そのような負の体験が心理システムにどのように影響を与え、循環するのかを理解し、子どもと共にその解決に向けた取り組みを行います。具体的には、トラウマ解消のための技法や自己発見のプロセスを通じて、過去の負の経験に対処し、新たな自己概念を構築するサポートを行います。
- 親子関係による負の自己イメージの軌道修正 親子関係は子どもの自己イメージに大きな影響を与えます。不登校の子どもにおいては、負の自己イメージが形成されることがあります。私たちは、子どもと親の関係を理解し、親子のコミュニケーションの改善や共感的な対話を通じて、子どもの自己イメージの軌道修正を支援します。親には、子どもの感情や困難に対して理解を示し、受け入れる姿勢を促すためのアドバイスや指導を提供します。
- 学校環境での存在価値の促進 不登校の子どもは学校環境での存在価値や自己肯定感に欠けていることがあります。私たちは、子どもが学校での存在感を取り戻すための支援を行います。具体的には、学校との連携や学校内でのサポート体制の構築を行い、子どもが自分の能力や才能を発揮できる場を提供します。また、学校生活の中での達成感や成功体験を通じて、子どもの自信を育む取り組みも行います。
- 過去ー現在ー未来の時間軸の自然循環 不登校の子どもは、過去の困難や現在の問題に囚われる傾向があります。私たちは、子どもが過去、現在、未来の時間軸を自然に循環できるように支援します。過去の出来事への執着や現在の問題に対する固執を解放し、未来に向けて前向きに取り組むことを促します。具体的な方法としては、目標設定や将来のビジョンの明確化、行動計画の策定などがあります。
- 幼少期に遺伝的に持っているエネルギーの再生成 子どもの行動や感情は、幼少期に遺伝的に受け継がれたエネルギーによって影響を受けることがあります。私たちは、子どもが遺伝的に持っているエネルギーを再生成し、ポジティブな方向へと導くための支援を行います。具体的には、子どもが自己観察や自己理解を深めるプロセスを通じて、自己変容を促すことに焦点を当てます。
- 学校環境で経験した負の要素への関わり 不登校の子どもは、学校環境での負の要素に対して適切に関わることができない場合があります。私たちは、子どもが学校環境での負の要素に対して適切に対処できるように支援します。具体的には、コミュニケーションスキルのトレーニングや問題解決能力の向上を促すプログラムを提供し、子どもが対処方法を見つけられるようにサポートします。
- 学校環境で作られた他者との競争原理の滅尽 学校環境では競争原理が存在し、不登校の子どもにとっては負の影響を与えることがあります。私たちは、他者との競争原理を滅尽し、協力や共感の文化を醸成する支援を行います。具体的には、協調性やチームワークの重要性を学ぶ活動や、他者との比較ではなく自己の成長に焦点を当てる指導を行います。
- 母親では得られなかった愛着をカウンセラーとの共有で再獲得 不登校の子どもの中には、母親からの愛着が不足している場合があります。私たちは、子どもがカウンセラーとの関係を通じて、得られなかった愛着を再獲得できるように支援します。子どもが安心感や信頼感を育み、自己価値感や自己受容感を高めるために、カウンセラーとの関係性を重視したアプローチを取ります。
- 幼少期のゼロベースでの人間像への気づき 不登校の子どもには、幼少期に根付いた人間像や自己イメージに問題がある場合があります。私たちは、子どもが自己観察や内省を通じて、幼少期のゼロベースから新たな人間像への気づきを促す支援を行います。具体的には、自己評価の見直しやポジティブな特性の発見、適応的な思考や行動パターンの構築をサポートします。
- 負の心理システムで構成された世界観の抑制 不登校の子どもは、負の心理システムで構成された世界観を持っていることがあります。私たちは、子どもがそのような負の世界観から抜け出し、ポジティブな視点や心理的な柔軟性を取り戻すための支援を行います。
具体的には、認知行動療法やポジティブ心理学の手法を用いて、子どもの思考や信念の再構築を促し、より健康的な心理システムを構築します。 株式会社Osaka-Childの臨床心理士(カウンセラー・セラピスト・不登校専門カウンセラー)として、私たちは不登校の子どもとその家族に対して、個別に適した支援を提供します。子どもの心の健康を重視し、不登校の原因や状況を的確に把握した上で、専門知識や経験に基づいたアプローチを用いてサポートを行います。私たちの目標は、子どもが健やかな学校生活を送り、自己成長や社会参加の機会を最大限に引き出すことです。
不登校カウンセリングでHSCの子どもを復学支援に|HSCの子どもを持つ40代の母親に向けて
こちらもCHECK
株式会社Osaka-Childのカウンセリング技法
カウンセリングとは?心理システムを正常化して生きづらさを克服する効果最大
-

-
参考カウンセリングとは?心理システムを正常化して生きづらさを克服する効果最大
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
来談者中心療法で心理システムを自然状態にして精神的苦しみを克服|40代女性の生きづらさ克服
-

-
参考来談者中心療法で心理システムを自然状態にして精神的苦しみを克服|40代女性の生きづらさ克服
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
トラウマインフォームドケアをカウンセリングで心理システムの最短正常化に
-

-
参考トラウマインフォームドケアをカウンセリングで心理システムの最短正常化に
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
オンラインカウンセリングのメリット・デメリットを知って手軽に心理システムを正常化する
-

-
参考オンラインカウンセリングのメリット・デメリットを知って手軽に心理システムを正常化する
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
精神分析的心理療法でカウンセリングを実施し心理システムの正常化で生きづらさ克服
株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの身体調整


支援内容
1. 子どもの姿勢コントロールの修正
2. 姿勢コントロールによる身体アライメント構築
3. 姿勢コントロールから重心作り
4. 学習に不可欠な座り姿勢での姿勢コントロールの促通
5. 姿勢に伴う手の運動構成のバランス
6. 姿勢と視覚・聴覚情報の同期
7. 全身の関節運動・筋肉の出力調整
8. 三半規管や脳神経系の出力の修正
9. ハンドリングによる触覚刺激で感覚系のコントロール
10. 皮ふ刺激によるオキシトシン分泌の促進
11. 皮ふ・筋膜・筋肉・筋肉の長さのセンサーのコントロール
12. 感覚ー認識システム促通から無の状態へのアップデート
13. 身体への関わりによる不足した愛着の向上
14. 負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化
15. 負の心理システムから身体への過剰な意識への抑制
不登校の子どもの身体調整の具体的なアプローチ
株式会社Osaka-Childでは、不登校の小中学高校生や発達障害の子どもの復学支援の一環として、身体調整の支援を行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。
- 子どもの姿勢コントロールの修正 子どもの姿勢は、身体の調整や感覚統合に重要な役割を果たします。不適切な姿勢が存在する場合、学習や集中力に悪影響を与えることがあります。私たちは、子どもの姿勢を正しい形に修正し、適切な姿勢コントロールをサポートします。具体的には、姿勢の矯正や筋力トレーニング、姿勢保持のためのエルゴノミクス指導などを行います。
- 姿勢コントロールによる身体アライメント構築 姿勢の改善は、身体のアライメントやバランスの向上につながります。私たちは、子どもの身体アライメントを構築するために、姿勢コントロールのトレーニングを行います。これには、正しい姿勢の保持や身体の軸の調整、バランス感覚の向上などが含まれます。
- 姿勢コントロールから重心作り 姿勢と重心の関係は、身体の安定性や運動の質に大きな影響を与えます。私たちは、姿勢コントロールから重心の形成に焦点を当て、子どもが適切な重心を持つことをサポートします。具体的には、姿勢トレーニングやバランスボードを使ったトレーニングなどを通じて、重心の安定化を促します。
- 学習に不可欠な座り姿勢での姿勢コントロールの促通 適切な座り姿勢は、学習において重要な要素です。不適切な座り姿勢は集中力の低下や身体の疲労を引き起こすことがあります。私たちは、子どもが学習に不可欠な座り姿勢を維持できるように、姿勢コントロールの促通を支援します。具体的には、正しい座り方やデスク環境の調整、体操やストレッチの指導などを行います。
- 姿勢に伴う手の運動構成のバランス 姿勢と手の運動は密接に関連しています。不適切な姿勢は手の運動にも影響を与えることがあります。私たちは、子どもの手の運動構成をバランス良く整えるために、姿勢と手の連動性を意識した支援を行います。具体的には、手の筋力や協調性のトレーニング、細かい手指の動作の指導などを行います。
- 姿勢と視覚・聴覚情報の同期 姿勢の調整と視覚・聴覚情報の適切な処理は、子どもの学習や集中力に影響を与えます。私たちは、子どもが姿勢と視覚・聴覚情報を適切に同期させるための支援を行います。具体的には、視覚情報や聴覚情報の統合を促すトレーニングやセンサリー処理の指導などを行います。
- 全身の関節運動・筋肉の出力調整 全身の関節運動や筋肉の出力の調整は、身体の柔軟性や運動能力に影響を与えます。私たちは、子どもの全身の関節運動や筋肉の出力を調整し、適切な身体の動きをサポートします。具体的には、関節の可動域の拡大や筋力トレーニング、コーディネーションの向上を目指したプログラムを提供します。
- 三半規管や脳神経系の出力の修正 三半規管や脳神経系の出力の調整は、バランス感覚や運動の調整に関与します。私たちは、子どもの三半規管や脳神経系の出力を修正し、バランス感覚や運動の質を改善するための支援を行います。具体的には、バランス感覚のトレーニングや目の運動の指導などを行います。
- ハンドリングによる触覚刺激で感覚系のコントロール 触覚刺激は感覚統合や身体の調整に重要な役割を果たします。私たちは、子どもの感覚系のコントロールを促すために、ハンドリングと呼ばれる触覚刺激を活用した支援を行います。具体的には、身体全体に触覚刺激を与えることで感覚統合を促し、身体の安定性や調整能力を高めます。
- 皮ふ刺激によるオキシトシン分泌の促進 皮ふ刺激はオキシトシンの分泌を促し、リラックスや安定感をもたらします。私たちは、子どもの皮ふ刺激を活用してオキシトシンの分泌を促進し、心身の安定をサポートします。具体的には、マッサージや触れ合いのアクティビティを通じて、子どもがリラックスした状態に入る機会を提供します。
- 皮ふ・筋膜・筋肉の長さのセンサーのコントロール 身体の皮ふ、筋膜、筋肉は長さの変化を感知するセンサーを持っています。私たちは、子どもの皮ふ・筋膜・筋肉の長さのセンサーをコントロールし、正常な身体の感覚を促します。具体的には、ストレッチや筋膜リリースなどの手法を用いて、身体の柔軟性や感覚統合を促進します。
- 感覚ー認識システム促通から無の状態へのアップデート 感覚と認識のシステムが促通し、無の状態にアップデートされることは、子どもの集中力や学習能力に大きな影響を与えます。私たちは、子どもの感覚と認識のシステムを促通させ、無の状態へのアップデートを支援します。具体的には、身体を使ったアクティビティやセンサリー統合の手法を用いて、感覚と認識の調整を促します。
- 身体への関わりによる不足した愛着の向上 不登校の子どもには、不足した愛着が存在する場合があります。私たちは、身体への関わりを通じて子どもの不足した愛着を向上させる支援を行います。具体的には、身体的な接触やアクティビティを通じて子どもとの関係性を構築し、安心感や信頼感を促します。
- 負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化 負の心理システムは、子どもの身体に過緊張や緊張を引き起こすことがあります。私たちは、負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化をサポートします。具体的には、筋肉の緊張を緩めるエクササイズやリラクゼーション法の指導を行い、身体の緊張を軽減します。
- 負の心理システムから身体への過剰な意識への抑制 負の心理システムから身体への過剰な意識は、子どもの集中力や学習に悪影響を与えることがあります。私たちは、負の心理システムから身体への過剰な意識を抑制する支援を行います。
株式会社Osaka-Childの身体調整とカウンセリング技法
催眠療法と心理カウンセリング併用で精神作用をリセット|40代女性の心理システムを正常化に
-

-
参考催眠療法と心理カウンセリング併用で精神作用をリセット|40代女性の心理システムを正常化に
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
自律訓練法とカウンセリングの併用で40代女性生きづらさ克服|自宅で簡単にできる
-

-
参考自律訓練法とカウンセリングの併用で40代女性生きづらさ克服|自宅で簡単にできる
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
呼吸法とカウンセリングで身体と精神をコントロールし40代女性が安定した人生を送る
-

-
参考呼吸法とカウンセリングで身体と精神をコントロールし40代女性が安定した人生を送る
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
メンタライゼーション・ベースド・セラピーで40代女性の心理システムを整える
-

-
参考メンタライゼーション・ベースド・セラピーで40代女性の心理システムを整える
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
グリーフケアカウンセリングで新しい自分で自然世界と調和した生き方を獲得する
-

-
参考グリーフケアカウンセリングで新しい自分で自然世界と調和した生き方を獲得する
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
リラクゼーション法で40代女性の生きづらさの身体症状を克服|目的・やり方・コツを解説
-

-
参考リラクゼーション法で40代女性の生きづらさの身体症状を克服|目的・やり方・コツを解説
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
具体的には、身体感覚の調整やマインドフルネスなどの技法を用いて、子どもの心身のバランスを整えます。 株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの身体の健康と調整を重視し、個別に適した身体調整の支援を提供します。子どもとその家族との協力を通じて、身体の調整や感覚統合の促進を図り、学習や社会生活の質を向上させることを目指します。
📌 あなたに必要な支援は、今すぐ手に届きます。
ここまで読んで「これ、私のことだ」と感じた方へ。
私たちが提供している再設計プログラムは、表面的なアドバイスではなく、根本から人生を整えるための実践型サポートです。
現在【銀行振込の方限定で割引案内】をご用意しています。
🔸 本日 2月7日(土)23:59まで のご入金分までのご案内となります。
🔸 『あと2名様限定』
※銀行振込限定・先着順での受付となります。
銀行振込限定で 最大5万円割引・個別相談枠の優先予約も受付中。
株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの家庭学習支援


支援内容
1. オンラインによる苦手教科の徹底的学習サポート
2. 自分に合った教材と学習法の発見と実践
3. 得意科目を地域で成績上位に入るための学習法
4. 苦手科目の時間的な関わり(量→質)
5. 予習・復習の時間共有
6. 脳内の特性に合わせた学習プログラムの実践
7. 脳内と心理システムを促通した個人に合った学習方法の習得
8. 勉強量から勉強の質への関わり
9. 不登校中の自宅でのスケジューリング
10. 勉強に対する苦手意識への心理システムの調整
11. 成績に反映する個人に合った勉強法の獲得
12. 全教科の要素分解と要素の合成への考え方の習得
13. 不登校中に偏差値を20以上向上させる学習時間と質の習得
不登校の子どもの家庭学習支援の具体的なアプローチ
株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、家庭学習の支援を行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。
- オンラインによる苦手教科の徹底的学習サポート オンラインを活用して、子どもの苦手とする教科について徹底的な学習サポートを行います。個別のオンラインチューターや学習プラットフォームを活用し、子どもが理解を深めるための指導を提供します。
- 自分に合った教材と学習法の発見と実践 子どもに合った教材や学習法を見つけ、実践するサポートを行います。子どもの学習スタイルや興味・関心に合わせて教材を選定し、効果的な学習方法を指導します。
- 得意科目を地域で成績上位に入るための学習法 子どもの得意科目を活かして、地域で成績上位に入るための学習法を指導します。具体的な学習戦略やアプローチを提供し、子どもが得意科目での自信と成果を得られるように支援します。
- 苦手科目の時間的な関わり(量→質) 苦手科目に対する学習時間を質の高いものにするための支援を行います。集中力を高めるための学習スケジュールの作成や、効果的な学習方法の指導を通じて、苦手科目への取り組みを効果的に進める方法を提供します。
- 予習・復習の時間共有 予習と復習の重要性を理解し、効果的に取り組むために、子どもと共有する時間を設けます。予習や復習の方法や具体的な計画の立て方を指導し、子どもが学習内容を定着させるサポートを行います。
- 脳内の特性に合わせた学習プログラムの実践 子どもの脳の特性に合わせた学習プログラムを実践します。例えば、視覚的な学習スタイルを持つ子どもにはマインドマップやイメージングを活用し、効果的な学習を促します。
- 脳内と心理システムを促通した個人に合った学習方法の習得 子どもの脳内の機能と心理システムを促通させ、個人に合った学習方法を習得させる支援を行います。具体的には、脳の情報処理や学習スタイルを理解し、それに基づいた学習戦略やアプローチを提案します。
- 勉強量から勉強の質への関わり 勉強の量だけでなく、質の高い学習を実現するための関わりをサポートします。集中力の向上や学習環境の整備、効果的な学習テクニックの指導などを通じて、子どもが効率的かつ効果的に学習できるように支援します。
- 不登校中の自宅でのスケジューリング 不登校中の子どもが自宅での学習をスムーズに進めるためのスケジューリングのサポートを行います。適切な時間配分やタスク管理の方法を指導し、子どもが自主的に学習を進められるように支援します。
- 勉強に対する苦手意識への心理システムの調整 勉強に対する苦手意識を持つ子どもに対して、心理システムの調整を行います。適切な支援方法や学習環境の整備、ポジティブなフィードバックの提供などを通じて、子どもの勉強への意欲や自信を高める支援を行います。
- 成績に反映する個人に合った勉強法の獲得 子どもの個別の特性や学習スタイルに合わせて、成績に反映される勉強法を獲得させる支援を行います。具体的には、学習戦略の指導や学習プランの作成、効果的な学習テクニックの習得などを通じて、子どもが効果的に学習できるようにサポートします。
- 全教科の要素分解と要素の合成への考え方の習得 全教科において、学習内容を要素分解し、それらを合成する考え方を習得させる支援を行います。具体的には、重要なキーポイントの抽出や概念の整理、総合的な学習アプローチの指導などを通じて、子どもの学習能力を向上させます。
- 不登校中に偏差値を20以上向上させる学習時間と質の習得 不登校中に子どもの学習時間と質を向上させ、偏差値を20以上上げる支援を行います。適切な学習計画の策定や時間管理の指導、効果的な学習方法の習得などを通じて、子どもの学力向上を支援します。
発達支援・発達相談をカウンセリングと療育で発達障害の子どもの機能性を120%アップ
動機づけ面接とカウンセリングの併用で40代女性の個人の人生に合った生き方を見つける
ナラティヴセラピーをカウンセリングで過去の経験値を未来軸に近づけ40代女性を自己実現に
ペアレント・トレーニングで40代母親の子育てを楽にする|子どもの育ちを大切にできる
不登校中の勉強しない・遅れる不安を解決する40代母親ができる接し方とは
中3不登校生徒で勉強してない場合の受験対策や進路の選択肢|今からでも間に合う!
【40代母親必見】不登校の子が復学後に勉強しない?その原因と解決策を詳解
中学3年間不登校だと勉強してないから高校受験は難しい?中学生の不登校の原因と親ができる対応
発達障害をカウンセリングで心理システムをスムーズにし克服へ|40代女性生きづらさ解決
学習障害(LD)をカウンセリングで最短で負担なく克服させる|生きづらさ解決に
株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの家庭学習をサポートし、個別に適した学習方法や戦略を提供します。子どもとその家族との協力を通じて、学習の成果を最大化し、不登校からの復学を支援します。
株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポート


支援内容
1. カウンセリングによる自己イメージのリセット
2. 意識と覚醒の自然現象への共有
3. 好きなこと・得意なこと・使命感への気づき
4. 未来像のマインドからの発見
5. 未来像と現実の自己へのプログラミング
6. 自己内から具体的な人生設計
7. 誕生から死への人生軸への関わりと意識の促通
8. トレンド情報に流されない個人に合った生き方の習得
9. 努力せずありのままで成果が出るキャリアとプロセスの構築
10. 学校環境での失敗体験の再現化と捨てる作業
11. 世界を構造から見つけていくトレーナーとの共有
不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポートの具体的なアプローチ
株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、進学やキャリアデザインのサポートを行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。
- カウンセリングによる自己イメージのリセット カウンセリングを通じて、子どもの自己イメージをリセットします。過去の失敗や困難な経験に縛られず、新たな可能性や自己評価を見つける支援を行います。
- 意識と覚醒の自然現象への共有 子どもに対して、意識や覚醒の自然現象について共有し、自己の内面に目覚めるきっかけを与えます。具体的には、マインドフルネスや瞑想などの方法を取り入れ、子どもが内なる気づきや成長を促します。
- 好きなこと・得意なこと・使命感への気づき 子どもが自分の好きなことや得意なこと、そして使命感を見つけるための支援を行います。興味や才能を引き出し、将来の方向性を探るための活動や自己探求のプロセスをサポートします。
- 未来像のマインドからの発見 子どもが自分自身の未来像を持つことで、目標や希望を見つける手助けをします。未来を具体的にイメージすることで、自己の成長や進学・キャリアの方向性を見出すサポートを行います。
- 未来像と現実の自己へのプログラミング 子どもが描いた未来像と現実の自己を結び付けるためのプログラミングをサポートします。具体的な目標設定や行動計画の策定、自己肯定感や自己効力感の醸成を通じて、子どもの進学やキャリアの実現を支援します。
- 自己内から具体的な人生設計 子どもが自己内に持つ資源や価値観を活かし、具体的な人生設計を立てるサポートを行います。自己の内なる声や目標に基づき、将来の進路やキャリアの方向性を考えるプロセスを共に進めます。
- 誕生から死への人生軸への関わりと意識の促通 子どもに対して、人生の意義や目的、誕生から死への人生軸について考える機会を提供します。自己の存在意義や時間の尊さを理解し、将来に向けた意識の促進を支援します。
- トレンド情報に流されない個人に合った生き方の習得 子どもがトレンド情報や社会の期待に流されず、自己に合った生き方を見つけるための支援を行います。個別の特性や価値観を尊重し、自己を大切にする生き方の習得をサポートします。
- 努力せずありのままで成果が出るキャリアとプロセスの構築 子どもが努力せずにありのままの自己で成果を出せるキャリアやプロセスの構築をサポートします。個々の能力や資質を活かし、自己の個性や魅力を最大限に生かした進学やキャリアの選択を支援します。
- 学校環境での失敗体験の再現化と捨てる作業 学校環境での失敗体験を再現し、それらを手放すプロセスを支援します。過去のネガティブな体験やトラウマからの解放を促し、自己成長と前向きな展望を持つためのサポートを提供します。
- 世界を構造から見つけていくトレーナーとの共有 子どもが世界の構造や社会の仕組みを理解し、自己の進学やキャリアの選択に生かすために、トレーナーとの共有を行います。具体的な情報や知識の提供、意義や意味の理解を通じて、子どもの進学やキャリアデザインに役立つサポートをします。
対人関係療法カウンセリングで治りにくい精神疾患を正常化する|うつ病・摂食障害に効果的
ソリューション・フォーカスト・アプローチで人生の悩みを最短解決|40代女性生きづらさ克服
キャリアカウンセリング(キャリアコンサルティング)で40代女性の人生を幸福に導く
コーチングで40代女性の子育てやキャリアアップを最速に機能させる
株式会社Osaka-Childのカウンセリング技法
【2023年最新】認知行動療法(CBT)とは?方法、効果やメリット・デメリット、療法の流れなどを解説
ストレスマネジメントとは?40代女性が子育て・キャリアアップで活かせる効果ややり方を解説
-

-
参考ストレスマネジメントとは?40代女性が子育て・キャリアアップで活かせる効果ややり方を解説
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
アサーショントレーニングとは?職場や子育てで実践する方法や自己表現タイプを解説
-

-
参考アサーショントレーニングとは?職場や子育てで実践する方法や自己表現タイプを解説
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
認知再構成法とカウンセリングで40代女性の生きづらさを生む認知のゆがみを克服
-

-
参考認知再構成法とカウンセリングで40代女性の生きづらさを生む認知のゆがみを克服
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの進学やキャリアデザインを支援し、自己の可能性や夢を追求するサポートを行います。子どもとその家族との協力を通じて、自己の価値を見出し、将来への道を切り拓くお手伝いをします。
株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの子どもの不登校復学支援内容:不登校復学後の1年間のサポート


支援内容
1. 復学後の学校との連携
2. 復学後の母親と子どものカウンセリングの実施
3. 復学後に生まれる諸問題の解決と実践
4. 復学後の生きづらさの軌道修正
5. 復学後の母親のメンタルサポートの継続
6. 復学後にぶつかる学校環境での負の体験への関わり
7. 母親に生まれる子どもへの過負荷の調整
8. 母親の人生サポートの継続による子どもの自由の解放
9. 復学後に生まれる母親と子どもへの不安の共有
不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポートの具体的なアプローチ
株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学後の1年間にわたるサポートを提供しています。以下に、具体的な支援内容を説明します。
- 復学後の学校との連携 子どもの復学後において、学校との綿密な連携を行います。学校とのコミュニケーションを円滑にし、子どもの学習状況や生活面でのサポートが必要な点を把握し、適切な支援策を立てるために協力します。
- 復学後の母親と子どものカウンセリングの実施 復学後においても母親と子どものカウンセリングを実施し、お互いの心情や課題に対して向き合います。母親の支えや理解を促し、子どもの心理的な安定と学校生活への適応をサポートします。
- 復学後に生まれる諸問題の解決と実践 復学後に生じる様々な問題や課題に対して、具体的な解決策を見つけて実践する支援を行います。学校生活や人間関係のトラブル、学習上の困難などに対して、子どもと母親の双方が適切に対処できるようにサポートします。
- 復学後の生きづらさの軌道修正 復学後に感じる生きづらさや不安に対して、子どもの心理的な軌道修正を支援します。自己肯定感の向上や適切なストレス管理の方法を教えることで、子どもが学校での生活に前向きに取り組むことを支えます。
- 復学後の母親のメンタルサポートの継続 母親のメンタルサポートを復学後も継続的に行います。母親が子どもの復学に伴うストレスや不安を抱える場合には、心理的な支えや情報提供を通じて、彼女の心の健康状態を維持し、子どもへのサポートを続けます。
- 復学後にぶつかる学校環境での負の体験への関わり 復学後に学校環境での負の体験が生じた場合には、子どもがそれに適切に関わることができるようにサポートします。適切なコーピングスキルの習得や自己肯定感の強化を通じて、子どもが学校での困難に立ち向かう力を育みます。
- 母親に生まれる子どもへの過負荷の調整 復学後において、母親が子どもに対して過度な負荷を感じる場合には、適切な調整を行います。母親の負担を軽減し、子どもとの関係性を健全に保ちながら、サポートのバランスを取ることが重要です。
- 母親の人生サポートの継続による子どもの自由の解放 母親の人生全体にわたるサポートを継続し、彼女が自己の成長と発展に集中できる環境を整えます。母親の支えが安定することで、子どもはより自由に自己を表現し、学校生活を充実させることができます。
- 復学後に生まれる母親と子どもへの不安の共有 復学後に母親と子どもが抱える不安や心配事に対して、お互いがそれを共有し、解消するための場を提供します。相互の理解を深め、不安を和らげることで、子どもの復学後の安定と成長をサポートします。
ストレスコーピングとカウンセリングの併用で40代女性のキャリア・子育てに成果
マインドフルネスとカウンセリングで効果を最大に|40代女性のキャリア・子育てに成果を出す
行動活性化療法で精神的抑うつを改善|40代女性生きづらさ克服でキャリア・育児両立に
株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの不登校復学後の1年間にわたり、学校との連携や心理的なサポートを通じて、子どもと母親の両方を支えます。子どもの安定した学校生活の確立と母親のメンタルヘルスの維持に注力し、一人ひとりのニーズに合わせたサポートを提供します。
Osaka-Childは小学生・中学生の不登校のお子さまに対して最短復学支援を提供しています

株式会社Osaka-Childの支援内容とは
- 母親のメンタルサポート
- 不登校子どものカウンセリング
- 不登校子どもの身体調整
- 不登校子どもの家庭学習支援
- 不登校子どもの進学・キャリアデザインサポート
- 不登校復学後の1年間のサポート
不登校子どものカウンセリング Osaka-Childでは、専門のカウンセラーによる個別のカウンセリングを行い、不登校の原因や問題を解決するための支援を提供しています。不登校子どもの身体調整 心身共に健康であることは、不登校克服に不可欠な要素の1つです。Osaka-Childでは、体の不調を訴える子どもに対して、運動や栄養指導などの支援を提供しています。不登校子どもの家庭学習支援 学校に行けない状況であっても、家庭学習を続けることが重要です。 Osaka-Childでは、家庭学習の計画立案や実践支援を行い、学習習慣の維持や向上に貢献しています。不登校子どもの進学・キャリアデザインサポート 不登校期間中に進路について考えることは、将来の自分自身の希望や目標を明確にするためにも重要です。 Osaka-Childでは、進路相談や進学・就職に関する情報提供など、キャリアデザインに必要な支援を提供しています。不登校復学後の1年間のサポート 不登校克服後の生活は、新たな課題やストレスを伴うことがあります。Osaka-Childでは、不登校復学後の1年間にわたって、学校生活や社会生活のサポートを行っています。
🔚 最後まで読まれたあなたへ。
もし「私は変わりたい」と思われたのなら、
それは変わる準備が、すでに整い始めている証拠です。
✅ 現在【銀行振込の方限定で割引案内・特別価格&3大特典】をご案内中です
🔸 本日 2月7日(土)23:59まで のご入金分までのご案内となります。
🔸 『あと2名様限定』
※銀行振込限定・先着順での受付となります。
33万円・50万円の再スタート支援プログラムでは、
家族関係・心理構造・生き方の再構築を、あなたのペースでじっくり支援します。
すでに診断済みの方も、そのまま詳細ページへ進めます。
あなたの心と体に合ったサポートを、今すぐ確認してみてください。













































の-女性専門カウンセリング支援.png)


で-40代女性の人生を幸福に導く-〜株式会社Osaka-Childの効果的なアプローチ〜-150x150.png)






