
私が頑張ればうまくいく。
そう信じてきた。
でも、いつもどこかで苦しくなる。
もう気づいているはずです。
パートナーや親との関係で、
我慢ばかりしてきたのは、
いつも「あなた」の側だったことに。
- 相手の機嫌を読み、
- 求められる前に動き、
- 断るよりも引き受けてしまう。
それなのに、
感謝されるどころか、
ますます空回りしていく――。
それは、
あなたの優しさが間違っているわけでも、
努力が足りないわけでもありません。
ただ、
「人との境界線の引き方」を教わらずに育ってきたことが、
今の苦しさにつながっているのです。
この記事では、
そんな「尽くしすぎて苦しくなる」関係の背景にある
「共依存」という仕組みを、
やさしく丁寧に紐解いていきます。
この記事を読むとわかること
- 「共依存」とは何か、どういう関係のことを指すのか
- 共依存に陥りやすい人の特徴や心理パターン
- 親子・恋愛・夫婦関係でよく見られる共依存の形
- なぜ自分ばかりが我慢する構造になってしまうのか
- 共依存から回復し、「自分の人生」を取り戻すための具体的な道筋
もちろん、
知識だけでは
人間関係はすぐに変わらないこともわかっている。
- 優しくなりたいのに怒ってしまう自分、
- 突き放せずに疲れていく日々。
頭では理解しても、
ココロがついてこないと感じる瞬間もある。
それでも大丈夫。
大切なのは、
「これまでの関係のなかで、あなたがどう育ってきたか」に目を向け直すことです。
自分の人生を
「誰かの期待」ではなく、
「自分の感情」で選び直す。
そのための回復のステップとして、
「共依存から『私』を取り戻す」3週間リペアレンティング・サポート
という選択肢をご用意しています。
これまでの関係のなかで
「自分の存在が消えていくような苦しさ」を抱えてきたあなたにとって、
この3週間は、人生を立て直すための確かな一歩になります。
監修者
株式会社Osaka-Child所属 精神科医
- 名前: 川村恵子
- 出身地: 福岡県
- 最終学歴: 京都大学医学部 精神神経学専攻
- 専門分野: 精神病理学、ストレス管理、認知療法
- 職歴: 京都大学医学部附属病院精神科勤務(10年)、独立後、大阪で精神科クリニックを開設
専門分野について一言: 「心の健康は全身の健康へとつながります。一人ひとりの心の声を大切にしたいと思っています。」
監修者
株式会社Osaka-Child所属 臨床心理専攻大学教授
- 名前: 森本哲夫
- 出身地: 奈良県
- 最終学歴: 米国ハーバード大学心理学部 博士課程修了
- 専門分野: 臨床心理学、発達心理学
- 職歴: ハーバード大学研究員(5年)、大阪大学人間科学部教授
専門分野について一言: 「心の成長とは、自己理解の旅でもあります。その旅のお手伝いができれば幸いです。」
期間限定
「私ばっかり、我慢してる気がする」
──気づけばいつも、相手の顔色を読んで、自分の気持ちは後回し。
優しい人ほど、共依存の関係に深く巻き込まれていきます。
「助けてあげたい」「支えたい」その気持ちの裏で、
本当は、「自分が必要とされたい」と願ってきた──そんな自分に、うすうす気づいていたはずです。
でももう、その「誰かのための人生」から、降りていいんです。
この《「共依存から『私』を取り戻す」3週間リペアレンティング・サポート》は、
「相手ありきの私」から、「自分の感情を大切にできる私」への転換点。
「自分の人生」を生き直すための、安全な土台づくりを一緒に始めましょう。
こんなあなたへ
- 頼られないと不安で、人に尽くしすぎてしまう
- NOが言えず、後から一人で疲れてしまう
- 親やパートナーに対して、言いたいことが言えない
✅ 【銀行振込限定・特典付き】でご案内中です。
🔸 本日 2月28日(土)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと2名様限定』
※銀行振込限定・先着順
さらに──
「私の代で、この苦しみを終わらせたい」と思ったあなたには、
《人生再統合プログラム(50万円)》をご用意しています。
「母でも妻でもない、私」として。
他人の期待ではなく、自分の感情と価値観で生きていく3週間です。
- 親や家族の価値観から距離をとりたい
- 「これからの人生」を「自分基準」で創り直したい
- 母としてではなく、ひとりの人間として立ちたい
「誰かのために生きる」人生から、「私を生きる」人生へ。
※《3週間集中リペアレンティングサポート》受講者限定
「ちゃんとしてるのに、苦しい」
「頑張ってるのに、うまくいかない」
——そんな違和感を抱えたまま、ずっと我慢していませんか?
LINEで3分セルフ診断ができます。
あなたの“今の感覚”の正体が、見えてきます。
共依存ってなに?その意味をわかりやすく

「共依存」って聞くとちょっとむずかしそうだけど、
ざっくり言うと
「だれかの問題に深くかかわりすぎて、自分を後まわしにしちゃう関係」
のことです。
たとえば、旦那さんがアルコール依存症だったとします。
奥さんは一生懸命ささえてるけど、
実はその関係が依存症を続けさせてしまってる
…なんてことがあるんです。
本人もつらいけど、
ささえてる側も知らないうちに巻きこまれて苦しくなってる。
これが共依存のパターンです。
よくある例としてはこんな感じ。
- 相手のダメなとこを責めすぎて、逆に相手がもっと問題をかくすようになる
- 自分を犠牲にしてまで相手の世話を焼いちゃう
- 問題がバレないように隠したりフォローばっかりしてる
- 「そんなことない」って問題そのものを認めない
- 相手がしらふの時は緊張してて、飲むと逆に怒りが爆発
- 普段は奥さんが支配的だけど、相手が飲むと主導権が逆になる
- 苦しいのに別れられなくて、「私は犠牲者」と思いつづけてる…などなど
共依存って、
相手に必要とされることで「自分の存在価値」を感じてしまうんです。
でもそのぶん、自分自身がどんどん見えなくなってしまう。
家族だけじゃなく、友だちとか仕事仲間でも起こりうることなんですよね。
共依存体質ってこんな感じ

「共依存体質」っていうのは、
カンタンに言えば
「つい他人のことで頭がいっぱいになっちゃう人」のこと。
周りの期待に応えようとがんばりすぎて、
自分の気持ちとか願いがおいてけぼりになること、ありませんか?
- 誰かに喜んでもらいたい
- 好かれたい
- 役に立ちたい
そんな気持ちはすごく自然なことです。
でも、それが「無理してでも応えなきゃ」ってなって、
自分がどんどんしんどくなっていくとしたら…
それは共依存反応がココロで引き起こされているのです。
気づかないうちに
- 「わたしがなんとかしなきゃ」
- 「あの人が困ってるのは私のせいかも」
って思って、自分を責めてしまうことも。
だから大事なのは、
「自分を大切にする」こと。
自分がどう感じてるか、どうしたいのかにちゃんと目を向けてみることです。
共依存って言葉、どうやって生まれたの?
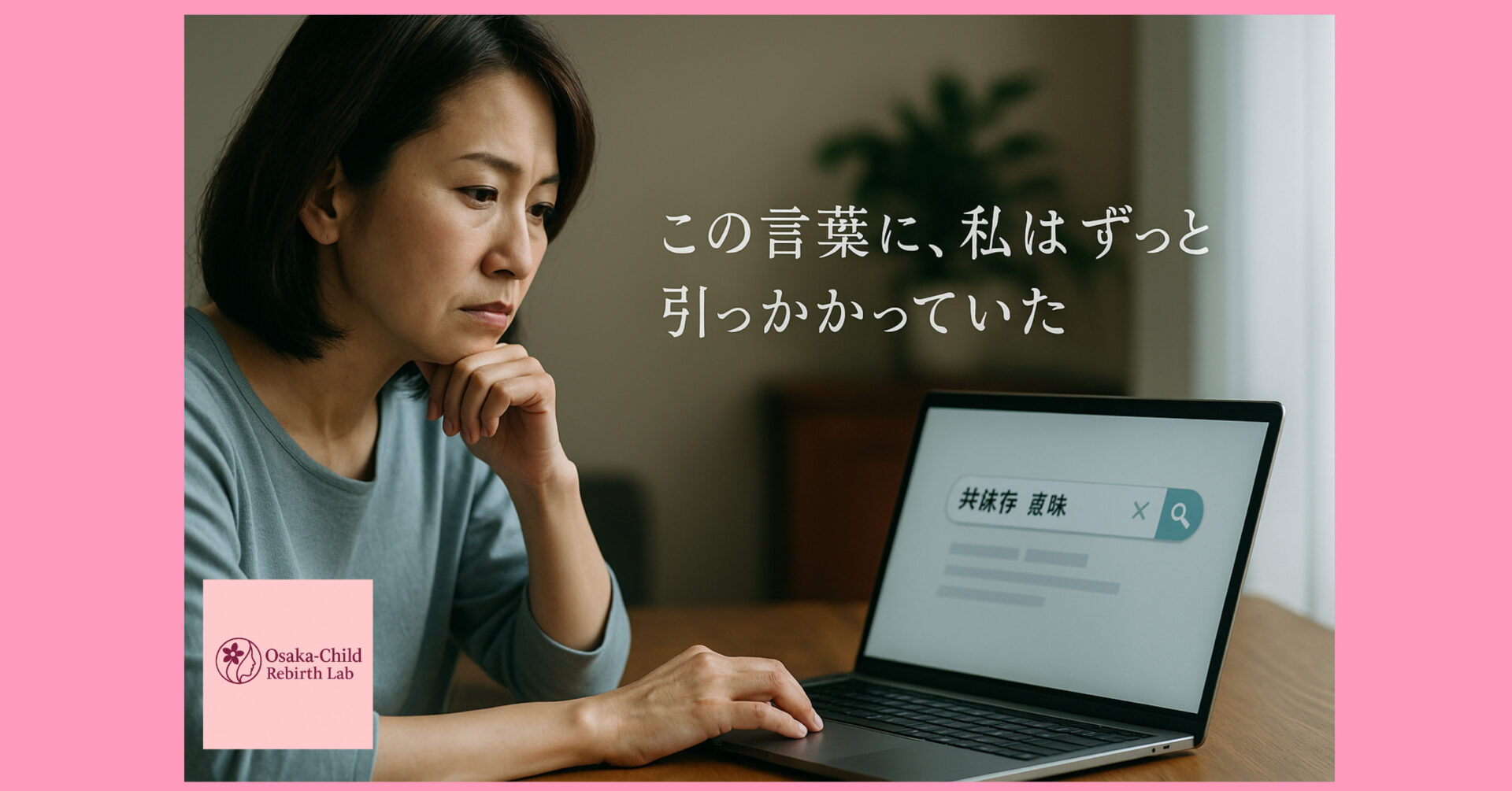
「共依存」って言葉は、
もともと1970年代のアメリカで、
アルコール依存症の旦那さんを支えてた奥さんたちの姿
から生まれたんだそうです。
当時、奥さんたちは家族を守るために必死で、
旦那さんに飲ませないように説教したり、
失敗の後始末をしたり…って
いろいろがんばってた。
ポイント
でもその必死さが、逆に旦那さんをもっと依存させてしまってたんです。
それで
「これは共に依存している状態だよね」として、
「co-dependency」=共依存
って言葉ができたんですね。
今ではアルコール依存だけじゃなく、
- 恋愛
- 親子
- 職場など
いろんな人間関係にも使われる言葉になっています。
「自分を大事にする」ってどういうこと?
共依存に悩む人って、
「なんでこんなにがんばってるのに報われないの?」
って思うことが多いです。
疲れてるのにやめられないし、
「どうしてわたしばっかり」って感じることもあるかもしれません。
でも、そういう時こそ
「相手じゃなくて、自分に目を向けてみよう」
って考えてほしいんです。
あなたがしんどいのは、
- 優しさがあるから
- 誰かを支えたい気持ちが強いから
でもそのやさしさ、自分にも向けていいんですよ。
カウンセラーや信頼できる人と話して、
「わたしはどうしたいのか」を少しずつ見つけていく。
そこから、気持ちがだんだん軽くなっていきます。
共依存から自由になるためにできること

無料LINE診断|今のあなたに必要なサポートは?
『何から始めればいいかわからない…』そんなあなたへ。
LINEで“数字”を入力するだけで、今のあなたに合ったサポート商品を診断できます。
今すぐLINEに【 1〜5 】の番号を入力してください。
それぞれの商品内容と「ぴったりの理由」が届きます。
共依存から抜け出すためには、
「自分の感情や考えに気づいてあげること」
がスタートです。
- 「わたし、ほんとうはどう感じてるんだろう?」って自分に聞いてみる
- 無理をしてまでがんばりすぎない
- 相手の人生は相手のもの、とちょっと距離をとる
こうした意識を少しずつ持つことで、自分軸が取りもどせていきます。
もちろん、ひとりでやるのはむずかしいことも多いです。
だから、プロの力を借りるのもぜんぜんOK。
カウンセリングやグループサポートは、とてもココロ強い味方になりますよ。
共依存:あなたの経験に当てはまるかも?

無料診断|あなたの“心のパターン”を知る
「なぜか同じことで悩んでしまう…」
そんな方のために、LINEで「キーワード」を送るだけで診断できるサービスをご用意しました。
LINEに「共依存抜け出したい」と入力して送信してください。
あなたに合った視点と解説をすぐにお届けします。
「共依存」という言葉、ちょっと堅いけど、
じつは日常の中にもよくあることなんです。
たとえば…
- 他人の気持ちにすごく振りまわされる
- だれかの問題を自分が何とかしようとがんばりすぎる
- 自分の気持ちよりも、相手の期待にこたえなきゃって思ってしまう
こんなこと、心当たりはありませんか?
また、だれかに
- 「認められたい」
- 「必要とされたい」
と思って、それがないと不安になる…。
そんなときは、
自己価値を他人の評価に預けてしまってるのです。
自分のことを後まわしにして、
相手を優先しすぎてしまう。
無意識のうちに、相手の人生を生きようとしていないか、
ちょっと立ちどまって見つめてみることも大切です。
共依存に気づいたら、そこが出発点です。
「わたしはどうしたいの?」って、自分に問いかけてみましょう。
そして、必要があればカウンセラーや専門家といっしょに、自分らしい生き方を見つけていけたらいいですね。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「私ってアダルトチルドレンなのかな…?」
そんな迷いを感じた方へ。
共依存や生きづらさの「根っこ」を紐解く視点として、アダルトチルドレンの特徴や5つのタイプを詳しく解説しています。
👉 「私ってアダルトチルドレン?」と思ったあなたへ|特徴・5つのタイプ・回復ステップを解説【精神科医監修】
-

-
参考「私ってアダルトチルドレン?」と思ったあなたへ|特徴・5つのタイプ・回復ステップを解説【精神科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「親の育て方のせいにしたって、何も変わらない」 ──そう思いながらも、ふとした瞬間に ...
続きを見る
自分ばかり頑張っていませんか?自己犠牲に気づく
「またわたしだけががんばってる…」
って感じたこと、ありませんか?
だれかのために動いて、気づいたら自分が疲れきってる。
そんなとき、ちょっとだけ自分に問いかけてみてください。
- 相手のために、自分の気持ちを抑え込んでいない?
- 何かあるたびに「自分がやらなきゃ」って思ってない?
やさしい気持ちからの行動でも、
行き過ぎると「自己犠牲」
になってしまいます。
それって、ちょっとしんどいですよね。
しかも、
そんなにがんばっても、
相手が変わらなかったり感謝されなかったりすると、
「わたしって何やってるんだろう…」
ってむなしくなることも。
「他人のために動くこと=正しい」
と思いがちですが、
自分がボロボロになるようなら、
一度そのバランスを見直してみる
ことが大切です。
ほんとうに大事なのは、
「自分の気持ちも同じくらい大事にしていい」
と思えること。
サポートしたい気持ちはすばらしいけど、
自分を犠牲にしないやさしさの形、少しずつ見つけていきましょう。
介入しすぎていませんか?「手を出しすぎてないかな」のサイン
つい、だれかのことが気になって、
- あれこれ口を出したり
- 代わりにやってあげたり…。
そんなふうに「お世話しすぎて」しまっている自分に気づいたこと、ありませんか?
- 「わたしが言ってあげないとダメでしょ」
- 「わたしがなんとかしないと、この人また失敗する」
そんな気持ち、共依存のサインです。
誰かを心配して行動すること自体は悪くないんですが、
相手が自分で考える力や責任感を育てるチャンスを、
知らず知らずのうちに奪ってしまうこともあるんです。
それに、自分が介入しすぎると、
相手は「この人がやってくれるからいいや」ってなってしまい
結果的に依存が深まるケースも。
大事なのは、
- 「見守る勇気」
- 「自分と相手の境界線を大切にすること」
ポイント
おたがいに「自分の人生を生きる」関係のほうが、実は長くうまくいくことが多いんですよ。
自分を追い詰めていませんか?完璧じゃなくていいんです
いつも誰かのために動いていて、
ふとした瞬間「わたしってなんなんだろう…」って思うこと、ありませんか?
- 「助けてあげないと、わたしって冷たい人?」
- 「だれからも好かれないとダメな気がする」
- 「ちゃんとやらないと、自分を認められない」
そんなふうに、自分にプレッシャーをかけすぎていないでしょうか。
共依存の傾向があると、
自分の価値を「他人の評価」で決めてしまう
ことが多いです。
そして、その期待に応えつづけるために、自分をどんどん追いつめてしまう…。
でも、ちょっと考えてみてください。
あなたが疲れてしまったら、
大切な人をささえることもできなくなってしまいますよね。
だからこそ、
- 「ちゃんと休む」
- 「ちゃんと断る」
- 「ちゃんと自分の気持ちを大事にする」
ことって、すごく大切です。
自分を大切にするって、わがままなんかじゃありません。
自分のココロとカラダをととのえることで、結果的にまわりとの関係もよくなっていきます。
共依存の5つの特徴って?

共依存にはいくつかの特徴があって、
それがわたしたちの人間関係をややこしくしてしまうことがあります。
アメリカの臨床家ピア・メロディさんは、
その中でも特に大切な
「核となる5つの特徴」
を挙げています。
ここでは、それぞれの特徴を日常の言葉でわかりやすく説明していきますね。
1. 人に頼りすぎてしまう
共依存の人は、
自分ひとりでは不安で、
誰かにそばにいてもらわないと落ち着かない…
そんな気持ちを抱えていることがあります。
- 「この人がいないと私なんて…」
- 「誰かに必要とされていたい」
そんな思いが強すぎると、
自分の気持ちや存在価値を相手に預けてしまって、
自己肯定感がどんどん下がっていく
ことがあります。
2. つい自分を後回しにしてしまう
だれかのために一生懸命になりすぎて、
自分のことは後まわし…
それ、共依存の大きな特徴です。
- 「家族のためだから」
- 「子どもが困ってるから」
と、
どこかで自分を犠牲にすることで満足感を得てしまっていないでしょうか?
それって一見「やさしさ」に見えるけれど、
- 自分の幸せ
- 満たされる感覚
を置きざりにしてしまう原因にもなります。
3. 自分と他人の境界があいまいになる
共依存の人は、
「自分」と「相手」の境界線がぼやけてしまう
ことがよくあります。
たとえば、
- 相手の機嫌や問題を自分のせいだと思ってしまったり、
- 逆に自分の感情を飲み込んで相手に合わせたり…。
その結果、何が自分の本音なのか、わからなくなってしまうんです。
4. 自分の価値を低く見てしまう
共依存の人は、他人にどう見られているかをとても気にします。
そして、
- 「ちゃんとしてないとダメ」
- 「役に立たなければ意味がない」
と、自分にきびしすぎる傾向があります。
完璧じゃないと自分に価値がないように感じてしまう…
そんなふうに、自分で自分を追いつめていませんか?
5. 感情を抑え込んでしまう
感情を我慢して飲みこんでしまうことがクセになっていませんか?
- 「怒っちゃダメ」
- 「泣いたら迷惑」
- 「こんな気持ち言えない」…
そうやって自分の気持ちをしまいこんでしまうと、
だんだん自分がほんとうはどう感じているのかもわからなくなってしまいます。
共依存が引き起こす心理作用

“私ばかりが苦しい関係”から抜け出したい方へ
「私のせいかな」「私が頑張ればいい」──
そんなふうに、自分ばかりが我慢してきた関係に心当たりがある方へ。
たった3週間で、その苦しみの「正体」が言葉になるサポートです。
共依存って、
ココロの中でいろんな「ゆがみ」を生み出します。
自分では気づきにくいけれど、
知らず知らずのうちに
「しんどさ」を増やしてしまっているんです。
ここからは、
そんなココロの中で起きていることを、
わかりやすく整理していきますね。
自尊心がグラグラしているときに
共依存の背景には、
「自分はこれでいい」という感覚=セルフエスティーム(自尊心)の不安定さ
があります。
小さいころ、
- 親からの保護がなかったり
- 逆に親に頼られすぎていたりする
と、
自分と他人の境界線がうまく持てなくなってしまう
んです。
そして大人になってから…
- 傷つきたくないから人と距離をとって孤立してしまう
- 相手に頼られて、自分の意見や感情を抑えこんでしまう
この両極端を行ったり来たりしてしまうことがあります。
共依存から抜け出すには、
自分と他人の間にちょうどいい境界を作ることが大事なんです。
- 「これはわたしのこと」
- 「それは相手のこと」
と線びきできると、人間関係もずっとラクになります。
現実をまっすぐ見られないとき
共依存が強いとき、
人は「カンペキでなきゃいけない」と思いこんで、
現実をありのままに見るのが難しくなります。
たとえば…
- ちょっとのミスが許せない
- 感情が揺れるのが怖い
- 白か黒か、ゼロか100かで考えてしまう
でも本当は、間違ってもいいし、弱くても大丈夫。
感情がゆれるのは人間として自然なことです。
ポイント
白黒ではなくグレーがあることを許すと、自分も他人ももっと楽になりますよ。
依存しすぎていませんか?
共依存の人は、
「自分の価値は他人に決めてもらうもの」
と思ってしまう傾向があります。
子ども時代に、
自分で選んだり、考えたりする機会が少なかった場合、
- 「人に頼ることが当たり前」
- 「なんでも自分でやらなきゃダメ」
と思い込んでしまうことがあります。
でも本来は、
ちょうどいいバランスで
- 「頼ること」
- 「自立すること」
もできていいんです。
他人にすべてを預けるのではなく、自分の気持ちを大事にすることから、少しずつ始めてみませんか?
ちょうどいい加減がわからない
共依存の人は、感情や行動が「極端」になりがち。
- 我慢しすぎる
- 逆に爆発してしまう
- 「言いたいけど言えない」のくり返し
こんなふうに、ちょうどいい自己表現がむずかしいことがあります。
これは、
自分のほんとうの気持ちに気づけなかったり、
どうやって出していいかがわからなかったりする
からなんです。
共依存から回復していくには、
「ちょうどいいバランス」を少しずつ見つけていくことが大事です。
「本当はこうしたいんだけど…」って、
自分の中の声を聞く練習からはじめてみましょう。
期間限定
「私が頑張らなきゃ、この関係は壊れてしまう気がしてた」
──そうやって、いつも自分を犠牲にしてきたはずです。
親の期待、パートナーとの関係、子どもへの接し方。
「愛しているから」「助けたいから」と言い聞かせながら、
本当は、「嫌だ」「苦しい」と感じていた気持ちを、何度も飲み込んできた。
でもね、誰かのために無理を重ねる関係は、もう終わらせていいんです。
「私を大切にすること」が、相手との関係を壊すことにはならない。
そのことを、安心できる場所でゆっくり確かめていきませんか?
この《「共依存から『私』を取り戻す」3週間リペアレンティング・サポート》は、
人との境界線が曖昧になっていた「ココロのパターン」を整え直す時間。
「誰かに合わせる人生」から、「自分で選ぶ人生」へと、静かに舵を切るサポートです。
こんなあなたへ
- 相手に尽くしてばかりで、自分が空っぽになっていく感覚がある
- 本音を伝えるのが怖くて、いつも「平気なふり」をしてしまう
- 助けたいのに、なぜか関係がこじれてしまう
✅ 【銀行振込限定・特典付き】でご案内中です。
🔸 本日 2月28日(土)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと2名様限定』
※銀行振込限定・先着順
さらに──
「私の人生、このままで終わらせたくない」と感じたあなたには、
《人生再統合プログラム(50万円)》もご用意しています。
「母でも妻でもない、私」として。
これからの人生を、「他人基準」ではなく「自分の感情と価値観」で歩み直すための本格サポートです。
- 子育てが一段落した今、空虚さや迷いを感じている
- 誰かに認められる人生から、自分に誇れる人生に切り替えたい
- 役割ではなく「本当の私」として生きたい
「自己犠牲」のその先に、「自己再定義」という選択肢を。
※《3週間集中リペアレンティングサポート》受講者限定
自分らしく生きるためにできること

- 「わたしって、いったい何がしたいんだろう?」
- 「だれかの期待に応えるばかりで、自分の気持ちがよくわからない…」
そんなふうに感じるときは、
もしかしたら共依存の関係に巻きこまれているのかもしれません。
自分らしく生きるためには、
まず「今の自分ってどんなふうに感じてるの?」
と、
ココロの声に耳を傾けることから始まります。
信頼できる人や安心できる場所で、
普段口にできなかった気持ちを話すこと。
それが大きな一歩になります。
共依存のパターンは長年のクセになっていることも多いので、
いきなり変えようとしてもむずかしいのは当たり前。
でも、カウンセリングなどを通して
少しずつ「自分を大事にする練習」をしていく
ことで、
あたらしい自分に出会えるようになりますよ。
自分の気持ちや欲求に気づいて、それに正直に行動すること。
自分を受け入れて、肯定してあげること。
それが「自分らしさ」を取りもどす大切なステップです。
恋愛で見える共依存のパターン
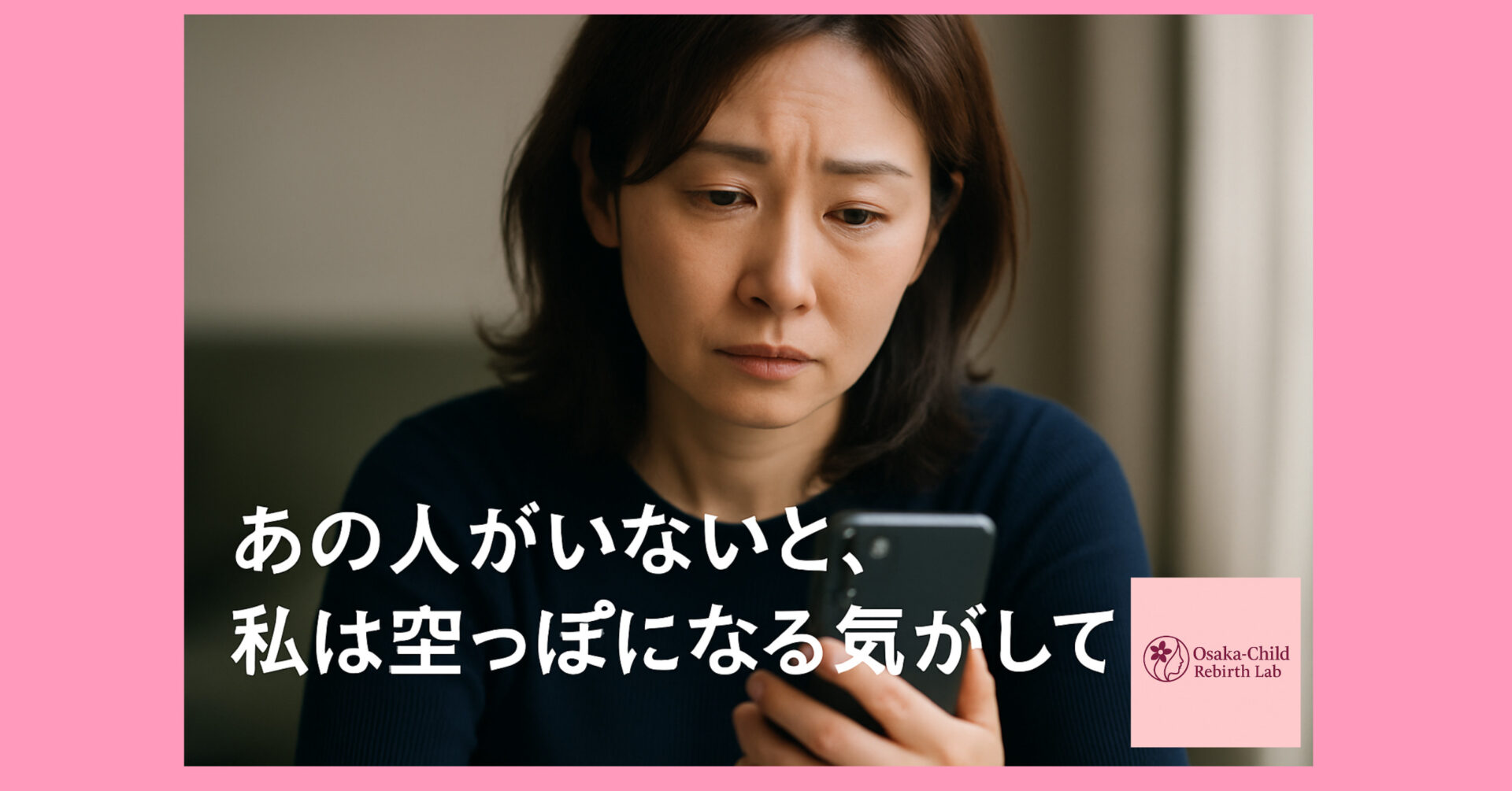
恋愛の中で“わたし”を見失ってしまう方へ
「嫌われたくなくて、本音が言えなかった」
そんな恋愛を繰り返してきた40代女性へ。
母との関係で覚えた「我慢グセ」が、今もあなたを縛っているのです。
3週間で、その根っこをほどくサポートをお届けします。
恋愛でも、共依存の関係って意外とよくあります。
とくに、
- 相手がいないと不安でたまらないとか
- 逆に人との距離が近くなると逃げたくなる…
そんなパターンがくり返されているなら、
少し立ちどまって考えてみてください。
【1】恋愛依存タイプの関係
恋愛依存タイプの人は、
「だれかに愛されていないと、自分には価値がない」
と感じやすい傾向があります。
恋をしているときは気持ちが満たされているけど、
ひとりになると空虚で不安になってしまう。
そんな人同士がカップルになると、いつもベッタリ。
ふたりだけの世界を作って、
他の人や予定をすべて後まわしにしてしまうことも。
相手からの「愛されてる感」がないと、自信も不安定になります。
回避依存タイプの関係
回避依存の人は、
「人と近づきすぎると苦しくなる」と感じるタイプ。
相手が好きでも、
近づきすぎると逃げたくなってしまうんです。
そんな2人がカップルになると、見た目はあっさり、ドライ。
でも、
ココロの中は
- 「ほんとは誰かにわかってほしい」
- 「でも怖い」
が入りまじっていて、ちょっと孤独です。
恋愛依存タイプ×回避依存タイプ
いちばん多いと言われているのがこのパターン。
いっぽうが「もっとそばにいてよ」と求め
もう一方が「ちょっと離れてて」と逃げる。
くっついて、離れて、またもどって…という関係のくり返しで、
ココロがすごく疲れてしまいます。
でも、
おたがいに「この人しかいない」と思っているからこそ、
なかなか離れられないんです。
恋愛依存タイプ同士だとどうなる?

恋愛依存タイプ同士のカップルは、
おたがいに「あなたがいないとわたしダメになる」
という気持ちが強くなりすぎてしまうことがあります。
ふたりで過ごす時間が中心になり、
他の人とのかかわりが減ってしまったり、
ケンカが激しくなったり…。
ちょっとしたすれ違いでも
「見捨てられるかも」
と
不安になりやすく、傷つきやすい関係になってしまいます。
さらに問題なのは、
どちらかが急にいなくなったとき(たとえば病気や別れなど)、
もういっぽうがココロのささえを完全にうしなってしまうこと。
そのくらい、
自分の存在価値を相手にあずけすぎてしまう関係
なんです。
このタイプの関係から抜け出すには、
「わたし自身の人生をどう生きたいか?」
に立ちかえることが大切。
カウンセリングなどのサポートを受けながら、
少しずつ自分の足で立てるようになると、関係も安定していきます。
恋愛依存タイプ×回避依存タイプのすれ違い

- 「いっしょにいたい」と思って追いかける人と
- 「距離をとりたい」と思って逃げる人
この組み合わせでは、
ふたりの距離感がなかなか合わず、
ずっとすれちがい
がつづきます。
依存タイプの人は「見捨てられた!」と感じ、
回避タイプの人は「重すぎて無理」と感じてしまう。
だけど、
逃げた回避タイプの人も、離れてみると寂しくなって戻ってきたりするんですよね。
でも、またいっしょになると「やっぱりしんどい」って離れていく。その繰り返し。
この関係から抜けるためには、おたがいが自分自身と向き合うことが大事です。
自分の不安やさみしさをどう受けとめるか、その方法を知っていくことが回復のカギになります。
回避依存タイプ同士の関係
回避依存タイプ同士の関係は、ちょっと不思議な距離感。
つかず離れずの関係で、定期的に会うけど深くふみ込まない…。
どこか「ドライで大人の関係」
に見えることもあります。
でも実際には、
「だれかとつながりたい」という気持ちをかかえながらも、近づくのが怖い。
だから、
ほんとうの意味で安心できる関係が築けないまま、
孤独感がずっと残ってしまうんです。
回避タイプ同士の関係は、
見た目以上に「満たされなさ」を抱えています。
だからこそ、
おたがいのココロの中を少しずつ共有しながら、
信頼関係を築くプロセスがとても大切です。
共依存の恋愛から抜け出すには?──対策と方法

- 「この恋愛、なんだか苦しい」
- 「でも、離れられない」…
そんな気持ちを抱えていませんか?
共依存の恋愛から抜け出すには、
まず「自分をよく知ること」
が大事です。
とくに、
子どものころから感じていた気持ちや家庭環境を振り返ってみると、
今の恋愛パターンにつながっている
ことがあるんです。
では、どうすればそこから一歩抜け出せるのか?
以下のような方法が役に立ちます。
自分の気持ちに気づく練習をする
- 「わたし、今どう感じてる?」
- 「ほんとうはどうしたい?」
そんな問いを日常でちょっとずつ自分に投げかけてみましょう。
自分を大切にする意識が高まると、他人への過剰な依存が減っていきます。
カウンセリングで話してみる
一人で考えるのがつらいときは、
専門家に話を聞いてもらうのがいちばん早い
です。
頭でわかっていても、ココロがついてこないことってありますよね。
ポイント
セラピーは「今まで気づかなかった自分」に出会える場所です。
同じ経験をした人たちと話してみる
「わたしだけじゃなかったんだ」と思えるだけでも、すごく救われます。
共依存に悩む人のグループ(たとえばCoDAやアル・アノンなど)
に参加してみると、
にた経験をした人と出会えて、
ココロが軽くなることもあります。
相手との「ちょうどいい距離」を見つける
最適な関係は、おたがいが自立しながらささえ合うもの。
- 「全部相手に合わせる」
- 「全部相手に求める」
では、苦しくなってしまいます。
自分の考えや時間も大切にしながら関係を築く工夫が必要です。
自分の時間や趣味を持ってみる
他人中心の生活になっていませんか?
まずは、
自分の
- 「好きなこと」
- 「やってみたいこと」
に目を向けてみましょう。
それが、自立の第一歩になります。
自分の“過去”を振り返ってみる
今の自分の思考やクセ、
実は子どものころの経験が大きくかかわっていることがあります。
たとえば、
- 家族の中で我慢ばかりしてきた
- ちゃんとしないと愛されないと思っていた
- 母親の顔色ばかり気にして育った
そんな記憶が、
今の「人に嫌われたくない」「捨てられたくない」という不安のもと
になっているかもしれません。
ノートに書き出すだけでも、
自分の中のパターンが見えてきますよ。
「ああ、わたしってこういうとこで無理してたんだな」
って気づくことから、変化は始まります。
「足りなかったもの」に気づくこと
子ども時代に受けとるべきだった「ココロの栄養」
あなたはちゃんと受け取れていましたか?
たとえば…
- 「そのままでいいよ」と言ってくれる人がいなかった
- 自分の気持ちを安心して話せる場所がなかった
- 家族の中に、安心できる空気がなかった
そんな「欠けていたもの」が、
自分の中にぽっかりと穴を空けてしまう。
そして、その穴を埋めるために
- 「誰かに必要とされたい」
- 「見捨てられたくない」
という気持ちが強くなってしまうんです。
でも、大丈夫。
その「欠け」に気づけたら、
これから自分で満たしていくことができます。
グリーフ・ワークって知ってる?
グリーフ・ワークとは、
「過去の喪失や傷に向き合う作業」のこと。
よく「大切な人を亡くしたとき」に使われる言葉ですが、
実は共依存の回復にもすごく役立ちます。
たとえば…
- 子どものころに言えなかったことを、親に宛てて手紙にしてみる
- 昔のつらかった出来事を、信頼できる人に話してみる
これって、言葉にすることで、ココロの中で整理がついていく作業なんです。
「あのとき、わたしは本当はこう感じてたんだ」
って涙が出てくることもあります。
そしてそれが、過去の痛みを乗りこえる第一歩になります。
同じ経験をした仲間とのつながり
一人でがんばりすぎていませんか?
共依存から抜け出すとき、
同じ経験をした仲間の存在は大きな支えになります。
自助グループでは、家族やパートナーの話ってなかなか外では言えないことも、安心して話すことができます。
「わたしも同じだったよ」と言われるだけで、涙が出ることもあります。
仲間との対話は、
自分では気づかなかった感情やパターン
に気づくきっかけにもなります。
自分だけじゃない、
という安心感がココロの回復を後おししてくれるんです。
「現実」をちゃんと見てみよう
恋愛や人間関係で、つい「理想」ばかり追いかけていませんか?
- 「いつかこの人は変わってくれるはず」
- 「わたしががんばればうまくいく」
- 「この人じゃなきゃダメなんだ」
こういった思いにしばられてしまうと、
今の現実が見えなくなってしまいます。
でも、本当の意味で自分を大切にするには、
「現実をそのまま受けとめる力」も必要です。
自分と相手の限界を知ること。
今ある関係が、自分を苦しめていないかを見つめ直すこと。
つらい作業かもしれないけど、
現実を受け入れたとき、自分自身がやっと自由になれるんです。
さいごに:自分の人生を「取り戻す」ために
共依存の恋愛って、
自分を見失ってしまいやすい関係です。
でも、
それに気づけた今、あなたはもう「変われる力」を持っているということ。
過去の癖や傷があっても、それを癒していく方法はいくらでもあります。
- 自分を責めないこと
- 一人で抱えこまないこと
- 少しずつ、でも確実に、自分の足でたつこと
ポイント
あなたが「あなたらしい人生」を生きるためのヒントは、いつもココロの中にあります。
サポートを受けながら、一歩ずつすすんでいきましょう。
共依存を走った40代母親が子どもの不登校を解決した5つの実際の支援例
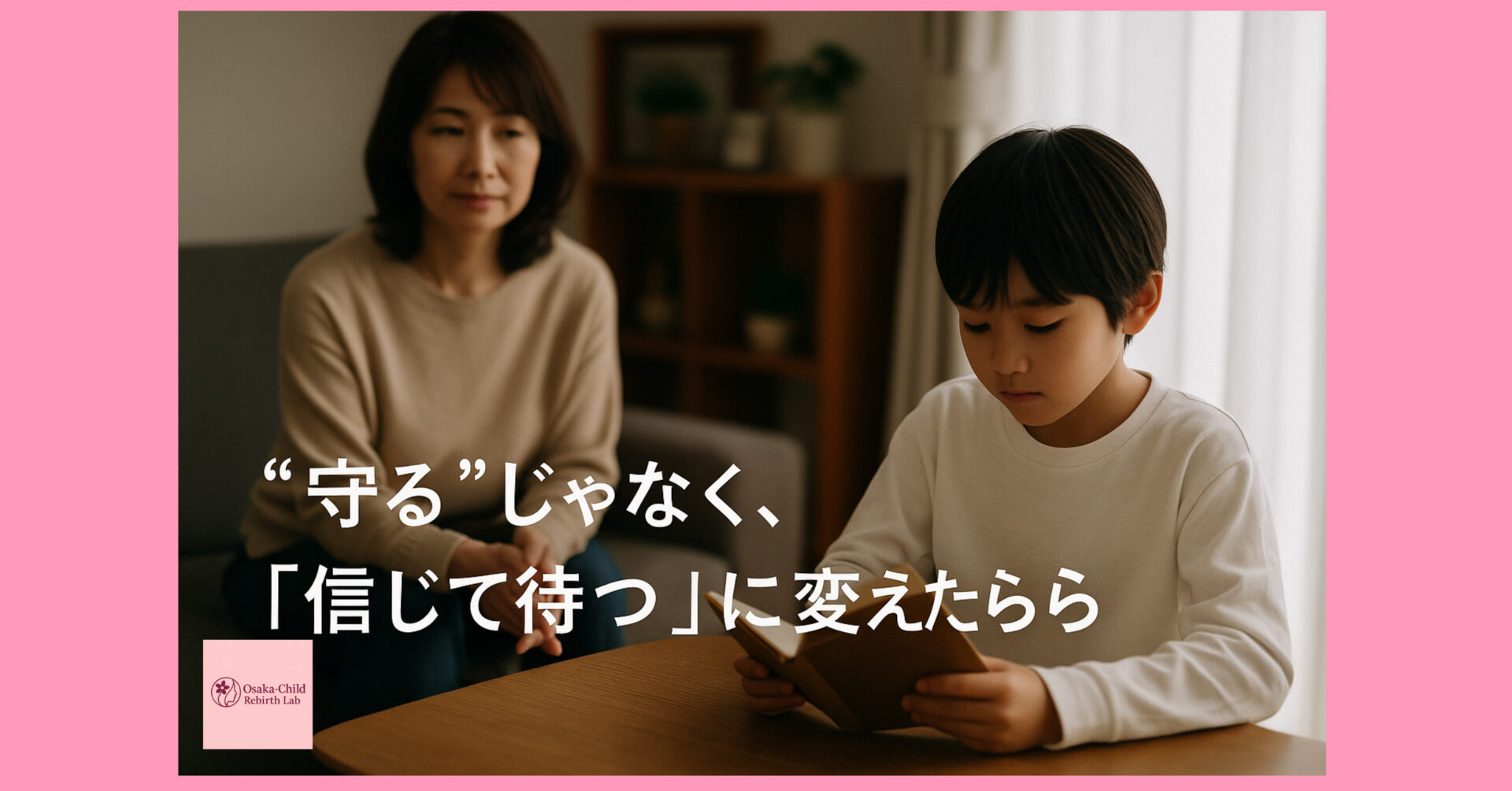
“親子の共依存”に気づいた今が、変わるタイミングです
「子どものため」に頑張ってきたはずなのに、
なぜか親子関係がすれ違ってしまう…。
その背景にあるのが、「母との共依存」の連鎖かもしれません。
3週間で、その連鎖を「わたしの代で終わらせる」サポートです。
共依存という見えにくい悩みを抱えながら、子どもの不登校問題に直面していた40代の母親たち。
彼女たちが
「株式会社OsakaChildの自己再構築支援プログラム」をつうじて、
どのように自分を見つめ直し、
親子関係を再構築していったのか──その実例を読みもの形式でご紹介します。
【事例1】「ママといると苦しい」──小学6年生T君と、共依存に悩むCさんの挑戦
T君は2年間の不登校生活のなかで、無気力になり、学校どころか日常への興味さえ失っていました。
母親のCさんは、毎日「どうすればいいのかわからない」と自責の念にかられ、共依存的な言動が強まっていました。
Osaka-Childの支援がはじまったのは、Cさんが「もう自分ではささえきれない」と電話をしてきた日からでした。
支援ではまず、Cさんにたいするカウンセリングとセラピーを開始。
Cさんは幼少期から誰かの期待に応えることで自分の価値を感じていたことに気づき、はじめて「自分の気持ち」に目を向ける時間を持ちました。
同時にT君にも、自己否定から自己肯定へとつなぐ心理ワークが施されました。
触覚刺激を中心としたカラダの調整(これは別プログラムです)により安心感を得たT君は、家庭学習にも意欲を見せはじめました。
「株式会社OsakaChildの自己再構築支援プログラム」では親子それぞれに10回以上の個別セッションと、復学後の生活支援が1年つづきました。
結果、T君は中学1年の3学期から登校を再開。
「学校って、前より居やすい」と笑えるまでに回復しました。
ポイント
Cさんもまた、「子どもに頼られなくても、自分には価値がある」と言えるようになったのです。
【事例2】「家の中が戦場だった」──小5M君と、怒鳴る母Rさんの再出発
小学5年のM君は、家庭内の争いを目にするたびに涙を流し、「学校に行くより家にいた方がマシ」とココロを閉ざしていました。
母親のRさんは、不安が高まると怒りに転化し、息子を叱責する日々。
夫婦間のつかみ合いも日常的でした。
Osaka-Childは、まずRさんの過去──母親から認めてもらえなかった子ども時代に焦点をあて、「親である前に、ひとりの女性としてのRさん」を取りもどすセッションを開始しました。
いっぽう、M君には家庭外の安心できる大人としてのカウンセラーを配置。
心理面と身体面の両方からサポートし、「怖くない大人」「受け止めてくれる存在」がいることを繰り返し伝えていきました。
「株式会社OsakaChildの自己再構築支援プログラム」では、家庭内暴力による恐怖の記憶をケアするワークや、学校復帰後に起こるであろう再フラッシュバックに備えた準備も行いました。
M君は6年の2学期から登校を再開し、今では友達と鬼ごっこをするほどに。
ポイント
Rさんも「怒りに任せて叱ることがなくなった」と、親子の会話が穏やかになったことを実感しています。
【事例3】「受験はゴールじゃなかった」──中3Uさん、脱力と母Kさんのうつからの回復
中学3年で受験を乗り越えたUさん。
しかし、入学後は「何のためにがんばったのか分からない」と燃え尽き、不登校に。
母親のKさんも「こんなふうにさせたのは自分」と責めつづけ、ついにうつ症状にまで悪化してしまいます。
Osaka-Childでは、まずKさんのココロの安全を確保するため、週2回のカウンセリングと1日1回のサポートLINEを提供。
「わたしは失敗していない」という自己肯定感を取り戻すプロセスをていねいに支援しました。
Uさんには、学校に行けないことを「自分のせい」と思わない視点を与え、「今ここ」の感覚に意識を戻す練習を続けました。
「株式会社OsakaChildの自己再構築支援プログラム」では母子にそれぞれ個別サポートが提供され、特に母Kさんの「感情の言語化」が鍵となりました。
Uさんは高校1年の秋から再登校。
受験のがんばりは「今の自分の糧だった」と言えるようになりました。
【事例4】「勉強はできる。でも心が動かない」──中2T君と、ASD傾向に寄り添った支援
中学2年のT君は、家で教科書を何度も読み込み、自習していましたが、成績は伸びず「結果が出ない」と絶望していました。
母親のPさんは、そんな息子に「もっとがんばれ」と声をかけ続けるいっぽうで、自分自身も孤独と無力感を抱えていました。
Osaka-Childでは、T君のASD傾向をふまえ、カラダをつうじてココロを緩めるアプローチを導入。
わらべ歌運動やリズム運動、小さな成功体験の積み上げを重ねていきました。
Pさんには「共感的無関心(過干渉ではなく見守る力)」を習得するためのワークと、インナーチャイルドケアを提供。
「株式会社OsakaChildの自己再構築支援プログラム」では復学後の1年間支援も含まれており、学習支援と並行して生活習慣の整え直しも実施。
T君は中学3年の2学期に復学。
今では部活の仮入部も経験し、「自分から友達に話しかけてみた」と報告してくれるまでになりました。
【事例5】「受験に勝って、人生に負けた気がした」──高1U君と母Cさんの再起動
U君は、偏差値を25も上げて進学校に合格しました。
しかし、入学してすぐに「なんのためにがんばったのか分からない」と無気力に。
朝起きると吐き気がして、登校できなくなりました。
母親のCさんは「せっかくここまで来たのに」とあせり、次第にU君にプレッシャーをかけるようになっていました。
Osaka-Childは、Cさんの共依存的パターンをていねいにほどき、「母としての役割」と「女性としての自分」を分けて考えるセッションを実施。
U君には、身体の調整(重心・自律神経・姿勢バランス・別プログラム)と並行して、「勉強以外の成功体験」に意識を向ける支援が行われました。
「株式会社OsakaChildの自己再構築支援プログラム」では、将来設計と学び直しをセットで提供。
U君は自分の強みと興味を再発見し、「自分なりの生き方」を模索しはじめました。
復学後も継続支援が行われ、高校2年を迎える今、「週3日は登校できる自分」を誇らしく感じているそうです。
どのケースも、「共依存を抱える母」と「不登校の子ども」がていねいに向き合うプロセスがありました。
株式会社OsakaChildの自己再構築支援プログラムは、ただのカウンセリングではなく、親子の再構築に必要なすべてを支える包括的なサポートです。あなたやあなたの家族にも、再出発のチャンスはきっとあります。
「共依存から『私』を取り戻す」ことが、子どもの人生を守ることにつながる
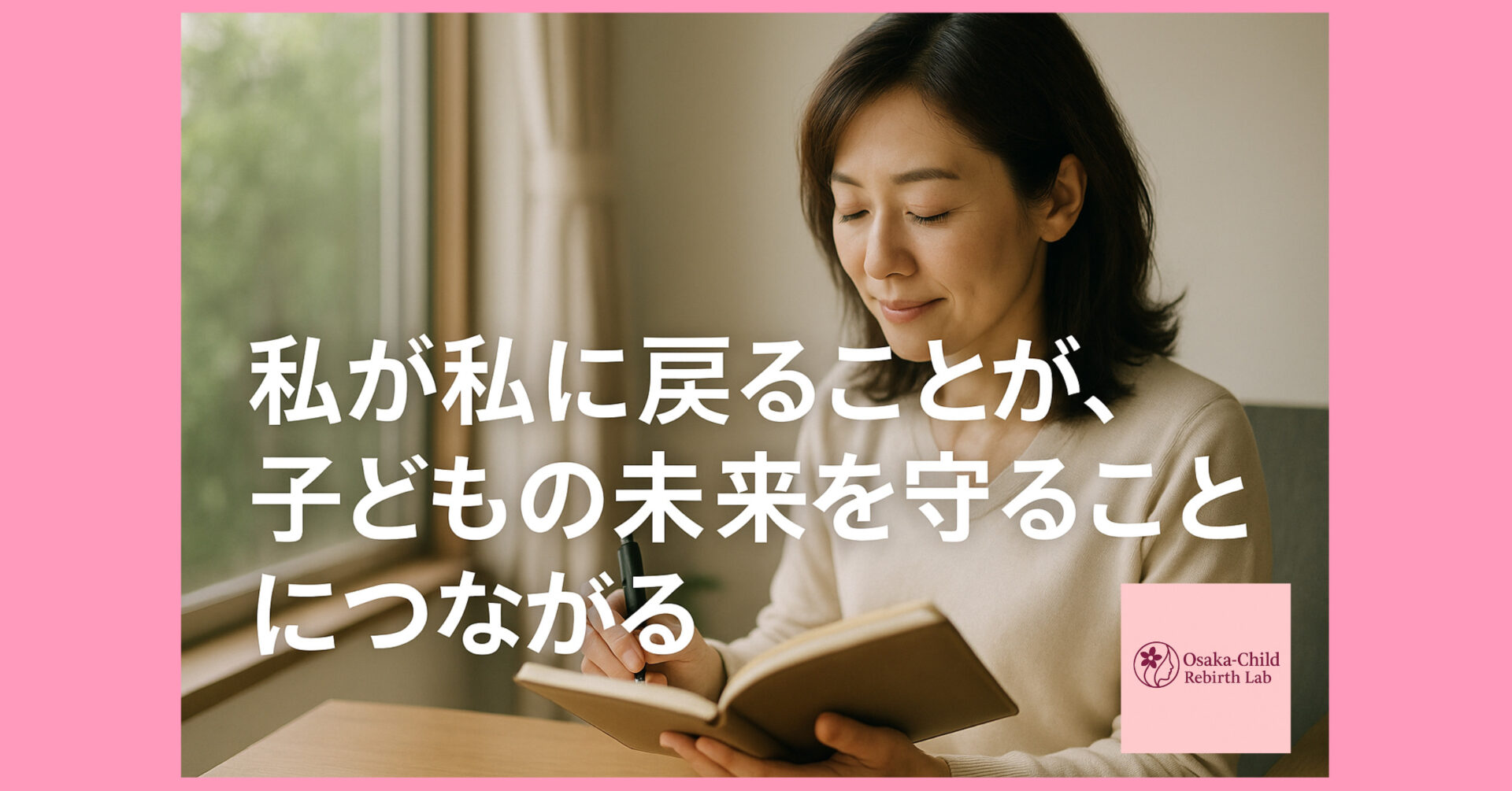
ここまで紹介してきた5つの事例は、
決して遠い誰かの話じゃありません。
- 感情的になりたくて怒ったわけじゃない。
- 傷つけたくて言い過ぎたわけでもない。
ただ、本当に守りたかっただけなんです。
家族を壊さないように。
子どもを失わないように。
でもね――
その「守ろうとする気持ち」が、
いつの間にか「我慢」や「犠牲」に変わっていた。
そんな気がして、苦しかったはずです。
それはあなたが悪かったわけじゃない。
ただ、
「自分と人との境界線を持つ」ということを、
誰にも教えてもらえなかっただけです。
ずっと、一人でがんばってきた証なんですよね。
我慢と犠牲でつながっていた親子関係を、健やかな「共感」へと変える
- 「あなたのためを思って言ってる」
- 「勉強してくれなきゃ困るの」
- 「何度言えばわかるの?」
そうやって、
親の側の
- 「つらさ」
- 「不安」
が、
言葉を通して子どもに流れ込んでしまうことがあるんです。
しかも
それが、「愛情」の形だと思い込んできた場合には、
なおさら気づきにくい。
子どもって、本当に敏感です。
- 「ママを怒らせないように」
- 「これ以上、傷つけたくない」
そんなふうに、気づけば自分を消して親に合わせていく。
そして親のほうもまた、
自分の気持ちをうまく言えなくなっていくんですよね。
一生懸命やっているはずなのに、
- どこかズレていく。
- 通じない。
- 寂しい。
- 怖い。
でも、そこで必要なのは「関係を正すこと」じゃない。
まず、あなた自身が「自分を取り戻すこと」なんです。
関係は、
修正じゃなくて「再出発」でいい。
親子でも、やり直せます。
そのための最初の一歩は、
いつだって「あなた自身のために生き直す」と決めることから始まるんです。
自分を取り戻す3週間が、親子関係の「再出発」になる
- 「どうしてうまくいかないんだろう」
- 「こんなに頑張ってるのに」
- 「もう、どうしていいかわからない」
――そんな気持ちで、いっぱいになっていたはずです。
子どものために、
家族のために、
毎日なにもかも背負ってきたんですよね。
でもね、
どれだけ愛していても
どれだけ尽くしても
自分をすり減らすやり方では限界がきてしまう。
親子関係をやり直すために必要なのは、
子どもを変えることじゃありません。
まずは、
あなたが「自分の感情」を感じ直すことなんです。
- 「私は本当は、どう感じていたのか」
- 「なんでこんなに苦しかったのか」
- 「どこで『自分』が消えてしまったのか」
それを知るだけで、
親としての態度や言葉は自然と変わっていきます。
子どもに伝わるのは、正しさじゃなくて「本音の温度」だからです。
私たちが提供している
「共依存から『私』を取り戻す」3週間リペアレンティング・サポート
は、そんな「自分の感情と関係を結び直す時間」です。
- 自分の気持ちがよくわからない
- NOを言うのが怖い
- どうせ私が我慢すればいいと思ってしまう
──そんな毎日を終わらせて、
「私は私、子どもは子ども」と、
健やかな距離で関われるようになるための3週間です。
母親としての役割を果たすためじゃない。
人としての「あなた自身」を取り戻すために。
その変化は、必ず子どもにも届いていきます。
あなたが変わることで、
子どもも「安心して自由になっていい」と感じられるようになるんです。
“母のようにはなりたくない”と願うあなたへ
「母との関係が苦しかった」
──そう感じていたのに、気づけば自分も同じように子どもを縛ってしまう。
「もう、こんな生き方は終わりにしたい」
そう思ったあなたへ。
愛されるために自分を抑えて、
「いい娘」でいようと頑張りすぎてきた過去。
それが、今の生きづらさの根っこになっていることもあります。
「共依存から『私』を取り戻す」3週間リペアレンティング・サポートは、
親との関係で傷ついたあなたが、自分の気持ちに正直になる練習をする時間です。
母の期待に応えるためではなく、
子どもを正しく育てるためでもなく、
「私の人生」を、自分の感情で生き直すために。
今こそ、「母から受け継いだ共依存」を手放す3週間を。
まとめ|「もう私ばかりが我慢する関係は終わりにしたい」と思ったあなたへ
ずっと、誰かの期待に応えようとしてきた。
- 家族
- パートナー
- 子ども――。
大切にしたい人たちのことを考えて、
気づけば自分の感情や限界はどこかに押し込めていた。
- 「私さえ我慢すればうまくいく」
- 「私が支えなきゃ、あの人は壊れてしまう」
- そう思ってきたけれど、なぜかうまくいかない。
- いつも同じような関係で疲れて、傷ついて、でもやめられない。
それは、あなたが弱いからではありません。
ただ「人との境界線の引き方」を、
これまで誰にも教わってこなかっただけなのです。
この記事では、
共依存の関係がどう築かれ、
どう私たちを苦しめるのかを整理してきました。
あらためて、今日の要点を振り返ってみましょう。
この記事のまとめ
- 共依存とは「自分を犠牲にして相手に尽くしすぎる関係性」のこと
- アダルトチルドレン傾向の人ほど、共依存関係に陥りやすい
- 親子・恋愛・夫婦など、あらゆる関係で「境界のあいまいさ」が繰り返される
- 我慢や自己犠牲を「愛」だとすり替えられてきた背景がある
- 回復には、まず「自分の感情」に気づき、線引きを学ぶことが必要
この記事を読み終えたあなたが、
ふとココロのどこかで
「このままの関係を続けたくない」と感じたなら――。
それは、変わる準備がもう始まっているということです。
他人の期待や役割の中で生きてきた人生を、
ここで終わらせていい。
これからは、
「自分を大切にする」という関係性を、
あなたの人生に取り戻していく番です。
そんな、関係のなかで「自分を見失ってきた」あなたへ。
私たちは、
「共依存から『私』を取り戻す」3週間リペアレンティング・サポートをご用意しています。
このサポートは、
- 相手の顔色をうかがってしまう
- NOが言えず、いつも自分を後回しにしてきた
- 「私なんて」と自己価値を下げてしまう
──そんな関係パターンから抜け出し、
自分の感情に正直に、人と健やかに関われる自分を取り戻すための3週間です。
- 我慢ではなく、理解によってつながる関係へ。
- 傷つけ合うのではなく、尊重し合える関係へ。
そのためにまず必要なのは、
「他人の感情」ではなく、「自分の感情」を人生の中心に置くこと。
誰かに振り回される人生から、自分の足で立つ人生へ。
その第一歩を、ここから一緒に始めてみませんか?
期間限定
「このまま、我慢しつづける人生で終わりたくない」
──そう気づいたあなたが、今ここにいます。
関係を変えるって、怖いことです。
でもそれ以上に、「ずっと自分を後回しにしてきた人生」をこのまま続けるほうが、もっと怖い。
共依存から抜け出すには、
「誰かの感情」ではなく、「自分の感情」を人生の中心に置くことが、第一歩になります。
この《「共依存から『私』を取り戻す」3週間リペアレンティング・サポート》は、
「尽くしすぎる私」から、「境界線を持てる私」へと、ココロの立ち位置を変える3週間。
人間関係に振り回されない「自分軸」を、もう一度取り戻すための回復プログラムです。
こんなあなたへ
- 「助けなきゃ」と思って動いてしまい、あとでどっと疲れる
- パートナーや親との関係に、未消化な怒りや悲しさが残っている
- 人間関係の距離感がわからず、いつも消耗してしまう
✅ 【銀行振込限定・特典付き】でご案内中です。
🔸 本日 2月28日(土)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと2名様限定』
※銀行振込限定・先着順
ネットバンキングのご利用で、今すぐ開始することが可能です。
そして──
「もっと自由に、自分の人生を生きたい」と感じたあなたへ。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
「他人軸の人生」を終わらせ、「私としての人生」を再構築するための本格支援です。
- 自分の気持ちが一番後回しになってきた
- 「誰かのため」ではなく「私のため」に人生を創りたい
- 今度こそ「自分で決める」生き方に切り替えたい
「私がどうしたいか」を取り戻すことで、人生は動き出します。
※《3週間集中リペアレンティングサポート》受講者限定
▶︎ 株式会社Osaka-Childの母親・子ども支援まとめを見る(心理・不登校・身体調整など・左の▼をクリック)
株式会社Osaka-Childの3人の子育てでストレスがたかい40代女性の心理作用をととのえるカウンセリング
子育ての真っ最中で、仕事と家庭の間で揺れ動いている女性の皆さんへ。私たちのカウンセリングサービスは、あなたのためにあります。もし心の中で悩みや生きづらさを感じている場合、それは特別な心のケアが必要な証拠です。株式会社Osaka-Childとして、日々の生活で直面している困難を理解し、その解決をサポートします。
私たちは、あなたが人生の困難に立ち向かう勇気を見つけるための安全な空間を提供します。当社のプロフェッショナルなカウンセラーは、あなたの問題や感情に深い理解を持ち、あなたを尊重します。ここでは、あなたの気持ちを自由に表現し、過去の影響から解放され、自分自身を再発見することができるでしょう。
カウンセリングは、心理システムの問題を共に解決するための有力な手段です。私たちのカウンセリングでは、まずじっくりとあなたのお話を聴きます。過去の経験やトラウマ、日常生活でのストレスなど、あなたが抱える悩みや心の中での葛藤を理解し、共感します。その後、適切なカウンセリング技法を用いて、心の中のブロックを取り除き、自分自身と向き合い、成長するためのサポートを行います。
初めての方でも、私たちのサービスを利用することはとても簡単です。当社のウェブサイト上で、カウンセリングセッションの申し込みをすることができます。また、具体的な問い合わせや不明点がある場合は、お気軽に当社までメールをお送りください。
心の中で抱える悩みや生きづらさに苦しんでいるなら、あなたは一人ではありません。株式会社Osaka-Childは、あなたが自分自身の価値を見つけ、生活の質を改善するためのサポートを提供します。カウンセリングを通じて、あなたがより健康的で充実した人生を歩む手助けをいたします。
カウンセリングのプロセスは、あなたの個別のニーズや目標に合わせてカスタマイズされます。私たちは、あなたが心地よく感じるペースでサポートを提供し、尊重と信頼の関係を築くことを大切にしています。カウンセリングを通じて、自己理解を深め、心の中の問題を克服し、より充実した人生を築いていきましょう。
あなたが心の支えを必要としているなら、ぜひ株式会社Osaka-Childのカウンセリングにお越しください。私たちがあなたの側にいて、共に問題を解決し、より健康で幸せな未来を築くお手伝いをいたします。一歩踏み出す勇気を持ってください。私たちと一緒に、新しい人生の扉を開いてみましょう。
\本気で変わりたい40代母親へ/
子どもとの関係、自分の人生、どちらもあきらめない方法があります。
33万円・50万円の本格プログラムで、臨床心理士とマンツーマンであなたの「再スタート」をサポートします。
▶ 「母との関係を整える3週間集中プログラム」受付中(銀行振込限定価格)
▶ 自分を整えた“その先”へ──発信・働き方・人生の選び直しをサポート(受講者専用)
小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援事業をする株式会社Osaka-Childとは?




【 復学率100% 】小中学生復学支援Osaka-Childの支援策とは?
こちらもCHECK
-

-
【 復学率100% 】小中学生復学支援Osaka-Childの支援策とは?
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
【堺市】不登校の子どもをサポートする!Osaka-Childのカウンセリング支援
こちらもCHECK
-

-
【堺市】不登校の子どもをサポートする!Osaka-Childのカウンセリング支援
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 Osaka-Childは、堺市にある不登校の子どもたちとその家族を支援するカウンセリ ...
続きを見る
復学支援の専門家が教える、家庭学習支援のポイントと効果的な学習方法
株式会社Osaka-Childの心理技法・心理検査一覧
株式会社Osaka-Childの障害一覧
株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:母親のメンタルサポート


支援内容
1. オキシトシン分泌促進で子どもに接する母親の専門的なカウンセリング
2. 胎児期から乳児期のオキシトシン分泌状態の再経験
3. 母親の子育ての疲れやストレスの軽減
4. 母親の胎児期・幼少期の体験のインナーチャイルドの修正
5. 母親の親子関係をカウンセリングにより気づかせる
6. カウンセリングによって母親の生き方を主体性を持たせる
7. 幼少期に得られなかった愛着の再構築
8. 個人に合った最適な心理システムの再起動
9. 母親を子どもの親から一個人としての存在の獲得
10. 愛着育成による自己肯定感の向上
11. 人生軸上でインストールした感覚ー認識の空洞化
母親のメンタルサポートの具体的なアプローチ
株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、母親のメンタルサポートを提供しています。以下に、具体的な支援内容を説明します。
- オキシトシン分泌促進で子どもに接する母親の専門的なカウンセリング オキシトシンは愛着や絆の形成に関与するホルモンであり、母親と子どもの関係を深める重要な役割を果たします。カウンセリングにおいては、母親がオキシトシン分泌を促進する方法や子どもとの関わり方について学びます。
- 胎児期から乳児期のオキシトシン分泌状態の再経験 母親が胎児期から乳児期の自身のオキシトシン分泌状態を再経験することで、子どもとの関係性や愛着形成に関する理解を深めます。これにより、母親はより適切な愛着行動を身につけ、子どもの安定した成長を支援します。
- 母親の子育ての疲れやストレスの軽減 子育てにおける疲れやストレスは母親のメンタルヘルスに大きな影響を与えます。専門的なカウンセリングにより、母親の疲れやストレスを軽減し、心の健康を保つための具体的なケア方法を提供します。
- 母親の胎児期・幼少期の体験のインナーチャイルドの修正 母親の胎児期や幼少期におけるトラウマや負の体験は、子育てに影響を及ぼすことがあります。カウンセリングにより、母親は自身のインナーチャイルド(内なる子どもの存在)の修正を通じて、子育てにおける負のパターンを変容させます。
- 母親の親子関係をカウンセリングにより気づかせる 母親の親子関係に潜むパターンや影響をカウンセリングを通じて明示し、母親自身がその関係性に気づくことを支援します。これにより、母親はより良好な親子関係を構築し、子どもの成長を促進します。
- カウンセリングによって母親の生き方を主体性を持たせる 母親が自身の生き方を主体的に選択し、子どもとの関係性をより意識的に築いていくことを支援します。母親の個別のニーズや目標を考慮し、適切なカウンセリングプランを策定します。
- 幼少期に得られなかった愛着の再構築 母親が幼少期に得られなかった愛着を再構築することで、自己肯定感や安心感を向上させます。カウンセリングにおいては、母親が自身の愛着スタイルや関わり方を理解し、健全な愛着関係の構築に向けた具体的なアプローチを身につけます。
- 個人に合った最適な心理システムの再起動 母親の心理システムの再起動により、ストレスへの対処能力や情緒調整能力を向上させます。カウンセリングにより、母親は自身の心理的な困難や制約を克服し、より健康的な心の状態を取り戻すことができます。
- 母親を子どもの親から一個人としての存在として認識 母親が自身を単に子どもの親としてではなく、個別の存在として認識することを支援します。母親の自己アイデンティティや自己実現の重要性を再確認し、自己成長とバランスの取れた生活を促進します。
- 愛着育成による自己肯定感の向上 母親が子どもとの愛着関係を育むことで、自己肯定感や自己価値感を向上させます。カウンセリングにおいては、母親が愛着行動やコミュニケーションスキルを向上させるための具体的な手法やアドバイスを受け取ります。
- 人生軸上でインストールした感覚ー認識の空洞化 母親が人生軸上で自身の感覚や認識を見つめ直し、新たな視点や意味づけを行うことを支援します。これにより、母親はよりポジティブな心理状態を持ち、子どもとの関係や子育てにおいてより健全な選択を行うことができます。
具体的な支援内容として、母親は定期的なカウンセリングセッションを通じて自身のメンタルヘルスや子育てに関する課題を共有し、カウンセラーとの対話やアドバイスを受け取ります。また、母親には日常生活におけるストレス管理や自己ケアの方法、感情の調整やコミュニケーションスキルの向上など、実践的なツールや戦略が提供されます。
大阪の不登校カウンセリング|40代の母親が必知!子供の不登校を解決する支援方法と専門家のアドバイス
こちらもCHECK
-

-
大阪の不登校カウンセリング|40代の母親が必知!子供の不登校を解決する支援方法と専門家のアドバイス
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 子供の不登校は多くの40代の母親にとって深刻な悩みです。その解決には適切な支援方法と ...
続きを見る
【40代母親からの第一歩】不登校問題解決への道と専門カウンセリングでの導き
こちらもCHECK
-

-
【40代母親からの第一歩】不登校問題解決への道と専門カウンセリングでの導き
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 40代の母親が抱える不登校問題は深刻な課題です。子どもの不登校により家庭や学校の関係 ...
続きを見る
【幸せホルモン】オキシトシンの増やし方12選|瞑想やマインドセット・身体調整が効果的
不登校の原因を知る方法!40代の母親が的確にサポートする方法とは?
中学生の不登校の原因は母親にあった!母親へのカウンセリングで復学につなげる
【40代子育ての悩み】不登校の原因を解明!不登校になる子の親の特徴と改善策
株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どものカウンセリング


支援内容
1. 不登校の子どもが抱えるココロの動きの促進
2. 幼少期の負の体験の心理システムの循環
3. 親子関係による負の自己イメージの軌道修正
4. 学校環境での存在価値の促進
5. 過去ー現在ー未来の時間軸の自然循環
6. 幼少期に遺伝的にもっているエネルギーの再生成
7. 学校環境で経験した負の要素への関わり
8. 学校環境で作られた他者との競争原理の滅尽
9. 母親では得られなかった愛着をカウンセラーとの共有で再獲得
10. 幼少期のゼロベースでの人間像への気づき
11. 負の心理システムで構成された世界観の抑制
不登校の子どものカウンセリングの具体的なアプローチ
- 不登校の子どもが抱えるココロの動きの促進 不登校の子どもは心理的な負担を抱えている場合があります。私たちは、子どものココロの動きを理解し、彼らが抱える不安やストレスを軽減するための支援を行います。具体的な方法としては、感情の表現や認識のトレーニング、リラクゼーション技法の導入などがあります。また、子どもが自己理解を深め、自己肯定感を高めるために、自己探索のプロセスにも取り組みます。
- 幼少期の負の体験の心理システムの循環 幼少期に経験した負の出来事やトラウマは、不登校の原因となることがあります。私たちは、そのような負の体験が心理システムにどのように影響を与え、循環するのかを理解し、子どもと共にその解決に向けた取り組みを行います。具体的には、トラウマ解消のための技法や自己発見のプロセスを通じて、過去の負の経験に対処し、新たな自己概念を構築するサポートを行います。
- 親子関係による負の自己イメージの軌道修正 親子関係は子どもの自己イメージに大きな影響を与えます。不登校の子どもにおいては、負の自己イメージが形成されることがあります。私たちは、子どもと親の関係を理解し、親子のコミュニケーションの改善や共感的な対話を通じて、子どもの自己イメージの軌道修正を支援します。親には、子どもの感情や困難に対して理解を示し、受け入れる姿勢を促すためのアドバイスや指導を提供します。
- 学校環境での存在価値の促進 不登校の子どもは学校環境での存在価値や自己肯定感に欠けていることがあります。私たちは、子どもが学校での存在感を取り戻すための支援を行います。具体的には、学校との連携や学校内でのサポート体制の構築を行い、子どもが自分の能力や才能を発揮できる場を提供します。また、学校生活の中での達成感や成功体験を通じて、子どもの自信を育む取り組みも行います。
- 過去ー現在ー未来の時間軸の自然循環 不登校の子どもは、過去の困難や現在の問題に囚われる傾向があります。私たちは、子どもが過去、現在、未来の時間軸を自然に循環できるように支援します。過去の出来事への執着や現在の問題に対する固執を解放し、未来に向けて前向きに取り組むことを促します。具体的な方法としては、目標設定や将来のビジョンの明確化、行動計画の策定などがあります。
- 幼少期に遺伝的に持っているエネルギーの再生成 子どもの行動や感情は、幼少期に遺伝的に受け継がれたエネルギーによって影響を受けることがあります。私たちは、子どもが遺伝的に持っているエネルギーを再生成し、ポジティブな方向へと導くための支援を行います。具体的には、子どもが自己観察や自己理解を深めるプロセスを通じて、自己変容を促すことに焦点を当てます。
- 学校環境で経験した負の要素への関わり 不登校の子どもは、学校環境での負の要素に対して適切に関わることができない場合があります。私たちは、子どもが学校環境での負の要素に対して適切に対処できるように支援します。具体的には、コミュニケーションスキルのトレーニングや問題解決能力の向上を促すプログラムを提供し、子どもが対処方法を見つけられるようにサポートします。
- 学校環境で作られた他者との競争原理の滅尽 学校環境では競争原理が存在し、不登校の子どもにとっては負の影響を与えることがあります。私たちは、他者との競争原理を滅尽し、協力や共感の文化を醸成する支援を行います。具体的には、協調性やチームワークの重要性を学ぶ活動や、他者との比較ではなく自己の成長に焦点を当てる指導を行います。
- 母親では得られなかった愛着をカウンセラーとの共有で再獲得 不登校の子どもの中には、母親からの愛着が不足している場合があります。私たちは、子どもがカウンセラーとの関係を通じて、得られなかった愛着を再獲得できるように支援します。子どもが安心感や信頼感を育み、自己価値感や自己受容感を高めるために、カウンセラーとの関係性を重視したアプローチを取ります。
- 幼少期のゼロベースでの人間像への気づき 不登校の子どもには、幼少期に根付いた人間像や自己イメージに問題がある場合があります。私たちは、子どもが自己観察や内省を通じて、幼少期のゼロベースから新たな人間像への気づきを促す支援を行います。具体的には、自己評価の見直しやポジティブな特性の発見、適応的な思考や行動パターンの構築をサポートします。
- 負の心理システムで構成された世界観の抑制 不登校の子どもは、負の心理システムで構成された世界観を持っていることがあります。私たちは、子どもがそのような負の世界観から抜け出し、ポジティブな視点や心理的な柔軟性を取り戻すための支援を行います。
具体的には、認知行動療法やポジティブ心理学の手法を用いて、子どもの思考や信念の再構築を促し、より健康的な心理システムを構築します。 株式会社Osaka-Childの臨床心理士(カウンセラー・セラピスト・不登校専門カウンセラー)として、私たちは不登校の子どもとその家族に対して、個別に適した支援を提供します。子どもの心の健康を重視し、不登校の原因や状況を的確に把握した上で、専門知識や経験に基づいたアプローチを用いてサポートを行います。私たちの目標は、子どもが健やかな学校生活を送り、自己成長や社会参加の機会を最大限に引き出すことです。
不登校カウンセリングでHSCの子どもを復学支援に|HSCの子どもを持つ40代の母親に向けて
こちらもCHECK
株式会社Osaka-Childのカウンセリング技法
カウンセリングとは?心理システムを正常化して生きづらさを克服する効果最大
-

-
参考カウンセリングとは?心理システムを正常化して生きづらさを克服する効果最大
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
来談者中心療法で心理システムを自然状態にして精神的苦しみを克服|40代女性の生きづらさ克服
-

-
参考来談者中心療法で心理システムを自然状態にして精神的苦しみを克服|40代女性の生きづらさ克服
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
トラウマインフォームドケアをカウンセリングで心理システムの最短正常化に
-

-
参考トラウマインフォームドケアをカウンセリングで心理システムの最短正常化に
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
オンラインカウンセリングのメリット・デメリットを知って手軽に心理システムを正常化する
-

-
参考オンラインカウンセリングのメリット・デメリットを知って手軽に心理システムを正常化する
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
精神分析的心理療法でカウンセリングを実施し心理システムの正常化で生きづらさ克服
株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの身体調整


支援内容
1. 子どもの姿勢コントロールの修正
2. 姿勢コントロールによる身体アライメント構築
3. 姿勢コントロールから重心作り
4. 学習に不可欠な座り姿勢での姿勢コントロールの促通
5. 姿勢に伴う手の運動構成のバランス
6. 姿勢と視覚・聴覚情報の同期
7. 全身の関節運動・筋肉の出力調整
8. 三半規管や脳神経系の出力の修正
9. ハンドリングによる触覚刺激で感覚系のコントロール
10. 皮ふ刺激によるオキシトシン分泌の促進
11. 皮ふ・筋膜・筋肉・筋肉の長さのセンサーのコントロール
12. 感覚ー認識システム促通から無の状態へのアップデート
13. 身体への関わりによる不足した愛着の向上
14. 負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化
15. 負の心理システムから身体への過剰な意識への抑制
不登校の子どもの身体調整の具体的なアプローチ
株式会社Osaka-Childでは、不登校の小中学高校生や発達障害の子どもの復学支援の一環として、身体調整の支援を行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。
- 子どもの姿勢コントロールの修正 子どもの姿勢は、身体の調整や感覚統合に重要な役割を果たします。不適切な姿勢が存在する場合、学習や集中力に悪影響を与えることがあります。私たちは、子どもの姿勢を正しい形に修正し、適切な姿勢コントロールをサポートします。具体的には、姿勢の矯正や筋力トレーニング、姿勢保持のためのエルゴノミクス指導などを行います。
- 姿勢コントロールによる身体アライメント構築 姿勢の改善は、身体のアライメントやバランスの向上につながります。私たちは、子どもの身体アライメントを構築するために、姿勢コントロールのトレーニングを行います。これには、正しい姿勢の保持や身体の軸の調整、バランス感覚の向上などが含まれます。
- 姿勢コントロールから重心作り 姿勢と重心の関係は、身体の安定性や運動の質に大きな影響を与えます。私たちは、姿勢コントロールから重心の形成に焦点を当て、子どもが適切な重心を持つことをサポートします。具体的には、姿勢トレーニングやバランスボードを使ったトレーニングなどを通じて、重心の安定化を促します。
- 学習に不可欠な座り姿勢での姿勢コントロールの促通 適切な座り姿勢は、学習において重要な要素です。不適切な座り姿勢は集中力の低下や身体の疲労を引き起こすことがあります。私たちは、子どもが学習に不可欠な座り姿勢を維持できるように、姿勢コントロールの促通を支援します。具体的には、正しい座り方やデスク環境の調整、体操やストレッチの指導などを行います。
- 姿勢に伴う手の運動構成のバランス 姿勢と手の運動は密接に関連しています。不適切な姿勢は手の運動にも影響を与えることがあります。私たちは、子どもの手の運動構成をバランス良く整えるために、姿勢と手の連動性を意識した支援を行います。具体的には、手の筋力や協調性のトレーニング、細かい手指の動作の指導などを行います。
- 姿勢と視覚・聴覚情報の同期 姿勢の調整と視覚・聴覚情報の適切な処理は、子どもの学習や集中力に影響を与えます。私たちは、子どもが姿勢と視覚・聴覚情報を適切に同期させるための支援を行います。具体的には、視覚情報や聴覚情報の統合を促すトレーニングやセンサリー処理の指導などを行います。
- 全身の関節運動・筋肉の出力調整 全身の関節運動や筋肉の出力の調整は、身体の柔軟性や運動能力に影響を与えます。私たちは、子どもの全身の関節運動や筋肉の出力を調整し、適切な身体の動きをサポートします。具体的には、関節の可動域の拡大や筋力トレーニング、コーディネーションの向上を目指したプログラムを提供します。
- 三半規管や脳神経系の出力の修正 三半規管や脳神経系の出力の調整は、バランス感覚や運動の調整に関与します。私たちは、子どもの三半規管や脳神経系の出力を修正し、バランス感覚や運動の質を改善するための支援を行います。具体的には、バランス感覚のトレーニングや目の運動の指導などを行います。
- ハンドリングによる触覚刺激で感覚系のコントロール 触覚刺激は感覚統合や身体の調整に重要な役割を果たします。私たちは、子どもの感覚系のコントロールを促すために、ハンドリングと呼ばれる触覚刺激を活用した支援を行います。具体的には、身体全体に触覚刺激を与えることで感覚統合を促し、身体の安定性や調整能力を高めます。
- 皮ふ刺激によるオキシトシン分泌の促進 皮ふ刺激はオキシトシンの分泌を促し、リラックスや安定感をもたらします。私たちは、子どもの皮ふ刺激を活用してオキシトシンの分泌を促進し、心身の安定をサポートします。具体的には、マッサージや触れ合いのアクティビティを通じて、子どもがリラックスした状態に入る機会を提供します。
- 皮ふ・筋膜・筋肉の長さのセンサーのコントロール 身体の皮ふ、筋膜、筋肉は長さの変化を感知するセンサーを持っています。私たちは、子どもの皮ふ・筋膜・筋肉の長さのセンサーをコントロールし、正常な身体の感覚を促します。具体的には、ストレッチや筋膜リリースなどの手法を用いて、身体の柔軟性や感覚統合を促進します。
- 感覚ー認識システム促通から無の状態へのアップデート 感覚と認識のシステムが促通し、無の状態にアップデートされることは、子どもの集中力や学習能力に大きな影響を与えます。私たちは、子どもの感覚と認識のシステムを促通させ、無の状態へのアップデートを支援します。具体的には、身体を使ったアクティビティやセンサリー統合の手法を用いて、感覚と認識の調整を促します。
- 身体への関わりによる不足した愛着の向上 不登校の子どもには、不足した愛着が存在する場合があります。私たちは、身体への関わりを通じて子どもの不足した愛着を向上させる支援を行います。具体的には、身体的な接触やアクティビティを通じて子どもとの関係性を構築し、安心感や信頼感を促します。
- 負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化 負の心理システムは、子どもの身体に過緊張や緊張を引き起こすことがあります。私たちは、負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化をサポートします。具体的には、筋肉の緊張を緩めるエクササイズやリラクゼーション法の指導を行い、身体の緊張を軽減します。
- 負の心理システムから身体への過剰な意識への抑制 負の心理システムから身体への過剰な意識は、子どもの集中力や学習に悪影響を与えることがあります。私たちは、負の心理システムから身体への過剰な意識を抑制する支援を行います。
株式会社Osaka-Childの身体調整とカウンセリング技法
催眠療法と心理カウンセリング併用で精神作用をリセット|40代女性の心理システムを正常化に
-

-
参考催眠療法と心理カウンセリング併用で精神作用をリセット|40代女性の心理システムを正常化に
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
自律訓練法とカウンセリングの併用で40代女性生きづらさ克服|自宅で簡単にできる
-

-
参考自律訓練法とカウンセリングの併用で40代女性生きづらさ克服|自宅で簡単にできる
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
呼吸法とカウンセリングで身体と精神をコントロールし40代女性が安定した人生を送る
-

-
参考呼吸法とカウンセリングで身体と精神をコントロールし40代女性が安定した人生を送る
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
メンタライゼーション・ベースド・セラピーで40代女性の心理システムを整える
-

-
参考メンタライゼーション・ベースド・セラピーで40代女性の心理システムを整える
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
グリーフケアカウンセリングで新しい自分で自然世界と調和した生き方を獲得する
-

-
参考グリーフケアカウンセリングで新しい自分で自然世界と調和した生き方を獲得する
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
リラクゼーション法で40代女性の生きづらさの身体症状を克服|目的・やり方・コツを解説
-

-
参考リラクゼーション法で40代女性の生きづらさの身体症状を克服|目的・やり方・コツを解説
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
具体的には、身体感覚の調整やマインドフルネスなどの技法を用いて、子どもの心身のバランスを整えます。 株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの身体の健康と調整を重視し、個別に適した身体調整の支援を提供します。子どもとその家族との協力を通じて、身体の調整や感覚統合の促進を図り、学習や社会生活の質を向上させることを目指します。
📌 あなたに必要な支援は、今すぐ手に届きます。
ここまで読んで「これ、私のことだ」と感じた方へ。
私たちが提供している再設計プログラムは、表面的なアドバイスではなく、根本から人生を整えるための実践型サポートです。
銀行振込限定で 最大5万円割引・個別相談枠の優先予約も受付中。
▶ 「母との関係を整える3週間集中プログラム」受付中(銀行振込限定価格)
▶ 自分を整えた“その先”へ──発信・働き方・人生の選び直しをサポート(受講者専用)
株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの家庭学習支援


支援内容
1. オンラインによる苦手教科の徹底的学習サポート
2. 自分に合った教材と学習法の発見と実践
3. 得意科目を地域で成績上位に入るための学習法
4. 苦手科目の時間的な関わり(量→質)
5. 予習・復習の時間共有
6. 脳内の特性に合わせた学習プログラムの実践
7. 脳内と心理システムを促通した個人に合った学習方法の習得
8. 勉強量から勉強の質への関わり
9. 不登校中の自宅でのスケジューリング
10. 勉強に対する苦手意識への心理システムの調整
11. 成績に反映する個人に合った勉強法の獲得
12. 全教科の要素分解と要素の合成への考え方の習得
13. 不登校中に偏差値を20以上向上させる学習時間と質の習得
不登校の子どもの家庭学習支援の具体的なアプローチ
株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、家庭学習の支援を行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。
- オンラインによる苦手教科の徹底的学習サポート オンラインを活用して、子どもの苦手とする教科について徹底的な学習サポートを行います。個別のオンラインチューターや学習プラットフォームを活用し、子どもが理解を深めるための指導を提供します。
- 自分に合った教材と学習法の発見と実践 子どもに合った教材や学習法を見つけ、実践するサポートを行います。子どもの学習スタイルや興味・関心に合わせて教材を選定し、効果的な学習方法を指導します。
- 得意科目を地域で成績上位に入るための学習法 子どもの得意科目を活かして、地域で成績上位に入るための学習法を指導します。具体的な学習戦略やアプローチを提供し、子どもが得意科目での自信と成果を得られるように支援します。
- 苦手科目の時間的な関わり(量→質) 苦手科目に対する学習時間を質の高いものにするための支援を行います。集中力を高めるための学習スケジュールの作成や、効果的な学習方法の指導を通じて、苦手科目への取り組みを効果的に進める方法を提供します。
- 予習・復習の時間共有 予習と復習の重要性を理解し、効果的に取り組むために、子どもと共有する時間を設けます。予習や復習の方法や具体的な計画の立て方を指導し、子どもが学習内容を定着させるサポートを行います。
- 脳内の特性に合わせた学習プログラムの実践 子どもの脳の特性に合わせた学習プログラムを実践します。例えば、視覚的な学習スタイルを持つ子どもにはマインドマップやイメージングを活用し、効果的な学習を促します。
- 脳内と心理システムを促通した個人に合った学習方法の習得 子どもの脳内の機能と心理システムを促通させ、個人に合った学習方法を習得させる支援を行います。具体的には、脳の情報処理や学習スタイルを理解し、それに基づいた学習戦略やアプローチを提案します。
- 勉強量から勉強の質への関わり 勉強の量だけでなく、質の高い学習を実現するための関わりをサポートします。集中力の向上や学習環境の整備、効果的な学習テクニックの指導などを通じて、子どもが効率的かつ効果的に学習できるように支援します。
- 不登校中の自宅でのスケジューリング 不登校中の子どもが自宅での学習をスムーズに進めるためのスケジューリングのサポートを行います。適切な時間配分やタスク管理の方法を指導し、子どもが自主的に学習を進められるように支援します。
- 勉強に対する苦手意識への心理システムの調整 勉強に対する苦手意識を持つ子どもに対して、心理システムの調整を行います。適切な支援方法や学習環境の整備、ポジティブなフィードバックの提供などを通じて、子どもの勉強への意欲や自信を高める支援を行います。
- 成績に反映する個人に合った勉強法の獲得 子どもの個別の特性や学習スタイルに合わせて、成績に反映される勉強法を獲得させる支援を行います。具体的には、学習戦略の指導や学習プランの作成、効果的な学習テクニックの習得などを通じて、子どもが効果的に学習できるようにサポートします。
- 全教科の要素分解と要素の合成への考え方の習得 全教科において、学習内容を要素分解し、それらを合成する考え方を習得させる支援を行います。具体的には、重要なキーポイントの抽出や概念の整理、総合的な学習アプローチの指導などを通じて、子どもの学習能力を向上させます。
- 不登校中に偏差値を20以上向上させる学習時間と質の習得 不登校中に子どもの学習時間と質を向上させ、偏差値を20以上上げる支援を行います。適切な学習計画の策定や時間管理の指導、効果的な学習方法の習得などを通じて、子どもの学力向上を支援します。
発達支援・発達相談をカウンセリングと療育で発達障害の子どもの機能性を120%アップ
動機づけ面接とカウンセリングの併用で40代女性の個人の人生に合った生き方を見つける
ナラティヴセラピーをカウンセリングで過去の経験値を未来軸に近づけ40代女性を自己実現に
ペアレント・トレーニングで40代母親の子育てを楽にする|子どもの育ちを大切にできる
不登校中の勉強しない・遅れる不安を解決する40代母親ができる接し方とは
中3不登校生徒で勉強してない場合の受験対策や進路の選択肢|今からでも間に合う!
【40代母親必見】不登校の子が復学後に勉強しない?その原因と解決策を詳解
中学3年間不登校だと勉強してないから高校受験は難しい?中学生の不登校の原因と親ができる対応
発達障害をカウンセリングで心理システムをスムーズにし克服へ|40代女性生きづらさ解決
学習障害(LD)をカウンセリングで最短で負担なく克服させる|生きづらさ解決に
株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの家庭学習をサポートし、個別に適した学習方法や戦略を提供します。子どもとその家族との協力を通じて、学習の成果を最大化し、不登校からの復学を支援します。
株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポート


支援内容
1. カウンセリングによる自己イメージのリセット
2. 意識と覚醒の自然現象への共有
3. 好きなこと・得意なこと・使命感への気づき
4. 未来像のマインドからの発見
5. 未来像と現実の自己へのプログラミング
6. 自己内から具体的な人生設計
7. 誕生から死への人生軸への関わりと意識の促通
8. トレンド情報に流されない個人に合った生き方の習得
9. 努力せずありのままで成果が出るキャリアとプロセスの構築
10. 学校環境での失敗体験の再現化と捨てる作業
11. 世界を構造から見つけていくトレーナーとの共有
不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポートの具体的なアプローチ
株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、進学やキャリアデザインのサポートを行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。
- カウンセリングによる自己イメージのリセット カウンセリングを通じて、子どもの自己イメージをリセットします。過去の失敗や困難な経験に縛られず、新たな可能性や自己評価を見つける支援を行います。
- 意識と覚醒の自然現象への共有 子どもに対して、意識や覚醒の自然現象について共有し、自己の内面に目覚めるきっかけを与えます。具体的には、マインドフルネスや瞑想などの方法を取り入れ、子どもが内なる気づきや成長を促します。
- 好きなこと・得意なこと・使命感への気づき 子どもが自分の好きなことや得意なこと、そして使命感を見つけるための支援を行います。興味や才能を引き出し、将来の方向性を探るための活動や自己探求のプロセスをサポートします。
- 未来像のマインドからの発見 子どもが自分自身の未来像を持つことで、目標や希望を見つける手助けをします。未来を具体的にイメージすることで、自己の成長や進学・キャリアの方向性を見出すサポートを行います。
- 未来像と現実の自己へのプログラミング 子どもが描いた未来像と現実の自己を結び付けるためのプログラミングをサポートします。具体的な目標設定や行動計画の策定、自己肯定感や自己効力感の醸成を通じて、子どもの進学やキャリアの実現を支援します。
- 自己内から具体的な人生設計 子どもが自己内に持つ資源や価値観を活かし、具体的な人生設計を立てるサポートを行います。自己の内なる声や目標に基づき、将来の進路やキャリアの方向性を考えるプロセスを共に進めます。
- 誕生から死への人生軸への関わりと意識の促通 子どもに対して、人生の意義や目的、誕生から死への人生軸について考える機会を提供します。自己の存在意義や時間の尊さを理解し、将来に向けた意識の促進を支援します。
- トレンド情報に流されない個人に合った生き方の習得 子どもがトレンド情報や社会の期待に流されず、自己に合った生き方を見つけるための支援を行います。個別の特性や価値観を尊重し、自己を大切にする生き方の習得をサポートします。
- 努力せずありのままで成果が出るキャリアとプロセスの構築 子どもが努力せずにありのままの自己で成果を出せるキャリアやプロセスの構築をサポートします。個々の能力や資質を活かし、自己の個性や魅力を最大限に生かした進学やキャリアの選択を支援します。
- 学校環境での失敗体験の再現化と捨てる作業 学校環境での失敗体験を再現し、それらを手放すプロセスを支援します。過去のネガティブな体験やトラウマからの解放を促し、自己成長と前向きな展望を持つためのサポートを提供します。
- 世界を構造から見つけていくトレーナーとの共有 子どもが世界の構造や社会の仕組みを理解し、自己の進学やキャリアの選択に生かすために、トレーナーとの共有を行います。具体的な情報や知識の提供、意義や意味の理解を通じて、子どもの進学やキャリアデザインに役立つサポートをします。
対人関係療法カウンセリングで治りにくい精神疾患を正常化する|うつ病・摂食障害に効果的
ソリューション・フォーカスト・アプローチで人生の悩みを最短解決|40代女性生きづらさ克服
キャリアカウンセリング(キャリアコンサルティング)で40代女性の人生を幸福に導く
コーチングで40代女性の子育てやキャリアアップを最速に機能させる
株式会社Osaka-Childのカウンセリング技法
【2023年最新】認知行動療法(CBT)とは?方法、効果やメリット・デメリット、療法の流れなどを解説
ストレスマネジメントとは?40代女性が子育て・キャリアアップで活かせる効果ややり方を解説
-

-
参考ストレスマネジメントとは?40代女性が子育て・キャリアアップで活かせる効果ややり方を解説
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
アサーショントレーニングとは?職場や子育てで実践する方法や自己表現タイプを解説
-

-
参考アサーショントレーニングとは?職場や子育てで実践する方法や自己表現タイプを解説
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
認知再構成法とカウンセリングで40代女性の生きづらさを生む認知のゆがみを克服
-

-
参考認知再構成法とカウンセリングで40代女性の生きづらさを生む認知のゆがみを克服
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの進学やキャリアデザインを支援し、自己の可能性や夢を追求するサポートを行います。子どもとその家族との協力を通じて、自己の価値を見出し、将来への道を切り拓くお手伝いをします。
株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの子どもの不登校復学支援内容:不登校復学後の1年間のサポート


支援内容
1. 復学後の学校との連携
2. 復学後の母親と子どものカウンセリングの実施
3. 復学後に生まれる諸問題の解決と実践
4. 復学後の生きづらさの軌道修正
5. 復学後の母親のメンタルサポートの継続
6. 復学後にぶつかる学校環境での負の体験への関わり
7. 母親に生まれる子どもへの過負荷の調整
8. 母親の人生サポートの継続による子どもの自由の解放
9. 復学後に生まれる母親と子どもへの不安の共有
不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポートの具体的なアプローチ
株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学後の1年間にわたるサポートを提供しています。以下に、具体的な支援内容を説明します。
- 復学後の学校との連携 子どもの復学後において、学校との綿密な連携を行います。学校とのコミュニケーションを円滑にし、子どもの学習状況や生活面でのサポートが必要な点を把握し、適切な支援策を立てるために協力します。
- 復学後の母親と子どものカウンセリングの実施 復学後においても母親と子どものカウンセリングを実施し、お互いの心情や課題に対して向き合います。母親の支えや理解を促し、子どもの心理的な安定と学校生活への適応をサポートします。
- 復学後に生まれる諸問題の解決と実践 復学後に生じる様々な問題や課題に対して、具体的な解決策を見つけて実践する支援を行います。学校生活や人間関係のトラブル、学習上の困難などに対して、子どもと母親の双方が適切に対処できるようにサポートします。
- 復学後の生きづらさの軌道修正 復学後に感じる生きづらさや不安に対して、子どもの心理的な軌道修正を支援します。自己肯定感の向上や適切なストレス管理の方法を教えることで、子どもが学校での生活に前向きに取り組むことを支えます。
- 復学後の母親のメンタルサポートの継続 母親のメンタルサポートを復学後も継続的に行います。母親が子どもの復学に伴うストレスや不安を抱える場合には、心理的な支えや情報提供を通じて、彼女の心の健康状態を維持し、子どもへのサポートを続けます。
- 復学後にぶつかる学校環境での負の体験への関わり 復学後に学校環境での負の体験が生じた場合には、子どもがそれに適切に関わることができるようにサポートします。適切なコーピングスキルの習得や自己肯定感の強化を通じて、子どもが学校での困難に立ち向かう力を育みます。
- 母親に生まれる子どもへの過負荷の調整 復学後において、母親が子どもに対して過度な負荷を感じる場合には、適切な調整を行います。母親の負担を軽減し、子どもとの関係性を健全に保ちながら、サポートのバランスを取ることが重要です。
- 母親の人生サポートの継続による子どもの自由の解放 母親の人生全体にわたるサポートを継続し、彼女が自己の成長と発展に集中できる環境を整えます。母親の支えが安定することで、子どもはより自由に自己を表現し、学校生活を充実させることができます。
- 復学後に生まれる母親と子どもへの不安の共有 復学後に母親と子どもが抱える不安や心配事に対して、お互いがそれを共有し、解消するための場を提供します。相互の理解を深め、不安を和らげることで、子どもの復学後の安定と成長をサポートします。
ストレスコーピングとカウンセリングの併用で40代女性のキャリア・子育てに成果
マインドフルネスとカウンセリングで効果を最大に|40代女性のキャリア・子育てに成果を出す
行動活性化療法で精神的抑うつを改善|40代女性生きづらさ克服でキャリア・育児両立に
株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの不登校復学後の1年間にわたり、学校との連携や心理的なサポートを通じて、子どもと母親の両方を支えます。子どもの安定した学校生活の確立と母親のメンタルヘルスの維持に注力し、一人ひとりのニーズに合わせたサポートを提供します。
Osaka-Childは小学生・中学生の不登校のお子さまに対して最短復学支援を提供しています

株式会社Osaka-Childの支援内容とは
- 母親のメンタルサポート
- 不登校子どものカウンセリング
- 不登校子どもの身体調整
- 不登校子どもの家庭学習支援
- 不登校子どもの進学・キャリアデザインサポート
- 不登校復学後の1年間のサポート
不登校子どものカウンセリング Osaka-Childでは、専門のカウンセラーによる個別のカウンセリングを行い、不登校の原因や問題を解決するための支援を提供しています。不登校子どもの身体調整 心身共に健康であることは、不登校克服に不可欠な要素の1つです。Osaka-Childでは、体の不調を訴える子どもに対して、運動や栄養指導などの支援を提供しています。不登校子どもの家庭学習支援 学校に行けない状況であっても、家庭学習を続けることが重要です。 Osaka-Childでは、家庭学習の計画立案や実践支援を行い、学習習慣の維持や向上に貢献しています。不登校子どもの進学・キャリアデザインサポート 不登校期間中に進路について考えることは、将来の自分自身の希望や目標を明確にするためにも重要です。 Osaka-Childでは、進路相談や進学・就職に関する情報提供など、キャリアデザインに必要な支援を提供しています。不登校復学後の1年間のサポート 不登校克服後の生活は、新たな課題やストレスを伴うことがあります。Osaka-Childでは、不登校復学後の1年間にわたって、学校生活や社会生活のサポートを行っています。
🔚 最後まで読まれたあなたへ。
もし「私は変わりたい」と思われたのなら、
それは変わる準備が、すでに整い始めている証拠です。
33万円・50万円の再スタート支援プログラムでは、
家族関係・心理構造・生き方の再構築を、あなたのペースでじっくり支援します。
すでに診断済みの方も、そのまま詳細ページへ進めます。
あなたの心と体に合ったサポートを、今すぐ確認してみてください。













































の-女性専門カウンセリング支援.png)


で-40代女性の人生を幸福に導く-〜株式会社Osaka-Childの効果的なアプローチ〜-150x150.png)






