
「どうしてこんなに教えてるのに、できないんだろう」
そう思ったあとで、
つい声を荒らげてしまって、
自己嫌悪に沈む夜。
そんな日々を、
今もくり返している方も多いですよね。
- わかってあげたいのに、言葉がすれ違ってしまう。
- やさしく接したいのに、気づけば責めるような口調になってしまう。
どうにかしたいのに、
自分だけが空回りしているようで、
ふと涙がこぼれる──。
- ひらがなを何度教えても、書き順がバラバラ。
- 計算は暗記でなんとか乗り切っているように見えるけれど、応用問題になるとまったく歯が立たない。
- まじめに取り組んでいるように見えるのに、ミスばかり──。
「努力不足」とはどうしても思えなくて、
でも誰に相談すればいいのかもわからなくて。
そんなふうに、
「わかってあげたいのに、届かない」関わりに
疲れてしまっているお母さんへ、
この記事では、
学習障害(LD)という視点から、
子どもの苦手の正体を一緒に見つめ直していきます。
この記事で得られる5つのこと
- 「ひらがな」「時計」「文章題」が苦手な背景にある特性を知る
- 学習障害(LD)と性格や努力の違いを、具体例から理解できる
- 「教えてもできない理由」が家庭でも見えてくるチェックポイント
- 周囲に誤解されがちな「できなさ」への関わり方のヒント
- 診断や医療に進む前に、家庭でできる「安心の対応」方法
でも、
知識を得ただけでは、
現実はなかなか変わらないこともありますよね。
頭では「責めちゃダメ」とわかっていても、
目の前で何度も同じミスをされると、
どうしてもイライラが先に出てしまう。
そしてまた、
「私がちゃんと教えてあげられなかったから」と、自分を責めてしまう。
そんな、
「わかってるのに、できない」苦しさに向き合ってきたあなたにこそ、
届けたいサポートがあります。
- 何度言ってもできない。
- それなのに、何度も怒ってしまう。
- あとから「また責めちゃった…」って落ち込むのに、どうしても止められない──
そんな子育てのくり返しに、
ココロがすり減ってきたお母さんもたくさんいます。
「勉強が苦手なわが子に、どう関わればいいのかわからなかった私が、『この子らしさ』に気づきはじめた──3週間集中再安心サポート」では、
まず「この子の困りごと」を、
「親である私の視点」から丁寧に見直すところから始めていきます。
「努力不足」ではなく
「届いていなかった理由」が見えてきたとき、
関わり方も、
まなざしも、
ほんの少しだけやわらいでいく。
そんな「やさしい変化」を、
無理のないステップで整えていく3週間のサポートです。
ひとりで頑張りすぎてきた日々に、
そっと終わりを告げたいと願うなら──
ここから一緒に、見方を変えていくことから始めていきませんか。
記事とあわせて、「私自身の安心」から始める3週間も、ぜひ知ってみてください。
監修者
株式会社Osaka-Child所属 小児神経科医
- 名前: 三浦あすか
- 出身地: 兵庫県西宮市
- 最終学歴: 神戸大学医学部 小児科専攻
- 専門分野: 小児神経、DCD(協調運動障害)、発達性ディスプラクシア、HSP気質の子ども支援
- 職歴: 兵庫県立こども病院 小児神経センター勤務(11年)
専門分野について一言: 「できないことの奥にある“がんばっているサイン”を、もっと社会全体で受けとめていけたらと思っています。」
監修者
株式会社Osaka-Child所属 臨床心理専攻大学教授
- 名前: 森本哲夫
- 出身地: 奈良県
- 最終学歴: 米国ハーバード大学心理学部 博士課程修了
- 専門分野: 臨床心理学、発達心理学
- 職歴: ハーバード大学研究員(5年)、大阪大学人間科学部教授
専門分野について一言: 「心の成長とは、自己理解の旅でもあります。その旅のお手伝いができれば幸いです。」
「なんでこの子だけ、こんなに勉強が進まないんだろう」…と検索し続けた夜に
- ひらがな
- 時計
- 算数の文章題…
何度教えても間違えてしまうわが子に、
今日もつい声を荒げてしまった。
「ふざけてるんじゃないの?」
──そんなふうに思いたくて言ったわけじゃないんですよね。
できない理由が、どうしてもわからない。
でも、それを一番苦しんでいるのは、母親であるあなた自身です。
『どうしてできないの?』と責めてばかりだった私が、『この子らしい学び方』に気づけた──3週間集中再安心サポートは、
「努力不足」でも「性格のせい」でもなかった子どものつまずきを、
家庭の中から見直していく心理サポートです。
こんな方におすすめです
- 毎晩、宿題を見るたびにため息が出る
- 発達障害じゃないと言われたけど、納得できない
- 「私の教え方が悪いの?」と自分を責めている
- 病院や診断より、まず家庭でできることを探している
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 1月20日(火)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと2名様限定』
※銀行振込限定・先着順
▶ なんでできないの?から、「この子らしさ」に気づきたい方はこちら
そして──
わが子との関係に少し余裕が持てるようになった今、
「私自身の人生」をもう一度見つめ直したいと感じているあなたへ。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
「母としての安心」を土台に、
「わたしとしての人生」を再設計する3週間。
これまで後回しにしてきた自分の気持ちに、
ようやく手を伸ばせるようになる時間です。
- 少しずつ子どもと向き合えるようになってきた
- でも「私って何者だったっけ」と感じている
- 「母親役」だけじゃない生き方を取り戻したい
このプログラムでは、
「子育ての葛藤を超えた私」から出発して、
「本当のわたし」を取り戻していきます。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
「ちゃんとしてるのに、苦しい」
「頑張ってるのに、うまくいかない」
——そんな違和感を抱えたまま、ずっと我慢していませんか?
LINEで3分セルフ診断ができます。
あなたの“今の感覚”の正体が、見えてきます。
学習障害(LD)とは?|「できない」の背景にある見えにくい困りごと
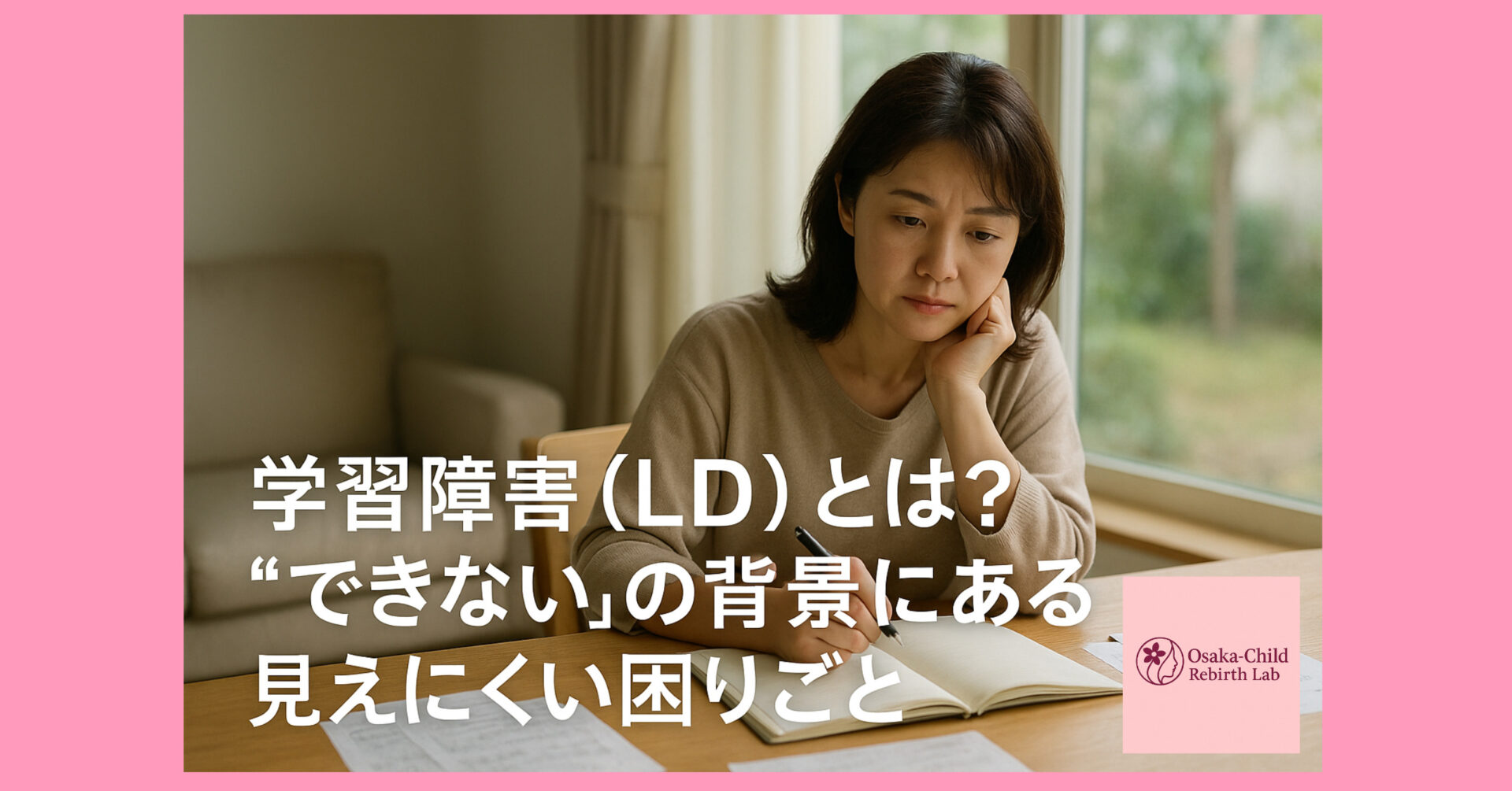
“できない理由”を責めないために、今できることから整えていく
「勉強が苦手」とひとことで言っても、その奥には理由があります。
学び方の「クセ」を、責めるのではなく理解する視点に変えてみませんか?
家庭の中で「この子らしさ」に気づいていく──
「勉強が苦手なわが子に、どう関わればいいのかわからなかった私が、『この子らしさ』に気づきはじめた──3週間集中再安心サポート」は、その第一歩となる心理サポートです。
学校で
「勉強についていけない」と言われたとき、
母親として、どう受け止めたらいいのか戸惑いますよね。
- がんばっているのに結果が出ない。
- 繰り返しても覚えられない。
- 同じように教えても、なぜか通じていかない感じがする。
それでも、本人なりに毎日向き合ってきたはずです。
もしかすると、
その奥には
「見えにくい苦手さ」が隠れているという背景があります。
ここではまず、
「学習障害(LD)」の基本的な見え方や特徴を、
あなたの感覚に寄り添いながら、一緒に見つめていきましょう。
「できない」ではなく「伝わりにくい」特性
「なんでこれができないの?」
そう思ってしまう瞬間、
母親なら何度も経験してきました。
でも、
学習障害の子どもにとっては、
私たちが「当たり前」に理解してきたことが、
頭の中でうまくつながらないという感覚があるんですよね。
たとえば、
- 黒板の文字が目には入っているのに、意味として受け取れない。
- 先生の話をちゃんと聞いていたのに、あとで内容がごっそり抜けてしまっている。
これは、
「やる気がない」でも「集中していない」でもなく、
情報の受け取り方に独特なズレがあるという状態なんです。
本人なりには一生懸命やっているのに、
なぜか結果につながらない──
その「伝わりにくさ」を、まず親が理解することがとても大切です。
とはいえ、
「伝わりにくい」と言われても、
実際にどう表れるのかがわからないと、
つかみにくいですよね。
ここからは、
学習障害の「タイプごとの特徴」を、もう少し具体的に見ていきます。
3つのタイプ|読字・書字・算数に現れる違い
学習障害(LD)は、
大きく3つの分野にわかれています。
- 読むのが極端に苦手(読字障害)
- 書くことに強い困難がある(書字障害)
- 計算や数量がつかめない(算数障害)
たとえば、
読字障害のある子は、
一文字ずつたどって読むのに時間がかかり、
文章の意味が入ってきません。
書字障害の子は、
丁寧に書いているつもりでも、
字が崩れてしまったり、形が不安定だったりします。
算数障害の子は、
足し算や時計、文章題の理解が苦手で、
数字の感覚そのものにズレがあるように
見えます。
それぞれのタイプに共通しているのは、
「努力では越えられない壁」に、親子で直面しやすいこと。
だからこそ、
「教え方」を変える前に、
「この子のつまずきは、どこにあるのか?」という視点を持つことが必要になります。
でも、
「もしかして学習障害?」と思ったときに気になるのが、
発達障害や知的障害との違いですよね。
似ているようで違う
──その「境目」について、次で整理していきましょう。
発達障害・知的障害との違いとは?
学習障害(LD)は、
よく発達障害や知的障害と混同されがちです。
でも実は、
それぞれ「困りごとが現れる領域」が異なります。
たとえば、
学習障害は
「読み書き・計算などの一部領域」に
限定してつまずきがあり、
それ以外の会話や日常生活には、
ほとんど困難がないことも多いです。
一方、
発達障害は、
- コミュニケーション
- 注意力
- 感覚の過敏さなど
より広い範囲で特性が現れます。
また、
知的障害は「全体的な発達の遅れ」が軸になりますが、
学習障害の子どもには
「得意と不得意の差が極端に大きい」という特徴があります。
だからこそ、
- 「手を抜いている」
- 「やる気がない」
ように誤解されやすいんですよね。
けれど実際は、
その子なりに精一杯取り組んでいるのに、
結果が出にくいだけ──
その背景にある「認知のつまずき」に、
親が気づいていくことが、支援の第一歩になります。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「うちの子は“学習障害”か“発達障害”か、わからない…」
そんなふうに悩んでいる方へ。
性格との違いや診断の重なりを整理しながら、母親としてできることをやさしく解説したガイドです。
-

-
参考学習障害と発達障害の違いとは?|「うちの子はどっち?」と迷ったときの整理ガイド【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 障害なのか、性格の問題なのか ──わからないまま悩んできた方へ 「学習障害か、発達障 ...
続きを見る
学習障害と他の発達特性の違い|ASD・ADHD・DCDとどう違う?
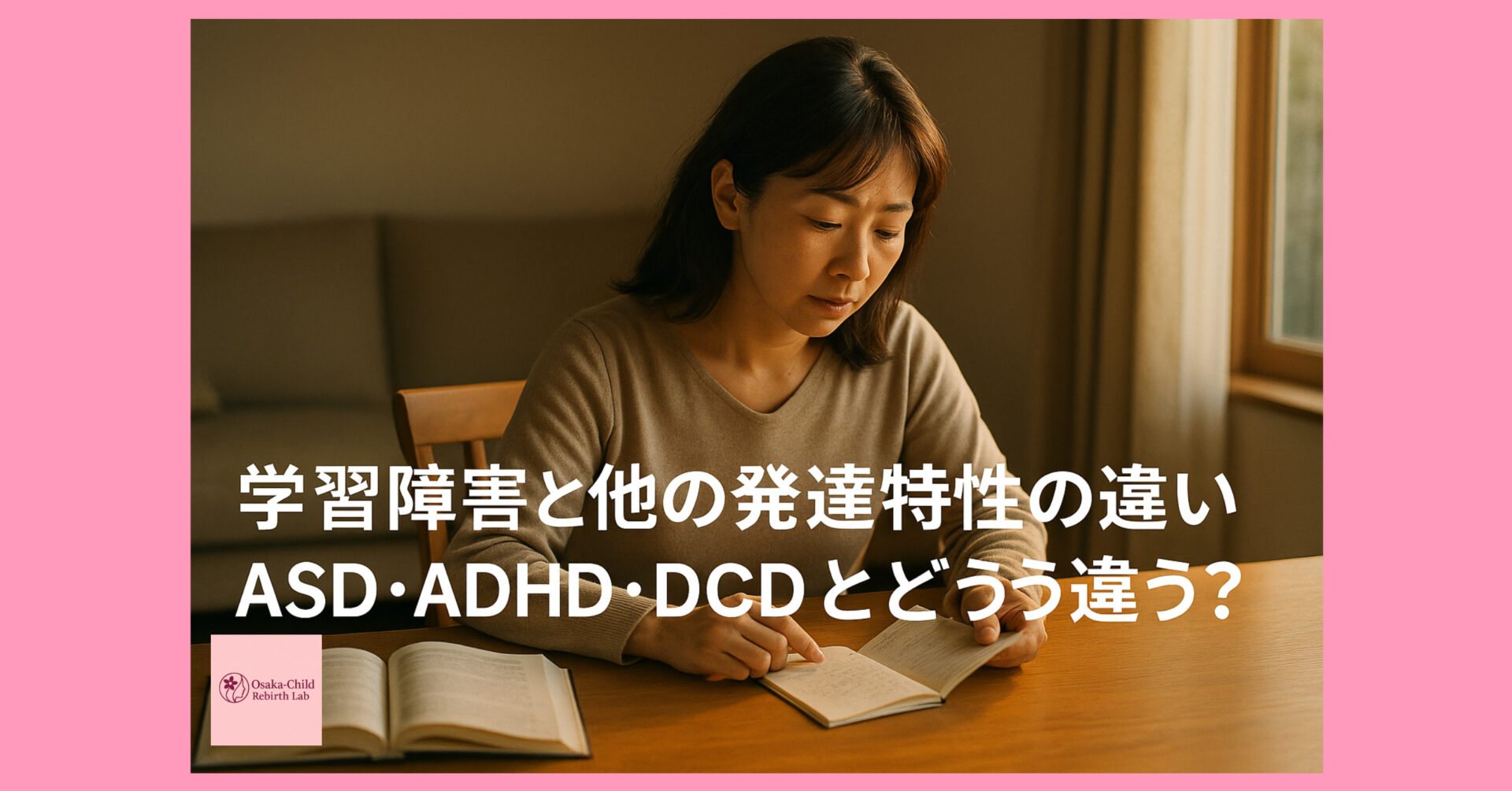
「うちの子、発達障害なのかな…それとも学習障害…?」
そうやって迷いながら、
検索を繰り返してきた方も多いです。
診断名って、
簡単にはつけられないし、
逆に「問題ありません」と言われても、
納得しきれなかった経験がある方もいますよね。
でも実は、
「何に当てはまるのか」を急いで決めるよりも、
「どこでつまずいているのか」をていねいに見ていく視点がいちばん大切です。
ここでは、
学習障害(LD)とよく混同されやすい
ADHD・ASD・DCDとの違いを、やさしく整理していきます。
無料診断|あなたの“心のパターン”を知る
「なぜこの子だけ、こんなに勉強が苦手なんだろう?」
そんな疑問にヒントを届けるLINE無料診断をご用意しました。
📩 LINEに「学習障害」と入力して送ってください。
あなたの悩みに合った視点と、支援の考え方をお届けします。
ADHDとLD|集中力だけじゃない「つまずき」
ADHDの子は、
集中が続きにくかったり、
注意があちこちに向いたりと、
- 「落ち着きがない」
- 「話を聞いていない」
と見えることが多いですよね。
でもその多くは、
- 「周囲の刺激に敏感すぎる」
- 「興味の切り替えが早すぎる」
といった、
注意のコントロールに関する特性からきています。
一方で、
学習障害の子は、
ちゃんと座って話を聞いていても、
- 「言葉がうまく入ってこない」
- 「意味がつながらない」
といった、認知の処理のズレがあることが多いです。
つまり──
ADHDは「集中し続けること」が難しくて、
LDは「情報を受け取ること」自体に違和感がある、
という違いがあります。
見た目は似ていても、
原因も対応もまったく違う。
この違いを知っているだけで、
責める気持ちが少しやわらぐこともあるんですよね。
一方で、
- 「こだわりが強すぎるかも」
- 「急な予定変更が苦手」など、
ASD(自閉スペクトラム症)との違いに引っかかる場面もありますよね。
次は、
ASDとLDがどこで分かれるのか、
ココロの輪郭をなぞるように整理していきます。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「LDとADHD、どう違うの?」
そんなモヤモヤを感じていた方へ。
「できなさ」と「落ち着かなさ」の違いを、図解でやさしく整理した記事をご紹介します。
-

-
参考学習障害とADHDの違いとは?ASD・DCDとの重なりも図解でわかりやすく整理【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 うまく言えないけど、 ずっと引っかかっていた。 宿題に何時間もかかる。 読んでるのに ...
続きを見る
ASDとLD|「こだわり」と「理解の抜け」の違い
ASDの子どもには、
- 「予測できないことに強く反応する」
- 「いつもの順番が変わると混乱する」
といった、
こだわりや不安の強さが見られます。
でも、
LDの子も「混乱する場面」があるんですよね。
たとえば、
言葉が頭に入らず状況が把握できなかったとき、
突然怒ったり、黙り込んだりすることもあります。
ASDは
「こうでなきゃ嫌だ」という内側のルールがベースにあって、
LDは
「わからないことがわからない」状態に混乱してしまう、
という背景があります。
どちらも困っているのは同じ。
でも、
苦しさの出どころが違えば、
寄り添い方も変わってきます。
最後に、
- 「手先が不器用」
- 「書くのが遅い」
- 「何度教えても動きがぎこちない」
そんな姿を見てきた方へ
──DCD(発達性協調運動障害)との違いも一緒に整理していきましょう。
DCDとLD|「身体の不器用さ」と「学習の苦手」の切り分け
DCDは、
- 手足の動き
- 姿勢のコントロール
に特性がある子に見られる発達障害のひとつです。
- ハサミがうまく使えない
- 鉛筆を持つ手がふらふらする
- ボールを投げても思った方向に飛ばない
──そんな「運動の計画や協調」にズレがあることで、
結果的に学習にも影響が出やすくなります。
一方、
LDの子が文字を書くのが遅いのは、
体の動きというより、
書く内容そのものの処理がうまくいっていないことが多いです。
DCDは「動かし方そのもの」に難しさがあり、
LDは「理解して→記憶して→書く」
というプロセスにズレがある。
つまり、
同じ「書くのが苦手」という見え方でも、
根っこがまったく違うということなんですよね。
もしかして「グレーゾーン」?|診断がつかない子の特徴と関わり
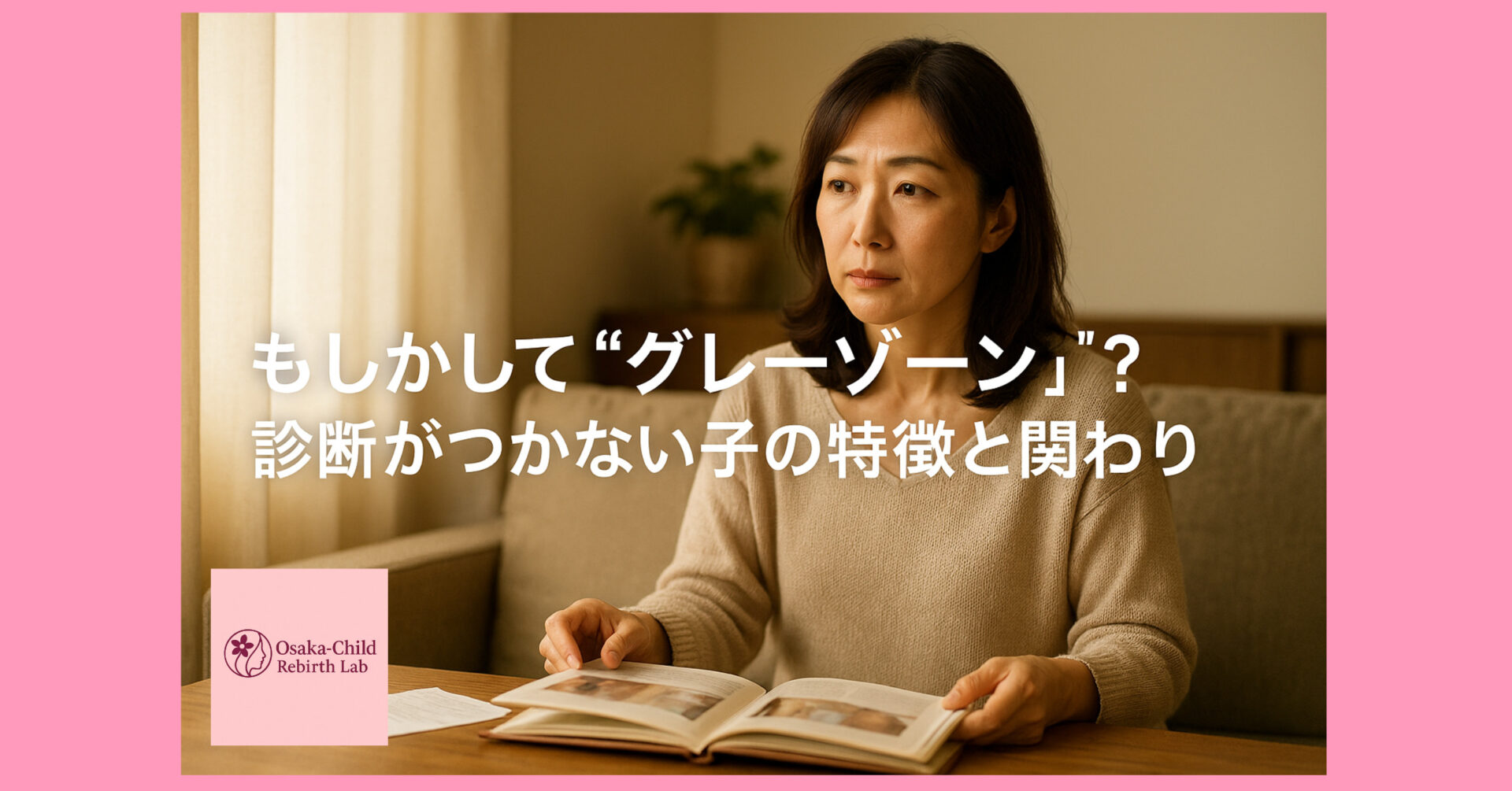
「発達障害でも、学習障害でもない」
そう言われたとき、
ホッとしたような、
置いていかれたような気持ちが混ざったことはありませんか。
病院に行っても、
「診断には当てはまりませんね」と
やんわり返されて、
それきり…という経験をしてきたお母さんも多いです。
でも、
診断がつかないからといって、
その子の「育てにくさ」が消えるわけではないんですよね。
ここでは、
いわゆる「グレーゾーン」と呼ばれる子の特徴や、
親としてどんなふうに関わっていけばいいのかを、
一緒に整理していきます。
診断がつかない子の「困りごと」を見逃さない
- 学校では問題なく過ごせている。
- 集団生活にもなんとか馴染んでいる。
でも、
- 家に帰ってくるとグズグズ
- イライラ
- そして癇癪…。
何かあるのに、
どこにも相談できないまま、
「このくらいなら様子見で」と言われ続けてきた。
そんな日々に疲れているお母さんも、
多いですよね。
- 診断が出るほどの「特性」はない。
- でも、どこか育てにくい。
何をするにも時間がかかるし、
ちょっとしたことで気持ちが崩れる。
こうした子どもたちは、
表面上は「普通にできているように見える」からこそ、
困っていること自体が見落とされがちです。
けれど、
親だけは気づいています。
その子が、
ぎりぎりのところでがんばっていることを。
見えない困りごとほど、
外からは理解されにくい。
だからこそ、
親の直感にちゃんと目を向けることが大切です。
でも実際には、
「何か違う」と感じて病院に行った方もいますよね。
そして、
専門家からは「発達には問題なし」と言われて終わってしまった…。
あのときの気持ちを、
もう一度見つめてみましょう。
「発達には問題なし」と言われたのに…
診断が出なかったこと。
それ自体は、
医師から見て
「基準に当てはまらない」という判断だったのでしょう。
でも、
「問題ありませんよ」と言われたあとのあの空虚感──
言葉にできないけど、
モヤモヤとした思いが残りましたよね。
- やっぱり私の気にしすぎなの?
- この子の「困ってる感」は、私にしか見えていないの?
そんなふうに、
自分を責める方向に向かってしまった経験、ありませんか。
診断がない=支援はいらない、
ということではありません。
困っている子がいて、
気づいている親がいる。
それだけで、
関わりを変えていく理由としては十分です。
むしろ、
診断名がないぶん、
「どこにも頼れない」と感じてしまいやすいからこそ、
家庭の中でこそ、
「小さな理解」を積み重ねていく必要があります。
そのためにもまずは、
「誰よりもあなたが、この子の『ちょっとした違和感』に気づいてきた」ことを、
しっかり受け取ってください。
次は、
周囲には見えにくい「育てにくさ」と、
そこに気づける親の感覚についてお話しします。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「検査では問題なしと言われたけど、やっぱり何か気になる…」
そんな違和感を感じてきた方へ。
診断がつかなくても困っている子の特徴と、家庭でできる見極め方をわかりやすく解説しています。
👉 診断がつかない「グレーな子」の「できなさ」を見逃さないために
-

-
参考学習障害の「グレーゾーン」とは?診断がつかない子どもの「できなさ」をどう見極めるか【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「どうして、こんなにひらがなに時間がかかるんだろう」 そう感じる日が続いていた。 書 ...
続きを見る
親だけが気づいている「育てにくさ」とは
言葉では説明できないけれど、
「この子、なんだか他の子とちょっと違う気がする」
そう感じてきたお母さんの「感覚」は、
けっして間違っていません。
たとえば──
- 小さな予定変更にパニックを起こす
- 指示が通っていないように見える
- 失敗を極端に恐れる
- 一度崩れると、立て直すのに時間がかかる
これらは「性格」や「気分」では片づけられない、
その子なりの「つまずき」の表れです。
周りの人に説明しても伝わらない。
それでも、あなたはずっと気づいていた。
だからこそ、ここまで頑張ってこれたんですよね。
この先どう関わればいいのか、まだ見えない部分もあると思います。
でもまずは、
「この子には、この子なりのペースがある」
そう信じて寄り添えることが、
いちばんの安心になります。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「診断がないから支援はムリ」って、本当?
そんな不安を抱えながら、「グレーゾーンの子」にできるサポートの選び方を整理した専門家監修コンテンツをご用意しました。
👉 「診断なし」でも学校でできる配慮・関わり方を見直したい方へ
-

-
参考学習障害の「診断がない子」は、学校で支援を受けられる?|グレーゾーンの子への配慮の引き出し方【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 何度教えても、 また同じところでつまずく。 「なんでまた忘れてるの?」と、 わかって ...
続きを見る
中学生になって気づいた学習障害──小学生では見過ごされていた理由
小学生のころは
- 「ちょっと不器用」
- 「苦手な単元がある子」
と受け止められていた。
でも、中学生になると、それでは済まされなくなる場面が増えていきます。
- 黒板の板書が間に合わない。
- 文章題の指示が理解できず、何をすればいいのかわからない。
- 漢字が覚えられず、何度練習してもテストで書けない。
- ノートは殴り書きのようになり、先生に注意されてもどう直せばいいのか自分でもわからない。
学年が上がるごとに求められるスキルが複雑になる中で、
ようやく「これは努力不足ではなく、何か違う理由があるのでは」と気づいた親もいます。
ポイント
学習障害は、
知的な遅れがない分、
特に小学生期には見逃されやすい。
けれど、
気づくのが遅かったとしても、
向き合い直すのに遅すぎるということはありません。
中学生になられたお子さまの
今の勉強の「覚えられない・理解できない」から、
この子の「ほんとうのつまずき」を見つめていくことができます。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「もっと早く気づいてあげればよかった…」
そんな後悔を抱えながらも、中学生になった今だからこそできる支援を探しているあなたへ。
👉 中学生になってから「学習障害かも」と思った親ができることとは?
-

-
参考学習障害に「今さら気づいた」中学生の親ができること|高校生にも通じる支援の始め方【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 できない子を責めたくなんてない。 でも、また間違えているのを見ると、イライラが先にき ...
続きを見る
家庭で気づける「サイン」から始める|見逃さないためのチェックポイント
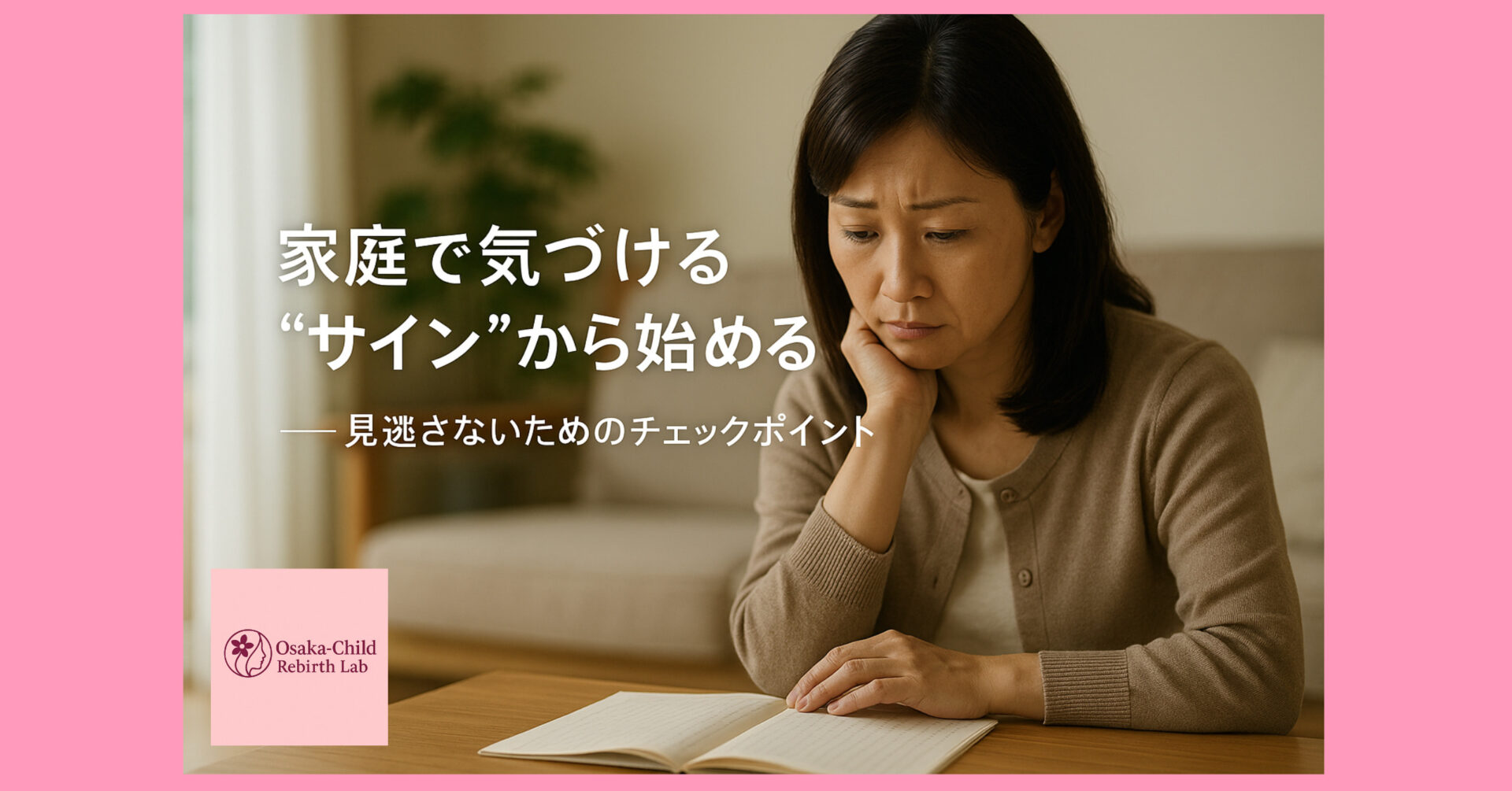
- 「気のせいかも」
- 「きっとそのうち慣れる」
──そうやって見逃されてきた「違和感」が、実は最初のサインだった。
そう感じてきた方も多いはずです。
他の子と同じように教えているのに、
- なぜか伝わらない。
- 何度やっても身につかない。
その背景には、
「教え方の問題」ではなく、
受け取り方そのものに違いがあるという視点があります。
ここでは、
家庭で最初に気づける
「見えにくい学習のつまずき」の特徴と、
見逃さないためのチェックポイントをご紹介します。
読み書きでつまずく子に見られる特徴とは?
最初のつまずきが、
じわじわと勉強の苦手意識に変わっていく。
そんなプロセスを、
読み書きで感じた方も多いですよね。
- 「ひらがなだけがなかなか覚えられない」
- 「読めるのに、なぜか書けない」
- 「音読がぎこちなくて、リズムがつかめない」
こうしたサインは、
- 「集中力がない」
- 「練習不足」
と見られがちですが、
目から入った情報を正確に処理する力にズレがある場合があります。
それでも、
子ども自身は頑張って覚えようとしている。
なのに、結果が出ない。
だから、どんどん自信がなくなっていく──。
読み書きの苦手さには、
そうした「がんばりの空回り」が隠れているのです。
算数で極端に苦戦する子の「認知のズレ」
数字の計算そのものではなく、
- 「量」
- 「順序」
をどうイメージするか。
算数に出てくる問題には、
目に見えない「感覚」の理解が求められます。
たとえば、
- 「時計の針がいつまでも読めない」
- 「繰り上がりの計算で、同じところで間違えてしまう」
- 「文章題になると、何を聞かれているのかがつかめない」
これらの特徴は、
ただ「算数が苦手」というだけでは説明できません。
見えない数の動きや、関係性をイメージする力が弱い場合に、
こうしたズレが生まれます。
「どうして、そこを間違えるの?」
そんな親の戸惑いの裏には、
子どもが言葉にできない「わからなさ」が潜んでいます。
12のチェックリストで「家庭の気づき」をサポート
学習障害(LD)は、
診断の有無よりも先に、
「家庭での違和感」から始まるケースがほとんどです。
でも、
つまずきが日常に溶け込んでしまっていると、
それが「困りごと」だと気づきにくい。
だからこそ、
「あれ?」と感じたその感覚を、
ちゃんと整理してあげる時間が必要になります。
以下のチェックリストでは、
読み書きや算数の初期サインを具体的に取り上げています。
- 「この子らしさ」なのか、
- 「サポートが必要な特性」なのか
──そんな見極めのヒントとして、ぜひ活用してみてください。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「なんでこれができないの?」
そんなふうに悩んだ経験がある方へ。
日常の中に隠れた「気づきのヒント」を整理するための専門家監修チェックリストをご紹介しています。
-

-
参考学習障害チェックリスト|読み書き・計算が苦手な子に気づく12のサイン【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「教えてるのに、伝わらない」 ──その苦しさを、ずっとひとりで抱えてきた きっとあな ...
続きを見る
小学生によくある「学習のつまずき」|見逃されやすい初期サインとは?
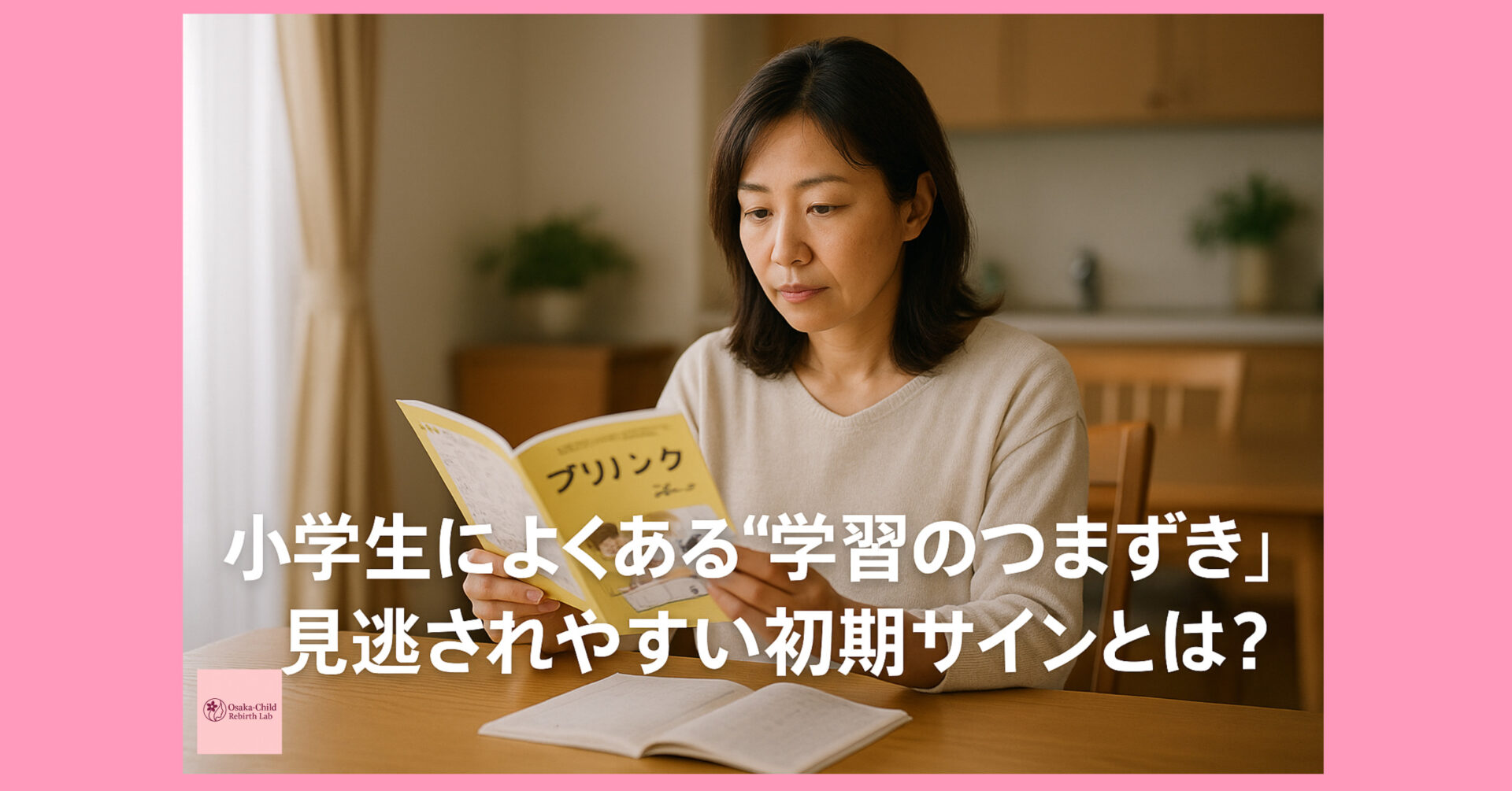
「なんでこの子だけ、こんなに苦労しているんだろう」
ふと、そう感じたことはありませんか?
- テストで平均点は取れているのに、なぜか一部の単元だけが極端に苦手だったり
- 毎日がんばっているのに、結果に結びつかなくて、自己肯定感が下がっていく
その背景には、
学習障害(LD)に起因する
「特定のつまずき方」があるケースもあります。
ここでは、
小学生に多く見られる3つの初期サインにしぼって、
具体的に見ていきますね。
「どうしてこの子だけ、こんなことでつまずくんだろう…」
- ひらがなが読めない
- 時計が読めない
- 文章題の意味も取れない
それなのに
- 「ふざけてるだけ」
- 「教え方が甘い」
と言われて、
あなた自身が一番傷ついてきましたよね。
学校では「様子見でいい」と言われた。
でも毎晩の宿題がつらくて、
「親がなんとかしなきゃ」と追い詰められてきた日々。
『教えても伝わらなかった日々に限界を感じていた私が、「この子なりのつまずき」を理解できた──3週間集中再安心サポート』は、
「なんでできないの?」から、
「この子らしい学び方って何だろう?」への視点転換をサポートします。
こんな方におすすめです
- 毎日、同じミスにイライラしてしまう
- 学校では理解されず、家ではひとりで抱えている
- 「ちゃんと向き合いたいのに、怒ってばかり」と悩んでいる
- 病院や制度より、まず家庭でできることを探している
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 1月20日(火)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと2名様限定』
※銀行振込限定・先着順
そして──
わが子にやさしくなれたぶん、
「私自身のココロの声」にも耳を傾けたくなってきたあなたへ。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
「母としての役割」をいったん手放し、
「私という人間」を取り戻す3週間。
ずっと置き去りにしてきた自分の感情に、
少しずつふれていく時間をつくりませんか?
- 子どもとの関係が少しラクになってきた
- でも自分のことになると、ココロが空っぽな感じがする
- 「誰かの母」を超えて、「私」として生き直したい
このプログラムでは、
子育てを通して見つけた「私の強さと弱さ」を
これからの人生につなげていきます。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
「ひらがなだけが苦手」…これって?
- 音読が苦手
- 書き取りが苦手
- 書いてもすぐ忘れる
でも、
- 話すのは上手
- 図工も得意
- 記憶力だって悪くない
なのに、
「なぜかひらがなだけができない」
──そんな子、あなたの周りにもいませんか?
このタイプのつまずきは、
学習障害(LD)の
「読字障害」と関係している場合があります。
とはいえ、
見た目ではわかりづらく、
本人も「どうしてできないのか」が説明できないことが多いです。
そのぶん、
努力不足や不注意と見なされやすく、
自信をなくしてしまう子もいます。
本人は、
ただ違うやり方で理解しているだけ。
でも
その「違い」に気づいてもらえず、
ずっと間違え続けてしまう。
「ひらがなだけが苦手」というのは、
じつは気づくべきサインなんです。
ひとつ言えるのは、
この子は手を抜いているわけじゃないということ。
むしろ、人知れずがんばってきたはずです。
「算数だけが極端にできない」
- 数字を見ただけで顔が曇る。
- 計算カードを持たせると泣きそうになる。
「算数だけ、なんでこんなに…」と感じたこと、ありませんか?
- 簡単な足し算はできるのに、繰り上がりになると急に止まってしまう。
- 九九も何度も練習したのに、テストになると飛んでしまう。
そんな
「極端な苦手さ」には、
学習障害(LD)の
「算数障害」とのつながりがあるケースがあります。
数の感覚そのものをつかむのが難しかったり、
空間の認識に時間がかかる
ことが原因になっていることもあります。
でも、
それを知らないと
「手を抜いている」と誤解され、
叱られてしまうことが多いんです。
ただ、見え方や捉え方が違うというだけ。
理解に時間がかかることもあるし、
段階を飛ばさずゆっくり進めれば届くことも多いです。
この子も、ずっと頑張ってきた。
ただ、
何度やっても伝わらない現実の前で、どう動けばいいのかわからなくなっていただけ。
「わからないまま、責められる」──そんな苦しさを、ずっとひとりで抱えてきた。
ミスが多い、忘れっぽい、集中が続かない
- 「また宿題忘れてるよ」
- 「今、何やってるの?」
そう声をかけたあとで、
胸の奥に重たさが残るような日もあった。
ちゃんと向き合いたいのに、うまく届かない
──そのもどかしさだけが積もっていった。
- 集中しようとするのに、他のことが気になってしまう。
- 一度に複数のことを処理しようとすると、何かを落としてしまう。
こうした「気が散る」タイプの子も、
学習障害(LD)に含まれるケースがあります。
特に、
作業を順序立てて進めるのが苦手な子は、
「集中できない」のではなく、
「集中する準備がうまく整わない」だけということもあります。
その背景には、
- 注意や記憶
- 切り替えの難しさなど
目に見えにくい個人差があります。
決して、
怠けているわけじゃない。
「がんばり方」が合っていなかっただけ。
そう思えたとき、親子の関係も少しずつ変わっていくはずです。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「うちの子、小学生になってから勉強が苦手で…」
そんなふうに感じてきた方へ。
家庭で気づける「学習障害のサイン」と、親にできる関わり方をまとめました。
👉 小学生の勉強の苦手さから、わが子の「特性」に気づくヒント
-

-
参考小学生の学習障害とは?勉強が苦手な子の「家庭での気づき方」をわかりやすく解説【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 宿題を見ていると、 なぜか不安になる。 簡単なひらがなが読めなかったり、 昨日できて ...
続きを見る
どう教えたらいい?|家庭でできる勉強サポートと工夫

“教え方”を変える前に、“見方”を少し変えてみませんか?
ノートが書けない
宿題が続かない──
その「やる気のなさ」に見える行動の奥には、気づかれにくい理由が隠れています。
「勉強が苦手なわが子に、どう関わればいいのかわからなかった私が、『この子らしさ』に気づきはじめた──3週間集中再安心サポート」は、
「正しい教え方」よりも、「あたたかな見方」から関係を整える家庭向けの心理サポートです。
- 「もう10回教えたのに」
- 「どうして机に向かわないの」
そう思ったことがありますよね。
でも、
そのやり方が「合っていなかっただけ」です。
学習障害(LD)のある子にとって、
- 「覚える」
- 「続ける」
- 「取り組む」
は、周りが思っているより
ずっとハードルが高い行動なんです。
ここでは、
家庭でできるサポートや工夫を3つの視点から紹介します。
何度やっても覚えられないときは?
同じことを何度も教えているのに、
すぐ忘れてしまう。
そんな日が続くと、
親の方がココロ折れそうになることもありますよね。
でも子どもにとっても、それは苦しいこと。
「わかりたいのに、頭に残らない」
──そんなもどかしさを、ずっと抱えている子もいます。
学習障害(LD)には、
- 「記憶の仕方」
- 「インプットの方法」
に偏りがあるタイプもいます。
- 文字より音で覚えるほうが得意だったり、
- 視覚の手がかりがあったほうが安心できたり。
ただの「繰り返し」ではなく、
「どうしたら記憶しやすいか」を一緒に探すことが大切です。
- 声に出して覚える
- イラストとセットで覚える
- 体の動きを加えてリズムで覚える
そんなふうに、
本人の「得意な入り口」からアプローチしてあげることで、
「覚えられた」という実感が少しずつ増えていきます。
この子なりのやり方を見つけてきたあなたも、
ずっと向き合ってきました。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「何度教えてもわからない」
──そんな悩みには、理由があります。
「覚えにくさ」の背景と、わが子に合った勉強の伝え方を具体的に紹介した解説記事をご用意しました。
👉 伝わらない原因と、学習障害の子に合った勉強の工夫をくわしく見る
-

-
参考学習障害の子どもに合った勉強の工夫7選|「何度教えても覚えられない」に悩んだら【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「何度も教えたのに、また忘れてる」 そう思った瞬間、わたしの中でスイッチが入ってしま ...
続きを見る
ノート・宿題が続かない子への工夫
やる気があるのに、すぐ中断してしまう。
「最初の5分だけ」で終わってしまう──。
そんな姿を見て、がっかりしてしまった日もあったかもしれません。
でもそれは、
集中力がないわけではなく、
「やり方がうまく噛み合っていない」だけです。
学習障害(LD)のある子には、
作業の手順や優先順位を整理するのが苦手なタイプもいます。
「やらなきゃ」と思っているのに、
どこから手をつけたらいいのかわからない。
そうしているうちに気が散ってしまう
──という流れが起きているだけなんです。
だからこそ、
- 時間で区切る(例:5分だけやって休憩)
- 「ここまでやればOK」のゴールを見せる
- 1ページ全部やらせず、3行だけに減らす
そんな「取りかかりやすさ」を整えてあげることが、
親にできるサポートになります。
完璧じゃなくていい。
「今日はここまでやれたね」と一緒に喜べることこそ、
子どもの自信につながっていきます。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「ひらがなや計算が苦手なのは、やる気の問題…?」
そんなふうに悩んできた方へ。
「国語と算数、それぞれのつまずき」に合わせた家庭での教え方を、小児神経科医監修でくわしく解説しています。
-

-
参考学習障害の子どもに合った「国語と算数」の教え方とは?ノート・宿題につまずく小学生への関わり【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 ひらがなを何度教えても、また忘れている 算数の文章題を読んでも、どこから手をつけてい ...
続きを見る
親がイライラしないために知っておきたいこと
- いけないとわかっていても、つい声が荒くなる。
- 「こんなに教えてるのに…」と怒ってしまって、あとから自己嫌悪になる。
そんな経験を重ねてきた方も、
たくさんいますよね。
でもそれは、
あなたが「ちゃんと見てきた証拠」なんです。
期待してるから、
がんばってほしいと願ってるから、
ココロが揺れる。
その背景には、
不安と焦りが隠れています。
学習障害(LD)をもつ子どもたちは、
「できない」のではなく、
「伝わっていない」だけ。
本人なりに努力していることを知っていると、
親のまなざしも少しずつ変わっていきます。
ポイント
あなたが「ずっと怒らない親」でいなくていいんです。
ただ、
この子の「理解の仕方」を一緒に知っていこうとするだけで、
親子の関係は確実に変わっていきます。
【✅ 補助No.10|“できなさ”を責めない関わり方へ】
学習障害の「原因」って?|親のせいにされやすい誤解をほどく
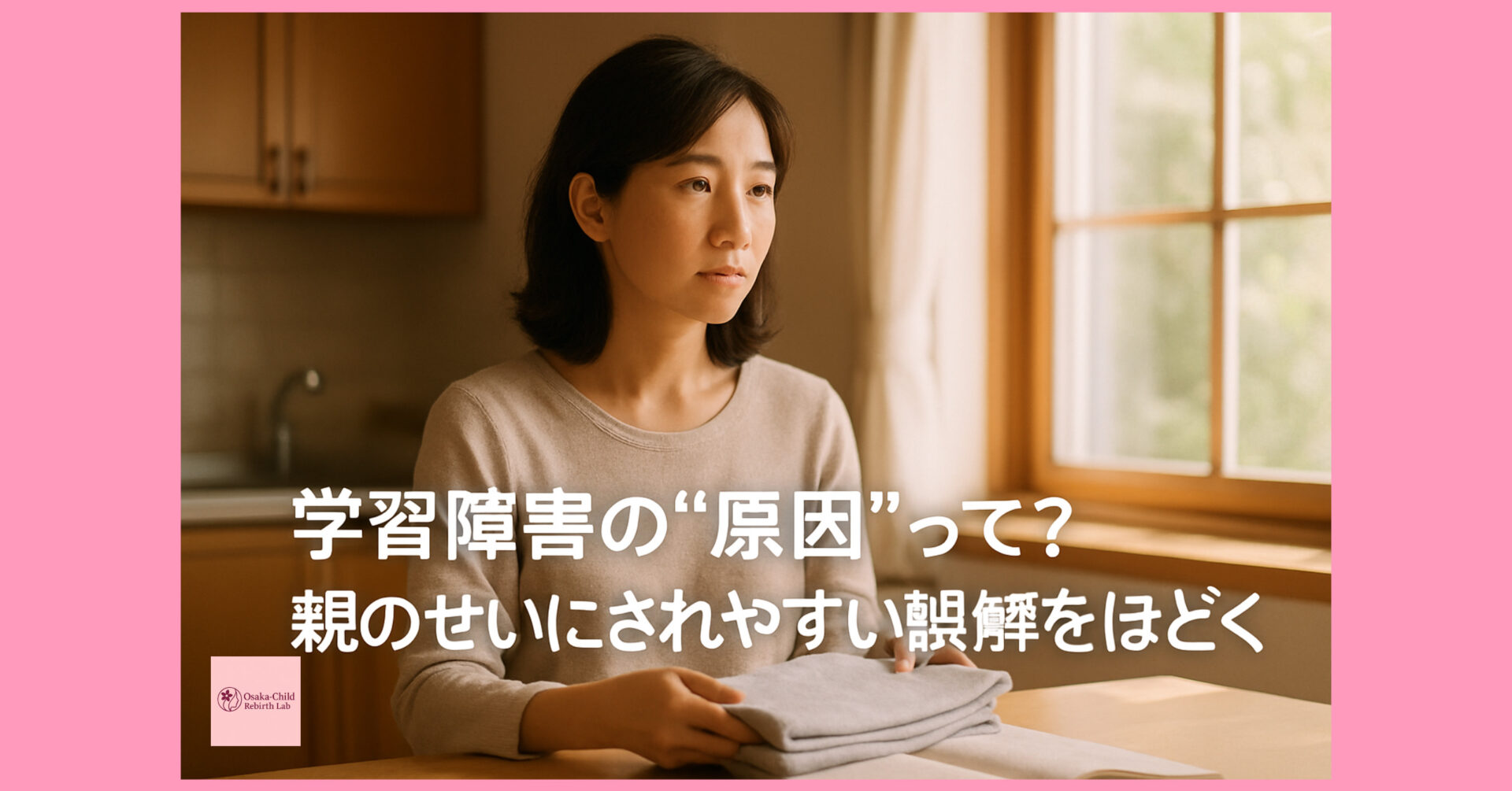
子どもの学習のつまずきに直面したとき、
「私の育て方が悪かったのかな…」と感じたことはありませんか?
まじめに子育てをしてきた人ほど、
自分を責めやすくなります。
でも、
学習障害(LD)の
「原因」について正しく知っておくことができれば、
その重たい罪悪感を少しずつ手放せるようになっていきます。
ここでは、
多くの人が抱く3つの誤解と、
その背景を一緒にほどいていきます。
“この子なりのペース”に気づけたとき、関わり方がやさしく変わりはじめる
「ひらがなだけが苦手」「算数の文章題だけが極端にできない」──
そんな「部分的なつまずき」には、特性のサインが隠れていることもあります。
「勉強が苦手なわが子に、どう関わればいいのかわからなかった私が、『この子らしさ』に気づきはじめた──3週間集中再安心サポート」では、
わが子の「できない」を正しく見つめ直すための視点を、家庭の中から整えていきます。
「育て方が悪かった?」の問いに答える
- 「もっと厳しくしつけていたら…」
- 「私がちゃんと教えなかったからかも」
そんなふうに、自分を責めるようになったお母さんも多いですよね。
でも、
学習障害(LD)は
家庭のしつけや関わり方が原因で起こるものではありません。
脳の情報処理のしかたに特徴がある、
という見方が広がっています。
たとえば、
- いくら教えても読み書きだけが極端に苦手だったり、
- 時計の読み方だけがずっと身につかない
子がいます。
本人は努力しているのに、
うまく定着しない
──そこに「育て方の問題」をあてはめてしまうと、
本質を見失ってしまうんです。
必要なのは、
できていないところを責めることではなく、
どう支えるかを考える視点。
ポイント
これまでの
あなたの関わりがムダだったなんてことは、
ひとつもありません。
遺伝と脳の発達の関係
- 「私も子どもの頃、似たようなことで苦労してた」
- 「親戚にちょっと似たタイプの子がいる」
そう感じた経験がある方もいますよね。
実際に、
学習障害(LD)には
遺伝的な傾向が見られるという報告もあります。
でも、
これは「親からそのまま受け継がれる」という意味ではありません。
- 脳の情報処理のクセ
- 得意・不得意のパターン
は人によって違います。
同じ家庭で育ったきょうだいでも、
まったく別の特徴を持つこともよくあるんです。
むしろ
「私も同じようにつまずいたな」と
共感できることが、
支援の力になることもありますよね。
「わかるよ」と言える親がそばにいる
──それが子どもにとって、なによりの安心になります。
家庭環境が支援のカギを握る理由
学習障害(LD)は
「生まれつきの特性」として語られることが多いですが、
それと同時に、
「関わり方次第で変化していける力」も持っています。
たとえば、
学校では目立たなかった子が、
家での接し方が変わっただけで、
自信をつけはじめることがあります。
それは、
家庭が「安心できる場所」になったからこそ起こる変化です。
支援のポイントは、
本人のペースややり方に合わせて、
環境を「整えてあげる」こと。
- 間違えても怒らない
- やり方を工夫する時間を一緒につくる
- 小さな達成感を見逃さずに認める
そんなふうに、
「できない」を責めず、
「伝わる方法」を探していくスタンスが、
親子の関係を支える軸になっていきます。
子どもがのびのび取り組めるようになるには、
あなたの「見ているよ」というまなざしが、
何より大きな力になりますよね。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「学習障害って、やっぱり私の育て方が悪かったの…?」
そんなふうに自分を責めてきた方へ。
遺伝や家庭環境との関係をわかりやすく整理した専門家監修の解説記事をご紹介します。
👉 「親のせい」ではない理由を、医学と心理の視点からやさしく解説
-

-
参考学習障害の原因は「遺伝」だけ?それとも育て方や家庭環境?──自分を責めてきた母へ【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「また忘れてる」 「何度言っても伝わらない」 そんな場面ばかりが続いて、 気づけば毎 ...
続きを見る
相談・支援はどう受ける?|診断・学校・カウンセリングの選び方
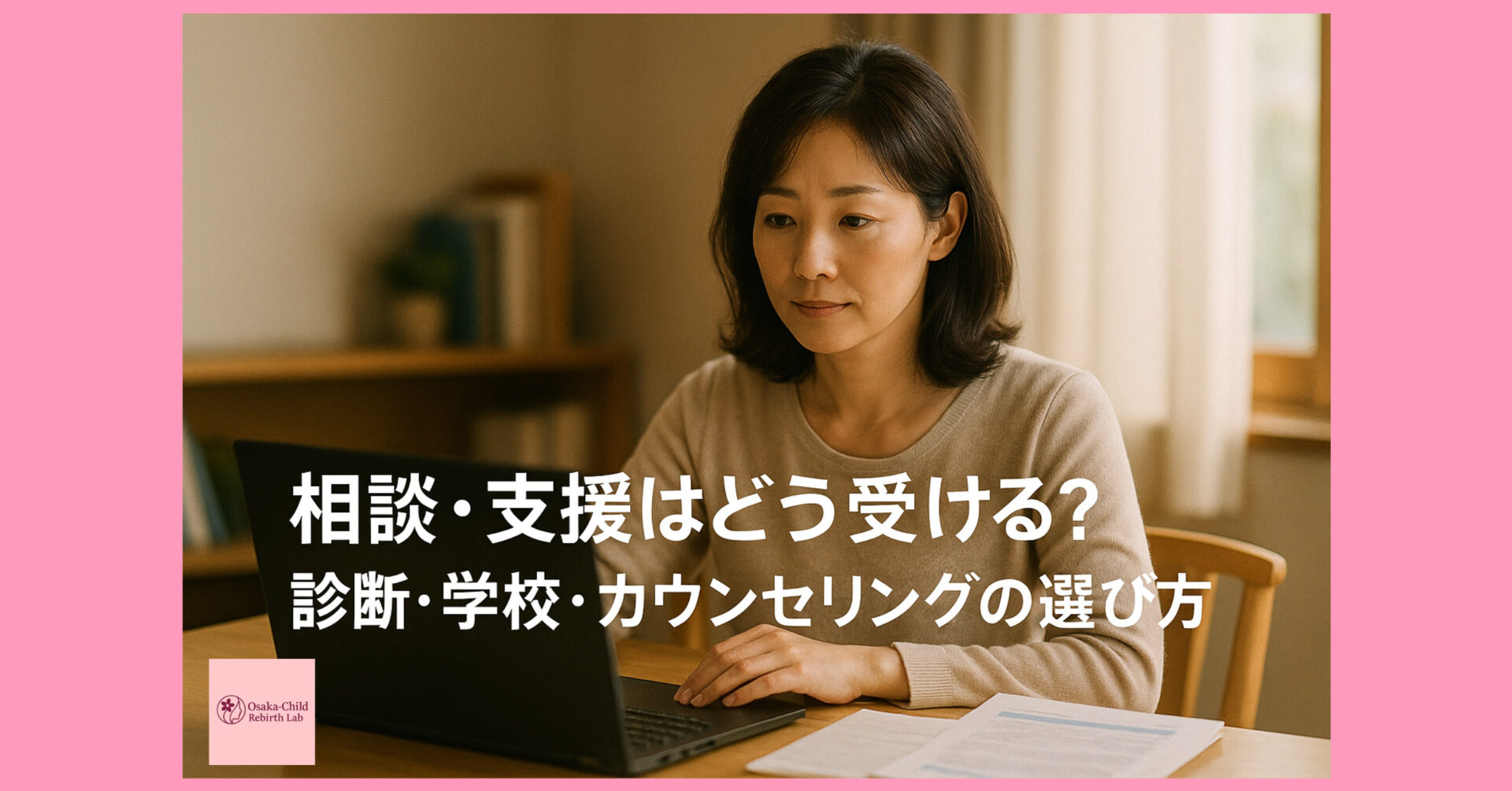
- 「気になってはいるけど、病院に行くほどのことなのかな…」
- 「どこに相談したらいいかわからない」
──そんなふうに、
動けないまま時間だけが過ぎていく日々が、確かにあった。
わが子のために何かしたいのに、
どうしたらいいのかが見えなくて、
ただ立ち止まるしかなかった。
迷いを抱えながら、
それでも毎日、わが子と向き合ってきた日々があった。
学習障害(LD)は、
「診断名がつくこと」よりも、
「必要な支援を受けること」の方がずっと大切です。
ここからは、
- 相談先
- 学校の支援
- カウンセリング
という3つの入口から、無理のない一歩を見つけていきましょう。
まず誰に相談するべき?
「なんとなく気になるけど、深刻なのかはわからない」
そんなとき、いきなり病院に行かなくても大丈夫です。
最初に頼れる場所としては、
- 地域の発達支援センター
- 教育相談窓口
- または通っている学校の担任やスクールカウンセラーなど
があげられます。
どこでもいいから、
「話せる場所」にアクセスすることが大切なんですよね。
ポイント
親が感じている
「言葉にしにくい不安」でも、
ちゃんと相談していいんです。
支援機関の方も、
「それならすぐに病院へ」という判断ではなく、
「もう少し様子を見ながらできることは?」という視点で
話を聞いてくれることが多いです。
診断ではなく、
「この子らしさに合った関わり方」を見つけていく──。
そんな柔らかい目的でも、十分すぎるスタートになります。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「相談したいけど、どこに行けばいいの?」
そんな迷いを感じた方へ。
誰にも言えなかった不安を整理し、安心して話せる場所について、専門家監修でわかりやすくまとめました。
👉 「最初の一歩」として、どこに相談すればいいかを知りたい方へ
-

-
参考学習障害の相談先は?誰にも言えなかった私が「安心して話せた場所」【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「どこに相談すればいいのか、ずっとわからなかった」 気づけば、 そんな気持ちを抱えた ...
続きを見る
学校での配慮・支援ってどうなるの?
「学校に相談したら、厄介な親だと思われる」
だから、いつも自分の中でなんとか処理してきた。
でも今の学校現場には、
「学習障害(LD)を含む多様な学びのスタイル」を
支援するための体制があります。
たとえば、
- 音読をやめてプリント対応にしてもらう
- 図や写真を使った教材に切り替えてもらう
- 宿題を減らして成功体験を優先してもらう
といった、「ちょっとした工夫」が実は大きな支援になることもあるんです。
大切なのは、
「うちの子は診断があるから」という伝え方ではなく、
「こんな場面で困っているようで…」という
「リアルな日常の困りごと」を共有すること。
家庭と学校が
「子どもの橋渡し役」として協力できれば、
それだけで子どもの居場所は広がっていきます。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「通級と支援級って、どう違うの?」
そんな疑問を持った方へ。
学習障害の子どもにとって安心できる環境の選び方を、制度別にわかりやすく整理しています。
-

-
参考学習障害の「学校支援」はどこまで受けられる?通級・支援級・通常級の違いをわかりやすく解説【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 何度教えても覚えられない。 何度言い聞かせても同じミスを繰り返す。 わかっていても、 ...
続きを見る
カウンセリングでできることとは?
学校や病院とはまた違う、
「ココロに寄り添う場所」として、
カウンセリングを選ぶ親子も増えています。
学習障害(LD)がある子どもは、
努力が結果に結びつきにくいことが続くと、
- 「自分はダメ」
- 「どうせできない」
と思い込むようになってしまうことがありますよね。
カウンセリングでは、
- その子の気持ちを受け止める
- 「できたこと」を丁寧に言葉にして返す
- 「わかってくれた」という感覚を育てる
そんな関わり方を通して、
少しずつ自己肯定感を回復していくサポートが行われています。
また、
親自身が「どう接していいかわからない」と感じたときも、
安心してその気持ちを打ち明けられる場所として使えるのがカウンセリングの良さです。
うまく言えない不安や、
自分では処理しきれなかった感情も、
誰かと一緒に見つめ直せるだけでココロが軽くなっていく──。
そんな実感を得られた方も、かなり多いです。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「なんでできないの?」と怒ってしまう日が続いていた
そんな悩みを抱えたお母さんに向けて、カウンセリング的な視点で関係を見直すヒントをまとめました
-

-
参考学習障害はカウンセリングで変わる?「なんでできないの…」と責めてしまった母のココロが軽くなるまで【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 何度教えても、翌日には抜けている。 やる気がないわけじゃないのに、また最初からになる ...
続きを見る
親自身が気づく|「もしかして私も?」という視点

無料LINE診断|今のあなたに必要なサポートは?
『何から始めればいいかわからない…』そんなあなたへ。
LINEで「数字」を入力するだけで、今のあなたに合ったサポート商品を診断できます。
📩 今すぐLINEに【 4 】と入力してください。
「勉強が苦手なわが子に、どう関わればいいのかわからなかった私が、『この子らしさ』に気づきはじめた──3週間集中再安心サポート」
あなたに合った理由と内容をお届けします。
子どもの困りごとに向き合っていく中で、
「なんだか昔の自分と似ている…」と感じたことはありますよね?
- ひらがなが覚えられなかった日々。
- 授業についていけず、劣等感ばかりが残っていた学生時代。
それなのに、誰にも理解されなかった記憶──。
子どもを見る目を通して、
自分自身の「学びのつまずき」に気づくお母さんも増えています。
ここでは、
大人になった今だからこそ見えてくる、
学習障害(LD)との向き合い方を整理していきます。
子どもを見ていて「自分と重なる」こと
「なんでそんなミスをするの?」と注意しながら、
ふと、昔の自分を思い出す瞬間ってありますよね。
- 計算だけ極端に苦手だった
- 音読が嫌で学校に行きたくなかった
- ノートをとるのが遅くて、いつも置いていかれていた
そんな記憶が、ココロの奥からよみがえることがあります。
当時は、
それを
- 「性格」
- 「怠け」
のせいにされることが多くて、
誰にも頼れないまま、
どうにかここまでやってきたんですよね。
でも、今ならわかりますよね。
ポイント
それは「努力不足」ではなく、
「学び方の特性」が合っていなかっただけだと。
子どもと自分が重なるのは、
弱さじゃなく、
支援につながるチャンス。
あのとき言ってほしかった言葉を、
今あなたがこの子に届けていけるんです。
大人になっても困難が続いている例
「学生時代の困りごとは終わった」と
思っていたのに、
社会に出てからも、やっぱり苦労が絶えない──。
そんな方も多いのですよね。
- メールの文章をまとめるのに時間がかかる
- 会議の指示を一度で理解できない
- 段取りを組むのが苦手で、仕事が遅れてしまう
それは、
「甘え」や「社会性の問題」ではなく、
大人の学習障害(LD)の可能性もあります。
特に女性は、
家庭や育児の中で
「自分の不得意」に気づきにくい傾向があります。
でも、
子どもとの関わりを通して、
「もしかして私もそうだった?」と感じることが増えていく。
見逃されてきた過去を責める必要はありません。
むしろ、
今ここで気づけたことが、自分自身を大切にするスタートになりますよね。
親自身もサポートを受けていい
子どものことで手いっぱいなのに、
「自分のケアまで手が回らない…」と
思ってしまうこともありますよね。
でも本当は、
親自身が「わかってもらえる経験」を持つことが、
子どもへの関わりを支える「土台」になってきます。
カウンセリングや心理相談では、
- 自分の苦手に気づき直す
- 長年抱えてきた「やりづらさ」を言語化する
- 「私もサポートされてよかった」と感じる
そんなふうに、
大人としての自分にも「安心できる場所」があると
実感できる時間を持つことができます。
あなたの生きづらさや苦手さに向き合うことは、
決して「わがまま」ではありません。
ずっとがんばってきたあなたこそ、
本当は一番、支えられてよかったはずです。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「子どもの『覚えられない・できない』に、自分を重ねて苦しくなる…」
そんな気づきを抱えたあなたへ。
親としての不安と「自分自身の生きづらさ」を一緒に見つめ直す時間を届けます。
👉 「子どもを通して気づいた『私自身の困りごと』を整理したい方へ」
-

-
参考大人の学習障害とは?子どもの「読み・書き・集中の苦手さ」に、自分を重ねたあなたへ【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「読み間違いが多い」 「ノートがうまく取れない」 「集中が続かない」 ──そんな子ど ...
続きを見る
「教えても届かない…」と悩むあなたへ|3週間集中再安心サポートのご案内

- 何度教えても、また同じところでつまずいてしまう。
- できない姿を見るたびに、焦りと不安が積み重なっていく──。
そんな日々をくぐり抜けてきたあなたに届けたいのが、
「教えても届かない『できなさ』に悩んだ私が、『わかってあげられる関わり方』を見つけた──3週間集中再安心サポート」です。
ここでは実際にこのサポートを通じて
「関わり方」が変わった親の体験を、
3つの視点からご紹介します。
「努力不足」じゃなかった──「見方」が変わるとき
- 「やればできるはず」
- 「やらないのは甘え」
そう信じて、
何度も声をかけてきましたよね。
でもそれは、
目に見える行動だけを見て判断していたから。
このサポートでは、
まず「その行動の裏にある気持ち」に目を向けるところから始めます。
すると、「できない」のではなく、
- 「伝わらなかった」
- 「整理ができなかった」
──そんな背景が少しずつ見えてくるようになります。
本当は、
ずっと努力していたのは子どもの方だった。
そう気づけたとき、
親子の関係がやわらかく変わり始めていきます。
怒らなくても関われるようになった理由
「もう怒りたくないのに、また怒ってしまった」
その繰り返しに、自分を責めてきたと思います。
このサポートでは、
「伝え方を変える」のではなく、
「なぜこんなにイライラしてしまうのか」を、
親自身が丁寧に見つめ直します。
ポイント
焦りや不安がほどけていくと、
不思議と「怒らなくても届く」瞬間が増えていきます。
イライラの奥にあった
「わかってほしかった」という気持ちに、
自分自身が気づけるようになる。
それが大きな転機になります。
「この子らしさ」に気づけたあなたへ
「どうしてできないの?」と
原因を探し続けてきた毎日。
でも今は、
「この子には、この子なりの世界がある」と、
見方が変わっていきます。
ノートの前で手が止まっていた時間も、
「サボっていた」のではなかった。
言葉にならない思いを、
表情や仕草で必死に伝えようとしていた。
そんな姿に、ようやく目を向けられるようになります。
このサポートでは、
親が「変わる」のではなく、
「見方」を切り替えるところから始まります。
すると、
不思議なくらい子どもとの距離が近づいていく。
「この子らしさ」を受け取れるようになったとき、
あなた自身も、少しずつほどけていくのを感じるはずです。
「教えても届かない…」と悩むあなたへ──3週間集中再安心サポート
- 「ちゃんと教えれば、できるはず」
- 「どうしてまた同じミスをするの?」
そう思って責めたあとで、
眠れなくなるほど後悔したこと、ありますよね。
わかってあげたいのに、
イライラが止められない。
そんな自分に嫌気がさして、
「私の育て方が悪かったのかも」と苦しくなっていました。
困っているのに、
「どこにも当てはまらない」ように感じて、
誰に相談すればいいのかもわからない──。
その説明のつかない孤独に、
ずっとひとりで向き合ってきたあなたへ。
「勉強が苦手なわが子に、どう関わればいいのかわからなかった私が、『この子らしさ』に気づきはじめた──3週間集中再安心サポート」は、
「診断名」よりも、
「母親の安心」を整えることを大切にした心理サポートです。
子どもを変えるのではなく、
母親のまなざしを「少しだけ切り替える」ところから始めていきます。
STEP①|「できなさ」の正体を知る
最初の1週間では、
子どもが「わからない」と感じている背景を一緒に整理します。
苦手の奥にある「認知のクセ」を、
できるだけわかりやすく言語化していきます。
親の中にある
「普通ならできるはず」という前提を少しずつ手放し、
他の子と比べない、
「この子だけの理解のしかた」を見つけていく時間です。
STEP②|関わり方を変える「見方の転換」
2週目からは、
「教え方」よりも「関係性のつくり方」に焦点を当てます。
怒らないよう努力するのではなく、
怒らなくてよくなる関係を育てること。
そのために、
- 言葉のかけ方
- 時間のかけ方
を一緒に調整していきます。
母親が「教える人」から、
「見守る人」にポジションを変えていくことで、
子どもも自分のペースを取り戻していけるようになります。
STEP③|「この子らしさ」と向き合いなおす
最後の1週間では、
母親自身の視点をあらためて整えます。
「こうあるべき」にとらわれすぎず、
「うちの子は、うちの子」と思える目線をつくっていく。
支援機関や学校任せではなく、
「母親としての信じる軸」を取り戻す時間です。
完璧な親になるのではなく、
「大丈夫、これでいい」と思える安心感が、
少しずつ日常に戻ってきます。
このサポートを受けた多くのお母さんが、
こう言葉にしています。
- 「『伝わらない』のではなく、『伝え方』でもなく、『見方』が変わった」
- 「ノートの前で手が止まる姿を、『サボり』じゃなく『がんばりの限界』として見られるようになった」
- 伝わらなかった言葉が届くようになる。
- 目が合わなかった子と、少しずつ呼吸が合うようになる。
- 家の空気がやわらぎ、叱る回数が減っていく。
そんな変化が、家庭のなかに静かに積み重なっていきます。
あなたが安心して関われるようになること。
それが、
この子にとっての最大の安心につながっていきます。
「勉強が苦手なわが子に、どう関わればいいのかわからなかった私が、『この子らしさ』に気づきはじめた──3週間集中再安心サポート」は、
「教える方法」を探すより先に、
「信じて見守る視点」を取り戻すためのサポートです。
「私の関わり方で、まだできることがある」
そう感じたときから、親子の関係はあたたかく動き出します。
“診断の前に、家庭でできる安心の選択肢を
「どうしてこんなこともできないの?」と責めたあとで、自分を責めて泣いた夜がある方も多いはずです。
この3週間が、「怒らなくても関われる私」に出会い直す時間になります。
- ひらがな
- 時計
- 文章題…
苦手の理由がわからないまま、何度も教えて、何度もつまずいて。
家庭の中で感じてきた違和感は、決してあなたのせいではありません。
「診断の前にできること」を、一緒に見つけてみませんか?
まとめ|「怒りたくないのに怒ってしまう…」そんなあなたへ
どうして、こんなにも苦しかったんでしょうね。
- 「やればできる」
- 「なんでこんなこともできないの?」
そう言われるたびに、
わが子を守れなかったような気がして、
誰よりも責めていたのは、きっとあなた自身だったのです。
学校でも、
家庭でも、
「この子の『できなさ』は普通じゃない」と感じてきた。
でも、誰に言えばいいのかわからなくて、
情報を集めれば集めるほど、さらに混乱が増してしまって。
「私のせいだったのかも」と、自分だけを責め続けてきた日々。
もう、ひとりで背負わなくて大丈夫です。
「どう関わればいいのか分からない」という戸惑いは、
「努力不足」ではなく、
「まだ届いていないだけ」の愛情が、きっとそこにあったんですよね。
この記事で伝えたかったこと
- 「できない」には、その子なりの理由や背景がある
- 学習障害(LD)は見えにくく、性格や努力では説明しきれない
- 教えても届かない「苦手さ」は、親のせいではない
- 医療や診断に頼る前に、家庭でできることもある
- 親が安心すると、子どもも変わりはじめる
今すぐ、全部を解決する必要なんてありません。
ただ、
少しでも「あの子らしさを、見つけてあげたい」と願う気持ちがあるなら、
そのまなざしこそが、これからの関係をつくっていく土台になります。
そんなあなたと一緒に、「今できること」を探していきたい。
私たちは、そう思っています。
「どうしてこんなに怒ってしまうんだろう」
記事を読み進めるうちに、
そんなふうに自分の関わり方を見つめ直したと思います。
がんばって教えてきたのに、うまく伝わらなかった。
その苦しさを、ずっとひとりで抱えてきたんですよね。
「勉強が苦手なわが子に、どう関わればいいのかわからなかった私が、『この子らしさ』に気づきはじめた──3週間集中再安心サポート」では、
子どもの特性に合った関わり方を、一緒に探していきます。
「努力不足」ではなく
「努力の限界」として見つめ直す視点、
怒らなくていい関係性のつくり方、
「うちの子はうちの子」と思える感覚を取り戻すプロセス。
ひとりで背負わなくても、関係は整えていけます。
正解を探す時間じゃなくて、
一緒に「関わり方を育てていく時間」なんです。
ここから、ゆっくり始めていきましょう。
「“努力してるのにできない”って、わが子が一番くやしそうだった」
- 文章題の意味がわからない
- 時計の針も読めない
それでも頑張ろうとする姿に、どう接すればいいのか分からなかった。
- 「私の教え方が悪かったのかな」
- 「ちゃんと見てあげられてなかったのかも」
と、ずっと自分を責めてきた。
でも本当は──
できない理由を、誰よりも探し続けてきたのもあなたでした。
ただ、「それが『努力不足じゃなかった』と、誰かに認めてほしかった」だけ。
『何度やってもできない子』と思い込んでいた私が、『この子なりの理解のペース』に気づけた──3週間集中再安心サポートは、
「学習の苦手さ」を責める日々から、
「この子とつながり直す関わり方」への転換を支えます。
こんな方におすすめです
- 「どうしてできないの?」と毎日責めてしまう
- できる子と比べてしまって、自分を責めている
- わが子の特性を、きちんと理解したい
- 診断名よりも、「関わり方」を変えたい
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 1月20日(火)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと2名様限定』
※銀行振込限定・先着順
ネットバンキングのご利用で、今すぐ開始することが可能です。
そして──
この子の「苦手さ」に寄り添えるようになってきたあなたへ。
その歩みは、もう「自分自身を取り戻す準備」になっています。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
子育ての葛藤を経て築いた土台から、
「母」ではなく「私」としての人生を再設計する3週間。
- 子育てだけの毎日を抜け出したいと感じている
- でも「私はどうしたいのか」がまだ曖昧なまま
- 誰かのためではなく、自分の軸で生き直したい
このプログラムでは、
「母として悩み続けた日々」を越えて、
「私自身の人生」を歩み直す力を育てていきます。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
▶︎ 株式会社Osaka-Childの母親・子ども支援まとめを見る(心理・不登校・身体調整など・左の▼をクリック)
株式会社Osaka-Childの3人の子育てでストレスがたかい40代女性の心理作用をととのえるカウンセリング
子育ての真っ最中で、仕事と家庭の間で揺れ動いている女性の皆さんへ。私たちのカウンセリングサービスは、あなたのためにあります。もし心の中で悩みや生きづらさを感じている場合、それは特別な心のケアが必要な証拠です。株式会社Osaka-Childとして、日々の生活で直面している困難を理解し、その解決をサポートします。
私たちは、あなたが人生の困難に立ち向かう勇気を見つけるための安全な空間を提供します。当社のプロフェッショナルなカウンセラーは、あなたの問題や感情に深い理解を持ち、あなたを尊重します。ここでは、あなたの気持ちを自由に表現し、過去の影響から解放され、自分自身を再発見することができるでしょう。
カウンセリングは、心理システムの問題を共に解決するための有力な手段です。私たちのカウンセリングでは、まずじっくりとあなたのお話を聴きます。過去の経験やトラウマ、日常生活でのストレスなど、あなたが抱える悩みや心の中での葛藤を理解し、共感します。その後、適切なカウンセリング技法を用いて、心の中のブロックを取り除き、自分自身と向き合い、成長するためのサポートを行います。
初めての方でも、私たちのサービスを利用することはとても簡単です。当社のウェブサイト上で、カウンセリングセッションの申し込みをすることができます。また、具体的な問い合わせや不明点がある場合は、お気軽に当社までメールをお送りください。
心の中で抱える悩みや生きづらさに苦しんでいるなら、あなたは一人ではありません。株式会社Osaka-Childは、あなたが自分自身の価値を見つけ、生活の質を改善するためのサポートを提供します。カウンセリングを通じて、あなたがより健康的で充実した人生を歩む手助けをいたします。
カウンセリングのプロセスは、あなたの個別のニーズや目標に合わせてカスタマイズされます。私たちは、あなたが心地よく感じるペースでサポートを提供し、尊重と信頼の関係を築くことを大切にしています。カウンセリングを通じて、自己理解を深め、心の中の問題を克服し、より充実した人生を築いていきましょう。
あなたが心の支えを必要としているなら、ぜひ株式会社Osaka-Childのカウンセリングにお越しください。私たちがあなたの側にいて、共に問題を解決し、より健康で幸せな未来を築くお手伝いをいたします。一歩踏み出す勇気を持ってください。私たちと一緒に、新しい人生の扉を開いてみましょう。
\本気で変わりたい40代母親へ/
子どもとの関係、自分の人生、どちらもあきらめない方法があります。
33万円・50万円の本格プログラムで、臨床心理士とマンツーマンであなたの「再スタート」をサポートします。
現在【銀行振込の方限定で割引案内】をご用意しています。
🔸 本日 1月20日(火)23:59まで のご入金分までのご案内となります。
🔸 『あと2名様限定』
※銀行振込限定・先着順での受付となります。
小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援事業をする株式会社Osaka-Childとは?




【 復学率100% 】小中学生復学支援Osaka-Childの支援策とは?
こちらもCHECK
-

-
【 復学率100% 】小中学生復学支援Osaka-Childの支援策とは?
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
【堺市】不登校の子どもをサポートする!Osaka-Childのカウンセリング支援
こちらもCHECK
-

-
【堺市】不登校の子どもをサポートする!Osaka-Childのカウンセリング支援
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 Osaka-Childは、堺市にある不登校の子どもたちとその家族を支援するカウンセリ ...
続きを見る
復学支援の専門家が教える、家庭学習支援のポイントと効果的な学習方法
株式会社Osaka-Childの心理技法・心理検査一覧
株式会社Osaka-Childの障害一覧
株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:母親のメンタルサポート


支援内容
1. オキシトシン分泌促進で子どもに接する母親の専門的なカウンセリング
2. 胎児期から乳児期のオキシトシン分泌状態の再経験
3. 母親の子育ての疲れやストレスの軽減
4. 母親の胎児期・幼少期の体験のインナーチャイルドの修正
5. 母親の親子関係をカウンセリングにより気づかせる
6. カウンセリングによって母親の生き方を主体性を持たせる
7. 幼少期に得られなかった愛着の再構築
8. 個人に合った最適な心理システムの再起動
9. 母親を子どもの親から一個人としての存在の獲得
10. 愛着育成による自己肯定感の向上
11. 人生軸上でインストールした感覚ー認識の空洞化
母親のメンタルサポートの具体的なアプローチ
株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、母親のメンタルサポートを提供しています。以下に、具体的な支援内容を説明します。
- オキシトシン分泌促進で子どもに接する母親の専門的なカウンセリング オキシトシンは愛着や絆の形成に関与するホルモンであり、母親と子どもの関係を深める重要な役割を果たします。カウンセリングにおいては、母親がオキシトシン分泌を促進する方法や子どもとの関わり方について学びます。
- 胎児期から乳児期のオキシトシン分泌状態の再経験 母親が胎児期から乳児期の自身のオキシトシン分泌状態を再経験することで、子どもとの関係性や愛着形成に関する理解を深めます。これにより、母親はより適切な愛着行動を身につけ、子どもの安定した成長を支援します。
- 母親の子育ての疲れやストレスの軽減 子育てにおける疲れやストレスは母親のメンタルヘルスに大きな影響を与えます。専門的なカウンセリングにより、母親の疲れやストレスを軽減し、心の健康を保つための具体的なケア方法を提供します。
- 母親の胎児期・幼少期の体験のインナーチャイルドの修正 母親の胎児期や幼少期におけるトラウマや負の体験は、子育てに影響を及ぼすことがあります。カウンセリングにより、母親は自身のインナーチャイルド(内なる子どもの存在)の修正を通じて、子育てにおける負のパターンを変容させます。
- 母親の親子関係をカウンセリングにより気づかせる 母親の親子関係に潜むパターンや影響をカウンセリングを通じて明示し、母親自身がその関係性に気づくことを支援します。これにより、母親はより良好な親子関係を構築し、子どもの成長を促進します。
- カウンセリングによって母親の生き方を主体性を持たせる 母親が自身の生き方を主体的に選択し、子どもとの関係性をより意識的に築いていくことを支援します。母親の個別のニーズや目標を考慮し、適切なカウンセリングプランを策定します。
- 幼少期に得られなかった愛着の再構築 母親が幼少期に得られなかった愛着を再構築することで、自己肯定感や安心感を向上させます。カウンセリングにおいては、母親が自身の愛着スタイルや関わり方を理解し、健全な愛着関係の構築に向けた具体的なアプローチを身につけます。
- 個人に合った最適な心理システムの再起動 母親の心理システムの再起動により、ストレスへの対処能力や情緒調整能力を向上させます。カウンセリングにより、母親は自身の心理的な困難や制約を克服し、より健康的な心の状態を取り戻すことができます。
- 母親を子どもの親から一個人としての存在として認識 母親が自身を単に子どもの親としてではなく、個別の存在として認識することを支援します。母親の自己アイデンティティや自己実現の重要性を再確認し、自己成長とバランスの取れた生活を促進します。
- 愛着育成による自己肯定感の向上 母親が子どもとの愛着関係を育むことで、自己肯定感や自己価値感を向上させます。カウンセリングにおいては、母親が愛着行動やコミュニケーションスキルを向上させるための具体的な手法やアドバイスを受け取ります。
- 人生軸上でインストールした感覚ー認識の空洞化 母親が人生軸上で自身の感覚や認識を見つめ直し、新たな視点や意味づけを行うことを支援します。これにより、母親はよりポジティブな心理状態を持ち、子どもとの関係や子育てにおいてより健全な選択を行うことができます。
具体的な支援内容として、母親は定期的なカウンセリングセッションを通じて自身のメンタルヘルスや子育てに関する課題を共有し、カウンセラーとの対話やアドバイスを受け取ります。また、母親には日常生活におけるストレス管理や自己ケアの方法、感情の調整やコミュニケーションスキルの向上など、実践的なツールや戦略が提供されます。
大阪の不登校カウンセリング|40代の母親が必知!子供の不登校を解決する支援方法と専門家のアドバイス
こちらもCHECK
-

-
大阪の不登校カウンセリング|40代の母親が必知!子供の不登校を解決する支援方法と専門家のアドバイス
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 子供の不登校は多くの40代の母親にとって深刻な悩みです。その解決には適切な支援方法と ...
続きを見る
【40代母親からの第一歩】不登校問題解決への道と専門カウンセリングでの導き
こちらもCHECK
-

-
【40代母親からの第一歩】不登校問題解決への道と専門カウンセリングでの導き
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 40代の母親が抱える不登校問題は深刻な課題です。子どもの不登校により家庭や学校の関係 ...
続きを見る
【幸せホルモン】オキシトシンの増やし方12選|瞑想やマインドセット・身体調整が効果的
不登校の原因を知る方法!40代の母親が的確にサポートする方法とは?
中学生の不登校の原因は母親にあった!母親へのカウンセリングで復学につなげる
【40代子育ての悩み】不登校の原因を解明!不登校になる子の親の特徴と改善策
株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どものカウンセリング


支援内容
1. 不登校の子どもが抱えるココロの動きの促進
2. 幼少期の負の体験の心理システムの循環
3. 親子関係による負の自己イメージの軌道修正
4. 学校環境での存在価値の促進
5. 過去ー現在ー未来の時間軸の自然循環
6. 幼少期に遺伝的にもっているエネルギーの再生成
7. 学校環境で経験した負の要素への関わり
8. 学校環境で作られた他者との競争原理の滅尽
9. 母親では得られなかった愛着をカウンセラーとの共有で再獲得
10. 幼少期のゼロベースでの人間像への気づき
11. 負の心理システムで構成された世界観の抑制
不登校の子どものカウンセリングの具体的なアプローチ
- 不登校の子どもが抱えるココロの動きの促進 不登校の子どもは心理的な負担を抱えている場合があります。私たちは、子どものココロの動きを理解し、彼らが抱える不安やストレスを軽減するための支援を行います。具体的な方法としては、感情の表現や認識のトレーニング、リラクゼーション技法の導入などがあります。また、子どもが自己理解を深め、自己肯定感を高めるために、自己探索のプロセスにも取り組みます。
- 幼少期の負の体験の心理システムの循環 幼少期に経験した負の出来事やトラウマは、不登校の原因となることがあります。私たちは、そのような負の体験が心理システムにどのように影響を与え、循環するのかを理解し、子どもと共にその解決に向けた取り組みを行います。具体的には、トラウマ解消のための技法や自己発見のプロセスを通じて、過去の負の経験に対処し、新たな自己概念を構築するサポートを行います。
- 親子関係による負の自己イメージの軌道修正 親子関係は子どもの自己イメージに大きな影響を与えます。不登校の子どもにおいては、負の自己イメージが形成されることがあります。私たちは、子どもと親の関係を理解し、親子のコミュニケーションの改善や共感的な対話を通じて、子どもの自己イメージの軌道修正を支援します。親には、子どもの感情や困難に対して理解を示し、受け入れる姿勢を促すためのアドバイスや指導を提供します。
- 学校環境での存在価値の促進 不登校の子どもは学校環境での存在価値や自己肯定感に欠けていることがあります。私たちは、子どもが学校での存在感を取り戻すための支援を行います。具体的には、学校との連携や学校内でのサポート体制の構築を行い、子どもが自分の能力や才能を発揮できる場を提供します。また、学校生活の中での達成感や成功体験を通じて、子どもの自信を育む取り組みも行います。
- 過去ー現在ー未来の時間軸の自然循環 不登校の子どもは、過去の困難や現在の問題に囚われる傾向があります。私たちは、子どもが過去、現在、未来の時間軸を自然に循環できるように支援します。過去の出来事への執着や現在の問題に対する固執を解放し、未来に向けて前向きに取り組むことを促します。具体的な方法としては、目標設定や将来のビジョンの明確化、行動計画の策定などがあります。
- 幼少期に遺伝的に持っているエネルギーの再生成 子どもの行動や感情は、幼少期に遺伝的に受け継がれたエネルギーによって影響を受けることがあります。私たちは、子どもが遺伝的に持っているエネルギーを再生成し、ポジティブな方向へと導くための支援を行います。具体的には、子どもが自己観察や自己理解を深めるプロセスを通じて、自己変容を促すことに焦点を当てます。
- 学校環境で経験した負の要素への関わり 不登校の子どもは、学校環境での負の要素に対して適切に関わることができない場合があります。私たちは、子どもが学校環境での負の要素に対して適切に対処できるように支援します。具体的には、コミュニケーションスキルのトレーニングや問題解決能力の向上を促すプログラムを提供し、子どもが対処方法を見つけられるようにサポートします。
- 学校環境で作られた他者との競争原理の滅尽 学校環境では競争原理が存在し、不登校の子どもにとっては負の影響を与えることがあります。私たちは、他者との競争原理を滅尽し、協力や共感の文化を醸成する支援を行います。具体的には、協調性やチームワークの重要性を学ぶ活動や、他者との比較ではなく自己の成長に焦点を当てる指導を行います。
- 母親では得られなかった愛着をカウンセラーとの共有で再獲得 不登校の子どもの中には、母親からの愛着が不足している場合があります。私たちは、子どもがカウンセラーとの関係を通じて、得られなかった愛着を再獲得できるように支援します。子どもが安心感や信頼感を育み、自己価値感や自己受容感を高めるために、カウンセラーとの関係性を重視したアプローチを取ります。
- 幼少期のゼロベースでの人間像への気づき 不登校の子どもには、幼少期に根付いた人間像や自己イメージに問題がある場合があります。私たちは、子どもが自己観察や内省を通じて、幼少期のゼロベースから新たな人間像への気づきを促す支援を行います。具体的には、自己評価の見直しやポジティブな特性の発見、適応的な思考や行動パターンの構築をサポートします。
- 負の心理システムで構成された世界観の抑制 不登校の子どもは、負の心理システムで構成された世界観を持っていることがあります。私たちは、子どもがそのような負の世界観から抜け出し、ポジティブな視点や心理的な柔軟性を取り戻すための支援を行います。
具体的には、認知行動療法やポジティブ心理学の手法を用いて、子どもの思考や信念の再構築を促し、より健康的な心理システムを構築します。 株式会社Osaka-Childの臨床心理士(カウンセラー・セラピスト・不登校専門カウンセラー)として、私たちは不登校の子どもとその家族に対して、個別に適した支援を提供します。子どもの心の健康を重視し、不登校の原因や状況を的確に把握した上で、専門知識や経験に基づいたアプローチを用いてサポートを行います。私たちの目標は、子どもが健やかな学校生活を送り、自己成長や社会参加の機会を最大限に引き出すことです。
不登校カウンセリングでHSCの子どもを復学支援に|HSCの子どもを持つ40代の母親に向けて
こちらもCHECK
株式会社Osaka-Childのカウンセリング技法
カウンセリングとは?心理システムを正常化して生きづらさを克服する効果最大
-

-
参考カウンセリングとは?心理システムを正常化して生きづらさを克服する効果最大
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
来談者中心療法で心理システムを自然状態にして精神的苦しみを克服|40代女性の生きづらさ克服
-

-
参考来談者中心療法で心理システムを自然状態にして精神的苦しみを克服|40代女性の生きづらさ克服
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
トラウマインフォームドケアをカウンセリングで心理システムの最短正常化に
-

-
参考トラウマインフォームドケアをカウンセリングで心理システムの最短正常化に
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
オンラインカウンセリングのメリット・デメリットを知って手軽に心理システムを正常化する
-

-
参考オンラインカウンセリングのメリット・デメリットを知って手軽に心理システムを正常化する
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
精神分析的心理療法でカウンセリングを実施し心理システムの正常化で生きづらさ克服
株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの身体調整


支援内容
1. 子どもの姿勢コントロールの修正
2. 姿勢コントロールによる身体アライメント構築
3. 姿勢コントロールから重心作り
4. 学習に不可欠な座り姿勢での姿勢コントロールの促通
5. 姿勢に伴う手の運動構成のバランス
6. 姿勢と視覚・聴覚情報の同期
7. 全身の関節運動・筋肉の出力調整
8. 三半規管や脳神経系の出力の修正
9. ハンドリングによる触覚刺激で感覚系のコントロール
10. 皮ふ刺激によるオキシトシン分泌の促進
11. 皮ふ・筋膜・筋肉・筋肉の長さのセンサーのコントロール
12. 感覚ー認識システム促通から無の状態へのアップデート
13. 身体への関わりによる不足した愛着の向上
14. 負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化
15. 負の心理システムから身体への過剰な意識への抑制
不登校の子どもの身体調整の具体的なアプローチ
株式会社Osaka-Childでは、不登校の小中学高校生や発達障害の子どもの復学支援の一環として、身体調整の支援を行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。
- 子どもの姿勢コントロールの修正 子どもの姿勢は、身体の調整や感覚統合に重要な役割を果たします。不適切な姿勢が存在する場合、学習や集中力に悪影響を与えることがあります。私たちは、子どもの姿勢を正しい形に修正し、適切な姿勢コントロールをサポートします。具体的には、姿勢の矯正や筋力トレーニング、姿勢保持のためのエルゴノミクス指導などを行います。
- 姿勢コントロールによる身体アライメント構築 姿勢の改善は、身体のアライメントやバランスの向上につながります。私たちは、子どもの身体アライメントを構築するために、姿勢コントロールのトレーニングを行います。これには、正しい姿勢の保持や身体の軸の調整、バランス感覚の向上などが含まれます。
- 姿勢コントロールから重心作り 姿勢と重心の関係は、身体の安定性や運動の質に大きな影響を与えます。私たちは、姿勢コントロールから重心の形成に焦点を当て、子どもが適切な重心を持つことをサポートします。具体的には、姿勢トレーニングやバランスボードを使ったトレーニングなどを通じて、重心の安定化を促します。
- 学習に不可欠な座り姿勢での姿勢コントロールの促通 適切な座り姿勢は、学習において重要な要素です。不適切な座り姿勢は集中力の低下や身体の疲労を引き起こすことがあります。私たちは、子どもが学習に不可欠な座り姿勢を維持できるように、姿勢コントロールの促通を支援します。具体的には、正しい座り方やデスク環境の調整、体操やストレッチの指導などを行います。
- 姿勢に伴う手の運動構成のバランス 姿勢と手の運動は密接に関連しています。不適切な姿勢は手の運動にも影響を与えることがあります。私たちは、子どもの手の運動構成をバランス良く整えるために、姿勢と手の連動性を意識した支援を行います。具体的には、手の筋力や協調性のトレーニング、細かい手指の動作の指導などを行います。
- 姿勢と視覚・聴覚情報の同期 姿勢の調整と視覚・聴覚情報の適切な処理は、子どもの学習や集中力に影響を与えます。私たちは、子どもが姿勢と視覚・聴覚情報を適切に同期させるための支援を行います。具体的には、視覚情報や聴覚情報の統合を促すトレーニングやセンサリー処理の指導などを行います。
- 全身の関節運動・筋肉の出力調整 全身の関節運動や筋肉の出力の調整は、身体の柔軟性や運動能力に影響を与えます。私たちは、子どもの全身の関節運動や筋肉の出力を調整し、適切な身体の動きをサポートします。具体的には、関節の可動域の拡大や筋力トレーニング、コーディネーションの向上を目指したプログラムを提供します。
- 三半規管や脳神経系の出力の修正 三半規管や脳神経系の出力の調整は、バランス感覚や運動の調整に関与します。私たちは、子どもの三半規管や脳神経系の出力を修正し、バランス感覚や運動の質を改善するための支援を行います。具体的には、バランス感覚のトレーニングや目の運動の指導などを行います。
- ハンドリングによる触覚刺激で感覚系のコントロール 触覚刺激は感覚統合や身体の調整に重要な役割を果たします。私たちは、子どもの感覚系のコントロールを促すために、ハンドリングと呼ばれる触覚刺激を活用した支援を行います。具体的には、身体全体に触覚刺激を与えることで感覚統合を促し、身体の安定性や調整能力を高めます。
- 皮ふ刺激によるオキシトシン分泌の促進 皮ふ刺激はオキシトシンの分泌を促し、リラックスや安定感をもたらします。私たちは、子どもの皮ふ刺激を活用してオキシトシンの分泌を促進し、心身の安定をサポートします。具体的には、マッサージや触れ合いのアクティビティを通じて、子どもがリラックスした状態に入る機会を提供します。
- 皮ふ・筋膜・筋肉の長さのセンサーのコントロール 身体の皮ふ、筋膜、筋肉は長さの変化を感知するセンサーを持っています。私たちは、子どもの皮ふ・筋膜・筋肉の長さのセンサーをコントロールし、正常な身体の感覚を促します。具体的には、ストレッチや筋膜リリースなどの手法を用いて、身体の柔軟性や感覚統合を促進します。
- 感覚ー認識システム促通から無の状態へのアップデート 感覚と認識のシステムが促通し、無の状態にアップデートされることは、子どもの集中力や学習能力に大きな影響を与えます。私たちは、子どもの感覚と認識のシステムを促通させ、無の状態へのアップデートを支援します。具体的には、身体を使ったアクティビティやセンサリー統合の手法を用いて、感覚と認識の調整を促します。
- 身体への関わりによる不足した愛着の向上 不登校の子どもには、不足した愛着が存在する場合があります。私たちは、身体への関わりを通じて子どもの不足した愛着を向上させる支援を行います。具体的には、身体的な接触やアクティビティを通じて子どもとの関係性を構築し、安心感や信頼感を促します。
- 負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化 負の心理システムは、子どもの身体に過緊張や緊張を引き起こすことがあります。私たちは、負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化をサポートします。具体的には、筋肉の緊張を緩めるエクササイズやリラクゼーション法の指導を行い、身体の緊張を軽減します。
- 負の心理システムから身体への過剰な意識への抑制 負の心理システムから身体への過剰な意識は、子どもの集中力や学習に悪影響を与えることがあります。私たちは、負の心理システムから身体への過剰な意識を抑制する支援を行います。
株式会社Osaka-Childの身体調整とカウンセリング技法
催眠療法と心理カウンセリング併用で精神作用をリセット|40代女性の心理システムを正常化に
-

-
参考催眠療法と心理カウンセリング併用で精神作用をリセット|40代女性の心理システムを正常化に
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
自律訓練法とカウンセリングの併用で40代女性生きづらさ克服|自宅で簡単にできる
-

-
参考自律訓練法とカウンセリングの併用で40代女性生きづらさ克服|自宅で簡単にできる
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
呼吸法とカウンセリングで身体と精神をコントロールし40代女性が安定した人生を送る
-

-
参考呼吸法とカウンセリングで身体と精神をコントロールし40代女性が安定した人生を送る
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
メンタライゼーション・ベースド・セラピーで40代女性の心理システムを整える
-

-
参考メンタライゼーション・ベースド・セラピーで40代女性の心理システムを整える
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
グリーフケアカウンセリングで新しい自分で自然世界と調和した生き方を獲得する
-

-
参考グリーフケアカウンセリングで新しい自分で自然世界と調和した生き方を獲得する
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
リラクゼーション法で40代女性の生きづらさの身体症状を克服|目的・やり方・コツを解説
-

-
参考リラクゼーション法で40代女性の生きづらさの身体症状を克服|目的・やり方・コツを解説
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
具体的には、身体感覚の調整やマインドフルネスなどの技法を用いて、子どもの心身のバランスを整えます。 株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの身体の健康と調整を重視し、個別に適した身体調整の支援を提供します。子どもとその家族との協力を通じて、身体の調整や感覚統合の促進を図り、学習や社会生活の質を向上させることを目指します。
📌 あなたに必要な支援は、今すぐ手に届きます。
ここまで読んで「これ、私のことだ」と感じた方へ。
私たちが提供している再設計プログラムは、表面的なアドバイスではなく、根本から人生を整えるための実践型サポートです。
現在【銀行振込の方限定で割引案内】をご用意しています。
🔸 本日 1月20日(火)23:59まで のご入金分までのご案内となります。
🔸 『あと2名様限定』
※銀行振込限定・先着順での受付となります。
銀行振込限定で 最大5万円割引・個別相談枠の優先予約も受付中。
株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの家庭学習支援


支援内容
1. オンラインによる苦手教科の徹底的学習サポート
2. 自分に合った教材と学習法の発見と実践
3. 得意科目を地域で成績上位に入るための学習法
4. 苦手科目の時間的な関わり(量→質)
5. 予習・復習の時間共有
6. 脳内の特性に合わせた学習プログラムの実践
7. 脳内と心理システムを促通した個人に合った学習方法の習得
8. 勉強量から勉強の質への関わり
9. 不登校中の自宅でのスケジューリング
10. 勉強に対する苦手意識への心理システムの調整
11. 成績に反映する個人に合った勉強法の獲得
12. 全教科の要素分解と要素の合成への考え方の習得
13. 不登校中に偏差値を20以上向上させる学習時間と質の習得
不登校の子どもの家庭学習支援の具体的なアプローチ
株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、家庭学習の支援を行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。
- オンラインによる苦手教科の徹底的学習サポート オンラインを活用して、子どもの苦手とする教科について徹底的な学習サポートを行います。個別のオンラインチューターや学習プラットフォームを活用し、子どもが理解を深めるための指導を提供します。
- 自分に合った教材と学習法の発見と実践 子どもに合った教材や学習法を見つけ、実践するサポートを行います。子どもの学習スタイルや興味・関心に合わせて教材を選定し、効果的な学習方法を指導します。
- 得意科目を地域で成績上位に入るための学習法 子どもの得意科目を活かして、地域で成績上位に入るための学習法を指導します。具体的な学習戦略やアプローチを提供し、子どもが得意科目での自信と成果を得られるように支援します。
- 苦手科目の時間的な関わり(量→質) 苦手科目に対する学習時間を質の高いものにするための支援を行います。集中力を高めるための学習スケジュールの作成や、効果的な学習方法の指導を通じて、苦手科目への取り組みを効果的に進める方法を提供します。
- 予習・復習の時間共有 予習と復習の重要性を理解し、効果的に取り組むために、子どもと共有する時間を設けます。予習や復習の方法や具体的な計画の立て方を指導し、子どもが学習内容を定着させるサポートを行います。
- 脳内の特性に合わせた学習プログラムの実践 子どもの脳の特性に合わせた学習プログラムを実践します。例えば、視覚的な学習スタイルを持つ子どもにはマインドマップやイメージングを活用し、効果的な学習を促します。
- 脳内と心理システムを促通した個人に合った学習方法の習得 子どもの脳内の機能と心理システムを促通させ、個人に合った学習方法を習得させる支援を行います。具体的には、脳の情報処理や学習スタイルを理解し、それに基づいた学習戦略やアプローチを提案します。
- 勉強量から勉強の質への関わり 勉強の量だけでなく、質の高い学習を実現するための関わりをサポートします。集中力の向上や学習環境の整備、効果的な学習テクニックの指導などを通じて、子どもが効率的かつ効果的に学習できるように支援します。
- 不登校中の自宅でのスケジューリング 不登校中の子どもが自宅での学習をスムーズに進めるためのスケジューリングのサポートを行います。適切な時間配分やタスク管理の方法を指導し、子どもが自主的に学習を進められるように支援します。
- 勉強に対する苦手意識への心理システムの調整 勉強に対する苦手意識を持つ子どもに対して、心理システムの調整を行います。適切な支援方法や学習環境の整備、ポジティブなフィードバックの提供などを通じて、子どもの勉強への意欲や自信を高める支援を行います。
- 成績に反映する個人に合った勉強法の獲得 子どもの個別の特性や学習スタイルに合わせて、成績に反映される勉強法を獲得させる支援を行います。具体的には、学習戦略の指導や学習プランの作成、効果的な学習テクニックの習得などを通じて、子どもが効果的に学習できるようにサポートします。
- 全教科の要素分解と要素の合成への考え方の習得 全教科において、学習内容を要素分解し、それらを合成する考え方を習得させる支援を行います。具体的には、重要なキーポイントの抽出や概念の整理、総合的な学習アプローチの指導などを通じて、子どもの学習能力を向上させます。
- 不登校中に偏差値を20以上向上させる学習時間と質の習得 不登校中に子どもの学習時間と質を向上させ、偏差値を20以上上げる支援を行います。適切な学習計画の策定や時間管理の指導、効果的な学習方法の習得などを通じて、子どもの学力向上を支援します。
発達支援・発達相談をカウンセリングと療育で発達障害の子どもの機能性を120%アップ
動機づけ面接とカウンセリングの併用で40代女性の個人の人生に合った生き方を見つける
ナラティヴセラピーをカウンセリングで過去の経験値を未来軸に近づけ40代女性を自己実現に
ペアレント・トレーニングで40代母親の子育てを楽にする|子どもの育ちを大切にできる
不登校中の勉強しない・遅れる不安を解決する40代母親ができる接し方とは
中3不登校生徒で勉強してない場合の受験対策や進路の選択肢|今からでも間に合う!
【40代母親必見】不登校の子が復学後に勉強しない?その原因と解決策を詳解
中学3年間不登校だと勉強してないから高校受験は難しい?中学生の不登校の原因と親ができる対応
発達障害をカウンセリングで心理システムをスムーズにし克服へ|40代女性生きづらさ解決
学習障害(LD)をカウンセリングで最短で負担なく克服させる|生きづらさ解決に
株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの家庭学習をサポートし、個別に適した学習方法や戦略を提供します。子どもとその家族との協力を通じて、学習の成果を最大化し、不登校からの復学を支援します。
株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポート


支援内容
1. カウンセリングによる自己イメージのリセット
2. 意識と覚醒の自然現象への共有
3. 好きなこと・得意なこと・使命感への気づき
4. 未来像のマインドからの発見
5. 未来像と現実の自己へのプログラミング
6. 自己内から具体的な人生設計
7. 誕生から死への人生軸への関わりと意識の促通
8. トレンド情報に流されない個人に合った生き方の習得
9. 努力せずありのままで成果が出るキャリアとプロセスの構築
10. 学校環境での失敗体験の再現化と捨てる作業
11. 世界を構造から見つけていくトレーナーとの共有
不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポートの具体的なアプローチ
株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、進学やキャリアデザインのサポートを行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。
- カウンセリングによる自己イメージのリセット カウンセリングを通じて、子どもの自己イメージをリセットします。過去の失敗や困難な経験に縛られず、新たな可能性や自己評価を見つける支援を行います。
- 意識と覚醒の自然現象への共有 子どもに対して、意識や覚醒の自然現象について共有し、自己の内面に目覚めるきっかけを与えます。具体的には、マインドフルネスや瞑想などの方法を取り入れ、子どもが内なる気づきや成長を促します。
- 好きなこと・得意なこと・使命感への気づき 子どもが自分の好きなことや得意なこと、そして使命感を見つけるための支援を行います。興味や才能を引き出し、将来の方向性を探るための活動や自己探求のプロセスをサポートします。
- 未来像のマインドからの発見 子どもが自分自身の未来像を持つことで、目標や希望を見つける手助けをします。未来を具体的にイメージすることで、自己の成長や進学・キャリアの方向性を見出すサポートを行います。
- 未来像と現実の自己へのプログラミング 子どもが描いた未来像と現実の自己を結び付けるためのプログラミングをサポートします。具体的な目標設定や行動計画の策定、自己肯定感や自己効力感の醸成を通じて、子どもの進学やキャリアの実現を支援します。
- 自己内から具体的な人生設計 子どもが自己内に持つ資源や価値観を活かし、具体的な人生設計を立てるサポートを行います。自己の内なる声や目標に基づき、将来の進路やキャリアの方向性を考えるプロセスを共に進めます。
- 誕生から死への人生軸への関わりと意識の促通 子どもに対して、人生の意義や目的、誕生から死への人生軸について考える機会を提供します。自己の存在意義や時間の尊さを理解し、将来に向けた意識の促進を支援します。
- トレンド情報に流されない個人に合った生き方の習得 子どもがトレンド情報や社会の期待に流されず、自己に合った生き方を見つけるための支援を行います。個別の特性や価値観を尊重し、自己を大切にする生き方の習得をサポートします。
- 努力せずありのままで成果が出るキャリアとプロセスの構築 子どもが努力せずにありのままの自己で成果を出せるキャリアやプロセスの構築をサポートします。個々の能力や資質を活かし、自己の個性や魅力を最大限に生かした進学やキャリアの選択を支援します。
- 学校環境での失敗体験の再現化と捨てる作業 学校環境での失敗体験を再現し、それらを手放すプロセスを支援します。過去のネガティブな体験やトラウマからの解放を促し、自己成長と前向きな展望を持つためのサポートを提供します。
- 世界を構造から見つけていくトレーナーとの共有 子どもが世界の構造や社会の仕組みを理解し、自己の進学やキャリアの選択に生かすために、トレーナーとの共有を行います。具体的な情報や知識の提供、意義や意味の理解を通じて、子どもの進学やキャリアデザインに役立つサポートをします。
対人関係療法カウンセリングで治りにくい精神疾患を正常化する|うつ病・摂食障害に効果的
ソリューション・フォーカスト・アプローチで人生の悩みを最短解決|40代女性生きづらさ克服
キャリアカウンセリング(キャリアコンサルティング)で40代女性の人生を幸福に導く
コーチングで40代女性の子育てやキャリアアップを最速に機能させる
株式会社Osaka-Childのカウンセリング技法
【2023年最新】認知行動療法(CBT)とは?方法、効果やメリット・デメリット、療法の流れなどを解説
ストレスマネジメントとは?40代女性が子育て・キャリアアップで活かせる効果ややり方を解説
-

-
参考ストレスマネジメントとは?40代女性が子育て・キャリアアップで活かせる効果ややり方を解説
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
アサーショントレーニングとは?職場や子育てで実践する方法や自己表現タイプを解説
-

-
参考アサーショントレーニングとは?職場や子育てで実践する方法や自己表現タイプを解説
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
認知再構成法とカウンセリングで40代女性の生きづらさを生む認知のゆがみを克服
-

-
参考認知再構成法とカウンセリングで40代女性の生きづらさを生む認知のゆがみを克服
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの進学やキャリアデザインを支援し、自己の可能性や夢を追求するサポートを行います。子どもとその家族との協力を通じて、自己の価値を見出し、将来への道を切り拓くお手伝いをします。
株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの子どもの不登校復学支援内容:不登校復学後の1年間のサポート


支援内容
1. 復学後の学校との連携
2. 復学後の母親と子どものカウンセリングの実施
3. 復学後に生まれる諸問題の解決と実践
4. 復学後の生きづらさの軌道修正
5. 復学後の母親のメンタルサポートの継続
6. 復学後にぶつかる学校環境での負の体験への関わり
7. 母親に生まれる子どもへの過負荷の調整
8. 母親の人生サポートの継続による子どもの自由の解放
9. 復学後に生まれる母親と子どもへの不安の共有
不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポートの具体的なアプローチ
株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学後の1年間にわたるサポートを提供しています。以下に、具体的な支援内容を説明します。
- 復学後の学校との連携 子どもの復学後において、学校との綿密な連携を行います。学校とのコミュニケーションを円滑にし、子どもの学習状況や生活面でのサポートが必要な点を把握し、適切な支援策を立てるために協力します。
- 復学後の母親と子どものカウンセリングの実施 復学後においても母親と子どものカウンセリングを実施し、お互いの心情や課題に対して向き合います。母親の支えや理解を促し、子どもの心理的な安定と学校生活への適応をサポートします。
- 復学後に生まれる諸問題の解決と実践 復学後に生じる様々な問題や課題に対して、具体的な解決策を見つけて実践する支援を行います。学校生活や人間関係のトラブル、学習上の困難などに対して、子どもと母親の双方が適切に対処できるようにサポートします。
- 復学後の生きづらさの軌道修正 復学後に感じる生きづらさや不安に対して、子どもの心理的な軌道修正を支援します。自己肯定感の向上や適切なストレス管理の方法を教えることで、子どもが学校での生活に前向きに取り組むことを支えます。
- 復学後の母親のメンタルサポートの継続 母親のメンタルサポートを復学後も継続的に行います。母親が子どもの復学に伴うストレスや不安を抱える場合には、心理的な支えや情報提供を通じて、彼女の心の健康状態を維持し、子どもへのサポートを続けます。
- 復学後にぶつかる学校環境での負の体験への関わり 復学後に学校環境での負の体験が生じた場合には、子どもがそれに適切に関わることができるようにサポートします。適切なコーピングスキルの習得や自己肯定感の強化を通じて、子どもが学校での困難に立ち向かう力を育みます。
- 母親に生まれる子どもへの過負荷の調整 復学後において、母親が子どもに対して過度な負荷を感じる場合には、適切な調整を行います。母親の負担を軽減し、子どもとの関係性を健全に保ちながら、サポートのバランスを取ることが重要です。
- 母親の人生サポートの継続による子どもの自由の解放 母親の人生全体にわたるサポートを継続し、彼女が自己の成長と発展に集中できる環境を整えます。母親の支えが安定することで、子どもはより自由に自己を表現し、学校生活を充実させることができます。
- 復学後に生まれる母親と子どもへの不安の共有 復学後に母親と子どもが抱える不安や心配事に対して、お互いがそれを共有し、解消するための場を提供します。相互の理解を深め、不安を和らげることで、子どもの復学後の安定と成長をサポートします。
ストレスコーピングとカウンセリングの併用で40代女性のキャリア・子育てに成果
マインドフルネスとカウンセリングで効果を最大に|40代女性のキャリア・子育てに成果を出す
行動活性化療法で精神的抑うつを改善|40代女性生きづらさ克服でキャリア・育児両立に
株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの不登校復学後の1年間にわたり、学校との連携や心理的なサポートを通じて、子どもと母親の両方を支えます。子どもの安定した学校生活の確立と母親のメンタルヘルスの維持に注力し、一人ひとりのニーズに合わせたサポートを提供します。
Osaka-Childは小学生・中学生の不登校のお子さまに対して最短復学支援を提供しています

株式会社Osaka-Childの支援内容とは
- 母親のメンタルサポート
- 不登校子どものカウンセリング
- 不登校子どもの身体調整
- 不登校子どもの家庭学習支援
- 不登校子どもの進学・キャリアデザインサポート
- 不登校復学後の1年間のサポート
不登校子どものカウンセリング Osaka-Childでは、専門のカウンセラーによる個別のカウンセリングを行い、不登校の原因や問題を解決するための支援を提供しています。不登校子どもの身体調整 心身共に健康であることは、不登校克服に不可欠な要素の1つです。Osaka-Childでは、体の不調を訴える子どもに対して、運動や栄養指導などの支援を提供しています。不登校子どもの家庭学習支援 学校に行けない状況であっても、家庭学習を続けることが重要です。 Osaka-Childでは、家庭学習の計画立案や実践支援を行い、学習習慣の維持や向上に貢献しています。不登校子どもの進学・キャリアデザインサポート 不登校期間中に進路について考えることは、将来の自分自身の希望や目標を明確にするためにも重要です。 Osaka-Childでは、進路相談や進学・就職に関する情報提供など、キャリアデザインに必要な支援を提供しています。不登校復学後の1年間のサポート 不登校克服後の生活は、新たな課題やストレスを伴うことがあります。Osaka-Childでは、不登校復学後の1年間にわたって、学校生活や社会生活のサポートを行っています。
🔚 最後まで読まれたあなたへ。
もし「私は変わりたい」と思われたのなら、
それは変わる準備が、すでに整い始めている証拠です。
✅ 現在【銀行振込の方限定で割引案内・特別価格&3大特典】をご案内中です
🔸 本日 1月20日(火)23:59まで のご入金分までのご案内となります。
🔸 『あと2名様限定』
※銀行振込限定・先着順での受付となります。
33万円・50万円の再スタート支援プログラムでは、
家族関係・心理構造・生き方の再構築を、あなたのペースでじっくり支援します。
すでに診断済みの方も、そのまま詳細ページへ進めます。
あなたの心と体に合ったサポートを、今すぐ確認してみてください。


























































の-女性専門カウンセリング支援.png)


で-40代女性の人生を幸福に導く-〜株式会社Osaka-Childの効果的なアプローチ〜-150x150.png)






