
中学生のお子さんが、最近なにもやる気を見せない。
声をかけても反応が薄くて、親のほうがどう接していいか分からない――
そんなふうに感じている40代の母親の方へ。
「きっと思春期だから仕方ないよね」とやり過ごしてみたけれど、なんとなくモヤモヤがつづいている…。
実は、こうした「無気力」の背景には、
- 発達障害
- そのグレーゾーン
- 診断はされていないけれど発達特性がある
子どもたちのしんどさが関係しているケースもあるんです。
この記事では、そんな中学生の「無気力」の奥にあるサインを見のがさず、母親としてどう理解し、どうささえていけばいいのかを、実際のフェーズごとにわかりやすくお伝えしています。
この記事を読んでわかること
- 中学生に見られる「無気力」の背景にある発達障害やグレーゾーンの特徴
- 診断がつかなくても支援が必要な「発達特性」の見きわめ方
- 無気力期に子どもがどのような心理状態にあるのか、4つのフェーズ別で理解できる
- 母親自身が抱く不安や疲労感との向き合い方
- 子どもの自己肯定感を育てる具体的なかかわり方のヒント
そして、記事の後半では「母親が無理なく支えていくために大切な視点」や、必要におうじてどこに相談すればいいのかという情報もご紹介しています。
わたしたちOsaka-Childは、不登校支援に限定されたサービスではありません。
子育てに悩むすべての40代母親が、自分らしさを取りもどしながら子どもと向き合えるように、
専門カウンセラーによるプログラムやサポートを提供しています。
「これって私だけかな?」と思っていた不安や悩みも、知ることで整理できることがあります。
この機会に、まずは「わかってあげたい気持ち」から一歩、ふみ出してみませんか?
監修者
株式会社Osaka-Child所属 精神科医
- 名前: 川村恵子
- 出身地: 福岡県
- 最終学歴: 京都大学医学部 精神神経学専攻
- 専門分野: 精神病理学、ストレス管理、認知療法
- 職歴: 京都大学医学部附属病院精神科勤務(10年)、独立後、大阪で精神科クリニックを開設
専門分野について一言: 「心の健康は全身の健康へとつながります。一人ひとりの心の声を大切にしたいと思っています。」
監修者
株式会社Osaka-Child所属 小児科医
- 名前: 高橋和明
- 出身地: 大阪府
- 最終学歴: 東京大学医学部 小児科学専攻
- 専門分野: 小児感染症、アレルギー科学
- 職歴: 東京大学医学部附属病院小児科勤務(10年)、その後、大阪で小児科クリニックを開設
専門分野について一言: 「子供たちは未来です。彼らが健康に、元気に育つことをサポートします。」
母親向け限定サポート
「どう関わっても響かない…」──
無気力な中学生と向き合い続けることに、限界を感じていませんか?
このプログラムは、発達障害・グレーゾーン・不登校傾向の子どもとの関わりに悩む母親のための【初期対応サポート】です。
“家庭の空気”が変わり始める、3週間をご一緒します。
✅ こんな方に適しています
・昼夜逆転や寝たきり状態の中学生に戸惑っている
・スマホ依存・無反応で、家庭内に会話がない
・「どう関わればいいのか」すら分からなくなっている
🔸 現在【銀行振込の方限定で割引+3大特典】をご案内中です
🔸 本日 1月24日(土)23:59まで のご入金分までのご案内となります
🔸 『あと2名様限定』 ※銀行振込限定・先着順
▶ 発達傾向の子どもに悩む母親のための3週間集中サポートを見る
🎁 銀行振込の方には、3大特典をPDFで即日進呈
✅「母親の感情整理チェックリスト」
✅「学校・医療機関への伝え方テンプレ」
✅「無気力対応・やってはいけない5つの行動」
────
さらに、「整えたその先」を歩みたい方へ
子どもとの関係を見直した後、「自分の人生・働き方」も再構築したい方に向けた上位プログラム(50万円)もご案内しています。
※段階的サポートのため、まずは3週間サポートからご参加ください。
「ちゃんとしてるのに、苦しい」
「頑張ってるのに、うまくいかない」
——そんな違和感を抱えたまま、ずっと我慢していませんか?
LINEで3分セルフ診断ができます。
あなたの“今の感覚”の正体が、見えてきます。
「無気力」は思春期だけじゃない?発達障害・グレーゾーンの子どもが抱える「目に見えない疲れ」
中学生になると、
母親との距離がぐっとひらいたように感じることがあります。
- 反抗的な態度
- 会話の減少
- 無気力な様子…。
「これは思春期だから仕方ない」と片づけてしまいがちですが、
実はその背後に
- 発達障害
- グレーゾーン
- 診断のついていない「発達特性」
がかくれている場合も少なくありません。
たとえばADHD(注意欠如・多動症)の子は、
- 集中力を保つことがむずかしく
- 学業についていけない苦しさ
を日々抱えています。
またASD(自閉スペクトラム症)の傾向がある子は、
クラスの人間関係にうまくなじめず、
居場所のなさからエネルギーを失っていくことも。
どちらのタイプにも共通するのは、
「がんばっているのに空回りする疲れ」です。
診断がついていない子や「グレーゾーン」の子どもたちは、
こうしたしんどさを自分でも説明できず、
「どうせ自分はできない」と無気力な状態におちいってしまう
ことがあります。
そして何よりやっかいなのは、
見た目には
- 「ただのサボり」
- 「なまけ」
に見えること。
周囲の理解が得られないことで、さらに孤立していく悪循環が生まれます。
わたしたち大人がまずできるのは、
「この子は『だらけている』のではなく、『疲れて動けない状態かもしれない』」という視点
を持つことです。
これは甘やかしではなく、遺伝作用による発達フェーズにある発達的な困りごとを見極める専門的な目線。
実際、現場の小児科医や臨床心理士も、
「気になる子どもの『無気力』には、発達評価の視点が欠かせない」と口をそろえます。
ポイント
子どもの行動だけを見るのではなく、その「行動の背景」にある理由を探る。
それが、無気力のサインを見のがさずに支援へとつなげていく、母親としてのさいしょの一歩になるのです。
「診断がない=問題なし」ではない。グレーゾーンの子どもへの見えにくい支援の必要性
- 「病院に行っても『発達障害ではない』と言われました」
- 「検査では正常範囲。でもなんとなく育てづらいんです」
そんな声を、多くの40代母親から聞きます。
こうした子どもたちは、
「診断のつかない発達特性」=グレーゾーンとよばれる状態
にある可能性があります。
グレーゾーンの子どもたちは、
発達障害の診断基準を完全には満たさないけれど、
- 認知
- 感覚
- 行動
- 対人関係
のいずれかに
「やや強めの特徴」を持つことが多いです。
たとえば、
- 小さな音や光に過敏で、教室内で集中できない
- 読み書きが極端に苦手で、授業についていけない
- 空気を読もうとしすぎて疲れ切ってしまう
こうした「特性」は、
医師や心理士でないととらえきれないケースも多く、
家庭では「なぜうまくいかないのか」がわからず、
親子ともに苦しさを抱えつづけてしまいます。
グレーゾーンの子どもたちは、
「特別支援」という枠組みにも入りづらく
学校でも家庭でも「支援が届きにくい層」
です。
とくに中学生になると、
まわりとの差が目に見えて広がるため、
「できない自分」を責めて無気力になりやすくなります。
こうした子どもへのサポートで大切なのは、
「診断があるかどうか」ではなく
「日常生活に支障をきたしているかどうか」という視点。
実際に、
発達臨床の現場では
「グレーの時期にしっかりかかわることが、二次的な不登校や自己否定を防ぐカギになる」
と言われています。
母親としては、
「何かおかしいな」と感じた時点で立ちどまり、
その感覚を信じて「医療でも教育でもない第三の支援」を探してみる
ことが、子どもを守る選択につながります。
中学生の「無気力」はその裏にある発達障害の可能性
- 「最近、うちの子、何もやる気がなさそうで…」
- 「部活も塾も『別に』って感じで反応が薄い」
そんな「無気力」に見える中学生の様子に、不安を感じていませんか?
実はその「無気力」、
単なる思春期の反抗や怠けではなく
発達障害の特性からくる
- 「疲れ」
- 「自信の喪失」
が関係しているケースがかかわっています。
とくに、
ADHD(注意欠如・多動症)の子どもたち
は、日常の中で気づかれない苦労をたくさん抱えています。
たとえば、
- うっかりミスが多くて何度注意されても改善できない
- 気が散りやすく、授業に集中しづらい
- 思いついたらすぐ行動してしまい、トラブルになる
こんなふうに
- 周囲とのズレ
- 失敗体験
が重なると、
「どうせ自分なんて…」という気持ちが育ち、
次第に何事にも意欲を持てなくなっていくことがあるのです。
「ただやる気がない」わけじゃない
「やる気がないように見える」その影に、
実は苦手なことに毎日さらされているしんどさ
がかくれていることがあります。
たとえば、
- 勉強についていけず、自信を失っている
- 友だちとの距離感がつかめず、人間関係がうまくいかない
- 周囲から「ちゃんとしなさい」と言われつづけ、ココロが閉じてしまった
こうした積み重ねが、母親であるあなたから見た「無気力な態度」につながっているのです。
「わが子の無気力や不登校…何が正解か分からない」
そんな悩みを抱えた母親が、“安心して関われる私”を取り戻すための3週間です。
専門家と一緒に、親としてのプレッシャーを手放し、子どもとの向き合い方を再構築しませんか?
発達障害と無気力の関係、どう捉える?
わたしたちOsakaChildがこれまで支援してきた経験から言えるのは、
「発達障害=無気力になる」とは一概には言えない
ということです。
- ADHD
- ASD(自閉スペクトラム症)など
発達特性がある子の中には、好奇心旺盛でエネルギッシュな子もたくさんいます。
ポイント
ただ、環境が合わなかったり、得意を発揮できないままだと、どんな子でもしんどくなっていくのは当然です。
つまり、「無気力」に見える状態は、発達障害そのものよりも、
- 周囲とのミスマッチ
- 支援の不在
がひき起こしている可能性があるのです。
無気力なとき、親にできること
子どもの「やる気のなさ」に悩むと、
つい「どうしたらやる気を出してくれるの?」とアプローチしたくなりますよね。
でもまず大切なのは、「今、どんなことがしんどいのか」に目を向けることです。
- 「勉強がうまくいかなくて悩んでる?」
- 「学校でイヤなことあったのかな?」
そんなふうに、本人の困りごとに寄りそう言葉をかけることが、回復の第一歩になります。
そして、必要であれば専門家の力を借りるのも一つの方法です。
発達特性を知るだけで、母親とお子さまのかかわり方がおどろくほど変わってきます。
株式会社OsakaChildの不登校とADHDについての記事
子どもの「無気力」が増えているという現実
さいきん、
「うちの子、何にも興味を持てなくなってきた気がする…」
と感じるお母さん、ふえています。
実際に、
子どもたちの「無気力」が目立つようになってきたという声は、
学校や家庭の現場でも多く聞かれています。
その背景には、
発達障害の子どもたちが感じている「しんどさ」が関係していることもあるのです。
なぜ、発達障害の子どもは無気力になりやすいの?
「発達障害がある=無気力」ではありません。
けれど、そうなりやすい「要因」があることはたしかです。
わたしたちが支援をつうじて感じている、大きな2つのポイントをご紹介します。
愛情のやりとりがズレやすいから
発達障害のある子は、
どうしても「できないこと」が目立ちやすいもの。
母親も心配するあまり「なんでできないの?」としかってしまったり、
きょうだいや他の子と比べてしまったり…。
そんなくり返しの中で、
子どもは「どうせ自分なんて」と感じ、
母親も無意識に愛情を伝えづらくなっていく
ことがあります。
ポイント
この「愛情のバロメーター」が下がってしまうと、子どもは気力を失いやすくなってしまうのです。
自信を持ちにくいから
成長とともに、
子ども自身も「自分だけちょっと違うかも」と気づきはじめます。
まわりができているのに、
- 自分だけできない
- 失敗する
- 注意される
その積み重ねが、
劣等感や自己否定感になってしまうことがあります。
そうなると、がんばる気持ちさえ持てなくなってしまうことも…。
まわりには「無気力」に見えても、
実は
- 「もう傷つきたくない」
- 「また失敗したくない」
から動けないだけ、ということもあるのです。
無気力の正体は、「子どもからのサイン」
無気力は、発達障害の「直接的な結果」ではありません。
でも、
- 「できないことが多い」
- 「わかってもらえない」
- 「比べられる」など
の環境が重なることで、
発達障害のある子は無気力になりやすい状況におかれがちです。
だからこそ、大事なのは「ラベル」じゃなくて
「その子自身の今の状態」を見ること。
「どうして動けないんだろう?」と、
背景にある思いや傷つきを探っていく視点が必要です。
母親としてできる中学生の子どもの無気力への2つのかかわり方
無気力に見える子どもと向き合うとき、母親としてできることはたくさんあります。
でも、まずはこの2つを意識するだけで、ぐっと変わってくることがあります。
その子らしさごと、まるごと愛する
「なんでできないの?」じゃなくて、
「あなたのペースでいいよ」と伝えること。
苦手なことがあっても、うまくいかなくても、子どもの存在そのものに愛情を注ぐことが大切です。
子どもは、「できた自分」より、
「ありのままの自分」を受け入れてもらった経験から、
少しずつココロを開きはじめます。
ポイント
愛されているという実感が、自己肯定感を育て、気力の土台になっていきます。
小さな“できた”を見つけて、しっかり褒める
- 「人にやさしくできた」
- 「自分から声をかけられた」
- 「今日は1時間だけでもがんばれた」
ポイント
そんな小さな「がんばり」をちゃんと見て、言葉にして伝えることが、子どものココロを育てます。
できて当たり前ではなく、「できたことそのもの」が価値あるもの。
褒められる経験を積み重ねることで、
子どもは「またやってみようかな」と思えるようになります。
株式会社OsakaChildの不登校とADHDについての記事
「無気力型」の子どもってどんなタイプ?特徴と関わり方
「登校しないことに、うちの子まったく罪悪感がないみたいで…」
そんなふうに感じたこと、ありませんか?
不登校の中でも「無気力型」とよばれる子どもたちは、
明確な理由が見えにくいぶん、
母親としてとまどいやすいものです。
でも、ちゃんと特徴があるんです。
無気力型の子どもに見られる特徴
- 学校には行かないけど、特に体調不良もない
- 行事や友だちに誘われると、ふっと登校することもある
- 家では元気そう。好きなことには夢中になれる(例:ゲーム・ネット)
でも、日常生活では自分から動こうとせず、意欲がほとんど見えないこんな様子がつづいているなら、
それは「サボり」でも「甘え」でもなく、
本人もどうしていいかわからない状態なのです。
無気力な子どもに、まず必要なのは「まるごと受けとめること」
つい母親としては、
- 「なんで行かないの?」
- 「少しはがんばりなさいよ」
と言いたくなりますよね。
でもこのタイプの子には、あれこれ言うよりも、
「受け入れてくれる大人」の存在がまず必要なんです。
- 登校しない=悪いこと、という前提を一度手放す
- 「行けない自分はダメなんだ」と思わせない
- 好きなことに熱中できているなら、それも「今のその子」の大事な表現
こんなふうに、今の姿をまるごと肯定してあげることが、次の一歩につながります。
興味が芽生えたときこそ、チャンス
無気力型の子どもでも、
- 好きな行事があるとき
- 友達の誘いがあったとき
には、ふっと動き出すことがあります。
そんなときはチャンスです!
- 「この前は行けてよかったね」
- 「楽しそうだったね」
こんなふうに、行動したこと自体を肯定的にフィードバックするだけで、
子どもの「やってみよう」が少しずつ育っていきます。
家では「好き」を大事にする時間を
無気力型の子にとって、家が安心できる場所であることはとても大事。
家では「やらせる」よりも、
- 「休ませる」
- 「整える」
を意識してみてください。
好きなことに没頭できる時間
- 強制されない、安心して自分を出せる空間
- 「今日は何もできなかった」と落ち込まないための声かけ
そのうえで、少しずつ外との接点を作っていければOKです。
放っておくと長引くことも。だから「見守り」と「働きかけ」のバランスを
無気力型の子は、
体調不良があるわけではないので「とりあえず様子見で…」と長引きがち。
でも、本人の中には
- 進路への不安
- 「自分なんてどうせ…」という思い
がくすぶっていることも多いんです。
だから、ただそばにいるだけではなく、
「この先どうしていきたい?」と未来に向けた対話も必要なんです。
無気力な子どもに母親としてできること
小さな成功体験を積ませてあげる
たとえば、
- 「今日は朝ちゃんと起きられたね」
- 「久しぶりに外に出られてすごいね」
そんなほんの少しのがんばりを言葉にして認めることで、
子どもの自己肯定感は回復していきます。
新しい体験のチャンスをつくる
今まで触れたことのない世界に出会うことで、“何かをやってみたい”という芽がふっと出てくることもあります。
- 体験学習
- 趣味の講座
- ボランティア体験でもOK
大事なのは、「やってみたら案外楽しかった」という感覚を育てることです。
無気力型の子どもは、4つの“心のフェーズ”をたどる
不登校になる子どもたちの中には、
「何かがしんどい」と言いながらも、
- 理由をはっきり言えなかったり
- 家では普通に過ごしていたりする
タイプがいます。
それが「無気力型」の特徴です。
そしてこのタイプの子どもは、時間の経過とともにココロの状態が変化していきます。
あせらず、その子なりのリズムで回復に向かっていけるよう、4つのフェーズに分けて理解しておきましょう。
フェーズ①|前駆期(なんとなく行きたくない…の始まり)
どんな時期?
- 「学校、だるい」
- 「なんか行きたくない」など
口には出すけれど、はっきりした理由がない時期。
先生や友達のことを話題にしながらも、
ゲームやYouTubeには夢中で
家では比較的元気に過ごしている
ことが多いです。
親ができること
- 「何が嫌なの?」と問いつめず、子どもの言葉に共感するだけでOK
- ゲームやテレビを完全に取りあげるのではなく、安心できる時間として見守る
- ときどき友達や先生とのポジティブな話題を投げて、小さな刺激のきっかけに
「まだ大丈夫そう」に見えるけれど、この時期こそ関係性を深めるチャンスです。
株式会社OsakaChildの無気力と不登校についての記事
親子関係を“いま”から変えられる3週間
「うちの子も、これに当てはまる…」
そう思った今が、親としての“選び直し”のタイミングです。
発達障害・グレーゾーン・診断がつかないけれど気になる状態──
その子どもたちは、“わざと”ではなく、内側で葛藤し続けています。
この3週間で親ができることは、「責めない」「焦らせない」関わり方を整えること。
ほんの少しの工夫で、子どもが安心して立ち直る土台ができます。
✅ 現在【銀行振込限定で割引+3大特典】をご案内中
🔸 本日 1月24日(土)23:59まで のご入金分まで
🔸 『あと2名様限定』
───
さらに、「子どもと向き合えるようになった今こそ」
自分自身の人生も整え直したいと感じる方へ──
50万円のライフリスタート個別サポートもご用意しています(※受講者限定)
フェーズ②|進行期(本格的なひきこもり状態)
どんな時期?
「もう学校行かない」と自分から口にするようになったり、昼夜逆転して、ほぼ一日中スマホやネット漬けになることも。
表情も沈みがちで、家族との会話も減り、学校の話題を極端に嫌がるようになります。
親ができること
- 登校刺激はさける。「行った方がいい」などの声かけは逆効果
- かわりに、子どもの興味に寄りそった話題で、「普通の会話」を少しずつ取りもどす
- 出席日数や進級条件などは、親が先生と連携して情報を整理しておく(子どもに無理に伝えなくてOK)
進行期の「やってはいけないこと」
- 「自分の人生なんだから、ちゃんとしなさい」と突き放す言葉
- 「なまけてるだけでしょ?」と決めつける態度
こうした言葉は、子どもの心をさらに閉ざしてしまうことがあります。
ポイント
この時期は、「今の状態でいいよ」と、まずは認めてあげることがなにより大切です。
少しずつ外の世界とつながる準備を
- 無理に外出させようとせず、「ちょっといっしょに買い物行く?」くらいの声かけから
- 興味があるイベントや体験があれば、「見てみるだけでもいいよ」と提案
家族の中に「味方がいる」という感覚を育てることで、子どもが次のステップへ進みやすくなります
フェーズ③|混乱期(ちょっと気になってくる…けどまだ怖い)
どんな時期?
急に「出席日数ってどうなってるの?」と学校のことを聞いてきたり、
「もう高校行けないのかな…」とつぶやいたりする
ことが増えてきます。
ポイント
表面的にはまだ不安定ですが、意識が少しずつ外に向きはじめているサインです。
フェーズ④|回復期(自分から一歩を踏み出す時)
どんな時期?
家庭内での会話が自然にふえ、
外出や社会活動にも少しずつ関心がもどってきます。
- 「そろそろ〇〇やってみようかな」
- 「高校どうしようかな」
と、未来のことを自分の口から語り出す時期です。
母親ができること
- できたことを認めて、しっかりほめる(小さなことでも大歓迎!)
- 興味や進路につながりそうな情報を、押しつけず、そっと提案してみる
- 引き続き、「味方でいるよ」という姿勢をキープ
無気力の子どものフェーズ|混乱期
少し前までは一日中部屋にこもっていたのに、
最近、
- 「高校って出席日数どれくらい必要なん?」
- 「通信制高校ってどんな感じ?」
…そんなことをポロッと聞いてくる。
それが、「混乱期」のサインです。
混乱期の子どもに見られる変化
- 母親との会話がぽつぽつもどってくる
- 学校の話題を自分から出すようになる
- 「バイトしてみたい」「一人暮らししてみたい」など、将来に関心が向きはじめる
- ネットで転校・編入や進学、就職の情報をこっそり調べている
まだ本格的に動く気持ちにはなれないけれど、
ココロの中では「何か変えたい」と思いはじめている時期なんです。
母親ができること
- 子どもの口から出てきた話題に否定せず寄り添うこと(たとえ内容が極端でもOK)
- 「こうすれば学校に行けるよ」などの“取引き”は避けて、一緒に考えていくスタンスで
- 先生との連携も大切。「まだ間に合うよ」という声を、信頼できる大人から届けてもらう
- 進級が難しい場合も、「じゃあどうする?」を一緒に調べる気持ちで、見学や資料請求も親子で動く
「やる気が出てきた!」と思っても焦らないで
この時期は、
良くなったり落ち込んだりをくり返します。
母親が先まわりしすぎると、子どもは逆に引いてしまうことも。
ポイント
だからこそ大事なのは、「いっしょに動くよ」という姿勢を見せること。
子どもにとって、ひとりじゃないという実感は、次のステップをふむ力になります。
無気力の子どものフェーズ|回復期
そしてある日、子どもがこんなふうに言いはじめます。
- 「そろそろ、あの先生に会ってみてもいいかも」
- 「別室登校なら行けるかも」
これは、いよいよ「回復期」のはじまりです。
回復期の子どもに見られる変化
- 興味のあることに取り組もうとする姿勢が出てくる
- 「進路どうしようか」「将来は〇〇したい」と自分の言葉で語る
- 家族との会話も深まり、自分の意見を素直に出せるようになる
- 保健室・別室登校や、放課後の先生訪問など、「ちょっと行ってみよう」という動きが出てくる
親ができること
- 「じゃあ、いつ行く?」「それいいね」と子どもの言葉を前向きに受けとめる
- 興味や好きなことを応援し、その子の「やってみたい」を伸ばすかかわりを意識
- 先生との連携を取りながら、無理のない登校スタイル(別室・短時間など)をいっしょに考える
- 勉強や課題への取りくみは、「やれるところから」でOK。カンペキを求めないことが大切
回復期は「再出発」の時期
気持ちが前に向きはじめたこのタイミングこそ、母親のサポートが子どもの自信に変わっていきます。
大切なのは、
- 「もう大丈夫だね」と手を放すのではなく、
- 「いつでも戻ってきていいよ」と寄りそいながら見守る姿勢を持ちつづけること。
株式会社OsakaChildの不登校の回復期についての記事
不登校の回復期に起きやすい逆戻りをシンプルに防ぐ!5つのサインと対策と対応
-

-
参考不登校の回復期に起きやすい逆戻りをシンプルに防ぐ!5つのサインと対策と対応
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 不登校は子どもや家族にとって大きな悩みの一つです。学校への行かない理由や心の中の葛藤 ...
続きを見る
不登校の回復期に陥る昼夜逆転を克服|40代母親ができるその主な原因と解決のコツ
-

-
参考【40代母親対象】 不登校の回復期に陥る昼夜逆転を 最適な接し方でカンタン克服 【精神科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 40代母親であるお子さまが不登校になると、復学までの時間的フェーズにお子さまの状態に ...
続きを見る
発達障害・発達グレーゾーン・診断はついていないが母親からみて発達障害ではないかと反応ある中学生の無気力事例紹介
事例①|「なまけてるだけでしょ」と言われ続けた息子に、診断のつかない「しんどさ」があった
中学2年の息子は、これまで一度も「発達障害」と診断されたことはありませんでした。
けれども、わたしはずっと「この子はどこかみんなとちがう」と感じていました。
たとえば、先生の話を聞いているふうでも、
- 内容がまったく頭に入っていなかったり
- 提出物を何度言っても出せなかったり。
通知表には
- 「集中力に課題がある」
- 「努力すればできる」
といったコメントがならびました。
でもわたしは、息子が「努力していない」とは思えませんでした。
本人も「がんばってるのに、できない」とポツリともらすことが何度もあって、そのたびにわたしの胸が痛みました。
3年生になる前の冬、息子はとうとう学校に行けなくなりました。
朝起こしても布団から出られず、スマホを触るだけで1日が終わる日々。
夫は「なまけ癖がついたんだろ」と冷たく言い、わたしもさいしょは「このままじゃ進学できない」とあせる気持ちばかりが先に立ちました。
でも、ある日、ふと気づいたんです。
息子は、遊びにも出かけず、友達とも連絡を取らず、本当に「元気がない」というより「エネルギーが枯れている」ように見えたんです。
もしかしたらこれは、ただのなまけじゃないかもしれない――。
そう思って調べているときに、
- 「発達グレーゾーン」
- 「診断のつかない発達特性」
という言葉に出会いました。
それはまさに、息子の状態そのものでした。
「だれにも理解されないまま、ずっとひとりでがんばって、疲れ果てていたのかもしれない」
そう思ったとき、わたしの中で何かが変わりはじめました。
3週間プログラムで、「何もできない日」すら意味があると思えるようになった
Osaka-Childの3週間プログラムを知ったのは、検索していて偶然出てきた記事がきっかけでした。
「診断がつかなくても、子どものしんどさは確かに存在する」
という言葉に、ココロをつかまれました。
すぐに面談を申し込み、わたしは「母親としてできること」をゼロから見直すつもりで3週間のサポートを受けました。
さいしょにおどろいたのは、「子どもをどう変えるか」ではなく、
「母親がどんなかかわりをしてきたか」をいっしょに振りかえるところからはじまったこと。
わたしは、良かれと思っていた声かけが、息子には「責められている」ように感じられていたことを知り、胸が締めつけられました。
プログラムの中で、
毎日LINEで息子の様子を報告したり、
自分の感情をていねいに書き出したりするうちに、
少しずつわたし自身のあせりやイライラが薄れていきました。
息子が布団から出られなかった日でも、
「今日は気温が下がってたし、休息も必要だよね」
と自然に思えるようになったんです。
すると、ある朝息子のほうから「今日は昼から先生と話してみようかな」と言ってきました。
わたしは泣きそうになりながら、「いいね、付き合うよ」と答えました。
親が変わると、子どもは少しずつ反応してくれます。
プログラムをつうじて私たちは、「ちゃんと進んでるよね」と思える関係を築けるようになりました。
ポイント
今も不安がゼロになったわけじゃないけれど、息子の中に小さな火が灯ったこと、
それを信じて待てる自分になれたことが、何より大きな変化です。
事例②|ASDグレーと診断された娘。「ちゃんとして」と言われ続けた日々が、自信を奪っていた
中学1年の娘は、小さいころから「おとなしいけど繊細な子」でした。
集団行動は嫌がるけど、勉強は真面目にコツコツタイプ。
母親としても「手のかからない子」という認識でした。
けれど、中学生になった娘は次第に学校での出来事を話さなくなり、表情が曇ることが増えていきました。
宿題を忘れる、ノートを取らない、グループワークを拒む。
先生からは「ちゃんと周囲と協調しないと」と言われるようになり、わたしも「もう中学生なんだから」としかるように。
そして、秋ごろ。
ある日突然、「もう学校には行かない」と布団にもぐりこみ、
娘は何日も起きてこなくなりました。
食事も最低限、スマホもほとんど触らず、
まるで「感情のスイッチ」が切れてしまったような状態。
不安になり、小児精神科に相談すると、
「ASD(自閉スペクトラム症)の傾向があるグレーゾーンです」
と告げられました。
とくに
社会的な場面での情報処理が難しく
集団の中で過剰に気を使い
疲弊していた可能性が高いとのこと。
私はショックでした。
「あの子はちゃんとしてた」と思っていたけれど、実は「ちゃんとしなきゃ」と無理をつづけていた。
「母親のわたしが、気づいてあげられなかった」――その後悔でいっぱいになりました。
娘の「今はまだ無理」という言葉を、責めずに受けとめられるようになった
Osaka-Childの3週間プログラムに申し込んだのは、母親であるわたし自身の気持ちの整理が必要だと感じたからです。
初回のZoom面談では、娘の話をするつもりが、
いつの間にか「どうしてこんなことになったんだろう」と涙が止まらなくなってしまいました。
でもカウンセラーの方は
「お母さんも、精いっぱいがんばってきたんですね」と、まず私の気持ちを受けとめてくれました。
プログラムでは、「行動を変える」のではなく、「視点を変える」練習をしました。
- 「できないこと」ではなく「さけている背景」を想像する。
- 「休んでいる娘」にも意味があると考える。
このアプローチをつうじて、わたしはようやく
「娘の無気力」を「回復へのサイン」と受けとめられるようになりました。
ある日、娘が私に「学校のホームページだけ見てもいい?」と言ってきました。
それは、ほんの小さな一歩。でも、わたしにとっては希望でした。
その後、放課後に学校の先生と面談を設定し、
娘自身の言葉で「今はまだ無理だけど、行けるようになったらもどりたい」と話してくれたんです。
プログラムを受けたことで、
私は「がんばらせる親」から「今の状態をいっしょに大切にできる親」へと変わりました。
子どもは「今の自分でもいいんだ」と感じられて初めて、前を向く力を取りもどせる。
今の私たちは、まだ完全な復帰ではないけれど、関係性が大きく変わったという実感があります。
親子関係を“いま”から変えられる3週間
「うちの子も、これに当てはまる…」
そう思った今が、親としての“選び直し”のタイミングです。
発達障害・グレーゾーン・診断がつかないけれど気になる状態──
その子どもたちは、“わざと”ではなく、内側で葛藤し続けています。
この3週間で親ができることは、「責めない」「焦らせない」関わり方を整えること。
ほんの少しの工夫で、子どもが安心して立ち直る土台ができます。
✅ 現在【銀行振込限定で割引+3大特典】をご案内中
🔸 本日 1月24日(土)23:59まで のご入金分まで
🔸 『あと2名様限定』
───
さらに、「子どもと向き合えるようになった今こそ」
自分自身の人生も整え直したいと感じる方へ──
50万円のライフリスタート個別サポートもご用意しています(※受講者限定)
事例③|ADHDと診断された息子。「元気なのにやる気がない」その誤解が、関係をすれ違わせていた
中学1年生の息子は、幼少期にADHD(注意欠如・多動症)と診断されていました。
小学生のころから
- とにかく落ち着きがなく
- 忘れ物が多くて
- 宿題もやりっぱなし
けれど本人は天真爛漫で、「明るくて元気な子」として育ってきました。
中学に入り、思春期の影響もあってか、
- 「勉強なんて無駄」
- 「どうせ怒られるだけ」
とつぶやくようになり、次第に部活も休みがちに。
家ではゲームやYouTubeに夢中で、口を開けば「ダルい」「うるさい」と反抗的な言葉ばかり。
わたしもつい、「元気なんだから、やる気の問題でしょ」と言ってしまい、ぶつかる毎日でした。
でもある日、学校から
- 「授業中に何度も立ち歩く」
- 「注意しても聞き流している」
と連絡があり、息子が教室で孤立していることを知りました。
それまでの「元気なキャラ」は、
どうやら本人なりの「しんどさをかくす演技」だったのしれないと気づいてきたのです。
実は彼は、
- 「やりたいけど集中できない」
- 「わかってるのに止まらない」
という自分自身へのイライラを抱えていたのです。
わたしは、息子を「なまけている」と決めつけていたことに気づき、ココロから申し訳なくなりました。
「このままでは、あの子は『困っている子』ではなく、『問題児』になってしまう」
そう思ったとき、わたしは本気でかかわり方を変えなければと思いました。
母親が「変わろう」としたとき、息子の目に少しずつ力がもどってきた
そんなとき出会ったのが、Osaka-Childの3週間集中プログラムでした。
ADHDについての知識はあるつもりだったけれど、
- 「知っている」
- 「寄りそえる」
はまったく別物でした。
プログラムの中では、
息子の
- 「衝動性」
- 「不注意」
の背景を整理しながら、
わたし自身の対応をいっしょに見直していきました。
- 「指示は短く一つだけ」
- 「先回りしすぎず、選ばせる」
- 「感情的になりそうなときは3秒待つ」
一見当たり前のようで、
でも日常ではできていなかった「かかわり方の工夫」を、毎日のLINEサポートで少しずつ実践していきました。
何より効果があったのは、「ちゃんと見てるよ」と伝えること。
- 息子が自分から歯を磨いた
- 5分だけでもプリントを開いた
そんな小さな行動に
「やるね」
「気づいてたよ」
と声をかけると、彼はてれながらもうれしそうな表情を見せるようになったんです。
3週間の終わりころ、息子が突然、
「来週の社会見学、行ってみようかな」とつぶやきました。
学校から離れていくばかりだった彼が、
自分から「行ってみよう」と思えたことが何よりうれしかった。
子どもを変えるのではなく、「母親としての見方」を変えること。
それが、発達障害を抱える息子にとって最大の支援だったと、今は実感しています。
今でも凸凹はありますが、以前のようにぶつかることは減り、笑い合える時間が少しずつもどってきています。
まとめ|発達障害かもしれない中学生の「無気力」に悩んだ母親が、わが子と希望を見つけるまで
「わが子の無気力や不登校…何が正解か分からない」
そんな悩みを抱えた母親が、“安心して関われる私”を取り戻すための3週間です。
専門家と一緒に、親としてのプレッシャーを手放し、子どもとの向き合い方を再構築しませんか?
ネットバンキングのご利用で、今すぐ開始することが可能です。
「さいきん、うちの子がやる気なくて…」
そんなひと言からはじまったわたしの悩みは、思ったよりも根が深くて、想像よりもずっと複雑でした。
朝起きない。何を言ってもひびかない。好きだったはずのことにすら反応がない。
一番つらかったのは、何をしても届かないような気がして、自分が「ダメな母親」のように感じてしまったこと。
でも、この記事をとおして知ったのは、子どもの「無気力」には理由があるってこと。
それは「サボり」じゃなくて、もしかしたら発達障害という背景が関係しているのです。
そして、そのことに早く気づいて、適切なかかわり方ができれば、子どもは少しずつ元気を取りもどしていけるってこと。
正直、すぐには変わらないと思います。
でも、「どうして動けないの?」と責めるより、「どうしたらいっしょに前にすすめるかな?」と考えられるだけで、関係は変わりはじめる。
そうやって、小さなすれ違いをひとつずつ、親子で乗りこえていけたら。
無気力に見える日々の中にも、ほんの少しの希望の種はちゃんとあるんだと、今なら思えます。
それでも、どうしても一人じゃ抱えきれないときは、「株式会社Osaka-Child」のカウンセリングがあります。
ここでは、発達障害や発達グレーゾーンの中学生と向き合う母親たちの気持ちをわかってくれる専門家が、そっと伴走してくれます。
「相談してもいいのかな?」そんな不安さえ受けとめてくれる、あたたかい場所です。
母親だって、迷っていい。泣いてもいい。止まったって、また歩き出せばいい。
子どもの未来は、まだ何も決まっていないからこそ、今のこの一歩が、きっと大きな力になるはずです。
あなたとあなたのお子さんが、少しでも軽やかな明日をむかえられますように。
その願いをこめて、ここまで読んでくださったあなたに、そっとエールを送ります。
母子の関係を整える“最初の3週間”
📩 ご案内枠の最新状況
✅ 今だけ【銀行振込の方限定で割引+3大特典付き】でご案内中です
🔸 本日 1月24日(土)23:59まで のご入金分まで
🔸 『あと2名様限定』
※銀行振込限定・先着順での受付となります
---
このプログラムは、「中学生の無気力・発達傾向」に揺れる今、
母親が“軸”を取り戻し、子どもとの信頼関係を整えるための3週間です。
🎁 特典PDF(即日お届け)
✅「母親の感情整理チェックリスト」
✅「学校・医療機関への伝え方テンプレ」
✅「無気力対応・やってはいけない5つの行動」
---
焦って行動するのではなく、
今こそ「自分を整える」決断を。
その一歩が、子どもに安心を届け、家庭の空気を変えていきます。
───
そして、子どもとの関係を整えた“その先”へ──
「これからの人生を、もう一度選び直したい」方には、
【受講者限定】のライフリスタートサポート(50万円)もご案内しています。
▶︎ 株式会社Osaka-Childの母親・子ども支援まとめを見る(心理・不登校・身体調整など・左の▼をクリック)
株式会社Osaka-Childの3人の子育てでストレスがたかい40代女性の心理作用をととのえるカウンセリング
子育ての真っ最中で、仕事と家庭の間で揺れ動いている女性の皆さんへ。私たちのカウンセリングサービスは、あなたのためにあります。もし心の中で悩みや生きづらさを感じている場合、それは特別な心のケアが必要な証拠です。株式会社Osaka-Childとして、日々の生活で直面している困難を理解し、その解決をサポートします。
私たちは、あなたが人生の困難に立ち向かう勇気を見つけるための安全な空間を提供します。当社のプロフェッショナルなカウンセラーは、あなたの問題や感情に深い理解を持ち、あなたを尊重します。ここでは、あなたの気持ちを自由に表現し、過去の影響から解放され、自分自身を再発見することができるでしょう。
カウンセリングは、心理システムの問題を共に解決するための有力な手段です。私たちのカウンセリングでは、まずじっくりとあなたのお話を聴きます。過去の経験やトラウマ、日常生活でのストレスなど、あなたが抱える悩みや心の中での葛藤を理解し、共感します。その後、適切なカウンセリング技法を用いて、心の中のブロックを取り除き、自分自身と向き合い、成長するためのサポートを行います。
初めての方でも、私たちのサービスを利用することはとても簡単です。当社のウェブサイト上で、カウンセリングセッションの申し込みをすることができます。また、具体的な問い合わせや不明点がある場合は、お気軽に当社までメールをお送りください。
心の中で抱える悩みや生きづらさに苦しんでいるなら、あなたは一人ではありません。株式会社Osaka-Childは、あなたが自分自身の価値を見つけ、生活の質を改善するためのサポートを提供します。カウンセリングを通じて、あなたがより健康的で充実した人生を歩む手助けをいたします。
カウンセリングのプロセスは、あなたの個別のニーズや目標に合わせてカスタマイズされます。私たちは、あなたが心地よく感じるペースでサポートを提供し、尊重と信頼の関係を築くことを大切にしています。カウンセリングを通じて、自己理解を深め、心の中の問題を克服し、より充実した人生を築いていきましょう。
あなたが心の支えを必要としているなら、ぜひ株式会社Osaka-Childのカウンセリングにお越しください。私たちがあなたの側にいて、共に問題を解決し、より健康で幸せな未来を築くお手伝いをいたします。一歩踏み出す勇気を持ってください。私たちと一緒に、新しい人生の扉を開いてみましょう。
\本気で変わりたい40代母親へ/
子どもとの関係、自分の人生、どちらもあきらめない方法があります。
33万円・50万円の本格プログラムで、臨床心理士とマンツーマンであなたの「再スタート」をサポートします。
現在【銀行振込の方限定で割引案内】をご用意しています。
🔸 本日 1月24日(土)23:59まで のご入金分までのご案内となります。
🔸 『あと2名様限定』
※銀行振込限定・先着順での受付となります。
小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援事業をする株式会社Osaka-Childとは?




【 復学率100% 】小中学生復学支援Osaka-Childの支援策とは?
こちらもCHECK
-

-
【 復学率100% 】小中学生復学支援Osaka-Childの支援策とは?
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
【堺市】不登校の子どもをサポートする!Osaka-Childのカウンセリング支援
こちらもCHECK
-

-
【堺市】不登校の子どもをサポートする!Osaka-Childのカウンセリング支援
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 Osaka-Childは、堺市にある不登校の子どもたちとその家族を支援するカウンセリ ...
続きを見る
復学支援の専門家が教える、家庭学習支援のポイントと効果的な学習方法
株式会社Osaka-Childの心理技法・心理検査一覧
株式会社Osaka-Childの障害一覧
株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:母親のメンタルサポート


支援内容
1. オキシトシン分泌促進で子どもに接する母親の専門的なカウンセリング
2. 胎児期から乳児期のオキシトシン分泌状態の再経験
3. 母親の子育ての疲れやストレスの軽減
4. 母親の胎児期・幼少期の体験のインナーチャイルドの修正
5. 母親の親子関係をカウンセリングにより気づかせる
6. カウンセリングによって母親の生き方を主体性を持たせる
7. 幼少期に得られなかった愛着の再構築
8. 個人に合った最適な心理システムの再起動
9. 母親を子どもの親から一個人としての存在の獲得
10. 愛着育成による自己肯定感の向上
11. 人生軸上でインストールした感覚ー認識の空洞化
母親のメンタルサポートの具体的なアプローチ
株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、母親のメンタルサポートを提供しています。以下に、具体的な支援内容を説明します。
- オキシトシン分泌促進で子どもに接する母親の専門的なカウンセリング オキシトシンは愛着や絆の形成に関与するホルモンであり、母親と子どもの関係を深める重要な役割を果たします。カウンセリングにおいては、母親がオキシトシン分泌を促進する方法や子どもとの関わり方について学びます。
- 胎児期から乳児期のオキシトシン分泌状態の再経験 母親が胎児期から乳児期の自身のオキシトシン分泌状態を再経験することで、子どもとの関係性や愛着形成に関する理解を深めます。これにより、母親はより適切な愛着行動を身につけ、子どもの安定した成長を支援します。
- 母親の子育ての疲れやストレスの軽減 子育てにおける疲れやストレスは母親のメンタルヘルスに大きな影響を与えます。専門的なカウンセリングにより、母親の疲れやストレスを軽減し、心の健康を保つための具体的なケア方法を提供します。
- 母親の胎児期・幼少期の体験のインナーチャイルドの修正 母親の胎児期や幼少期におけるトラウマや負の体験は、子育てに影響を及ぼすことがあります。カウンセリングにより、母親は自身のインナーチャイルド(内なる子どもの存在)の修正を通じて、子育てにおける負のパターンを変容させます。
- 母親の親子関係をカウンセリングにより気づかせる 母親の親子関係に潜むパターンや影響をカウンセリングを通じて明示し、母親自身がその関係性に気づくことを支援します。これにより、母親はより良好な親子関係を構築し、子どもの成長を促進します。
- カウンセリングによって母親の生き方を主体性を持たせる 母親が自身の生き方を主体的に選択し、子どもとの関係性をより意識的に築いていくことを支援します。母親の個別のニーズや目標を考慮し、適切なカウンセリングプランを策定します。
- 幼少期に得られなかった愛着の再構築 母親が幼少期に得られなかった愛着を再構築することで、自己肯定感や安心感を向上させます。カウンセリングにおいては、母親が自身の愛着スタイルや関わり方を理解し、健全な愛着関係の構築に向けた具体的なアプローチを身につけます。
- 個人に合った最適な心理システムの再起動 母親の心理システムの再起動により、ストレスへの対処能力や情緒調整能力を向上させます。カウンセリングにより、母親は自身の心理的な困難や制約を克服し、より健康的な心の状態を取り戻すことができます。
- 母親を子どもの親から一個人としての存在として認識 母親が自身を単に子どもの親としてではなく、個別の存在として認識することを支援します。母親の自己アイデンティティや自己実現の重要性を再確認し、自己成長とバランスの取れた生活を促進します。
- 愛着育成による自己肯定感の向上 母親が子どもとの愛着関係を育むことで、自己肯定感や自己価値感を向上させます。カウンセリングにおいては、母親が愛着行動やコミュニケーションスキルを向上させるための具体的な手法やアドバイスを受け取ります。
- 人生軸上でインストールした感覚ー認識の空洞化 母親が人生軸上で自身の感覚や認識を見つめ直し、新たな視点や意味づけを行うことを支援します。これにより、母親はよりポジティブな心理状態を持ち、子どもとの関係や子育てにおいてより健全な選択を行うことができます。
具体的な支援内容として、母親は定期的なカウンセリングセッションを通じて自身のメンタルヘルスや子育てに関する課題を共有し、カウンセラーとの対話やアドバイスを受け取ります。また、母親には日常生活におけるストレス管理や自己ケアの方法、感情の調整やコミュニケーションスキルの向上など、実践的なツールや戦略が提供されます。
大阪の不登校カウンセリング|40代の母親が必知!子供の不登校を解決する支援方法と専門家のアドバイス
こちらもCHECK
-

-
大阪の不登校カウンセリング|40代の母親が必知!子供の不登校を解決する支援方法と専門家のアドバイス
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 子供の不登校は多くの40代の母親にとって深刻な悩みです。その解決には適切な支援方法と ...
続きを見る
【40代母親からの第一歩】不登校問題解決への道と専門カウンセリングでの導き
こちらもCHECK
-

-
【40代母親からの第一歩】不登校問題解決への道と専門カウンセリングでの導き
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 40代の母親が抱える不登校問題は深刻な課題です。子どもの不登校により家庭や学校の関係 ...
続きを見る
【幸せホルモン】オキシトシンの増やし方12選|瞑想やマインドセット・身体調整が効果的
不登校の原因を知る方法!40代の母親が的確にサポートする方法とは?
中学生の不登校の原因は母親にあった!母親へのカウンセリングで復学につなげる
【40代子育ての悩み】不登校の原因を解明!不登校になる子の親の特徴と改善策
株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どものカウンセリング


支援内容
1. 不登校の子どもが抱えるココロの動きの促進
2. 幼少期の負の体験の心理システムの循環
3. 親子関係による負の自己イメージの軌道修正
4. 学校環境での存在価値の促進
5. 過去ー現在ー未来の時間軸の自然循環
6. 幼少期に遺伝的にもっているエネルギーの再生成
7. 学校環境で経験した負の要素への関わり
8. 学校環境で作られた他者との競争原理の滅尽
9. 母親では得られなかった愛着をカウンセラーとの共有で再獲得
10. 幼少期のゼロベースでの人間像への気づき
11. 負の心理システムで構成された世界観の抑制
不登校の子どものカウンセリングの具体的なアプローチ
- 不登校の子どもが抱えるココロの動きの促進 不登校の子どもは心理的な負担を抱えている場合があります。私たちは、子どものココロの動きを理解し、彼らが抱える不安やストレスを軽減するための支援を行います。具体的な方法としては、感情の表現や認識のトレーニング、リラクゼーション技法の導入などがあります。また、子どもが自己理解を深め、自己肯定感を高めるために、自己探索のプロセスにも取り組みます。
- 幼少期の負の体験の心理システムの循環 幼少期に経験した負の出来事やトラウマは、不登校の原因となることがあります。私たちは、そのような負の体験が心理システムにどのように影響を与え、循環するのかを理解し、子どもと共にその解決に向けた取り組みを行います。具体的には、トラウマ解消のための技法や自己発見のプロセスを通じて、過去の負の経験に対処し、新たな自己概念を構築するサポートを行います。
- 親子関係による負の自己イメージの軌道修正 親子関係は子どもの自己イメージに大きな影響を与えます。不登校の子どもにおいては、負の自己イメージが形成されることがあります。私たちは、子どもと親の関係を理解し、親子のコミュニケーションの改善や共感的な対話を通じて、子どもの自己イメージの軌道修正を支援します。親には、子どもの感情や困難に対して理解を示し、受け入れる姿勢を促すためのアドバイスや指導を提供します。
- 学校環境での存在価値の促進 不登校の子どもは学校環境での存在価値や自己肯定感に欠けていることがあります。私たちは、子どもが学校での存在感を取り戻すための支援を行います。具体的には、学校との連携や学校内でのサポート体制の構築を行い、子どもが自分の能力や才能を発揮できる場を提供します。また、学校生活の中での達成感や成功体験を通じて、子どもの自信を育む取り組みも行います。
- 過去ー現在ー未来の時間軸の自然循環 不登校の子どもは、過去の困難や現在の問題に囚われる傾向があります。私たちは、子どもが過去、現在、未来の時間軸を自然に循環できるように支援します。過去の出来事への執着や現在の問題に対する固執を解放し、未来に向けて前向きに取り組むことを促します。具体的な方法としては、目標設定や将来のビジョンの明確化、行動計画の策定などがあります。
- 幼少期に遺伝的に持っているエネルギーの再生成 子どもの行動や感情は、幼少期に遺伝的に受け継がれたエネルギーによって影響を受けることがあります。私たちは、子どもが遺伝的に持っているエネルギーを再生成し、ポジティブな方向へと導くための支援を行います。具体的には、子どもが自己観察や自己理解を深めるプロセスを通じて、自己変容を促すことに焦点を当てます。
- 学校環境で経験した負の要素への関わり 不登校の子どもは、学校環境での負の要素に対して適切に関わることができない場合があります。私たちは、子どもが学校環境での負の要素に対して適切に対処できるように支援します。具体的には、コミュニケーションスキルのトレーニングや問題解決能力の向上を促すプログラムを提供し、子どもが対処方法を見つけられるようにサポートします。
- 学校環境で作られた他者との競争原理の滅尽 学校環境では競争原理が存在し、不登校の子どもにとっては負の影響を与えることがあります。私たちは、他者との競争原理を滅尽し、協力や共感の文化を醸成する支援を行います。具体的には、協調性やチームワークの重要性を学ぶ活動や、他者との比較ではなく自己の成長に焦点を当てる指導を行います。
- 母親では得られなかった愛着をカウンセラーとの共有で再獲得 不登校の子どもの中には、母親からの愛着が不足している場合があります。私たちは、子どもがカウンセラーとの関係を通じて、得られなかった愛着を再獲得できるように支援します。子どもが安心感や信頼感を育み、自己価値感や自己受容感を高めるために、カウンセラーとの関係性を重視したアプローチを取ります。
- 幼少期のゼロベースでの人間像への気づき 不登校の子どもには、幼少期に根付いた人間像や自己イメージに問題がある場合があります。私たちは、子どもが自己観察や内省を通じて、幼少期のゼロベースから新たな人間像への気づきを促す支援を行います。具体的には、自己評価の見直しやポジティブな特性の発見、適応的な思考や行動パターンの構築をサポートします。
- 負の心理システムで構成された世界観の抑制 不登校の子どもは、負の心理システムで構成された世界観を持っていることがあります。私たちは、子どもがそのような負の世界観から抜け出し、ポジティブな視点や心理的な柔軟性を取り戻すための支援を行います。
具体的には、認知行動療法やポジティブ心理学の手法を用いて、子どもの思考や信念の再構築を促し、より健康的な心理システムを構築します。 株式会社Osaka-Childの臨床心理士(カウンセラー・セラピスト・不登校専門カウンセラー)として、私たちは不登校の子どもとその家族に対して、個別に適した支援を提供します。子どもの心の健康を重視し、不登校の原因や状況を的確に把握した上で、専門知識や経験に基づいたアプローチを用いてサポートを行います。私たちの目標は、子どもが健やかな学校生活を送り、自己成長や社会参加の機会を最大限に引き出すことです。
不登校カウンセリングでHSCの子どもを復学支援に|HSCの子どもを持つ40代の母親に向けて
こちらもCHECK
株式会社Osaka-Childのカウンセリング技法
カウンセリングとは?心理システムを正常化して生きづらさを克服する効果最大
-

-
参考カウンセリングとは?心理システムを正常化して生きづらさを克服する効果最大
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
来談者中心療法で心理システムを自然状態にして精神的苦しみを克服|40代女性の生きづらさ克服
-

-
参考来談者中心療法で心理システムを自然状態にして精神的苦しみを克服|40代女性の生きづらさ克服
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
トラウマインフォームドケアをカウンセリングで心理システムの最短正常化に
-

-
参考トラウマインフォームドケアをカウンセリングで心理システムの最短正常化に
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
オンラインカウンセリングのメリット・デメリットを知って手軽に心理システムを正常化する
-

-
参考オンラインカウンセリングのメリット・デメリットを知って手軽に心理システムを正常化する
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
精神分析的心理療法でカウンセリングを実施し心理システムの正常化で生きづらさ克服
株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの身体調整


支援内容
1. 子どもの姿勢コントロールの修正
2. 姿勢コントロールによる身体アライメント構築
3. 姿勢コントロールから重心作り
4. 学習に不可欠な座り姿勢での姿勢コントロールの促通
5. 姿勢に伴う手の運動構成のバランス
6. 姿勢と視覚・聴覚情報の同期
7. 全身の関節運動・筋肉の出力調整
8. 三半規管や脳神経系の出力の修正
9. ハンドリングによる触覚刺激で感覚系のコントロール
10. 皮ふ刺激によるオキシトシン分泌の促進
11. 皮ふ・筋膜・筋肉・筋肉の長さのセンサーのコントロール
12. 感覚ー認識システム促通から無の状態へのアップデート
13. 身体への関わりによる不足した愛着の向上
14. 負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化
15. 負の心理システムから身体への過剰な意識への抑制
不登校の子どもの身体調整の具体的なアプローチ
株式会社Osaka-Childでは、不登校の小中学高校生や発達障害の子どもの復学支援の一環として、身体調整の支援を行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。
- 子どもの姿勢コントロールの修正 子どもの姿勢は、身体の調整や感覚統合に重要な役割を果たします。不適切な姿勢が存在する場合、学習や集中力に悪影響を与えることがあります。私たちは、子どもの姿勢を正しい形に修正し、適切な姿勢コントロールをサポートします。具体的には、姿勢の矯正や筋力トレーニング、姿勢保持のためのエルゴノミクス指導などを行います。
- 姿勢コントロールによる身体アライメント構築 姿勢の改善は、身体のアライメントやバランスの向上につながります。私たちは、子どもの身体アライメントを構築するために、姿勢コントロールのトレーニングを行います。これには、正しい姿勢の保持や身体の軸の調整、バランス感覚の向上などが含まれます。
- 姿勢コントロールから重心作り 姿勢と重心の関係は、身体の安定性や運動の質に大きな影響を与えます。私たちは、姿勢コントロールから重心の形成に焦点を当て、子どもが適切な重心を持つことをサポートします。具体的には、姿勢トレーニングやバランスボードを使ったトレーニングなどを通じて、重心の安定化を促します。
- 学習に不可欠な座り姿勢での姿勢コントロールの促通 適切な座り姿勢は、学習において重要な要素です。不適切な座り姿勢は集中力の低下や身体の疲労を引き起こすことがあります。私たちは、子どもが学習に不可欠な座り姿勢を維持できるように、姿勢コントロールの促通を支援します。具体的には、正しい座り方やデスク環境の調整、体操やストレッチの指導などを行います。
- 姿勢に伴う手の運動構成のバランス 姿勢と手の運動は密接に関連しています。不適切な姿勢は手の運動にも影響を与えることがあります。私たちは、子どもの手の運動構成をバランス良く整えるために、姿勢と手の連動性を意識した支援を行います。具体的には、手の筋力や協調性のトレーニング、細かい手指の動作の指導などを行います。
- 姿勢と視覚・聴覚情報の同期 姿勢の調整と視覚・聴覚情報の適切な処理は、子どもの学習や集中力に影響を与えます。私たちは、子どもが姿勢と視覚・聴覚情報を適切に同期させるための支援を行います。具体的には、視覚情報や聴覚情報の統合を促すトレーニングやセンサリー処理の指導などを行います。
- 全身の関節運動・筋肉の出力調整 全身の関節運動や筋肉の出力の調整は、身体の柔軟性や運動能力に影響を与えます。私たちは、子どもの全身の関節運動や筋肉の出力を調整し、適切な身体の動きをサポートします。具体的には、関節の可動域の拡大や筋力トレーニング、コーディネーションの向上を目指したプログラムを提供します。
- 三半規管や脳神経系の出力の修正 三半規管や脳神経系の出力の調整は、バランス感覚や運動の調整に関与します。私たちは、子どもの三半規管や脳神経系の出力を修正し、バランス感覚や運動の質を改善するための支援を行います。具体的には、バランス感覚のトレーニングや目の運動の指導などを行います。
- ハンドリングによる触覚刺激で感覚系のコントロール 触覚刺激は感覚統合や身体の調整に重要な役割を果たします。私たちは、子どもの感覚系のコントロールを促すために、ハンドリングと呼ばれる触覚刺激を活用した支援を行います。具体的には、身体全体に触覚刺激を与えることで感覚統合を促し、身体の安定性や調整能力を高めます。
- 皮ふ刺激によるオキシトシン分泌の促進 皮ふ刺激はオキシトシンの分泌を促し、リラックスや安定感をもたらします。私たちは、子どもの皮ふ刺激を活用してオキシトシンの分泌を促進し、心身の安定をサポートします。具体的には、マッサージや触れ合いのアクティビティを通じて、子どもがリラックスした状態に入る機会を提供します。
- 皮ふ・筋膜・筋肉の長さのセンサーのコントロール 身体の皮ふ、筋膜、筋肉は長さの変化を感知するセンサーを持っています。私たちは、子どもの皮ふ・筋膜・筋肉の長さのセンサーをコントロールし、正常な身体の感覚を促します。具体的には、ストレッチや筋膜リリースなどの手法を用いて、身体の柔軟性や感覚統合を促進します。
- 感覚ー認識システム促通から無の状態へのアップデート 感覚と認識のシステムが促通し、無の状態にアップデートされることは、子どもの集中力や学習能力に大きな影響を与えます。私たちは、子どもの感覚と認識のシステムを促通させ、無の状態へのアップデートを支援します。具体的には、身体を使ったアクティビティやセンサリー統合の手法を用いて、感覚と認識の調整を促します。
- 身体への関わりによる不足した愛着の向上 不登校の子どもには、不足した愛着が存在する場合があります。私たちは、身体への関わりを通じて子どもの不足した愛着を向上させる支援を行います。具体的には、身体的な接触やアクティビティを通じて子どもとの関係性を構築し、安心感や信頼感を促します。
- 負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化 負の心理システムは、子どもの身体に過緊張や緊張を引き起こすことがあります。私たちは、負の心理システムで過緊張した筋肉の正常化をサポートします。具体的には、筋肉の緊張を緩めるエクササイズやリラクゼーション法の指導を行い、身体の緊張を軽減します。
- 負の心理システムから身体への過剰な意識への抑制 負の心理システムから身体への過剰な意識は、子どもの集中力や学習に悪影響を与えることがあります。私たちは、負の心理システムから身体への過剰な意識を抑制する支援を行います。
株式会社Osaka-Childの身体調整とカウンセリング技法
催眠療法と心理カウンセリング併用で精神作用をリセット|40代女性の心理システムを正常化に
-

-
参考催眠療法と心理カウンセリング併用で精神作用をリセット|40代女性の心理システムを正常化に
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
自律訓練法とカウンセリングの併用で40代女性生きづらさ克服|自宅で簡単にできる
-

-
参考自律訓練法とカウンセリングの併用で40代女性生きづらさ克服|自宅で簡単にできる
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
呼吸法とカウンセリングで身体と精神をコントロールし40代女性が安定した人生を送る
-

-
参考呼吸法とカウンセリングで身体と精神をコントロールし40代女性が安定した人生を送る
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
メンタライゼーション・ベースド・セラピーで40代女性の心理システムを整える
-

-
参考メンタライゼーション・ベースド・セラピーで40代女性の心理システムを整える
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
グリーフケアカウンセリングで新しい自分で自然世界と調和した生き方を獲得する
-

-
参考グリーフケアカウンセリングで新しい自分で自然世界と調和した生き方を獲得する
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
リラクゼーション法で40代女性の生きづらさの身体症状を克服|目的・やり方・コツを解説
-

-
参考リラクゼーション法で40代女性の生きづらさの身体症状を克服|目的・やり方・コツを解説
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
具体的には、身体感覚の調整やマインドフルネスなどの技法を用いて、子どもの心身のバランスを整えます。 株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの身体の健康と調整を重視し、個別に適した身体調整の支援を提供します。子どもとその家族との協力を通じて、身体の調整や感覚統合の促進を図り、学習や社会生活の質を向上させることを目指します。
📌 あなたに必要な支援は、今すぐ手に届きます。
ここまで読んで「これ、私のことだ」と感じた方へ。
私たちが提供している再設計プログラムは、表面的なアドバイスではなく、根本から人生を整えるための実践型サポートです。
現在【銀行振込の方限定で割引案内】をご用意しています。
🔸 本日 1月24日(土)23:59まで のご入金分までのご案内となります。
🔸 『あと2名様限定』
※銀行振込限定・先着順での受付となります。
銀行振込限定で 最大5万円割引・個別相談枠の優先予約も受付中。
株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの家庭学習支援


支援内容
1. オンラインによる苦手教科の徹底的学習サポート
2. 自分に合った教材と学習法の発見と実践
3. 得意科目を地域で成績上位に入るための学習法
4. 苦手科目の時間的な関わり(量→質)
5. 予習・復習の時間共有
6. 脳内の特性に合わせた学習プログラムの実践
7. 脳内と心理システムを促通した個人に合った学習方法の習得
8. 勉強量から勉強の質への関わり
9. 不登校中の自宅でのスケジューリング
10. 勉強に対する苦手意識への心理システムの調整
11. 成績に反映する個人に合った勉強法の獲得
12. 全教科の要素分解と要素の合成への考え方の習得
13. 不登校中に偏差値を20以上向上させる学習時間と質の習得
不登校の子どもの家庭学習支援の具体的なアプローチ
株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、家庭学習の支援を行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。
- オンラインによる苦手教科の徹底的学習サポート オンラインを活用して、子どもの苦手とする教科について徹底的な学習サポートを行います。個別のオンラインチューターや学習プラットフォームを活用し、子どもが理解を深めるための指導を提供します。
- 自分に合った教材と学習法の発見と実践 子どもに合った教材や学習法を見つけ、実践するサポートを行います。子どもの学習スタイルや興味・関心に合わせて教材を選定し、効果的な学習方法を指導します。
- 得意科目を地域で成績上位に入るための学習法 子どもの得意科目を活かして、地域で成績上位に入るための学習法を指導します。具体的な学習戦略やアプローチを提供し、子どもが得意科目での自信と成果を得られるように支援します。
- 苦手科目の時間的な関わり(量→質) 苦手科目に対する学習時間を質の高いものにするための支援を行います。集中力を高めるための学習スケジュールの作成や、効果的な学習方法の指導を通じて、苦手科目への取り組みを効果的に進める方法を提供します。
- 予習・復習の時間共有 予習と復習の重要性を理解し、効果的に取り組むために、子どもと共有する時間を設けます。予習や復習の方法や具体的な計画の立て方を指導し、子どもが学習内容を定着させるサポートを行います。
- 脳内の特性に合わせた学習プログラムの実践 子どもの脳の特性に合わせた学習プログラムを実践します。例えば、視覚的な学習スタイルを持つ子どもにはマインドマップやイメージングを活用し、効果的な学習を促します。
- 脳内と心理システムを促通した個人に合った学習方法の習得 子どもの脳内の機能と心理システムを促通させ、個人に合った学習方法を習得させる支援を行います。具体的には、脳の情報処理や学習スタイルを理解し、それに基づいた学習戦略やアプローチを提案します。
- 勉強量から勉強の質への関わり 勉強の量だけでなく、質の高い学習を実現するための関わりをサポートします。集中力の向上や学習環境の整備、効果的な学習テクニックの指導などを通じて、子どもが効率的かつ効果的に学習できるように支援します。
- 不登校中の自宅でのスケジューリング 不登校中の子どもが自宅での学習をスムーズに進めるためのスケジューリングのサポートを行います。適切な時間配分やタスク管理の方法を指導し、子どもが自主的に学習を進められるように支援します。
- 勉強に対する苦手意識への心理システムの調整 勉強に対する苦手意識を持つ子どもに対して、心理システムの調整を行います。適切な支援方法や学習環境の整備、ポジティブなフィードバックの提供などを通じて、子どもの勉強への意欲や自信を高める支援を行います。
- 成績に反映する個人に合った勉強法の獲得 子どもの個別の特性や学習スタイルに合わせて、成績に反映される勉強法を獲得させる支援を行います。具体的には、学習戦略の指導や学習プランの作成、効果的な学習テクニックの習得などを通じて、子どもが効果的に学習できるようにサポートします。
- 全教科の要素分解と要素の合成への考え方の習得 全教科において、学習内容を要素分解し、それらを合成する考え方を習得させる支援を行います。具体的には、重要なキーポイントの抽出や概念の整理、総合的な学習アプローチの指導などを通じて、子どもの学習能力を向上させます。
- 不登校中に偏差値を20以上向上させる学習時間と質の習得 不登校中に子どもの学習時間と質を向上させ、偏差値を20以上上げる支援を行います。適切な学習計画の策定や時間管理の指導、効果的な学習方法の習得などを通じて、子どもの学力向上を支援します。
発達支援・発達相談をカウンセリングと療育で発達障害の子どもの機能性を120%アップ
動機づけ面接とカウンセリングの併用で40代女性の個人の人生に合った生き方を見つける
ナラティヴセラピーをカウンセリングで過去の経験値を未来軸に近づけ40代女性を自己実現に
ペアレント・トレーニングで40代母親の子育てを楽にする|子どもの育ちを大切にできる
不登校中の勉強しない・遅れる不安を解決する40代母親ができる接し方とは
中3不登校生徒で勉強してない場合の受験対策や進路の選択肢|今からでも間に合う!
【40代母親必見】不登校の子が復学後に勉強しない?その原因と解決策を詳解
中学3年間不登校だと勉強してないから高校受験は難しい?中学生の不登校の原因と親ができる対応
発達障害をカウンセリングで心理システムをスムーズにし克服へ|40代女性生きづらさ解決
学習障害(LD)をカウンセリングで最短で負担なく克服させる|生きづらさ解決に
株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの家庭学習をサポートし、個別に適した学習方法や戦略を提供します。子どもとその家族との協力を通じて、学習の成果を最大化し、不登校からの復学を支援します。
株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの不登校復学支援内容:不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポート


支援内容
1. カウンセリングによる自己イメージのリセット
2. 意識と覚醒の自然現象への共有
3. 好きなこと・得意なこと・使命感への気づき
4. 未来像のマインドからの発見
5. 未来像と現実の自己へのプログラミング
6. 自己内から具体的な人生設計
7. 誕生から死への人生軸への関わりと意識の促通
8. トレンド情報に流されない個人に合った生き方の習得
9. 努力せずありのままで成果が出るキャリアとプロセスの構築
10. 学校環境での失敗体験の再現化と捨てる作業
11. 世界を構造から見つけていくトレーナーとの共有
不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポートの具体的なアプローチ
株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学支援の一環として、進学やキャリアデザインのサポートを行っています。以下に、具体的な支援内容を説明します。
- カウンセリングによる自己イメージのリセット カウンセリングを通じて、子どもの自己イメージをリセットします。過去の失敗や困難な経験に縛られず、新たな可能性や自己評価を見つける支援を行います。
- 意識と覚醒の自然現象への共有 子どもに対して、意識や覚醒の自然現象について共有し、自己の内面に目覚めるきっかけを与えます。具体的には、マインドフルネスや瞑想などの方法を取り入れ、子どもが内なる気づきや成長を促します。
- 好きなこと・得意なこと・使命感への気づき 子どもが自分の好きなことや得意なこと、そして使命感を見つけるための支援を行います。興味や才能を引き出し、将来の方向性を探るための活動や自己探求のプロセスをサポートします。
- 未来像のマインドからの発見 子どもが自分自身の未来像を持つことで、目標や希望を見つける手助けをします。未来を具体的にイメージすることで、自己の成長や進学・キャリアの方向性を見出すサポートを行います。
- 未来像と現実の自己へのプログラミング 子どもが描いた未来像と現実の自己を結び付けるためのプログラミングをサポートします。具体的な目標設定や行動計画の策定、自己肯定感や自己効力感の醸成を通じて、子どもの進学やキャリアの実現を支援します。
- 自己内から具体的な人生設計 子どもが自己内に持つ資源や価値観を活かし、具体的な人生設計を立てるサポートを行います。自己の内なる声や目標に基づき、将来の進路やキャリアの方向性を考えるプロセスを共に進めます。
- 誕生から死への人生軸への関わりと意識の促通 子どもに対して、人生の意義や目的、誕生から死への人生軸について考える機会を提供します。自己の存在意義や時間の尊さを理解し、将来に向けた意識の促進を支援します。
- トレンド情報に流されない個人に合った生き方の習得 子どもがトレンド情報や社会の期待に流されず、自己に合った生き方を見つけるための支援を行います。個別の特性や価値観を尊重し、自己を大切にする生き方の習得をサポートします。
- 努力せずありのままで成果が出るキャリアとプロセスの構築 子どもが努力せずにありのままの自己で成果を出せるキャリアやプロセスの構築をサポートします。個々の能力や資質を活かし、自己の個性や魅力を最大限に生かした進学やキャリアの選択を支援します。
- 学校環境での失敗体験の再現化と捨てる作業 学校環境での失敗体験を再現し、それらを手放すプロセスを支援します。過去のネガティブな体験やトラウマからの解放を促し、自己成長と前向きな展望を持つためのサポートを提供します。
- 世界を構造から見つけていくトレーナーとの共有 子どもが世界の構造や社会の仕組みを理解し、自己の進学やキャリアの選択に生かすために、トレーナーとの共有を行います。具体的な情報や知識の提供、意義や意味の理解を通じて、子どもの進学やキャリアデザインに役立つサポートをします。
対人関係療法カウンセリングで治りにくい精神疾患を正常化する|うつ病・摂食障害に効果的
ソリューション・フォーカスト・アプローチで人生の悩みを最短解決|40代女性生きづらさ克服
キャリアカウンセリング(キャリアコンサルティング)で40代女性の人生を幸福に導く
コーチングで40代女性の子育てやキャリアアップを最速に機能させる
株式会社Osaka-Childのカウンセリング技法
【2023年最新】認知行動療法(CBT)とは?方法、効果やメリット・デメリット、療法の流れなどを解説
ストレスマネジメントとは?40代女性が子育て・キャリアアップで活かせる効果ややり方を解説
-

-
参考ストレスマネジメントとは?40代女性が子育て・キャリアアップで活かせる効果ややり方を解説
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
アサーショントレーニングとは?職場や子育てで実践する方法や自己表現タイプを解説
-

-
参考アサーショントレーニングとは?職場や子育てで実践する方法や自己表現タイプを解説
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
認知再構成法とカウンセリングで40代女性の生きづらさを生む認知のゆがみを克服
-

-
参考認知再構成法とカウンセリングで40代女性の生きづらさを生む認知のゆがみを克服
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんとしてるのに、苦しい」 「頑張ってるのに、うまくいかない」 ——そんな違和感 ...
続きを見る
株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの進学やキャリアデザインを支援し、自己の可能性や夢を追求するサポートを行います。子どもとその家族との協力を通じて、自己の価値を見出し、将来への道を切り拓くお手伝いをします。
株式会社Osaka-Childの小中学高校生・発達障害の子どもの子どもの不登校復学支援内容:不登校復学後の1年間のサポート


支援内容
1. 復学後の学校との連携
2. 復学後の母親と子どものカウンセリングの実施
3. 復学後に生まれる諸問題の解決と実践
4. 復学後の生きづらさの軌道修正
5. 復学後の母親のメンタルサポートの継続
6. 復学後にぶつかる学校環境での負の体験への関わり
7. 母親に生まれる子どもへの過負荷の調整
8. 母親の人生サポートの継続による子どもの自由の解放
9. 復学後に生まれる母親と子どもへの不安の共有
不登校の子どもの進学・キャリアデザインサポートの具体的なアプローチ
株式会社Osaka-Childでは、小中学高校生や発達障害の子どもの不登校復学後の1年間にわたるサポートを提供しています。以下に、具体的な支援内容を説明します。
- 復学後の学校との連携 子どもの復学後において、学校との綿密な連携を行います。学校とのコミュニケーションを円滑にし、子どもの学習状況や生活面でのサポートが必要な点を把握し、適切な支援策を立てるために協力します。
- 復学後の母親と子どものカウンセリングの実施 復学後においても母親と子どものカウンセリングを実施し、お互いの心情や課題に対して向き合います。母親の支えや理解を促し、子どもの心理的な安定と学校生活への適応をサポートします。
- 復学後に生まれる諸問題の解決と実践 復学後に生じる様々な問題や課題に対して、具体的な解決策を見つけて実践する支援を行います。学校生活や人間関係のトラブル、学習上の困難などに対して、子どもと母親の双方が適切に対処できるようにサポートします。
- 復学後の生きづらさの軌道修正 復学後に感じる生きづらさや不安に対して、子どもの心理的な軌道修正を支援します。自己肯定感の向上や適切なストレス管理の方法を教えることで、子どもが学校での生活に前向きに取り組むことを支えます。
- 復学後の母親のメンタルサポートの継続 母親のメンタルサポートを復学後も継続的に行います。母親が子どもの復学に伴うストレスや不安を抱える場合には、心理的な支えや情報提供を通じて、彼女の心の健康状態を維持し、子どもへのサポートを続けます。
- 復学後にぶつかる学校環境での負の体験への関わり 復学後に学校環境での負の体験が生じた場合には、子どもがそれに適切に関わることができるようにサポートします。適切なコーピングスキルの習得や自己肯定感の強化を通じて、子どもが学校での困難に立ち向かう力を育みます。
- 母親に生まれる子どもへの過負荷の調整 復学後において、母親が子どもに対して過度な負荷を感じる場合には、適切な調整を行います。母親の負担を軽減し、子どもとの関係性を健全に保ちながら、サポートのバランスを取ることが重要です。
- 母親の人生サポートの継続による子どもの自由の解放 母親の人生全体にわたるサポートを継続し、彼女が自己の成長と発展に集中できる環境を整えます。母親の支えが安定することで、子どもはより自由に自己を表現し、学校生活を充実させることができます。
- 復学後に生まれる母親と子どもへの不安の共有 復学後に母親と子どもが抱える不安や心配事に対して、お互いがそれを共有し、解消するための場を提供します。相互の理解を深め、不安を和らげることで、子どもの復学後の安定と成長をサポートします。
ストレスコーピングとカウンセリングの併用で40代女性のキャリア・子育てに成果
マインドフルネスとカウンセリングで効果を最大に|40代女性のキャリア・子育てに成果を出す
行動活性化療法で精神的抑うつを改善|40代女性生きづらさ克服でキャリア・育児両立に
株式会社Osaka-Childの臨床心理士として、私たちは子どもの不登校復学後の1年間にわたり、学校との連携や心理的なサポートを通じて、子どもと母親の両方を支えます。子どもの安定した学校生活の確立と母親のメンタルヘルスの維持に注力し、一人ひとりのニーズに合わせたサポートを提供します。
Osaka-Childは小学生・中学生の不登校のお子さまに対して最短復学支援を提供しています

株式会社Osaka-Childの支援内容とは
- 母親のメンタルサポート
- 不登校子どものカウンセリング
- 不登校子どもの身体調整
- 不登校子どもの家庭学習支援
- 不登校子どもの進学・キャリアデザインサポート
- 不登校復学後の1年間のサポート
不登校子どものカウンセリング Osaka-Childでは、専門のカウンセラーによる個別のカウンセリングを行い、不登校の原因や問題を解決するための支援を提供しています。不登校子どもの身体調整 心身共に健康であることは、不登校克服に不可欠な要素の1つです。Osaka-Childでは、体の不調を訴える子どもに対して、運動や栄養指導などの支援を提供しています。不登校子どもの家庭学習支援 学校に行けない状況であっても、家庭学習を続けることが重要です。 Osaka-Childでは、家庭学習の計画立案や実践支援を行い、学習習慣の維持や向上に貢献しています。不登校子どもの進学・キャリアデザインサポート 不登校期間中に進路について考えることは、将来の自分自身の希望や目標を明確にするためにも重要です。 Osaka-Childでは、進路相談や進学・就職に関する情報提供など、キャリアデザインに必要な支援を提供しています。不登校復学後の1年間のサポート 不登校克服後の生活は、新たな課題やストレスを伴うことがあります。Osaka-Childでは、不登校復学後の1年間にわたって、学校生活や社会生活のサポートを行っています。
🔚 最後まで読まれたあなたへ。
もし「私は変わりたい」と思われたのなら、
それは変わる準備が、すでに整い始めている証拠です。
✅ 現在【銀行振込の方限定で割引案内・特別価格&3大特典】をご案内中です
🔸 本日 1月24日(土)23:59まで のご入金分までのご案内となります。
🔸 『あと2名様限定』
※銀行振込限定・先着順での受付となります。
33万円・50万円の再スタート支援プログラムでは、
家族関係・心理構造・生き方の再構築を、あなたのペースでじっくり支援します。
すでに診断済みの方も、そのまま詳細ページへ進めます。
あなたの心と体に合ったサポートを、今すぐ確認してみてください。






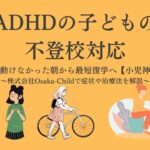









































の-女性専門カウンセリング支援.png)


で-40代女性の人生を幸福に導く-〜株式会社Osaka-Childの効果的なアプローチ〜-150x150.png)






