
- 何度教えても覚えられない。
- 何度言い聞かせても同じミスを繰り返す。
わかっていても、つい怒鳴ってしまって──
あとで自己嫌悪に押しつぶされそうになる。
そうやって誰にも言えないまま、毎日を抱え続けてきた方も多いですよね。
- 「あのとき怒ってしまった」
- 「もっと早く気づいてあげればよかった」──
何度もそうやって、自分を責めてばかりいた日もあったと思います。
でもそれは、ずっとこの子を想ってきた証なんですよね。
先生や周囲に相談しても、
- 「気のせい」
- 「成長すれば落ち着く」
と流されてしまう。
本当は困っていたのに、
どこにも「当てはまらなかった」あの感じ──
あの孤独を、もう繰り返さなくていいんですよね。
このページにたどり着いたあなたは、
すでに
何度も検索し、
何度も迷い、
それでもわが子のためにヒントを探し続けてきた方です。
この子に合った支援の形を、
落ち着いて考える時間。
気づけば、それがずっと足りなかったと感じてきました。
この記事では、
学習障害のある小学生が学校でどのような支援を受けられるのか、
- 通級・支援級・通常級の違い
- 親としての向き合い方
までを、小児神経科医監修のもとでわかりやすくまとめています。
この記事では、次の5つのことがわかります。
この記事を読むとわかること
- 通常級・通級・支援級の違いが支援の視点からつかめる
- 学習障害のある子が学校で受けられる支援内容が見える
- 支援制度の選び方を「わが子の今」から考え直せる
- 選べない苦しさの背景にある親の葛藤に気づける
- 学校の対応に困ったときの相談先と初動がわかる
- 「どう育てたらいいのかわからない」
- 「怒ってしまう自分が嫌だった」
- 「何度もやり方を変えたのに、うまくいかなかった」
そんな苦しさの中で、ずっと孤独に頑張ってきたんですよね。
ここまで、
自分ひとりで抱えてきたこと自体が、
もう十分すごいことだったと思います。
そんなあなたのためにご用意したのが、
- 教えても伝わらない、
- 宿題が終わらない、
- 気づけばまた怒ってしまっている──
そんな日々に疲れきって、
「私の関わり方が悪いのかも」と自分を責め続けてきた方も多いです。
でもそれは、この子を誰よりも想い続けてきた証でもありますよね。
そんな迷いに寄り添うのが、
「学習障害の支援をどうすべきか…迷い続けた私が、『この子に合う環境』を見つけられた──3週間集中再安心サポート」です。
- 1週目は「迷い」と向き合い
- 2週目は「わが子の特性」を見つめ
- 3週目は「安心できる関係」を整えていく──
視点が変わることで、関わりも少しずつ変わり始めます。
制度を選ぶ前に、
「わが子にとっての安心とは何か」に立ち戻る時間を届けたい。
この3週間が、そのためのやさしい出発点になるはずです。
ここまで読み進めた今のあなたなら、きっと踏み出せますよ。
監修者
株式会社Osaka-Child所属 小児神経科医
- 名前: 三浦あすか
- 出身地: 兵庫県西宮市
- 最終学歴: 神戸大学医学部 小児科専攻
- 専門分野: 小児神経、DCD(協調運動障害)、発達性ディスプラクシア、HSP気質の子ども支援
- 職歴: 兵庫県立こども病院 小児神経センター勤務(11年)
専門分野について一言: 「できないことの奥にある『がんばっているサイン』を、もっと社会全体で受けとめていけたらと思っています。」
監修者
株式会社Osaka-Child所属 臨床心理専攻大学教授
- 名前: 森本哲夫
- 出身地: 奈良県
- 最終学歴: 米国ハーバード大学心理学部 博士課程修了
- 専門分野: 臨床心理学、発達心理学
- 職歴: ハーバード大学研究員(5年)、大阪大学人間科学部教授
専門分野について一言: 「心の成長とは、自己理解の旅でもあります。その旅のお手伝いができれば幸いです。」
「このままでいいのかな…」と答えを探していたあなたへ
- 「支援級って、そんなに重い子が行く場所じゃないの?」
- 「通級に通わせたら、もう戻れないのかな…」
──どれを選んでも間違いのような気がして、ずっと決められなかった。
学校から渡されたパンフレットも、
夫の「普通でいいやん」という一言も、
どれも正解に見えなくて、答えを出せずにいた。
《学習障害の支援をどうすべきか…迷い続けた私が、『この子に合う環境』を見つけられた──3週間集中再安心サポート》は、
「支援の選び方」に悩んでいる母親のための心理サポートです。
こんな方におすすめです
- 支援級・通級・通常級…どれを選んでも不安が消えない
- 制度の説明を読んでも、具体的にイメージが湧かない
- 子どもの「できなさ」に毎晩悩んでしまう
- 周りに相談できず、一人で答えを出そうとしている
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 1月19日(月)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと3名様限定』
※銀行振込限定・先着順
そして──
少しずつ「この子らしさ」が見えてきた今、
「私自身のこれから」にも目を向けてみたくなった方へ。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
「母としての安心」を土台に、
「わたしとしての人生」を再設計する3週間。
子どものことで手いっぱいだった日々から、
自分のための時間を取り戻す日常へ。
- 子育ての悩みが少し落ち着いてきた
- でも「自分の時間が止まっている」と感じている
- 母親だけで終わりたくない気持ちがある
このプログラムでは、
「役割だけでない私」に立ち返るサポートを行います。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
「ちゃんとしてるのに、苦しい」
「頑張ってるのに、うまくいかない」
——そんな違和感を抱えたまま、ずっと我慢していませんか?
LINEで3分セルフ診断ができます。
あなたの“今の感覚”の正体が、見えてきます。
通級・支援級・通常級の違いとは?|学習障害の支援制度を比較

- 通級か
- 支援級か
- それとも通常級のままか──
目の前の選択肢を並べられたとき、
すぐには決められなかった。
何を優先すべきかが見えなくなっていたから。
支援してもらえるなら安心なはずなのに、どうして不安になるのか。
制度の説明を受けても、ずっと引っかかっていた。
大切なのは、
「合っているかどうか」を自分の目で見つめ直すこと。
その視点がないまま選ばされたような気持ちになると、
後悔がついてくる。
ここでは、
それぞれの制度がどう違うのかだけでなく、
母としての「受け止め方」も含めて整理していきます。
通級・支援級の違いをわかりやすく整理
- 通級
- 支援級
は、
どちらも学習障害(LD)の子どもに向けた特別支援教育の枠組みに入ります。
それでも、
- 支援の受け方
- 毎日の過ごし方
には明確な違いがあります。
通級は、
通常の学級に在籍したまま、
週に数時間だけ別室で支援を受けるスタイルです。
子どもが日常のなかでクラスに溶け込みながら、
困難な部分だけサポートを受けられるという仕組みがあります。
一方の
支援級では、
生活そのものが少人数・個別対応のクラスで営まれます。
- 学習の進め方
- コミュニケーションのとり方
まで含めて、
子どもに合わせた形で構成されていることが多いです。
ただ、
「どちらが軽い・重い」という話ではありませんよね。
選ぶべきは、
「無理なく過ごせる場所」がどこかという視点だったと気づかされました。
制度の説明だけでは見えてこない部分にこそ、
親のまなざしが必要になることを実感してきました。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「どうしてこんなに読み書きが苦手なんだろう?」
そんな疑問を感じた方へ。
学習障害の基礎知識から、家庭でできる対応までを専門家監修でわかりやすくまとめました。
-

-
参考学習障害とは?読み書き・計算が「できない理由」と家庭でできる対応法【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「どうしてこんなに教えてるのに、できないんだろう」 そう思ったあとで、 つい声を荒ら ...
続きを見る
通常級の支援はどこまで受けられる?
学習障害(LD)があっても、
通常級に在籍しながら支援を受けている子どももいます。
たとえば、
- 板書を減らす
- 音読を免除する
- 教材を調整するなど、
合理的配慮と呼ばれる工夫が可能です。
ただ、
その支援が
「どこまで実行されるか」は、
学校の理解や担任の姿勢によって変わります。
制度上は同じでも、
現場での温度差に戸惑ったことがある方も多いです。
- 「伝えたのに配慮してもらえなかった」
- 「親の要望だと思われて、子どもが浮いてしまった」
そんな経験を持つ家庭もたくさんいます。
通常級でも支援はある
──それは事実だけれど、安心できるかどうかはまた別の話だったように感じます。
「できないことがある」という現実に、
どれだけていねいに寄り添ってもらえるか。
その視点を抜きにしては、
子どもにとっての居場所にはならないと痛感してきました。
支援級・通級は将来にどう影響する?進学・高校進学への不安
- 支援級や通級に進んだら
- この先の進路はどうなるのか。
そんな不安を口にしたことがある母親は、
きっと自分だけじゃないはずです。
- 通知表の様式
- 内申への影響
- 高校受験の選択肢──
「見えない将来」の要素が多いほど、
今の選択にも迷いがつきまといますよね。
でも実際には、
支援級や通級から通常の高校へ進学している子もいます。
その逆に、
安心を優先して特別支援学校や通信制を選んだ家庭もありました。
ポイント
進路は一つではない。
どこにいたとしても、
「この子らしく学べる場所」を選ぶことはできると、何度も聞いてきました。
だからこそ、
制度を選ぶというより、
「わが子の生活を支える形を選ぶ」という気持ちで向き合っていきたい。
それが、
後悔しない選び方だったと、今なら感じています。
無料LINE診断|今のあなたに必要なサポートは?
『高校進学は?』
『このまま普通級で大丈夫?』
──将来が見えずに不安になったら、まずは今の自分に合った視点を知ることから。
📩 LINEで【 4 】と送信するだけで、
《学習障害の支援をどうすべきか…迷い続けた私が、「この子に合う環境」を見つけられた──3週間集中再安心サポート》
が「今のあなたに合っている理由」をお届けします。
「うちの子も対象なの?」学校支援が受けられないと感じたとき
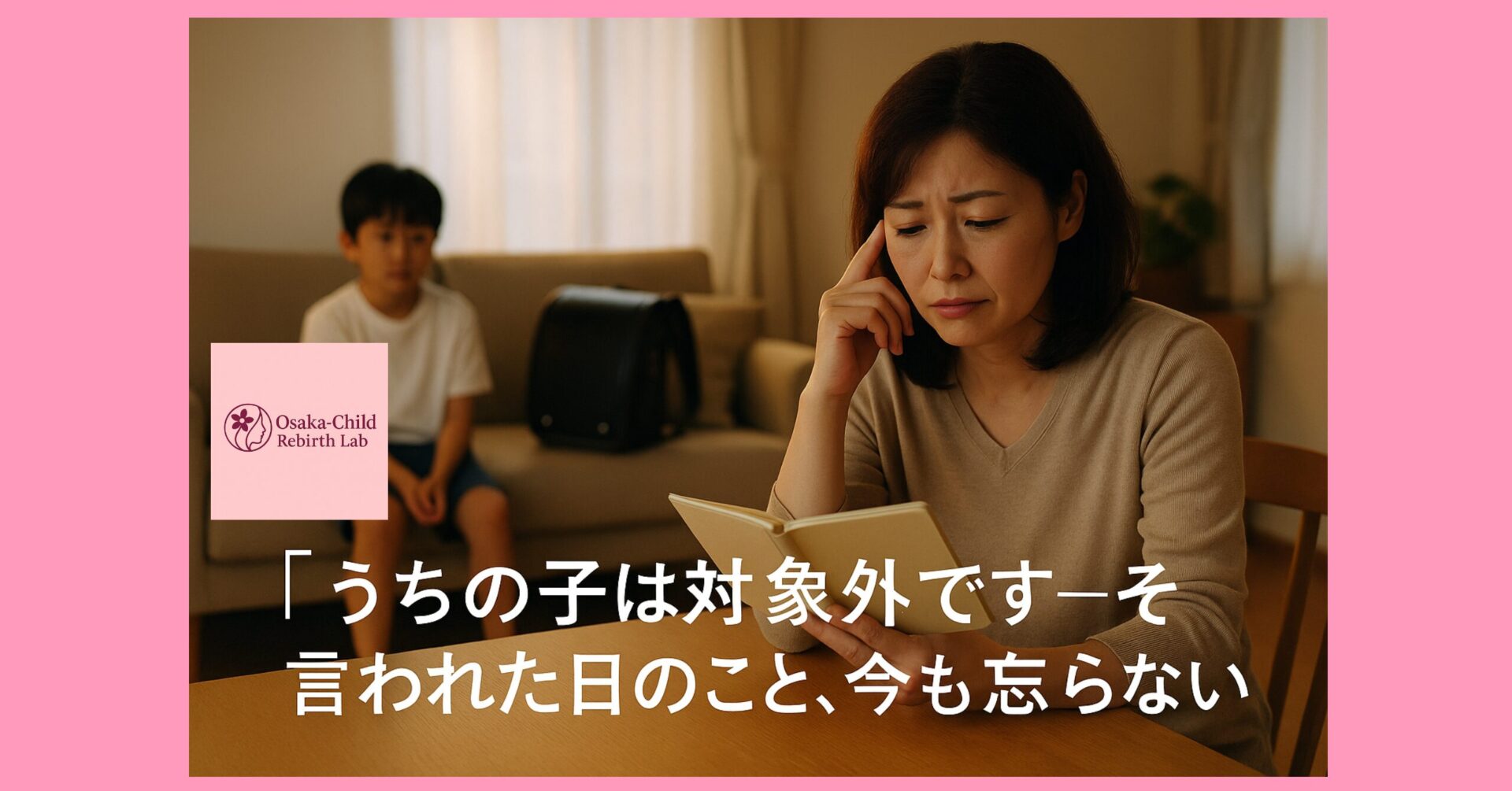
“うちの子も対象なのかな…”と不安になったときに読んでほしい
「通級は対象外です」と言われた。
でも、それで「何もできない」ってことなの…?
──そんなふうに支援からこぼれ落ちたような感覚に、ずっと戸惑っていた方へ。
《学習障害の支援をどうすべきか…迷い続けた私が、「この子に合う環境」を見つけられた──3週間集中再安心サポート》は、
「支援を受けられない不安」そのものに寄り添い、
親子に合った「選び方」を整理していく心理サポートです。
明らかに学びにくさがあるのに、
学校では「様子を見ましょう」と言われるだけ。
「支援を受けられるのはもっと困っている子」
──そんなニュアンスで伝えられると、
自分の子は「中途半端」に見られているようで、胸がざわついたこともありました。
でも、
ほんとうに知りたかったのは、
「誰が対象か」ではなく、
「どうすればこの子が安心して学べるか」だったのです。
制度の枠を超えて、
必要な支援をどう届けてもらえるのか。
その視点で整理していきます。
学習障害に対する配慮内容とは?
学習障害(LD)のある子どもに対しては、
学校内で「合理的配慮」と呼ばれる支援が
行われる場合があります。
この配慮は、
本人の困りごとに合わせて、
学びやすくするための
環境調整や手段の工夫を行うものです。
たとえば、
- 黒板を写すことが難しい子にはプリント配布や板書の写真撮影が許可される。
- 読み書きに時間がかかる子には、音読や作文の代わりに口頭説明や選択肢形式で対応する方法も取られるなど
ただ、
こうした配慮が
「当たり前のように受けられる」と
感じたことはありませんでした。
むしろ、
お願いすること自体に遠慮が必要で、
まるで特別な頼み事をしているような気持ちになることもあったんです。
制度としては整っていても、
現場での温度差に戸惑った方も多いのです。
だからこそ、
- 「こういうときに困っている」
- 「こんなふうに助けてほしい」
と伝える勇気が、支援の第一歩になっていくと感じています。
学校に相談しても対応してくれないときは?
「その程度なら、まだ様子を見ましょう」
学校に相談したとき、
そう返されて言葉に詰まってしまった経験がありました。
「見守る」という言葉は、
一見やさしさに聞こえるけれど、
何も変わらない時間だけが過ぎていくと、
焦りだけが積み重なっていきますよね。
ポイント
学習障害(LD)は、
目に見えづらい困難です。
気づかれにくい特性だからこそ、
周囲に伝わらず、
配慮が後回しになる状況が続いてきました。
でも、
それが
「支援の対象ではない」と
いう意味ではありません。
伝え方や関わる相手を変えることで、
受け止められ方が変わっていく場面もありました。
たとえば、
担任の先生では難しかった内容も
- 学年主任
- 特別支援コーディネーター
に相談すると、
別の角度から対応を検討してくれます。
保健室や相談室との連携をつなげていくことで、
学校全体が少しずつ動いていく感覚を持てたこともあります。
いきなり変わらなくても、
「話を聞いてもらえた」という実感が、
母親の安心につながっていきます。
通級を断られた/拒否されたときの受け止め方
「通級は今のところ難しいです」
そう告げられた瞬間、
自分の中にあった支援への希望が
しぼんでいくのを感じました。
せっかく踏み出したのに、
扉を閉められたような感覚。
- 自分の伝え方が悪かったのか、
- この子の状態が「足りなかった」のか
ぐるぐると自問する時間が続いていました。
でも通級は、
希望すれば必ず通える制度ではないことをあとで知りました。
- 学校や地域の枠組み
- 基準や人員配置
によって、
支援の内容や判断は大きく変わります。
それでも、
「通級がだめなら終わり」ではありません。
通常級のなかで受けられる配慮や、
家庭でできるサポートもたくさん残っています。
実際に、
通級に行けなかった子が、
担任との毎朝のやりとりや宿題の調整を通じて、
少しずつ安心を取り戻していった姿もありました。
どの道を通るかではなく、
どこで「安心して学べるか」。
その軸さえブレなければ、
支援の形が変わっても意味は失われないと感じています。
支援制度を選ぶ前に整理したい「親の迷い」と向き合い方
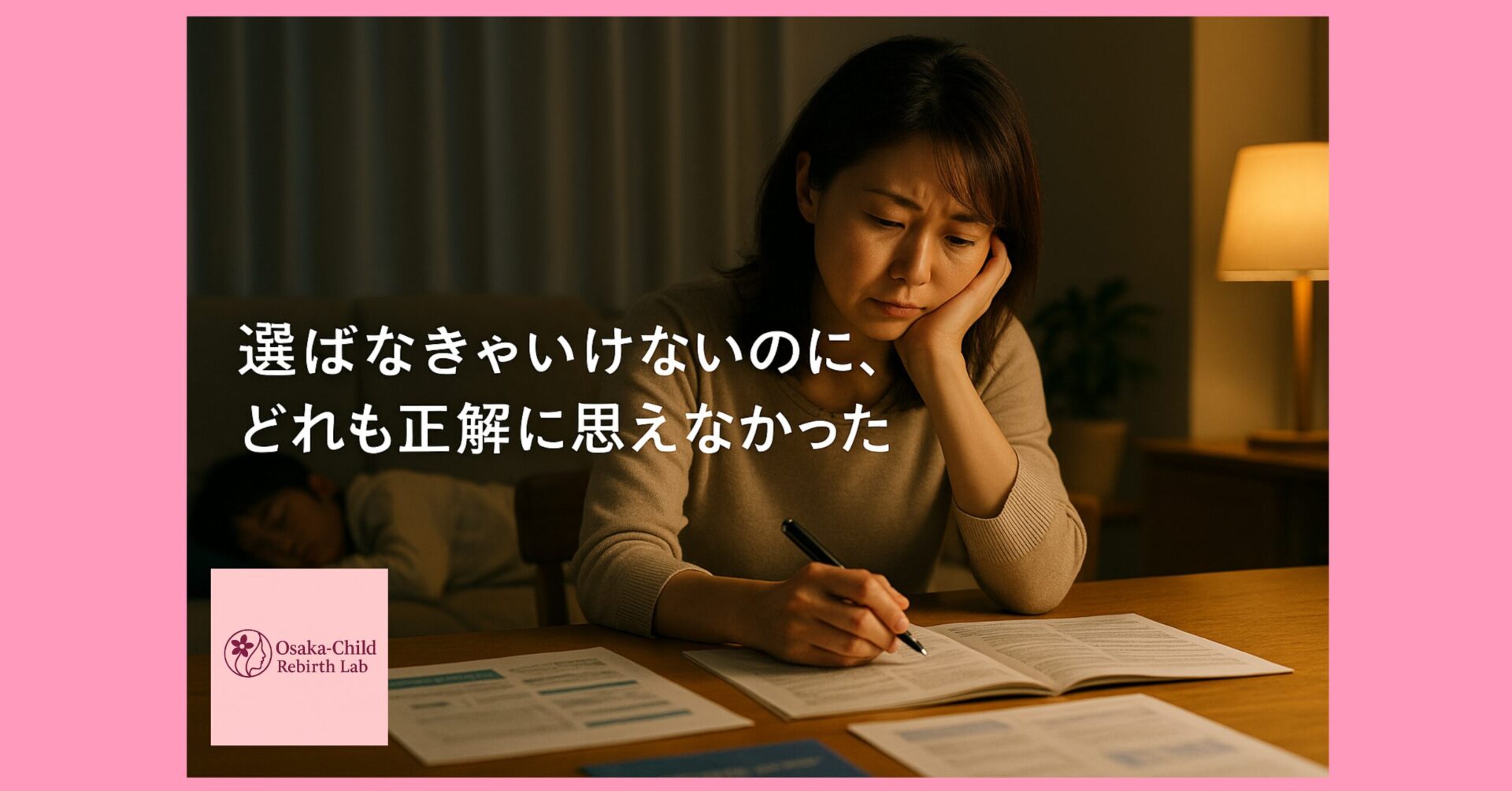
「“診断を受けるべきか…”と迷いながら、ここまで読み進めたあなたへ
- 「支援って、どのくらいの子が対象なの?」
- 「このまま様子を見ていても大丈夫なんだろうか…」
──制度のパンフレットを見ても、不安ばかりがふくらんでいった。
「そのうちできるようになるやろ」と笑う夫。
「大げさじゃない?」と話をそらすママ友。
ちゃんと向き合ってきたからこそ、誰にもわかってもらえなかった。
《学習障害の支援をどうすべきか…迷い続けた私が、『この子に合う環境』を見つけられた──3週間集中再安心サポート》は、
「判断しきれない不安」と向き合う母親のための心理サポートです。
こんな方におすすめです
- 支援級・通級の違いが、よくわからないまま悩み続けている
- 調べても調べても、不安ばかりが増えてしまう
- 周囲の無理解に、気持ちがすり減ってきた
- 「私が決めなきゃ」と一人で背負っている
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 1月19日(月)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと3名様限定』
※銀行振込限定・先着順
そして──
子どもの将来を考えながら、自分のこれからにも目を向けたくなった方へ。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
「母としての安心」を礎に、
「わたしとしての未来」を再構築する3週間。
迷い続けた日々の先に、
「私の人生」にも選択肢があると気づけたなら。
- 子育て中心の毎日が、少しずつ落ち着いてきた
- でも、気づけば「私」は置き去りになっていた
- 母としてだけでなく、人としての未来を描き直したい
このプログラムでは、
「誰かのために」から、「自分のために」へと視点を変える時間を届けます。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
どの制度がいいのか、
ずっと考えているのに決めきれない。
焦りと不安がココロの中をぐるぐる回って、
気づけば返事の締切だけが迫っている。
そういう状況、何度も経験してきました。
「この子にとってベストな選択をしたい」
その気持ちが強ければ強いほど、
間違うことが怖くなってしまう。
だからこそ、
支援制度を選ぶ前に
「親としての迷い」にちゃんと向き合うことが必要だったのだと、
今ははっきり感じています。
通級か支援級か、決めきれないまま時間だけが過ぎていく
選ばなきゃいけないのに、
ココロが動かない。
頭では
「どちらにもメリットとデメリットがある」と
理解しているのに、
なぜか踏み出せなかった。
- 通級は在籍学級が変わらない安心感がある。
- 支援級は手厚く見てもらえる分、特別視される不安もある。
そんな風に表面的な比較ばかりして、
本当に大切なことを見落としていたように思います。
親として「どう見られるか」を気にしていた。
「この子にレッテルを貼ることにならないか」って、
勝手に決めつけていた節があった。
でも実際は、
制度ではなく、
自分の中のこだわりにブレーキをかけられていただけだったんですよね。
迷い続けてしまったのは、
優柔不断だからじゃない。
ずっと、
この子のことを真剣に考えてきた証だったと受け取れるようになりました。
支援級に入れると「この子の将来」が決まってしまうの?
「ここで支援級を選んだら、進路まで狭まるのではないか」
そんな思いにとらわれて、
なかなか決められずにいました。
進学や就職に響くんじゃないか──
何度も、未来のことばかり考えて立ち止まっていました。
でも、
支援級から通常級に戻ることは可能です。
さらに、
その後に希望の高校へ進学していった子もいます。
制度はあくまで
「今」の困りごとを支えるものであって、
将来の選択を狭めるものではありません。
支援の形は、
そのときどきで変わっていい。
大切なのは
「今、この子が安心して学べる環境かどうか」だと気づかされました。
将来を見据えることも大事だけど、
「今ここ」の安心がなければ、
その未来だって成り立たない。
支援級=将来を決める場所ではないと、
ようやく腑に落ちた瞬間がありました。
「通級はいつから?」適切なタイミングと見極め方
支援を意識しはじめたのは、
小学校2年生の冬ごろでした。
でも、
- 「もう遅いのでは?」
- 「もっと早く動いていれば…」
と、自分を責めるような気持ちが強くなっていった。
通級は、
年度や学年ではっきりと区切られているものではありません。
必要と判断されたときに、
家庭や学校との相談のうえで柔軟にスタートすることができます。
それを知ったとき、
「今からでもいい」と肩の力が抜けたのを覚えています。
焦る必要はなかった。
この子のペースで、
「支援が必要だ」と思えたときに動き出せたことこそ、
大事な一歩だった。
支援に「早すぎる・遅すぎる」という基準はありません。
必要だと感じたときに、
その気持ちを受け止めて行動する。
それだけで、
もう支援は始まっているのだと実感できました。
相談できる場所がない…支援制度に迷ったときの初動ステップ

「誰にも相談できなかった」を終わらせる一歩として
- 「学校にも相談した。でも何も変わらなかった」
- 「どこに頼ればいいのか、もうわからない」
──そんなふうに「立ち止まってしまった気持ち」にも、答えの糸口があります。
《学習障害の支援をどうすべきか…迷い続けた私が、“この子に合う環境”を見つけられた──3週間集中再安心サポート》は、
迷っていた気持ちを丁寧に整理し、
自分たちに合った環境を見つけていく3週間です。
子どもに学習のつまずきが見えてきたとき、
「誰に話せばいいのか分からない」という不安に
直面することがある。
学校には相談しづらいまま、
病院に行く決心もつかず、
ずっとひとりで抱え続けてきた方も多いですよね。
支援制度があることは知っていても、
どこから始めればいいのかが見えない。
このセクションでは、
そんな「はじめの一歩」をどこに向ければいいのかを整理していきます。
まずはどこに相談すればいい?
学校の先生に話そうとしたけれど、
どんな言葉で伝えればいいのか分からなかった。
「うちの子、学習障害じゃないかと思っていて…」と
切り出すのは、勇気がいる。
だからといって家庭で抱え込んでも、
不安はふくらむばかりなんですよね。
最初の相談先として多いのは、
やはり担任の先生や学年主任。
ただし、先生によって受け止め方に差があるのも事実です。
だからこそ、
学校に話すときには
「勉強の様子で気になる点」など、
事実ベースで伝えてみるのが入りやすい。
もし学校でのやり取りに不安があるときは、
- 市区町村の保健センター
- 教育相談所など、
学校の外の公的窓口にアクセスすることも
選択肢に入れてほしいです。
「相談すること自体が間違いじゃない」と感じられる場所とつながれることが、
最初の安心につながっていきます。
小学生の学習障害に利用できる支援制度とは?
「うちの子にも使える制度があるのかな」
そんな疑問を持ちながらも、
調べてみると情報が多すぎて、
かえって分からなくなってしまう。
専門用語や申請条件ばかりが並んでいると、
それだけでココロが折れそうになることもあるんですよね。
学習障害(LD)のある小学生が利用できる制度は、
主に2種類に分かれています。
- ひとつは通常学級に在籍しながら特定の教科や時間に支援を受ける「通級指導教室(通級)」
- もうひとつは、より継続的なサポートを受ける「特別支援学級(支援級)」
です。
ただ大切なのは、
制度の違いを理解することよりも、
「この子にどんな支えが必要か」を丁寧に考えること。
- 通級が合う子もいれば、
- 支援級で安心する子もいる。
目の前の子どもの反応を見ながら、
少しずつ合う環境を探っていくことが、
いちばん確かな選び方だと感じています。
無料診断|あなたの“心のパターン”を知る
「うちの子に合う支援制度って、どう見つければいいの…?」
そんな方のために、LINEで「キーワード」を送るだけで診断できる無料サービスをご用意しました。
📩 LINEに「学習障害 学校 支援」と送ってください。
あなたの悩みに合わせた視点とアドバイスが届きます。
先生が学習障害に理解を示さないときの対応
勇気を出して相談したのに、
「様子を見ましょう」と流されてしまった。
こちらはずっと悩んでいたのに、
そう言われると、
話したこと自体が間違いだったように感じてしまう。
そんな経験をしてきた方も、きっといますよね。
先生に悪気はなかったとしても、
学習障害(LD)への理解度には個人差があります。
学校がすぐに動けない事情があるのは、頭ではわかっている。
でも、
そのあいだに募っていく不安は、どうしたらいいのか──。
そんなふうに立ち止まっていた方もたくさんいます。
どうしても学校だけでは難しそうなときは、
- 医療機関
- 心理士
- 教育センターなど
専門性のある第三者に相談してみるのも有効です。
その際、
- 「どんな場面でつまずいているのか」
- 「家庭ではどう見えているのか」
をメモにしておくと、話しやすくなります。
「伝わらなかった」という体験はつらいけれど、
それが「もう誰にも相談しない」という理由にならなくていい。
関係をあきらめるのではなく、
つながる場所を変えることが、
母子にとっての支えになっていくはずです。
「学習障害の支援をどうすべきか…」迷い続けた私が、「この子に合う環境」を見つけられた理由
- 支援級にするか
- 通級で様子を見るか
どちらにしても、
あとから「やっぱり違った」と思うのが怖かった。
でも、
そもそも
何が「合っている」のかが分からなくて、
支援という言葉が、
どこか他人ごとのように思えていた。
選択肢はいくつもある。
けれど、どれを選んでも間違いそうで、怖かった。
情報も揃っているのに、自信が持てない。
気づけば、
「決めなきゃ」と「決められない」の間で、
ずっと動けずにいた。
けれど実は、
「どの制度にするか」よりも、
「この子がどう安心できるか」を軸にしたとき、
少しずつ見えてくるものがあるんですよね。
「学校の支援」に振り回されていた母親が変わったきっかけ
通級の説明を受けたとき、
なぜか納得できなかった。
支援級もすすめられたけれど、
そこまでではない気もして、また迷ってしまう。
結局、
どの制度にも決め手がなくて、
ただ時間だけが過ぎていった。
制度を選ぶはずなのに、
選ばれているような感覚。
母親自身が置いていかれているような気持ちになるのも
無理はないと思います。
けれど、
支援の種類ではなく、
「この子がどこなら安心できるか」という視点に立ち戻れたとき、
状況は静かに変わり始めていくんです。
この子に「合った環境」を見つけられた理由
普段は落ち着いていても、
ある日突然パニックになったり、
得意だったはずのことが急にできなくなったり。
そんな不安定さに、周りが振り回されることも多かった。
でも、
そういう揺れも含めて
「この子らしさ」なんだと受け取れたとき、
支援環境の見え方が変わっていく。
制度の説明だけでは拾いきれない部分が、
実際の生活にはたくさんある。
だからこそ、
「書類上の適合」ではなく、
「日常の中で安心していられる場所」を見つけていくことが、
母親にとっての支援の納得につながる。
- 迷って
- 試して
- やめて
- また選び直して。
そんな繰り返しの中で、
「この子にはここが合っている」と思える瞬間に出会えることがあるんです。
「学習障害の支援をどうすべきか…迷い続けた私が、「この子に合う環境」を見つけられた──3週間集中再安心サポート」
学校や地域の制度には、
それぞれのルールがある。
でも、
母親が支援に迷うときって、
制度のことが分からないからじゃない。
「この子がどこで安心できるのか」を、
自分で見つけられないことが、
いちばんの不安なんですよね。
「学習障害の支援をどうすべきか…迷い続けた私が、『この子に合う環境』を見つけられた──3週間集中再安心サポート」では、
そうした迷いの根っこから、
母親自身が向き合える設計になっています。
- 最初の1週間は、
「なぜこんなに悩んでいたのか」を整理する時間。
自分を責め続けていた気持ちや、判断できなかった理由が見えてくるだけで、
次のステップに進める方も多いんです。 - 2週目では、学習障害(LD)の特性を、わが子の姿と重ねながら理解していきます。
学校の制度や仕組みに惑わされず、
「この子にとって」必要な支援を整理していくことが目的です。 - そして3週目には、「この子らしさ」を中心に支援環境を考え直す時間。
支援級か通級かではなく、「この子が安心して通える環境とは何か」を、母親自身の言葉で語れるようになっていく。
選択の迷いを超えて、「この子に合った道」を一緒に探していく。
それがこのサポートのいちばんの力だと感じています。
「この子に合う環境が見えた」と感じられるまでの3週間のステップ
迷っていたのは、
「この子に合う場所がわからない」という現実。
でも本当は、
どんな選択をしても自信が持てない自分の気持ちに戸惑っていた。
- 支援級
- 通級
- 通常級
どれを選んでも、
何かを間違えてしまうような気がして、
前に進めなかった。
そんなふうに、
「支援を選ぶこと」がプレッシャーになって、
前に進めなくなっていた母親も多い。
「学習障害の支援をどうすべきか…迷い続けた私が、『この子に合う環境』を見つけられた──3週間集中再安心サポート」は、
制度や診断に振り回されず、
「この子らしさ」を軸に安心して選べる視点を取り戻すためのオンライン伴走サポートです。
- 学校との関係
- 母親自身の不安
- 子どもの特性
──この3つを整理し、「納得して決められる私」へとシフトしていきます。
Week1は、「選べない不安」と向き合う週。
最初は、
母親自身の気持ちを丁寧に整理するところから始まります。
子どもの様子と支援への迷いを初回セッションで言語化し、
- 「周囲の目」
- 「間違えたら取り返しがつかない」
という焦りにも寄り添っていきます。
迷いに飲み込まれていた思考に、
少しずつスペースが生まれていく。
すると、「冷静に考えられる自分」が、ゆっくりと戻ってくる。
Week2は、「困りごと」の本質を見つめる週。
- 学習障害(LD)の特性
- 子どもがつまずいている場面
を結び直しながら、
- 通級
- 支援級
- 通常級
それぞれの
支援内容と適応性を
専門家と一緒にシミュレーションします。
比較するのではなく、
「この子にはどこが合うのか」という視点に切り替えることで、
制度選びの基準そのものが変わっていく実感があります。
Week3は、「この子らしさ」を活かした進路と関係を整える週。
- 学校との関わり方や伝え方、
- 就学後の生活への見通しづくり
も含めて、
より実践的なサポートを行います。
「支援を受けることで、この子の未来が狭まるわけではない」と気づけたとき、
支援を「選ぶ」ことへの不安がやわらいでいきます。
- 家庭内での声かけ
- 学習サポート
についても、
その子の特性に合った提案を行います。
必要に応じて、
- 学校面談の準備支援
- 進学・進級を見据えたアドバイス
も対応可能です。
気持ちが揺らいだときに立ち戻れる
「振り返りガイド」もご用意しています。
母親の迷いが整ってくると、
子どもにも少しずつ変化が生まれていきます。
「怒られないかな」と身構えていた表情が、
ゆるんでくる瞬間。
「ここでなら大丈夫」と感じられる環境が、
ふたりの日常をやわらかく支えはじめます。
「この子に合う支援」が見つかる安心の3週間
「もう迷いたくない」「でも間違いたくない」──支援の選択に、ずっと揺れてきた方へ。
この3週間で、「この子に合う環境」を安心して選べるようになります。
- 通級?
- 支援級?
- 通常級?
制度の違いだけでは見えてこなかった、「わが子らしさに合う場所」を一緒に見つけるためのサポートです。
支援の選び方ではなく、「選べる自分」を取り戻すところから始めてみませんか?
まとめ|支援を「選ぶ苦しさ」から、「わが子の今」に目を向ける視点へ
- 「支援級に入れたら、この子の将来が決まってしまうのでは」
- 「通級のタイミングを間違えたら、取り返しがつかないのでは」
そうやって、
何度も何度も検索して、
答えが見つからずに立ち止まってきた日々がありましたよね。
でもその背景には、
- 「ちゃんと守ってあげたい」
- 「間違えたくない」
という、まっすぐな思いがあったはず。
支援を選べなかったのは、
優柔不断だからではなく、
ずっと「この子のことを本気で考えてきた」証だったんです。
学校制度の違いを理解しようとすることも、
支援の種類を調べることも大切。
けれど本当に必要だったのは、
「どの制度に入れるか」ではなく、
「この子がどんな環境なら安心して過ごせるか」──
その軸を、
自分の中に持てるようになることだったのですよね。
このページで分かったこと
- 通常級・通級・支援級、それぞれの支援スタイルと対象となる子どもの特徴
- 学習障害(LD)のある子どもが、診断の有無にかかわらず学校で受けられる支援の内容
- 制度の比較ではなく、「いまのわが子の様子」から選ぶ視点の重要性
- 担任に伝わらないときにできる相談先やアクションの具体策
- 支援を選べない背景にある「親の迷い」を整理することで、見えてくる選択肢の広がり
【学習障害の支援をどうすべきか…迷い続けた私が、『この子に合う環境』を見つけられた──3週間集中再安心サポート】では、
制度を押しつけるのではなく、
「この子らしさに合った環境」を一緒に探していきます。
- 1週目は、支援を選べない「迷い」に寄り添い、親の視野を広げる時間。
- 2週目は、子どもの特性と困りごとの背景を整理し、「どんな支援が合うか」を見立てていく時間。
- 3週目は、学校との関わりや家庭の安心を再設計し、母子が安心して進める道を整えていく時間です。
「制度を選ぶ前に、自分の気持ちを整える」──
その順番こそが、親としての安心と、この子の未来をつなぐ一歩になっていきます。
ここまで読み進めたあなたは、
もう十分すぎるほど
- 迷って
- 考えて
- 立ち止まってきた
人です。
これからは、「この子らしさ」とともに、安心を取り戻していきましょう。
一緒に、新しいスタートを整えていけたら嬉しいです。
「“どれを選んでも間違いそうで怖かった”──そんな時間を越えてきたあなたへ
- 「支援級にしたら、将来が決まってしまうのでは」
- 「でも、このまま通常級にいていいのかな…」
堂々巡りの中で、「何が正しいか」より「どうしてあげたいか」を見失いかけていた。
──そんな日々に寄り添う声があります。
「この子に合う環境を考えることが、やっと前向きなことに思えてきた」
そう感じはじめた方が、少しずつ安心を取り戻しています。
《学習障害の支援をどうすべきか…迷い続けた私が、『この子に合う環境』を見つけられた──3週間集中再安心サポート》は、
「選ぶこと」に責任を感じすぎて、動けなくなっていた母親のための心理サポートです。
こんな方におすすめです
- 通常級・通級・支援級…どの選択も不安で決められない
- 「大丈夫だよ」と言われても、安心できなかった
- この子にとって一番いい環境を、冷静に考えたい
- 迷い続けた気持ちを、ようやく言葉にできそうな気がしている
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 1月19日(月)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと3名様限定』
※銀行振込限定・先着順
ネットバンキングのご利用で、今すぐ開始することが可能です。
そして──
ここまで向き合ってきた「母としての時間」を、
これからの「わたしの人生」へつなげていきたい方へ。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
「母として悩み、考え、決断してきた日々」を、
「これからの生き方」につなぐための3週間です。
- 子育ての悩みでいっぱいだった毎日を、少しだけ肯定できた
- 今度は「自分自身の気持ち」にも耳を傾けたい
- 誰かのためだけでなく、自分の未来にも選択肢を持ちたい
このプログラムでは、
「母という役割の先」にある私自身の輪郭を、もう一度取り戻していきます。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
▶ 子どもの安心と一緒に、「私の人生」も動かしていきたい方へ
()
すでに診断済みの方も、そのまま詳細ページへ進めます。
あなたの心と体に合ったサポートを、今すぐ確認してみてください。








