
「どこに相談すればいいのか、ずっとわからなかった」
気づけば、
そんな気持ちを抱えたまま、何ヶ月も過ぎていた。
小学2年の長男は、
ひらがながなかなか定着せず、
計算もよく間違える。
- ノートを見ても、
- 空白が多くて、
- 書いてある文字もどこかあやしい。
でも、
先生には「そのうち慣れますよ」と笑われてしまって。
家では
夫に「考えすぎだって」と軽くあしらわれて、
どこにも安心できる場所がなかった。
「うちの子、学習障害かもしれない」
そう思ったとき、
検索で出てくるのは
診断名や専門機関ばかり。
でも、
そんな大ごとのように扱っていいのかも、わからなかった。
誰かに相談する前に、
まず自分の不安を整理したくて──
ようやくたどり着いたのが、
「学習障害の相談先」という言葉だった。
この記事では、
「学習障害(LD)かもしれない」と感じたときに、
どこに・何を・どう相談すればいいのかを、
家庭の視点で丁寧にまとめています。
この記事を読むとわかること
- 小学生の子どもが見せる「学習のつまずき」とは?
- 「発達には問題ない」と言われた子の見逃されやすい特徴
- 保健センター・学校・医療、それぞれの相談先の違いと役割
- 家庭の中で気づける「初期サイン」と、安心の土台づくり
- そして、自分を責め続けてきた母親自身の気持ちを整える選択肢
「なんでできないの?」と声を荒げてしまったあと、
寝顔を見ながら何度も後悔して、
涙がにじんだ日もありましたよね。
子どものことが心配で、
自分のせいだと思い込んで、
でも本当は、
誰よりも理解してあげたかっただけなんです。
ここまで、ひとりで本当によくがんばってきたと思います。
そんなあなたに届けたいのが、
「学習障害に悩んでいた私が、『子ども』ではなく『自分自身』の心を整える時間に出会えた──3週間集中再安心サポート」です。
このサポートでは、
- 1週目に「この子のつまずき方」を見つけ、
- 2週目は「どう伝えたら届くか」を一緒に探っていきます。
- そして3週目には、「怒らなくても伝わる関係」を家庭の中に整えていきます。
「やり方」ではなく
「見方」が変わることで、
わが子の努力やがんばりにも、自然と目が向くようになっていきます。
どうしたらいいかわからなかった気持ちに、
少しずつ答えが見えてくる時間。
ここから、一緒に整えていけたらうれしいです。
監修者
株式会社Osaka-Child所属 小児神経科医
- 名前: 三浦あすか
- 出身地: 兵庫県西宮市
- 最終学歴: 神戸大学医学部 小児科専攻
- 専門分野: 小児神経、DCD(協調運動障害)、発達性ディスプラクシア、HSP気質の子ども支援
- 職歴: 兵庫県立こども病院 小児神経センター勤務(11年)
専門分野について一言: 「できないことの奥にある“がんばっているサイン”を、もっと社会全体で受けとめていけたらと思っています。」
監修者
株式会社Osaka-Child所属 臨床心理専攻大学教授
- 名前: 森本哲夫
- 出身地: 奈良県
- 最終学歴: 米国ハーバード大学心理学部 博士課程修了
- 専門分野: 臨床心理学、発達心理学
- 職歴: ハーバード大学研究員(5年)、大阪大学人間科学部教授
専門分野について一言: 「心の成長とは、自己理解の旅でもあります。その旅のお手伝いができれば幸いです。」
「相談してもいいのかな…」と夜中に検索していたあなたへ
- 「どうしてこの子は、ひらがなを何度教えても覚えられないの?」
- 「漢字も計算も、また忘れてる…」
──そんなふうに悩むほど、自分の関わり方を責めてしまう。
学校では「様子を見ましょう」で終わり、
夫にも「気にしすぎ」と言われる。
でも本当は、「一緒に考えよう」って誰かに言ってほしかった。
学習障害に悩んでいた私が、『子ども』ではなく『自分自身』の心を整える時間に出会えた──3週間集中再安心サポートは、
「診断の前」の迷いや孤独に寄り添う、母親のための心理サポートです。
こんな方におすすめです
- 子どもの苦手さに気づいているけれど、誰に相談すればいいかわからない
- 「育て方が悪かったのかな」と感じて、自分を責めてきた
- 相談しても、気にしすぎと言われて傷ついた経験がある
- 家族にも頼れず、モヤモヤをずっと一人で抱えている
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 1月20日(火)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと2名様限定』
※銀行振込限定・先着順
そして──
少しずつ「この子らしさ」が見えてきた今、
「私自身のこれから」にも目を向けてみたくなった方へ。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
「母としての安心」を土台に、
「わたしとしての人生」を再設計する3週間。
子どものことで手いっぱいだった日々から、
自分のための時間を取り戻す日常へ。
- 子育ての悩みが少し落ち着いてきた
- でも「自分の時間が止まっている」と感じている
- 母親だけで終わりたくない気持ちがある
このプログラムでは、
「役割だけでない私」に立ち返るサポートを行います。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
「ちゃんとしてるのに、苦しい」
「頑張ってるのに、うまくいかない」
——そんな違和感を抱えたまま、ずっと我慢していませんか?
LINEで3分セルフ診断ができます。
あなたの“今の感覚”の正体が、見えてきます。
最初に相談すべき「学習障害の相談先」とは?|初期対応と不安の整理

ずっと「様子を見ているだけ」だった。
でも、ココロのどこかでは、何か違和感を抱えていた気がする。
- 勉強をしていると、どうしてもつまずきが目立ってくる。
- 繰り返し教えても、次の日には忘れている。
「頑張っているのに、どうしてこんなにできないんだろう」
そう思うようになっていった。
学校や夫に相談しても、
返ってくる言葉はいつも曖昧だった。
- 「そのうち慣れるよ」
- 「みんなそういう時期あるし」
──でも、
その「みんな」と同じじゃない気がして、
気持ちが置き去りになったままだった。
ここでは、
そんな迷いを抱えながらも、
子どもの「今」にちゃんと向き合おうとしている方に向けて、
安心して相談を始められる場所を、
段階ごとに整理していきます。
ポイント
不安を抱えたまま立ち止まるより、
まずは「話してみる」ことから始めていいんです。
「勉強が苦手な子ども」…どこに相談すればいい?
最初は、
「ただ苦手なだけかも」と受け止めていた。
でも、
教えたことが翌日にはゼロになっているような感覚が続くと、
「このままじゃいけない」と思いはじめた。
ただ、
いざ動こうとしても、
どこに相談すればいいのかがわからない。
- 医療?
- 学校?
- 支援センター?
- カウンセラー?
選択肢が多すぎて、
結局また足が止まってしまっていた。
一番大事なのは、
「何に困っているのか」を言葉にしてみること。
たとえば──
- ひらがなを何度教えても忘れる
- 簡単な計算に時間がかかる
- 教えた内容が伝わっていないように感じる
- 宿題になると親子の関係がピリピリする
こうした状態が続くとき、
学習障害(LD)の初期サインとして整理することもできます。
でも、
だからといって、
いきなり診断や病院に飛び込まなくてもいいんです。
「この状況、どう捉えたらいいのか聞いてほしい」
そんな思いで扉をたたける場所──
そこが「最初の相談先」になります。
小学生の学習障害を相談できる場所は?
小学生になると、
「できる子」と「できない子」の差が
見えやすくなります。
ポイント
特に2〜3年生になると、
授業のスピードや内容についていけなくなる子も出てきます。
読み書きや計算に顕著なつまずきがある場合、
学習障害(LD)としての視点を持つことが重要になってきます。
そのとき相談できる場所には、
次のようなものがあります。
- 学校(担任、特別支援コーディネーター)
- 地域の発達障害者支援センター・教育相談室
- 民間の心理相談・カウンセリング窓口
学校の先生は、
日々の様子をいちばん近くで見ている立場です。
ポイント
家庭で気になることがあれば、
まず相談してみることで、
新しい視点が得られることもあります。
また、
教育センターや支援センターでは、
「診断前の相談」も受け入れてくれる体制があります。
「うちの子、検査が必要?」
そんな問いを整理してくれる場所としても機能しています。
民間のカウンセリングを選ぶ方も増えてきました。
とくに、
「家族以外に気持ちを受け止めてもらう場所」があることで、
母親自身が安心を取り戻すケースも多いんです。
まずは保健センター・小児科も視野に
- 「病院に行くのは大げさかも」
- 「まだ診断って段階じゃない気がする」
そう感じて、ずっと迷っていた。
でも、
そんなときこそ活用したいのが、
- 保健センター
- 小児科
という
「間口の広い相談先」です。
保健センターでは、
家庭での困りごとを丁寧に聞いてくれる担当者がいます。
学習のことだけでなく、
子どもの発達や育ち全体について、
気軽に相談できる場です。
小児科では、
発熱や風邪だけでなく、
「生活面の違和感」も話題にして大丈夫。
医師から
「専門機関に相談してみませんか」と
提案してもらえることもあります。
「もっと早く話してみればよかった」
──そう感じる母親の声も、実際に多く届いています。
気づいたタイミングが、その子と向き合うチャンスになる。
そう信じて、一歩だけ動き出してみてください。
“誰に相談したらいいかわからない”と立ち止まっていた方へ
「この子のこと、どこに相談すればいいの…?」
そんなふうに迷っていた母親たちが、一歩を踏み出せたサポートがあります。
「学習障害に悩んでいた私が、『子ども』ではなく『自分自身』の心を整える時間に出会えた──3週間集中再安心サポート」
- 「相談の仕方がわからない」
- 「いきなり診断は不安」──
そんな迷いの段階から、一緒に気持ちを整えていく個別支援です。
「診断が必要か迷うとき」に考えたいこと|焦らず進むステップ

“診断の前に整える安心”を、ここから始めてみませんか?
- 「診断って本当に必要?」
- 「もっと様子を見た方がいいの?」
──そんな迷いに寄り添う、診断の「前」から始められる支援があります。
「学習障害に悩んでいた私が、『子ども』ではなく『自分自身』の心を整える時間に出会えた──3週間集中再安心サポート」
「診断を受ける前に」家庭でできることを一緒に考える、3週間の個別サポートです。
- 「今のままで大丈夫なのか」
- 「でも、診断ってそんなに急ぐものなの?」
いろんな思いが頭の中で交差して、
どうしていいのかわからなくなっていた。
この段階がいちばん苦しい。
でも、
それは「この子のことをちゃんと考えている証」なんだと思う。
だからこそ、すぐに答えを出そうとしなくていい。
ここでは、
そんな迷いの中にいるときに、
どんなステップで進んでいけるのかを整理していきます。
焦らずに、いまできることをひとつずつ見つけていくこと。それが、安心の土台になる気がする。
学習障害の診断は必要?判断に迷うときのヒント
診断って、
どうしても特別なものに感じてしまう。
「何か決定的なこと」を突きつけられるようで、
正直こわかった。
でも、
それでも迷っているということは、
やっぱり向き合おうとしている証拠だったんですよね。
ポイント
学習障害(LD)の診断は、
決して「確定させるための判定」ではありません。
本当は、
子どもの困りごとを整理し、
よりよいサポートに繋げていくための道しるべなんです。
実際に診断が検討されるのは、
次のような状況が続いているときです。
- 読み書きや計算のつまずきが長く続いている
- 周囲の支援や努力だけでは補えない
- 日常生活や学校生活に影響が出始めている
それでも「すぐに診断」と決めなくていい。
必要なことは、
「この状態をどう見ていけばいいか」を
誰かと一緒に考えてみること。
「どうしてこんなに苦手なんだろう」
その問いに向き合ったとき、
診断という選択肢がやっと見えてくる気がした。
支援センター・専門機関の役割とは
- 誰に相談したらいいのかわからない。
- いきなり病院に行くのも不安だし、学校にも言いにくい。
そう感じている方にとって、
支援センターは
「安心して話せる中間地点」のような存在です。
発達障害者支援センター
教育相談室
には、
- 子どもの発達や学習の困りごとに詳しいスタッフがいて
- 保護者の気持ちも丁寧に聞いてくれて
- 必要に応じて医療機関や支援制度にもつなげてくれる
──そんな役割があります。
「診断が必要かどうか」だけに
焦点をあてるのではなく、
まずは
「何が起きているのか」を整理することから始めていいんです。
「今のままじゃしんどい」
その声を、誰かに聞いてもらうだけで、
視界が少しずつ開けていく感覚がありますよね。
「診断が怖い」と感じるのはおかしくない
診断って、こわい。
それが正直な気持ちでした。
- 「この子に『なにかある』って認めることになりそうで」
- 「いったん診断されたら、もう普通には戻れないような気がして」
そんなふうに感じている自分が、
間違ってるように思えていた。
でも、
診断がこわいのは、
「この子のことをちゃんと考えてきたから」。
誰よりも、
この子のことを思っているからこそ、
決めつけたくなかっただけなんだと気づいた。
学習障害(LD)の診断がついたあと、
- 学校からの支援が受けやすくなった
- 無理に合わせることをやめられた
- 子ども自身が「できる方法」で学べるようになった
──そうやって、
安心のステップを踏めるようになった家庭もたくさんあります。
「こわい」と感じるのは、自然なこと。
その気持ちも抱えたままでいい。
だけど、
前に進みたかったら、
誰かと一緒にその不安を言葉にしていくことで、
少しずつ光が差し込んでくるような気がしています。
カウンセリングという「もうひとつの相談先」|診断だけが答えじゃない
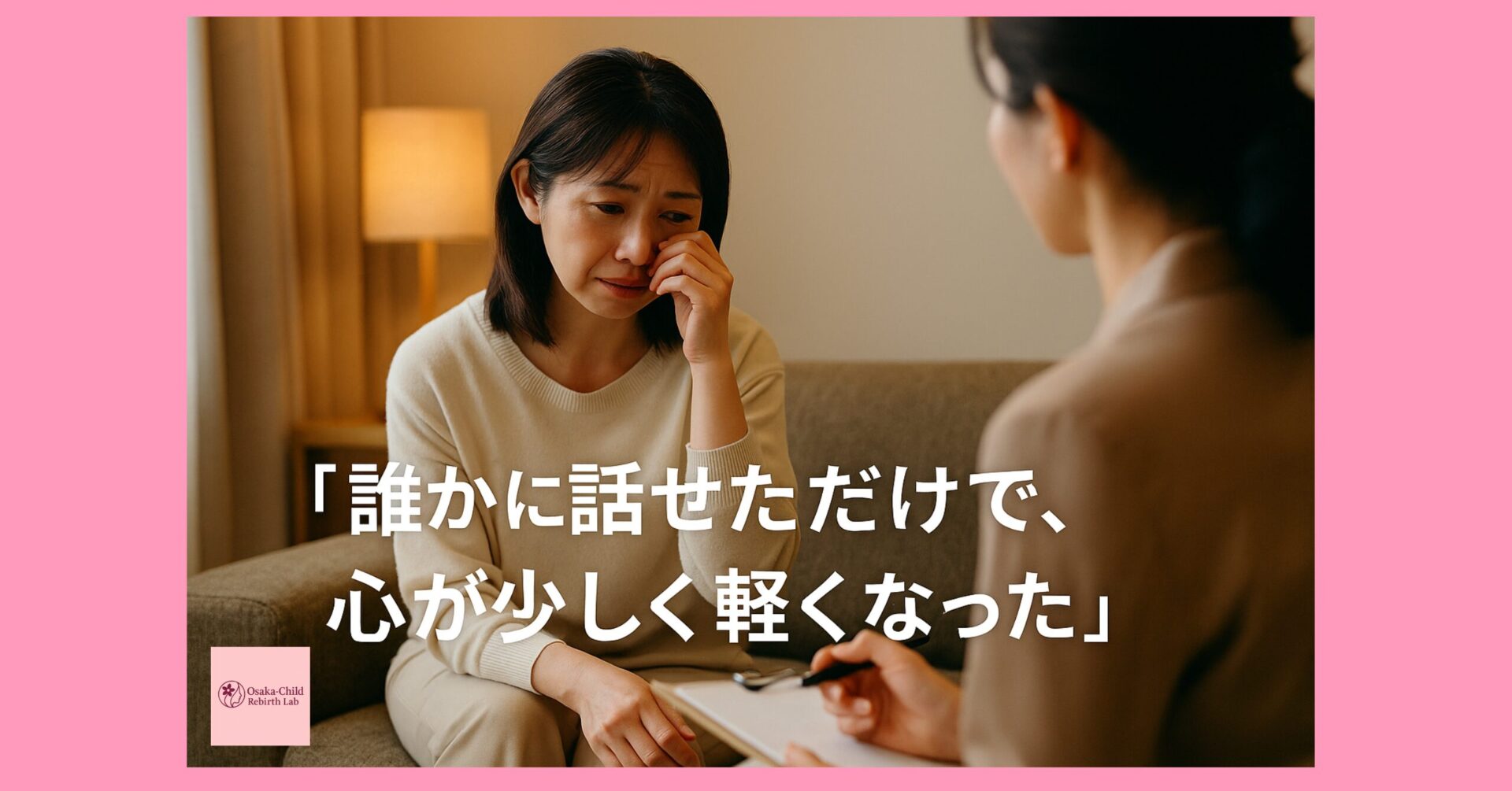
「“診断までは早いのかも”と迷いながら、ここまで読み進めたあなたへ
- 「どうしてこんなに計算が苦手なんだろう」
- 「また間違えてる…ちゃんと見てたはずなのに」
──子どもの「できなさ」を前に、気づけばため息ばかりになっていた。
「うちは大丈夫よ」と言うママ友。
「気にしすぎ」と流す夫。
誰も悪気はないけど、「わかってほしい」気持ちはどこにも届かなかった。
学習障害に悩んでいた私が、『子ども』ではなく『自分自身』の心を整える時間に出会えた──3週間集中再安心サポートは、
「相談の一歩手前」にある孤独や戸惑いに寄り添う、母親のための心理サポートです。
こんな方におすすめです
- 「このままでいいのかな…」と不安を抱え続けている
- 育児の情報を調べるほど、自分だけが間違っている気がする
- 話しても理解されず、ますます言えなくなっている
- 「専門家に相談する勇気」までは、まだ持てていない
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 1月20日(火)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと2名様限定』
※銀行振込限定・先着順
そして──
子どもと向き合いながら、「自分の人生」にも意識が向きはじめた方へ。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
「母としての時間」を支えに、
「私自身の未来」を育て直す3週間。
やっと少し落ち着いてきた今だから、
「本当の自分」に目を向けてみませんか。
- 気づけば、自分のことはずっと後回しにしてきた
- 母としてだけでなく、「私らしく」生き直したい
- 新しい一歩を、もう一度踏み出したい気持ちがある
このプログラムでは、
「母」を軸にしてきた人生を、やさしく「自分軸」へと再設計します。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
「診断を受けた方がいいのかな」
そんなふうに迷いながら、
でもココロのどこかでは、
「違う形で誰かに話したい」と思っていた。
学校や医療に相談するのが正解のように感じても、
本当はまず、
自分の気持ちを受け止めてほしいだけだった。
カウンセリングは、
「この子の困りごと」を解決する場ではありません。
でも、
「母親として抱えてきた気持ち」を整理していく中で、
新しい向き合い方が見えてくる場所でもあるんですよね。
学習障害でもカウンセリングは効果ある?
正直、
最初は
「カウンセリングなんて関係ない」と思っていた。
勉強のことで困っているのに、
話すだけで何が変わるんだろうって。
でも、
実際に行ってみると、
何かを「治す」場所じゃなく、
ただ、
「話してもいい場所」だったんです。
学習障害(LD)に関する専門的なアドバイスではなくても、
日々の
- 「イライラ」
- 「不安」
- 「誰にも言えなかった気持ち」
を聞いてもらえただけで、
少し肩の力が抜けたような感覚がありました。
- 子どもに優しくしたいのに、毎日怒ってばかりだった
- 自分ばかり頑張っている気がして、苦しかった
- 「このままじゃダメだ」とわかっていても、動けなかった
そういうココロの声を、
一つずつ整理していける場所だったんですよね。
何かがすぐに変わるわけじゃないけど、
「自分が崩れずにいるための支え」になる気がしています。
「誰かに話せたことでラクになれた」母親の声
「この子のことを話したのって、
もしかしたら初めてだったかもしれない」
そんなふうに感じた時間がありました。
学校でも、
家族の中でも、
- 「甘やかしてる」
- 「親のせい」──
そんな言葉がどこかにある気がして、
ずっと黙っていた。
でも本当は、
ただ「誰かに話を聞いてほしかった」だけなんですよね。
- カウンセラーは、何も評価しなかった。
- 泣いてもいいし、黙っていてもよかった。
「そのままでいいですよ」と言われたとき、
ずっと張りつめていたものが、
一気にゆるんでいく感覚があった。
「ただ話すだけ」なのに、
話したあとのココロの軽さは、
ちょっと信じられないくらいだった。
──うまく言えないけど、
「私も大切にされていい」と思えたことが、
いちばん大きかった気がします。
「関わり方」を整える支援とは?
子どもに合った勉強方法を探すことも大事。
でも、
その前に、
「この子とどう関わるか」を
整える時間が必要だった。
カウンセリングでは、
「教え方」よりも
「向き合い方」を
一緒に考えてくれます。
どうやって接すればいいのか、
自分を責めすぎないで済む方法が見えてくるんです。
- 何度も同じことで怒ってしまう
- 頑張らせようとするほど、関係がぎくしゃくする
- 本当は、この子の味方でいたいのに、うまくいかない
──そんな関係の「ほつれ」を、
やさしく結びなおすような支援でした。
母親が安心できると、子どもの表情も変わるんですよね。
家庭の空気が少しずつやわらかくなっていって、
「うまく言えないけど、前よりラクになった」
そんな感覚が、関係を大きく変えていく力になる気がしています。
無料診断|あなたの“心のパターン”を知る
「誰に相談すればいいのかわからない…」
そんな方のために、LINEで「キーワード」を送るだけで診断できるサービスをご用意しました。
LINEに「学習障害 相談」と入力して送信してください。
あなたの悩みに合った視点とアドバイスを、すぐにお届けします。
「相談先、どこが正解?」と迷ったときに見る地図
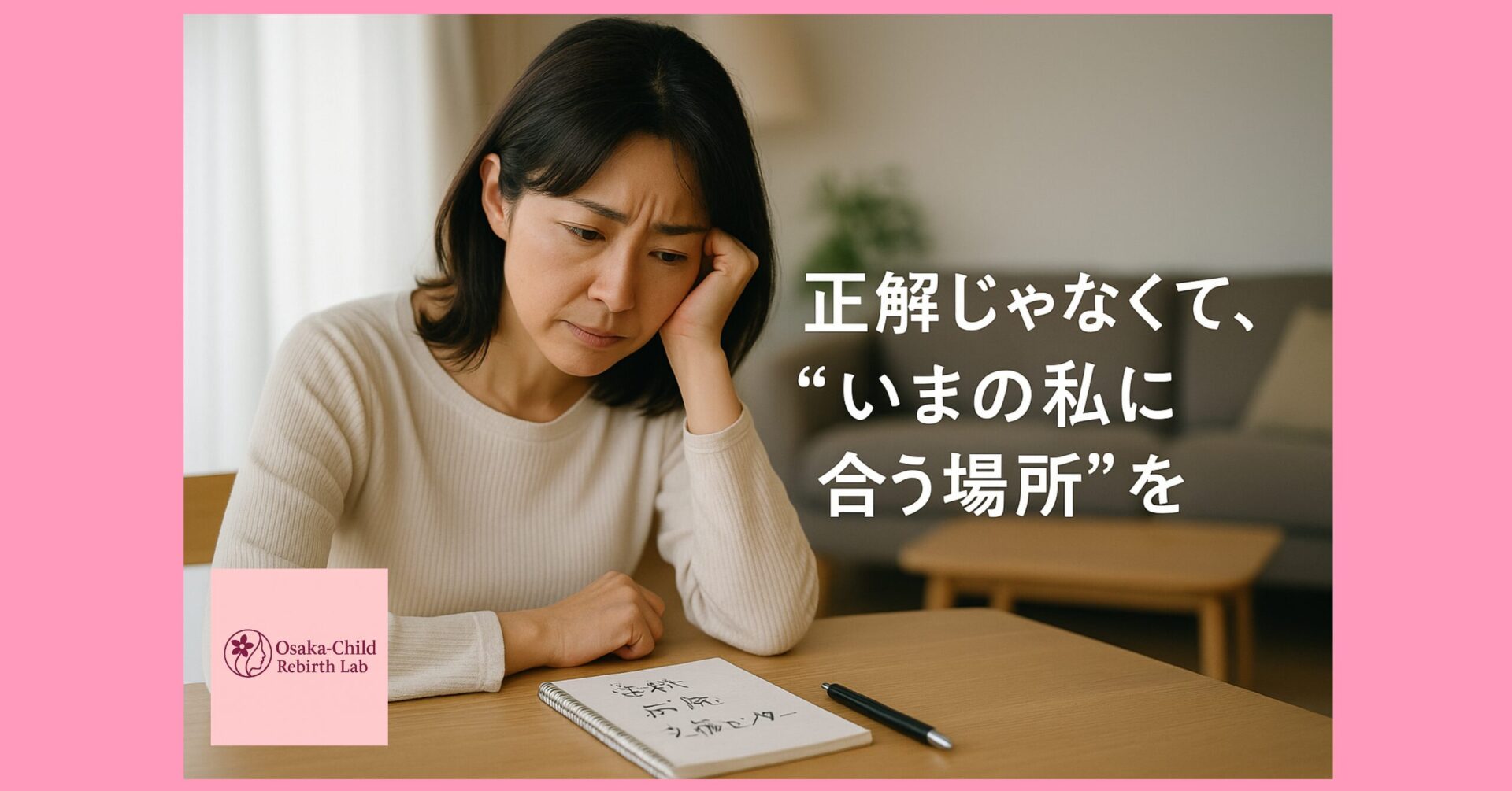
「この子、どこに相談すればいいんだろう」
そう思って調べ始めたのに、
情報が増えるほど、選べなくなっていった。
- 病院?
- 支援センター?
- 学校?
──正しさを求めているつもりなのに、
いつのまにか
「間違えたくない不安」に変わっていた気がする。
でも本当は、「正解の場所」なんて、誰にも決められない。
子どもの状態はもちろんだけど、
今のあなた自身の気持ちに合う場所かどうかが、
とても大切な視点なんです。
ここでは、
「どこに相談すればいいかわからない」と感じている状態から、
ほんの少し前に進めるように、
3つの切り口で整理していきます。
正解よりも「今のあなたに合う場所」を選ぶ
「どこに行くのが正解なんだろう」
そう考え始めると、
どの選択肢にも決め手が見つからなくて、
時間だけが過ぎていった。
誰かに相談したい。
でも、
どこを選んでも「それでいいのかな」と不安になる。
調べれば調べるほど、
頭がいっぱいになっていた気がします。
でも今になって思うのは、
「正しい場所」じゃなくて、
「行ける場所」でよかったんですよね。
そのときの自分にとって、
負担が少なく、
安心できそうなところ。
それが、最初に選ぶ相談先でよかったんです。
ポイント
いきなり病院に行くのがしんどいなら、
まず保健センターでもいい。
まずは
- 話せる場所、
- 否定されない場所。
「ちゃんと聞いてもらえた」
──そう感じられることが、何よりも支えになっていく。
子どもの状態がまだ「初期段階」の場合は?
ちょっと気になるところがある。
でも、深刻というわけでもない。
そういうとき、相談することにためらいが出てしまう。
- 「これくらいで相談していいのかな」
- 「気にしすぎなだけだったらどうしよう」
そんな気持ちを抱えながら、
ずっと迷っていた方もいるはずです。
でも、
早めに動くことは、決して間違いじゃない。
むしろ、
「初期の段階だからこそ相談できる場所」もあるんです。
- 保健センター
- 子育て支援拠点
- 小児科
- 学校の先生など。
重たい判断を求められる場所じゃなくて、
「ちょっと話を聞いてもらいたい」ときに頼れる窓口もちゃんとあります。
気になった時点で、もう動いていいんです。
それは、
「この子をちゃんと見てきた証」でもありますから。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「読み・書き・計算のつまずきには、何か理由があるのかも…」
そんなふうに感じた方へ。
学習障害の特徴や家庭でできる対応法を、わかりやすく整理した解説記事をご紹介します。
👉 どう向き合えばいいのか迷ったときに読んでほしい「学習障害の基本」ガイド
-

-
参考学習障害とは?読み書き・計算が「できない理由」と家庭でできる対応法【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「どうしてこんなに教えてるのに、できないんだろう」 そう思ったあとで、 つい声を荒ら ...
続きを見る
「発達障害かも」でも確信が持てないとき
「発達障害なのかな…」と、
何度も思いながら、
確信が持てないまま動けなかった。
そんなふうに悩んできた方は、
とても多いです。
見た目には問題なさそうで、
周りからも理解されにくい。
「ただの性格でしょ」と言われるたびに、
自分の感覚が間違っている気がしてきて、
ますます誰にも話せなくなっていった。
でも、
不安があるということ自体が、
十分な「理由」なんです。
診断の有無よりも先に、
今の気持ちを言葉にできる場所があるだけで、
呼吸がしやすくなります。
確信じゃなくていい。
「なんとなく気になっている」
その感覚に目を向けた時点で、
すでに向き合い始めているということなんです。
子どもの学習障害に悩んでいた私が、「自分自身」のココロを整えた理由

子どもの「できなさ」に向き合おうとすればするほど、
自分を責める気持ちが強くなっていった。
学習障害(LD)の情報を集めるたび、
正しい関わりを探すたび、
「私は間違っていたのかも」と苦しくなっていった。
でもふと立ち止まったときに、気づいたことがある。
しんどかったのは、
子どもよりも、
母親である自分自身のココロが整っていなかったからだった。
ここでは、
「この子のために」とがんばってきた母親が、
「まずは自分自身を整える」という視点に出会うまでのプロセスをお伝えします。
「この子を支えるには、まず私の不安を整えることだった」
どれだけ調べても
どれだけ考えても
気持ちは晴れなかった。
頭ではわかっているのに、ココロがついていかない。
学習障害(LD)の可能性が気になり始めたとき、
揺れていたのは子どもではなく、
私自身のほうだった。
誰かを頼っていいのかもわからないまま、
毎日モヤモヤを抱えて過ごしていた。
眠れない夜も増えていって、
「こんな気持ちのままで、本当にこの子を支えられるのかな」とさえ感じていた。
でも、ようやく気づけた。
「まず私が安心しないと、子どもの安心も受け止められない」って。
ポイント
「子どもの問題」に見えていたけど、
最初に必要だったのは、
私の不安に名前をつけることだったんです。
誰かに聞いてもらえたとき、
初めて「大丈夫かもしれない」って思えた。
あの瞬間から少しずつ、子どもへの見え方も変わっていった気がします。
母親自身が安心できると、子どもも少しずつ変わりはじめた
この子が変わった、というよりも、
私が変わった。
そう感じる瞬間が、少しずつ増えていった。
前はいつも張り詰めていた。
イライラしたくないのに怒ってしまって、
「またやってしまった」と落ち込む日々だった。
でも、
自分の気持ちを認めてあげられるようになったら、
子どものことも否定せずに見られるようになっていった。
小さなことにも「できたね」と声をかけられた。
すると、
子どもの
目つきも言葉も
やわらかくなっていったんです。
安心は、伝染する。
母親が整うと、
そのあたたかさが、
静かに家庭全体に広がっていく。
あの頃の私は、それを実感しながら、少しずつ笑えるようになっていった。
学習障害に悩んでいた私が、「子ども」ではなく「自分自身」のココロを整える時間に出会えた──3週間集中再安心サポート
あのとき必要だったのは、
「正しい接し方」じゃなかった。
それよりも、
「私自身が安心できる場所」だった。
この「学習障害に悩んでいた私が、『子ども』ではなく『自分自身』の心を整える時間に出会えた──3週間集中再安心サポート」では、
学習障害(LD)の情報だけでなく、
母親自身の気持ちの整理にじっくり向き合います。
- 「私ばかり責めていた」
- 「泣きたくても泣けなかった」
──そんな思いも、安心して話せる場があります。
ここから始めるのは、
「子どもを変えること」ではありません。
まず、
自分の視点や気持ちが整うことで、
親子の関係がやわらかく動き出していく。
その流れを、丁寧に支えてくれる時間です。
子どもの学習障害(LD)に悩んでいた私が、
「どうすればこの子を変えられるか」ではなく、
「どうすれば私自身が安心できるか」という視点に出会えたこと。
それが、いちばんの転機になりました。
子どもよりも、まず自分の心を整える時間に出会えた
- 「この子、どこに相談すればいいのかわからない」
- 「でも、誰にも言えない」
そうやって、
私はずっとひとりで悩んでいました。
困っているのに、
「どこにも当てはまらない」ように感じて。
支援機関の情報を読んでも、
診断名を聞いても、
なぜか気持ちがついていかなくて。
一番しんどかったのは、
説明のつかないこの孤独感だった気がします。
このサポートは、
そんな私の「こころの置き場所」になってくれたものでした。
診断名よりも先に、
母親である私の安心を整える──。
その視点に出会えたことで、
ようやく私たち親子は、スタート地点に立てた気がしています。
この3週間では、こんなふうに進んでいきます。
STEP①|「どうして私ばっかり…」を言葉にする時間
自分の中に溜め込んでいた
「言えなかった気持ち」を、
一緒に整理していきます。
「何度教えても伝わらない…」そんな日々の違和感を、
感覚に名前をつけていくステップです。
無料LINE診断|今のあなたに必要なサポートは?
『何から始めればいいかわからない…』そんなあなたへ。
LINEで「数字」を入力するだけで、今のあなたに合ったサポート商品を診断できます。
今すぐLINEに【 4 】と入力してください。
「学習障害に悩んでいた私が、『子ども』ではなく『自分自身』の心を整える時間に出会えた──3週間集中再安心サポート」の内容と、
あなたに「ぴったりの理由」が届きます。
STEP②|「この子に届く関わり方」を見つける時間
- 音の聞き取り
- 文字の理解
- 記憶のズレ
「この子らしさ」をいっしょに言語化しながら、
「こう伝えれば届くんだ」と体感していきます。
STEP③|「私たちのペース」で育てるまなざし
支援や診断に振り回されない、
母子だけの「安心の関係性」を育てていきます。
- 焦りより、対話。
- コントロールより、信頼。
その切り替えが、
私の中にゆっくり根づいていきました。
3週間の終わりには、
子どもの表情が少しやわらいでいました。
私の声に耳を傾けてくれる場面が増えて、
毎日の空気がすこし穏やかに変わっていきました。
あのときの私に、こう伝えたくなります。
「誰かに『相談する前に』、自分自身の気持ちと向き合える時間が必要だったんだよ」って。
「母親の安心」が、この子の安心に必ずつながっていく。
その感覚を、あなたにも受け取ってほしいです。
“相談先を探す前に、自分の気持ちを整える選択肢
「相談したいけど、どこに頼ればいいのかわからない…」
そんな戸惑いの中で、ずっとひとりで頑張ってきたあなたへ。
この3週間が、“母としての安心”を取り戻す転機になります。
「診断がつくかどうか」よりも、
「この子とどう向き合えばいいのか」を一緒に見つけていく時間です。
焦らなくていい。“わからないまま”で動き出しても大丈夫。
まずは、あなた自身の気持ちを整えることから始めませんか?
まとめ|「どうしたらいいのかわからなかった」時間に、やっと言葉が見つかった
あの頃の私は、
何に悩んでいたのかも、
うまく言えなかった。
誰に何を相談したらいいのか、
そのことすら自信が持てなくて。
それでも毎日、
「このままでいいのかな」と思いながら過ごしていました。
- 子どものノートを見て、また同じところでつまずいていたとき。
- なんて声をかければいいかわからず、ただ見守るしかなかった夜。
そのたびに、自分の無力さばかりが胸に残っていた気がします。
でも今なら言えます。
本当に苦しかったのは、
子どもの課題じゃなくて、
「自分はどうしたらいいのか」がわからないまま、
立ち尽くしていた私自身の不安だったんですよね。
この記事で、一緒に見つけてきた答えをあらためて整理しておきます。
この記事で分かったこと
- 学習障害(LD)のつまずきは、がんばり不足や甘えとは違うということ
- 「そのうちできるようになる」と言われても、母親の不安が消えるわけではないということ
- 医療や診断だけでなく、「話せる場所」が必要だったということ
- 自分の気持ちに向き合うことが、最初の一歩だったということ
- 子どもの学び方には、その子らしいリズムがあるということ
「じゃあ、今の私にできることは?」
勉強を教えるたび、なぜこんなに伝わらないのか──
怒ったあとで、自分ばかり責めてきた方も多いです。
でもこの記事を読み終えた今、
- 「子どもの特性」
- 「私の不安」
が絡み合っていたことに気づき始めた方もいます。
その関係を、ここから整えていけます。
「学習障害に悩んでいた私が、『子ども』ではなく『自分自身』の心を整える時間に出会えた──3週間集中再安心サポート」は、
- 母親の感情整理
- 子どもの特性理解
- 家庭での関わり実践
を3ステップで支えるプログラム。
「何度教えても伝わらないのはなぜ?」から始まり、
「この子らしさ」に合った
- 接し方
- 声かけ
- 環境づくり
まで、週ごとのセッション+日々の伴走で一緒に取り組みます。
もう、正しさで押しつけなくていい。責める関係を終わらせられます。
[/st-mybox]
一緒に迷って、一緒に見つけていく3週間。
あなただけの「わが子との関係づくり」を、ここから始めてください。
「“誰に相談したらいいかも分からなかった”──そんな時間を越えてきたあなたへ
「この子の『できなさ』は、私の育て方のせいなのかな」
「誰かに相談しても、また否定されるだけかもしれない」
そんなふうに悩んできたあなたに届いた声があります。
──「子どもの苦手さを、『悪いこと』じゃなく見られるようになった」
「理解の入口」が見えたとき、母子の関係が少しずつ変わり始めたという方もいます。
学習障害に悩んでいた私が、『子ども』ではなく『自分自身』の心を整える時間に出会えた──3週間集中再安心サポートは、
母親ひとりで抱えてきた不安を、言葉にしてもいいと思える場所です。
こんな方におすすめです
- 「様子を見ましょう」と言われ続け、立ち止まっていた
- 相談しても話がすれ違い、ますます孤独を感じた
- 子どもを信じたいのに、焦りや不安に飲まれてしまう
- 診断より先に、「向き合える私」になりたいと思っている
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 1月20日(火)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと2名様限定』
※銀行振込限定・先着順
ネットバンキングのご利用で、今すぐ開始することが可能です。
▶ 『この子とちゃんと向き合える私になりたい』と感じている方へ
そして──
「この子と歩いてきた道のり」を少し肯定できた今、
「私自身のこれから」にも目を向けてみませんか。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
「母として頑張ってきた時間」を、
「自分らしく生き直す力」に変えていく3週間。
- 今の自分に、ほんの少しでも余白ができてきた
- 母としてだけでなく、自分としても大切に生きたい
- これからの人生を、私自身の選択で動かしていきたい
このプログラムでは、
「母の役割を越えた私」に出会うサポートを行います。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
すでに診断済みの方も、そのまま詳細ページへ進めます。
あなたの心と体に合ったサポートを、今すぐ確認してみてください。








