
学校での発表や友だちや親戚の子と話をしている状況で
子どもの言葉がつまる瞬間を見て、
これから先、他者とのコミュニケーションに困るだろうなと
あなたは胸が締めつけられるように痛むときがありますよね。
- 音読の順番が近づくとソワソワして落ち着かない息子、
- 発表で詰まって笑われて下を向く姿。
それを横で見ているだけで
「どうして私ばかりが苦しいんだろう」と
涙があふれてきた日もありましたよね。
このココロの動きは、
吃音の子どもを育てている
あなたにしかわからない感情です。
家族間ではスムーズに話せたのに
外に出るとうまく話せないことに焦り、
つい怒鳴ってしまいたくなった自分をあとから責めて落ち込む。
夫には
「いつか話せるようになるよ、気にしすぎ」と言われてしまい、
孤独な夜を過ごしてきました。
母親として、
これ以上どうしたらいいのか、
わからなくなってしまいますよね。
この記事は、
子どもの吃音に悩み、
「私の育て方が悪いからかも」と罪悪感を抱えながらも、
どう向き合えばいいのか答えを探している母親に向けて書かれています。
吃音の仕組みや特徴を整理し、
学校生活での困りごとや家庭でできる関わり方までまとめることで、
「一人で背負わなくていい」と安心できる入り口になるよう構成しています。
ここで得られるのは、次の5つです。
この記事を読むとわかること
- 吃音とは何かをわかりやすく整理できる
- 小学生で起こりやすい吃音の困りごとを把握できる
- ADHDやASDなどとの違いや重なりを理解できる
- 家庭でできる関わり方の工夫を知ることができる
- 学校や先生とどうつながればいいか視点を持てる
他者と話をして自分の気持ちや考えを伝える場面はたくさんあるのに、
わが子は吃音症状でうまくできない。
何度も言葉がつまるわが子を前にして、
つい強く注意してしまいたくなる日もありましたよね。
- 「吃音のせいで授業で困っているのでは」
- 「私の育て方が悪かったのでは」
と胸が痛む。
責めてしまったあとに後悔して、
夫や子どもが眠ったあと夜になると自分を責め直す。
周りからは「気にしすぎ」と言われても、
吃音を抱える子どもの姿を
一番近くで見ている母親の不安は消えません。
守りたいだけなのに、
どう関わればいいのか分からなくなる瞬間が積み重なってきた
──そんな気持ちに寄り添いながら、
この先にできる子どもの吃音への理解と支え方を整理していきます。
ここまで、本当によくがんばってきました。
吃音のある子どもを抱えている母親のあなたにとって、
毎日の生活は想像以上にココロを揺さぶられます。
- 授業での音読で言葉がつまるとき、
- 吃音を理由に友達に笑われるとき、
- 発表の場を嫌がって俯いてしまうとき。
母親は胸を締めつけられるように感じ、
- 「どうしてできないの?」
- 「何度言っても変わらないのは私のせい?」と
罪悪感に苦しんできました。
吃音が出るわが子を支えたいのに、
焦って責めてしまい、
「もっとうまく話をしてよ」と
無理な要求を無意識のうちに思ってきたことに
罪悪感を抱えていました。
そんなあなたに届けたいのが、
「子どもに吃音の症状が現れ、『私のせいかも』と抱え込んでいた母が、安心を取り戻し笑顔で支えられるようになる──3週間集中再安心サポート」です。
このサポートは、吃音を「治す」ことを目的にするのではなく、
母親自身が安心して見守れる関わりを整えることに焦点を置いています。
- 1週目は、母親の中に積み重なった「吃音は自分のせい」という罪悪感を丁寧に言葉にし、安ココロの土台を作ります。LINEでのやり取りや個別対話を通して、抱えてきた不安や孤独を安心の中で整理していきます。
- 2週目は、吃音の脳の仕組みや特徴をわかりやすく共有しながら、「親のせいではない」という理解を一緒に育てていきます。学校生活での困りごとを整理し、母親が心を支えられるよう伴走します。
- 3週目は、「待つ・見守る」関わりを整え、吃音が出ても「大丈夫」と表情で伝えられる母親へと変わっていきます。家庭の空気がやさしくなることで、子どもは「話しても安心」と感じられるようになり、学校や友達との関わりにも前向きな変化が広がります。
この3週間を通して、
母親は
「吃音があるから困る子」ではなく、
「吃音があっても挑戦できる子」としてわが子を信じられるようになります。
そして子どもは
「話せる安心」を手に入れ、
自己肯定感を取り戻していきます。
見方が変われば関わりが変わり、
吃音のある毎日は、
安心して歩んでいける未来へとつながっていきます。
ここから一緒に整えていけます。
この3週間の流れを知るだけでも、
「待つ・見守る」という関わりに
少し安心を感じられましたよね。
けれど、
安心を深めるためにはまず
「吃音とは何か」を整理することが欠かせません。
わが子の吃音症状を理解できれば、
これまでの不安や罪悪感を少しずつ手放せるようになります。
ここからは、
吃音の基本的な特徴や原因についてわかりやすく解説していきます。
監修者
株式会社Osaka-Child所属 小児神経科医
- 名前: 三浦あすか
- 出身地: 兵庫県西宮市
- 最終学歴: 神戸大学医学部 小児科専攻
- 専門分野: 小児神経、DCD(協調運動障害)、発達性ディスプラクシア、HSP気質の子ども支援
- 職歴: 兵庫県立こども病院 小児神経センター勤務(11年)
専門分野について一言: 「できないことの奥にある『がんばっているサイン』を、もっと社会全体で受けとめていけたらと思っています。」
監修者
株式会社Osaka-Child所属 臨床心理専攻大学教授
- 名前: 森本哲夫
- 出身地: 奈良県
- 最終学歴: 米国ハーバード大学心理学部 博士課程修了
- 専門分野: 臨床心理学、発達心理学
- 職歴: ハーバード大学研究員(5年)、大阪大学人間科学部教授
専門分野について一言: 「心の成長とは、自己理解の旅でもあります。その旅のお手伝いができれば幸いです。」
「吃音の悩みを一人で抱え込んでいる母親へ」
小学生のわが子が音読で吃音につまるたび、
「私のせい?」と自分を責めていませんか。
学校では友達に笑われ、
先生からは「そのうち良くなる」と言われる。
夫からも「気にしすぎ」と突き放され、
母親だけが孤独に悩んでいる。
吃音の子どもにとって「言葉がつまる」のは努力不足でも育て方のせいでもありません。
- 脳や神経の働きに関わる特性
- 学校での緊張や不安
が重なって、吃音が強まっているのです。
無理に直そうとするほど吃音は悪化し、母親も安心を失っていきます。
必要なのは、吃音を正しく理解し、母親自身が「安心して寄り添える関わり」を築くことです。
「子どもに吃音の症状が現れ、『私のせいかも』と抱え込んでいた母が、安心を取り戻し笑顔で支えられるようになる|3週間集中再安心サポート」は、
孤独と不安に疲れた母親が、吃音への理解を深め、
安心して見守れる家庭を整えていくための伴走プログラムです。
こんな方におすすめです
- 吃音が原因で学校生活に不安を抱える子どもを支えたい
- 「私の育て方が悪かった」と自責してしまう母親
- 夫の理解がなく、孤独に悩んでいる
- 家庭の雰囲気にまで吃音の悩みが影響している
- 「責める母」から「安心して寄り添える母」に変わりたい
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 2月6日(金)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと1名様限定』
※銀行振込限定・先着順
そして──
吃音への関わりを整え、家庭に安心を取り戻したあと、
「母としての安心」だけでなく、「私自身のこれから」にも目を向けたい方へ。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
吃音の子育てを経験した母親が、
家庭を落ち着かせながら「一人の女性としての生き方」を再設計する3週間です。
家族の安心を守りながら、
「私自身の軸」と「未来の選択」を取り戻していきます。
- 吃音の子育てを通じて価値観が揺らいでいる
- 家庭の安心を整えたあと、自分の人生にも取り組みたい
- これからの選択に確信を持ちたい
「吃音のある子の母」という枠を超え、
「私自身の未来を選べる私」へ進んでいけます。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
「ちゃんとしてるのに、苦しい」
「頑張ってるのに、うまくいかない」
——そんな違和感を抱えたまま、ずっと我慢していませんか?
LINEで3分セルフ診断ができます。
あなたの“今の感覚”の正体が、見えてきます。
子どもの吃音に気づいたとき、母親が理解しておきたいこと

子どもの言葉が
人前でうまく話せず、
吃音症状が出て
止まる瞬間を目にすると、
ココロが苦しくなる気持ちになりますよね。
まわりの子はすらすら読んでいるのに、
うちの子だけ言葉がつまる。
その姿に
「なぜ?わが子は話す前に声が震えるの?」と戸惑い、
同時に
- 「私の遺伝のせい?」
- 「私の話し方のせい?」
と責めてきました。
- 吃音は話し方のスキル不足でも、
- 話すことに対する努力不足でも
- 甘えでもありません。
脳の仕組みや神経の働きと関係していて、
誰のせいでもなく表れる特性です。
だからこそ、
母親が吃音について
正しく理解して安心できることが、
子どもにとっても支えになります。
このキャプションでは、
吃音の基本を整理しながら、
罪悪感を少しずつ手放すための視点を重ねていきます。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「育てにくさって、もしかして発達障害?」
そんな不安を感じた方へ。発達障害の種類や症状、子どもの将来の見通しまで整理できる専門家監修コンテンツをご用意しています。
👉 「発達障害とは何か」を整理して、子どもの困りごとを理解する
-

-
参考発達障害とは?子どもの「育てにくさ」の正体と種類・症状・進路までわかりやすく解説【児童精神科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「ちゃんと育ててるはずなのに…」が、 頭から離れなかったあなたへ 毎日、がんばってる ...
続きを見る
吃音とは?子どもの「言葉がつまる理由」を安心して知る
吃音とは、
子どもが話すときに
- 「繰り返す」
- 「音を引き伸ばす」
- 「声が出ない」など
の症状が現れる状態をいいます。
普段の会話では流れるように話せても、
授業の音読や人前での発表では急につまることがある。
吃音の子どもは、
その差にとまどいながら、
人前では極度の恥ずかしさを経験してきています。
医学的には、
吃音は
- 脳の言語ネットワークの発達
- 神経伝達のリズム
に関わるといわれています。
- 言葉を組み立てる前頭葉や、
- タイミングを調整する小脳・基底核、
- そして自分の声をモニターする聴覚の働きが、
うまく同期しにくい。
こうした背景があるからこそ、
吃音は「意志が弱い」などで説明できるものではありません。
吃音の子どもは、
ただ話すこと自体よりも
「またつまるかもしれない」という不安に大きく揺さぶられます。
その緊張が
さらに吃音を強める反応もあります。
母親のあなたが
「吃音には理由がある」と知ることは、
子どもにとって安心の出発点になります。
吃音の子どもがつまずきやすい場面(音読・発表・会話)
吃音は
どんな場面でも
同じように出るわけではありません。
とくに
音読や発表のように、
クラス全員の視線が集まる場面で
強く表れやすい特徴があります。
- 自己紹介や点呼
- 電話の応答など、
始まりがはっきりしている状況も同じです。
生理学的には、
注目されることで自律神経が緊張し、
呼吸や発声のタイミングが乱れやすくなります。
そのため
吃音の子どもは、
落ち着いて遊んでいるときは流暢でも、
人前になると急につまるという落差を見せることがあります。
これは性格ではなく、
負荷のかかり方に
神経が反応しているという仕組みです。
母親にできるのは、
「吃音が出ても大丈夫」と
子どもが感じられる環境をつくることです。
- 急がせない
- 言い直しを求めない
- 最後まで待つ。
この三つが
家庭でできるシンプルなサポートであり、
吃音の不安を和らげる力になります。
母親が「私のせい?」と感じてしまうココロの背景
吃音に気づいたとき、
多くの母親が
「このように話すのが苦手になったのは、私の育て方が悪かったのでは」と
自分を責めてしまいます。
そのように、
自分を責めるしか、ココロの逃げ道がなかったからです。
- 忙しさで十分に向き合えなかったこと、
- 大きな声で叱ってしまったこと
――その一つひとつを思い返しては、
原因探しを繰り返してきました。
しかし
研究でわかっているのは、
吃音は
母親の接し方が引き起こすものではないということです。
- 脳のネットワークの成熟のタイミング
- 神経の働き方
- 家系的な素因など
複数の要因が関わります。
だから
「私のせい」と結論づけてしまうのは事実とは違います。
それでも母親が自分を責めてしまうのは、
子どもを守りたい気持ちが強いからこそです。
その気持ちに
気づけたときこそ、
罪悪感から一歩離れるきっかけになります。
吃音の子どもに必要なのは、
責める母親ではなく、
安心してそばにいられる母親です。
次のキャプションでは、
吃音の子どもへの
学校生活や家庭での関わり方を具体的に見ていきましょう。
ポイント
「息子の吃音は、私の育て方が悪いの?」
──そんな罪悪感を抱えていませんか。
吃音は母親のせいではなく、
脳や神経の働きに関わる特性です。安心できる関わり方から整理していきましょう。
『子どもに吃音の症状が現れ、「私のせいかも」と抱え込んでいた母が、安心を取り戻し笑顔で支えられるようになる──3週間集中再安心サポート』は、
「吃音の不安」と「母親の孤独」を一緒に整えるための伴走プログラムです。
吃音の症状と特徴を整理する
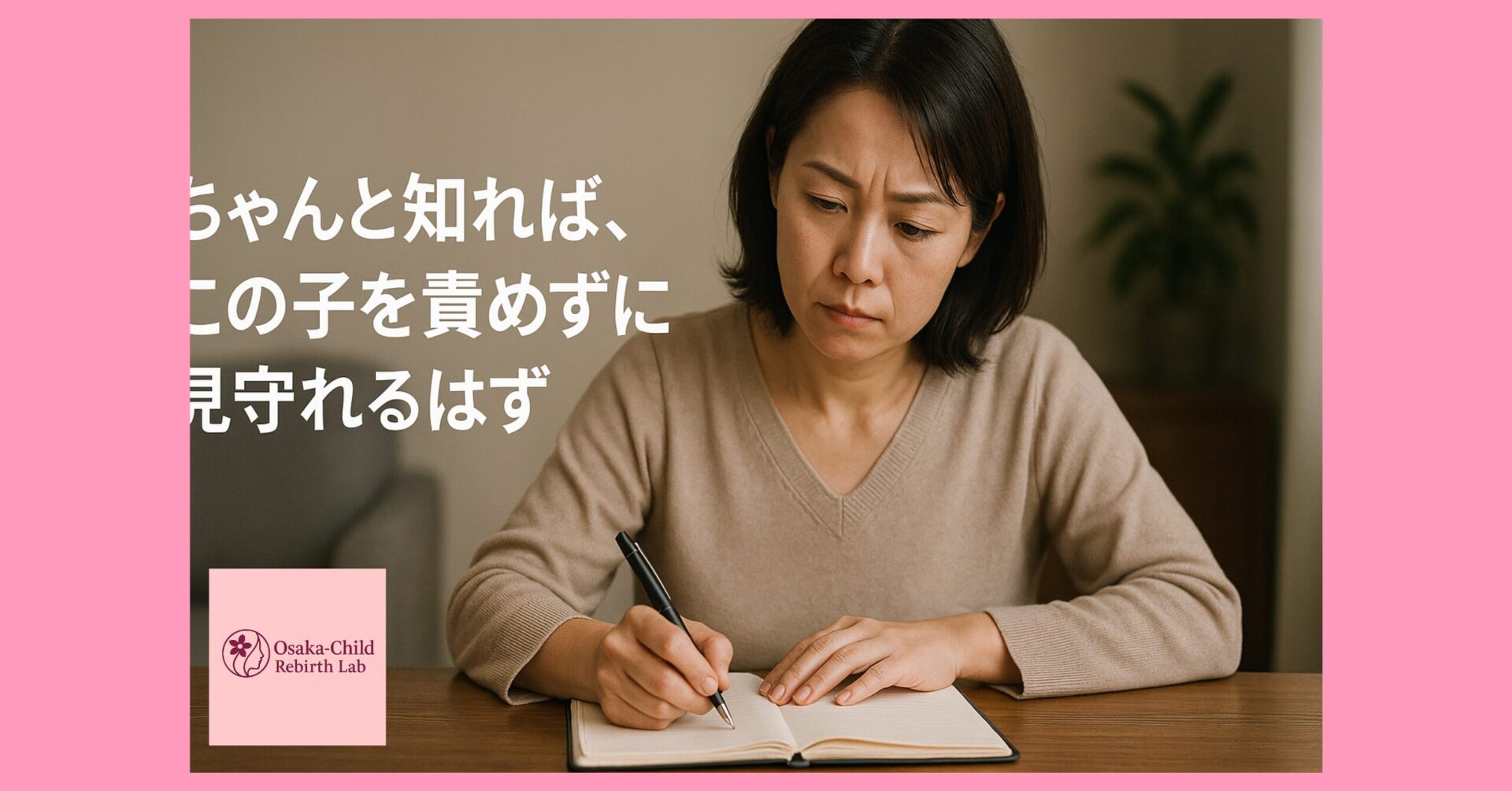
同じ「言葉につまる」でも、
毎回まったく同じではないですよね。
- 昨日は平気だったのに今日は止まる、
- 家では話せるのに学校では言葉が出ない。
揺れ動く子どもの吃音症状に合わせて
ココロまで揺れてきましたよね。
このキャプションでは、
吃音の見え方の言葉をそろえ、
年齢での変化を押さえ、
関連する特性までを一度に見渡せるように整理します。
理解がそろうと、
吃音に振り回される感情が少しずつ落ち着いていきます。
無料LINE診断|今のあなたに必要なサポートは?
『何から始めればいいかわからない…』そんなあなたへ。
LINEで「数字」を入力するだけで、今のあなたに合ったサポート商品を診断できます。
今すぐLINEに【 4 】の番号を入力してください。
「子どもに吃音の症状が現れ、『私のせいかも』と抱え込んでいた母が、安心を取り戻し笑顔で支えられるようになる──3週間集中再安心サポート」の詳細と、
あなたにぴったりの理由が届きます。
吃音に多い3つの症状(繰り返し・引き伸ばし・ブロック)
まずは、
日々の観察とことばが一致するように、
吃音の基本の型を確認します。
吃音には
三つの代表的な出方があります。
- ひとつめは繰り返し。吃音では「ぼ、ぼ、ぼく」のように音や語の先頭を何度も出す形が目立ちます。
- ふたつめは引き伸ばし。吃音では「ーーーぼく」と音を長く伸ばす出方が起きます。
- みっつめはブロック。吃音では言葉が出そうで止まり、数秒間声が出ない瞬間が生まれます。
医学的には、
- 吃音は発話計画(前頭葉・補足運動野)、
- タイミング調整(基底核・小脳)、
- 聞き返しの微調整(聴覚野)の同期のずれ
で説明されます。
吃音の繰り返しやブロックは、
呼気・発声・舌の起動が同時に立ち上がりにくいことでも強まります。
だから
吃音は性格や努力では整いません。
家庭では、
- 吃音の繰り返し/引き伸ばし/ブロックのどれが多いか、
- いつ・どこで・どの言葉で出たかを短くメモすると、
吃音の全体像がつかめます。
吃音を正しく呼ぶ言葉がそろうだけで、
子どもへの声かけがぶれにくくなります。
吃音の特徴は年齢や成長によって変化する
次に、
時間の流れの中で
吃音がどう変わるかを見ます。
就学前は、
語彙を一気に増やす時期です。
吃音では音の入り口が不安定になりやすく、
繰り返しが多く見えます。
小学生になると、
音読・発表といった注目の集まる課題が増え、
吃音のブロックや引き伸ばしが前に出ます。
思春期には
自意識が鋭くなり、
吃音の「また出るかも」という予期不安が強まり、
出方の波が大きくなることがあります。
生理学的には、
吃音の場面で交感神経が優位になり、
呼吸が浅くなる→喉頭の緊張が高まる→起動が遅れるという反応が
生じます。
心理学的には、
吃音に伴う失敗予期が集中を狭め、
さらに吃音を強める循環が起きます。
これらは
「気合いなどの精神状態」で抜ける問題ではありません。
長い目で見ると、
吃音は固定ではなく推移があります。
- 環境調整
- 安心の経験
が重なるほど、
吃音の波は整いやすくなります。
母親が
- 急がせない
- 言い直しを求めない
- 最後まで待つを重ねるだけ
で、吃音への恐れは確実に減ります。
吃音と発達障害・ADHD・ASDとの関連
最後に、
吃音とほかの特性が重なるときの見方をそろえます。
吃音は単独で現れることもありますが、
ADHDやASDなどの発達特性と併存するケースもあります。
ADHDがあると
- 注意の切り替えの難しさ
- 衝動的に話し始めて息が浅くなることで、
吃音のブロックや繰り返しが目立ちやすくなります。
ASDがあると
- 感覚過敏
- 対人場面の緊張
が強く、
吃音の予期不安が高まりやすい反応があります。
脳科学の視点では、
- 吃音
- ADHD
- ASD
はいずれも
- 前頭葉ネットワーク
- 基底核の調整機能など、
タイミングと制御に関わる回路の働きがポイントになります。
これは
「吃音=発達障害」という意味ではなく、
一部の回路が重なるために
困りごとが増えやすいという理解が適切です。
学校では、
吃音そのものに加えて
- 集中の波
- 刺激への反応
が誤解され、
子どもが二重に負荷を受けることがあります。
ここで効くのは、
吃音だけを切り離さず、
子どもの全体像として捉える視点です。
- 吃音が出ても安全、
- ADHDの落ち着きの波があっても安全、
- ASDの感覚に合わせても安全
――安全の合図を積み上げるほど、吃音は落ち着く方向に向かいます。
必要に応じて、
次のキャプション以降で扱う
学校への伝え方や家庭での環境調整、
そして
母親自身の土台を整える3週間集中再安心サポートへつないでください。
吃音の原因と脳の仕組みを正しく知っておく

家族とはスムーズに話せていたのに
外に出て吃音が出た瞬間に、
胸の奥で音が止まったように感じてきましたよね。
理由がわからないまま、
毎晩「どうして」と考え続けてきた感情がありました。
原因を見つけられたら、
吃音も一緒にほどけるような気がして、
過去の関わりまで何度も巻き戻してきましたよね。
このキャプションでは、
吃音を
脳と神経の働きから整理し、
遺伝と多因子の視点で受け止め、
最後に
「親のせいではない」を土台に置き直します。
吃音は脳の発達や神経の働きと関係している
まず、
吃音をからだの仕組みとして理解できる位置に
戻します。
吃音は、
言葉を組み立てて声にするまでの
脳内ネットワークの同期のずれと関係があります。
吃音では、
- 前頭葉・補足運動野が発話の計画を立て、
- 基底核・小脳がタイミングを刻み、
- 聴覚野が自分の声をモニターして微調整します。
この連携が乱れると、
- 吃音の繰り返し、
- 吃音の引き伸ばし、
- 吃音のブロックが
起きます。
吃音の場面では、
- 自律神経が緊張しやすく、
- 呼吸が浅い→喉頭が硬くなる→発声の起動が遅れると
いう反応があります。
吃音が出るかもしれないという予期不安が、
その緊張をさらに高めます。
ここまでの一連は、
吃音の根性や意志では動かせません。
吃音を
脳・神経の現象として捉えるだけで、
「叱れば直る」という誤解を手放しやすくなります。
吃音のメカニズムまとめ
- 吃音=発話計画×タイミング×聴覚フィードバックの同期不全
- 吃音の悪循環=予期不安→自律神経の緊張→発声の起動遅延
- 吃音は性格や努力の問題ではない
吃音と遺伝の関係について研究でわかっていること
次に、
「家系に似た子がいる」という実感を
科学と言葉で受け止めます。
吃音は
家族内集積が高いことが報告されています。
双子研究では、
一卵性が二卵性より一致率が高く、
吃音に遺伝的要因が関与することが示されています。
分子レベルでは、
吃音に関連する複数遺伝子(例:GNPTAB など)の報告があり、
- 細胞内輸送
- 神経発達
に関わる仕組みが
焦点になっています。
ただ、
吃音は
単一遺伝子で決まる疾患ではありません。
ポイント
吃音は
遺伝的素因+発達のタイミング+環境の負荷
が重なって表れます。
ここでいう
環境は「親の性格」ではなく、
- ストレス強度
- 注目される場面
- 睡眠や体調
のような生理的条件です。
だから、
吃音を多因子の特性として扱うのが正確です。
この視点は、
吃音を
「母親のせい」に結びつける思考から離れるエビデンスになります。
吃音は
生物学と発達の交差点に立つ現象です。
家系の要素に触れても、
吃音は変えられない宿命ではありません。
- 関わり方
- 環境調整で、
吃音の波は確実に整います。
吃音は親の育て方のせいではない
最後に、
これまで吃音の子どもと母親と向き合ってきて
何度も胸に刺さってきた言葉を事実で上書きします。
吃音は親の育て方のせいではありません。
ポイント
吃音の研究は、
かつての
「厳しい親が原因」という仮説を
否定しています。
吃音には
脳ネットワークの
- 同期特性
- 遺伝的素因
- 発達段階
が関与します。
ここを事実として言い切ると、
ココロの重さが少し動きます。
罪悪感は行動を固めます。
- 吃音が出た瞬間の表情の変化、
- 言い直しの要求、
- 急がせる声かけ
――どれも子どもの神経に「危険サイン」として届きます。
今日からは、
- 吃音が出ても表情を変えない
- 吃音の途中で言葉を奪わない
- 吃音が落ち着くまで呼吸を合わせて待つ。
これは何もしないことではなく、
吃音に安全を返す積極的な関わりです。
ひとりで抱え続けてきたなら、
母親の土台を先に整える支えを受け取って大丈夫です。
- 予期不安に巻き込まれない呼吸
- 家庭内の合図の整え方
- 学校との伝え方
――この三点を短期間で並べる伴走があります。
次のキャプション以降で
環境調整を具体化し、
必要に応じて
「3週間集中再安心サポート」へつなげます。
吃音が出ても、親子のあいだに安心の帯を戻せます。
「吃音の理解と安心サポート」で一人で抱え込んでいる母親へ
小学生のわが子が授業で吃音につまるたび、
「私のせい?」と胸が苦しくなっていますよね。
先生からは「そのうち良くなる」、
夫からは「気にしすぎ」。
吃音の現実を分かってもらえず、母親だけが孤独に悩み続けている。
吃音の子どもにとって「言葉がつまる」のは話すのが苦手でも甘えでもありません。
- 脳や神経の特性
- 学校生活での不安や緊張
が重なって起きる自然な現象です。
無理に直そうとするほど
吃音は悪化し、
母親も安心を失っていきます。
必要なのは、
吃音を「特性」として整理し、
母親が安心して見守れる関わり直しです。
「子どもに吃音の症状が現れ、『私のせいかも』と抱え込んでいた母が、安心を取り戻し笑顔で支えられるようになる|3週間集中再安心サポート」は、
孤独と不安に疲れた母親が、吃音を正しく理解し、
安心して寄り添える関係を取り戻すための伴走プログラムです。
こんな方におすすめです
- 吃音で友達に笑われる息子を前に涙している
- 「私の育て方が悪かった」と自責してしまう
- 夫の理解がなく、母親だけが孤立している
- 下の子への影響や家庭の空気が気になっている
- 「責める母」から「安心して寄り添える母」に変わりたい
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 2月6日(金)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと1名様限定』
※銀行振込限定・先着順
そして──
吃音への関わりを整え、家庭に安心を取り戻したあと、
「母としての安心」だけでなく、「私自身のこれから」にも目を向けたい方へ。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
吃音の子育てに向き合った母親が、
家庭を落ち着かせながら「一人の女性としての生き方」を再設計する3週間です。
家族の安心を守りつつ、
「私自身の軸」と「未来の選択」を取り戻していきます。
- 吃音の子育てを通じて価値観が揺らいでいる
- 家庭の安心を整えたあと、自分の人生にも取り組みたい
- これからの選択に確信を持ちたい
「吃音のある子の母」という枠を超え、
「私自身の未来を選べる私」へ進んでいけます。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
学校生活で目立つ吃音の困りごと

家では落ち着いて話せても、
吃音を抱えるあなたの子どもが
教室に入るだけで空気が変わる感じ、
ありますよね。
- 注目
- 時間制限
- 評価
──学校の場面は吃音を強く揺らす条件がそろいます。
このキャプションでは、
授業・友達関係・先生への伝え方という順で、
吃音の困りごとと支え方を整理していきます。
授業での発表や音読で困る子どもへの理解
呼ばれる順番が近づくほど、
肩に力が入り、
手のひらが冷たくなる。
名前を呼ばれた瞬間、
胸と喉が固まり、
最初の一音が出ない。
あの瞬間のしんどさ、
ずっと見てきましたよね。
吃音は
「意志」ではなく
脳の言語ネットワークのタイミング調整と、
- 呼吸
- 発声
- 発音
の協調が乱れたときに強く出ます。
- 教室の注目(視線)
- 時間制限(早く)
- 評価(正しく)
が重なると、
吃音は一気に増幅します。
だから
- 「努力不足」
- 「子どもが話すのが苦手」
ではありません。
ここを母親が言葉にできると、
子どもは自分を責めにくくなります。
授業での具体ポイント
- 入り口を軽くする:音読は「最初の一文だけ母と先読み→本番」の二段構え。入り口の成功が吃音の立ち上がりを安定させます。
- 量より質:短い段落×回数少なめで「最後まで言えた」を積む。成功体験が吃音の予期不安を下げます。
- 伴走読み:家庭では二人で同時にゆっくり読む。安定テンポに同調し、吃音の揺れが和らぎます。
- 評価の言い換え:「上手に読めた?」ではなく「伝えようとした勇気、届いた」。吃音があっても挑戦できた事実を肯定します。
ここまでが整うと、
吃音が出た瞬間にも「待てる私」が戻ってきます。
子どもは
「また読んでみよう」と
教室に向き合いやすくなります。
友達に笑われたりからかわれたりする影響
人の前で、
吃音症状が現れ、笑われた記憶は、
子どものココロにも母親の感情にも
長く胸に残りますよね。
吃音で詰まった瞬間の
- 「真似」
- 「失笑」
- 「小声の囁き」。
この体験は、
吃音そのものよりも強くココロを傷つけます。
すると
「また吃音が出たらどうしよう」という予期不安が育ち、
話さない選択が増えます。
回避が増えるほど吃音への怖さが
強化されるという神経系の抑制が出てきます。
家庭でできる守り方
- 返しフレーズの準備:「今、ゆっくり話してる」「最後まで聞いてくれたら言える」。短い言葉を一緒に練習。吃音が出た場面で自分を守れます。
- 目撃後のケア:「教えてくれてありがとう」「話してくれてうれしい」。事実と気持ちをまず受け止める。吃音が出たかより、伝えようとした行為を肯定します。
- 「安心の家ルール」を固定:途中で補わない/遮らない/笑わない。家が安全基地になると、吃音があっても挑戦に戻れます。
母親が
「吃音があっても大丈夫」という姿勢を毎日示すと、
友達との関係で揺れたココロが戻る場所ができます。
ここが学校での自信につながります。
先生や学校に吃音を伝えるときの工夫
吃音反応が
「ただの恥ずかしがり」と受け取られると、
子どもはさらに苦しくなりますよね。
ポイント
学校には、
吃音の特性と具体的な配慮を短く、
はっきり伝えます。
背景は
「吃音は脳の仕組みと神経の働きに関わる言語の特性。
指示や努力で即時にコントロールできない」という一文で十分です。
伝える要点(メモ1枚でOK)
- 目的:子どもが吃音があっても安心して授業に参加できる環境づくり。
- 配慮例:
音読は任意参加/順番は最初を避ける、事前に一文だけ先読み時間。
発表は「指名→即回答」ではなく「考える時間→合図で回答」。
詰まっても遮らない・言い直させない・「ゆっくり」連呼を避ける。
評価は流暢さより「伝えようとした内容」と「参加の姿勢」。 - 連絡ルート:家庭→担任→必要に応じて校内委員会(養護・コーディネーター)。共有を「人」で切らさない。
- 渡し方のコツ:短い書面+面談5分で要点だけ。
母親が落ち着いた声で
「吃音があってもこの子は参加できる」を軸に話すと、
先生は動きやすくなります。
家庭と学校が同じ方向を向くと、
吃音に揺れない毎日が増えていきます。
「学校で目立つ吃音」に悩む母親へ届けたい安心
授業での発表や音読で吃音につまる息子を前に、毎日は辛く、子どもの未来が心配ですよね。
- 「友達に笑われたらどうしよう」
- 「このまま学校生活がつらくなるのでは」と、
不安を抱える母親はあなただけではありません。
「子どもに吃音の症状が現れ、『私のせいかも』と抱え込んでいた母が、安心を取り戻し笑顔で支えられるようになる──3週間集中再安心サポート」で、
「責める関わり」から「安心して待てる関わり」へ切り替えていきましょう。
母親にできる吃音への関わり方と将来の見通し

子どもの吃音が
家庭内でも現れてしまうと、
まだこの子は家ではスムーズに話せていたのに、
それでさえできないの?と思うと
ココロが苦しくなってきますよね。
吃音が目の前で起きるたび、
- 助けたいのにうまく届かない感じが残る。
- 責めても直らない、励ましても動かない。
ここからは、
吃音の子どもが
「話しても大丈夫」と感じ直せるように、
母親が
今日からできる吃音の子どもへの関わりを、
医学・心理の視点でやさしく整理します。
安心の積み重ねが、
吃音に揺さぶられない日常を作ります。
無料診断|あなたの「ココロのパターン」を知る
「なぜか同じことで悩んでしまう…」
そんな方のために、LINEで「キーワード」を送るだけで診断できるサービスをご用意しました。
LINEに『吃音とは』と入力して送信してください。
あなたに合った視点と解説をすぐにお届けします。
吃音の子どもを安心させる接し方
まずは、
吃音症状が出て、
子どもと母親の自我が揺らいでしまう
いちばんしんどい場面に寄り添う接し方から整える。
ここが土台ですよね。
言葉がつまった瞬間、
- 体の中で緊張が一気に高まる。
- 喉・胸・舌が固まって、声の出口が細くなる。
吃音は「意志の弱さ」ではなく、
- 脳の言語ネットワークのタイミング調整
- 呼吸・発声・発音の協調
が乱れたときに強く出ます。
母親の役割は「正すこと」ではなく、
安心の合図を繰り返し届けること。
メモ
- 待つ:言い終わるまで遮らない。途中で言い直させない。
- 受け止める:うなずき・目線・表情で「聞いているよ」を伝える。
- ことば:吃音が出ても「最後まで聞けてうれしい」「ゆっくりで大丈夫」と短く肯定。
- 呼吸の同調:自分がゆっくり息を吐く。母の呼吸が落ちると、子の自律神経も落ち着く。
医学的には、
吃音は
「予期不安(また出るかも)」で
増幅しやすい特徴があります。
- 否定
- 急かし
- 先回り
は予期不安を強めるので避ける。
吃音が出た瞬間ほど、
言い切りの評価より「一緒にいる安全」を示す。
これが、
吃音の子どもが
明日も話してみようという力になります。
家庭でできるサポートと声かけ
あなたが
吃音の子どもへの関わりの土台ができたら、
家のルールを小さく整える。
毎日の繰り返しが、
吃音の波に振り回されない力を育てます。
- 「最後まで聞く家」を合言葉に
途中で言い直させない。言い換えも求めない。吃音が出ても「聞けてうれしい」で締める。 - 二人読み(伴走読み)
音読は母子で同時にゆっくり読む。母の安定したテンポに神経が同調し、吃音の揺れが収まる方向に動く。 - 短文・短時間
音読は短い段落×1〜2回。成功体験を先に積む。量より安定。吃音の波に合わせて切り上げてOK。 - 選べる質問
「どこが楽しかった?」より「①ここ ②ここ」で選択式。言語負荷を下げると、吃音があっても話しやすい。 - 朝の3分ルーティン
肩を回す→深く吐く→今日の合言葉「ゆっくりでいい」。自律神経が整うと、吃音の立ち上がりが穏やかになる。 - からかわれ対策の「返しフレーズ」
「ゆっくり話してるだけ」「聞いてくれたら言えるよ」。練習しておくと、学校でも自分を守れる。
ポイント
心理の視点では、
「できた」を頻繁に言語化することが
自己効力感を底上げします。
吃音の有無ではなく、
- 「伝えられた」
- 「最後まで言えた」
を具体的に褒める。
母の言葉が、学校での挑戦へそのまま橋渡しになります。
吃音は成長とともに変化する|将来を見通すために
次にできることは、
時間の流れを置いておく。
見通しがあると、今日を焦らず選べますよね。
吃音は固定されたラベルではなく、
発達と環境で揺れながら変化します。
低学年は目立ちやすく、
中学年以降は脳のネットワークが整って
吃音の波が穏やかになる反応があります。
思春期は
人前の緊張が高まり、
吃音より「予期不安」が主役になりやすい時期もあります。
だからこそ、
今の目標は
「なくす」より
「一緒に運ぶ」に置く。
見通しを支えるミニ習慣
- 波ノート:どんな場面で吃音が強いか、弱いかを記録。増幅因子(急かし・注目・時間制限)と緩和因子(前もって読む・二人読み・休息)を見える化。
- 先読み台本:音読・発表の前に最初の一文だけ母と練習。入り口の成功が吃音の立ち上がりを安定させる。
- 安心の合図を家族で共有:きょうだい・父にも「最後まで聞く」「ゆっくり」が家ルールだと伝える。
将来の鍵は、
吃音があっても
「話して大丈夫」と体で覚えること。
この体験が積み上がるほど、
進学や友人関係の選択肢は広がっていきます。
母が守るのは
「安心の場」。
それが、長い目で見た一番の治療的関わりです。
「母親が安心して関われる私」になるための3週間集中再安心サポート

吃音に悩む毎日は、
気づけば
- 「どうして起きるの?」
- 「私のせい?」
と原因ばかりを探してしまいますよね。
そのたびにココロが重くなり、
子どもの吃音を見るだけで胸が痛む。
安心して支えたいのに、
責める言葉が先に出てしまう…。
そんな苦しさから抜け出し、
「安心して関われる私」に変わるための3週間サポートがあります。
吃音の原因探しから抜け出し、母親がココロを整えるステップ
吃音の子どもが
「話すのがうまくいかなくても傷つかず、
自分の神経系・ココロのリズムに適応していける最初の1歩」は、
母親自身のココロを整えることから始まります。
吃音を前にすると、
- 「育て方が悪かったのか」
- 「妊娠中のことが影響したのか」
と自分を責めてしまう。
その思い込みが強いほど、
子どもの吃音に過敏になり、
待てずに口を挟んでしまう反応が出てきます。
3週間集中再安心サポートでは、
1週目に
母親の感情を整理し、
原因探しから解放される時間をつくります。
- 吃音を「母親の責任」と結びつける思い込みを外す
- 「吃音を見ると苦しくなる自分」を否定せず受け止める
- 呼吸や体感を整えるセルフケアで、ココロの緊張をゆるめる
医学的にも
吃音は
脳の発達や神経系の特性と関わっていて、
母親のせいではありません。
母親のココロが整うと、
吃音を見ても揺れない安心感を届けられるようになります。
吃音の子どもを責めずに、待てる・寄り添える関係づくり
ココロが少し落ち着いたら、
次に「待つ力」を育てていきます。
吃音が出た瞬間に
- 「ゆっくり」
- 「落ち着いて」
と声をかけた経験、ありますよね。
でもそれは、
子どもに
「できていない」と突きつける感覚を残し、
吃音への不安を強めるになります。
サポートの2週目では、
吃音が出ても責めずに待ち、
寄り添う関わりを一緒に練習します。
- 吃音が出ても遮らずに最後まで聞く
- 言葉のスムーズさより「伝えようとした勇気」を評価する
- 家庭を「吃音があっても安心して話せる場所」に整える
ポイント
心理学の研究でも、
吃音が改善に向かうかどうかは
「正しく話せるか」よりも
「安心して話せる場があるか」で決まると
言われています。
母親が待てる関係に変わると、
吃音の子どもは
「また話してみよう」とチャレンジできる力を取り戻していきます。
吃音と共に歩む未来を安心して見通せる母親になるために
最後は、
あなた自身が
子どもの発達が遅れようが、
うまくいかない現実があっても
未来を安心して見られる自分に変わることです。
吃音は小学生で目立ちやすく、
中学以降に落ち着いていく子もいます。
時期によって波はありますが、
共通して大切なのは
「吃音があっても大丈夫」と母親が思えること。
サポートの3週目では、
吃音を抱えても安心して歩んでいける未来の見方を育てます。
- 吃音を「治す対象」ではなく「共に歩む特性」と捉える
- 将来を「安心して話せるかどうか」で見通す
- 母親自身が「吃音があっても関われる私」に変わる体験を積む
吃音に揺さぶられていた毎日から、
「一緒に進んでいける」と思える未来へ。
母親がその軸を持つことで、
子どもは吃音を抱えながらも安心して言葉を育てていけます。
3週間集中再安心サポートの具体的な内容と申し込み前に知っておきたいこと
吃音で困っているのに
「どこにも当てはまらない」と
感じてきましたよね。
子どもの吃音が出るたび
苦しくなり
「私のせいかも」と
飲みこむしかなかったのです。
先生に相談しても進まないまま、
吃音と向き合う力が削られていく。
そんな時間を止めるために用意しているのが、
「子どもに吃音の症状が現れ、『私のせいかも』と抱え込んでいた母が、安心を取り戻し笑顔で支えられるようになる──3週間集中再安心サポート」です。
診断名より先に、
母親の安心を整えることを土台に置き、
吃音と歩く毎日を立て直します。
このプログラムは、
2週目までは個別対話とLINE並走が中心です。
吃音を見るたびに
立ち上がる罪悪感や不安を、
その場で言葉にして受け渡せるルートをつくります。
吃音の脳の仕組みや症状の特徴をやさしく整理し、
「親のせいではない」という理解を
体感レベルまで落とし込みます。
焦りが静まると、
吃音が出た瞬間にも待てるココロのスペースが戻ってきます。
実践は、迷わず動ける3ステップにまとめています。
- STEP①|気づき(Week1)
個別対話とLINEで、吃音に触れた瞬間に湧き上がる罪悪感・不安・怒りを安全に言語化します。感情に名前がつくと、体の緊張がほどけ、家庭の空気が和らぎます。 - STEP②|実践(Week2)
吃音の脳のタイミング調整と呼吸・発声の協調という背景を共有しながら、「遮らず待つ」「最後まで聞く」「評価ではなく受け止める」を家庭の標準にします。音読・発表・友達との会話など、吃音が揺れやすい場面を一緒に分解し、今日からできる行動に置き換えます。ここも対話とLINEで並走し、つまずいた瞬間に支えます。 - STEP③|軸の再構築(Week3)
「吃音をなくす」ではなく「吃音があっても安心して話せる」未来を合言葉に、母子の関係を再配置します。家庭を「安心して話せる場」として固定し、先生との橋渡しや返しフレーズの準備まで整えて、学校での実践につなげます。
この3週間で起きる変化は、
難しい理屈ではなく体感です。
- 吃音が出ても慌てずに待てる。子どもの言葉を途中で補わず、最後の一音まで受け止められる。
- 家の中に「話しても大丈夫」が広がる。
- 授業や友達との会話でも、吃音があっても挑戦してみようという表情に変わる。
母の安心が、
子どもの「吃音があっても大丈夫」という安心に
そのまま届きます。
関わり方の要点もシンプルです。
- 吃音が出ても、表情と姿勢で「大丈夫」を見せる。
- 途中で言い直させず、最後まで聞く。
- 目標は「治す」ではなく「安心して話せる」。
- 学校や先生とは、叱責ではなく理解の共有でつながる。
出発点はいつも一つ。
あなたが安心できることが、この子の安心につながる。
吃音に振り回されてきた毎日から、「一緒に歩ける」に切り替える3週間です。
吃音に悩む母へ|「診断の前に」安心を取り戻す3週間
- 「吃音が出るたび胸が痛む」
- 「私のせいかも」
と抱え込んできたあなたへ。
まず「母の安心」を整えて、吃音と一緒に歩ける毎日へ。
「子どもに吃音の症状が現れ、『私のせいかも』と抱え込んでいた母が、安心を取り戻し笑顔で支えられるようになる──3週間集中再安心サポート」
- Week1|感情の整理(個別対話+LINEで罪悪感と不安を言語化)
- Week2|特性理解と心の支え(2週目まで対話とLINE並走が中心。吃音の仕組みと学校での困りごとを一緒に整理)
- Week3|関係再構築(「待つ・受け止める」関わりを定着/先生との橋渡し)
- 吃音が出ても「大丈夫」を表情で伝える。
- 途中で補わず最後まで聞く。
- 目標は「治す」ではなく「安心して話せる」。
いま、家の中から整えていきましょう。
まとめ|「吃音とは」を知ることで、母親として安心を取り戻せる
夫と子どもが眠った後、
孤独になり、子どもの未来が心配になる。
夜になるとスマホを手にして、
何度も「吃音」とネットで調べてきた毎日。
- 音読で言葉につまる姿を見て胸が締めつけられたり、
- 友達に笑われて下を向く子どもに心が痛んだり。
夫からは「気にしすぎ」と突き放され、
孤独に涙した夜もありました。
1人で抱えているという認識ほど、
苦しい感情はありませんからね。
「私のせいで吃音が出たのかもしれない」と
抱え込む日々は、
本当に苦しかったですよね。
でも、
吃音とは親の育て方や性格が原因ではありません。
言葉がスムーズに出にくい
「神経系の特性」であり、
責められるものではないのです。
大切なのは正しく理解し、
子どもに吃音があっても、
母親は安心できる関わり方を少しずつ積み重ねていくこと。
その気づきを得た今、
あなたの毎日を変えていく第一歩が始まります。
ここで整理しておきたい要点があります。
この記事で分かったこと
- 吃音とは、脳や神経の働きと関係する「言葉の流れの特性」である
- 小学生期は音読や発表、友達関係で吃音の困りごとが出やすい
- ADHDやASDなど他の特性と重なることもあり、まずは吃音そのものの理解が土台になる
- 家庭でできるのは「急がせない・待つ・最後まで聴く」こと
- 学校では、先生に具体的な配慮(発表の順番や音読の工夫など)を共有することが安心につながる
こうした視点を持てるだけでも、
「母親のせいではなかった」とココロが軽くなり、
子どもに安心を返せるようになります。
吃音が出たとき、
表情で「大丈夫」と伝え、
最後まで聞いてあげるだけでも
子どものココロは守られますよ。
記事を読み終えて、
- 「どうして子どもにあんなに怒ってしまっていたのか」
- 「私ばかりが責められているように感じてきたのはなぜなのか」
──あなたは少し見えてきました。
吃音があるわが子を前にして、
- 待つことができず、
- 急がせたり、
- つい叱ってしまった日々。
それは母親として弱さではなく、
どう向き合えばいいのかわからず苦しんできたからですよね。
学校で笑われる姿や音読で言葉につまる瞬間を見てきたら、
胸が締めつけられて当然です。
「私のせい」と抱え込んでしまうのも無理はありません。
だからこそ必要なのは、
母親がまず自分の気持ちを整える時間です。
ここで紹介したいのが、
「子どもに吃音の症状が現れ、『私のせいかも』と抱え込んでいた母が、安心を取り戻し笑顔で支えられるようになる──3週間集中再安心サポート」。
このプログラムでは、
3週間という区切りの中で、
母親の感情を整理し、
吃音の特性を理解し、
家庭での関わり方を整えるステップを伴走します。
- Week1では、ずっと胸の奥にたまってきた罪悪感を言葉にして吐き出すことから始めます。LINEでのやりとりと個別対話で、安心して気持ちを出せる環境を整え、母親自身が「私は悪くなかった」と少しずつ感じられるようになります。
- Week2では、吃音の脳の仕組みや特徴をわかりやすく伝えながら、「親のせいではない」という理解を根拠とともに届けていきます。学校で起きやすい困りごとを一緒に整理し、母親の心を支える力を強めていきます。
- Week3では、実際に「待つ・見守る」という安心した関わりを練習しながら、家庭の空気を整えていきます。子どもが言葉につまっても「大丈夫」という表情で返せるようになり、学校や先生とのやりとりも「叱る」ではなく「理解を共有する」姿勢へ変わっていきます。
この3週間を通して、
母親は「罪悪感を手放して待てる自分」へ変わり、
子どもは「安心して話せる自分」に戻っていきます。
孤独感に押しつぶされそうだった毎日から、
- LINEを通して安心を積み重ね、
- 笑顔を取り戻していく変化。
その積み重ねが、
子どものチャレンジする気持ちや自己肯定感にもつながります。
大切なのは、
吃音を
「治す」ことを目指すのではなく、
「安心して話せる関係を育てていく」こと。
正解を探す必要はなく、
一緒に試し、一緒に整えていく時間がここにあります。
これまで孤独に背負ってきたあなたの思いを、
安心に変えていける選択肢として受け取ってほしいのです。
「吃音で積み重なった不安と自責感」をこのままにしない私へ
- 「小3の息子が音読で吃音につまるたび、胸が締めつけられる」
- 「夫には理解されず、『母親の気にしすぎ』と誤解され、孤独に押しつぶされそう」
──この記事で「吃音は努力不足でも母親のせいでもなく、安心を整えることが未来を拓く道」と整理できた今、
母親としての自責や焦りを手放し、家庭から安心を再構築していく一歩を踏み出すタイミングです。
『子どもに吃音の症状が現れ、「私のせいかも」と抱え込んでいた母が、安心を取り戻し笑顔で支えられるようになる|3週間集中再安心サポート』は、
- 吃音の理解
- 学校生活との橋渡し
- 家庭内の関わり直し
を三本柱に、
「無理に直そうとする」日々から、「安心して見守れる家庭」へ整えていく伴走型サポートです。
こんな方におすすめです
- 吃音が原因で学校生活に不安を抱えている息子を支えたい
- 「私の育て方が悪かった」と自責してしまう母親
- 担任や先生とのやりとりに迷い、安心を失っている
- 夫や家族の理解がなく、孤独に悩んでいる
- 「責める母」から「安心して寄り添える母」へ変わりたい
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 2月6日(金)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと1名様限定』
※銀行振込限定・先着順
ネットバンキングのご利用で、今すぐ開始することが可能です。
そして──
吃音への関わりを整え、家庭に安心を取り戻したあと、「母としての私」に加えて、「私自身のこれから」にも光を当てたい方へ。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
吃音の子育てを経験した母親が、
家庭の安定と「一人の女性としての生き方」を両立させる3週間です。
家族を支えながらも、
「私らしい選択」と「私の軸」を取り戻していきます。
- 吃音の子育てを経て「自分」を見失いかけている
- 家庭の安心を守りつつ、「私の人生」も再構築したい
- これからの10年を、自分の選択に確信を持って歩みたい
「吃音のある子の母」という枠を超えて、
「私自身の未来を選び取れる私」へ。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
すでに診断済みの方も、そのまま詳細ページへ進めます。
あなたの心と体に合ったサポートを、今すぐ確認してみてください。








