
宿題を見ていると、
なぜか不安になる。
- 簡単なひらがなが読めなかったり、
- 昨日できていたはずの計算が、今日はできなくなっていたり。
教えても伝わらない場面が増えていくたびに、
声がきつくなっていく自分に、
あとから強く落ち込んでいた。
- 頑張っていないわけじゃない。
- やる気がないわけでもない。
それでも、
「なんでできないの?」と口にしてしまっていた日が、
何度もあった。
もしかして、
ほかの子とはどこか違うのかもしれない──
そう感じながらも、
誰にどう相談すればいいのかわからず、
ずっと自分の中だけで、ぐるぐる考えてきた。
この記事では、
学習障害(LD)に気づくための視点を中心に、
次の5つの内容を整理しています。
この記事を読むとわかること
- 小学生に見られる学習障害(LD)の特徴と家庭での初期サイン
- 「勉強が苦手」と「やる気がない」のちがい
- ADHDやASDなど他の発達特性との違いと重なり
- 親の「教え方」より「見方」を整える大切さ
- 診断の有無に関係なく、今できるサポートのヒント
- 「普通の子と何が違うのか、よくわからない」
- 「でも、どうにかしたい」
そんな思いでずっと動けずにいた方にこそ、
必要な時間があります。
「『学習障害かも』と迷い、どう関わればいいか悩んでいた私が、『この子らしさ』に寄り添えるようになった──3週間集中再安心サポート」は、
お母さん自身の中にある
「不安と期待のはざま」を、
ゆっくりほどいていくためのサポートです。
このサポートでは、
勉強を「できるようにする」ことだけを目指しません。
それよりも、
- 「この子はどう受け取っているのか」
- 「何が伝わっていなかったのか」
「できない」に振り回されていた毎日から、
「どう見守ればいいか」を整える3週間です。
- Week1では、責めていた気持ちに気づき、
- Week2で、この子に合った学び方の背景を理解する。
- そしてWeek3では、実践的な言葉かけと接し方を整え、
「叱らずに伝わる関係」を育てていきます。
がんばってきた親子関係を、ここからつなぎ直す。
その第一歩として、安心の土台を整える時間を届けます。
監修者
株式会社Osaka-Child所属 小児神経科医
- 名前: 三浦あすか
- 出身地: 兵庫県西宮市
- 最終学歴: 神戸大学医学部 小児科専攻
- 専門分野: 小児神経、DCD(協調運動障害)、発達性ディスプラクシア、HSP気質の子ども支援
- 職歴: 兵庫県立こども病院 小児神経センター勤務(11年)
専門分野について一言: 「できないことの奥にある“がんばっているサイン”を、もっと社会全体で受けとめていけたらと思っています。」
監修者
株式会社Osaka-Child所属 臨床心理専攻大学教授
- 名前: 森本哲夫
- 出身地: 奈良県
- 最終学歴: 米国ハーバード大学心理学部 博士課程修了
- 専門分野: 臨床心理学、発達心理学
- 職歴: ハーバード大学研究員(5年)、大阪大学人間科学部教授
専門分野について一言: 「心の成長とは、自己理解の旅でもあります。その旅のお手伝いができれば幸いです。」
「教え方が悪いのかな…」と、何度も検索してしまった夜に
- 「ひらがながなかなか読めない」
- 「算数の計算が毎回つまずく」
──そんな姿を見ているうちに、笑顔で教えられなくなっていた。
- 「もしかして学習障害なの?」
- 「でも、『普通の子』として育ってほしいだけなのに…」
教え方に問題がある気がして、
毎晩ひとりで答えを探していた──。
『学習障害かも』と迷い、どう関わればいいか悩んでいた私が、『この子らしさ』に寄り添えるようになった──3週間集中再安心サポートは、
診断よりも先に、「家庭でできる向き合い方」を整える
お母さんのための心理サポートです。
こんな方におすすめです
- 何度教えてもわかってもらえず、自信をなくしている
- つい怒ってしまって、あとで自己嫌悪している
- 学校の話を聞くたびにココロがざわつく
- 相談相手もいなくて、孤独を感じている
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 1月17日(土)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと2名様限定』
※銀行振込限定・先着順
そして──
少しずつ「この子らしさ」が見えてきた今、
「私自身のこれから」にも目を向けてみたくなった方へ。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
「母としての安心」を土台に、
「わたしとしての人生」を再設計する3週間。
子どものことで手いっぱいだった日々から、自分のための時間を取り戻す日常へ。
- 子育ての悩みが少し落ち着いてきた
- でも「自分の時間が止まっている」と感じている
- 母親だけで終わりたくない気持ちがある
このプログラムでは、
「役割だけでない私」に立ち返るサポートを行います。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
「ちゃんとしてるのに、苦しい」
「頑張ってるのに、うまくいかない」
——そんな違和感を抱えたまま、ずっと我慢していませんか?
LINEで3分セルフ診断ができます。
あなたの“今の感覚”の正体が、見えてきます。
小学生の「勉強の苦手さ」から見えてくる学習障害の特徴とは?
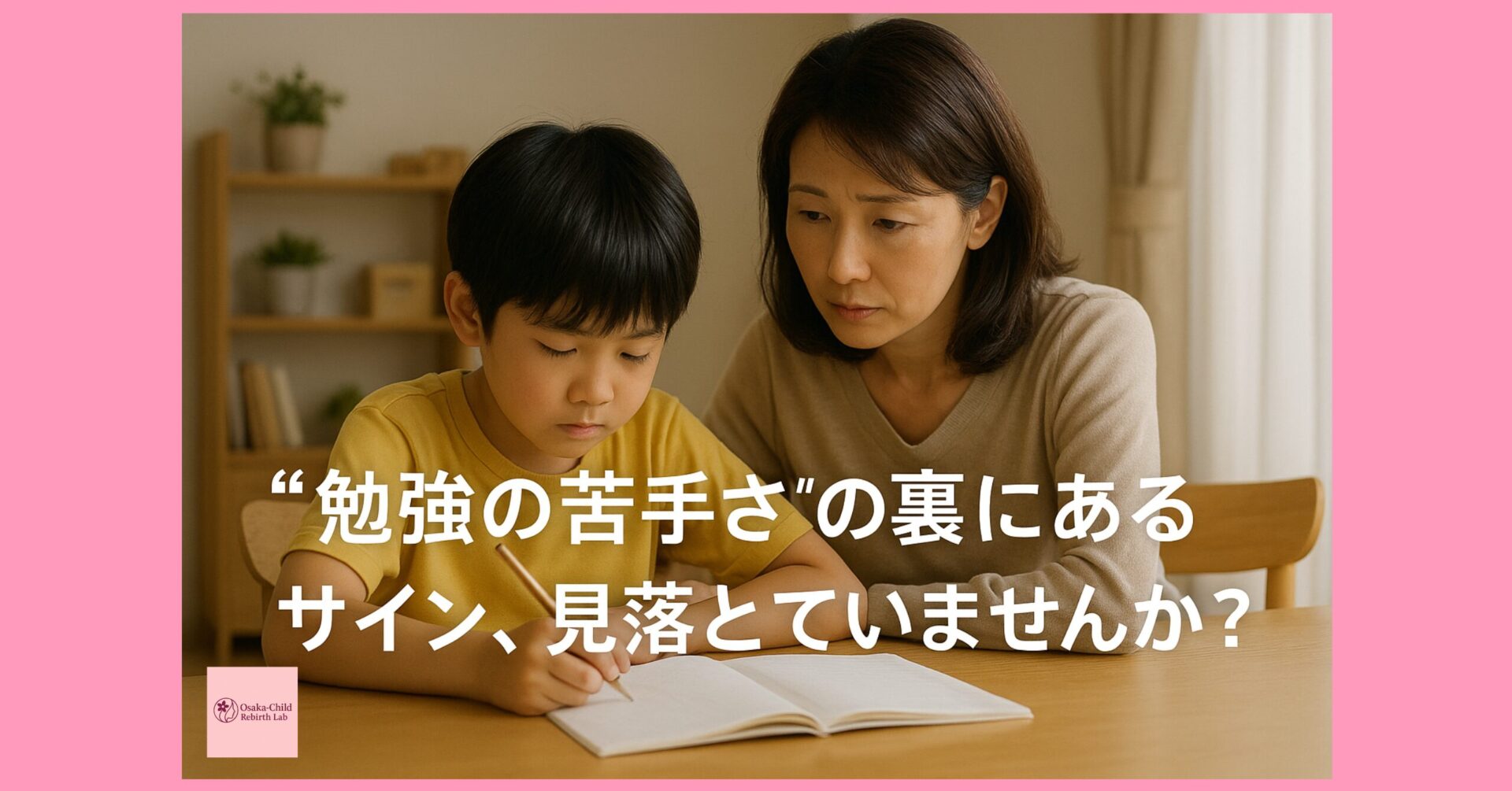
- 「なんでこんなに時間がかかるんだろう」
- 「やる気がないわけじゃないのに…」
気づけば、そんな戸惑いを何度も繰り返してきた。
がんばっている姿は見えている。
でも、
できないことばかりが目についてしまって、
どう向き合えばいいのかわからなくなっていた。
そうやって迷いながら、
毎日を過ごしてきた方も多いです。
でも実は、
「勉強の苦手さ」の裏側には、
学習障害(LD)と呼ばれる情報処理の特性が
隠れていることがあります。
これは、
努力不足や甘えではなく、
「認知のしくみ」が少し違うだけ。
その見方を知っていくことで、
親としてのまなざしが少しずつ変わっていきます。
ここからは、
家庭でも気づける「3つのサイン」を通して、
子どもたちが抱えている「つまずきの正体」を一緒に見つめていきましょう。
ひらがな・カタカナの読み書きが覚えられない
- 何度教えても、「を」と「ね」がごちゃごちゃになる。
- 昨日書けていた文字が、次の日には忘れている。
一生懸命書いているのに、
間違いだらけ
──そんな姿を、黙って見つめてきた日があった。
- ちゃんと練習しているのに定着しない。
- ふざけているわけでも、やる気がないわけでもない。
でも、
うまくいかない毎日の中で、
本人の自信も、
少しずつ削れていっていた。
こうした読み書きの困難さには、
学習障害(LD)の一つである
- 「読字障害」
- 「書字障害」
が関係しています。
音と文字が結びつきづらかったり、
文字の形を捉えるまでに時間がかかるのは、
この子の中で
「見え方」「聞こえ方」の処理がちょっとだけ違っているからです。
がんばっても伝わらなかったのではなく、
伝え方の土台が合っていなかった──
そう受け止めたとき、
自分の中の責める気持ちが、
少しずつ和らいでいきました。
算数だけ極端にできないのはなぜ?
文章を読むことはできているのに、
計算だけが止まってしまう。
- 時計
- 繰り上がり
- 図形
どれも他の教科とは反応がまるで違っていた。
「なんでこんなにできないの?」と、
思わず問い詰めてしまったこともあった。
でも、
よく見ると、
最初から手が動いていなかった。
理解できない以前に、
どこから取りかかればいいのかさえ分からず、
固まってしまっていたように見える。
学習障害(LD)の中でも
「算数障害(ディスカリキュリア)」と
呼ばれる特性があり、
これは
- 数のイメージや順序、
- 量の感覚
が捉えにくくなる傾向があります。
つまり、
「勉強が嫌い」なのではなく、
「どうしても入ってこない」感覚を抱えているのです。
無理やり繰り返させても、
かえって自信を失わせてしまっていた。
そう気づけたとき、
やり方ではなく
「見方」から変える必要があると思えるようになりました。
音読・発表を嫌がる子が見落とされがちな理由
- 家ではよく話すのに、学校では急に無口になる。
- 音読の時間が近づくとソワソワし始めて、発表では手がまったく挙がらない。
最初は
「恥ずかしがり屋なのかな」と思っていたけれど、
だんだんそれだけでは片づけられない気がしてきた。
- 読みのスピードが遅かったり、
- 意味が理解できるまでに時間がかかったりする場合、
「読みたくない」というより、
「読めない・ついていけない」という感覚
を抱えていることもあります。
ポイント
学習障害(LD)が関係していると、
音声にするまでの処理に苦手さが出やすく、
そのしんどさを隠そうとするあまり、
「話さない」という行動で防衛していることもあるのです。
「声が小さい」のではなく、
「声を出すとバレてしまう」ことを怖れていた。
その沈黙の奥に、どれだけの緊張や不安を抱えていたのか──
今なら、あの静けさの意味に、少しだけ寄り添える気がしています。
「勉強してるのにできない」…家庭で気づける初期サイン
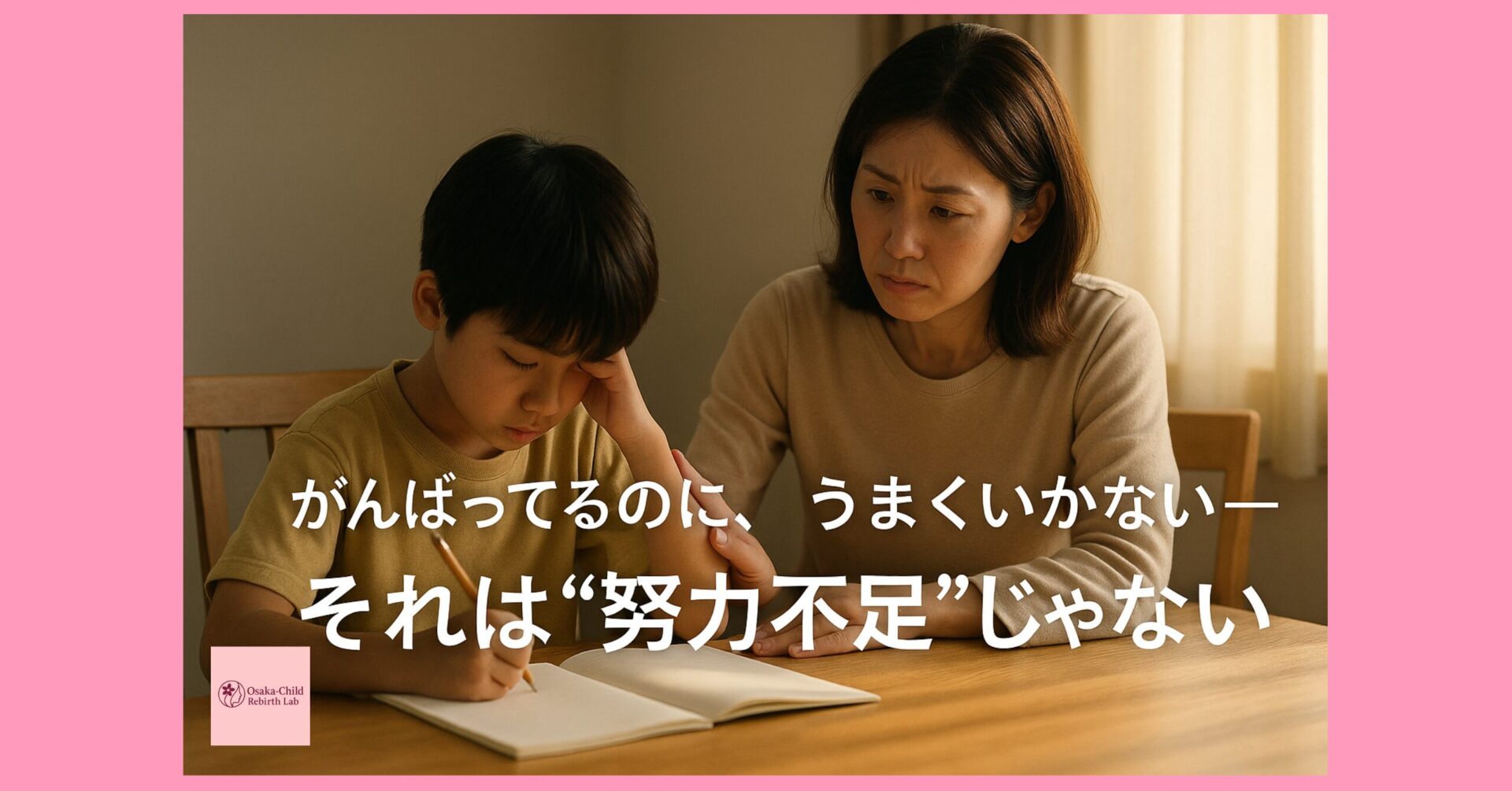
“正しい教え方”より、“この子らしい学び方”を見つけるために
- 何度教えても伝わらない。
- やる気がないわけじゃないのに、勉強が進まない。
そんな毎日の中に、「この子なりの理解のしかた」を見つけるヒントが隠れています。
『学習障害かも』と迷い、どう関わればいいか悩んでいた私が、『この子らしさ』に寄り添えるようになった──3週間集中再安心サポートは、
「教え方」ではなく「見方」から変えていく家庭心理サポートです。
- がんばっているのに、なぜか結果が出ない。
- やる気がないわけじゃないのに、うまく進まない。
そんな子どもの姿に、どう接していいのか迷ってしまうことがあった。
- 「もっと集中すればできるはず」
- 「何度も言ってるのに、どうして忘れるの?」
そう思いながら、
繰り返し声をかけてきたけれど、
うまく届かないまま時間だけが過ぎていった。
実はこうした
「がんばってもできない」姿こそ、
家庭で気づける学習障害(LD)の初期サインにつながっています。
家庭だからこそ見える違和感を、
大切な手がかりとして受け止めていきましょう。
何度教えても覚えられない・ミスが多い
- 繰り返し教えているのに、また同じところでつまずいている。
- 答えは合っていたのに、記号が違っていたり、途中式を飛ばしていたり。
「前にもやったよね?」と、
思わず強い声を出してしまった日もあった。
本人なりに集中しているのは伝わっていた。
でも、
自分が何を間違えたのかすらわからず、
ただ黙り込んでしまう姿を何度も見てきた。
学習障害(LD)があると、
- 処理の順序
- 情報の記憶
にズレが生じやすくなります。
頭の中では理解できていても、
それを言葉や行動に移すまでに、時間がかかることがあります。
そのズレが
「わかっていない」と
誤解されやすいだけなんです。
何度もミスを繰り返していたのは、
努力が足りなかったからじゃない。
間違えるたびに自信を失っていっただけだった
──あなたもそう感じてきました。
集中が続かない・忘れっぽいのは性格じゃない
- 最初はやる気があるのに、すぐに手が止まってしまう。
- 覚えていたはずのことを数分後には忘れていたり、話を最後まで聞けなかったり。
- 「落ち着きがないな」
- 「もっと集中して」
と何度も注意してきた。
でも、叱っても変わらなかった。
むしろ
どんどん自信をなくして、
言い訳も増えていったように感じていた。
こうした特性は、
学習障害(LD)やADHDに見られるものです。
「集中できない」のではなく、
「集中が続きにくい脳のはたらき方」があるということです。
つい性格の問題と受け取ってしまいがちですが、
それは本人のせいではなく、
どうしてもズレが生まれやすい仕組みだったというだけ。
そう気づいたとき、
ようやく叱る以外の関わり方を考えられるようになりました。
やる気がないわけじゃないのに手が止まる
無料LINE診断|今のあなたに必要なサポートは?
『何から始めればいいかわからない…』そんなあなたへ。
LINEで「数字」を入力するだけで、今のあなたに合ったサポート商品を診断できます。
今すぐLINEに【 4 】の番号を入力してください。
それぞれの商品内容と「ぴったりの理由」が届きます。
- ノートを開いて、しばらく動かない。
- ペンを持ってはいるけれど、何も書かずにじっとしている。
「やる気がないの?」と何度も聞いてしまった。
でも、返ってくる言葉はいつも同じだった。
- 「今、考えてた」
- 「どこからやればいいのか迷ってた」
学習障害(LD)やADHDのある子どもには、
課題を始めるまでに時間がかかります。
これは、
情報を整理したり、
行動を組み立てたり
するのが
苦手な特性からきています。
やろうとしていないのではなく、
頭の中がごちゃごちゃになって進めなかっただけ。
そう受け止められるようになったとき、
声かけのトーンが自然に変わっていきました。
「うちの子だけ?」と悩んだら|学習障害の見分け方とチェックの視点
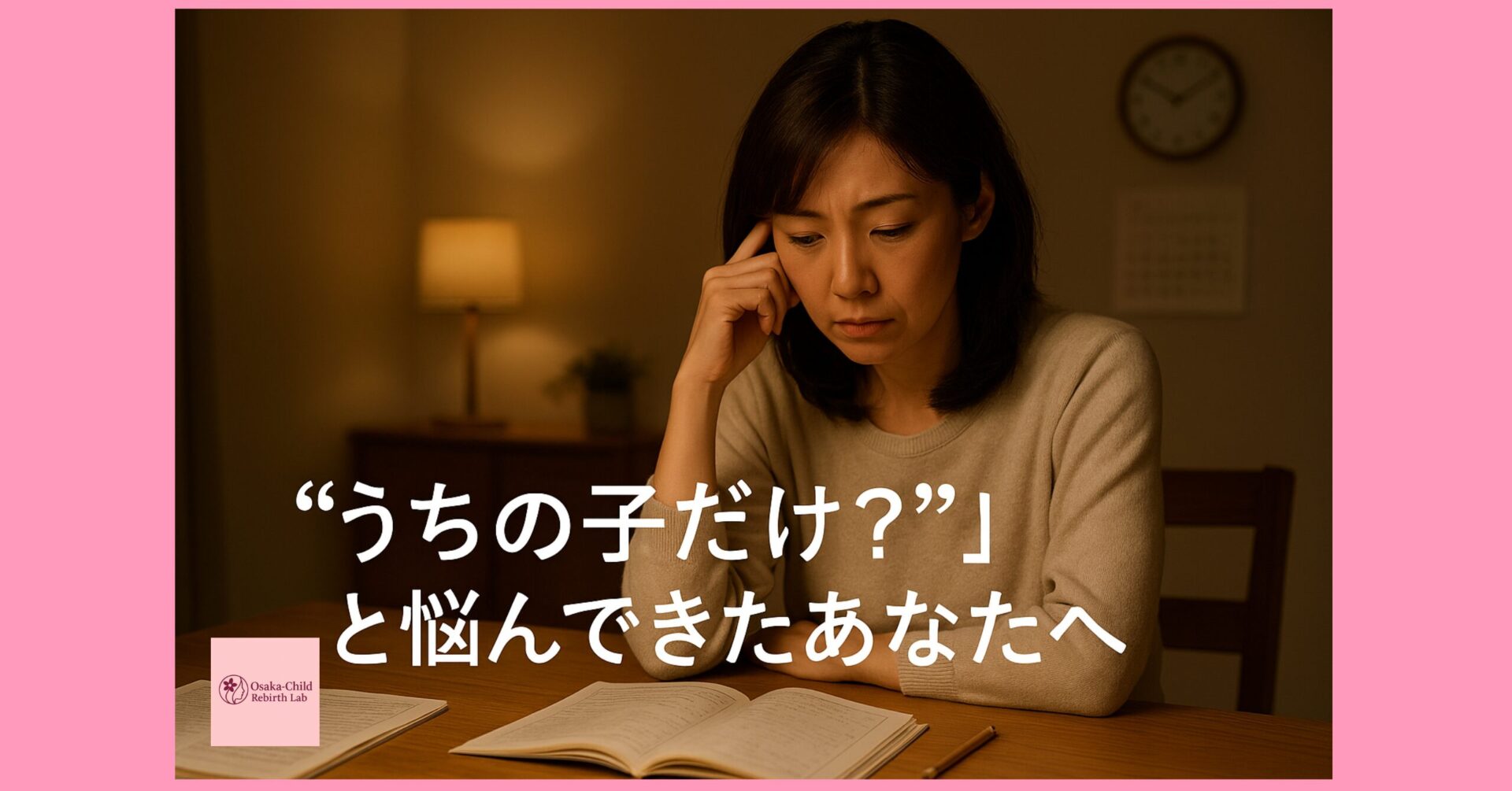
「やっぱりこの子だけ…?」と感じたときに考えてほしいこと
「ひらがなも算数もつまずいているのは、この子だけ」
そう感じたとき、不安よりも先に、
「この子の理解のしかた」を見直す視点を持てたら──
『学習障害かも』と迷い、どう関わればいいか悩んでいた私が、『この子らしさ』に寄り添えるようになった──3週間集中再安心サポートは、
「わが子の特性に気づく」ところから始まる家庭心理サポートです。
まわりの子と比べるつもりはなかった。
でも、
気づけば「なんでうちの子だけ、こんなに苦労してるんだろう」と
感じる時間が増えていた。
- 「成長過程で個人差があるから」
- 「もう少し見守ってみましょう」
そう言われてきたけれど、
それでも胸の奥がざわついていた。
本当は、何か手がかりが欲しかった。
「違いを理解したうえで、わが子と向き合いたい」と
あなたもそのように願っていますよね。
ここでは、
そんな迷いの中にいるときに
整理しておきたい3つの視点を通して、
学習障害(LD)の理解につながるヒントを一緒に見つけていきます。
性格?発達?グレーゾーンとの違いに迷ったら
- ミスが多い
- 集中が続かない
- 説明しても理解があいまい──
それを見て
- 「性格の問題なのかな」
- 「うちの育て方がよくなかったのかな」
と感じてきたことがあった。
でも、
どうしても引っかかるものが残っていて、
ココロのどこかで「何かが違う」と感じ続けていた。
ポイント
学習障害(LD)は
知的な遅れがないため、
見過ごされやすい特性です。
「わかっているのにできない」と
責められてきた子どももたくさんいます。
さらに、
ASDやADHDなどの他の発達特性と重なることもあり、
診断基準を満たさない
「グレーゾーン」に位置づけられる子も存在します。
このようなケースでは、
支援につながりにくい一方で、
困りごとは確かに日常にあらわれています。
性格でも育て方でもなく、
「脳の情報処理のズレ」が背景にあった──
そう気づいたとき、
「この子をどう変えるか」ではなく、
「どう支えるか」を考える視点に変わっていきました。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「もしかして学習障害?」
そう感じたときに、知っておきたい基本の知識と、家庭でできる対応のヒントをまとめています。
-

-
参考学習障害とは?読み書き・計算が「できない理由」と家庭でできる対応法【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「どうしてこんなに教えてるのに、できないんだろう」 そう思ったあとで、 つい声を荒ら ...
続きを見る
支援が必要なケースと「様子を見ていい」ケースの違い
「もう少し様子を見ましょう」
そう言われたとき、
何をどう見ればいいのかわからなくなっていた。
もちろん、
年齢や経験によって苦手な時期があるのは自然なこと。
でも、
- いつまでも変化がない
- むしろ困りごとが増えている──
そんな状態が続いているなら、
それは「見逃してはいけないサイン」です。
ポイント
学習障害(LD)への支援が必要とされる目安のひとつは、
「何度教えても改善されない困難さ」が、
教科や場面を越えて日常的に続いているという点です。
つまり、
教え方や環境を整えても状況が変わらないとき、
それは「育て方」ではなく
「特性」に基づく困難さだと受け止めることが必要になります。
「もっと早く気づいていればよかった」
──そう後悔しなくていいように、
気になった段階で、
小さくても動き出せる判断の軸を持っておくことが大切です。
無料診断|あなたの“心のパターン”を知る
「この子に本当に支援が必要なの?」
そんな迷いを感じたとき、LINEで「キーワード」を送るだけで診断できるサービスをご用意しています。
LINEに『学習障害 小学生』と入力して送ってください。
あなたに合った視点と解説をすぐにお届けします。
家庭でできる簡易チェックポイントとは?
- 「診断するほどじゃないのかな」
- 「誰に相談していいか分からない」
そうやって迷っている時間の中でも、
家庭で見えるサインは確実にあった。
ポイント
学習障害(LD)の初期サインは、
日々の生活のなかに小さく現れています。
以下のような様子が続いている場合は、
一度整理して見直してみてください。
- ひらがなやカタカナがなかなか覚えられない
- 音読を極端に嫌がる
- 繰り返し教えてもすぐに忘れてしまう
- 説明を最後まで聞けず、途中で内容が抜ける
- 計算や記号のミスを何度も繰り返す
こうした困りごとは、
家庭で一番気づきやすい「日常のサイン」です。
親だから見えていたこと。
それを
「気のせい」で済ませなくて、
本当によかった。
ここまで来るまでに、
ひとりで抱えてきた時間も長かったと思います。
勉強が苦手な子の「学び方」は、ひとつじゃない|家庭でできる関わり方

「何度教えてもできないのは、私の教え方が悪いのかな…」と悩んでいた頃に
- 「ひらがなが覚えられない」
- 「計算が遅すぎる」
──でも、わが子なりに毎日がんばっていることも分かっていた。
宿題を見ているうちに、ついイライラしてしまう。
そのたびに「また怒ってしまった」と、自分を責めていた日々。
『学習障害かも』と迷い、どう関わればいいか悩んでいた私が、『この子らしさ』に寄り添えるようになった──3週間集中再安心サポートは、
「伝え方」の前に、「見方」をやさしく整える」
家庭から始められる心理サポートです。
こんな方におすすめです
- 毎日、勉強をめぐって口調がきつくなってしまう
- 学校での様子を聞くたびに不安が募る
- 苦手の背景に何があるのか知りたい
- 母として、もっと寄り添ってあげたいと願っている
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 1月17日(土)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと2名様限定』
※銀行振込限定・先着順
そして──
少しずつ「この子の理解のしかた」に気づけるようになった今、
「私の時間」にもやさしい目を向けてみたくなっていませんか?
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
母として歩んできた経験を糧に、
「わたし自身のこれから」を築き直す3週間。
子育て中心だった毎日から、
少しずつ「自分の時間」を取り戻していく流れをつくります。
- わが子の見方を変えることができてきた
- でも、自分のことは後回しのまま
- 「母だけじゃない私」を再発見したい気持ちがある
このプログラムでは、
「母として」の時間のその先へ、
「私として生きる」新しいページを開いていきます。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
- 「何度教えてもわからない」
- 「やる気がないように見える」
──そんな姿を前に、焦ってしまったこともありますよね。
思うように伝わらなくて、
「どうしてわかってくれないの?」って、
ココロの中で叫んでいた日もあったと思います。
でも本当は、
「学び方が合っていない」だけのこともあります。
家庭での関わり方を少し見直すだけで、
子どもが前向きに取り組みはじめることもあるんです。
ここでは、
勉強に苦手意識を持つ子どもへの接し方を、一緒に見つめ直してみましょう。
「合わない方法」で教え続けていませんか?
- 「ノートに書いて覚えなさい」
- 「何回も音読したらいい」
──そうやって「自分が教わってきた方法」を、
そのまま子どもに伝えてきた方も多いはずです。
でも実は、
その方法が子どもに合っていません。
- 視覚的な情報より、耳からの情報のほうが入りやすい子もいれば、
- 音声では理解できず、図や具体物がないとイメージがつかめない子もいます。
学習障害(LD)のある子どもは特に、
「一通りのやり方」では伝わりにくいことが多いんです。
ポイント
だからこそ、
「この子に合う方法ってなんだろう?」と、
いったん立ち止まってみることが大切になります。
一度試してダメだったやり方を、
何度も繰り返すよりも、
別の方法に変えてみたほうが、
子ども自身が「わかった!」と感じやすくなります。
「理解していない」のか「伝わっていない」のか
一生懸命教えているのに、
なかなか覚えられない。
そんなとき、
「どうしてこんな簡単なこともわからないの?」と、
イライラが募ってしまうこともありますよね。
でも実は、
「わかっていない」のではなく、
「伝え方が伝わっていない」だけのこともあります。
たとえば、
- 一度に長く話されると、頭が真っ白になる子
- 言葉ではなく、手順を実際に見ないとイメージできない子
- 途中で話しかけられると、何をしていたか忘れてしまう子
──こうした特性があると、こちらの意図がうまく届かなくなります。
教える側が「言ったよね?」と思っていても、
子どもはそれを「情報として処理できていない」こともある。
だからこそ、
「伝え方のズレ」に目を向けるだけで、
親子のすれ違いはぐっと減っていきます。
勉強をめぐる親子関係がしんどくなっていたら
- 「またできなかったの?」
- 「なんで同じことを何回も聞くの?」
──そんな言葉が、つい口をついて出てしまったことはありませんか?
本当は、怒りたいわけじゃない。
「どうにかしてあげたい」という気持ちがあるからこそ、
言葉が強くなってしまう。
でも、そのたびに、
子どもとの距離が少しずつ広がっていくように感じていました。
勉強のことで衝突するたびに、
子どもは
- 「自分はできない」
- 「怒られる存在」
と感じやすくなります。
それが積み重なると、
「学び」そのものへの拒否感にもつながっていきます。
だからこそ、
勉強の前に必要なのは、
「わかってもらえる」という安心感なんです。
親子の関係がやわらぐだけで、
子どもの学ぶ姿勢がはっきりと変わっていきます。
「うまく伝えられなかった日が続いても、大丈夫」
今日ここから、関わり方を変えていけばいいんです。
「学習障害かも」と悩む毎日から、「この子らしさ」に寄り添える私へ

- どこまでサポートすればいいのか。
- どのくらい頑張れば、この子はできるようになるのか。
そんなことばかり考えて、毎日が張りつめた時間になっていた。
- ちゃんと向き合ってきたのに、うまく届かない。
- この子のためにと思って動いてきたのに、空回りしてしまう
──あの頃の私は、ずっとそんなふうに立ち尽くしていた。
でも今ならわかる。
必要だったのは「どう教えるか」よりも、
「どう見て、どう受けとめるか」という視点だったということ。
ここからは、
「できなさ」にばかり目を向けていた日々から、
「この子らしさ」を見つけ直していく関わり方へ。
その視点の転換が、親としての安心を取り戻す第一歩になるはずです。
「教え方」より「見方」を変えることで変わる関係
- 「何度も言ってるのに」
- 「この前できたのに、なんで今日はできないの?」
そんな苛立ちが積もっていった日々があった。
でも、
問いかける方向が間違っていた。
正しく教えることばかりに意識が向いて、
この子が
- 「どう見えているか」
- 「どう感じているか」
には、気づけていなかった。
「伝えた」つもりでも、
相手の受け取り方が違えば届いていない。
そのことに気づいた瞬間、
これまでの関係が少しずつ変わりはじめた。
教え方に答えがあるんじゃなくて、
この子の見え方に寄り添ったとき、
はじめて「伝わる」という体感が生まれていく。
「わからせる」ではなく「わかってあげる」関わりへ
- 「わかってくれない」
- 「やればできるのに」
そんな言葉で責めていたのは、自分の焦りをぶつけていたからだった。
本当は、この子の方がずっと困っていた。
どこでつまずいているのか、どうすれば理解できるのか。
そのプロセスに寄り添わず、結果だけを見て判断していた。
「わからせる」ことばかりに力を注いでいた頃は、
うまくいかないたびに、
- 自分を責め
- 子どもを責め
- 疲弊していた。
でも、問いかけ方を変えてみた。
「どこが難しかった?」と。
その言葉だけで、
子どもの表情が変わったことを、今でも覚えている。
「わかってあげる」ことから始める関わりが、
親子の空気をやわらかくしていく。
3週間集中サポートで取り戻す「親としての安心」
- 「このままじゃダメだ」
- 「でも、何をどう変えればいいのかわからない」
そんな日々を繰り返していた。
《3週間集中再安心サポート》では、
そうした迷いや不安を一人で抱え続けてきたお母さんに、
もう一つの関わり方の視点を届けています。
「『学習障害かも』と迷い、どう関わればいいか悩んでいた私が、『この子らしさ』に寄り添えるようになった──3週間集中再安心サポート」
このサポートは、
診断の有無ではなく、
「この子の特性」と「お母さんの感覚」をつなぎ直すプロセスを大切にしています。
勉強が苦手という現実の奥にある、
「伝わらなさ」の背景。
それに丁寧に目を向けることで、
叱ることから離れ、
「わかりあえる関係」をつくりなおしていく。
「自分が変わる」のではなく、
「この子との関係を、安心して見直せる場所」。
そんな時間を、ここから一緒に始めていけます。
「『この子らしさ』に寄り添える関わり方」が、ここから始まる
- ちゃんと教えてるのに、どうして伝わらないんだろう。
- 頑張ってるのに、なぜできないって言われるのか。
このモヤモヤを、誰にも説明できなかった。
「困ってるのに『どこにも当てはまらない』」
そんな孤独を抱えて、ただ時間だけが過ぎていった。
でも本当は、
診断名よりも先に必要だったのは、
「わかってあげたいのに、わかってあげられなかった」
その苦しさに、誰かと一緒に向き合う場所だった。
「『学習障害かも』と迷い、どう関わればいいか悩んでいた私が、『この子らしさ』に寄り添えるようになった──3週間集中再安心サポート」は、
「家庭の中でできること」に焦点をあてた、
母親のための心理サポートです。
このサポートでは、次の3ステップを通して、
お母さん自身の関わり方を見つめ直しながら、
子どもとの関係を少しずつ整えていきます。
STEP①|気づく
わが子の「できなさ」ばかりに
目が向いていた背景を整理し、
「この子らしさ」に光を当てる視点に切り替える。
STEP②|実践する
- 叱らずに伝える言葉
- 伝わる関わり方
を、日常の中に取り入れていく実践的ステップ。
STEP③|軸をつくる
ラベルや診断に頼らず、
「私たちなりの向き合い方」を信じられる軸を取り戻す。
この3週間で、
お母さん自身が少しずつ変わっていくと、
子どもとのやりとりにも、自然な変化が生まれていきます。
叱っていた場面で、そっと待てるようになる。
伝わらなかった言葉が、届くようになる。
気づけば、家庭の空気がやわらいでいる。
「どうしたらいいかわからない」
そう悩み続けてきたあなたにこそ、
この3週間は、「安心の土台」を整える時間になります。
この子にとっての安心は、
お母さんが「私も大丈夫」と感じられることから始まっていく。
その第一歩を、ここから一緒に踏み出してみてください。
“勉強の教え方”に限界を感じてきたあなたへ
「どう教えても伝わらない」「また怒ってしまった」──そんな毎日を繰り返して、ひとりで悩んできた方へ。
「この子の学び方」に合わせた関わりが、今日からできるようになります。
「学習障害かも」と感じても、すぐに答えが出ないこともあります。
でも、お母さん自身の関わり方を整えるだけで、親子の空気は変わっていきます。
焦らなくていい。「この子らしさ」を見つける3週間、ここから始めませんか?
まとめ|「この子の学び方を信じてみたい」そう願い始めたあなたへ
- できるようになってほしい。
- ちゃんと教えれば、この子もきっとできるようになる。
そう信じて頑張ってきたのに、またできなかった──
そんな日々が続くと、
自分の声がどんどん強くなっていって、
あとで後悔ばかりが残ることもありますよね。
宿題を見るたびに不安が増して、
「やる気がないわけじゃないのに」と感じながら、
どう声をかければいいのか分からなくなっていた。
でも、ふとした瞬間に思うんです。
この子には、この子なりの学び方があるんじゃないかって。
それに気づいたとき、
ずっと背負ってきたものが少しだけゆるんで、
ようやく「見守る」という選択肢が見えてきた気がして──
この記事で伝えたかったこと、5つにまとめます。
この記事で伝えたこと
- 学習障害(LD)は、「努力が足りない」ではなく「情報の受け取り方」に違いがある状態
- 「読み書き」や「計算」など、つまずきのパターンには明確な違いがある
- ADHDやASDなど、他の発達特性と重なっているケースもある
- 苦手を叱るより、「どう見えているか」に寄り添う視点が関係をやわらげていく
- 診断より先に、「母親自身が安心できる関わり方」を整えることが大切
できないことを正す前に、
この子がどんな世界を見ているのかに目を向ける。
それが、
学習障害(LD)という言葉に出会ったあなたに
必要な「もうひとつの視点」。
「小学生の勉強の苦手さが、こんなふうに見えてくるなんて」
読み進めるうちに、
わが子への関わり方を少し見直せた気がする──
そんな変化がココロのどこかに芽生えた方もいると思います。
この関わり方じゃ、苦しかったんですよね。
「『学習障害かも』と迷い、どう関わればいいか悩んでいた私が、『この子らしさ』に寄り添えるようになった──3週間集中再安心サポート」では、
「教え方」ではなく
「見方」を整える5ステップで、
小学生の学習障害によくある勉強のつまずきに向き合っていきます。
焦りや期待を手放しながら、伝わる言葉と接し方を一緒に整えていきます。
もう、ひとりで抱え込まなくて大丈夫。
正解探しをやめて、「この子とのつながり直し」を始める3週間。
ここから、少しずつ変えていけます。
「ひらがなも計算も、なぜこんなに苦手なんだろう…」と悩み続けてきた方へ
- 「ひらがなを何度練習しても覚えられない」
- 「算数の文章題を前に固まってしまう」
家庭学習のたびに、わが子が苦しそうな顔をする。
「どうしてこんなにできないの?」と聞きたくなって、
そのたびに自分を責めていた──。
『学習障害かも』と迷い、どう関わればいいか悩んでいた私が、『この子らしさ』に寄り添えるようになった──3週間集中再安心サポートは、
「できない理由」を探す前に、
「この子の感じ方・理解のしかた」に気づく
お母さんのための心理サポートです。
こんな方におすすめです
- ひらがな・カタカナが極端に苦手で気になっている
- 算数ドリルでよく止まってしまう
- 学校から「見守りが必要」と言われて戸惑っている
- 家庭で何かしてあげたいけど、どう関わればいいか分からない
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 1月17日(土)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと2名様限定』
※銀行振込限定・先着順
ネットバンキングのご利用で、今すぐ開始することが可能です。
そして──
少しずつ「この子のペースでいい」と思えるようになった今、
自分自身にも「優しい目」を向けたくなっていませんか?
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
わが子との関係を見つめ直してきた日々の先に、
「私の人生」を再設計する3週間のサポートです。
- 子育ての不安が少しずつ落ち着いてきた
- でも、「自分のこと」は後回しのままだと感じている
- 母である前に「私」としての時間を取り戻したい
このプログラムでは、
「母の役割」から少しだけ離れ、
「わたしの人生」を歩き直す準備を整えていきます。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
すでに診断済みの方も、そのまま詳細ページへ進めます。
あなたの心と体に合ったサポートを、今すぐ確認してみてください。








