
「教えてるのに、伝わらない」
──その苦しさを、ずっとひとりで抱えてきた
きっとあなたも、
何度もくり返してきたはずです。
- 「わからないの?」
- 「昨日もやったよね?」
そう声をかけながらも、
ココロのどこかでは、
「この子、ほんとうに困ってるんだろうな」って、感じていた。
でも、言葉にできなかった。
親として、
どう受け止めればいいのか、
誰にも教えてもらえなかった。
- 宿題を前に黙りこむ。
- 何度言っても音読が詰まる。
- 簡単な計算ですら、なぜか指が動かない──。
「なんでできないの?」
その問いは、
いつの間にか
- 「この子はダメなんだ」
- 「私はダメな親なんだ」
って、自分を責める呪いになっていった。
この記事では、
そんな「言葉にならない違和感」の正体を、ゆっくり整理していきます。
この記事で得られる5つのこと
- 性格ややる気のせいにされやすい「学習のつまずき」の本当の背景
- 読み書き・計算など、LD(学習障害)のタイプ別特徴
- 家庭で気づける12のチェックポイント
- 医療機関に行く前に、親ができる「まなざし」の切り替え
- 診断がつかなくてもできる、日々の関わり方の整え方
知識だけでは、解けないことがありますよね。
- わかってあげたいのに、また怒ってしまった。
- 関わりたくて声をかけたのに、余計に泣かせてしまった──。
そんな日々に、
「これじゃダメだ」って思いながらも、
一体どうしたらよかったのか、わからなくなっていました。
- 教えても届かない「できなさ」に、何度もココロが折れそうになった。
- 叱りたくないのに、また声を荒げてしまった。
ほんとは──ただ、わかってあげたかっただけなのに。
- 「教え方の問題なのかな」
- 「私が神経質すぎるのかな」
そんなふうに、自分を責めてきたあなたへ。
「教えても届かない『できなさ』に悩んだ私が、『わかってあげられる関わり方』を見つけた──3週間集中再安心サポート」
では、
親が「変わる」ことを目指しません。
はじめに取り戻すのは、
「この子を見るまなざし」です。
努力不足でも、怠けでもなかった。
ずっと、がんばってたのはこの子だった。
そのことに気づけたとき、
母親としてのココロの棘が、すっとやわらいでいきます。
この3週間は、知識を増やす時間ではありません。
怒りの奥にあった「届かなさ」をほどきながら、
どう関われば、ちゃんと受け取ってもらえるのか──
あなたとお子さんだけの「あたらしい関係」を、一緒に見つけていく時間です。
- 叱らなくても伝わる。
- 教え込まなくても、分かち合える。
そんな毎日が、ここから始まります。
この記事が、その最初の小さな入り口になりますように。
監修者
株式会社Osaka-Child所属 小児神経科医
- 名前: 三浦あすか
- 出身地: 兵庫県西宮市
- 最終学歴: 神戸大学医学部 小児科専攻
- 専門分野: 小児神経、DCD(協調運動障害)、発達性ディスプラクシア、HSP気質の子ども支援
- 職歴: 兵庫県立こども病院 小児神経センター勤務(11年)
専門分野について一言: 「できないことの奥にある“がんばっているサイン”を、もっと社会全体で受けとめていけたらと思っています。」
監修者
株式会社Osaka-Child所属 臨床心理専攻大学教授
- 名前: 森本哲夫
- 出身地: 奈良県
- 最終学歴: 米国ハーバード大学心理学部 博士課程修了
- 専門分野: 臨床心理学、発達心理学
- 職歴: ハーバード大学研究員(5年)、大阪大学人間科学部教授
専門分野について一言: 「心の成長とは、自己理解の旅でもあります。その旅のお手伝いができれば幸いです。」
「どうしてうちの子だけ、こんなに勉強が苦手なんだろう」…と検索し続けた夜に
宿題のたびに声を荒げてしまう。
- 「私の教え方が悪いの?」
- 「この子がふざけてるだけ?」って、
自分も子どもも責めていませんか?
「うちの子、やる気がないだけ」
──そんな言葉では片づけられない毎日があるんですよね。
頑張っても読み書きに時間がかかる。
それを見ているあなた自身が、一番つらかったはずです。
『何度言ってもできない子』にイライラしていた私が、『この子なりの理解のしかた』に気づけた──3週間集中再安心サポートは、
「性格」や「努力不足」ではなかった子どもの困難に、
家庭の中から気づき直していくための心理サポートです。
こんな方におすすめです
- 漢字や音読の宿題が毎日バトルになっている
- 勉強が苦手なだけ?と迷い続けてきた
- 「親のせい」と言われたようで誰にも相談できない
- 病院に行く前に、できることがあるなら知っておきたい
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 1月18日(日)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと1名様限定』
※銀行振込限定・先着順
▶ 今のこの子の困りごとを、家庭の中から理解したい方はこちら
そして──
わが子への不安が少しずつ落ち着いてきた今、
「私自身のこれから」を見つめ直したいと感じているあなたへ。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
「母としての安心」を土台に、
「私としての人生」を再設計する3週間。
子育てだけで埋まっていた時間に、
少しずつ「私自身の感情」が戻ってくる。
- わが子の特性に向き合えるようになってきた
- でも「私は何のために生きているんだろう」と感じている
- 誰かの期待ではなく、自分軸の人生を取り戻したい
このプログラムでは、
「子育ての葛藤を乗り越えた私」を出発点に、
「わたしの人生」にもう一度光をあてていきます。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
「ちゃんとしてるのに、苦しい」
「頑張ってるのに、うまくいかない」
——そんな違和感を抱えたまま、ずっと我慢していませんか?
LINEで3分セルフ診断ができます。
あなたの“今の感覚”の正体が、見えてきます。
どうしてできないの?|小学生の「学習障害」に気づけない理由

- 「なんでこんなに時間がかかるの?」
- 「さっき説明したのに、なんでまた同じことを聞くの?」
──こんなやりとりを、繰り返してきましたよね。
でもそれって、
- 親の教え方が悪かったわけでも、
- 子どもにやる気がないわけでもなかった。
見えない「つまずき」があった。
それが、
これまで気づかれずに隠れていただけだったんです。
ここではまず、
学習障害という視点から、
「どうしてできなかったのか」を一緒にひもといていきます。
読み書きが苦手な子どもに、どう接してきたか
「教えてるのに伝わらない…」そんな毎日から抜け出すヒント
- 何度教えても覚えられない
- 書けない
- 読めない
「ふざけてるの?」と怒ってしまったあと、自己嫌悪だけが残る──
そんなあなたに届けたいのが、
『教えても届かない「できなさ」に悩んだ私が、「わかってあげられる関わり方」を見つけた──3週間集中再安心サポート』です。
まずは、「親の関わり方」から整えていきませんか?
- 「何回言っても直らない」
- 「この前も教えたのに、なんでまた忘れるの?」
そんなふうに、
がっかりしてしまったこともありますよね。
でも、
それだけ何度も繰り返してきたのは、
ちゃんと関わってきた証です。
本気で向き合ってきたからこそ、
「できるようになってほしい」って願ってきた。
でも、
- 何度教えても覚えられない。
- 何回書いても間違えてしまう。
そのたびに、
「努力不足なのかな」と疑う気持ちが湧いてきても、
おかしくないですよね。
だけど実は、
- 「読みにくい」
- 「書きにくい」
といった「感覚そのもの」に違いがあることもあるんです。
そして
その「違い」は、
周りから見えづらくて、
ずっと本人だけが苦しんできた。
そう思えた今だからこそ、
見えなかったことを責める必要はありません。
「今、気づけたこと」こそが、大切な一歩なんです。
「ふざけてるのでは?」と誤解される構造
たとえば、
- 授業中にソワソワしたり、
- 突然話しかけたり、
- 忘れ物が多かったり。
──そういう行動を見ると、
「ふざけてるの?」と感じることもありますよね。
でも、
その奥にあったのは、
「困っていることを伝えられない」という、
言葉にならないもどかしさでした。
- 黒板の字がすっと入ってこない。
- プリントの文字が、どこから読めばいいかわからない。
- 質問されると、頭の中が真っ白になる。
その
- 「戸惑い」
- 「混乱」
を、どう伝えていいのかわからないから、
代わりに
- 「ふざける」
- 「黙る」
- 「逃げる」
といった行動で表現してしまうんです。
行動だけを見ると叱りたくなるけれど、
背景にある
「認知のしづらさ」に目を向けてみると、
きっとこれまでとは違うまなざしを持てるようになるはずです。
「努力不足じゃない」と言い切れる根拠とは
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「頑張ってるのに、どうしてできないんだろう」
そんな悩みを抱えてきた方へ。
学習障害(LD)の種類や気づき方を、全体像からわかりやすく整理した解説ガイドをご用意しました。
👉 「この子の困りごと」が理解に変わる|学習障害の種類と気づき方まとめ
-

-
参考学習障害とは?読み書き・計算が「できない理由」と家庭でできる対応法【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「どうしてこんなに教えてるのに、できないんだろう」 そう思ったあとで、 つい声を荒ら ...
続きを見る
いちばんしんどいのは、
本人自身です。
「がんばってるのに、できない」
それを一番感じてきたのは、
他でもない、子ども自身だったのです。
LD(学習障害)は、
知的な発達に問題がないのに、
「読み・書き・計算」の一部にだけ、
極端な苦手さが現れるという特性があります。
だからこそ、
「ほかのことはできるのに、なぜここだけ?」という
ギャップが生まれやすく、
そのたびに
「もっと努力すればいいのに」と誤解されてしまう。
でもこの「アンバランスさ」は、
育て方や性格の問題ではありません。
脳の情報処理の特性に由来するものです。
そう考えると、
これまで子どもに向けてきた
「がんばりなさい」という言葉を、
少し違う角度から見直してみたくなりませんか?
「この子は、努力が足りないんじゃなくて、『工夫』が必要な子だった」
そう気づいたとき、関わり方は大きく変わっていきます。
学習障害チェックリスト|家庭で見抜く12のサイン

無料診断|あなたの“心のパターン”を知る
「なぜこの子だけ、こんなに勉強が苦手なんだろう…?」
そんな疑問に向き合いたいあなたへ。
LINEで「学習障害 チェックリスト」と送るだけで、視点とヒントが届きます。
📩 LINEに「学習障害 チェックリスト」と入力してください。
あなたの不安に寄り添うメッセージを、すぐにお届けします。
「ここだけ、なぜかできない」
そう感じた場面は、これまで何度も積み重なってきています。
でもそれを
- 「甘えてる」
- 「集中してない」
と片づけてしまうのは、もう終わりにしていい。
ここでは、
学習障害(LD)の特徴として現れやすいサインを、
家庭の中で気づくための12のチェックポイントとして、
順番に紹介していきます。
読字障害(ディスレクシア)|読み間違え・音読の困難さ
音読の宿題を見ていて、
うまく言えないけど
「なんだか読みにくそうだな」と感じたことはありませんか?
たとえ音が出ていても、
読んでいる本人の頭の中は
ぐるぐる混乱していることもあります。
このキャプションでは、
読み取りに困難がある場合に見られやすい4つの行動を整理しました。
文字を飛ばして読んだり、行を間違える
一文一文、ていねいに読もうとしているのに、
いつの間にか
- 1行飛ばしていたり、
- 同じ行を繰り返していたり
する。
視線の動きに「リズムのズレ」があって、
読むことに集中しづらい様子が見られます。
見たことのある漢字が読めなくなる
学校では読めていた漢字なのに、
家では「これ何だっけ…?」と戸惑うことがある。
頭の中では覚えていても、
文字として「形」を認識する力にムラが出やすく、
読めたり読めなかったりが、日によって大きく揺れます。
本を読みたがらず、すぐに疲れてしまう
- 「本はイヤ」
- 「読んでもわからない」
と避けてしまう。
開いてもすぐに閉じてしまう姿を、何度も見てきた。
読み続けること自体がストレスになっていて、
ココロも体もすぐに疲れてしまいます。
読んだ内容を理解するのに時間がかかる
声に出して読むのはできても、
内容がまったく頭に入ってこない。
読んだはずなのに、
「何の話だったっけ?」と聞き返してくることも。
ポイント
読むことと理解することを同時に行うのが、
極端に負担になっている状態です。
書字障害(ディスグラフィア)|書くことが極端に苦手
ノートに何かを書くとき、
妙に疲れていたり、
集中が切れている様子に気づいたこと、ありませんか?
ただの
- 「雑さ」
- 「だらしなさ」
ではない、
書くことそのものに困難さを抱える子がいます。
文字の大きさや形がそろわない
ていねいに書こうとしているのに、
なぜか文字が大きくなったり小さくなったりする。
「ふつうに書いて」と言われても、
「どれくらいがふつうなのか」が、
うまくわからないんですよね。
ポイント
手の力加減や、
文字のサイズ感覚を調整するのが難しくて、
毎回ちがうバランスになってしまいます。
ノートの行に文字が収まらない
罫線の上に書いているつもりでも、
文字が上下にはみ出してしまう。
「ちゃんとマスの中に書いて」と
何度言っても変わらないと、
イライラする日もあったはずです。
でも実はこれ、
「線を基準に位置を合わせる」こと自体が、
想像以上にむずかしい感覚なんですよね。
同じ漢字・カタカナを何度教えても覚えられない
昨日できていた漢字が、
今日はすっかり抜けている。
「また忘れたの?」と声を荒げてしまった日も、
きっとあったと思います。
でもそれは、
「わかっていない」んじゃなくて、
「つながらない」だけ。
ポイント
記憶の道が不安定で、
毎回ゼロからがんばっている感覚に近いんです。
書くのに時間がかかり、宿題が終わらない
「急いで」と言いたくなるくらい、
1行に何分もかかってしまう。
途中で鉛筆が止まり、
空を見ている姿に、
つい責める気持ちが湧いてきたこともありますよね。
でもそれは、
サボっているんじゃなくて、
「書く」だけで体力をすごく使っている状態。
やりたくても、
追いつかない。
そのくり返しが、
どんどんココロも疲れさせていくんです。
算数障害(ディスカリキュリア)|数や量の理解ができない
計算だけじゃなく、
- 「時間」
- 「順番」
- 「数字の意味」
でも、
つまずく場面がこれまで何度も続いていました。
ここでは、
家庭の中で気づきやすい「算数のつまずき」を整理しています。
数の順番や大小が理解しにくい
「1、2、3…」と
声に出して数えているのに、
いつの間にか順番が崩れてしまう。
「どっちが大きい?」と聞いても、
目が泳いで、
答えに詰まることがある。
数字は知っていても、
それを「意味のある並び」としてつかむことがむずかしい状態です。
時計や時間の感覚がつかめない
- 「10時45分」
- 「5分前に来てね」
──そう伝えたのに、
まったく違う行動をしてしまうことがある。
- 針の位置
- 時間の流れ
が頭の中でつながらず、
「いつ・どれくらい」が見えにくくなっている状態です。
指を使っても簡単な計算で間違える
一生けんめい数えているのに、
答えがズレてしまう。
「それ、さっき教えたよね」と言いたくなる瞬間が、
何度もあった。
ポイント
数を数える動きと、
数字の意味を理解することが、
うまくかみ合っていない様子が見られます。
文章問題になると混乱してしまう
「りんごが3つで100円です。5つ買うといくら?」
そう聞かれた瞬間、
- 手が止まり、
- 表情が曇ってしまう。
文字は読めていても、
「どこをどう計算すればいいか」が見えてこない。
ポイント
文章と数字が頭の中で結びつかず、
問いの意図がつかみにくくなる特性があります。
「小学生らしくない」困りごとは、親のせいじゃない
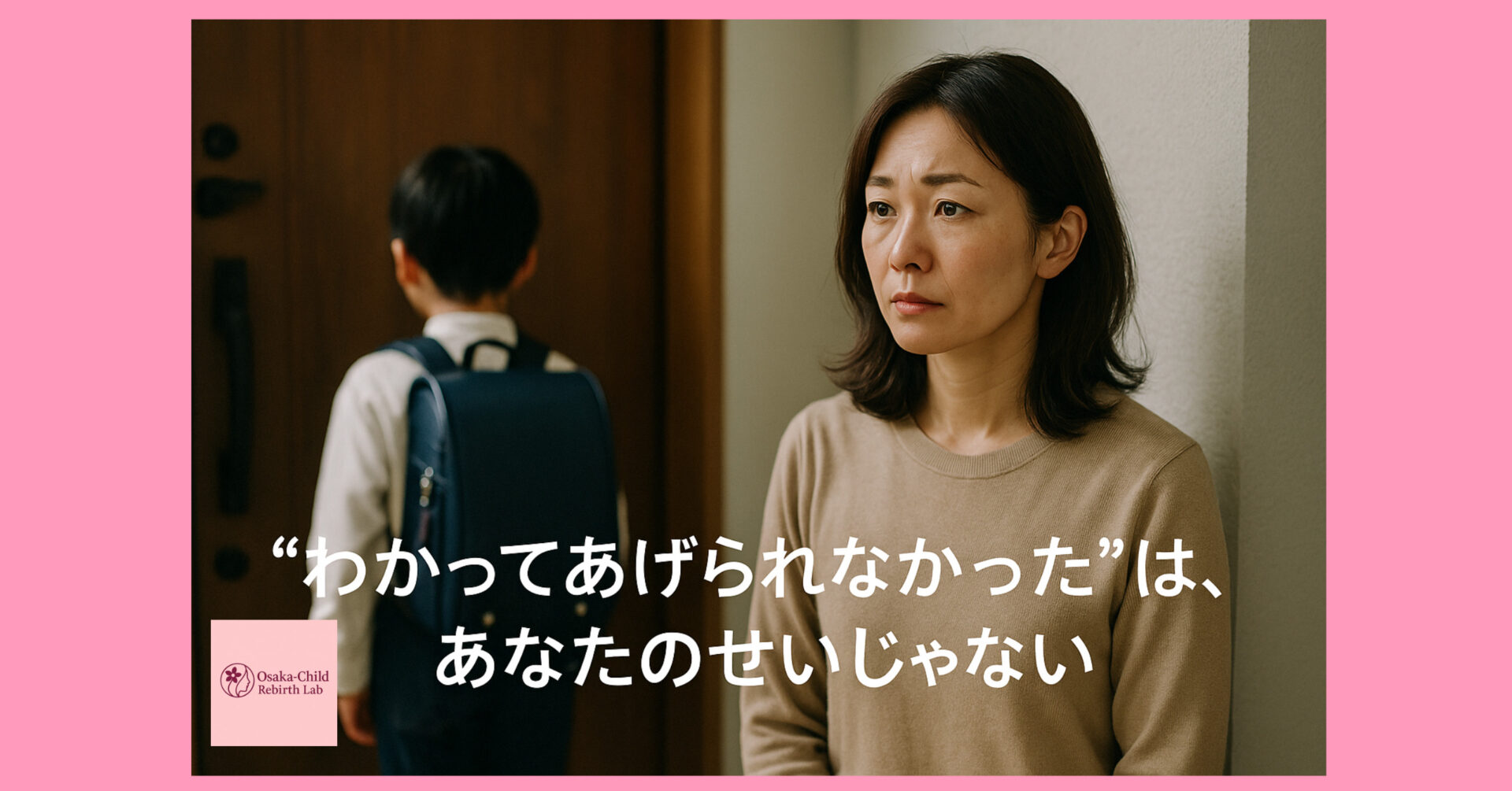
「もう小学生なんだから、これくらい普通できるでしょ」
──そう言われるたびに、自分のせいだと感じて、ずっと責めてきました。
でも、
子どもの「できなさ」は、
育て方やしつけで片づけられるものじゃありません。
ここでは、
「うちの子、なんでこんなに手がかかるんだろう」という疑問の奥にある、
「本当の原因」に気づいていく視点をお伝えします。
「何度言ってもわからない」の正体
「こんなことでつまずくなんて、うちの子だけ…?」
- 読み書きにすごく時間がかかる。
- ノートをとるのも苦手。
それなのに
「ふざけてるだけ」
「やる気がない」
と言われて、つい同じように怒ってしまう──
学校では「問題なし」と言われる。
でも家では毎日が大変で、
どう関わっていいのかわからない。
あなたの中には、そんな戸惑いが積み重なってきていませんか?
『努力不足だと思って叱っていた私が、『理解のしかた』が違っただけと気づけた──3週間集中再安心サポート』は、
診断名や制度に頼らず、家庭の中から整えていくための
「まなざしのリセット」を支える心理サポートです。
こんな方におすすめです
- 宿題のたびにイライラして、声を荒げてしまう
- まわりと比べて、うちの子だけ極端に遅れている気がする
- 頑張らせたいけど、どう関わればいいかわからない
- 夫にも理解されず、相談できる場所がない
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 1月18日(日)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと1名様限定』
※銀行振込限定・先着順
そして──
子どもとの関係が少し整ってきた今、
「自分のココロ」にも目を向けたくなってきたあなたへ。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
子育ての延長ではなく、
「私自身の人生」を見つめ直すための3週間。
誰かのために頑張ってきた日々を、
「私がどう在りたいか」にそっと戻していく。
- 子育てにひと区切りがついてきた
- でも「私が本当に望んでいること」がわからない
- 母という役割を超えて、「私」を取り戻したい
このプログラムでは、
「この子と向き合った経験」を糧に、
「わたし自身の再出発」をサポートします。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
- 「昨日も言ったよね」
- 「何度同じことを言わせるの?」
──そのたびにイライラして、でも本当は怒りたくなかった。
- わかってほしかっただけ。
- ちゃんとできるようになってほしかっただけ。
でも、
子どもが動かないのは
「言うことを聞いてない」からではなく、
「言葉を理解して、行動に移すまでのプロセス」に、
目に見えないつまずきがあるから。
- 耳では聞いていても、意味が入ってこない
- 手順を一つひとつ処理するのに時間がかかる
- 頭ではわかっていても、身体が動かない
それを「ふざけてる」と誤解されることが、
何度もありました。
でもそれは、
「わからないふり」ではなく、
本当に「つながらなかった」だけなんです。
子ども自身も「できない自分」に傷ついている
できないことで怒られるたびに、
- 「またダメだった」
- 「どうせ自分は無理」
と、子どもは自分を責め続けています。
それを表に出せない子ほど、
静かに傷ついて、
静かにあきらめていく。
最初はやろうとしていた。
がんばろうとしていた。
でも、
がんばっても結果が出ないと、
「もうやらないほうがマシ」と感じてしまうようになる。
だからこそ、
できないことを責めるのではなく、
「がんばっても伝わらなかった気持ち」に
目を向けてほしいんです。
その視点があるだけで、
子どもはもう一度、前を向けるようになります。
家で見せないのに、学校では困っている理由
「この子だけ、なぜか違う」…その違和感、大切にしてほしい
- 「うちの子だけ、どこか幼い」
- 「勉強以前につまずく」
そんな感覚を、あなたはずっと見てきたんですよね。
それは「過保護」ではなく、「ちゃんと見てきた」証拠です。
『教えても届かない「できなさ」に悩んだ私が、「わかってあげられる関わり方」を見つけた──3週間集中再安心サポート』では、
診断よりも前に、「あなたのまなざし」を整えていくことから始めます。
「うちの子は家では問題ないんですけど…」
そう言っていたお母さんが、
学校での様子を聞いて驚くこともありますよね。
- 「プリントを出し忘れる」
- 「先生の話を聞いていない」
- 「手が止まっていることが多い」
でも、
それは「気を抜いている」わけじゃない。
学校という環境が、
子どもにとって「負荷の大きい場所」になっているだけ。
- 集団の中で空気を読む
- 指示を一度で理解して動く
- 時間内にやり切る
この3つが同時に求められる学校では、
認知に特性を抱えた子にとって、
頭の中がフル稼働状態になります。
家では安心できていた。
でも、
学校では常に緊張と混乱の中にいた──
そのギャップこそが、
「見えにくい困りごと」の正体です。
病院より前に、「家庭でできるチェック方法」がある
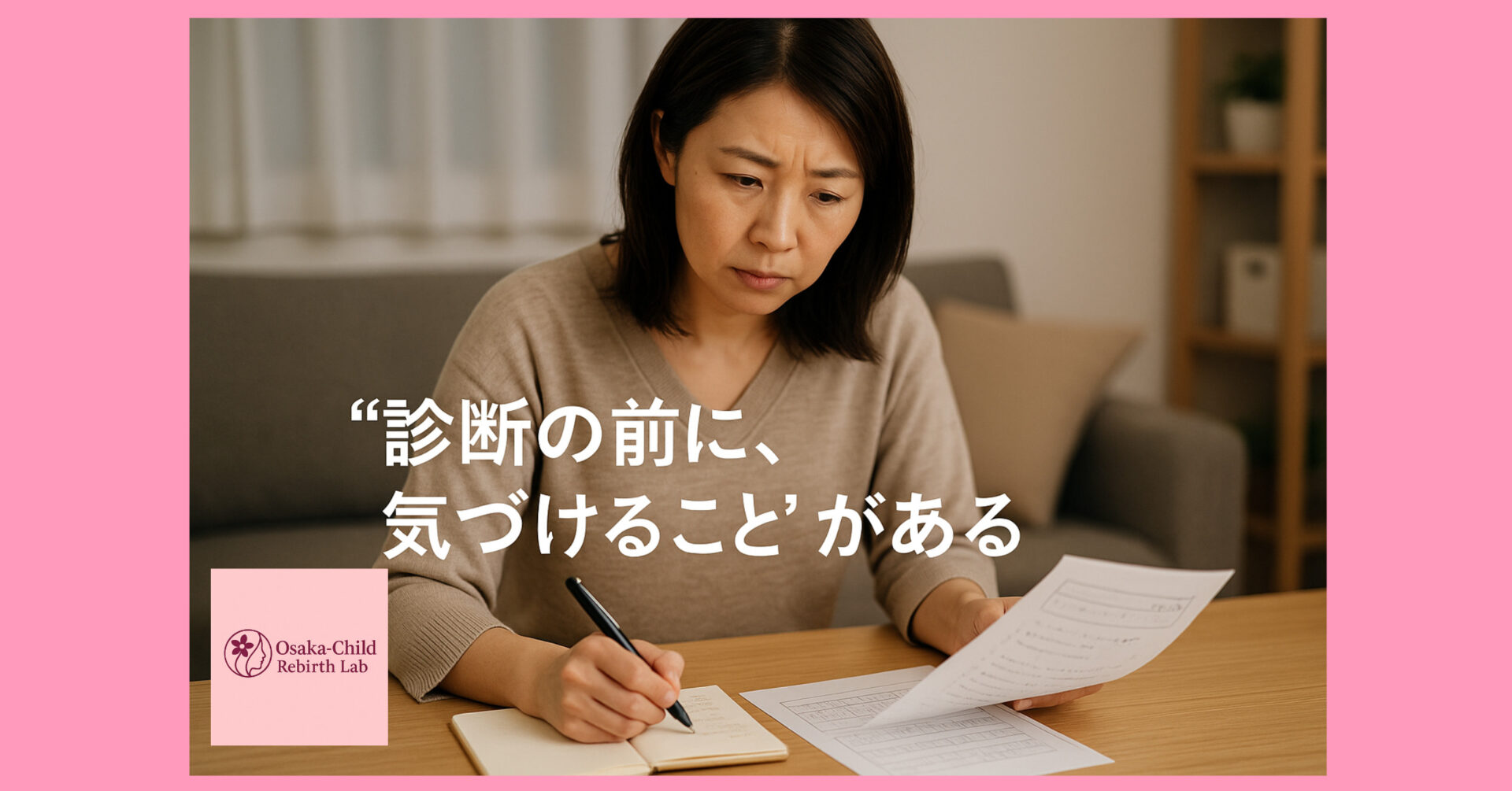
「病院に行ったほうがいいのかな」
でも、
何を基準に判断すればいいのかわからない。
誰にも言えないまま、
抱え続けてきた苦しさがあったんですよね。
すぐに専門家を頼るのもひとつの手段。
でもその前に、
「家庭の中だからこそできること」も、たくさんあります。
ここでは、
今この瞬間から始められる
- 「気づきの視点」
- 「支援の入り口」
をお伝えします。
医療機関にすぐ行く前にやっておきたい3つの視点
焦る気持ち、
ほんとうによくわかりますよ。
「この子を、どうすればいいのか」って、
必死に調べてここまでたどり着いたんですよね。
でも少しだけ深呼吸して、
いきなり病院に行く前に、
こんな3つの視点を持っておけたら──
その後の判断が、ぐっと楽になります。
① 比較じゃなく、「本人の中の変化」を見ること
他の子と比べて遅い・できないではなく、
「この子の中で、どこが止まってる?」という視点が必要です。
② 「困っているのは誰か」を見極めること
- 親が困っているのか、
- 子ども自身が苦しんでいるのか。
主語をすり替えないまなざしが大切になります。
③ 「診断をもらうため」だけの受診にならないようにすること
名前やラベルよりも、
「今ここでこの子に合う関わり方があるかどうか」が本質です。
これを意識しておくだけで、
受診の前段階でも、
ちゃんと「今できること」を見つけていけます。
家でできる学習障害の見抜き方と注意点
- 「何度教えても覚えない」
- 「毎回、同じところでつまずく」
──そんな「繰り返しの違和感」に気づいているなら、
それだけでもう立派なスタートです。
家でできるチェックの軸は、
「特定のパターンで困っているかどうか」
たとえば:
- 読み間違いが何度も起きる
- ノートを書くときだけ極端に疲れる
- 足し算だけやけに時間がかかる
- 「その教科だけ」になるとイライラする
こういう「限定されたつまずき」こそが、
支援のサインです。
ただし注意したいのは、
これをもとに「診断名」を断定しないこと。
家庭での気づきは、
医療的診断ではなく、
関わり方を整えるための情報です。
うまく言えないけど、
「あ、なんかこの子、苦しそう」っていう直感──
それを無視しないで、ぜひ拾い上げてください。
診断がなくても支援は始められる
“診断がなくても、始められる支援”がここにあります
「診断されるほどじゃない」と言われても、困っている現実は変わらない。
そのモヤモヤを、「ちゃんと向き合う力」に変えていく時間です。
『教えても届かない「できなさ」に悩んだ私が、「わかってあげられる関わり方」を見つけた──3週間集中再安心サポート』では、
診断や制度ではなく、「母親の直感と視点」を大切にした関わり方を提案しています。
「診断がないと、何もできない」
そんなふうに感じて、
ずっと立ち止まってきたんですよね。
でも実は、
支援は「診断後」ではなく、
「気づいたとき」から始められるんです。
たとえば:
- 順番をメモにしてあげる
- 目で見て選べるようにしておく
- 「どうしてできないの?」をやめて、「どうすればやりやすい?」に言い換える
こうした配慮は、
診断があってもなくても、有効です。
誰かから許可が下りなくても、
あなた自身が「やってみよう」と思えたなら、
それで十分。
この子にとって必要なのは、
「制度」じゃなくて、
そばにいる人の「理解」ですよね。
そんな気がして、
ずっと悩みながらここまで来たあなたなら、
もう支援の入口に、ちゃんと立てていますよ。
教えても届かない「できなさ」に悩んだ私が──3週間集中再安心サポート

何度も伝えたつもりだった。
- 「こうしたらいいよ」
- 「わかってるよね?」
って、何度も。
でも、
気づけば怒ってばかりで、
子どもとの距離だけが広がっていく。
本当は、わかってあげたかった。
ただそれだけだったのに。
そんなあなたへ届けたいのが、
《教え方》じゃなく、
《関わり方》を整えるための3週間サポートです。
叱っても解決しない「関わり」に疲れていた
- 「こんなに怒りたくないのに」
- 「なんで今日もまた、ぶつかってしまったんだろう」
そのたびに、
自分の声がむなしく響いて、
気づけば、
家の中がピリピリした空気になっていく。
ちゃんと向き合ってきたのに、
わかってもらえない日々が続いていた。
あの苦しさは、
誰にも言えないまま残っていたんですよね。
でもそれは、
「あなたの関わり方が間違っていた」わけじゃありません。
ただ、
この子に合った「入り口」を見つけられていなかったというだけ。
このサポートでは、
まずその「入口」を一緒に探していきます。
- 言葉じゃなく、まなざしで。
- 指示じゃなく、安心で。
あなたが届けたかったものを、
もう一度ちゃんと届ける準備を整えていきましょう。
「この子らしさ」に気づいた3つのプロセス
わたしたちが届けたいのは、
この子の「できる形」を取り戻す3ステップです。
①「どこで止まっていたか」を一緒に見つける
ただの「できない」じゃなく、
「いつ・どこで・どうつまずいていたか」を丁寧に紐解いていきます。
② 合うやり方で伝え方を変えてみる
- 文字じゃなく、カードで。
- 言葉じゃなく、タイミングで。
「この子なりの受け取り方」に寄せていくだけで、
表情が少しずつ変わっていきます。
③「この子らしさ」にもう一度出会い直す
うまく言えないけど──
「ちゃんとできる子」じゃなく、
目の前のこの子の
「リズム」が見えてきたとき、
あなたの中でも、なにかが静かに変わり始めていましたよね。
その変化を、
3週間かけて一緒に育てていくサポートです。
『わかってあげられる関わり方』が家庭に安心を取り戻す
気づけば、
毎日が「戦い」みたいになっていた。
- 朝の支度で怒鳴る
- 宿題のたびにイライラする
- 夜になると、自分ばかりが疲れている
本当は、笑って過ごしたかった。
ただ一緒に過ごすだけでよかったはずなのに。
「教えても届かない『できなさ』に悩んだ私が、『わかってあげられる関わり方』を見つけた──3週間集中再安心サポート」
- 「発達障害とまでは言えない」
- 「でも、やっぱり育てにくい」
困っているのに、どこにも当てはまらない。
その「説明できない不安」を、
誰にも伝えられないまま、
ずっと抱えてきた方もいると思います。
家庭の中で起きている現実に、
周りは何も気づいてくれなかった。
誰にも伝えられないまま、
どうしていいかわからずに抱えてきた毎日がありましたよね。
このサポートは、
診断名や支援の枠組みよりも、
まず「お母さん自身の安心」を整えることを大切にしています。
気づかれず、
理解されない日々を生きてきたあなたが、
もう一度「この子と向き合える自分」に戻るための3週間です。
サポートでは、以下の3ステップで“関わり方”を再構築していきます。
STEP①|気づきの整理
- 「イライラしてしまう理由」
- 「つい強く言ってしまう瞬間」
に名前をつけて、
自分の内側をやさしく言語化するところから始めます。
STEP②|届く関わり方の発見
この子の特性や反応を一緒に見つめながら、
どう伝えれば受け取ってもらえるのかを、
具体的に探っていきます。
STEP③|私たちなりのまなざしを育てる
支援や診断に頼らなくても、
家庭の中でできる「安心の土台」をつくり直していきます。
このプロセスを経て、
今まで通じなかった言葉が、
少しずつこの子に届いていく。
顔を合わせるたびに張りつめていた空気が、
やわらかくほどけていく。
お母さんのココロに余白が戻るたびに、
家庭全体にも安心感が広がっていきます。
ポイント
大切なのは、診断でも方法論でもありません。
あなたが安心して、
目の前のこの子と向き合えること。
それが、すべてのはじまりです。
“「ふざけてるんじゃない」と気づけたお母さんへ
努力不足じゃなかった。ふざけてるわけでもなかった──
「この子、困ってたんだ」と気づいたその瞬間から、関わり方は変えられます。
- 「教えても届かない」
- 「何度言っても同じ」
そんな毎日に疲れてしまったあなたへ。
この3週間は、「怒らなくても伝わる関係」を取り戻すための時間です。
診断がなくてもOK。
家庭の中から始められる、「わかってあげられる母親」への一歩を、一緒に歩いてみませんか?
まとめ|「怒らなくていい日常を取り戻したい」と願うあなたへ
- 「こんなに頑張ってるのに、どうして伝わらないの?」
- 「どうして、あの子だけがこんなに…」
うまく言えないけど、
「何かが違う気がする」という違和感を、あなたはずっと感じてきたはずです。
- 先生に言われた一言、
- ママ友との何気ない会話。
そのたびに、胸の奥がギュッとなって、
「私の育て方が悪いのかな…」と、
自分を責めてしまう日もありましたよね。
でも本当は、
- あなたはずっと向き合ってきた。
- 毎日、怒りながらも、諦めずに関わろうとしてきた。
それだけで、もう十分すぎるほど頑張ってきたんです。
だからこそ、今ここからは、
「どうすればできるようになるか」ではなく、
「どうしたらこの子と『わかり合える』か」を一緒に探していきませんか?
この記事で伝えたかったこと
- 読み・書き・計算の「できなさ」には、認知のつまずきが隠れている場合がある
- 家庭で見抜ける12のサインから、発見のきっかけはつかめる
- 「ふざけてる」と誤解していた背景には、本人の葛藤があった
- 医療機関に行く前に、親として「整えておける視点」がある
- 診断がなくても、家庭の中から支援は始められる
「教えても届かない『できなさ』に悩んだ私が、
『わかってあげられる関わり方』を見つけた──3週間集中再安心サポート」では、
毎日のバトルや、
伝わらないつらさを抱えてきたあなたの関わり方を、
「つながり直す」ために整えていく時間としてデザインしています。
子どもと一緒に、
「怒らなくても伝わる日常」を、
ここから少しずつ取り戻していきましょう。
私たちは、その第一歩を一緒に歩いていく準備ができています。
「『頑張ってるのにできない』って、本人が一番つらそうだった」
- 音読の宿題に1時間
- 漢字練習で毎回ケンカ
できない姿を見ているのが、つらくてたまらなかった。
- 「甘やかしてるのかな」
- 「やらせ方が悪いのかな」
と、何度も自分を責めた。
「努力不足に見える」その裏で、
この子なりに毎日、精いっぱい踏ん張っていた。
あなたもずっと、それに気づいていたんですよね。
『何度言ってもできない子』を責めていた私が、『理解のしかたが違っただけ』と気づけた──3週間集中再安心サポートは、
「できなさ」の奥にある特性に寄り添い直す
家庭の中から始める「まなざしの再構築」です。
こんな方におすすめです
- 勉強をめぐって毎日怒ってばかりになっている
- まわりの子と比べてしまって、落ち込んでいる
- この子の「できなさ」の正体を知りたい
- 「理解する関わり方」を家庭の中で見つけたい
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 1月18日(日)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと1名様限定』
※銀行振込限定・先着順
ネットバンキングのご利用で、今すぐ開始することが可能です。
そして──
この子との関係を、一歩ずつ整えてきたあなたへ。
その歩みは、もう「自分を生き直す準備」になっています。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
子どもの育ちに向き合ってきた日々を土台に、
「母」ではない「私自身」の人生に光をあて直す3週間。
- わが子の特性に対する理解が深まってきた
- でも「私はどう生きたいのか」がまだ見えていない
- 「家庭」だけではなく、「自分自身の軸」も整えたい
このプログラムでは、
「母としての葛藤を超えた私」から始まる、
「自分の人生」をていねいに再構築していきます。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
無料LINE診断|今のあなたに必要なサポートは?
「何から始めればいいかわからない…」そんなあなたへ。
LINEで“数字”を入力するだけで、今のあなたに合ったサポート商品を診断できます。
今すぐLINEに【 4 】と入力してください。
「教えても届かない『できなさ』に悩んだ私が、
『わかってあげられる関わり方』を見つけた──3週間集中再安心サポート」のご案内が届きます。
すでに診断済みの方も、そのまま詳細ページへ進めます。
あなたの心と体に合ったサポートを、今すぐ確認してみてください。








