
うまく言えないけど、
ずっと引っかかっていた。
- 宿題に何時間もかかる。
- 読んでるのに頭に入ってない。
- 字が歪んでる。
なのに、
集中していないようにも見えるし、
ふざけてるようにも見える。
そのたびに、
- 「ふざけないで」
- 「何度言えばわかるの?」
と、声が大きくなっていった。
でも本当は、わかりたかっただけ。
どうしてこんなにも、
この子が「できない」のか。
その理由が知りたくて、
毎晩検索して、
たどり着いたのが
- 「学習障害(LD)」
- 「ADHD」
という言葉だった。
調べれば調べるほど、
「どっちも当てはまる気がする」ようで、
でも、
「うちの子は違うかも」とも感じて…。
答えを探し続けて、さらに混乱していった。
この記事では、そんなあなたのために
「学習障害(LD)とADHDの違い」をやさしく整理しています。
この記事を読んでわかること
- 学習障害(LD)とADHD、それぞれの「つまずきの出かた」がわかる
- 両方の特性が重なって見える理由と、その背景が見えてくる
- ASD・DCDとの違いも、図解と視点で整理できる
- 支援の判断を「診断名」に頼らず考えられるようになる
- 「私の子はこれかも」と感じられる視点を取り戻せる
いちばん知りたかったのは、
「この子に何があるのか」じゃなかった。
ほんとうは、
「今、この子が何に困っているのか」を、
一緒に見つけたかっただけだった。
- 「どうして何度言ってもできないの?」
- 「うちの子、他の子と違うのかな…」
そんなふうに思っては、責めてしまった夜もあった。
でも本当は、わかってあげたかっただけ。
──わが子と向き合ってきたあなたの時間は、きっと間違っていなかった。
「LDかADHDか分からず責めていた私が、『この子らしさ』を見つけた──3週間集中再安心サポート」
では、
「できない理由」を、
母親の視点でやさしく整理しながら、
関わり方そのものを、少しずつ見つめ直していきます。
怒ってきた日々にも意味があったと知ることで、
関係の糸がほどけていく。
誰かに委ねなくても、
母親のまなざしから整えていける、
そんなサポートです。
「もうどうしていいかわからない」
──その気持ちが、ひとつの出発点になります。
「見え方」が変われば、「関わり方」も変わっていく。
ここから、あなたとわが子だけのペースで、やり直していけます。
監修者
株式会社Osaka-Child所属 小児神経科医
- 名前: 三浦あすか
- 出身地: 兵庫県西宮市
- 最終学歴: 神戸大学医学部 小児科専攻
- 専門分野: 小児神経、DCD(協調運動障害)、発達性ディスプラクシア、HSP気質の子ども支援
- 職歴: 兵庫県立こども病院 小児神経センター勤務(11年)
専門分野について一言: 「できないことの奥にある“がんばっているサイン”を、もっと社会全体で受けとめていけたらと思っています。」
監修者
株式会社Osaka-Child所属 臨床心理専攻大学教授
- 名前: 森本哲夫
- 出身地: 奈良県
- 最終学歴: 米国ハーバード大学心理学部 博士課程修了
- 専門分野: 臨床心理学、発達心理学
- 職歴: ハーバード大学研究員(5年)、大阪大学人間科学部教授
専門分野について一言: 「心の成長とは、自己理解の旅でもあります。その旅のお手伝いができれば幸いです。」
「ADHD?LD?…どれか分からない」混乱の中で、検索し続けてしまった夜に
- 「読む力にムラがある」
- 「集中が続かない」
学校からの言葉に、戸惑いと不安が押し寄せてきた。
- 「この子、発達障害なのかな…」
- 「私の育て方がいけなかったの?」
ネットで「正しそうな答え」を探しても、
どれもピンとこなくて、余計に混乱していく──。
LDかADHDか分からず責めていた私が、『この子らしさ』を見つけた──3週間集中再安心サポートは、
診断名の前に、「わが子を見る視点」を整える
お母さんのための心理サポートです。
こんな方におすすめです
- ADHDと言われたけど、納得しきれない
- 学習障害の可能性があると言われて不安
- 支援の話が出たけど、まだ決めきれない
- 誰にも相談できないまま、自分を責めている
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 1月16日(金)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと1名様限定』
※銀行振込限定・先着順
そして──
わが子の特性を受けとめられるようになった今、
「私自身の人生」にも目を向けてみたいと感じているあなたへ。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
「母としての安心」を土台に、
「わたしとしての人生」を再設計する3週間。
誰かのためだけじゃなく、
「私のために生きる」感覚を取り戻していきます。
- 子育ての不安が少しずつ落ち着いてきた
- でも「私って何が好きだったっけ?」と感じている
- 母親だけで終わらない人生を築きたい
このプログラムでは、
「役割をこえた自分」を取り戻すサポートを行います。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
「ちゃんとしてるのに、苦しい」
「頑張ってるのに、うまくいかない」
——そんな違和感を抱えたまま、ずっと我慢していませんか?
LINEで3分セルフ診断ができます。
あなたの“今の感覚”の正体が、見えてきます。
学習障害とADHDはどう違う?|「できない」と「落ち着かない」を整理する
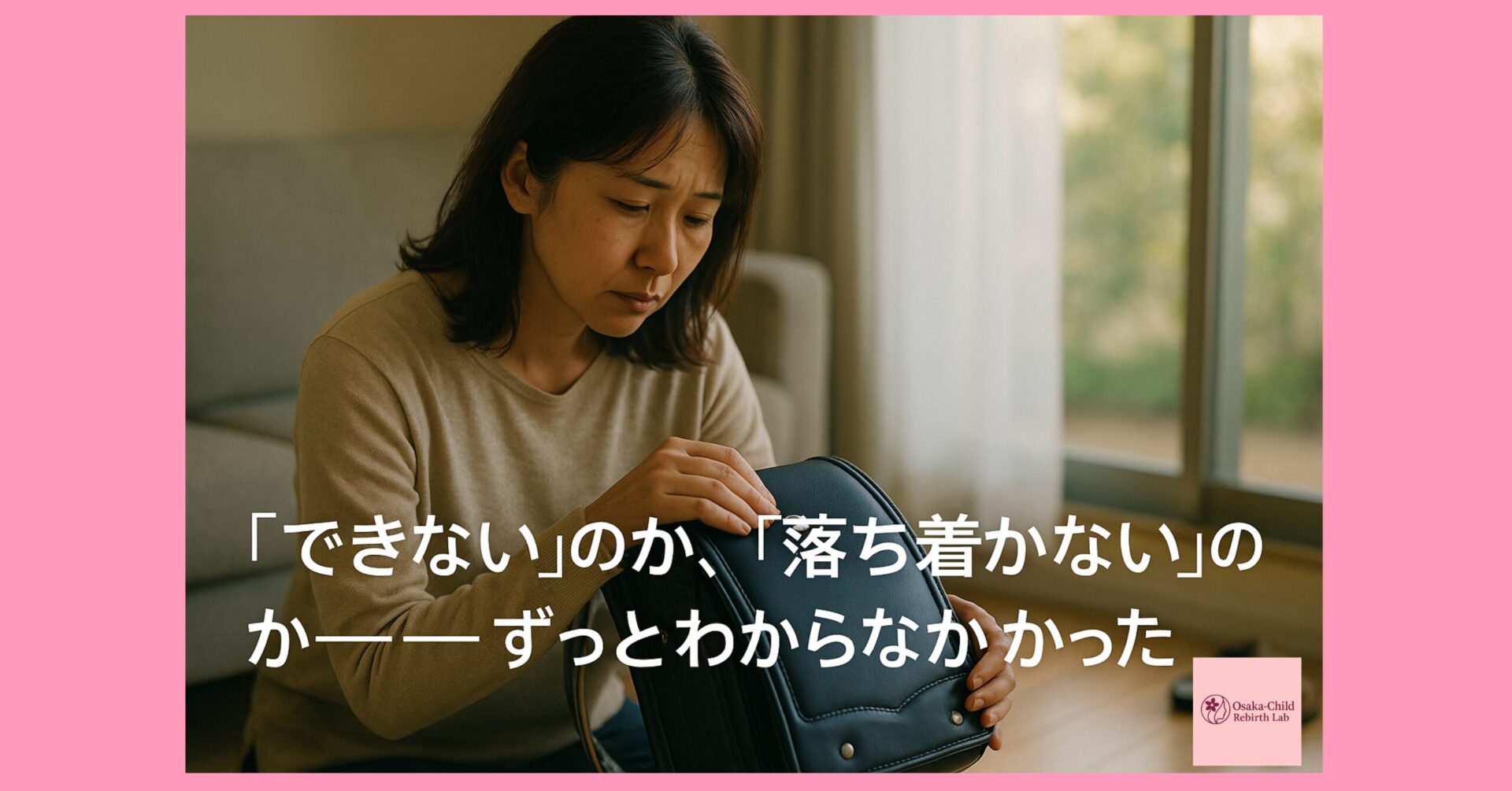
- 「授業に集中できてない気がする」
- 「読み書きになると、なぜか止まってしまう」
──そう感じたとき、学習障害なのか、ADHDなのか、見分けがつかずに悩んでいたことがありましたよね。
どちらも「学び」に関わる困難だけど、
実はその中身がまったく違います。
まずは、
- 「何が苦手なのか」
- 「どこでつまずいているのか」
という視点で整理していきましょう。
無料診断|あなたの“心のパターン”を知る
「LD?ADHD?どっちも当てはまる気がする…」
そんな迷いを感じているあなたへ。
LINEで「学習障害 ADHD」と送るだけで、
今のあなたに必要な視点とヒントが届きます。
📩 LINEに【 学習障害 ADHD 】と入力して送信してください。
あなたのモヤモヤを整理する、専門家監修の解説をお届けします。
学習障害(LD)は「読み書き・計算」の困難が中心
- プリントを書き写すのにすごく時間がかかる。
- 文章を読んでも意味が頭に入ってこない。
- 計算が進まないまま、ノートが真っ白になっていた──
そういうとき、やる気がないわけじゃなかった。
頑張っているのに、
「なぜかできない」という感覚だけが積み重なっていった。
学習障害(LD)は、
- 読み
- 書き
- 計算など
特定の学習分野だけに困難が現れる発達特性です。
「この子、怠けてるのかな?」と誤解されやすいけれど、
実際には脳の処理の仕方に違いがあるという背景があります。
本人の努力不足ではなく、
ポイント
ただ「情報の入り方・出し方」が他の子とちがうだけ。
それに気づけたとき、子どもとの関わり方がやわらかく変わり始めます。
ADHDは「注意・多動・衝動」のコントロールが課題
- 忘れ物が多い。
- 話しかけても、すぐどこかに意識が飛んでいる。
- 静かに座っていても、気づくと手足が動いてしまう──
ADHDの場合は、
「学ぶ内容」そのものではなく、
- 集中を保つ
- 落ち着いて取り組む
という部分に苦手さがあると感じてきたでしょう。
- やろうとしてるのに、止まってしまう。
- 分かっているのに、最後まで続けられない。
そんな「どうにもならなさ」が、
子ども自身をいちばん苦しめてきた。
周りの子と同じようにできないことを、
- 「甘え」
- 「しつけの問題」
にされてきた経験もありました。
でも、
ポイント
ADHDは
注意力や衝動のコントロールがうまくいかない発達特性であり、
「わざと」ではないという理解が必要です。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「結局うちの子って、学習障害なの?ADHDなの?」
そんな疑問を感じた方へ。
読み書き・計算の「つまずき」と、発達特性との関係を整理した専門解説をご覧ください。
-

-
参考学習障害とは?読み書き・計算が「できない理由」と家庭でできる対応法【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「どうしてこんなに教えてるのに、できないんだろう」 そう思ったあとで、 つい声を荒ら ...
続きを見る
併存することもある|LDとADHDの「重なり」に気づく視点
- 集中が続かないし、読み書きも苦手。
- どちらの特徴も当てはまる気がする──
そんなふうに感じたこともありますよね。
実は、
学習障害(LD)とADHDは
重なってあらわれることもよくあります。
たとえば、
- 注意が散りやすくて音読が定着しなかったり
- 計算のミスが多すぎて自信を失っていくなど
いくつもの困難が重なって見えることがあります。
「この子はどっちなんだろう」と決めようとすると、
かえって苦しくなることもありましたよね。
大切なのは、
どんな診断名よりも、
「今どこで困っているか」をひとつずつ丁寧に見ていく視点です。
そこから、
子ども自身が「わかってもらえた」と感じる関わり方が始まっていきます。
“どっちの傾向もあるかも”と感じたとき、安心のヒントを
「集中もできないし、読み書きも苦手…これって両方なの?」
そんなふうに、ひとりで悩んできたあなたへ。
- ADHDなのか
- LDなのか──
はっきりした答えが見つからない中でも、
「この子をちゃんと理解したい」という気持ちは、いつもあなたの中にあったはず。
この3週間で、「診断名に縛られずに向き合う力」を家庭の中から整えていけます。
ASDと学習障害の違いは?|「理解のズレ」と「読み書きの困難」を分けて考える
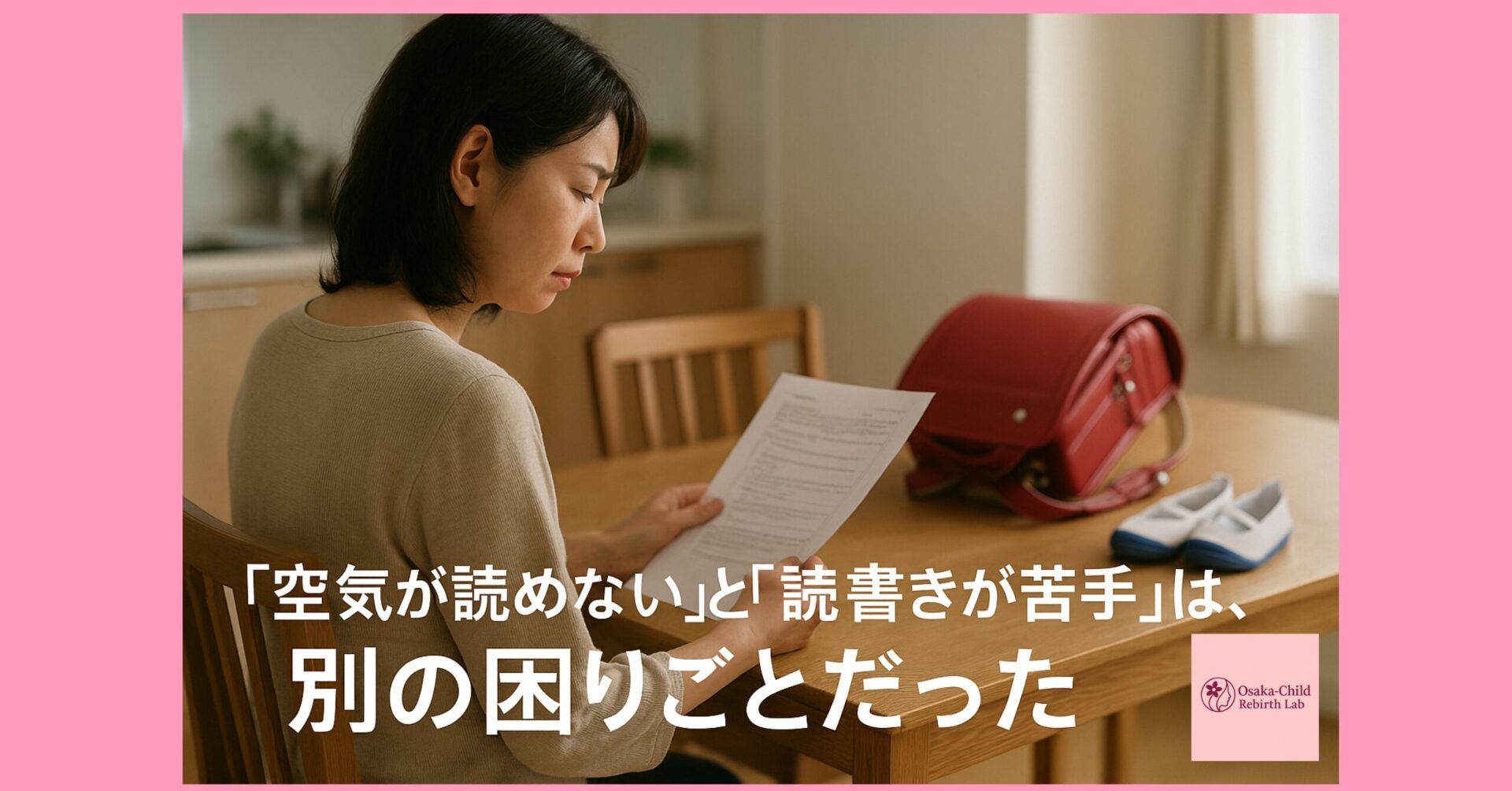
- 「授業にはついていけているのに、なんとなく浮いている気がする」
- 「コミュニケーションに違和感があるような…」
──そんな違和感と、読み書きや計算の困りごと。
どちらもあって、
どう捉えればいいかわからなくなっていた時期がありましたよね。
ここでは、
ASD(自閉スペクトラム症)と学習障害(LD)の違いを、
子どもの「見えづらい苦手さ」という視点から整理していきます。
ASDは「対人関係・空気の読み方」に特徴が出やすい
- 指示の意味は理解しているのに、ズレた行動をしてしまう。
- お友だちとの距離感がつかめず、トラブルになる。
- 空気を読もうとしても、どう動けばいいのかわからなくなっていた──
そんな場面が、日常の中に何度もあった。
ASDには、
相手の感情の変化や、
言葉の裏にあるニュアンスを受け取りにくいという特徴があります。
- 「言われた通りにやっているのに、なぜか怒られる」
- 「うまくやりたいのに、いつも浮いてしまう」
──そんなすれ違いが、積み重なっていった経験があります。
本人は一生懸命やろうとしていた。
でも、
まわりには「わざとやっている」ように見えてしまう。
そのズレが誤解を生み、
人との関係がぎくしゃくしていく原因になります。
だからこそ、
ただ「落ち着いて」と言うだけでは届かない。
まずは、
「空気を読む」という感覚自体にギャップがあるという視点を持つことが、
理解の入り口になります。
学習障害との違いを「読み書き」で見分ける視点
ASDの子にも読み書きの苦手さが見られることがある。
それと学習障害(LD)の「読み書きの困難」はどう違うのか──
迷ってしまった経験をあなたもありますよね。
違いを見極める視点として大切なのは、
「何が原因で読み書きが難しくなっているのか」という部分です。
学習障害(LD)の場合は、
- 文字の形を認識する
- 音と文字を結びつける
- 言葉を順番に処理するなど
「読み書きそのものの処理」に難しさがあるという背景があります。
一方で
ASDの子は、
- 読み書きの処理はできていても、
- 指示の意味を取り違えたり、
- 内容に興味を持てなかったりする
ことで手が止まるケースがあります。
つまり、
「能力の問題」ではなく、
- 「理解の仕方」
- 「受け取り方」
にズレがあるという構造です。
困っている「理由」を見つめ直すことで、
見分けにくかった部分がすこしずつ整理されていきます。
ASDとLDが併存するときのサインと支援の考え方
- 空気を読むのが難しく
- 指示も通らない
それに加えて、
読み書きや計算でもつまずきが出ている──
どちらの特性も重なって見えたとき、
どう受け止めればいいのかわからなかったこともありますよね。
ASDと学習障害(LD)は、
一緒にあらわれることもあります。
たとえば、
- 音読はできるけど内容が理解できない。
- あるいは、文字は読めているのに板書が追いつかない。
そんな
「ちぐはぐな困りごと」に出会ったとき、
支援の焦点がぼやけてしまうこともありました。
でも本当は、
「どの診断が正しいか」ではなく、
「今この子が、どこでつまずいているのか」をひとつずつ見ていくこと
がいちばんの土台になります。
行動や学習のズレの中には、
「わかってほしかった」気持ちが隠れていた。
そう気づけたとき、
関わり方が変わっていく感覚が生まれていきます。
「ADHDかLDか、やっぱり“育て方”の問題なのかな…」
- 「集中できない」
- 「文字が読みにくい」
──でもそれを、努力不足や性格のせいとは思えなかった。
家庭学習の中で何度もつまずく姿を見て、
「このまま見守っていて大丈夫?」と焦りだけが積み重なっていった。
LDかADHDか分からず責めていた私が、『この子らしさ』を見つけた──3週間集中再安心サポートは、
「この子を理解するために、今できることが知りたい」と願うお母さんのための
家庭から始める心理サポートです。
こんな方におすすめです
- 「ADHD」と決めつけられることに違和感がある
- LDの可能性に初めて触れて、戸惑っている
- 家庭でできる関わり方のヒントがほしい
- この子の「できなさ」に寄り添いたいと思っている
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 1月16日(金)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと1名様限定』
※銀行振込限定・先着順
そして──
少しずつ、「この子らしさ」を言葉にできるようになったあなたへ。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
「母としての経験」を足がかりに、
「自分らしく生きる感覚」を取り戻す3週間。
誰かに合わせるのではなく、
自分の内側から湧きあがる声に、ゆっくり耳を澄ませていきましょう。
- 子育てに少しずつ自信が持てるようになってきた
- でも、自分自身の時間がどこか止まったまま
- 「母」を越えて、「わたし」に還るきっかけがほしい
このプログラムでは、
「母の役割」を終えていく私たちが、
「人生の次のページ」を描き直す時間を過ごします。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
DCD(発達性協調運動障害)との違いとは?|「不器用さ」と「学習の困難」の切り分け

- 「どうしても、うまく書けない」
- 「動きがぎこちないって、ただの性格なのかな…」
そんな迷いを抱えながら、
- 「学習障害(LD)」
- 「DCD(発達性協調運動障害)」
の違いを調べてきたと思います。
どちらも「できなさ」につながるものですが、
その背景はまったく異なります。
ここでは、
動きの不器用さと学習の困難を、しっかり分けて見つめていきます。
DCDは「運動のぎこちなさ」「手先の不器用さ」が目立つ
- ボタンをとめるのが苦手だった。
- 鉛筆を持つと、力が入りすぎたり弱すぎたりして、うまくコントロールできない。
- 縄跳びのタイミングがずっと合わずに、笑われたこともあった。
がんばっていたのに、
- 「ふざけてる」
- 「もっと丁寧にしなさい」
と言われ続けてきた。
そんな悔しさや、言葉にできない苦しさがココロに残っていた。
DCD(発達性協調運動障害)は、
体の動きをスムーズに組み立てることに苦手さがある発達特性です。
- 運動全体のぎこちなさ
- 手先の動作にズレが出る
という特徴があります。
ポイント
ただの「不器用」と
片づけられてしまうことが多いからこそ、
見過ごされてきた子どもも、
たくさんいたという背景があります。
学習障害との違いは「読み書き」の習得パターンにある
- 字を書くのが遅い。
- 何度も練習しているのに、なかなか形が整わない。
その様子だけを見て、
「学習障害(LD)では?」と疑われることもあった。
でも実際には、
「なぜ書けないのか」がまったく違っていた。
学習障害(LD)の場合は、
- 「文字を読む」
- 「音をつかむ」
- 「順序を処理する」
といった、
言葉の情報そのものを扱うことに難しさがあります。
一方で
DCDの子どもは、
情報は理解できていても、
手をうまく動かして書き表すことに苦労するという特徴が見られます。
同じ「書けない」でも、
原因が異なれば、支援の方法も変わる。
そうやって、
困りごとの「中身」を見つめ直す視点が必要なんですよね。
学習障害(LD)とDCDが重なるとどうなる?家庭で見えるサイン
- ノートを取るのがとにかく遅い。
- ひらがなが定着せず、何度練習しても形がバラバラ。
- 書く場面になると、机の前でフリーズしてしまう──
そうした姿を前に、
どう声をかければいいのか分からず、
戸惑いながら毎日を乗り越えてきた方も多いですよね。
実際、
学習障害(LD)とDCDは
同時にあらわれることもあります。
たとえば、
- 読むのが苦手で、
- さらに手先も不器用だった場合、
「どこから手をつければいいのか」が見えづらくなることがある。
本人としては、
- 「わからない」
- 「できない」
- 「うまくいかない」
が全部重なっている状態。
でもまわりには、その理由が伝わらない。
そのギャップの中で、苦しさばかりが大きくなっていった。
だからこそ、
- 「怠けてる」
- 「ふざけてる」
と決めつける前に、
「この子の動きと学びのどこにズレがあるか」を、丁寧に見ていく姿勢が必要です。
“不器用さ”の奥にある、本当の困りごとに気づいたときに
「DCDかも?」と聞いたとき、少しだけホッとした。
でもそれだけで、すべてが説明できる気がしなかった──。
- 書く
- 読む
- 計算する…
そのどれもに時間がかかる姿を見て、
「やっぱりこの子は『学習』にも困っている」と感じたあなたへ。
「グレー」のまま悩む時間を、家庭から変えていくサポートがあります。
こんな時どうする?|違いがわからず不安なときの向き合い方
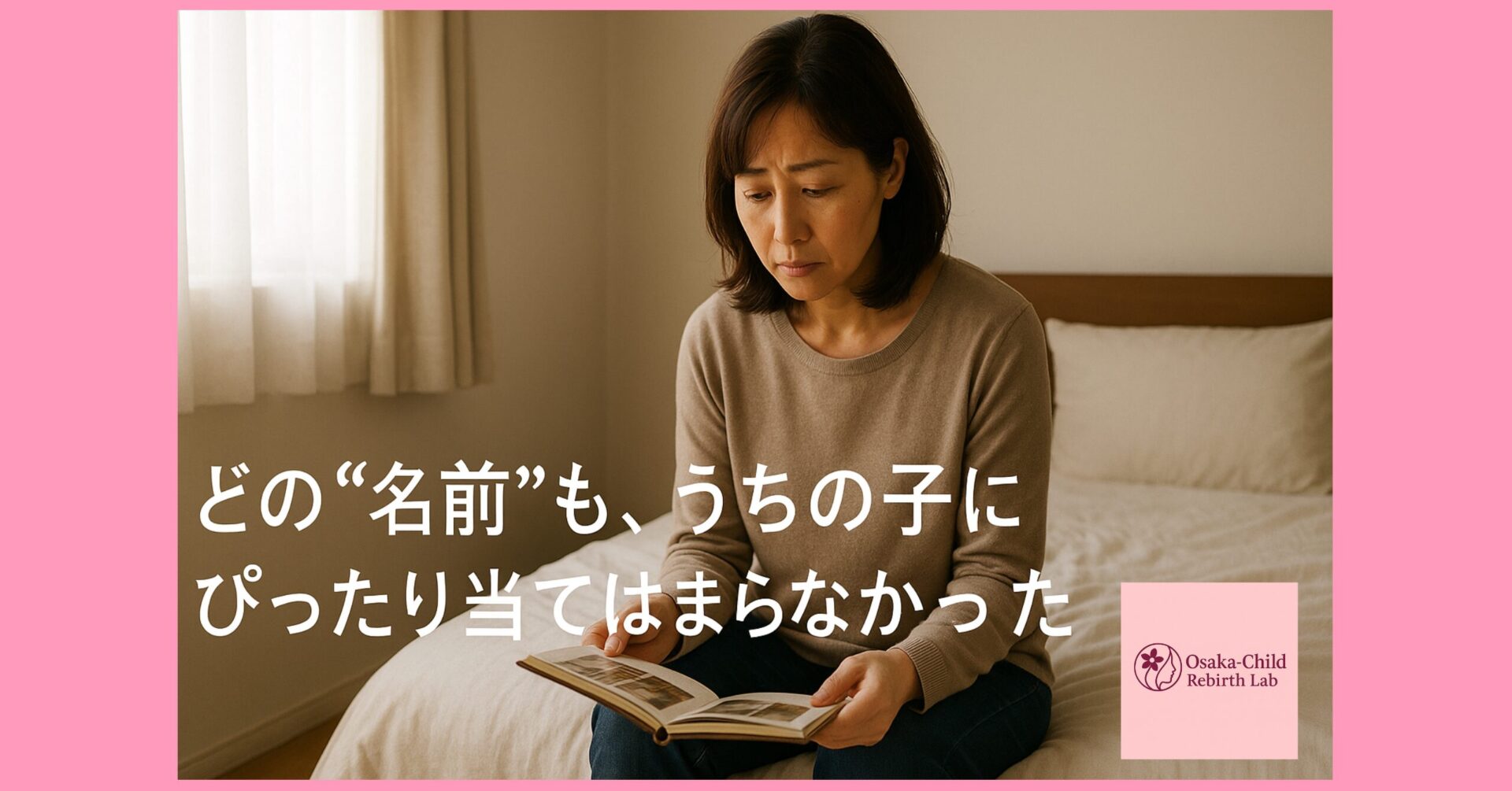
「ASD?ADHD?それとも学習障害(LD)?」
そうやって、
毎日のように検索しては迷っていた時期があった。
どの説明にも当てはまるようで、どれもしっくりこない。
そのまま時間だけが過ぎていくような感覚がありました。
ここでは、
「何に当てはまるか」よりも大切な、
「見方の切り替え」について整理していきます。
「この子はどのタイプ?」と迷った時に大切なこと
「タイプがわからないと、どうサポートすればいいのかもわからない」
そう感じて、
診断名や分類を必死に調べてきた日々があった。
でも調べるほどに、
「全部が重なって見える」こともあったはずです。
- ADHD
- ASD
- 学習障害(LD)
- DCD──
どれも名前は違うけれど、
「困っていることがある」という点では共通しています。
だからこそ大切なのは、
「名前を当てはめること」よりも、
「どこで困っているか」を具体的に見つけること。
たとえば、「指示が通らない」場面があるなら、
- 聞く前に気が散っているのか
- 言葉の意味がわかりにくいのか
- そもそも集中状態に入れていないのか
──そうやって、目の前の困りごとの「根っこ」を探していくことが、
支援の第一歩になるんですよね。
「グレーゾーン」という見えにくさとどう向き合うか
- 診断を受けても、「グレーゾーン」と言われて終わってしまった。
- 支援は必要ないと言われたのに、家ではずっと育てにくさを感じていた。
そうやって、
「宙ぶらりんの状態」に置かれてきた方もたくさんいます。
でも実際には、
「診断がないから大丈夫」というわけじゃないんですよね。
診断名は、
あくまで「医療の枠」で見るためのひとつの基準にすぎない。
家庭や学校で見えている困りごとは、
それとは別の視点で見つめる必要があります。
グレーゾーンとは、
「はっきりとは言えないけど、確かに困っている」状態。
そのモヤモヤを無視せず、
「親として感じてきた違和感」にこそ価値があると捉えることが大切です。
専門機関や支援級より前にできることがある
- 「病院に行くべきなのかな」
- 「支援級をすすめられたけど、まだ決断できない」
──そんなふうに立ち止まっていた時間も、ちゃんと意味があるはずです。
もちろん、専門機関の支援が必要なケースもあります。
でもその前に、
家庭の中で「見方」を変えるだけで、親子の関係がやわらぐこともあるんです。
たとえば、
「忘れ物が多い」ことを
「怠けてる」と決めつけるのではなく、
- 「どの工程でつまずいているのか」
- 「サポートの余白をどこに置けるか」
と考えてみる。
そうやって一つずつ、
「親のまなざし」を整えていくことが、いちばん身近な支援になります。
診断名よりも先に、
「わが子をどう見るか」という土台を作っていく──
その小さな視点の転換が、
安心できる日常の始まりにつながっていきます。
“わからないまま”動けなくなっていた私へ
「結局どうしたらいいの?」
──誰にも聞けないまま、考えすぎて疲れていませんか?
この子にとっての最善を願うからこそ、何も決められなくなっていた。
そんなあなたに届けたいのが、
「LDかADHDか分からず責めていた私が、『この子らしさ』を見つけた──3週間集中再安心サポート」
「わからないからこそ、家庭から始める」という選択肢もあるんです。
LDかADHDか分からず責めていた私が、『この子らしさ』を見つけた──3週間集中再安心サポート

「学習障害(LD)かADHDか…どちらにも当てはまる気がして、どちらでもないような気もして」
そんなふうに、
答えのない迷路をずっと歩き続けていた。
でも本当に探していたのは、
「この子が何に困っているのか」
そして「自分はどう関わればいいのか」
──そんな視点の「持ち直し」だったと気づかされた。
このサポートでは、
診断名やラベルに縛られず、
わが子との関係を見つめ直す「親の内面からの支援」を3週間で丁寧に進めていきます。
診断に縛られず、わが子の「困りごと」を見つけるサポート
「名前がつかないと支援が受けられない」
そう思い込んで、ずっと焦っていた。
でも、
名前よりも前に、
「目の前のわが子」をどう見るかという視点が
抜け落ちていたことに気づかされた。
このプログラムではまず、診断名や分類よりも、
- 「どこで止まっているのか」
- 「どの場面でつまずいているのか」
──そうやって、「困りごとの正体」を丁寧に見つけていくプロセスから始まります。
叱ってしまった背景にも、
自分なりに理由があった。
わかってあげられなかったのではなく、
「どう見ればいいのかわからなかっただけ」だった自分に、
やさしく気づいていく時間です。
「叱るしかなかった日々」が変わっていく3週間のプロセス
- 「わかってほしいのに伝わらない」
- 「また同じことで怒ってしまった」
──そんな毎日が、少しずつ変わっていった。
3週間の中では、
まず
- 〈Week1〉で「わが子の困りごと」の正体に触れながら、
- 〈Week2〉では「どう関わるか」ではなく、「どんな目で見ていたか」を見つめ直す。
そして - 〈Week3〉では、その子の「らしさ」を取り戻す関わり方に切り替えていきます。
「できるようにさせる」でもなく、
「親として正しく導く」でもない。
「この子といられることそのもの」が、少しずつ安心に変わっていく3週間です。
「わかってあげられる私」に出会い直すための時間
誰よりも、この子のことを考えてきた。
だからこそ、
- 「間違えたくない」
- 「正しく理解したい」
と強く思いすぎていた。
でも本当に必要だったのは、
「わかってあげられる私」に、
もう一度出会い直すことだったんですよね。
このサポートでは、
- 診断がなくても、見えない困りごとを受け止められる視点
- 親自身の「ちゃんと育てなきゃ」というプレッシャーの手放し方
- 「責めるしかなかった私」を許す感覚
──そういった「内側のほぐし」を通して、
子どもとの関係をやり直す準備を整えていきます。
名前じゃなく、
枠でもなく、
この子と生きていく私自身のまなざし。
そこから変わっていく未来が、そこに見えてきます。
「わかってあげられる私」に出会い直すための時間
学習障害(LD)のことは、
ある程度わかってきた。
でも、どうしても引っかかるところがあって──。
- 「急に話しかけても反応が薄い」
- 「じっと座ってられない」
- 「注意しても、また同じことを繰り返す」
これって、
ADHDの特性もあるのかもしれない。
そんなふうに感じ始めたのに、
誰にもはっきり言えずにいた。
「育てにくさ」だけが残って、
見通しが持てないまま、時間だけが過ぎていった。
STEP①|見えている「できなさ」の奥にあるもの
- 読み間違い
- 書き飛ばし
- 忘れもの──
「また?」と思いながらも、どこかで違和感が拭えなかった。
ただの学習障害(LD)だけじゃない気がして、
でも、何がどう重なっているのか説明できなかった。
このサポートでは、
学習障害(LD)とADHDの両方に共通する
「見えにくい困りごと」を、一緒に整理していく。
専門的な名前や診断じゃなく、
「今、この子は何に困ってるの?」という問いから始めていく。
STEP②|「責めてばかりだった日々」をやさしくほどく
- 「また忘れてる」
- 「ちゃんと聞いてって言ったよね?」
そのたびに、
声が大きくなってしまって。
自分でも後悔してるのに、気づけばまた怒ってしまっていた。
ほんとうは、わかってあげたかっただけ。
どうしたらいいかわからないまま、責めるしかなかっただけ。
STEP③|「この子らしさ」に戻っていける関わり方へ
たくさん抱えて、
たくさん頑張って、
それでも「うまくいかない」って顔をしてた。
この子なりに必死だった。
その姿に、やっと気づけた気がした。
学習障害(LD)の「できなさ」も、
ADHDの「落ち着かなさ」も、
全部ひっくるめて「この子らしさ」だったとしたら──
そのまなざしで、もう一度この子と向き合っていける気がした。
「この子は、何が苦手なの?」
そんな問いから、
「この子と、どう生きていく?」というあたたかい選択へ。
『LDかADHDか分からず責めていた私が、「この子らしさ」を見つけた──3週間集中再安心サポート』は、
その「見えにくかった輪郭」に、やさしく光を当てていく時間です。
「LD?ADHD?わからない」まま責めてきたあなたへ
「この子はLD?ADHD?ASD?もう何が正解なのかわからない」
そうやって、自分を責めながらも、毎日向き合ってきたあなたへ。
その迷いは、“理解しようとしてきた証”です。
診断がつく・つかないに関係なく、あなたの中にあった「この子をわかってあげたい」という想いは、ちゃんと届いていきます。
このサポートでは、学習障害(LD)とADHDの“重なり”を前提に、
今、この子がどこで困っていて、どんな関わりが必要なのかを、一緒に見つけていきます。
「また怒ってしまった…」
そんな夜をくり返さないために。
母としての安心を、ここから整えていきませんか?
まとめ|「この子は『できない子』じゃない」と信じたいあなたへ
うまく言えないけど、
ずっと違和感があった。
何かが引っかかっていて、
それを「母親の勘」で感じ続けてきた気がする。
だけど、
言葉にできなくて、
周りには伝えられなくて──
そのまま、
答えの出ない迷いだけが、
自分の中に残っていた。
- ADHDか
- 学習障害(LD)か
どちらもあるのか。
診断名に振り回されながら、
「この子を理解したいのに、見えなくなる」
そんなもどかしさと向き合ってきた方も多いです。
- 「私の育て方が間違ってた」
- 「ちゃんと教えてこなかったせい」
そうやって、何度も自分を責めてきたんですよね。
でも、本当はずっと、この子を理解したくてたまらなかった。
誰よりも真剣に向き合ってきたからこそ、迷い続けてきた。
それ自体が、親としてのあたたかさだったんです。
ここで、この記事の要点を振り返ってみましょう。
この記事で分かったこと
- 学習障害(LD)は「読み・書き・計算」のつまずきが中心
- ADHDは「注意・多動・衝動」のコントロールのしづらさが特徴
- 両者は重なって見えることがあり、混乱しやすい構造がある
- ASDとの違いは「対人関係の特性」や「空気の読みづらさ」
- DCD(発達性協調運動障害)は「運動のぎこちなさ」が主軸
- 診断よりも、「今この子が困っていること」から向き合う視点が大切
「どうしてうまくいかないんだろう」
その問いの奥には、
「この子をわかってあげたい」という願いがずっとあった。
自分を責めるのではなく、
その願いを「まなざし」に変えていくことが、
これからの土台になります。
どうして毎日、こんなに怒っていたのか──
この記事を読みながら、
「ああ、わが子は『できない』んじゃなくて、『むずかしかった』んだ」と気づいた方もいます。
この関わり方では、
母親である自分が苦しくなっていた。
「LDかADHDか分からず責めていた私が、『この子らしさ』を見つけた──3週間集中再安心サポート」
は、
診断やラベルにとらわれず、
わが子の「見えづらい困りごと」に
一緒に気づいていく時間です。
怒りの奥にあった
「わかってあげたかったのに」という想いに触れながら、
特性に合った関わり方を少しずつ整えていきます。
迷いながらでも大丈夫。
ひとりで抱えなくていいんです。
正しい答えを探すのではなく、
「この子とどう向き合えば、安心して過ごせるか」を一緒に考えていく。
そんな小さな一歩から、わが家の空気がやわらいでいきます。ここから、ゆっくり始めていきましょう。
「“支援を考えましょう”と言われたあの日から、ずっと迷ってばかりだった」
- ADHD
- LD
- ASD
- グレーゾーン──
診断名や制度の言葉がどんどん先に進んでいく中で、
母親としての私は、いつまでも立ち止まったままだった。
「この子は障害なの?それとも個性なの?」
いくら考えても、誰も答えをくれなかった。
でもその問いをくり返してきたのは、
ちゃんと理解したいという「母の願い」があったからなんですよね。
LDかADHDか分からず責めていた私が、『この子らしさ』を見つけた──3週間集中再安心サポートは、
「診断名」ではなく、「この子との向き合い方」を整えていく
お母さんのための家庭心理サポートです。
こんな方におすすめです
- 学習障害やADHDの違いに振り回されている
- この子にとってベストな支援が見えない
- 「結局どう動けばいいの?」と立ち止まっている
- 家庭の中から、納得できる関わり方を見つけたい
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 1月16日(金)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと1名様限定』
※銀行振込限定・先着順
ネットバンキングのご利用で、今すぐ開始することが可能です。
そして──
「この子らしさを大切にしたい」と思えるようになった今、
「母の役割」だけじゃない「自分の人生」も見つめ直してみたくなったあなたへ。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
これまで積み重ねてきた葛藤も、試行錯誤も、
「私としてのこれから」につなげていくための3週間。
- 子育ての迷いが少しだけ軽くなってきた
- でも、自分のこととなるとまだ曖昧なまま
- 「私自身の人生」を歩きなおす準備がしたい
このプログラムでは、
「母としての時間」のその先にある、
「本当のわたし」の歩みを整えていきます。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
無料LINE診断|今のあなたに必要なサポートは?
「何から始めればいいかわからない…」そんなあなたへ。
LINEで「数字」を入力するだけで、今のあなたに合ったサポート商品を診断できます。
今すぐLINEに【 4 】と入力してください。
「LDかADHDか分からず責めていた私が、『この子らしさ』を見つけた──3週間集中再安心サポート」
の詳細と、
あなたに「ぴったりの理由」が届きます。
すでに診断済みの方も、そのまま詳細ページへ進めます。
あなたの心と体に合ったサポートを、今すぐ確認してみてください。








