
あなたは
ADHDのわが子を前に、
朝の布団のそばで何度も息をつめてきた。
- 頻繁に起こる忘れ物
- すぐにイスから立ち上がる集中の切れやすさ
- 不注意による日常生活でのミス
に振り回され、
「何度言っても伝わらない」と
声が強くなる瞬間があった。
- 怒った直後に胸が痛くなり、夜は自己嫌悪で目が冴える。
- 学校からの電話に肩が跳ね、家の空気が重くなる。
夫は「そのうち大丈夫」と受け流し、
下の子は「ママちゃんとしてよ」と言わんばかりの感情で
表情まで曇っていく。
ADHDの特性が関係していると知っていても、
日常の渦の中で責める言葉が先に出てしまうもの。
ひとりで抱え、泣く場所もないまま、
ここまで踏ん張ってきたんですよね。
この記事は、
ADHDの子どもの不登校で限界を感じてきた母親に向けた
ADHDの子どもへの不登校サポートの実践ガイドです。
- 家庭を安全基地に整える
- 無理な登校より安心を優先する
- 母親のココロを落ち着かせる
- 学校と「対立ではなく対話」
を育てるという順で道筋を示し、
最後に『3週間集中再安心サポート』をご紹介します。
この記事で得られる5つのこと
- ADHDの不登校を「母親の失敗」にしない視点
- ADHDの子に合う「登校以外も含む」安心のつくり方
- ADHDの悪循環(怒る→自己嫌悪)を断つ関わり直し
- ADHDの子と学校に「対立ではなく対話」を育てるコツ
- ADHDと暮らす母親自身のココロを整え、家庭を安定させる手順
- 「できない姿ばかり見えて、責める言葉が増えていた」
- 「叱らなきゃと焦って、抱きしめる余裕を失っていた」。
そんな痛みを、まず受け止めたい。
ここまで本当によくがんばってきましたよね。
こうして整理してみると、
「じゃあ私はこれからどう動けばいいの?」という気持ちが湧いてきますよね。
ADHDの子どもの不登校に向き合う日々は、
母親のココロに深い傷を残します。
- 朝になると布団から出られないわが子を前に、どうしても声を荒げてしまう。
- 叱った直後に「また責めてしまった」と自己嫌悪で胸が苦しくなる。
学校からの電話に体が固まり、
夫に「大丈夫だろ」と軽く言われて孤独が増す。
下の子にまで気を配れず、
「家庭ごと壊れてしまう」と涙が止まらない夜もありましたよね。
ここまで必死にやってきたからこそ、
「私はどう動けばいいのか」と迷い続けてきました。
その答えの入り口として紹介したいのが、このサポートです。
「ADHDの子どもの不登校サポートに悩み、孤独と不安に押しつぶされていた母が、安心を取り戻し家庭を整えていく──3週間集中再安心サポート」です。
このサポートは、
母親のココロを整えることを出発点にしています。
ADHDの子どもの不登校を
「解決する方法」を押しつけるのではなく、
母親が安心を取り戻すことで、
家庭の空気そのものを変えていくことを目的にしています。
流れは段階的です。
1週目:母親の心を受け止める
「私のせいで不登校になった」と責め続けてきた罪悪感を言葉にし、孤独を和らげます。
泣きたくても泣けなかったココロを解きほぐし、まず母親自身が安心できる時間をつくります。
2週目:安心の土台を整える
ココロが落ち着きを取り戻すと、家庭の空気が少しずつ変わります。
急かす言葉を減らし、安心の声かけに切り替える。
無理に登校を迫らず、「ここは大丈夫」という空気を家庭に広げていく。母親の変化が、そのまま家庭環境を支える力になっていきます。
3週目:子どもと関わりを整える
母親のココロと家庭が整った段階で、初めて子どもに向き合います。
ここでは「できないことを責める」のではなく、「小さく一緒にやってみる」関わり方を始めます。
登校だけにこだわらず、家庭学習や先生とのやり取りなど「外とのつながり」を子どものリズムに合わせて築いていきます。
この3週間の流れを通して、母親の中で少しずつ変化が生まれます。
- 1週目には孤独に押しつぶされそうだったココロが軽くなり、
- 2週目には「無理に登校させなくてもいい」という安心が家庭に広がります。
- そして3週目には、「責めなくても支えられる」という新しい関わり方が自然にできるようになっている。
母親が変われば、子どもも変わります。
安心して過ごせる時間が増え、
叱られる日々から
受け止められる日々に変わります。
- 表情がやわらぎ、
- 生活リズムが整い、
- 登校へのハードルも下がっていく。
ADHDの子どもが
自分のペースで外の世界に戻る力を取り戻す流れが、
家庭の安心から始まります。
最終的に母親は、
「あのとき無理に登校させずに家庭を守ったことが正解だった」と胸を張れるようになります。
子どもは、
不登校の経験を「失敗」ではなく
「育ちのプロセス」として受け止められるようになります。
家庭全体が落ち着きを取り戻し、
夫も「君がいてよかった」と支え合える空気が生まれる。
正解探しに追われて自分を責めてきた日々から抜け出し、
「ここから整えていけばいい」と未来を見つめられるようになる。
その一歩を、この3週間で一緒に築いていきます。
ここまでで、
「母親のココロを整えることがスタートなんだ」と少し見えてきましたよね。
でも同時に、
「じゃあ具体的にはどうすればいいの?」という不安も残っていますよね。
だからこそ、
ここからは
ADHDの子どもの不登校に向き合うときに押さえておきたい視点を
一緒に整理していきます。
ひとつずつ見ていくことで、
あなたの中で
「安心して支えられる形」が、
もっとはっきりしていきます。
監修者
株式会社Osaka-Child所属 小児神経科医
- 名前: 三浦あすか
- 出身地: 兵庫県西宮市
- 最終学歴: 神戸大学医学部 小児科専攻
- 専門分野: 小児神経、DCD(協調運動障害)、発達性ディスプラクシア、HSP気質の子ども支援
- 職歴: 兵庫県立こども病院 小児神経センター勤務(11年)
専門分野について一言: 「できないことの奥にある『がんばっているサイン』を、もっと社会全体で受けとめていけたらと思っています。」
監修者
株式会社Osaka-Child所属 臨床心理専攻大学教授
- 名前: 森本哲夫
- 出身地: 奈良県
- 最終学歴: 米国ハーバード大学心理学部 博士課程修了
- 専門分野: 臨床心理学、発達心理学
- 職歴: ハーバード大学研究員(5年)、大阪大学人間科学部教授
専門分野について一言: 「心の成長とは、自己理解の旅でもあります。その旅のお手伝いができれば幸いです。」
「ADHDの不登校サポート」で一人で抱え込んでいるあなたへ
ADHDの不登校が続き、朝になると泣き叫ぶ子どもを前に
「どう支えればいいのか分からない」と感じていませんか?
学校からは「なんとか登校を」、
夫からは「そのうち行くようになる」。
ADHDの現実と周囲の期待の狭間で、母親だけが板挟みになっている。
ADHDの子どもにとって「不登校はわがまま」ではありません。
- ADHDの特性(不注意・衝動性・環境刺激)
- ココロの負担
が重なって、
「行きたくても行けない状態」が生まれているのです。
無理に登校させるほど、ADHDの不安は強まり、家庭の安心も揺らぎます。
まず整えるべきは、ADHDの子が
- 「安心して休める家」
- 「安心して戻れる関わり直し」。
「ADHDの子どもの不登校サポートに悩み、孤独と不安に押しつぶされていた母が、安心を取り戻し家庭を整えていく──3週間集中再安心サポート」は、
ADHDの不登校に向き合う母親が、無理に登校させる不安から解放され、
「家庭から安心を整える力」を取り戻すサポートです。
こんな方におすすめです
- ADHDと不登校が重なり、毎朝が親子でつらい戦いになっている
- 「学校に行かせなきゃ」と追い詰められ、安心を失っている
- 夫や家族に理解されず、母親だけが孤立している
- 下の子への影響や、将来の二次障害に強い不安を感じている
- 「責める母」から「安心して支えられる母」に変わりたい
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 2月16日(月)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと3名様限定』
※銀行振込限定・先着順
▶ ADHDの不登校を家庭から整え、「安心できる母」へ変わる3週間へ
そして──
不登校サポートを整えたあと、「母としての安心」だけでなく、「私自身のこれから」にも目を向けたい方へ。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
ADHDのある子を支えてきた経験を土台に、
母としても一人の女性としても「これからの生き方」を再設計する3週間です。
家族を落ち着かせながら、
「私らしい人生の軸」を取り戻していきます。
- ADHD子育てと不登校対応を通して価値観が揺らいでいる
- 家庭の安心を整えたあと、自分の人生にもしっかり取り組みたい
- これからの選択に自信を持ちたい
このプログラムでは、
「ADHDのある子の母」という枠を超えて、
「私自身のために未来を選べる私」へ変わります。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
「ちゃんとしてるのに、苦しい」
「頑張ってるのに、うまくいかない」
——そんな違和感を抱えたまま、ずっと我慢していませんか?
LINEで3分セルフ診断ができます。
あなたの“今の感覚”の正体が、見えてきます。
ADHDの子どもに不登校が重なったとき、母親が直面する現実

ADHDと診断された子どもを育てるだけでも、
毎日が挑戦の連続ですよね。
- 忘れ物が多い、
- 授業に集中できない、
- 衝動的に動いてしまう…。
そんな困りごとに向き合い続けてきただけでも、
ココロは限界に近づいていました。
そこに「学校に行きたくない」と不登校が重なった瞬間、
胸がつぶれるような感覚に襲われました。
- 「どうしたらいいの?」
- 「私のせい?」
──頭の中は答えの出ない問いで埋め尽くされ、
あなたは眠れない夜を過ごしてきました。
ADHDと不登校が重なったとき、
母親が直面する現実は想像以上に重いものです。
だからこそ、
このキャプションではそのつらさを整理しながら一緒に見ていきましょう。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「ADHDって何?うちの子に当てはまるのかな…?」
そんな不安を整理したい方へ。
ADHDの基本から、母親が「責める毎日」を手放すヒントをまとめた専門家監修記事をご用意しました。
-

-
参考ADHDとは?子育てに限界を感じたあなたへ|「責める毎日」を手放すヒント【児童精神科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 朝から何度も叱って、 疲れ果てた夜。 寝顔を見るたびに、 「また怒りすぎた」と後悔ば ...
続きを見る
「ADHDだから不登校?」と感じた母親がつまずく最初の壁
「ADHDだから不登校になったの?」──
そう考えてしまった瞬間が、
あなたのココロの最初の壁になりました。
ADHDの子どもは
忘れ物や課題の提出が苦手で、
先生や友達とのやり取りもうまくいかないことが多いですよね。
その積み重ねが
「学校がつらい」という気持ちにつながっていきます。
でも、
周りからは
- 「ただの甘え」
- 「無理にでも登校させればいい」
と言われる。
あなたの中では、
- ADHDの特性
- 不登校
が確かに結びついていると感じているのに、
理解されない。
その食い違いが、あなたをますます孤独に追い込んできました。
ADHDと不登校の関係を理解してもらえない苦しみ。
その中で、
「子どもをどう支えればいいのか」と足を止めてしまったのです。
忘れ物や勉強のつまずきが不登校につながる流れ
ADHDの子どもは
- 「忘れ物が多い」
- 「宿題をやっていない」
- 「授業についていけない」
といったつまずきが日常のように重なりますよね。
そのたびに注意を受け、
劣等感が深まっていく。
小さな失敗の積み重ねが、
学校生活全体を苦しいものに変えてしまいます。
- 「また忘れたの?」
- 「勉強しなさい」
──そんな声をかけながら、
自分でも本当は責めたいわけじゃないとわかっていました。
でも、
ADHDの特性によるできないことを止められない子どもは、
自信をなくし、
やがて「学校に行きたくない」と口にし始める。
気づけば毎朝の声かけが苦痛になり、
「今日はどうなるんだろう」と
不安でいっぱいになっていた。
ADHDの小さな「できないこと・困りごと」が、
不登校へとつながっていく現実を、
あなたは誰よりも身近で感じてきたのです。
思春期に入り、不登校が深まりやすいADHDの背景
小学校高学年から中学生にかけての思春期は、
ADHDの子どもにとって
特に不登校が深まりやすい時期です。
まわりの子と比べて
「自分はできない」と感じることが増え、
自己否定が強まっていきますよね。
感情をコントロールしにくい
ADHDの特性が加わると、
母親への反発や沈黙という形で
SOSを出してくることもある。
- 「なんで行けないの?」
- 「どうしてわかってくれないの?」
と、子どもとあなたの間で衝突が増えてしまう。
そうやって関係がこじれるほど、
不登校は長引いてしまいます。
「支えたいのに、支えられない」
──その葛藤に押しつぶされそうになりながらも、
必死で毎日を回してきたのです。
ADHDと不登校に向き合い続けた
あなたのココロの疲れは、
誰にだって見過ごせないほど大きなものです。
学校との板挟みで悩む母親へ|行きしぶりから「学校に行けない」まで

ADHDの診断を受けた子どもが
不登校になりはじめたとき、
何よりつらいのは
「学校と家庭のあいだに挟まれる自分の気持ち」です。
先生からは
「登校を促してください」と言われる。
でも朝になると、
ADHDの特性を抱えたわが子は
布団の中から動けない。
その姿を見てしまったら、
無理に連れていくなんてできないですよね。
- 「学校に行かせなきゃ」
- 「この子を守りたい」
のあいだで揺れて、
どちらを選んでも自分を責めてしまう。
あなたが抱えてきたその板挟みには、
ADHDの子どもの特性と、
不登校という現実が深く絡んでいます。
このキャプションから一緒に整理していきましょう。
朝の「行きしぶり」が続いたときに見直したいこと
ADHDの子どもにとって、
朝の準備は大きなハードルになりますよね。
- ランドセルの中にはまだ宿題が入っていない、
- 洋服を着替えるだけで時間がかかる…。
そのたびに
- 「早くして」
- 「また忘れてる」
と声を荒げてしまったこともありますよね。
けれど、
この「行きしぶり」には
ADHDの特性がはっきりと関係しています。
- 注意を切り替えるのが苦手
- 見通しを立てにくい
- 小さな失敗で自己肯定感が下がりやすい
──そんな子どもが自分への認識が、毎朝の足を重くしているんです。
「今日もダメだった」と落ち込む前に、
これはあなたの育て方のせいじゃない、
と気づいてほしい。
- ADHDの特性
- 不登校のサイン
が重なったサインとして受け止めることが、
次の関わり方の第一歩になります。
「学校に行けない」子どもに無理強いしないための視点
行きしぶりが続くと、
「学校に行けない」という言葉に
変わっていきます。
ADHDの子どもは忘れ物や失敗経験が多い分、
- 「また怒られる」
- 「またできない」
と感じやすい。
その積み重ねがココロを疲れさせ、
登校するために体を動かせなくします。
でも
- 学校からは「登校を促してください」と言われ、
- 夫からは「甘やかしているだけだ」と突き放される。
あなたはその真ん中で、
どうすればいいのか迷い続けてきました。
大切なのは
「行けない子を無理に行かせること」ではなく、
「行けない子を安心させること」。
ADHDの子どもにとって、
家庭が安心の拠点になれば、
外の世界に向かう力を少しずつ回復していけます。
焦らず、家庭で安心を積み重ねることが、
不登校サポートの本当の意味なんですよ。
思春期の不登校に寄り添うADHD 不登校 サポートの考え方
小学校高学年から中学生にかけて、
ADHDの子どもは
思春期特有の不安定さが重なり、
不登校が深まりやすくなります。
周囲と比べて「自分はできない」と感じやすく、
気持ちが爆発したり、
逆に言葉を閉ざしたりする姿に、
あなたもとまどってきました。
そんなとき「行きなさい」と押しても、
子どもはますますココロを閉ざしてしまう。
ADHDと不登校に向き合うとき必要なのは、
学校に戻すことを急ぐのではなく、
「家庭を安心できる場所にしていく」視点です。
あなたが「この子はこの子でいい」と
思えるようになったとき、
子どもの表情も変わり始めます。
ADHDの子どもにとって、
母親の安心はそのままサポートになる。
ここに気づくことが、
次のステップへと進むための大切な土台になっていきます。
「学校の板挟み」で疲れ切ったココロを、家庭から立て直す3週間
ADHDの行きしぶりが続くと、
- 学校からは「登校を」
- 夫からは「そのうち行く」。
ADHDの現実と期待のあいだで、母親だけが消耗しやすい。
無理に登校させる前に
——ADHDの子が「安心して休める家」を整えることが、回復の最短ルートです。
ADHDの不登校は「怠け」ではありません。
ADHDの特性(不注意・衝動性・感覚の負担)と不安が重なり、「行きたくても行けない状態」が起きます。
母親のココロが落ち着くほど、家庭の空気は安定し、ADHDの子は少しずつ力を取り戻します。
「ADHDの子どもの不登校サポートに悩み、孤独と不安に押しつぶされていた母が、安心を取り戻し家庭を整えていく──3週間集中再安心サポート」
- 1週目:ADHDと不登校に揺れる「私の不安・罪悪感・孤独」を受け止める
- 2週目:ADHDの前提に立ち、家庭を「安全基地」へ整える
- 3週目:無理な登校ではなく、「安心して戻れる関わり方」を始める
家庭でできるADHDの子どもの不登校サポート|母親が守る「安心の居場所」

ADHDの子どもが不登校になると、
学校での失敗やつまずきが
家の中にも影を落としますよね。
「勉強も遅れているのに、どうしたらいいの?」
──そんな焦りでココロが押しつぶされそうになる日もありました。
でも、
学校に行けない時間を
「空白」にしない方法があります。
それは、
家庭を子どもにとって安心できる居場所にすること。
このキャプションでは、
ADHDと不登校に揺れるあなたの家庭で、
すぐに取り入れられるサポートについて
一緒に整理していきましょう。
叱る声かけから「安心できる言葉」への切り替え方
ADHDの子どもは、
忘れ物や時間管理が苦手で、
毎日同じようなことでつまずきますよね。
- 「早くしなさい」
- 「また忘れたの?」
──そう言いたくなる気持ちは自然です。
でも、
そのたびに子どもの顔がこわばり、
不登校の気持ちが強くなっていった経験がある。
ポイント
ADHDの特性は
「努力不足」ではなく
「脳の働き方の違い」によるもの。
その理解を持って声をかけ直すと関係は変わっていきます。
- 「一緒に準備してみよう」
- 「ここまでできたね」
といった
安心の言葉に切り替えるだけで、
子どもの表情に少し光が戻ってきます。
叱る声かけをやめることは、
甘やかしではなくサポート。
ADHDの不登校を乗り越えるために、
母親の声は「安心のスイッチ」になるんです。
家庭を「安全基地」にすると不登校の子どもは落ち着きを取り戻す
学校で「できないこと」が目立ってしまう
ADHDの子どもにとって、
家庭が安心できない場所になってしまったら、
どこにも居場所がなくなってしまいますよね。
だからこそ、
家は「安全基地」であることが大切です。
- 安心して泣ける、
- 安心して休める、
- 安心して笑える
──その積み重ねが、
不登校に揺れるADHDの子どもにとって
ココロの回復を支える力になります。
ポイント
家庭が安全基地になると、
不登校の時間は「後退」ではなく
「整える時間」に変わります。
母親のまなざしが安心に変わるだけで、
ADHDの子どもは少しずつ自分の力を取り戻していけるようになります。
母親が疲れたときこそ大切にしたいココロのケア
ADHDの子どもと
不登校に向き合う毎日は、
あなた自身の神経やココロをすり減らしてきましたよね。
- 朝の声かけに失敗しては落ち込み、
- 家族からの理解がなく孤独を感じ、
「私まで壊れてしまいそう」と涙をこらえた日もあった。
でも、
母親が限界まで疲れてしまうと、
子どもはさらに不安定になります。
ADHDの子どもは
母親の感情を敏感に受け取るからこそ、
母親の安心がそのまま子どもの安心につながります。
だからこそ、
母親自身のココロへのアプローチによる正常化が欠かせないです。
- 誰かに話す、
- 一人で休む時間を持つ、
- 小さなことでも「自分を大切にする」工夫を続ける。
そうやって
母親が安心を取り戻したとき、
不登校で揺れるADHDの子どもも
「大丈夫」と感じられるようになるんです。
「ADHDの不登校サポート」で行き詰まっているあなたへ
ADHDの行きしぶりが続き、朝になるたび
- 「頭が痛い」
- 「今日は行けない」
と布団から出られない
——そのたびに母親だけが追い詰められていませんか?
担任からは「なんとか登校を」、
夫からは「そのうち行く」。
ADHDの現実と周囲の期待のあいだで、あなたの安心だけが削られていく。
ADHDの不登校は「怠け」ではなく、
- ADHDの特性(不注意・衝動性・感覚過敏)と
- 不安・疲労が重なった「行きたくても行けない状態」。
無理に登校させるほど、ADHDの緊張は高まり、家庭の安心が失われます。
いま必要なのは、ADHDの子が「安心して休める家」を整え、
小さな成功体験から「安心して戻れる関わり方」へつないでいくことです。
「ADHDの子どもの不登校サポートに悩み、孤独と不安に押しつぶされていた母が、安心を取り戻し家庭を整えていく──3週間集中再安心サポート」は、
ADHDの理解
学校との対話
家庭内の関わり直し
を3本柱に、迷いを整理し「責める毎日」から抜け出す力を取り戻すプログラムです。
こんな方におすすめです
- ADHDと不登校が重なり、朝の度に親子で消耗している
- 「登校させなきゃ」という圧で、家の安心が崩れている
- 夫や家族の理解が浅く、ADHDの現実を共有できない
- 担任・学年・スクールカウンセラーとの話し方を整えたい
- 「不安で動けない母」から「安心して支えられる母」に変わりたい
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 2月16日(月)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと3名様限定』
※銀行振込限定・先着順
そして──
不登校サポートで家庭の安心が整ったあと、「母としての安心」だけでなく、「私自身のこれから」にも光を当てたい方へ。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
ADHD子育ての経験を資産に変え、
母としても一人の女性としても「これからの生き方」を再設計する3週間です。
家族の落ち着きを守りながら、
「私らしい選択」と「私の軸」を取り戻します。
- ADHD子育てと不登校対応を通じて価値観が揺らいでいる
- 家庭の安心を保ちつつ、自分の人生にも本気で向き合いたい
- これからの選択に確信を持ちたい
「ADHDのある子の母」という枠を超えて、
「私自身の未来を選べる私」へ。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
孤独や夫婦の温度差に悩む母親へ|ADHD 不登校を一人で抱え込まないために

ADHDの子どもが不登校になると、
母親のココロは焦りやこれからの子どもへの心配などで
毎日すり減っていきますよね。
- 学校に行けなかった朝の重苦しさ
- 先生への電話をかけるときの緊張
- 妹や家族への気遣い…
全部を背負って
「私がやらなきゃ」と抱え込んできましたよね。
そんなとき、
夫が同じ温度で寄り添ってくれないと、
ココロの奥で「どうして私だけ…」と孤独を感じてしまう。
ADHDの不登校は
家族全体の課題なのに、
現実には母親ひとりの戦いになってしまうことが多いですよね。
このキャプションは、
その孤独を少し軽くする視点を一緒に見つけていきましょう。
「私だけが頑張っている」と感じるときの抜け道
ADHDの子どもの不登校を支えていると、
すべてを一人で回してきた
重圧の負の感覚に押しつぶされますよね。
- 朝は何度も子どもを呼びに行き、
- 学校に行けなかった日は「一日どう過ごさせればいいのか」と考え続ける。
忘れ物や宿題のサポートも母親にのしかかり、
気づけば「私だけが頑張っている」とココロが叫んでしまう。
でも、
その孤独は弱さではなく、
ADHDの子どもを一番近くで支えてきた証です。
ポイント
抜け道は「完璧をやめる」と決めること。
- 今日は学校に行けなかった、
- その事実を責めずに「そのままの子どもと過ごす」時間を持つ。
母親が肩の力を抜いた日こそ、
ADHDの子どもが「ここにいていい」と
安心できる日になるんですよね。
父親が非協力的に見えるとき、母親ができること
ADHDの子どもが不登校になると、
父親の口から
- 「甘やかしてるからだろ」
- 「もっと厳しくしろよ」
という言葉が出てくることがありますよね。
その瞬間、
胸の奥に「わかってくれない」という孤独が突き刺さる。
でも多くの場合、
父親は悪気があるわけではなく、
ADHDの子どもの不登校に関する知識をまだ持っていないだけ。
母親が毎日直面している
「脳の特性から生まれる現実」を、
父親は知らないんです。
だから母親にできるのは、
「怠けているんじゃなく、ADHDの脳の働きで難しいことがあるんだよ」と、
短い一言を繰り返し届けていくこと。
専門家の話や資料を一緒に見るだけでも、
父親の温度は少しずつ変わっていきます。
非協力に見える距離の裏には、
「知らないからわからない」という壁があるんですよね。
夫が妻の気持ちをわかってくれないときの伝え方
ADHDの子どもの不登校を支える毎日で、
「私の気持ちをわかってほしいのに、夫には届かない」と
あなたは感じてきました。
疲れて泣きそうになっても、
「大げさだな」と受け流されると、
ココロの奥でますます孤独が深まりますよね。
そこで大切なのは、
「わかってよ」と責めるのではなく、
「私は毎朝こんなふうに張りつめているんだ」と
「自分のココロの状態」をそのまま言葉にすること。
ADHDの子どもの不登校で
母親が抱えている緊張や不安を、
事実として伝えるだけで、
夫の受け取り方は変わっていきます。
相手を変えることが目的ではなく、
母親の気持ちを「見える形」にすること。
そうすることで、
少しずつ夫婦の温度差が縮まり、
母親が一人で抱え込む必要もなくなっていくんですよね。
無料LINE診断|今のあなたに必要なサポートは?
「何から始めればいいかわからない…」そんなあなたへ。
LINEで「数字」を入力するだけで、今のあなたに合ったサポート商品を診断できます。
今すぐLINEに【 4 】の番号を入力してください。
「ADHDの子どもの不登校サポートに悩み、孤独と不安に押しつぶされていた母が、安心を取り戻し家庭を整えていく──3週間集中再安心サポート」の概要と、
「なぜ今のあなたに合うのか」が届きます。
「親のせい?」という罪悪感に押しつぶされそうな母親へ
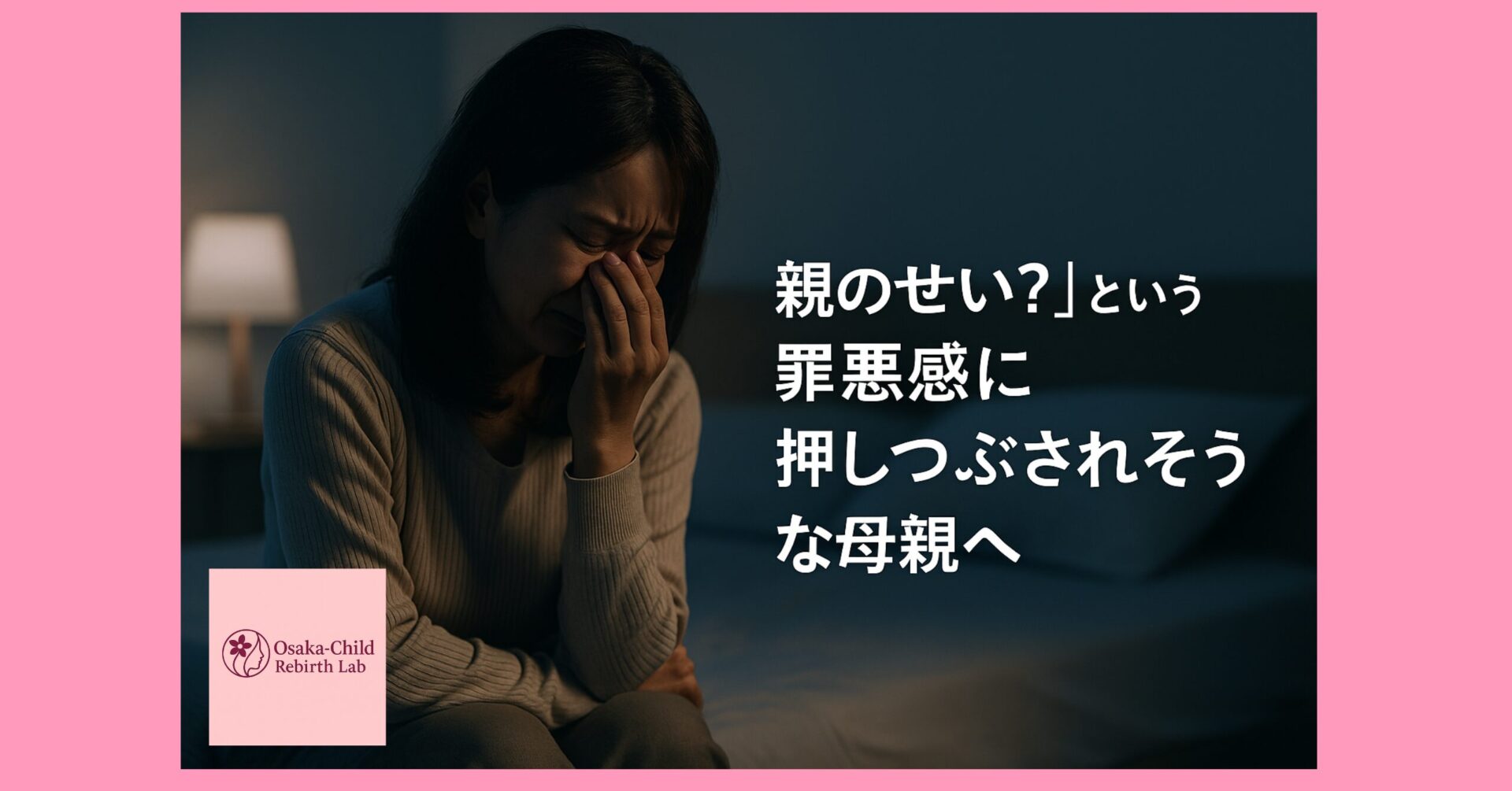
ADHDの子どもが不登校になると、
「やっぱり私のせいだった」と
あなたのココロの中で何度も繰り返してきましたよね。
周りからの言葉や視線が刺さり、
「母親として失敗した」と信じ込んでしまう。
夜になると涙が出て止まらなくなる日もあった。
このキャプションでは、
その重い罪悪感を少しずつ緩めていけるように、
一緒に見ていきましょう。
「育て方が間違っていた」と思い込んでしまう心理
ADHDの子どもが学校に行けなくなると、
- 「小さいころからの接し方が悪かったのかもしれない」
- 「もっと厳しく育てれば違ったはず」
と、自分を責め続けてきましたよね。
人から言われた何気ない一言が頭から離れず、
「やっぱり母親失格だった」と
思い込んでしまった日もありました。
でもそれは、
母親だからこそ
子どもの未来をすべて背負おうとする気持ちがあるから。
ADHDの不登校に向き合っていると、
「全部自分の責任だ」と
錯覚してしまうココロの反応があります。
罪悪感は、
子どもを誰よりも大切に思っている証拠なんですよね。
ADHDの特性と不登校は「親の責任」ではないと理解する
ADHDの子どもが不登校になるのは、
母親の育て方が原因ではありません。
ADHDの子どもの脳は
- 不注意
- 衝動性
をコントロールするのが難しく、
学校という環境で無理が重なれば、
不登校という形で現れます。
ポイント
それは
「親のせい」ではなく、
「特性と環境がぶつかった結果」という反応です。
罪悪感にとらわれていると、
毎日のサポートもつらくなってしまいますよね。
だからこそ、
「ADHDの不登校は親の責任ではない」という理解が必要です。
母親の努力不足ではなく、
脳の特性が背景にある。
その視点に立つことで、
少しずつ「私のせいじゃなかった」と呼吸ができるようになります。
親に理解されないときに支えを得る方法
ADHDの子どもの不登校を支える中で、
親や義父母から
- 「母親のしつけが悪い」
- 「昔はそんなことなかった」
と言われ、
ココロが深く傷ついたこともありますよね。
理解されない苦しさは、
罪悪感をさらに強めてしまいます。
そんなとき必要なのは、
「わかってくれない人を説得すること」ではなく、
「わかってくれる人から支えをもらうこと」。
同じように
ADHDの子どもと不登校を経験している母親の声に触れるだけで、
「私だけじゃなかった」と感じられる。
カウンセリングや支援につながることで、
「親のせいではなかった」と専門家の言葉で確認できる。
孤独を抱え込むのではなく、
支えを受け入れることで、
あなたの罪悪感は少しずつ和らいでいけます。
「親のせい?」の自責を手放し、ADHDの子を安心で支える3週間
「育て方が悪かった?」
——その自責は、ADHDの不登校を前にした多くの母親が抱える痛みです。
ADHDは「親の責任」ではありません。
まず母親が安心を取り戻すことが、ADHDの子の回復を加速させます。
ADHDの子どもは、責められるほど不安が高まり、動けなくなります。
「責める関わり」から「安心して支える関わり」へ切り替えると、
ADHDの子は自分のリズムで学校や外の活動に近づいていきます。
「ADHDの子どもの不登校サポートに悩み、孤独と不安に押しつぶされていた母が、安心を取り戻し家庭を整えていく──3週間集中再安心サポート」
- 1週目:ADHDと不登校に結びつく「自責と孤独」をほどく
- 2週目:家庭を「安心の居場所」へ——朝の声かけもADHD前提に整える
- 3週目:出席以外の「つながり方」で、無理なく回復の軌道へ
将来への不安を整理し、安心に変えるADHDの子どもの不登校サポート

ADHDの子どもが不登校になると、
夜になるたび
明日の朝も学校行けないのでは?と負の反応で
ココロが押しつぶされそうになりますよね。
「このまま学校に行けなかったら、この子の未来はどうなるんだろう」と
不安が頭から離れず、
眠れないまま朝を迎えた日もあった。
母親として子どもの
将来を守りたい気持ちが強いからこそ、
不安はどんどん膨らんでしまう。
このキャプションでは、
その不安を少しずつ整理して、
安心に変えていく視点を一緒に見つけていきましょう。
「二次障害になったらどうしよう」という不安の手放し方
ADHDの不登校に向き合っていると、
「このまま続いたら二次障害になってしまうのでは」と
怖くなることがありますよね。
テレビやネットで耳にする言葉が頭に残り、
「うちの子もそうなるんじゃないか」とココロが苦しくなる。
夜に布団に入っても、
そんな不安がぐるぐる回って眠れなかった日もありました。
あなたに知っておいて欲しいのは
ADHDの子どもが不登校を経験しても、
必ず二次障害につながるわけではありません。
母親ができるのは、
まだ来ていない未来を恐れることではなく、
「今日を安心して過ごせる場」を整えること。
安心して過ごせる毎日が積み重なれば、
未来のリスクは確実に小さくなります。
ADHDの子どもの不登校に向き合う母親が
「今」に目を向けることが、
子どもを守る力になるんですよね。
不登校は将来の失敗ではなく、成長のための一時停止
ADHDの子どもが不登校になると、
「この子の人生はもう終わった」と
あなたはココロの奥で決めつけてしまっていました。
学校に行けない現実が、
未来の失敗につながるように見えてしまうんですよね。
でも、
不登校は「人生の終わり」ではなく
「一時停止」です。
ADHDの子どもにとって、
- 合わない環境
- 過剰なストレス
から少し距離を置く時間は、
回復や自己理解のために大切な期間になります。
立ち止まったからこそ、
- 新しい学び方
- 自分に合うペース
を見つけられることもある。
不登校は後退ではなく、
次に進むための準備期間だと捉えることで、
母親自身の罪悪感や不安も少しずつ和らいでいきますよね。
カウンセリングや支援を取り入れて安心できる環境をつくる
ADHDの子どもの不登校を
母親一人で支え続けるのは、
ココロの大きな負担ですよね。
- 夫婦の温度差
- 親からの理解不足
も重なって、
「結局、私が全部やらなきゃ」と抱え込んできました。
その孤独が、
不安や罪悪感をさらに大きくしてしまうんです。
だからこそ、
カウンセリングや支援を取り入れることが必要です。
ADHDに理解のある専門家や、
同じ経験をしている母親の声に触れるだけで、
「私だけじゃなかった」と感じられる。
安心できる人とのつながりがあるだけで、
家庭の空気は少しずつ柔らかくなります。
ADHDの子どもの不登校は、
母親一人の問題ではなく、
支えを得ながら取り組んでいけるもの。
あなたが安心を取り戻すことこそが、
子どもの安心にも直結していくんですよね。
無料診断|あなたの“心のパターン”を知る
「なぜか同じことで悩んでしまう…」
そんな方のために、LINEで「キーワード」を送るだけで診断できるサービスをご用意しました。
LINEに「ADHD 不登校 サポート」と入力して送信してください。
あなたに合った視点と解説をすぐにお届けします。
「責めずに関われる母」に変わるまで──3週間集中再安心サポート

ADHDの子どもが不登校になったとき、
母親は毎日「どうすればいいの」と
胸が押しつぶされる気持ちになりますよね。
- 無理に登校させても悪化する気がして、
- かといって休ませ続けるのも不安で…。
その板挟みの中で、
自分を責めてきました。
このキャプションでは、
そんな状況にある
あなたが安心を取り戻し、
家庭を整えられる3週間のサポートについてお話しします。
母親が「不安」から「安心」に変わっていく3週間のプロセス
朝、
布団から出られないADHDの子どもを前に、
何度「早くしなさい」と言ってしまったでしょう。
そのたびに、
子どもはますます不登校が深まり、
あなたは「私のせいだ」と罪悪感を抱いてきましたよね。
だからこそ、
このサポートは子どもを変えることから始めません。
まずはあなたのココロを整えることが最初の一歩です。
- 1週目:不安と孤独を受け止めて、自分を責める気持ちをゆるめる
- 2週目:安心を取り戻し、家庭に落ち着きを広げる
- 3週目:その安心をもとに、ADHDの子どもへの具体的なアプローチを始める
こうして段階を踏むからこそ、
ADHDの子どもに「責められない安心」を届けられる段階があります。
家庭でできる支援を整えると子どもの表情も変わる
あなたが落ち着きを取り戻すと、
家庭はADHDの子どもにとって
安心の居場所に変わります。
「また休んだの?」と叱る代わりに、
「今日はここで一緒に過ごそう」と声をかけた日、
子どもの表情は少しずつ柔らかくなっていきます。
家庭でできる支援は難しいことではありません。
- 「できない宿題」を一緒に1問だけやってみる
- 登校できない朝に「今日は大丈夫だよ」と伝える
- 家族で過ごす時間を「安心できる空気」で満たす
そんな小さな積み重ねが、
不登校で揺れているADHDの子どもの神経を落ち着け、
安心につながっていきます。
母親が変われば、ADHDと不登校を抱えた家庭に安心が戻る
ADHDの子どもの不登校に
焦っていたときは、
家庭の中にいつも重苦しい空気が
ありましたよね。
けれど、
母親であるあなたが整うと、
不思議なくらい家庭全体の雰囲気も変わります。
- 下の子も安心し、
- 夫にも「無理に行かせなくてもいい」
という言葉を伝えられるようになる。
その積み重ねが、
ADHDと不登校に悩む家庭に
「もう大丈夫」という空気を戻していきます。
ポイント
母親が自然にココロの構造を整えると
ADHDの子どもも家庭も、安心を取り戻せるのです。
具体的な3週間サポート構造の紹介
ADHDの子どもが不登校になったとき、
「どうにか学校に行かせなきゃ」と
必死になってきましたよね。
でも、
どんなに声をかけても動けない姿を前にすると、
「私の育て方が悪かったのかな」と
ココロが苦しくなっていました。
周りの友達の家庭とは違う気がしても、
誰に話せばいいのか分からず、
言葉にできない孤独を抱えてきた…。
そんな日々が続いてきましたよね。
サポートの価値|「診断名より先に必要なもの」
「ADHDの子どもの不登校サポートに悩み、孤独と不安に押しつぶされていた母が、安心を取り戻し家庭を整えていく──3週間集中再安心サポート」
「ADHDだから不登校になった」と言われても、
その言葉だけではココロは救われません。
実際に一番苦しいのは、
「子どもが動けない現実」を前に責め続けてしまう
母親自身の気持ちです。
この3週間集中再安心サポートが大切にしているのは、
診断名よりも先に
「母親の安心」を整えること。
あなたが安心を取り戻すことこそが、
ADHDの子どもが安心して回復していくための出発点になるのです。
実践内容|具体的な3ステップ構造
この
「ADHDの子どもの不登校サポートに悩み、孤独と不安に押しつぶされていた母が、安心を取り戻し家庭を整えていく──3週間集中再安心サポート」プログラムは、
母親のココロを整えながら
家庭全体を安心の場所に変えていく3ステップで構成されています。
- STEP①|気づき
ずっと押し殺してきた不安や罪悪感に「名前をつける」ことから始めます。
「どうしても焦ってしまう」「夫に分かってもらえない」など、言葉にならなかった感覚を整理し、自分の気持ちを見つめ直します。 - STEP②|実践
母親自身が整い始めると、家庭での関わり方を変える余裕が生まれます。
「早く支度して」と急かす声かけを、「今日はここで安心して過ごそう」に変えるだけで、ADHDと不登校を抱えた子どもは表情を緩めていきます。
学校に行けなくても「一緒に宿題を1問だけやろう」と寄り添う。そんな小さな実践を重ねていきます。 - STEP③|軸の再構築
3週目からは、子どもへのアプローチを本格的に始めます。
「学校に行けない=失敗」ではなく、「家庭から安心を回復していくプロセス」と捉え直すこと。
診断や出席日数に縛られず、“私たちなりのまなざし”で子どもを支えていける軸を育てていきます。
変化|子どもや家庭に起きる体感レベルの変化
母親が安心を取り戻すと、
不思議なくらい家庭全体が和らぎます。
これまで伝わらなかった言葉が子どもに届き、
ふとした瞬間に笑顔が返ってくる。
「行かなきゃ」と責めていた空気が消え、
「ここにいても大丈夫」と思える場所に変わる。
下の子も安心して過ごせるようになり、
家族全体が落ち着きを取り戻していきます。
ADHDの子どもは、
家庭が安心で満たされることで、
少しずつ外の世界に関わろうとする力を取り戻します。
締めの境地|「母親の安心」がすべての出発点
この3週間のサポートが伝えたいのは、
ADHDと不登校に揺れる子どもを支えるためには、
まず母親が安心を取り戻すことが何よりも大切だということです。
あなたが安心できることが、
この子にとっての安心につながっていきます。
- 「責めなくてもいい」
- 「安心して関われる私でいい」
――その実感が、家庭と子どもの未来を変えていきます。
母親が安心を取り戻す3週間プログラム
「ADHDの子どもが不登校に…どう支えたらいいの?」と、ずっと悩んできたあなたへ。
この3週間で、「責める子育て」から「安心して寄り添える母」へ変わる一歩を踏み出せます。
- 孤独
- 罪悪感
- 将来への不安
に押しつぶされてきたココロを、まずは整えることから。
母親が安心を取り戻すと、家庭全体が落ち着きを取り戻し、
ADHDと不登校で揺れていた子どもも安心できるようになります。
「無理に登校させなくてもいい。安心して支えられる私でいい」
そう思える自分に、3週間で近づいてみませんか?
「ADHDの子どもの不登校サポートに悩み、孤独と不安に押しつぶされていた母が、安心を取り戻し家庭を整えていく──3週間集中再安心サポート」
まとめ|「無理に行かせるより、安心を守りたい」と感じてきたあなたへ
ADHDの子どもの不登校に向き合う毎日は、
誰にも見えないところで
涙があふれるほどつらいですよね。
朝になっても布団から出られない姿を前に、
声を荒らげてしまい、
そのあとで自己嫌悪に沈む夜。
学校や先生から
「なんとか登校を」と言われるたび、
責められているように感じてしまう。
夫は「そのうち行くようになる」と軽く流し、
下の子にまで気を配れず、
孤独と罪悪感だけが積もっていった。
ADHDの子どもの不登校を抱えてきた母親のココロは、
ずっと限界ぎりぎりだったのです。
けれど本当に大切なのは、
無理に登校させることではありません。
ADHDの子どもにとって一番の支えは、
「ここにいていい」と感じられる家庭の安心です。
母親がその視点を持つだけで、
家庭の空気は少しずつ変わり、
子どもも安心を取り戻していきます。
ADHDの不登校サポートで意識しておきたい5つの視点
- 登校をゴールにしない ─ ADHDの子に必要なのは「行くか行かないか」ではなく、安心できる環境。
- 家庭を安全な拠点にする ─ 学校で頑張れなくても、家が安心の場所なら立ち直る力が育つ。
- 怒りと罪悪感を手放す ─ 責めてしまうたびに自己嫌悪を繰り返す悪循環を断ち切る。
- 学校とは対立ではなく対話を ─ ADHDの特性を理解し、登校にこだわらない協力を得ていく。
- 母親自身の安心を最優先に ─ 母の心が落ち着くと、子どもも不登校の渦から抜け出しやすくなる。
これからの一歩は、
「学校に行かせなきゃ」という思い込みを少しずつ手放し、
家庭を安心で満たしていくことです。
母親が落ち着きを取り戻すと、
ADHDの子どもは少しずつ自分のペースで外の世界へ歩き出します。
下の子も
「お母さんは大丈夫」と感じ、
家庭全体に安心が広がっていきます。
夫との関係も変わり、
「あのとき無理に行かせずに守ってよかった」と
未来で思える日がきっと訪れます。
子どもの不登校に向き合って、
「どうして責めてばかりいたのか、少しわかってきた」と
感じていきます。
無理に登校させようと必死になり、
家庭の安心がすり減っていったことに気づくと、
涙が込み上げてきますよ。
「このやり方じゃ、母親も子どもも苦しかったんだ」と整理できた今こそ、
ここからの一歩を考える時です。
そこで用意したのが、
「ADHDの子どもの不登校サポートに悩み、孤独と不安に押しつぶされていた母が、安心を取り戻し家庭を整えていく──3週間集中再安心サポート」です。
このサポートでは、
子どもの不登校を「直接解決」するのではなく、
まず母親自身のココロを整えることから始めます。
母親が落ち着きを取り戻すと、
家庭の空気が自然に安定し、
子どもは「責められない安心の居場所」を感じられるようになります。
3週間は段階的な流れで進みます。
- 1週目:母親の孤独・罪悪感・不安をしっかり受け止める
- 2週目:ココロの回復と安心の土台をつくる
- 3週目:整った母親から子どもへの「責めない関わり」を始める
学んでいくのは、母親自身の心への関わり方と、家庭での具体的な声かけです。
- 「頑張らなきゃ」から「安心していい」へ切り替えること、
- 不登校を「失敗」ではなく「特性に合ったプロセス」と捉えること。
- 朝の声かけを「急かす言葉」から「安心の言葉」に変えること。
- 無理に登校を迫らず、家庭を安全基地にすること。
そして3週目からは
「できない」を責めず
「一緒に小さくやってみる」アプローチを重ね、
学校とも「出席以外のつながり方」を見つけていきます。
「ADHDの不登校で積み重なった迷いと不安」をこのままにしない私へ
「ADHDの不登校が続き、朝になるたび親子で消耗してしまう」
「無理に登校させるほど荒れてしまい、家の安心まで崩れていく」
──この記事で「ADHDの不登校は怠けではない・家庭の安心が最優先」と整理できた今こそ、
母親である私のココロを整え、子どもに合う一歩を現実にしていくタイミングです。
「ADHDの子どもの不登校サポートに悩み、孤独と不安に押しつぶされていた母が、安心を取り戻し家庭を整えていく──3週間集中再安心サポート」は、
ADHDの理解・学校との対話・家庭内の関わり直しを一緒に整理し、
「登校を急がず、安心を土台に回復させる」ための伴走型サポートです。
こんな方におすすめです
- ADHDと不登校が重なり、朝の行きしぶりやパニックで毎日が限界
- ADHDの特性を踏まえた「安心して休める家」と“安心して戻れる関わり方”を整えたい
- 担任・学校との会話で、ADHDの前提を共有し対立を避けたい
- 夫や家族にADHDの現実を伝え、温度差と孤立感を減らしたい
- 「責める母」から「安心して支えられる母」へ、確かな手順で変わりたい
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 2月16日(月)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと3名様限定』
※銀行振込限定・先着順
ネットバンキングのご利用で、今すぐ開始することが可能です。
そして──
家庭の安心と不登校サポートが整ったあと、
「母としての私」に加えて、「私自身のこれから」にも光を当てたい方へ。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
ADHD子育てで得た気づきを資産に変え、
家族の安定と「私の生き方」を両立させる3週間です。
家族を支えながらも、
「私らしい選択」と「私の軸」を取り戻していきます。
- ADHD子育てと不登校対応を経て、価値観が揺らぎ「自分」を見失いかけている
- 家庭の安心は維持しつつ、「私の人生」も再構築したい
- これからの10年を、自分の選択に確信を持って歩みたい
「ADHDのある子の母」という枠を超えて、
「私自身の未来を選び取れる私」へ。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
すでに診断済みの方も、そのまま詳細ページへ進めます。
あなたの心と体に合ったサポートを、今すぐ確認してみてください。








