
わが子のADHDらしさに気づいてから、
毎日が小さな引っかかりの連続になってしまう。
- 忘れ物が多く、
- 教室でもじっとしていられない。
- 何度伝えても動けず、時間だけが過ぎていく。
集団になると固まってしまい、
先生からも
「一度、専門の先生に相談してみては」と言われた。
それでも、
- 小児科?
- 発達外来?
- 精神科?
- 小児神経科?
──何科に行けばいいのかが分からない。
日常は待ってくれません。
- 朝の支度で時間をかけすぎ、イライラをぶつけてしまう。
- 買い物中に衝動的に動き出し、手を離してしまう。
- 宿題は机に向かっても数分で気が散り、声をかけるたび険悪になる。
そんな繰り返しに、
母親としての自信が削られていく感覚が続きます。
夫は
- 「気にしすぎだよ」
- 「そのうち落ち着くよ」
と言うだけで、具体的な動きはない。
学校に相談しても明確な答えは返ってこず、孤独なまま判断を迫られる。
ADHDのことを調べても、情報が多すぎて混乱するばかり。
深夜、家族が眠ったあとスマホを開き、
「ADHD 診断 何科」と検索しては、
答えの出ないまま画面を閉じる
──そんな夜を、何度も繰り返してきました。
この記事は、
「ADHD 診断 何科」と深夜に検索しながらも、
迷いと不安で立ち止まってきた母親が、
受診先の選び方や判断の流れを整理し、
安心して最初の一歩を踏み出せるようになるための道筋をまとめています。
この記事を読んでわかること
- ADHDの相談先をどう選ぶか──最初の入口の見つけ方
- 小児科・発達外来・精神科・小児神経科の違いと活かし方
- 迷ったときの判断軸(子どもの困りごと起点で整理する方法)
- 伝える内容と準備の要点(家庭で整えるミニチェック)
- 受け止め方を変えていく視点──ADHDのある日常を軽くするヒント
ここまで、
ひとりで抱えてきた日々を思い出してください。
やれることはやってきたのに止まってしまったのは、
弱いからではなく、
情報と不安が積み上がりすぎたからです。
ADHDの子どもに必要なのは、
「正しさ」よりも「合う関わり」。
母親の視点が整えば、
家庭の空気は少しずつやわらいでいきます。
そのためには、
受診先を決めることと同時に、
日々の関わりを見直すことが欠かせません。
迷いを整理しながら、家庭での関係も整えていける
──そんな時間を形にしたのが、
「ADHDの診断と受診先に迷い続けていた私が、特性に合った関わり方を見つけ、『安心して支えられる母』に変わっていく──3週間集中再安心サポート」は、
ADHDの受診先探し関わり方の再構築を同時に
行う3週間のプログラムです。
- Week1|言葉にして整理する時間
夜中に何度も検索しても、一歩も進めなかった理由を、一緒にゆっくり並べていきます。
「診てもらうべき?」「何科に行けばいい?」という迷い、
夫や学校にうまく話せなかった孤独感、受診が怖かった気持ち、自分を責めてきた思いも安心して口にしていただきます。
忘れ物、癇癪、集中が途切れる…ADHDでつまずく場面を具体的に書き出し、
「なぜ止まってしまっていたのか」をはっきりさせます。 - Week2|選び方を決める時間
ADHDの受診の目的をはっきりさせてから、小児科・発達外来・小児神経科・精神科の違いを「うちの子基準」で整理します。
病院で伝えるときの具体例(行動の頻度・場面・影響)も一緒にまとめ、
情報に振り回されず「この順番で行こう」と自信を持って選べる判断軸をつくります。 - Week3|関わりを整える時間
ADHDの特性に合わせた3つの整え直しを実際にやってみます。
①困りごとを「行動」ではなく「背景」から見る(脳の特性や情報処理のペースを理解する)
②声かけ・順序・環境を整える(短く区切る/選択肢を減らす/動線で示す)
③母親のココロの状態も関わりの一部として整える(呼吸や余白を取り戻し、焦りを減らす)
こうして「何度伝えても動けない」が「自然に動ける」に変わる土台をつくります。
サポートのBefore→After
- 何科かわからず停止 → 受診先を自分で決定
- 検索で混乱 → 必要情報だけを整理
- 注意と叱責が中心 → 背景理解の声かけへ
母親は少しずつ判断力と安心感を取り戻し、
子どもも反発や癇癪が減って、
挑戦する気持ちが育っていきます。
探すのは「正解」ではなく、
「ADHDのある毎日を、私の手で心地よく整えていくこと」
そんな3週間をご一緒します。
この3週間で感じた変化は、
受診の場面だけでなく、
ふだんの生活や声のかけ方にも広がっていきます。
だからこそ、
まずは日常の中にある小さな「気づき」から始めていきましょう。
ここからは、あなたが抱えてきた迷いや不安を、一つずつ整理していきます。
監修者
株式会社Osaka-Child所属 小児神経科医
- 名前: 三浦あすか
- 出身地: 兵庫県西宮市
- 最終学歴: 神戸大学医学部 小児科専攻
- 専門分野: 小児神経、DCD(協調運動障害)、発達性ディスプラクシア、HSP気質の子ども支援
- 職歴: 兵庫県立こども病院 小児神経センター勤務(11年)
専門分野について一言: 「できないことの奥にある『がんばっているサイン』を、もっと社会全体で受けとめていけたらと思っています。」
監修者
株式会社Osaka-Child所属 臨床心理専攻大学教授
- 名前: 森本哲夫
- 出身地: 奈良県
- 最終学歴: 米国ハーバード大学心理学部 博士課程修了
- 専門分野: 臨床心理学、発達心理学
- 職歴: ハーバード大学研究員(5年)、大阪大学人間科学部教授
専門分野について一言: 「心の成長とは、自己理解の旅でもあります。その旅のお手伝いができれば幸いです。」
「ADHDの診断は何科?」と迷い続けてきたあなたへ
ADHDの診断を受けたいけれど、小児科?発達外来?精神科?
──その迷いを抱えたまま、時間だけが過ぎていませんか?
──インターネットで調べるほど、
「ADHDの診断は何科に行けばいいの?」という答えが見えなくなる方も多いはずです。
ADHDと診断された子どもの母として、
または「ADHDかもしれない」と感じているあなたとして、
正しい受診先を選ぶことは、この先の関わり方を整える第一歩です。
- 「もし診断がついたらどうするのか」
- 「診断がつかなくても何ができるのか」──
その整理ができれば、もう迷いに振り回されません。
「ADHDの診断と受診先に迷い続けていた私が、特性に合った関わり方を見つけ、『安心して支えられる母』に変わっていく──3週間集中再安心サポート」は、
ADHDの診断目的と受診先を整理し、
診断後も安心して関われる関係づくりをサポートします。
こんな方におすすめです
- ADHDの診断を受けたいけれど、何科に行けばいいのか迷っている
- 小児科・発達外来・精神科の違いがわからず、不安で動けない
- 診断が必要かどうか、自分では判断できない
- ADHDの特性に合った関わり方を知りたい
- 第2子を考える前に、今の関係を整えておきたい
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 2月13日(金)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと1名様限定』
※銀行振込限定・先着順
▶ ADHDの診断先と関わり方を整理して、安心して動ける3週間へ
そして──
受診先と関わり方を整えたあと、
「母親としての私」だけでなく、「私自身のこれから」を考えたい方へ。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
ADHDの子どもとの関係を整えた先に、
自分の人生を再設計するための3週間です。
母であることも、妻であることも大事。
でも、「私の時間」も大切にしたい──
そんな思いを応援する再出発のプログラムです。
- ADHDの子育てを通じて、自分を見つめ直すようになった
- 「家庭だけの毎日」から、新しい一歩を踏み出したい
- これからの生き方に納得感を持って進みたい
このプログラムでは、
「誰かのために頑張る私」から、
「私のために整える私」へ変わっていきます。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
「ちゃんとしてるのに、苦しい」
「頑張ってるのに、うまくいかない」
——そんな違和感を抱えたまま、ずっと我慢していませんか?
LINEで3分セルフ診断ができます。
あなたの“今の感覚”の正体が、見えてきます。
「ADHDの診断は何科?」と検索した母親の「迷い」はどこから来ているのか

- 子どもの落ち着きのなさや、
- 何度注意しても同じことを繰り返す
姿を見て、
「もしかしてADHDかも」と感じ始めると、
最初にぶつかるのが「受診先の壁」です。
夜中にスマホで「ADHD 診断 何科」と検索しても、
小児科・発達外来・精神科・小児神経科…といった名前が並ぶばかりで、
どれが正解なのかははっきりしません。
この迷いは、
- 「間違った場所に行ったらどうしよう」という不安や、
- 「そもそも診断って必要なの?」という気持ち
と重なっていきます。
実は、
これはあなただけの悩みではなく、
多くの母親が同じ場所で立ち止まっているのです。
ADHDの診断で「何科かわからない」のは、母親だけの問題ではない
ADHDの診断先は、
全国で共通して決まっているわけではありません。
症状や年齢、地域の医療体制によって、
- 小児科
- 発達外来
- 小児神経科
- 児童精神科など、
複数の選択肢が存在します。
だから、
インターネットで調べても
「うちの子の場合はどこ?」という
疑問が残ったままになります。
正解が人によって違うからこそ、
検索しても迷いが消えず、
不安が続くのです。
母親がひとりで判断できないのは、
情報が不足しているからではなく、
そもそも状況が複雑だからです。
「とにかく受診すればいいわけじゃない」──ADHD診断の難しさ
ADHDの診断は、
病名をもらうことだけが目的ではありません。
診断後に、
家庭や学校での支援がきちんと整わなければ、
母親の負担も子どもの困りごとも変わらないままです。
「この子に一生レッテルを貼ることになるのでは」と感じて、
診断そのものに抵抗を持つ方もいます。
「支援を受けるには診断が必要?」と迷うこともありますよね。
だからこそ、
ただ急いで受診すればいいという話ではなく、
「診断の意味」を整理することが欠かせないのです。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「ADHDって、結局どういうことなの?」
そんな疑問を持った方へ。
子育てで感じる限界や、自分を責めてしまう気持ちを整理するための専門家監修コンテンツをご用意しています。
👉 ADHDの基礎と向き合い方をやさしく解説|安心して関係を整える第一歩
-

-
参考ADHDとは?子育てに限界を感じたあなたへ|「責める毎日」を手放すヒント【児童精神科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 朝から何度も叱って、 疲れ果てた夜。 寝顔を見るたびに、 「また怒りすぎた」と後悔ば ...
続きを見る
「小児科?発達外来?精神科?」──ADHD診断で科を選べない本当の理由
受診先が選べない理由は、
選択肢が多く、
それぞれの違いがはっきり見えないからです。
小児科は身近ですが、
発達障害の専門医が常勤しているとは限りません。
発達外来は専門的な対応が期待できますが、
予約が数か月先になることもあります。
精神科は年齢制限や紹介状が必要な場合も多く、
児童向けの診療枠は限られています。
こうした事情を知らないまま受診先を選ぶと、
「思っていた診療が受けられなかった」ということもあります。
有名だからと選んだ病院の予約が取れず、
また最初から探し直す…
そんな経験をする母親もたくさん多いです。
無料診断
「ADHDの診断は何科が正解?」と検索しても、迷いが消えない…
そんな方のために、LINEで「キーワード」を送るだけで診断できるサービスを用意しました。
受診の目的整理と、あなたに合う受診先のヒントが届きます。
LINEに「ADHD 診断 何科」と入力して送ってください。
あなたの状況に合った視点と、次の一歩をお届けします。
ADHD診断に対する不安と混乱─母親が受け止めきれない「背景の重なり」

ADHDの診断について調べていると、
画面の文字がそのまま胸に突き刺さりますよね。
検索すればするほど、
安心よりも不安が増えてしまう。
「この子がADHDと診断されたら、私たちの毎日はどうなるんだろう」
──頭の中で、その言葉だけが響き続ける日もあります。
不安と混乱の奥には、
ただ情報が足りないという理由だけではなく、
母親のココロの中に長年積み重なってきた思いや経験があります。
その絡まりがほどけないまま、
「診断に行くべきか」という判断がますます難しくなっていくのです。
ここからは、その背景を一つずつ見ていきましょう。
「この子が診断されたら…」と想像したときの、母親の中にある葛藤
ADHDの診断を受けた瞬間から、
学校や周りの見方が変わってしまうんじゃないか。
その不安が、何度も頭の中で繰り返されますよね。
「将来、進学や仕事に影響が出るかもしれない」という怖さも、
一緒に押し寄せてくる。
ADHDという診断名は、
支援や理解につながるきっかけになる一方で、
まだ偏見が残る場面もあります。
診断の本当の意味や、
その後の流れが見えないままだと、
「この子を守れるのかな」という不安ばかりが大きくなっていくのです。
受診すればすべてが解決するわけではないと感じているからこそ、
足が止まってしまう瞬間があります。
「うちの子は違う気もする」──ADHDと診断を結びつけられない理由
ADHDらしい行動が目立つ日もあれば、
落ち着いて過ごせる日もある。
好きなことには夢中で取り組めるし、
学校から「今日は頑張っていましたよ」と言われることもある。
そんなとき、
「本当にADHDなのかな」という気持ちが顔を出します。
ポイント
ADHDの特性は、
環境や状況によって出方が変わります。
だから、
母親の目に映るのは
「できているとき」と「できないとき」の両方で、
判断が揺れ動くのです。
さらに、
「何歳で診断を受けるべきか」という答えも
人によって違い、
その情報のバラつきが迷いを深くします。
診断を受けることで未来が一気に決まってしまうのでは、
という漠然とした恐れも、
その迷いを後押ししています。
「もしADHDだったら親の責任…?」という自責の思考回路
ADHDの可能性を考えるたびに、
「私の育て方が悪かったのでは」という言葉が
ココロの中で響く。
あのとき
叱りすぎた、
もっと優しく接すれば
…そんな後悔が消えませんよね。
ADHDの特性は、
母親の愛情や努力の有無で決まるものではありません。
それでも、
自分を責める気持ちは簡単には消えず、
「育てにくいのは私のせいだ」と思い込むことで、
疲れは何倍にも膨らみます。
その疲れが、
受診に向けての一歩をさらに遠ざけてしまうのです。
この自責のループから抜けるには、
「責任を探す」視点ではなく、
「これから関係を整える」視点を持つことが欠かせません。
ADHDであっても、
母と子の関係はこれから変えていくことができます。
「診断が怖い」を安心に変える3週間
「診断を受けたらラベルを貼られる気がする」
──そんな不安で受診を止めていませんか?
この3週間が、「怖い」を「判断できる安心」に変える第一歩になります。
ADHDの診断は、名前をつけるためだけのものではありません。
診断の目的を明確にして、受診する・しないの判断を自分で選べるようになれば、
迷いと不安に振り回される毎日から抜け出せます。
「ADHDの診断と受診先に迷い続けていた私が、特性に合った関わり方を見つけ、『安心して支えられる母』に変わっていく──3週間集中再安心サポート」
ADHDの診断は何科?|目的によって変わる「最初の相談先」
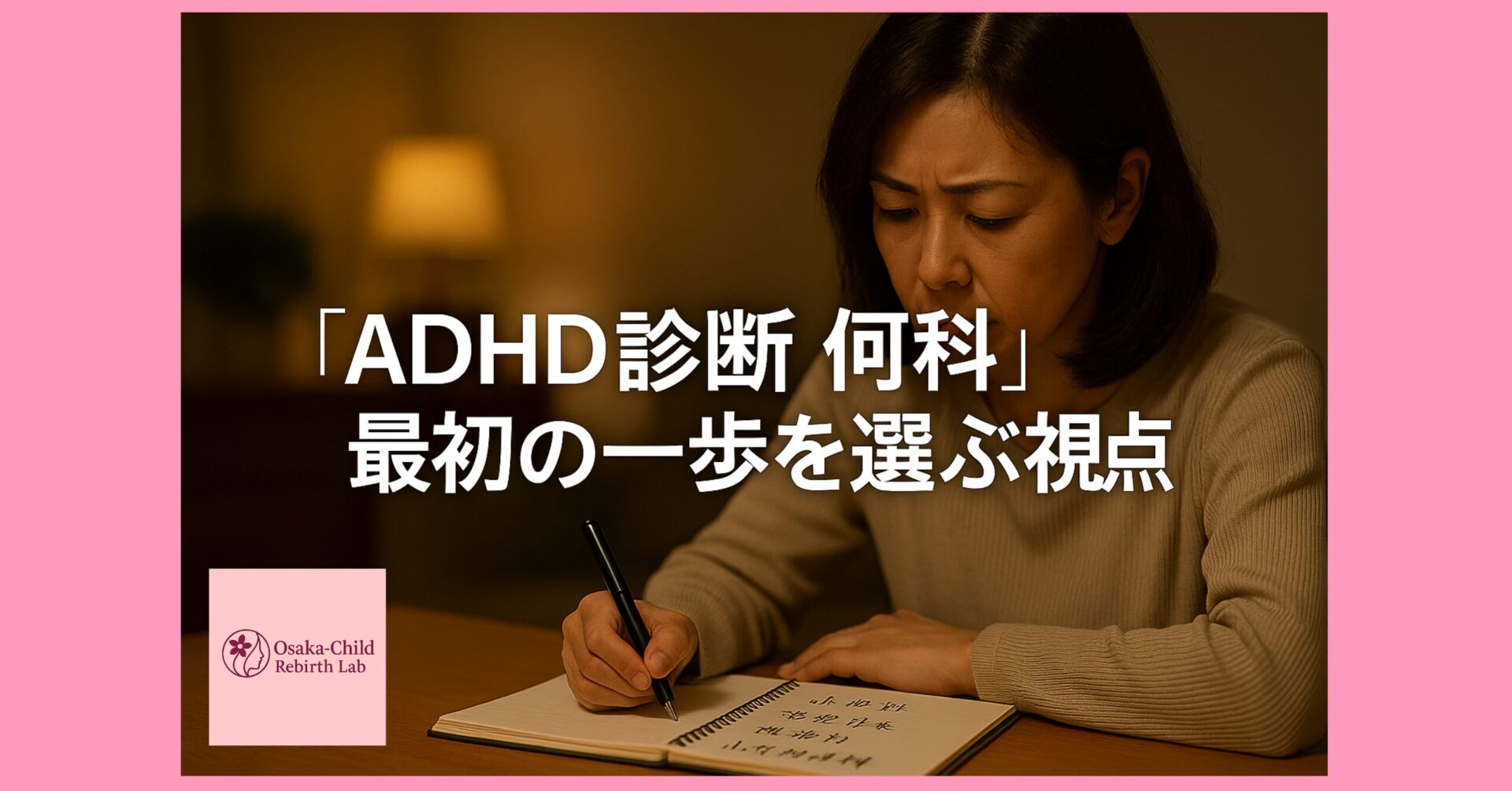
ADHDの診断を受けようと考えたとき、
「まずどこに行けばいいのか」が一番の壁になりますよね。
でも、
その前に立ち止まってほしいのは、
「なぜADHDの診断を受けたいのか」という目的です。
目的が見えていないまま病院を探すと、
- 検索結果を見ては迷い、
- 予約画面の前で手が止まる…
その繰り返しになってしまいます。
このキャプションからは、
あなたの中にある目的を整理しながら、
ADHDに向き合う最初の一歩を見つけていきます。
ADHDの診断目的が「アドバイス」なのか「支援導入」なのかを分けて考える
ADHDの診断を受けたい理由は、
実は人によって全く違います。
学校や家庭での困りごとを減らすために、
- 日常の関わり方や声かけのアドバイスが欲しいのか。
- それとも、療育や支援制度を利用するために、ADHDの診断書が必要なのか。
この2つは似て見えて、
求める結果がまったく違います。
「とにかくADHDの診断を受けなければ」と思っていたのに、
本当は支援制度が目的ではなかった…そんなこともありますよね。
目的がはっきりすれば、
- 小児科で幅広く相談するのか、
- 発達外来で専門的に評価を受けるのか、
- 小児神経科で詳しく見てもらうのか…
選ぶ道が自然に決まります。
診断名より「生活のしづらさ」を整理することが先のケースもある
ADHDの診断名をつけることよりも、
まずは「どこで困っているのか」を具体的に整理するほうが、
次の行動に結びつきます。
- 朝の支度で何度声をかけても動き出せない。
- 宿題に取りかかるまでが遅く、
つい強い口調になってしまう。
これらの場面を書き出すと、
ADHDによる生活のしづらさが見えてきます。
医療機関以外にも、
- 子育て支援センター
- 発達相談窓口
- スクールカウンセラーなど
ADHDについて話せる場所はあります。
診断はゴールではなく、
困りごとを解きほぐしていくための入口のひとつ。
そう考えるだけで、受診先の選択肢が増えていきます。
受診目的が見えると「何科に行くべきか」が自然に決まる
ADHDの診断は早いほうがいい
──そう感じるのは、子どもの将来や日々の負担を考えるからですよね。
でも、
本当に大切なのは、
受診のタイミングよりも「何を目的に行くのか」がはっきりしていることです。
目的が決まれば、
- 「まず小児科で全体を見てもらう」
- 「発達外来でADHDの専門評価を受ける」
- 「小児神経科で脳や神経発達の視点から確認する」など、
動き方が整理されます。
受診の流れも、
- 紹介状の有無
- 必要な書類
が見えてくるので、
無駄な動きが減ります。
ポイント
ADHDの診断は、
その日がゴールではありません。
そこから、
あなたと子どもの関係を整えていくためのスタートになるのです。
“受診先の迷い”を整理して、安心して選べる母へ
「小児科?発達外来?精神科?」
──ADHDの診断は何科に行けばいいのか、迷いが続いていませんか?
この3週間で、「この子に合う受診先」を整理し、安心して動き出せる母に変わります。
診断があってもなくても、
「どう育てていけばいいのかわからない」ままでは、家庭の不安は続きます。
受診の目的を明確にし、何科を選べばいいのかを一緒に整理することで、
「動けない時間」を終わらせませんか?
「ADHDの診断と受診先に迷い続けていた私が、特性に合った関わり方を見つけ、『安心して支えられる母』に変わっていく──3週間集中再安心サポート」
ADHD診断は何科?|小児科・発達外来・精神科・小児神経科の違いと特徴

夜中に「ADHD 診断 何科」と打ち込んで、
あなたは出てきた情報を
何度もスクロールしたことがありますよね。
- 小児科なのか
- 発達外来なのか
- 精神科や小児神経科なのか
──それぞれの違いがわからないまま、
「間違えたらどうしよう」と動けなくなることもありますよね。
ここからは、
ADHDの診断につながる主な診療科を、
母として安心して選べるように整理していきます。
ADHDと小児科|発達に詳しい医師と、そうでない医師の差
ADHDを相談する場所として、
一番近くにあるのは小児科です。
普段から通っている小児科だからこそ、
「まずここで聞いてみよう」と思える安心感がありますよね。
ただ、
- ADHDの診断や支援に詳しい小児科医もいれば、
- 発達面は専門外の医師もいます。
短い診察時間では、
家庭や学校でのADHDの困りごとを深く掘り下げられないこともあります。
ADHDを小児科で相談するときは、
単に「落ち着きがない」とだけではなく、
- 「忘れ物が毎日ある」
- 「授業中に立ち歩く」
- 「感情が爆発して泣き出す」など、
具体的なエピソードを持って行くことが大切です。
ポイント
発達に理解のある医師であれば、
ADHDの可能性を踏まえて、
発達外来や小児神経科への紹介につなげてくれます。
小児科は、
ADHD診断のスタート地点になり得る場所。
大事なのは、
発達を理解してくれる医師に出会えるかどうか、その見極めです。
ADHDと発達外来|窓口としての役割と、診断へのつながり方
「発達外来」という言葉を聞くだけで、
少し構えてしまうこともありますよね。
でも、
発達外来は
ADHDを含む発達特性を専門的に見てくれる窓口です。
家庭や学校でのADHDの困りごとを整理し、
診断や支援へつなぐ役割があります。
ポイント
発達外来では、
ADHDかどうかを判断するために、
問診・行動観察・心理検査などを組み合わせます。
診断が確定するまでに数回通院することもありますが、
その過程で「この子への関わり方」が見えてくることも多いです。
ADHDと診断されることがゴールではなく、
そこからどう支えるかを一緒に考えてくれるのが発達外来です。
「どこで診断を受ければいいかわからない」と迷っているなら、
まずはここが入り口になります。
小児神経科・児童精神科の違い|ADHDとどう向き合う科なのか
ADHDの診断に関わる専門科の中でも、
小児神経科と児童精神科は混同されやすい科です。
小児神経科は、
ADHDの背景にある脳や神経の働きを専門的に診ます。
- 発達性協調運動障害
- てんかんなど、
神経系の症状が重なる場合にも対応できます。
一方、
児童精神科は、
ADHDによる情緒や行動面の困りごとに焦点を当てます。
- 衝動性の強さ
- 感情の波の大きさ
- 不安の強さ
──そうした面が日常生活に影響しているときに力を発揮します。
どちらもADHDの診断・支援につながりますが、
「どこが中心の困りごとなのか」で選ぶ科が変わります。
迷ったときは、
小児科や発達外来で話し、
必要に応じて紹介状をもらうのが安全な流れです。
「ADHDの診断は何科に行けばいいのか…」と迷い続けてきたあなたへ
ADHDの診断を受けさせたいのに、
小児科・発達外来・精神科…どこに行けばいいのか決めきれない
──そんな状況ではありませんか?
──検索すればするほど、「ADHDの診断は何科が正しいのか」がわからなくなってしまう。
ADHDの診断先は、
子どもの年齢や目的によって選び方が変わります。
「まずは誰に相談すべきか」
「診断が必要な場合と不要な場合の違い」も整理できていないままでは、
受診しても迷いが残り、関わり方も定まりません。
本当は、「安心して動き出せる受診先」を見つけたいだけですよね。
「ADHDの診断と受診先に迷い続けていた私が、特性に合った関わり方を見つけ、『安心して支えられる母』に変わっていく──3週間集中再安心サポート」は、
ADHDの診断目的と受診先を整理し、
診断後も迷わず関われる家庭づくりをサポートします。
こんな方におすすめです
- ADHDの診断を受けたいが、何科を選べばいいのかわからない
- 小児科・発達外来・精神科の違いを整理して選びたい
- 診断が必要かどうか、自分だけでは判断できない
- ADHDの特性に合わせた関わり方を早く整えたい
- 第2子を考える前に、今の不安と迷いをなくしておきたい
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 2月13日(金)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと1名様限定』
※銀行振込限定・先着順
▶ ADHDの診断先と関わり方を整理して、安心して動き出せる3週間へ
そして──
診断先と関わり方を整えたあと、
「母親としての私」だけでなく、“私自身のこれから”も考えたい方へ。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
ADHDの子どもとの関係を整えた先に、
自分の人生を再設計するための3週間です。
母であることも、妻であることも大事。
でも、「私の時間」も大切にしたい──
そんな思いを応援する再出発のプログラムです。
- ADHDの子育てを通じて、自分を見つめ直すようになった
- 「家庭だけの毎日」から、新しい一歩を踏み出したい
- これからの生き方に納得感を持って進みたい
このプログラムでは、
「誰かのために頑張る私」から、
「私のために整える私」へ変わっていきます。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
ADHD診断は何科?|迷ったときの「最適な受診先」の選び方ガイド

ADHDの診断を受けたい気持ちはあるのに、
「この子の場合はどこに行くのが正しいのか」がわからず、
スマホの画面ばかり見つめてしまう夜が続くことがありますよね。
- 小児科
- 発達外来
- 小児神経科
- 精神科
──名前は知っていても、
その違いがわからないまま時間が過ぎてしまうものです。
このキャプションでは、
ADHDの診断を考えるとき、
迷いを整理しながら安心して動き出せる選び方の視点をお伝えします。
まず誰かに相談したいときのADHD診断先の選び方
ADHDの可能性が気になっていても、
「いきなり専門科に行くのは不安」というときは、
身近な小児科や発達外来が入り口になります。
小児科なら、
いつも見てもらっている医師に
家庭や学校でのADHDの困りごとを話せるので、
最初の一歩として踏み出しやすいですよね。
発達外来は、
ADHDを含む発達特性の診断に特化し、
心理検査や観察を通して次の受診先や支援方法を提案してくれます。
ADHDの診断先を選ぶときは、
「この子の困りごとを受け止めてくれる場所」から始めることが大切です。
完璧な受診先を探すより、
話をきちんと聞いてくれる窓口に行くことが、
その後の診断や支援の流れを整えてくれます。
「ADHDの可能性が高そう」と感じたときに選ぶべき診療科
家庭や学校での様子から、
「この子はADHDの傾向がはっきりしている」と感じるときは、
小児神経科や児童精神科が候補になります。
小児神経科では、
ADHDの背景にある
脳や神経の働きを専門的に診てくれます。
- 注意の切り替えが苦手
- 感覚の偏りが強いなど、
ADHDに関連する発達の特徴も含めて見てもらえます。
児童精神科は、
ADHDに伴う衝動性や感情の波が生活に影響している場合に力を発揮します。
- 学校や友人関係でのトラブル、
- 感情の爆発などへの関わり方
も一緒に考えてくれます。
ポイント
ADHDの診断先を選ぶときは、
「困りごとの中心は神経発達か、感情や行動面か」を意識すると、
より合った科にたどり着けます。
感情面の問題が強い子どもの場合は精神科が第一選択になる
ADHDの中でも、
感情の波や衝動性が強く、
日常生活や人間関係に影響が出ている場合は、
精神科(特に児童精神科)が第一選択になります。
- 些細なきっかけで怒る
- 泣き出す
- 物を投げる
──そんなADHDの行動が続くと、
母親も常に気が張ったままになりますよね。
精神科では、
ADHDの診断に加えて、
感情のコントロール方法や、
母親自身が安心して関われる環境づくりを相談できます。
「行動を抑える」だけでなく、
「感情を受け止め、次の行動につなげる関わり方」を一緒に探してくれるのが特徴です。
ADHDの診断を通して、
母と子の時間に少しでも安らぎを増やす
──そのために、
感情面のケアを優先できる診療科を選ぶことが、
これからの母親と子どもとのポテンシャルを高くしたままの
最適な関係を守る一歩になります。
「正しい受診先がわからず迷っていた母」が、安心して動き出せるまで──3週間集中再安心サポート

ADHDの診断を受けることを考えながら、
「何科に行けばいいのか」が決められず、
同じ検索ワードを何度も打ち込んできた夜が続いていましたよね。
この3週間集中再安心サポートは、
その迷いを整理し、
- 「診断の目的」
- 「その後の関わり方」
をはっきりさせていくための伴走プログラムです。
受診するかどうかよりも前に、
母としての安心の軸を整える
──それが動き出すためのファーストステップになります。
公式LINE無料診断
「どれも当てはまる気がして、何から始めればいいかわからない…」
そんなあなたへ。
5つのテーマから、今のあなたにぴったりのプログラムを無料で診断できます。
「ADHDの診断と受診先に迷い続けていた私が、特性に合った関わり方を見つけ、『安心して支えられる母』に変わっていく──3週間集中再安心サポート」です。
LINEで「4」(英数字)を入力するだけで、
商品④の内容とあなたに合う理由が自動で届きます。
「ADHDかもしれないけど、どこに相談すれば…」と止まっていた母の変化
ADHDの診断を受けたい気持ちはあっても、
何科に行けばいいのかわからず、
検索画面をスクロールしては閉じる日々。
診断が怖くて、
ADHDという言葉を頭の中で何度も押し込めてきた時間。
家庭での子どものADHDの困りごとや育てにくさを抱えたまま、
誰にも相談できず、
あなたは毎日をやり過ごしてきました。
このサポートでは、
最初に「今の迷い」を一緒に整理します。
ADHDかどうかだけでなく、
「どこで、何を話すのか」が見えてくると、
相談先が具体的に浮かびます。
その瞬間から、
怖さで止まっていたココロが、
「話してみたい」という動きに変わっていきます。
3週間で「ADHDの診断目的と関わり方」が明確になるプロセス
ADHDの診断は、
ただ名前をつけるためだけのものではありません。
「ADHDの診断と受診先に迷い続けていた私が、特性に合った関わり方を見つけ、『安心して支えられる母』に変わっていく──3週間集中再安心サポート」で
一緒に行うのは、
- 「診断を受ける目的」
- 「その後の関わり方」
を明確にすることです。
ADHDの特性が見えてくると、
- 支援の受け方も
- 家庭での工夫も、
驚くほど変わっていきます。
ポイント
診断が必要な場合と、
診断がなくても今からできる関わり方を整理することで、
「何を目指せばいいのか」がはっきりします。
- 「診断を受ければ支援が受けられるのか」
- 「診断がなくても始められることは何か」
──この2つを切り分けたとき、
あなたがずっと胸を占めていた迷いが薄れていきます。
方向が定まると、
受診先の選び方も、
わが子との関係の築き方も自然と整っていきます。
このあとのセクションで、
その3週間がどんな流れで進むのかを具体的にお伝えします。
読みながら、
「ここなら一緒に進める」と感じてもらえるはずです。
自分で判断できる「軸」が育つと、受診も関係も整っていく
ADHDの診断名だけでは、
不安が消えるわけではありません。
本当に必要なのは、
診断の有無にかかわらず
「この子に必要な関わり方は何か」を、
自分で判断できる軸を持つことです。
この3週間で、
その判断の「軸」を一緒に育てていきます。
ADHDの特性に
- 沿った声かけ
- 環境調整
を重ねることで、
母としての自信も戻ってきます。
受診が必要になったときも、
その軸があるから迷わず動ける。
診断後も同じ軸を持って関係を育て続けられます。
「正しい受診先がわからず迷っていた母」が、
自分の足で選び、安心して動き出せる
──その変化を、この3週間で形にしていきます。
「3週間集中再安心サポート」で、診断より先に「母としての安心」を整える
あなたはわが子の育てにくさで
生きる気力が失われるぐらい困っているのに、
診断への抵抗により
どこにも当てはまらない感じが続いてきた。
ADHDの診断先を調べても
「小児科?発達外来?精神科?」と
画面を行き来するだけで、
- ココロの不安や診断された後も
- どう子どもを育てたらいいのかの恐怖は収まらない。
診断が怖い気持ちや、
ADHDの三文字を見つめるだけで固まってしまう時間もあった。
そんな夜を越えてきたココロに、
まず必要なのは「正解のラベル」ではなく、
安心して選べる自分の軸。
そんなあなたにご提案するのは、
「ADHDの診断と受診先に迷い続けていた私が、特性に合った関わり方を見つけ、『安心して支えられる母』に変わっていく──3週間集中再安心サポート」
このプログラムは
その軸を一緒に整えるための伴走プログラムです。
このサポートが大切にするのは、
ADHDの診断名より先に
「母の安心」を回復させること。
ADHDの知識を増やすだけでは、
明日の関わりは変わりません。
診断の有無にかかわらず、
家庭でできる具体的な支え方を積み重ねることで、
ADHDに揺さぶられがちな毎日を、
少しずつ整えていきます。
- STEP①(Week1)気づきの整理
渦巻く不安を言葉にし、
「忘れ物」「衝動」「指示が通らない」などの行動を、
ADHDの脳特性や情報処理の負荷という背景から見直す。
責める視点をほどき、
語れる言葉に置き換える。 - STEP②(Week2)実践の設計
ADHDに届く関わり方を一緒に設計。
伝える量をしぼる・順序を分ける・動線で示す・切り替えの合図を決める等を
家庭の生活に落とし込む。
受診先の候補と受診の目的もここで明確にする。 - STEP③(Week3)判断軸の再構築
ネット情報に流されず、
「うちの子に必要か」で選べる軸を育てる。
ADHDへの声かけと環境調整を回しながら、
受診が必要なサインと
「今は家庭で進める」サインを見分ける。
【Before→After】
- 診断への意識:怖い・避けたい → 「診断は理解の入口」に整理。
- 受診行動:何科で止まる → 小児科/発達外来/小児神経科/精神科の選択理由を自分で説明できる。
- 情報の扱い:検索で混乱 → 必要な情報だけを選びメモ化。
- 関わり方:注意・指示中心 → 背景を見て「届く言葉」に置き換える。
【母の変化(内面+行動)】
- ADHDを責めずに見つめ直せる。
- 「動けない」から「何を整えれば動けるか」へ視点が切り替わる。
- 受診先の違いが腹落ちし、「うちの子はここから」と言える。
- 「叱る前に整える」が習慣化し、家庭の緊張が下がる。
- 判断を他人に委ねず、「今日やること」を自分で決められる。
【子どもの変化(家庭発の安心)】
- 話しかけに応じやすくなり、切り替えの合図に反応が出る。
- できない自分を責めにくくなり、小さな挑戦が戻ってくる。
- 「わかってもらえた」という経験が積み重なり、関係が安定していく。
このプログラムの着地点は
「受診そのもの」ではありません。
ADHDに振り回される毎日を、
母と子のペースで整え直すこと。
受診が必要なときは迷わず選べるし、
今日の家庭でもできることが増えていく。
診断名より先に、関係を支える土台を一緒に作ります。
あなたが安心を取り戻すと、
ADHDの子どもに揺れやすい時間にもあなたのココロの余白が生まれます。
ここからの3週間で、
- 「選べる」
- 「動ける」
- 「支えられる」
母に切り替えていきましょう。
まとめ|迷って立ち止まっていた時間を、今日で終わらせるために
夜中、家族が眠る静かな部屋で
「ADHD 診断 何科」とスマホに打ち込み、
答えを探し続けてきたあなた。
- 小児科?
- 発達外来?
- 精神科?
- 小児神経科?
どこが正しいのか分からず、
検索しては閉じ、
また翌日も同じことを繰り返してきましたよね。
動きたいのに動けないのは、
あなたが弱いからではありません。
ADHDの診断先を選ぶ情報は複雑で、
母親が一人で整理するにはあまりにも負担が大きいからです。
この記事では、
ADHDの診断に向かうための入口と、
- それぞれの科の特徴、
- 迷ったときの選び方
を整理しました。
「知識がないから不安」という状態から、
「知っているから動ける」に変わるための視点を、
何よりもやさしくまとめてきました。
この記事で押さえておきたい要点
- ADHD診断は目的によって最適な入口が変わる
- 小児科は身近でも、発達に詳しい医師かどうかの確認が必要
- 発達外来は診断への橋渡し役になる
- 小児神経科や児童精神科は、ADHDの専門的診療が受けられる
- 「何科か分からない」状態でも、まず一歩動き出すことが解決の始まりになる
記事を読み終えて、
「ADHDの診断先がわからず動けなかった理由」が
整理できてきました。
情報不足ではなく、
複雑な迷いを一人で抱え続けてきたからですよね。
受診先を決められないまま時間が過ぎれば、
子どもとの関係も、あなたの気持ちも疲れてしまう。
それを終わらせるために用意したのが、
「ADHDの診断と受診先に迷い続けていた私が、特性に合った関わり方を見つけ、『安心して支えられる母』に変わっていく──3週間集中再安心サポート」です。
このサポートは、
単に「何科に行けばいいか」を答えるだけではありません。
3週間で、迷いと不安を整理し、
受診先の選び方と関わり方を同時に整えます。
- Week1迷いや不安を言語化し、「この子の困りごと」を整理。情報過多・混乱状態から抜け出し、「受診が怖い理由」に気づけます。
- Week2診断の目的を明確化し、「どの診療科を選ぶべきか」を一緒に検討。「この子に必要なのは何か」に意識が向き始めます。
- Week3ADHD特性に合った声かけや環境づくりを学び直し、「母親としてできること」を整理。受診に踏み出せ、家庭内の空気が変わり始めます。
受講前は
- 「何科かわからず止まっている」
- 「ネット検索でさらに混乱」
- 「注意や指示ばかりで叱ってしまう」
という状態でも、
受講後には
- 「我が子に合う科を自分で選べる」
- 「必要な情報だけを選んで整理できる」
- 「困りごとの背景を理解した声かけ」
に変わります。
ポイント
母親が変われば、子どもも変わります。
反発や癇癪が減り、
気持ちを言葉で表せるようになり、
「話を聞いてもらえる」という安心感が積み重なります。
診断が目的ではなく、
「安心して支えられる関係」をつくることが、
この3週間のゴールです。
今の迷いを終わらせ、自分の判断で動けるあなたへ
──一緒にその一歩を始めましょう。
「ADHDの診断は何科が正解?」と迷い続けてきた私へ
- 「ADHDの診断については理解できたけれど、実際にどの『何科』へ行けばいいのか決めきれない」
- 「小児科・発達外来・精神科…説明は読んだのに、明日の一歩がまだ怖い──」
──この記事でADHDの受診先の違いを整理した今こそ、
ADHDの「目的に合った受診先」を決めて、
家庭の関わり方を動かしていく3週間があります。
「ADHDの診断と受診先に迷い続けていた私が、特性に合った関わり方を見つけ、『安心して支えられる母』に変わっていく──3週間集中再安心サポート」は、
ADHDの診断目的(評価・診断・治療・学校連携)を一緒に整理し、
ADHDに最適な「何科」を選び、受診後の家庭でのADHDの関わり方まで具体化するサポートです。
こんな方におすすめです
- ADHDの診断を受けたいが、何科に行けばいいのか最終決定できない
- 小児科・発達外来・精神科・小児神経科の違いをADHDの目的別に当てはめたい
- 「診断が必要か」「経過観察でよいか」ADHDの基準で整理してから動きたい
- 受診して終わりではなく、家庭でのADHDの関わり方(声かけ・環境)まで整えたい
- 第2子を考える前に、ADHDへの不安を減らし、安心して決断できる状態にしたい
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 2月13日(金)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと1名様限定』
※銀行振込限定・先着順
ネットバンキングのご利用で、今すぐ開始することが可能です。
▶ ADHDの受診先と関わり方を決めて、明日から動ける3週間へ
そして──
ADHDの受診先と関わり方を整えられたからこそ、
「母親としての私」だけでなく、「私自身のこれから」にも目を向けたいと感じたあなたへ。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
「ADHDの子どもを支える母」の次の3週間として、
「私という人生」を取り戻すための再設計を行うプログラムです。
- ADHDの子育てを通して、私の軸をもう一度整えたい
- 「母親だけ」で回る毎日に区切りをつけ、自分の時間と選択を取り戻したい
- これからの人生を、納得して選び抜きながら歩みたい
このプログラムでは、
「発達特性に向き合う私」から、
「私の人生そのもの」を整える3週間が始まります。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
すでに診断済みの方も、そのまま詳細ページへ進めます。
あなたの心と体に合ったサポートを、今すぐ確認してみてください。








