
ADHDと診断されたあの日(6歳)から、
あなたは毎日の子どもの小さなできないことが
日常生活への時間的負荷・ストレスが積み重なっていますよね。
- 朝の準備は忘れ物との戦い、
- 宿題は声をかけても進まず、
つい強い口調になってしまう。
怒ったあとに残るのは、
後悔と「またやってしまった」という気持ちだけ。
市の窓口で診断を受け、
結果の紙はもらったのに、
その後どう動けばいいのかは教えてもらえなかった。
ADHDの情報は探せばいくらでも出てくるのに、
わが子に当てはまる答えが見つからず、
夜になるとスマホを握りしめて検索ばかりしてしまっていました。
- ご主人は「もう少し様子を見よう」といい、
- 義母からの何気ない「あなたの育て方次第」
が胸に残ってしまう。
周りは「心配しすぎ」と軽く言うけれど、
毎日ADHDの特性と向き合っている母親にしかわからないつらさがあります。
何とかしたくて、
試してみた工夫も続かず、
気づけばまた同じことで悩んでいる。
そんな自分を責める日が今も続いています。
あなたは決して怠けてきたわけではありません。
ここまで本当に頑張ってきたんです。
だからこそ、
今度は「一人で抱え込まずに進める方法」を見つけてほしい。
ADHDと暮らす毎日に、
少しずつでも安心を取り戻せる
- 病院選び
- 関わり方を、
これから一緒に整えていきましょう。
この記事は、
ADHDと診断されたあと、
十分なフォローや相談先がないまま、
育てにくいADHDを抱える小学生の子どもを育てている母親のために書いています。
診断を受けた時は
「これで少し安心できる」と感じたのに、
その後の病院選びや関わり方がわからず、
不安と迷いを抱えたままになっています。
同じ困りごとが学校や家庭でくり返され、
夫や家族の理解も得られず、
「私がどうすればいいのか」が見えなくなってしまったあなたに伝えます。
ここでは、
ADHDと暮らす日々を少しでも安心に近づけるために、
- 病院の種類や選び方
- 受診前の準備、
- そしてその先の関わり方までを、
あなたと同じ立場の母親の目線で整理しています。
ここでわかるのは――
この記事を読んでわかること
- 発達外来・小児神経科・児童精神科、それぞれの特徴とできること
- 長く付き合える病院を選ぶための視点
- 学校や家庭と連携しやすい医師を見つける方法
- 受診前に準備しておくと診察がスムーズになる記録の工夫
- 初回診断から時間が経っても受け直すべき理由
ここまで読んで、
「やっぱり一人で抱えるのは限界がある」と感じてきた方も多いはずです。
ADHDと暮らす毎日は、情報を集めるだけでは変わらないこともあります。
実際に試し、続け、少しずつ整えていくためには、
寄り添ってくれる伴走が必要です。
そんなときの「もう一つの選択肢」が、このサポートです。
「ADHD診断後の病院選びに迷い続け、不安と孤立を抱えていた母が、『安心して支えられる私』に変わっていく──3週間集中再安心サポート」は、
まず母親のココロを落ち着けることから始めます。
ADHDの子どもに合った関わりを探す前に、
母親自身が安心して向き合える状態をつくります。
さらに、3週目にはADHDの子どもと向き合う暮らしを、
手順を追ってやさしく整えていく時間です。
- ADHDの困りごとを責めずに観察し、
- ADHDの学び方を一緒に試し、
- ADHDと過ごす関係を軽くしていきます。
自分なりに頑張ってきたけれど、
気づけば毎日が緊張と我慢の連続。
- 「もっと優しくしたいのに」
- 「怒らずに関わりたいのに」…
そんな気持ちと現実の間で、ずっと揺れてきましたよね。
進め方(3週間の流れ)
- 1週目|心をほどく
誰にも話せなかった不安や孤独感を、否定せずに受け止めます。
「動けなかったのは情報がなかっただけ」という事実を共有し、自分を責める気持ちを少しずつゆるめます。
・感情を整理し、息をつける時間を持つことで、日々の緊張を和らげます。 - 2週目|選ぶ軸を整える
「周りに合わせる」から「自分と子どもに合う」へ意識をシフトします。
病院選びや日常の優先順位を一緒に整理し、迷いを減らします。
夫や家族に落ち着いて説明できる言葉を持ち、対立を避けながら協力を得られる準備をします。 - 3週目|子どもに合う関わりを見つける
母親のココロが落ち着いた状態で、子どもの行動を事実として観察します。
困りごとの背景やタイミングを整理し、医師への相談ポイントを具体化します。
子どもに合った病院や関わり方を決め、次の一歩を踏み出します。
得られる変化
- 母親:自責が減り、選択の根拠を持って行動できるようになります。
- 子ども:責められる回数が減り、受け入れられる経験が増えます。
正解を探す旅ではなく、母親と子どもが安心して進める道を一緒につくる3週間です。
ここから整えていきましょう。
[/st-mybox]
正解探しに疲れたココロを休めて、
ここから整えていきましょう。
大きく変えるのではなく、小さく続けて効く関わりへ。
あなたとわが子の歩幅で、今日から始められます。
この3週間のサポートは、ADHDと暮らす毎日の土台を整えるための一つの方法です。
でも、
この記事ではサポートを受ける・受けないにかかわらず、
今すぐ自分で進められるヒントもまとめています。
まずは、
あなたの迷いがどこから生まれているのかを一緒に整理していきましょう。
ADHDの診断を受けたあと、
なぜ病院選びがこんなにも難しく感じられるのか――
その背景から見ていきます。
監修者
株式会社Osaka-Child所属 小児神経科医
- 名前: 三浦あすか
- 出身地: 兵庫県西宮市
- 最終学歴: 神戸大学医学部 小児科専攻
- 専門分野: 小児神経、DCD(協調運動障害)、発達性ディスプラクシア、HSP気質の子ども支援
- 職歴: 兵庫県立こども病院 小児神経センター勤務(11年)
専門分野について一言: 「できないことの奥にある『がんばっているサイン』を、もっと社会全体で受けとめていけたらと思っています。」
監修者
株式会社Osaka-Child所属 臨床心理専攻大学教授
- 名前: 森本哲夫
- 出身地: 奈良県
- 最終学歴: 米国ハーバード大学心理学部 博士課程修了
- 専門分野: 臨床心理学、発達心理学
- 職歴: ハーバード大学研究員(5年)、大阪大学人間科学部教授
専門分野について一言: 「心の成長とは、自己理解の旅でもあります。その旅のお手伝いができれば幸いです。」
「ADHD診断後の病院選び」で迷い続けているあなたへ
ADHDの診断を受けたのに、病院選びやその後の流れが見えず、不安と孤独を抱えていませんか?
発達外来・小児神経科・児童精神科…
ADHDに合う病院を選びきれず、診断後も「このままで大丈夫?」と迷いが続く。
ADHDの子どもにとっては「診断がゴール」ではなく、
「診断からの支援」こそが安心への第一歩。
でも、ADHDの病院選びを間違えると、
フォローが途切れ、母親のココロも揺さぶられます。
- 「わが子に合う病院はどこ?」
- 「どんな準備が必要?」
そんな疑問を整理することが、ADHDと向き合う母親のココロを軽くします。
「ADHD診断後の病院選びに迷い続け、不安と孤立を抱えていた母が、『安心して支えられる私』に変わっていく──3週間集中再安心サポート」は、
ADHDの診断後に必要な視点を、専門的に整理しながら「母親が一人で抱え込まない病院選び」を伴走するサポートです。
こんな方におすすめです
- ADHD診断後、どの病院に通えばよいか分からず不安が続いている
- 診断だけで終わらず、支援につながる病院を自信を持って選びたい
- 夫や家族にADHDの必要性を説明できる根拠を持ちたい
- 予約・待ち時間・連携体制など、病院選びの基準を整理したい
- 「迷う母」から「安心して選べる母」に変わりたい
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 2月9日(月)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと3名様限定』
※銀行振込限定・先着順
▶ ADHD診断後の病院選びを整理し、安心して支えられる母になる3週間へ
そして──
病院選びや診断後の流れを整えたあと、「母としての安心」だけでなく、「私自身のこれから」にも目を向けたい方へ。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
ADHDのある子を支えてきた経験を土台に、
母としても一人の女性としても「これからの生き方」を再設計する3週間です。
家族関係を落ち着かせながら、
「私らしい人生の軸」を取り戻していきます。
- ADHD子育てを通して価値観が揺らいだ
- 病院選びや支援導入が整ったあと、自分の人生に取り組みたい
- これからの選択に自信を持ちたい
このプログラムでは、
「ADHDのある子の母」という枠を超えて、
「私自身のために未来を選べる私」へ変わります。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
「ちゃんとしてるのに、苦しい」
「頑張ってるのに、うまくいかない」
——そんな違和感を抱えたまま、ずっと我慢していませんか?
LINEで3分セルフ診断ができます。
あなたの“今の感覚”の正体が、見えてきます。
9歳になっても続く困りごと──ADHD診断後、病院選びができずフォローが途切れた母親の悩み

ADHDの診断を受けたとき、
「これでやっと子どもの困りごとに合ったサポートが始まる」と感じましたよね。
けれど、
あれから9歳になった今も、
- 忘れ物や支度の遅さ、
- 宿題の終わらない夜
は減っていません。
学校からの連絡は増え、
家では叱る時間が長くなってきたと
あなたは感じています。
それでも
病院からは何の連絡もなく、
次の受診やフォローの案内もないまま。
「このままでいいの?」という不安は、
毎日の疲れと重なってココロの奥に沈んでいきます。
ポイント
ADHDの診断はゴールではなくスタートです。
あなたのように
病院からのフォローが途切れると、
母親は迷いと孤立の中で立ち止まったままになってしまいます。
ADHD診断後のフォローなしで深まる「このままでいいの?」という不安
ADHDと診断されたとき、
検査の結果や特性の説明は受けました。
けれど、
その後の通院や支援の予定がないまま
終わってしまっている方がほとんどです。
最初は
「きっとまた支えてくれる・また連絡してくれる」と信じていたのに、
何も変わらないまま数か月が過ぎる。
学校での困りごとが増えても、
どこに相談すればいいのかわからない。
ADHDの診断はスタートなのに、
フォローがないまま時間が経つと、
母親の不安は確実に膨らみます。
「このまま何もしなければ、できないことがもっと増える」という恐れが、
毎日の小さな出来事を重く感じさせます。
この不安は、
やがて
学校生活や家庭の空気にも
マイナス作用を与えていきます。
それは、
日々の学校生活での
「できないこと」が増える現実として現れてきます。
できないことが増えていく学校生活と母親の孤独感
ADHDの子どもは、
- 忘れ物や支度の遅れ、
- 指示を聞き逃す
といった困りごとが日常的に起こります。
9歳になると
- 授業のスピード
- 宿題の量、
- 友達との関わり方など、
求められることが増えていきます。
周りの子が自分で準備や計画を立てられるようになっていく中で、
うちの子だけが取り残されているように
見えてしまう瞬間がありますよね。
そのたびに先生から連絡が入り、
「また同じことが…」とため息をつく。
ADHDの特性による困りごとに向き合いながら、
相談できる場所もなく、
共感してくれる人も見つからない。
この孤独感は、
母親のココロを確実に削っていきます。
そして、
ふと「病院を変えたほうがいいのか」という考えが浮かび始めます。
その思いは、
次第に
「どこなら安心して通えるのか」という病院選びの迷いへと
つながります。
かかりつけの小児科では対応が難しいときに考える病院の選び方
ADHDの診断後も、
かかりつけの小児科でフォローしているご家庭は
多くあります。
けれど、
小児科は幅広い診療を行う場所で、
- ADHDの特性
- 学校生活の支援まで
深く対応するのは
難しい場合があります。
ポイント
9歳以降は、
- 学習
- 友人関係
- 自己管理
といった新しい課題が増えます。
こうした変化に対応するには、
- 小児神経科
- 児童精神科
- 発達外来など、
ADHDに詳しい医師とつながることが欠かせません。
病院によって
- 得意分野
- 支援体制、
- 学校との連携方法
は異なります。
ADHDの子どもに合うかどうかを軸に選ぶことが、
母親のココロの安心にもつながります。
迷いが長引くほど、
日常の困りごとは重なっていく。
だからこそ、
動けずにいる今こそ選択肢を整理し、
安心して一歩を踏み出せる形をつくることが大切です。
ADHDの診断や相談ができる病院と科の種類|選び方の前に知っておきたい基礎知識

ADHDの診断を受けたあと、
「この先、どこに相談すればいいのか」が分からず
立ち止まってしまうことがありますよね。
病院からの案内がなく、
次の受診も決まらないまま、
日常の子どものできないことだけが増えていく
──その状態が続くと、
病院選びはますます後回しになってしまいます。
だからこそ、
まずは
ADHDの診断や相談ができる
病院と科の種類を知っておくことが、
迷いから抜け出す第一歩になります。
知っているだけで「次の行き先」が見えやすくなりますよ。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「ADHDのことをもっと基礎から理解したい」
そんな方へ。症状や特徴を整理し、「責める毎日」を手放すヒントを専門家監修で解説しています。
👉 ADHDの基礎と子育ての悩みを整理して、安心の一歩を踏み出す
-

-
参考ADHDとは?子育てに限界を感じたあなたへ|「責める毎日」を手放すヒント【児童精神科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 朝から何度も叱って、 疲れ果てた夜。 寝顔を見るたびに、 「また怒りすぎた」と後悔ば ...
続きを見る
発達外来・小児神経科・児童精神科の特徴とADHD診断の流れ
「どこに行けばADHDを診てもらえるのか分からない」という不安は、
行動を止めてしまいます。
ADHDの診断や相談ができる場所は、
大きく分けて
- 「発達外来」
- 「小児神経科」
- 「児童精神科」
があります。
- 発達外来は発達特性の評価に特化し、ADHDの診断や学校生活での配慮について相談できます。
- 小児神経科は脳や神経の発達を専門的に診て、ADHDに必要な薬の処方や再評価も行います。
- 児童精神科はココロと行動の両面からADHDを診断し、情緒面のサポートも含めて伴走します。
診断の流れは、
- 問診
- 発達検査
- 行動観察
を経て結果と方針が伝えられる形が多いです。
ポイント
ADHDの特性を多角的に見てもらえる医療機関ほど、
その後の支援にもつながりやすくなります。
こうした特徴を知ることで、
「この先も安心して診てもらえる場所」が
選びやすくなります。
ADHD診断後も継続診療が可能な医療機関を選ぶメリット
ADHDは診断して終わりではなく、
成長とともに
見直しや調整が必要な特性です。
継続診療ができる病院とつながっていると、
- 学校生活での困りごと
- 家庭での行き詰まり
を、その都度ADHDの視点で相談できます。
次の受診日が決まっているだけで、
「今はここで話せる場所がある」
という安心感が生まれますよね。
ADHDの子どもは
年齢ごとに困りごとの形が変わるため、
同じ医師が長く関わってくれることは変化に対応でき、
すぐに現実に適応できますよね。
子どもも診察に慣れ、
安心して自分のことを話せるようになるので、
受診がスムーズになります。
では、
その病院を探すとき、
何を手がかりにすれば迷わず動き出せるのかを見ていきましょう。
病院ごとの特徴を理解し、主治医探しをスムーズに進める方法
ADHDを診る病院は、
同じ科名でも得意分野や支援体制が違います。
- ある病院は詳細な発達検査に強く、
- 別の病院は学校との連携が得意。
中には療育や支援機関の紹介を早く行うところもあります。
ポイント
主治医探しを始める前に、
「うちの子に必要なADHD支援は何か」を
整理しておくことが大切です。
- 診断書や発達検査の結果、
- 日常の行動記録
をまとめて持参すれば、
医師も状況を理解しやすくなります。
病院ごとの特徴を知り、
ADHDの特性と家庭の状況に合った場所を選ぶことで、
診断後の継続的な関わりができるようになります。
「ADHD診断後の病院選び」で迷い続けているあなたへ
「発達外来・小児神経科・児童精神科…どこに行けばいいの?」と
調べるほど混乱していませんか?
診断を受けたのにフォローがなく、不安のまま立ち止まってしまう母親はたくさんいます。
「ADHD診断後の病院選びに迷い続け、不安と孤立を抱えていた母が、「安心して支えられる私」に変わっていく──3週間集中再安心サポート」は、
「病院の種類を知っただけで終わらず、あなたと子どもに合う選び方」を一緒に整理していく伴走型サポートです。
ひとりで抱え込まず、3週間で「私の軸」を持った病院選びへ進んでみませんか?
ADHDの子どもの診断での病院の選び方の基準|改善につながるサポート体制を見極める
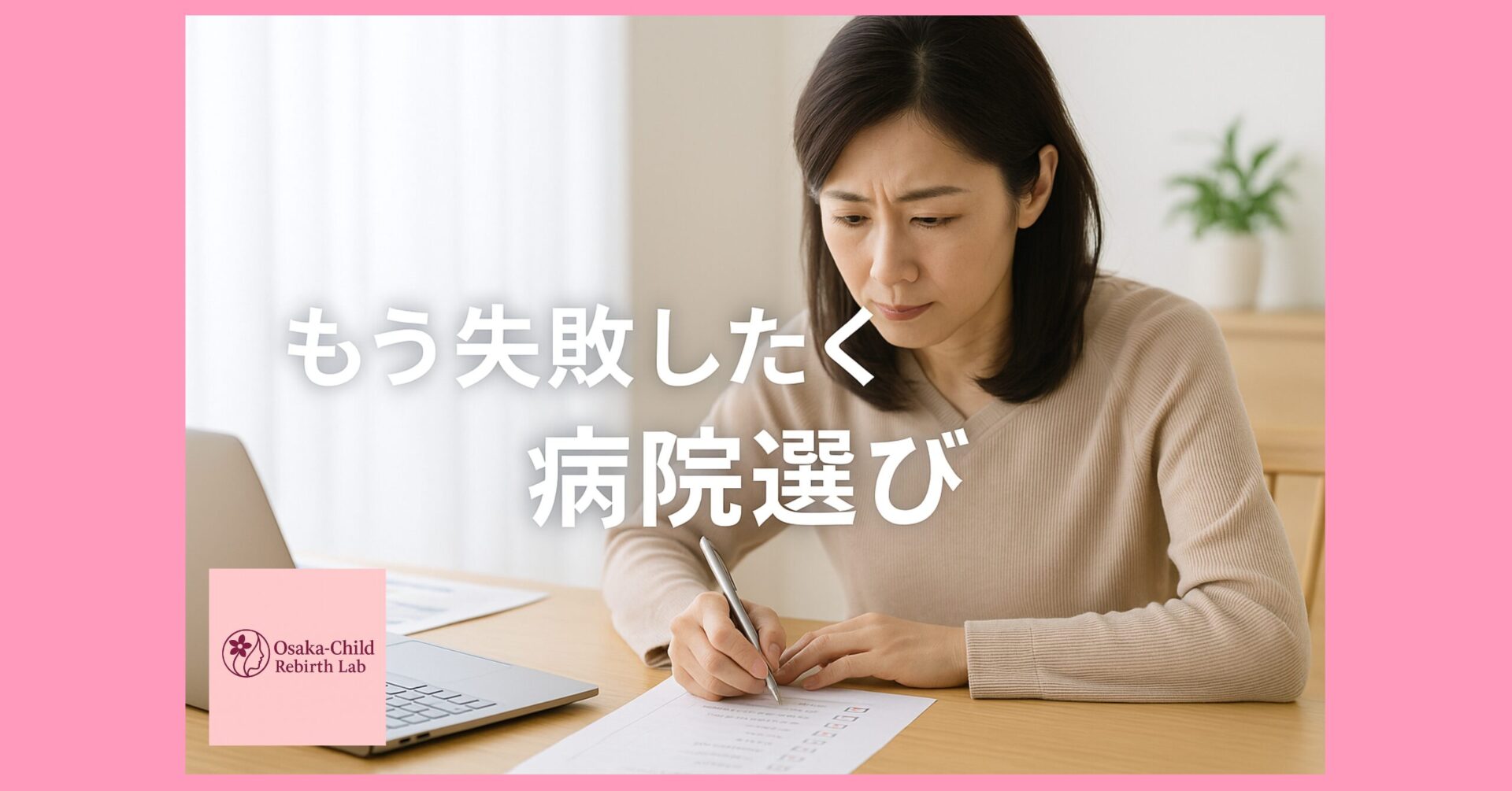
ADHDと診断されたあと、
「この病院で本当に前に進めるのか」を
見極める軸がほしくなりますよね。
診断だけで終わらせず、
ADHDのあなたの子どもに合った支援へつなぐには、
病院のサポート体制を具体的に確認していきましょう。
このキャプションでは、
迷いを減らして「動ける私」に変わるための基準を、
ひとつずつ整理します。
無料LINE診断|今のあなたに必要なサポートは?
「何から始めればいいかわからない…」そんなあなたへ。
LINEで「数字」を入力するだけで、今のあなたに合ったサポート商品を診断できます。
今すぐLINEに【 4 】の番号を入力してください。
「ADHD診断後の病院選びに迷い続け、不安と孤立を抱えていた母が、『安心して支えられる私』に変わっていく──3週間集中再安心サポート」の内容と、
「なぜ今のあなたに合うのか」が届きます。
学校や支援機関と連携できる病院を選ぶ理由
ADHDの診断後、
学校との連携がある病院を選ぶと、
毎日の子育ての負担が確実に軽くなります。
ADHDの配慮事項(宿題量・席の位置・声かけの頻度など)を、
病院が学校へ文書で伝えてくれると、
母親が説明役を背負い続けなくて済みます。
ADHDの理解が
教室側に広がると、
叱責が減り、
成功体験が増えます。
ADHDの子どもは環境の影響を強く受けるため、
「伝わる仕組み」があるだけで、
落ち着き方が変わります。
- 地域の支援機関(発達相談・放課後等デイなど)
- 定期的に情報共有する仕組みを持つ病院
もあります。
ADHD支援の輪がつながるほど、
母親は一人で抱え込まなくてよくなりますよね。
連携が整うと、
次にほしくなるのは「実際のサポート先」への段階です。
療育や発達支援を紹介してくれる医療機関かどうか
ADHDの診断後、
療育・発達支援への紹介が早い病院は、
その後のフォローをし続けてくれます。
ADHDの行動特性(不注意・多動・衝動)に合わせて、
実践的なトレーニング先を提案してくれる医療機関は
心強い存在です。
ADHD支援の紹介実績(紹介先の種類・待機期間・連携の頻度)を
受診時に確認しておくと、
子どものできない部分に対しての
改善アプローチがわかりやすくなりますよね。
家庭での困りごと(忘れ物・時間管理・感情の立て直し)を、
ADHD視点で療育へ橋渡ししてくれる医師は、
日常の改善スピードを上げます。
ADHDの再評価や方針見直しも
同じ窓口でつながると、
母親の動きが最小限になり、
余計な心配を抱えなくて良くなります。
紹介や体制が整っていても、
最後に大切なのは医師の「話しやすさ」です。
ADHD改善に向けた相談のしやすさと医師との相性
ADHDの診療は、
診断スタイルより「対話のしやすさ」が
あなたのADHDの子どもへの負担はだいぶん減らすことができます。
小さな違和感でも
遠慮なく伝えられる雰囲気なら、
ADHDの困りごと(宿題のつまずき、朝の支度、友だちトラブル)を
早めに調整できます。
初診・再診での質問に対し、
ADHDの視点で具体例を交えて返してくれる医師は、
家庭での再現性が高いです。
診察の最後に
「次回までの宿題(記録の付け方・試してみる声かけ)」を
提案してくれるかも、
相性を測るサインになります。
「聞いてもらえる」と感じられると、
- ADHDの再評価
- 薬の調整
- 学校への情報提供
もスムーズに依頼できます。
ポイント
診察室で
「この先生になら、今の葛藤をそのまま渡せる」と思えたら、
その病院が今のあなたと子どもに合う場所です。
ここで挙げた基準を手元に置けば、
次のキャプションで見ていく
「準備と持ち物(行動記録・質問リスト・検査結果)」が、
はっきり形になります。
動き出す準備を、一緒に整えていきましょう。
「ADHD診断後の病院選び」で行き詰まっているあなたへ
ADHDの診断を受けたあと、どの病院に通えばよいのか、情報が多すぎて迷っていませんか?
- 発達外来
- 小児神経科
- 児童精神科
──ADHDに合う病院は一つではなく、特徴を整理しないまま選ぶと「診断だけで終わる」不安につながります。
ADHDの診断後に必要なのは「次の一歩」を整理すること。
どの病院を選び、どんな準備をして受診するかで、支援につながるかどうかが大きく変わります。
不安のまま動くのではなく、ADHDの病院選びを一緒に整える3週間で、安心と行動力を取り戻しませんか。
「ADHD診断後の病院選びに迷い続け、不安と孤立を抱えていた母が、『安心して支えられる私』に変わっていく──3週間集中再安心サポート」は、
ADHDの病院選びを具体的に整理し、家族との温度差を埋めながら、自信を持って動き出せるよう伴走するプログラムです。
こんな方におすすめです
- ADHD診断後、どの科・どの病院に通えばよいか判断できない
- 診断だけで終わらず、学校や支援につながる病院を選びたい
- 夫や義母にADHD受診の必要性を根拠をもって説明したい
- 受診準備(困りごとメモ・行動記録)を整えて診察を活かしたい
- 迷い続ける状態から抜け出し、「安心して選べる母」に変わりたい
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 2月9日(月)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと3名様限定』
※銀行振込限定・先着順
▶ ADHD診断後の病院選びを整理し、不安を安心に変える3週間へ
そして──
病院選びや診断後の流れを整えたあと、
「母としての安心」に加えて、「私自身の人生」を見つめ直したい方へ。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
ADHDのある子を支えてきた経験を土台に、
母親としても女性としても「これからの生き方」を再設計する3週間です。
家族を支えながらも、
自分の人生を選び取る視点を取り戻していきます。
- ADHD子育てを通じて価値観が揺らいでいる
- 病院選びや支援導入が整ったあと、自分の人生に向き合いたい
- これからの選択に自信を持ちたい
このプログラムでは、
「ADHDのある子の母」という枠を超えて、
「私自身の未来を選べる私」へと進んでいきます。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
ADHD診断後の病院選びで重要な「医師との相性」

診断を受けたあと、
フォローがなくて
気持ちが宙ぶらりんになったままの日々。
ADHDの子どもと向き合う毎日は、
ただでさえ迷いが多いのに、
病院の診察室でまで肩に力が入ってしまう。
「もっと話せたらよかったのに…」
そうやって帰り道でため息をついたこと、
ありますよね。
医師との相性は、
ADHDの治療や支援の内容だけでなく、
母親の安心感にもダイレクトに関係します。
ここからは、
相性を見極めるための大切な視点を整理していきます。
無料診断|あなたの“病院選びの基準”を知る
「ADHDの診断後、どの病院が良いのか迷い続けてしまう…」
そんな方のために、LINEで「キーワード」を送るだけで診断できるサービスをご用意しました。
LINEに「ADHD 診断 病院 選び方」と入力して送信してください。
あなたに合った視点と、次の一歩の決め方をすぐにお届けします。
信頼できる医師に出会うためのチェックポイント
ADHDの診断後、
最初に通う病院で
「信頼できる」と感じられるかどうかは、
その後の支援の質を大きく左右します。
- 診察室で、こちらの話を途中で遮らず最後まで聞いてくれるか。
- ADHDの症状や日常の困りごとを、「それはよくあることだから」と片付けずに、背景や理由を説明してくれるか。
そして何より、
「この先生にならADHDの相談を続けられる」と
ココロから思える雰囲気があるか。
信頼は専門知識だけでは生まれません。
母親の不安や疲れを受け止め、
現実に沿ったアドバイスをくれるかどうかで決まります。
話をしやすい雰囲気と質問への丁寧な回答があるか
ADHDの診断後は、
学校生活や家庭でのできないことが、
少しずつ形を変えて現れてきます。
だからこそ、
何でも聞ける雰囲気を持つ医師が、
あなたの子育てを楽にしてくれる。
質問したとき、
「そんなに気にしなくて大丈夫」ではなく、
「それはADHDの特性からこういう理由があるんですよ」と、
- 納得できる説明をしてくれるか。
- 母親の視点に立って、困りごとを一緒に整理し、次の行動までイメージさせてくれる答え方をしてくれるか。
質問を重ねても、
丁寧に時間を割いて向き合ってくれる医師なら、
長く安心して通院できます。
初診時に確かめたい継続診療や再評価の体制
ADHDは診断が終わりではありません。
成長や生活環境の変化に合わせて、
- 支援内容
- 薬の見直し
が必要になります。
だからこそ、
初診の時点で
- 「継続して診てもらえる体制があるか」
- 「定期的な再評価ができるか」
を必ず確認しておきたい。
中には、
ADHD診断後に
学校や支援機関との連携まで
行ってくれる病院もあります。
一方で、
診断だけで終わってしまい、
その後のフォローが全くないケースがほとんど。
母親が安心して通える場所を見つけるためには、
この体制の有無を最初に確かめることが、
後悔しない病院選びの適切な選択となります。
通いやすく続けやすいADHD診断後の病院選び
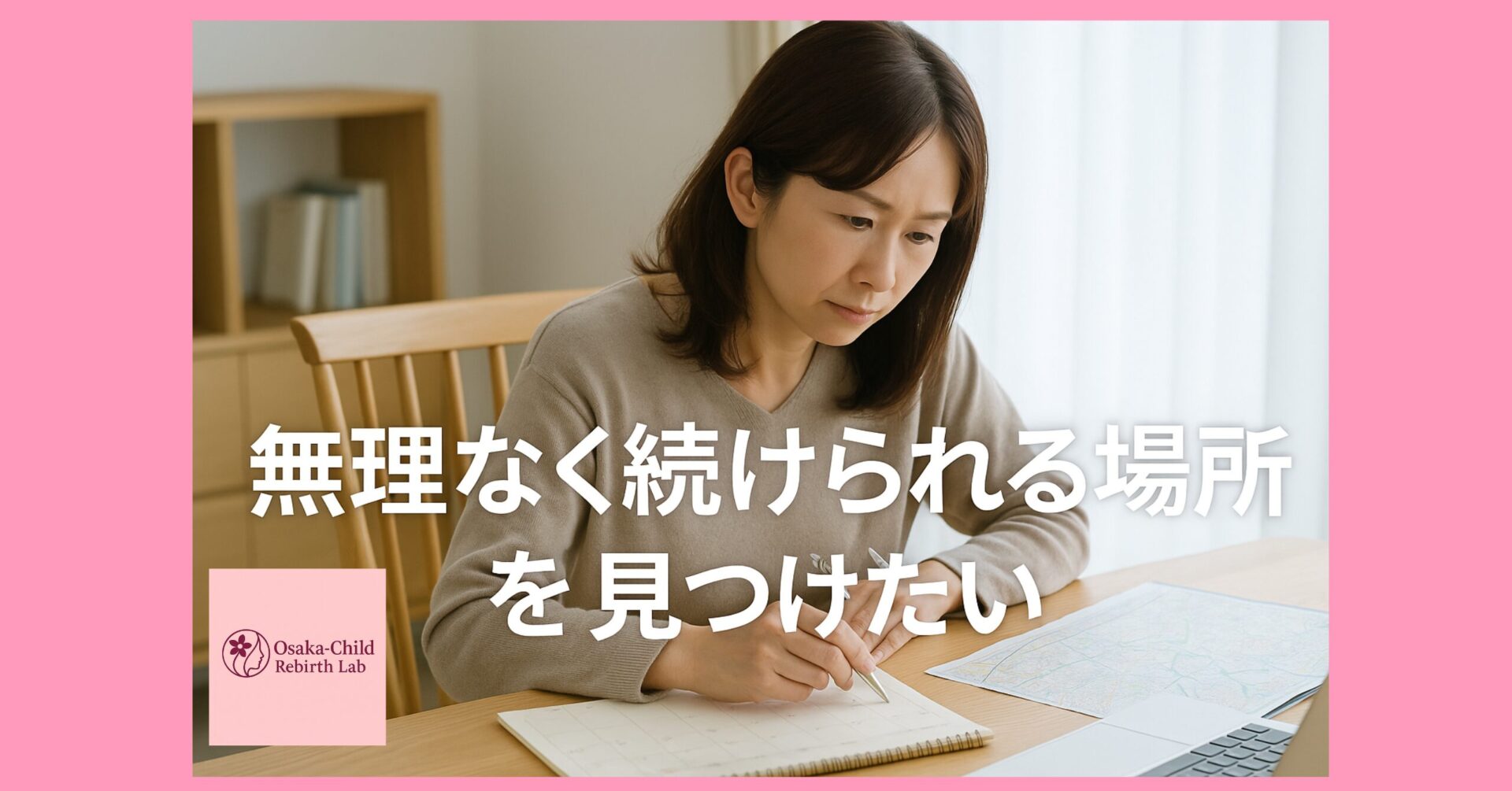
診断を受けたあと、
「ここからサポートが続くはず」と信じていたのに、
通院が負担になってくると、
その安心も揺らいでしまいますよね。
ADHDの診断後は、
- 薬の調整
- 経過観察
- 学校との情報共有などで、
病院に通う機会が何度も訪れます。
だからこそ、
無理なく通い続けられる環境を選ぶことは、
支援を長く続けるための大事な条件です。
このキャプションでは、
通いやすさを見極めるための具体的な視点をお伝えします。
予約しやすく待ち時間が少ないかどうかを見極める
ADHDの診断後、
予約がなかなか取れない病院では、
困りごとが積み重なったまま
次の受診を迎えることになります。
数週間も待つあいだに、
学校や家庭でのトラブルが増えてしまい、
母親であるあなたのココロもすり減っていきますよね。
さらに、
受診当日に長時間待たされると、
ADHDのある子は
- 集中力が切れやすく、
- 落ち着かない時間
が増えます。
母親も気力と体力を消耗します。
- 「予約がスムーズに取れるか」
- 「急な変更に柔軟に対応してくれるか」
──これらは診断後の通院を続けるうえで欠かせない条件です。
家からの距離・通院頻度・アクセスのバランス
ADHDの診断後は、
数か月ごとの再診や経過観察が続きます。
家からの距離が近ければ便利ですが、
それだけで選ぶと、
支援の質や医師との相性を見落としてしまいます。
電車やバスで通う場合は、
乗り換えの有無や混雑の時間帯も
子どもにとって大きな負担です。
車で通うなら、
駐車場の有無や停めやすさも重要な条件です。
「少し遠くてもADHDに詳しい先生のもとで、安心して診てもらえる」
──このバランスが取れる病院を選ぶことで、
通院を無理なく続けられます。
複数の病院を比較して自分と子どもに合う選び方をする
ADHDの診断後、
最初に決めた病院がすべてではありません。
相性や通いやすさを確かめるために、
複数の病院を比較してみることも一つの方法です。
病院ごとに、
- 診察の進め方や説明の仕方
- スタッフの対応
- 院内の雰囲気
は大きく異なります。
- 「ここならADHDのことを落ち着いて話せる」
- 「子どもが嫌がらず通える」
──そう感じられるかが大切です。
比較する過程そのものが、
「この病院なら安心して続けられる」という
確信を持つきっかけになります。
ADHD診断後の受診をスムーズにする準備
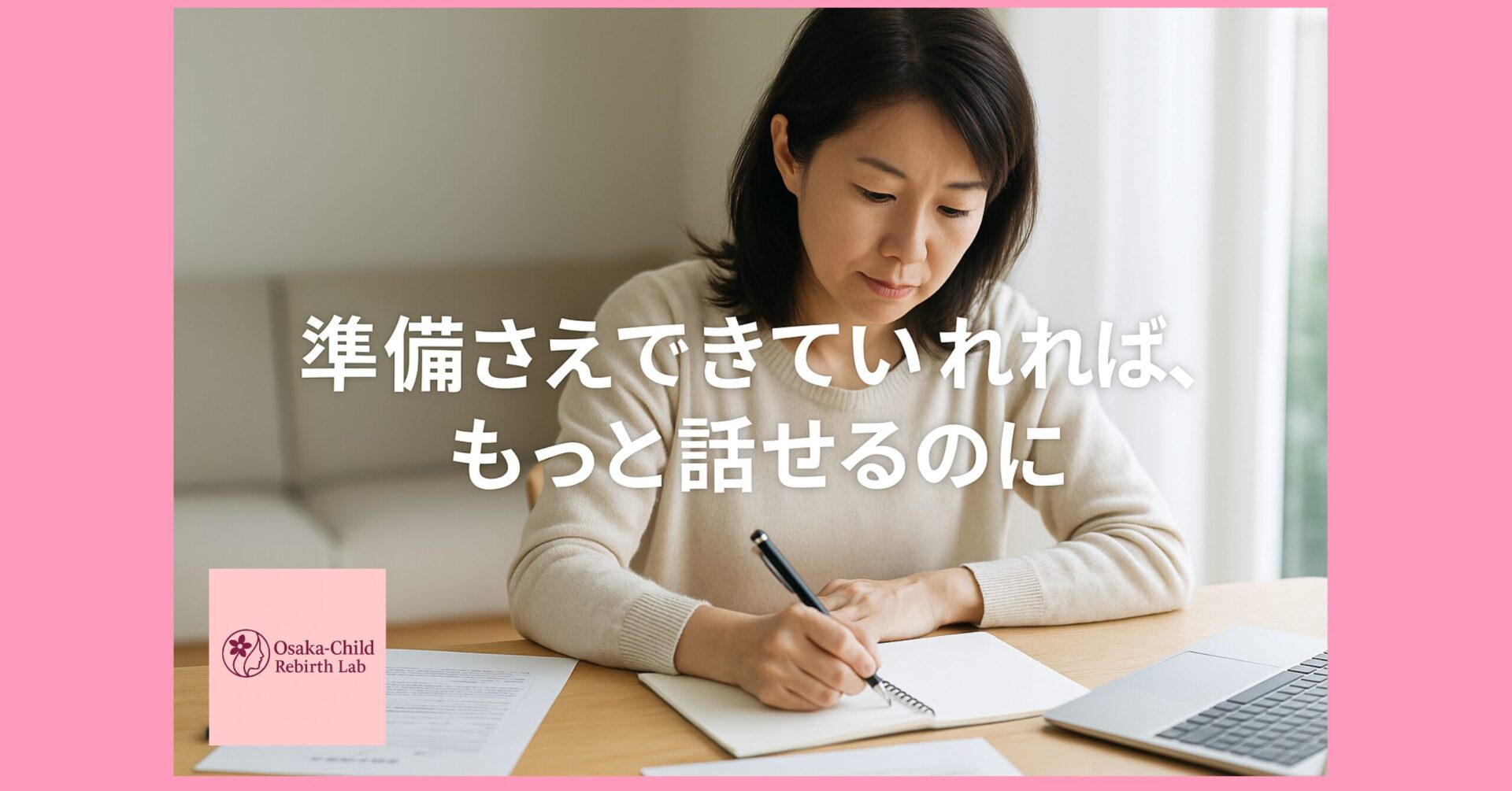
診断を受けたとき、
「これで少しは安心できる」と思ったのに、
実際の受診ではうまく話せず、
帰り道でモヤモヤが残る。
そんな経験をあなたは重ねてきました。
ADHDの診断後は、
- 日常の小さな困りごと
- 子どもの行動の変化
を、限られた診察時間でしっかり伝えることが大切です。
そのためには、
受診前の準備が
- 母親の安心にも、
- 支援の精度にも
つながります。
このキャプションでは、
今日から始められる
ADHDを再度受診する際の3つの準備方法をお伝えします。
困りごとや行動の記録をどうまとめるか
ADHDの診断後、
日々の出来事はその瞬間は鮮明でも、
受診の日になると順序があいまいになったり、
抜け落ちたりしがちです。
その結果、
本当に伝えたかった困りごとが
話せず終わることもありますよね。
おすすめは、
ADHDの行動や出来事を
- 「起きた日」
- 「どんな状況だったか」
- 「子どもの反応」
- 「そのときの気持ち」
この4つに分けて短く書き留めること。
- 「朝の着替えに30分かかった」
- 「宿題を始めても机に座れず歩き回っていた」など、
具体的に残しておくと、
医師がADHDの特性と生活の様子を正確につかめます。
その記録が、
次の支援や対応策を変えるきっかけになります。
受診時に持参すると役立つ書類や発達検査の結果
ADHDの診断後でも、
- 発達検査の結果
- 学校からの記録
は、診察をより有意義にする材料です。
過去の資料も含め、
医師が見返せるように毎回持参することが、
診察の質を高めます。
- 学校の支援計画
- 先生からのコメント
- 日々の連絡帳など
は、家庭だけでは見えない子どもの様子を補ってくれます。
ADHDは生活や環境の影響を受けやすいため、
医師に両方の情報を届けることが、
その後の支援内容や方針の精度を上げます。
すべてを一つのファイルやクリアケースにまとめておくと、
診察室で慌てずに取り出せます。
初診や再診で活用できるメモの作り方
ADHDの診断後は、
- 学校や家庭での変化、
- 薬の効果や副作用、
- 困りごとなど、
話したいことが一度に押し寄せます。
そのまま受診すると、
順序が混乱して大事なことを聞きそびれることがありますよね。
受診メモには、
まず「今回一番聞きたいこと」を一行で書き、
その下に具体的な出来事や相談内容を箇条書きにします。
ADHDの話題は、
症状や行動だけでなく、
- 子どもの感情
- 家庭の空気の変化
も入れると、
医師が全体像を理解しやすくなります。
このメモがあるだけで、
短い診察時間でも必要なことを漏らさず話せて、
診断後の支援がスムーズに進みます。
「受診準備はできたのに、不安が消えない」あなたへ
- 「行動記録もメモも準備したけれど…」
- 「本当にこの病院でいいのかな?」
──受診前の母親が一番揺れるのは「決断の瞬間」です。
「ADHD診断後の病院選びに迷い続け、不安と孤立を抱えていた母が、「安心して支えられる私」に変わっていく──3週間集中再安心サポート」は、
準備した内容をもとに、医師との会話や病院選びの軸を一緒に確認し、安心して一歩を踏み出せる状態へ整えます。
もう「このままでいいの?」と悩み続けなくて大丈夫です。
迷いを整理し、最適な病院選びへ導く3週間集中再安心サポート

ADHDの診断を受けたのに、
その後のフォローがなくて…。
小3になった今も
- 忘れ物、
- 支度の遅さ
- 宿題の終わらなさ
が続くと、
「私の関わり方が間違っているのかな」と
胸が締めつけられますよね。
ADHDの病院選びをしようと思っても、
- 発達外来
- 小児神経科
- 児童精神科…
どれが合うのか判断できない。
気づけば、
ひとりでスマホを握りしめて夜中まで検索している自分がいる。
この3週間のサポートは、
まずあなたのココロを整えるところから始まります。
ポイント
ADHDの子どもへのスムーズな対応は、
母親のココロが立て直されてから。
迷いと不安を少しずつ手放し、
最終的に「この病院で相談してみよう」と思える状態へ導きます。
フォローなしの状況から抜け出し、安心できる相談先を持つ
ADHDの診断後に病院のフォローがないと、
毎日が手探りで不安に飲み込まれますよね。
どこに相談すればいいか分からないまま時間だけが過ぎ、
ADHDの困りごとが増えていくと、
「私がもっと頑張れば良かったのかも」と、
自分を責めてしまう。
このサポートの
最初の2週間は、
ADHDの子どもへの指導や療育よりも、
あなたのココロだけに向き合います。
診断後に動けなかった理由や、
抱えてきた孤立感を一緒に整理し、
責める思考から解放される時間をつくります。
本音を安心して話せる相談先ができることで、
ADHDとの向き合い方を考える余裕が少しずつ戻ってきます。
病院選びの迷いを解消し、自信を持って決められるように
ADHDの子どもの病院選びは、
ただ口コミを調べても決められませんよね。
- 発達外来
- 小児神経科
- 児童精神科、
それぞれの特徴や得意分野、医師の姿勢…。
このサポートでは、
あなたと子どもに合う病院を選ぶ基準を一緒に作ります。
比較表や質問リストを使って、
ADHD診断後の条件整理を進めると、
「どこも同じ」に見えていた病院の違いがはっきりしてきます。
選択の軸が定まることで、
「ここで相談してみよう」と自信を持って動き出せるようになります。
母親のココロを整え、ADHDの子どもに合った支援へつなげる
3週目になる頃、
あなたのココロが安定し、
ADHDの子どもの行動が落ち着いて見える瞬間が増えます。
叱るよりも
「どう支えられるかな」という視点が自然に湧く。
このタイミングで、
ADHDの行動記録や困りごとメモを整理し、
医師や学校との相談準備を整えます。
信頼できる医師とつながり、
- 家庭
- 学校
- 医療
が一つのチームとして動き出すと、
「診断後、何も変わらなかった日々」が
「支援が動き出す日々」に変わります。
この流れを3週間で一緒に進めるのが、
「ADHD診断後の病院選びに迷い続け、不安と孤立を抱えていた母が、『安心して支えられる私』に変わっていく──3週間集中再安心サポート」です。
「母親の安心」を取り戻す3週間の伴走サポート
- 困っているのに、どこにも当てはまらない感覚。
- ADHDの診断は受けたのに、病院からのフォローはなく、学校からも具体的な提案がない。
- 夫には「そんなに気にしなくても」と言われ、義母には「しつけの問題」と片づけられる。
それでも日々は続き、
- 忘れ物
- 準備の遅さ
- 宿題の滞り
に向き合いながら、
「私がもっと頑張れば良かったのかも」と
あなたは自分を責めてきました。
そんな状態では、
病院や支援先を探そうと思っても、
頭とココロがもう動かないですよね。
発達外来、小児神経科、児童精神科…名前は知っていても、
- それぞれ何が違うのか、
- 何を基準に選べばいいのか
が分からない。
だからこそ、
この「3週間集中再安心サポート」は、
まず母親のココロを整えることから始めます。
診断名や支援内容を理解する力も、
安心できる土台があってこそ育っていくのです。
STEP①|気づき
最初の1週間は、
ADHDの子どもへの関わりではなく、
あなた自身のココロにだけ焦点を当てます。
今の不安やモヤモヤを言葉にし、
頭の中でぐるぐるしていた感情に名前をつけます。
「診断後に動けなかったのは、情報がなかったから」と
いう事実を確認することで、
自責のループから少しずつ抜け出せます。
ここでは、
感情を整理するためのシートや会話を通して、
「病院選び=子どものため」から
「まずは私の安心のため」という軸を持てるようにします。
STEP②|実践
2週目は、
母親としての
- 価値観
- 生活リズム
を大切にしながら、
病院選びの基準を整えます。
発達外来、小児神経科、児童精神科など、
それぞれの特徴や得意分野を整理し、
あなたと子どもに合う条件を明確にしていきます。
- 距離や予約の取りやすさ、
- 医師との相性
- 学校や療育との連携体制…。
これらを比較できる表を一緒に作り、
迷いの原因をなくしていきます。
また、
この週では「子どもを責めずに過ごせた瞬間」を一緒に振り返ります。
例えば、
- 朝の支度で怒らずに声かけできた日や、
- 宿題の途中で笑い合えた時間。
こうした経験が積み重なると、
「病院選びは子どもを助けるためだけじゃない。私が穏やかでいるためにも必要なんだ」と
実感できるようになります。
STEP③|軸の再構築
3週目になる頃には、
ココロの緊張がほどけてきます。
そうなると、
不思議なくらいADHDの子どもの行動が
落ち着いて見える瞬間が増えます。
叱る前に
「どう支えられるかな」という視点が自然に出てきて、
関係の空気が変わります。
このタイミングで、
行動記録や困りごとメモを事実ベースで整理します。
評価やジャッジではなく、
- 「この時間帯は集中が切れやすい」
- 「宿題の前におやつを食べるとスムーズ」など、
支援に直結する情報に変えていきます。
そして、
医師への相談内容を決め、
初診時の会話シミュレーションを行います。
ここまで準備が整えば、
「この病院に行ってみよう」という気持ちが迷いよりも大きくなります。
サポート中の母親の変化
- 「私が悪い」という思考が和らぎ、安心できる時間が増える
- 孤立感が減り、感情が爆発する頻度が少なくなる
- 病院選びの軸が明確になり、自信を持って判断できる
- 家族にも落ち着いて話せるようになり、協力が得られやすくなる
子どもの変化(母親の変化に伴って)
- 家庭での表情や声かけが柔らかくなり、安心感が増す
- 責められる回数が減り、自分を受け入れてもらえる経験が増える
- 学校・家庭・医療の対応がつながり、一貫したサポートが受けられる
- 自己肯定感が少しずつ回復していく
このサポートは、
最初から子どもへの対応を詰め込むのではなく、
まず母親の回復を優先します。
母親が安心を取り戻すことで、
ADHDの子どもへの見方が自然に変わり、
必要な支援や病院選びも迷わず進められるようになります。
あなたが安心できることが、この子の安心につながっていきます。
その一歩を、ここから一緒に始めませんか。
今の不安を「安心の行動」に変える3週間──まずは私の心を整える
ADHDの診断は受けたのに、病院のフォローがなくて止まっていた時間。
「ADHD 診断 病院 選び方」で検索してきた今が、安心を取り戻すはじまりです。
- 「叱ってばかり」
- 「夜にひとりで検索を続けてしまう」
- 「家族に説明しきれない」
——その重さをいったん降ろして、まず「母である私の安心」を整える3週間を一緒に歩きます。
「ADHD診断後の病院選びに迷い続け、不安と孤立を抱えていた母が、『安心して支えられる私』に変わっていく──3週間集中再安心サポート」
- 1週目:不安・孤立・自責を受け止め、言葉にして軽くする
- 2週目:価値観に合う病院選びの基準づくり(発達外来/小児神経科/児童精神科の整理、質問リスト作成)
- 3週目:行動記録の整えと受診準備、学校連携まで「安心して動ける」形に
診断名より先に、「私の安心」を整える。
そこから、ADHDの子どもの反応が自然に見えて、受け入れられる日常へ。
まとめ|「診断で終わらせない」と決めた夜から
ADHDと診断された日、
少しだけ安心したのに
その夜にはもう、次の不安が胸をしめつけていましたよね。
- 「このまま放っておいたら、わが子はどうなるんだろう」
- 「どの病院なら、ADHDのことをちゃんとわかってくれるんだろう」
そうやってスマホを握りしめ、
深夜までスクロールしてきました。
病院選びは、
ただの「場所探し」じゃありません。
ADHDと向き合う日々を、
安心と支援につなげてくれる
これからの暮らしの土台になるからです。
ここまでで見えてきた、後悔しないための視点は――
この記事で分かったこと
- ADHD診断後も継続的にフォローできる医師・科を選ぶこと
- 小児神経科・児童精神科・発達外来などの違いと特徴を知って比べること
- 学校や支援機関とつながりやすい体制があるかを確かめること
- ADHDの行動記録や困りごとメモを準備して診察に臨むこと
- 医師との相性や話しやすさを大切にすること
ADHDの診断を受けたあと、
病院選びも関わり方も止まったまま。
夜中にスマホを見ながら、
「この子のために何を選べばいいのか」がわからず、
気づけば同じ記事を何度も読み返していた。
怒ってしまう日も、
守りたかったのは本当はこの子の安心だったのに──。
「ADHD診断後の病院選びに迷い続け、不安と孤立を抱えていた母が、『安心して支えられる私』に変わっていく──3週間集中再安心サポート」は、
そんな立ち止まってしまった時間を、行動に変えていくための伴走です。
- 1週目は、誰にも言えなかった不安や孤立、自責感をすべて受け止めます。
「診断後に動けなかったのは、あなたのせいじゃない」という事実を共有し、まずは心を守る状態をつくる。焦りや苛立ちなど、ADHDと暮らす中で積もってきた感情を整理し、「病院選び=子どものため」ではなく「私の安心のため」という軸を持てるようにします。 - 2週目は、母親自身の価値観と生活に沿った選び方を明確にします。
ADHDに合う病院を探す前に、「何を優先するか」の判断基準を一緒に整理。朝の支度や宿題時間など、日常で責めずに過ごせた小さな瞬間を振り返りながら、家族への説明方法も練習し、協力を引き出す言葉を持ちます。 - 3週目は、落ち着いたココロでわが子のADHDの姿を見つめ直す時間。
行動記録や困りごとを評価ではなく事実としてまとめ、医師に相談したい要点を整理。初診や再診での会話をシミュレーションし、病院選びとその後の行動(受診・学校連携)を具体化します。
この3週間で、
ココロの中にあった「私が悪い」という思い込みがほどけ、
迷いが減り、
家族に落ち着いて話せるようになります。
そして、
ADHDの困りごとを冷静に見て
「この関わりが合いそう」と根拠を持てる状態へ。
その変化は子どもにも届きます。
責められる回数が減り、
受け入れられる安心感が増え、
ADHDのある日常が少しずつ整っていく。
正解を急ぐのではなく、
あなたとわが子に合う関わりを、一緒に試しながら育てていける時間です。
「ADHD診断後の病院選びで積み重なった迷いと不安」をこのままにしない私へ
- 「ADHDの診断を受けたのに、病院選びで迷い続けている」
- 「発達外来・小児神経科・児童精神科…どこに行けば安心できるのか決められない」
──この記事で「ADHD診断後の流れや病院の違い」が少し整理できた今こそ、
母親としてのココロを整え、悠斗に合う一歩を踏み出すタイミングです。
「ADHD診断後の病院選びに迷い続け、不安と孤立を抱えていた母が、「安心して支えられる私」に変わっていく──3週間集中再安心サポート」は、
ADHDの病院選びを一緒に整理し、診断後も安心して支援につなげていくための伴走型サポートです。
こんな方におすすめです
- ADHD診断後、病院や科を選べず不安が続いている
- 診断で終わらず、支援や学校連携に進める病院を見つけたい
- 夫や義母にADHDの必要性を根拠をもって説明したい
- 孤立感や自責から抜け出し、安心して選べる母になりたい
- 「この子に合うサポートは必ずある」と確信して関わりたい
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 2月9日(月)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと3名様限定』
※銀行振込限定・先着順
ネットバンキングのご利用で、今すぐ開始することが可能です。
▶ ADHD診断後の病院選びを整え、安心して動き出す3週間へ
そして──
病院選びや診断後の不安を整えたあとは、
「母親としての私」だけでなく、「私自身のこれから」にも目を向けてみませんか。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
ADHDの子育てを通して得た気づきを土台に、
家族の安心と自分の人生を両立させるための3週間です。
母としても、妻としても、そして「私」としても、納得して歩める未来を描いていきます。
- ADHD子育てを経て、価値観が揺らぎ「自分」を見失いかけている
- 家族の安心を整えたあと、自分自身の生き方を再構築したい
- これからの10年を、自分の選択に自信を持って進みたい
このプログラムでは、
「家族のためだけに動く私」から、
「自分の未来を選び取れる私」へ変わっていきます。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
すでに診断済みの方も、そのまま詳細ページへ進めます。
あなたの心と体に合ったサポートを、今すぐ確認してみてください。








