
何度言っても伝わらない。
「さっきも言ったよね?」が、口癖になっていた。
それなのにまた怒ってしまって、
「また傷つけてしまった」と
夜中にひとりで落ち込んでいた。
ADHDと診断されたとき、
「やっと理由がわかった」と安心していたのに。
でも、
それだけでは説明できないこの子の反応に、
ずっとひっかかってきた。
- 予定が変わると泣き出したり、
- 言葉をそのまま受け取ってしまったり。
「なんでわかってくれないの?」って、
怒った自分に傷ついていたのは、
誰よりも、この子だったんだろう。
学校では「マイペースな子」で済まされても、
家では、どうしても気になってしまうズレや反応。
その違和感に気づけていたからこそ、
「ADHDだけじゃない気がする」と、
あなたは思い始めていたのです。
それでも、
「また新しい診断をつけるの?」と夫に言われるのが怖くて、
誰にも言えずに、
スマホだけが寄り添ってくれる時間が続いていた。
検索しては閉じて、また別のページを開く夜──
この記事は、
「ADHDと診断されたのに、それだけでは説明がつかない」と感じてきた母親であるあなたに向けて、
ADHDとASDの違い・重なり・伝わり方のズレを整理し、
今の関わり方を見直す視点を届けるために書いています。
この記事では、以下の5つの視点を整理していきます。
この記事を読むとわかること
- ADHDとASDが「どこで重なり、どこで違うか」を感覚レベルで理解する
- 「この関わり方じゃうまくいかない理由」に気づく
- 支援が届かなかった背景にある「視点のズレ」を整える
- 「わかってほしかった」子どもの気持ちに気づけるようになる
- 「この子に合った関係」を、母として少しずつ整えていけるようになる
こうして視点を整理できたとしても、
「じゃあ、どう関わればいいの?」という答えは、
すぐには見つかりませんよね。
頭ではわかっていても、
日常の中ではうまく伝えられず、
結局また怒ってしまった…
そんな日が、これまで何度もありましたよね。
怒ってばかりの毎日に、
「なんで伝わらないんだろう」とずっと悩んできた。
ADHDのことは調べていたし、関わり方も変えたつもりだった。
それなのに、
- 癇癪はおさまらず
- 会話はかみ合わなくて、
「きっとわたしが間違ってる」と、
自分ばかり責めていた時間がありましたよね。
だけど本当は、
ADHDだけでは届かない「違い」があっただけなんです。
この子には、この子の受け取り方や感じ方がある。
そのことに気づいた今だからこそ、
あなたと子どもとの関係を整えていくための「次のステップ」が必要です。
そんな母親に向けたのが、
「ADHDと診断されたのに、それだけでは説明できなかった子どもの『違い』に悩んでいた母が、特性を見つめ直し、安心して関われるようになる──3週間集中再安心サポート」です。
このサポートでは、
- Week1で、「ADHDの関わり方では噛み合わなかった理由」を整理します。「この子の見え方」「伝わらなさの背景」を、やさしく言葉にしていく時間です。
- Week2では、ASD的な視点も取り入れた関わり方を一緒に整えていきます。予定変更が苦手な子への声かけ、感覚的なこだわりへの対応、ズレて見える反応を「理解の違い」として捉え直す実践を進めます。
- そしてWeek3では、「どう伝えるか」より「どう届くか」へ。「ちゃんと見てるよ」「わかってきたよ」と伝えられる関係を、日々の中で少しずつ育てていく時間になります。
この3週間を通して、
母親の「モヤモヤしていた視点」が整理されていき、
「この子の関わりに、これでいいんだ」と、安心して向き合える感覚が育っていきます。
正解を探すのではなく、
「この子に合った関わり方を、一緒に見つけていけばいいんだ」と思えたとき、
母と子の間に、確かな「信頼の通り道」が生まれ始めます。
この子を「理解したい」と願ってきた気持ちは、
ずっと消えずに、ここまで歩いてきました。
その想いがあるからこそ、
最初に気づいた
「ほんの小さな違和感」に、もう一度、目を向けてみてください。
そこに、この関係を整えていく第一歩があります。
監修者
株式会社Osaka-Child所属 小児神経科医
- 名前: 三浦あすか
- 出身地: 兵庫県西宮市
- 最終学歴: 神戸大学医学部 小児科専攻
- 専門分野: 小児神経、DCD(協調運動障害)、発達性ディスプラクシア、HSP気質の子ども支援
- 職歴: 兵庫県立こども病院 小児神経センター勤務(11年)
専門分野について一言: 「できないことの奥にある『がんばっているサイン』を、もっと社会全体で受けとめていけたらと思っています。」
監修者
株式会社Osaka-Child所属 臨床心理専攻大学教授
- 名前: 森本哲夫
- 出身地: 奈良県
- 最終学歴: 米国ハーバード大学心理学部 博士課程修了
- 専門分野: 臨床心理学、発達心理学
- 職歴: ハーバード大学研究員(5年)、大阪大学人間科学部教授
専門分野について一言: 「心の成長とは、自己理解の旅でもあります。その旅のお手伝いができれば幸いです。」
「ADHDだけじゃないかも…」と感じ始めたあなたへ
ADHDの診断を受けたのに、
「なんだかそれだけじゃ説明できない」と感じていませんか?
- 冗談が通じない
- 予定変更でパニック
- こだわりが強すぎる。
そんな「ASD的な特性」が見えてきて、あなたは戸惑っていますよね。
- ADHDの特徴
- ADHDの支援
- ADHDとASDの違い
調べれば調べるほど、「うちの子はどこに当てはまるの?」と
余計にわからなくなってしまう検索の夜。
でも本当は、「この子に合った関わり方が知りたい」だけだったはずです。
「ADHDと診断されたのに、それだけでは説明できなかった子どもの『違い』に悩んでいた母が、
特性を見つめ直し、安心して関われるようになる──3週間集中再安心サポート」は、
ADHDとASDが重なって見える子どもに、
「今ここでできる関わり方」を整えるためのサポートです。
こんな方におすすめです
- ADHDの支援を受けているけれど、噛み合わない場面が多い
- ASDの可能性にも気づいているが、怖くて見ないふりをしてきた
- ADHDとASDの違いを調べても、結局よくわからず混乱してしまう
- この子に必要な「見え方・伝え方・安心の土台」を整えたいと思っている
- 「母親の直感」を信じていいのか、不安になっている
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 2月2日(月)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと3名様限定』
※銀行振込限定・先着順
▶ ADHDとASDの「違い」に悩んだ母が、安心して関われるようになる3週間へ
そして──
「母親としての私」を整えたあと、
「わたし自身のこれから」を考えていきたいと感じたあなたへ。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
ADHDの子どもとの関係を整理した先に、
「自分の人生」を見つめ直すための3週間です。
母であることも、妻であることも大事だけど、
「私の時間」も大切にしたい──
そんな思いを応援する再出発のプログラムです。
- ADHDの子育てを通じて、自分と向き合うようになった
- 「家庭だけの毎日」に、そろそろ息苦しさを感じている
- これからの生き方に、もっと納得感がほしいと思っている
このプログラムでは、
「誰かのために頑張る私」から、
「私のために整える私」へ変わっていきます。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
「ちゃんとしてるのに、苦しい」
「頑張ってるのに、うまくいかない」
——そんな違和感を抱えたまま、ずっと我慢していませんか?
LINEで3分セルフ診断ができます。
あなたの“今の感覚”の正体が、見えてきます。
ADHDとASDの違いがわからなくなった母親が、最初に整理すべき視点とは
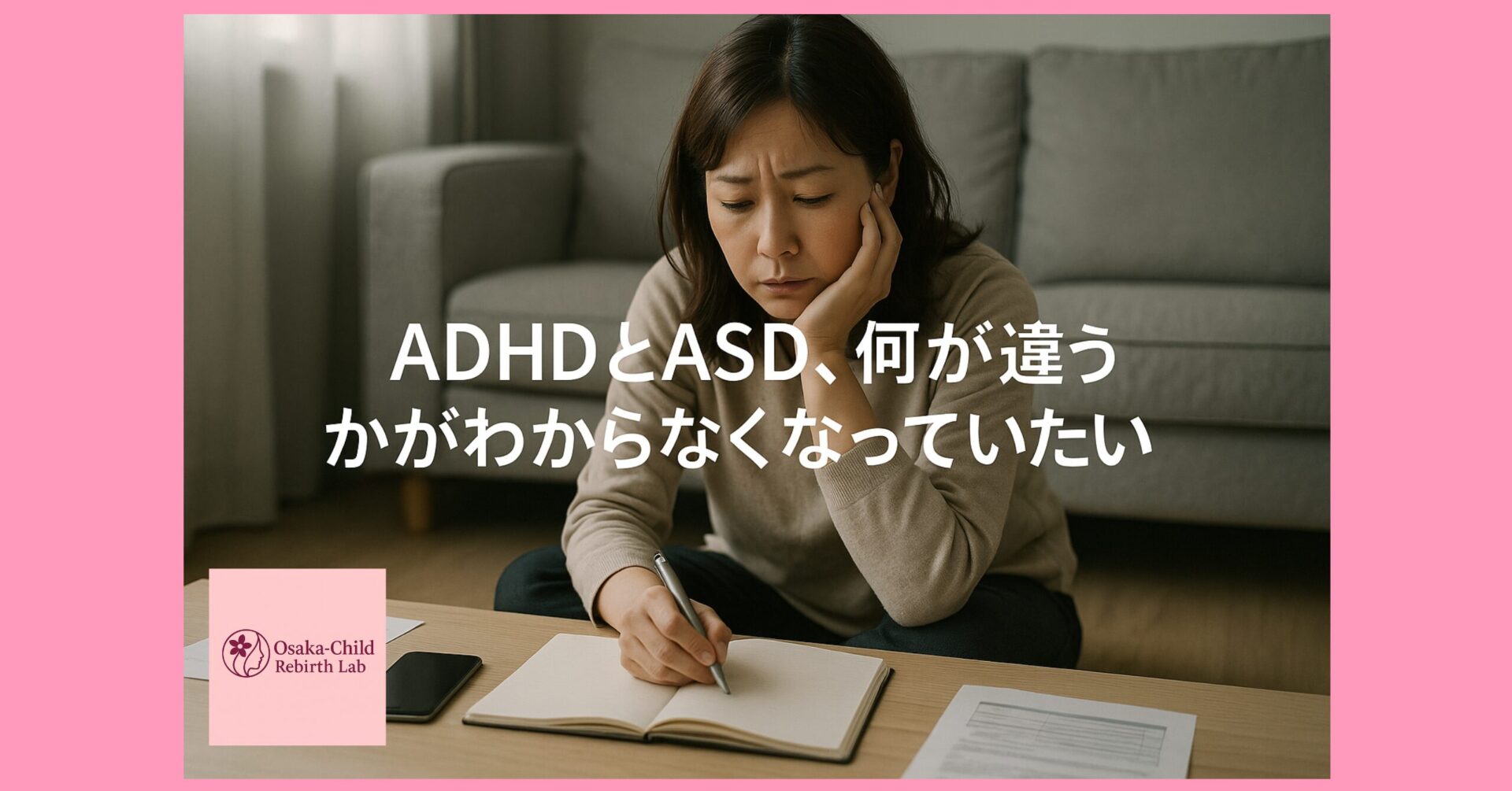
ADHDと診断されたとき、
「育てにくさの原因が分かったから、これで少し楽になれる」と
あなたは感じました。
でも、
育てにくい子どもと関わる毎日のなかで、
「ADHDだけじゃない気がする」と、
うっすらとした違和感が積もっていった。
そんなふうに「モヤモヤ」を抱えたまま、
検索欄に「ADHD ASD 違い」と入力していた自分がいた
──そうあなたは振り返っているのです。
ADHDとASDの違いは、
ネットで調べても専門用語が多く、
結局よくわからなかったという40代母親も多いです。
でも、
本当に知りたいのは、
診断名の違いではなく、
「この子にどう関わればいいか」ということですよね。
「どっちなのか」より、
「今、目の前のこの子とどう過ごせば安心できるか」が、
何より大切です。
このキャプションでは、
ADHDとASDの違いに迷った母親であるあなたが、
最初に整理すべき「視点の整え方」を、
一緒に見つめていきます。
ADHDとASDの違いとは?見分け方に迷ったときの基本視点
ADHDとASDの違いは、
専門家の間でも「重なりが多い」とされています。
それくらい、
きれいに線引きするのが難しい領域なんですよね。
育てている母親の側から見れば、
「今日はADHDっぽい、でも昨日はASDみたいだった」
──そんな日があなたは続いていました。
ADHDは、
- 不注意
- 多動
- 衝動性
といった特徴が見られやすいです。
ASDは、
- 空気が読みにくい
- こだわりが強い
- 急な変化に混乱しやすいなど
の反応が中心に出る傾向があります。
けれど、
実際の子どもはそんな分類通りには動いてくれません。
ADHDの診断が出ていても、
ASDのような行動が見えることがあります。
逆に、
ASD傾向が強い子が
ADHDのような衝動的な行動を見せる場面もあります。
だから、
「ADHD ASD 違い」を見極めようとすればするほど、
母親の中に混乱が広がってしまうんですよね。
本当に必要なのは、
「この子がどの特性を持っているか」ではなく、
「どんなときに困っているか」を見ていく視点です。
診断名で仕分けるのではなく、
生活の中で「何が起きているか」を一緒に見ていく。
あなたのその姿勢が、子どもとの関わりを整えていく土台になります。
「ADHDだけではない気がする」と感じた母親が最初に見るべき特性の重なり
子どもがADHDの診断を受けたとき、
「ようやく理由が見えた」とあなたは感じました。
でも、その安心は長く続きませんでした。
むしろそこから、
- 「これって本当にADHDなの?」
- 「なんだか違う気がする」
という戸惑いが少しずつ増えていった。
たとえば──
- 服の肌ざわりに過敏に反応する
- 同じ言葉を何度も繰り返す
- 予定変更に極端に混乱する
こうした特徴は、ADHDというよりASDに近い反応に見えることがあります。
ポイント
実際には、
「ADHD ASD 両方ある場合」もあります。
両方の特性をあわせ持っている子どもはたくさんいます。
ただ、
それを
「そうか、ASDもあるんだ」と
すぐに受け止めるのは簡単ではないですよね。
母親としては、
もうこれ以上「診断名」にふりまわされたくなかった。
でも、
「ADHDだけでは説明がつかない」という気づきは、
無視できないものでもあった。
そうやって、
自分の直感に向き合いながら、
なんとか関わり方を探してきた日々がありました。
だからこそ、
「診断を増やす」よりも、
「生活のなかで何が起きているか」を見つめていくことが、
母親にとって子どもにあった関わりを見つける機会になります。
特性の重なりに気づいたということは、
すでに関わり方を見直そうとしている証なのです。
診断を受けたのにモヤモヤが残るのはなぜか──「違い」の混在と母親の直感
ADHDの診断が出たとき、
どこかで安心していた自分がいた。
ようやく
この子の特性がわかって、
向き合っていける
──そんな希望を持っていた時期もありました。
けれど、
現実はそう簡単ではなかった。
- 説明された通りに関わってみても、
- うまくいかない場面が増えていった。
そして、
いつのまにか「ADHDだけじゃない気がする」と思い始めていた。
たとえば、
- 何度言っても同じ行動を繰り返す
- 急な予定変更でパニックになる
- 集団の中で浮いてしまうような場面が続く
それは、
「ADHDの子だから」では説明が足りないと感じる行動だったのです。
「うちの子はADHD以外の発達障害があるのでは?」
そうした違和感に気づいていたこと、
そして言葉にできないまま抱えていたこと。
それこそが、
母親の「まなざし」の深さです。
この子の苦しさを、
名前ではなく「感覚」で受け取ってきた、
その積み重ねがあった。
ADHDとASDの違いを正確に見分ける必要はありません。
でも、
「診断を受けたのに、まだモヤモヤしている」という気持ちは、
確かに存在していますよね。
その直感は、
この子のために向き合おうとしてきた証です。
違いに気づいたときこそ、
個性ある子どもの特徴を理解し、
母親のあなたにとっても最適な関わりを見つめ直すタイミングです。
無料診断|あなたの「心のパターン」を知る
「ADHDとASD、どっちなのかよくわからない…」
そんな方のために、LINEで「キーワード」を送るだけで診断できるサービスをご用意しました。
LINEに「ADHD ASD 違い」と入力して送ってください。
あなたに合った視点と、今必要な情報をお届けします。
ADHDとASDの違いを具体的に見つめるために|子どもの行動をどう読み解くか
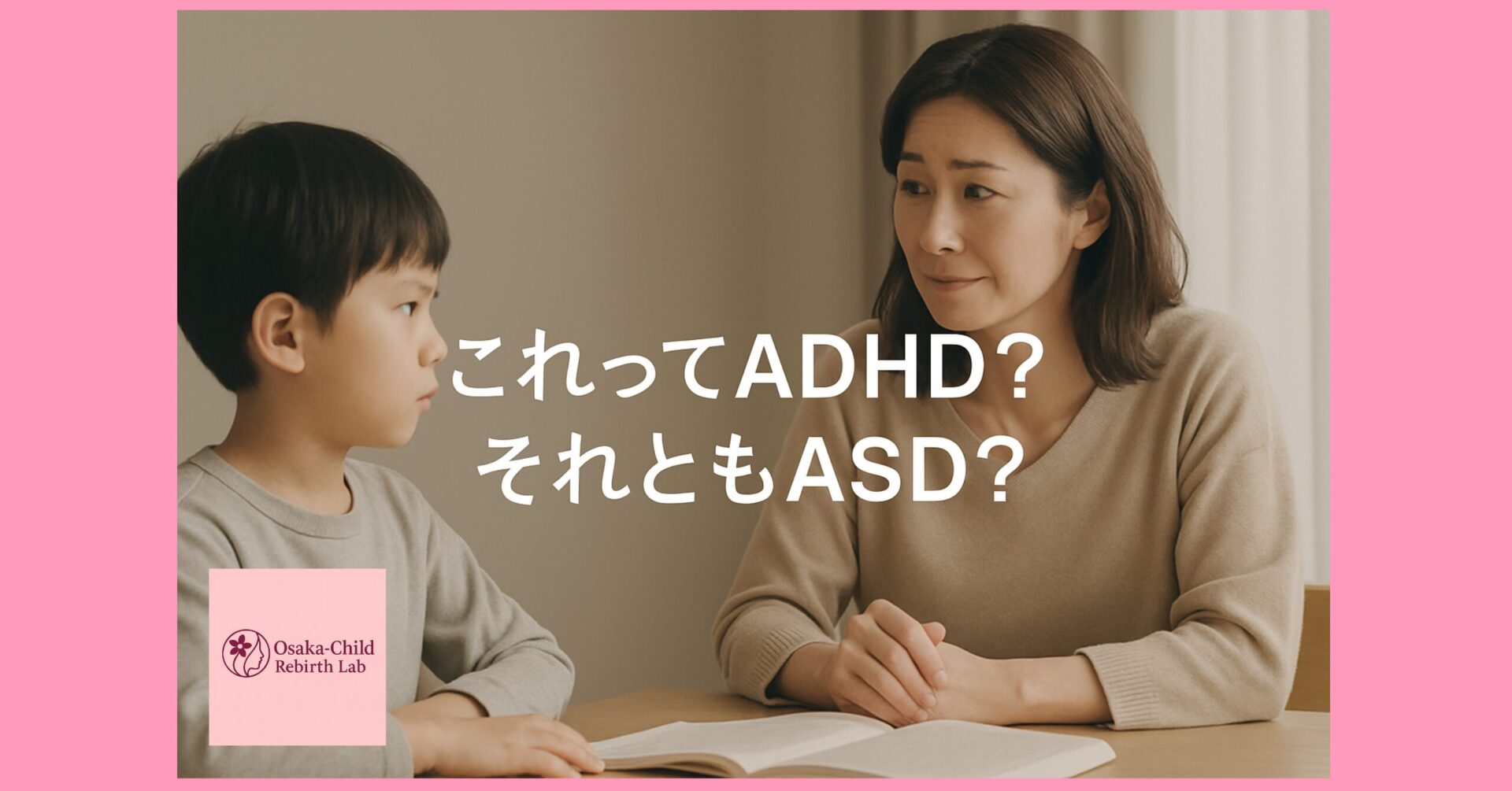
ADHDの診断を受けたあと、
あなたは「ああ、やっぱりそうだったんだ」と
少しホッとしたこともあった。
けれど、
日常の中でふと浮かんでくる
ADHD以外の特性もあるのでは?という違和感が、
消えてくれなかったんですよね。
「この子の困りごとは、ほんとうにADHDだけなのかな……」
──そんな気持ちが頭の中に残り続けていた。
ADHDとASDの違いを整理しようとして、
あなたは書籍やネット検索を重ねてきました。
でも、
専門的な説明を読めば読むほど、
「うちの子はどっちにも当てはまる気がする」と
あなたは混乱が深まってしまいましたよね。
このキャプションでは、
ADHDとASDの違いが「行動」としてどう表れてくるのかを、
具体的な3つの視点から見つめ直していきます。
ADHDとASDの違いは「会話のズレ」に表れる|冗談・言い換えが通じない子の見え方
ADHDの子どもは、
話の途中で話題が飛んだり、
思いついたことをそのまま口にしたりしやすいですよね。
ASDの子どもも会話でつまずくことがあるけれど、
ADHDとはちがう「ズレ」が起きている場面があります。
たとえば、
「あとで片づけようね」と伝えたとき。
ADHDの子なら、
「うん、あとでね」と言いながら忘れてしまうことが多いです。
でも
ASD傾向がある子は、
- 「『あとで』っていつ?」と混乱してしまったり、
- 「『片づける』ってどうやるの?」と
動けなくなってしまうこともあります。
冗談やたとえ話もそうです。
ADHDの子が話を途中で遮ってしまうのとはちがって、
ASDの子は
「言葉を文字どおりに受け取る」という形でズレが出てくることがあるんですよね。
- ADHDの衝動性による話の乱れと、
- ASDの認知のズレによる会話のズレ。
同じ「うまく伝わらない」でも、
そこにある背景はちがうという視点が、
この違いを読み解く鍵になります。
実際に、
- 「冗談がまったく通じなかった」
- 「比喩を言ったら真顔で返された」
──そんな反応は子どもによくみられるなら、
ASDの特徴を視点に入れて子どもを見てみると、
自然と関わり方が見えてきます。
「こだわり」と「空気が読めない」はADHD?ASD?──重なる特徴の違いを知る
ADHDにも、
ひとつのことにこだわりやすい傾向があります。
でもASDの場合、
それが
「譲れないもの」として
表に出てくることがあるんですよね。
たとえば、
- 朝の支度の順番が決まっていて、
- それが変わるだけで泣き出してしまう。
- お箸がいつものじゃないと怒ってしまう
──そんな「絶対こうでないとダメ」な反応に、
戸惑ってきました。
ADHDの子どもも
- 「気分が乗らないから動かない」
- 「他のことに気を取られて支度が進まない」
ということはありますが、
それは
「こだわり」というより
「注意の散漫さ」から来ている場合が多いです。
ポイント
ASD傾向のある子は、
「こだわりが守られない=安心が壊れる」という感覚を持っています。
そのため、少しでもズレると大きく反応してしまう。
この違いは、
関わり方を見直すうえでとても大切な視点になります。
同じように、
「空気が読めない」という行動も、
ADHDとASDで理由が異なります。
ADHDの子は
衝動的な発言で場を乱してしまうことが多いのに対し、
ASDの子は
「場そのものの意味がわからない」という背景で動けなくなったり、
意図せず浮いてしまったりします。
「どうしてこの子は、いつもズレてしまうんだろう」──
そう感じていたその違和感には、
子どもの脳内の構造の特徴からきているのです。
「ADHDの支援が合わないかも…」と感じたら
「ADHDの診断は出ているけど、今の支援がこの子に合っていない気がする…」
──そんな「違和感」が芽生えたときこそ、
関わり方を見直すタイミングです。
ADHDとASDの「重なり」に気づいた母親が、
安心して向き合える関係を取り戻していく──
3週間集中再安心サポートという選択肢があります。
「ADHDと診断されたのに、それだけでは説明できなかった子どもの『違い』に悩んでいた母が、
特性を見つめ直し、安心して関われるようになる──3週間集中再安心サポート」
ASD傾向もあるADHDの子どもは、どんな場面で「違い」が見えてくる?
ADHDの特徴を知ったとき、
これまでの育てにくく、
子どもの個性が嫌になることがなくなるのではと
感じました。
でも、
そのあともずっと残り続けた
「それだけでは足りない」という思い
──それが、ASDの傾向に気づくきっかけになっていました。
たとえば、
- 集団の中でいつも浮いてしまう
- 同じ話題ばかり繰り返す
- 教室のにおいが気になって集中できない
- ルールの曖昧さに混乱して動けなくなる
そんな場面にあなたは何度も立ち会ってきました。
ADHDの特性だけでは説明しきれない。
でも、
ASDという言葉に対する怖さや抵抗感があって、
なかなか認められなかった。
その気持ちは、
とても自然なものだと思います。
けれど、
「この子の困りごとを、ちゃんと理解したい」という思いは、
ずっと変わらずにありました。
だからこそ、
「ADHDかASDか」と分けるのではなく、
重なりの中でこの子が何につまずいているのかを、
もう一度見直していくことが必要なんですよね。
違いに気づいたからといって、
母親が何か間違っていたわけじゃない。
むしろ、
日々の中で「気づこうとしていた自分」を、
少しだけ認めてあげてもいいのです。
「ADHDと診断されたのに…」と感じる母親が陥りやすい支援の迷路
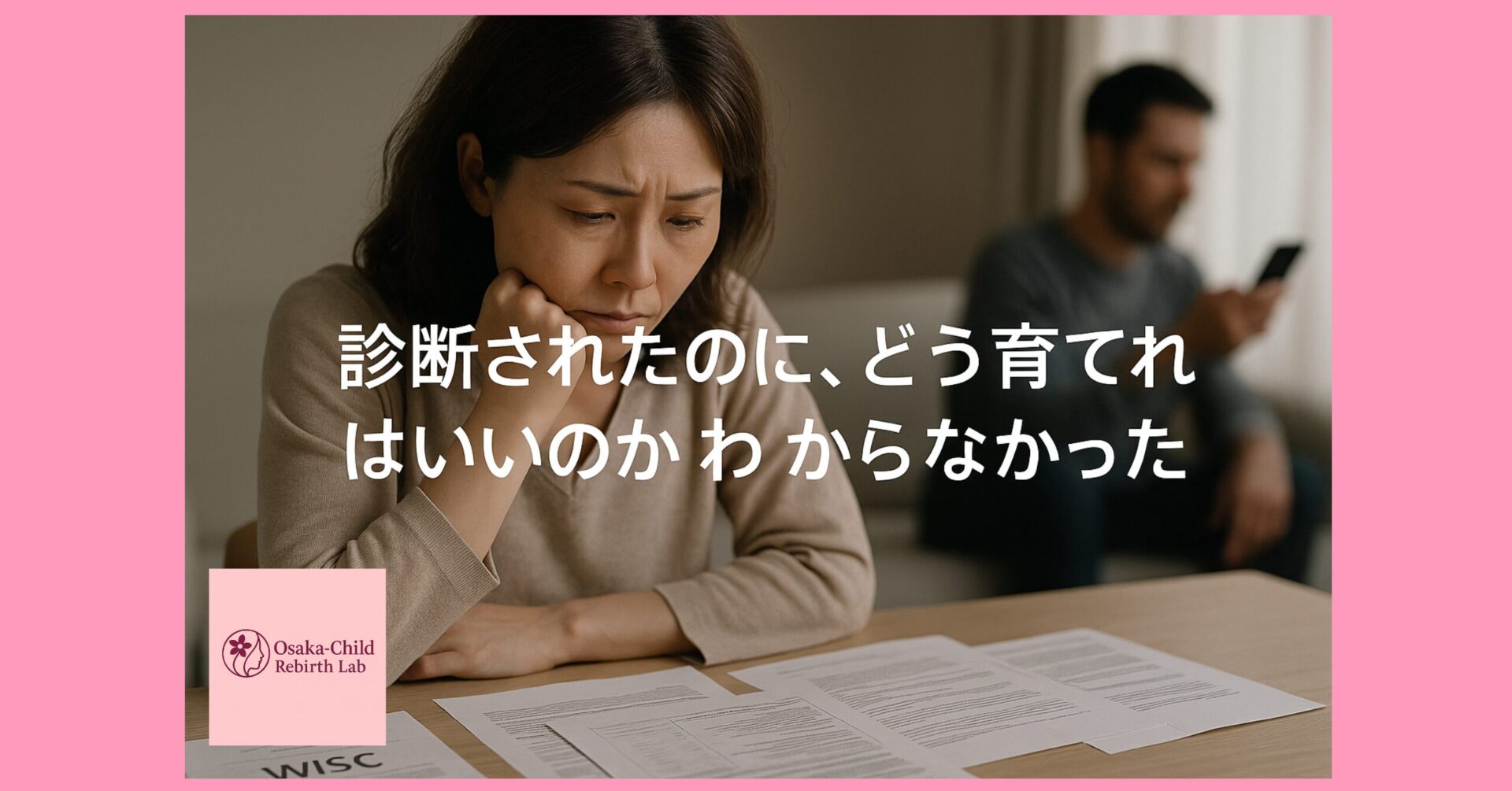
ADHDと診断されたあと、
子どもへの育てにくさによるストレスが少なくなり
「これで何かが変わる」と思ったことがあった。
- 支援の道が開ける、
- 学校との話もスムーズになる、
- 関わり方も少しはわかるようになる
──そんなふうに期待していた時期がありました。
けれど実際は、
どこに相談すればいいのか、
何をしてあげればいいのかがわからなくなっていった。
- 医療と教育のはざま、
- 支援と通常のあいだ、
白でも黒でもない「グレー」な領域で立ち尽くしてしまうような感覚。
診断名があるのに、
支援にはつながらない。
その「ズレ」に、
ココロが置いてけぼりになることがあるんです。
このキャプションでは、
ADHDとASDの違いが関わる
「支援の迷路」について、
3つの視点から丁寧に整理していきます。
「ADHDだけじゃ説明できない」と感じているあなたへ
ADHDの支援をしてきたのに、
「どうもこの子には当てはまらない部分がある」と感じていませんか?
- 会話のズレ
- こだわりの強さ
- 感覚の敏感さ…
「ASDかもしれない」という違和感に、あなたは戸惑ってきました。
- ADHDの特性
- ADHDの支援
- ADHDとASDの違い──
検索しても、「この子の場合は?」が見えてこないまま、
深夜にスマホを閉じる日々が続いています。
でも本当は、診断名を探しているのではなく、
「この子と向き合える視点」が欲しかったんですよね。
「ADHDと診断されたのに、それだけでは説明できなかった子どもの『違い』に悩んでいた母が、
特性を見つめ直し、安心して関われるようになる──3週間集中再安心サポート」は、
ADHDの支援だけでは届きにくかった「ズレ」や「不一致」に対して、
ASDの視点も取り入れながら整えていく3週間のサポートです。
こんな方におすすめです
- ADHD的な対応が、この子には通じていない気がしている
- ASDもあるかも…と気づき始めたが、誰にも言えずにいる
- ADHDとASDの違い・重なりを整理できず、混乱が続いている
- 今の支援が合っていないと感じるが、どう変えたらいいかわからない
- 母親としての「直感」を、安心に変える言葉がほしい
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 2月2日(月)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと3名様限定』
※銀行振込限定・先着順
▶ ADHDとASDの「境界」に悩んだ母が、安心して関われるようになる3週間へ
そして──
「母親としての私」を整えたあと、
「わたし自身のこれから」を考えていきたいと感じたあなたへ。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
ADHDの子どもとの関係を整理した先に、
「自分の人生」を見つめ直すための3週間です。
母であることも、妻であることも大事だけど、
「私の時間」も大切にしたい──
そんな思いを応援する再出発のプログラムです。
- ADHDの子育てを通じて、自分と向き合うようになった
- 「家庭だけの毎日」に、そろそろ息苦しさを感じている
- これからの生き方に、もっと納得感がほしいと思っている
このプログラムでは、
「誰かのために頑張る私」から、
「私のために整える私」へ変わっていきます。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
ADHD ASD 支援はどう違う?──診断名で分けられない「グレー」な子どもの支援方法
「ADHDの診断は出た。でも、それだけじゃ支援につながらなかった」
──あなたはこのような体験をしました。
実際、
ASDと比べると、
ADHDは
「特別な支援が必要ない」とされてしまう場面も多いんですよね。
ASDの子どもは、
- 特別支援学級
- 個別指導
の対象として認識されやすいです。
一方、
ADHDの子どもは、
- 「少し気をつければ対応できる」
- 「周囲の配慮で十分」
と言われてしまうこともある。
でも、
どちらにも当てはまらない
「境界グレー」の状態にいる子どもたちは、
どこにもぴったりはまらないまま、
支援を受けにくい状況に置かれてしまうんです。
ADHDの特性だけでなく、
ASDのようなこだわりや感覚のズレを併せ持つ場合
通常の学級ではフォローが足りないことがあります。
かといって、
ASDのような明確な特性で認識されていないと、
支援学級への移行も難しい。
そんな「はざま」に置かれた子どもたちを、
どう支えていけばいいのか。
母親として、
あなたはその迷いを抱えたまま過ごしてきました。
診断名で支援を決めるのではなく、
「どんな場面で、どんな困りごとが起きているのか」に注目すること。
その視点が抜け落ちてしまうと、
支援が機能しない現実があるんです。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「ADHDってどう理解したらいいの?」
そんな迷いを感じたときに、「この子の困りごと」の背景や、家庭でできる向き合い方を専門家の視点と共にまとめた記事です。
👉 はじめての「ADHDの向き合い方」──特性と家庭での関わりをやさしく整理する
-

-
参考ADHDとは?子育てに限界を感じたあなたへ|「責める毎日」を手放すヒント【児童精神科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 朝から何度も叱って、 疲れ果てた夜。 寝顔を見るたびに、 「また怒りすぎた」と後悔ば ...
続きを見る
WISC検査ではわからなかった「支援の合わなさ」の理由を解く視点
WISC(ウィスク)検査を受けたとき、
「これで子どものことがよくわかる」と
あなたは期待しました。
知的には問題ない。
だから「通常学級で大丈夫」と言われた。
でも、
そのあとに待っていたのは、
「合わなさ」の連続だった
──そんな経験はたくさんありますよね。
ADHDの子どもは、
検査のときに集中力が続くかどうかで結果が大きく変わります。
ASDの傾向が重なっている場合、
質問の意図が伝わらなかったり、
検査そのものの文脈を理解できなかったりする場面もあります。
つまり、
WISCで数値が出ても、
「その子が実際にどこで困っているのか」までは見えてこないことがあるんです。
検査で示された
- 「平均」
- 「凸凹」
のデータだけでは、
- 学校生活でのつまずきや不安、
- 感覚の過敏さまでは拾いきれない。
そのズレが、
支援がうまくいかない理由になっているケースもあります。
- 「支援が合わない」
- 「何を試してもうまくいかない」
──そんなときこそ、
診断名や検査結果から離れて、
「この子は何に困っているのか」を見直す視点が必要になります。
- ADHDの特性だけで支援を考えると、
- ASD的な反応が見落とされてしまう。
そのことが、
子どもにも母親にも、
「合っていない支援」という負担を残してしまうんですよね。
診断は受けた。でも「どう育てればいいのか」がわからない母親へ
ADHDと診断されて、
あなたは少し気持ちが楽になった気がした。
- 「育て方が悪かったわけじゃなかった」
- 「この子の特性だったんだ」
と思えたあの日。
でも、
そこからどう育てていけばいいのかがわからなくなってしまった
──そんな気持ちがずっとココロの中にあった。
- 支援はあった。
- アドバイスももらった。
それでも、毎日の生活の中では、うまくいかないことの方が多かった。
- ADHDの対応に従ってみても、どこかでつまずいてしまう
- ASDのような反応も見えるけれど、そうとははっきり言われていない
その曖昧さが、
母親をさらに混乱させていったんですよね。
「結局、どう育てればいいの?」──
その問いが、
あなたは何度も頭の中に浮かんできました。
ADHDとASDの違いが重なる子どもは、
「どちらの教科書にも載っていない育て方」が必要になります。
でも、
その正解を誰かが与えてくれるわけじゃない。
だからこそ、
必要なのは、
ポイント
「診断」や「支援の形」ではなく、
「この子との関係」を見つめ直すことなんです。
- ADHDの視点だけでは見えなかったこの子の反応。
- ASDとして受け止めるにはまだ勇気がいった「違い」
その狭間に気づいていた母親だからこそ、
もう一度、
「この子をどう育てていくか」を、
自分の言葉で見つけ直す準備ができているのです。
「この子に合う関わり方」を見つけたい母へ
「ADHD的な関わり方では通じない」
──そんな実感が増えてきた母親へ。
ASD的な特性にも目を向けて、
この子に合う関係を「安心の視点」から整えていきませんか?
「ADHDと診断されたのに、それだけでは説明できなかった」
その違和感に気づいた母が、
「安心して向き合える関係」を取り戻す3週間です。
「ADHDと診断されたのに、それだけでは説明できなかった子どもの『違い』に悩んでいた母が、
特性を見つめ直し、安心して関われるようになる──3週間集中再安心サポート」
ADHDとASDが「重なって見える」子への関わり方|家庭でできる視点の整え方

ADHDと診断されたとき、
やっと子どもの困りごとに理由があるとわかって、
少し安心できました。
けれどその後も、
ADHDではない反応が子どもにあり
不安をベースにした何かひっかかるような感覚が残っていました。
たとえば、
- 「伝わりづらい」
- 「急な予定変更で大きく動揺する」
- 「表情が読みづらい」──
そうした特性が見え始めたとき、
「もしかしてASDもあるのでは?」という不安がよぎりました。
ADHDだけの支援では届かない感覚がある。
けれどASDと決まったわけでもない。
この「重なり」に揺れながら、
毎日手探りで子どもと向き合っているあなたへ、
このキャプションでは、
あなたでもできる、
家庭でできる
ADHDと診断され、
ASDの反応がみられる子どもへの視点の整え方を丁寧に見つめていきます。
ASDもあるのでは?と感じた子に「ADHD的関わり」が通じない理由
ADHDに合った接し方を実践しているのに、
どうしてもうまくいかない──。
そんな状態が増えてきたとき、
ASDの傾向もあるのではと気づきますよね。
たとえば、
ADHDの子どもには、
「短く・具体的に・テンポよく」声をかけるのが効果的だとされています。
けれど、
同じように関わっても、
子どもがまったく反応を返してくれない。
こちらの表情にも戸惑い、
視線も合わず、
まるで届いていないように感じることがあるんです。
実際、
ADHDとASDは「併発」するケースも多く、
どちらか一方では捉えきれない子もいます。
ADHDの関わり方が通じないとき、
それは
ASD的な感覚の違いが影響しています。
ADHDでは
- 「集中しづらい」
- 「衝動的」
といった「動き」の特性が中心ですが、
ポイント
ASDでは
「感じ方や受け取り方の違い」が
日常のつまずきに現れやすいです。
たとえば、
「今やろうね」と言っても、
ADHDの子は気が散ってしまい、
忘れてしまうことがあります。
一方で、
ASDの子は
- 「『今』の意味がわからない」
- 「予定と違うことが起きて混乱する」
という反応を見せることがあります。
つまり、
「伝え方が悪い」わけではなく、
伝わる回路そのものが違う。
その違いに母親自身が気づけていないと、
毎日が「なぜ伝わらないの?」という苦しみになってしまいます。
ADHDの関わり方を頑張っているのにうまくいかないとき、
それは
「伝え方」の問題ではなく、
「伝わり方」の違いがあっただけ。
そう気づけた瞬間から、
ADHDでASDを抱えた子どもへの関わりの視点が大きく変わっていきます。
ADHD ASD 違いが曖昧なとき、子どもに伝わる声かけ・環境づくりとは
ADHDとASDの違いがはっきりしない状態では、
どんな対応が必要なのか迷ってしまいますよね。
一生懸命に支援の方法を探しているのに、
「何がこの子に合うのか」が見えない毎日は、
とてもつらいものです。
ADHDに対しては、
- 「気が散らないように整理された空間」
- 「明るい声かけ」
が効果的だとされています。
でも、
ASD傾向がある場合、
その空間が逆に
「刺激の強すぎる場所」になってしまうこともあるんです。
たとえば、
- ポスターやカラフルな装飾が貼られている部屋
- いくつもの声が飛び交う中での指示
- 光や音の刺激が強いリビング空間
ADHDの子には
「集中しやすい工夫」として使われるものでも、
ASD的な感覚を持つ子にとっては
「落ち着かない・安心できない空間」になってしまいます。
また、
「頑張って伝えたのに、まったく届かなかった」と感じる声かけも、
ASD的な受け取りの違いによって、
「そもそも意味がわからない・表現が曖昧すぎる」ものに
なってしまっていることもあるのです。
ここで大切なのは、
「診断名で分ける」のではなく、
「どの関わり方が伝わったか」を一つひとつ観察する姿勢です。
ポイント
ADHDの関わりが通じなかったとき、
ASD的な安心感を意識してみる。
それでも難しいときには、
さらに感覚の違いを見つめていく。
そうやって、
「今ここで、この子に伝わっているかどうか」を軸に考えることで、
日常が少しずつ楽になり、子どもとココロとココロの共有ができるようになります。
診断名ではなく「理解の視点」を整えるために母親ができること
診断されたとき、
「これで子どもの困りごとに名前がついた」とあなたは少し安心しました。
でも実際には、
ADHDと診断されたあとも、
毎日の子どもの反応を見て
他にも発達障害を持っているのでは?と
ココロの中に説明しきれない違和感が残っていました。
- 「これってASDもあるのかな」
- 「ADHDだけでは説明がつかない感じがする」──
そんなふうに、
診断名の「外側」であなたは悩み続けてきました。
実際、
ADHDとASDは完全に分けられるものではなく、
グラデーションのように重なり合う部分も多くあります。
だからこそ、
「ADHDかASDか」にこだわりすぎると、
目の前の子どもが見えなくなってしまうことがあるんです。
では、母親にできることは何でしょうか。
それは、
診断名を見分けることではなく、
「どんなときにこの子が安心しているか」に気づくことです。
たとえば、
- 急な予定変更で混乱するとき
- 言葉の意図が伝わりづらくて止まってしまうとき
- 環境の刺激に耐えられず、不安定になるとき
これらが見られたとき、
「またできなかった」と責めるのではなく、
「これはADHDだけじゃなく、ASDの傾向も重なっている」と受け止めてあげること。
ADHDという診断を軸にしつつも、
ASD的な安心の整え方も少しずつ取り入れてみる。
それだけで、
親子のコミュニケーションが大きく変わっていきます。
診断名で正そうとする必要はありません。
母として「安心して関われる関係」を築いていくことが、
子どもにとって一番の支援になるということ。
それに気づけたとき、
悩み続けていた毎日に、光が差し始めます。
「それだけじゃなかった」と気づいた母親が、「安心して関われるようになる」まで

ADHDと診断されたとき、
子どもの困りごとに
「名前がついた」安心感がありましたよね。
けれど、
時間が経つにつれて、
また違う困りごとが見えてくるようになった
──そんな感覚があなたには生まれていました。
- 「今の支援では届かない」
- 「この子には、もっと別の支え方が必要な気がする」
そうやって、
ADHDだけでは説明がつかない感覚に向き合い続けてきました。
このキャプションでは、
ASD傾向のある子どもに対して
「ADHD的関わり」だけでは届かなかった理由と、
そこから安心して関われる母に変わっていくまでの道のりを、
3つのステップに分けて見つめていきます。
ADHDと診断された子にASD傾向を感じた母が、悩み続けていた理由
最初はADHDと診断されて、
毎日子どもの特性にふりまわされ疲れていたときだったので
「やっぱりそうだったんだ」と安心した記憶がある。
けれどその後、
支援を受け始めても、
家庭ではなかなかうまくいかないことが増えていった。
そのたびに、
「もしかしてASDもあるのかも」と感じるようになっていきました。
ADHDの支援は、
- 「集中のコントロール」
- 「行動の調整」
に焦点をあてた対応が中心です。
でもASDの傾向が重なると、
- 「感覚の鋭さ」
- 「言葉の裏を読み取れない困難」
- 「予定変更への強い不安」など
まったく違う対応が必要になります。
それなのに、
「ADHDの診断が出ているから」と、
ASD傾向へのアプローチが後回しにされてしまうことがある。
「発達障害は境界があいまい」とは言われても、
「じゃあどこで相談すればいいの?」という迷いが残ったまま、
母親だけが悩み続ける構図ができてしまいます。
- 何科を受診すればいいのか、
- どんな支援が必要なのか。
ADHDのことは学んできたけれど、
ASDについてはわからないことだらけ。
それでも、
- 子どもの表情の変化
- 言葉にできない反応
に、確かな違和感を抱き続けてきました。
そうやって、
「診断されたのに、何も変わらない」と
いう状態が続いていくと、
母親自身が、
「自分が悪いのでは」と自責を深めてしまいます。
ADHDとASDの「違い」を正しく理解していないのではなく、
支援の枠がその「重なり」に対応しきれていなかっただけ。
そう気づけることが、次の一歩につながります。
特性の重なりに合った関わり方へ──3週間で整えていく視点と実践方法
ADHDとASDの違いをいくら学んでも、
「どっちなの?」という疑問ばかりが残ってしまう。
そんな状態では、
家庭の中でどんな関わりをしていいのか、
毎日が手探りのままになってしまいますよね。
特に、
ADHDの支援では
- 「指示は短く具体的に」
- 「選択肢をしぼる」
- 「行動で動かす」など
の対応が中心です。
一方で、
ASDが重なると、
指示よりも
- 「見通しの提示」
- 「感覚の調整」
- 「言語の曖昧さの配慮」
が必要になることがあります。
この「真逆にも見える対応」の中で、
母親が1人でバランスを取ろうとするのは、
とても負担が大きいのです。
そこで必要になるのが、
特性の重なりを前提とした視点の整え方です。
- 「ADHDの対応」
- 「ASDの対応」
を、対立するものではなく、
子どもの反応に合わせて調整する「組み合わせ」として捉え直す視点が必要になってきます。
この3週間サポートでは、
以下のようなステップで母親自身の視点を整えていきます。
- Week1:ADHDとASD、両方の「違い」ではなく「重なり」に気づく時間
- Week2:子どもの反応から「どんな関わり方が安心につながるか」を見直していく
- Week3:母自身が「この子と一緒にいられる安心」を取り戻していく関係づくり
ADHDという診断を出発点に、
ASD的な特徴も含めた「実際の反応」をていねいに見つめていくこと。
それが、
子どもにとっても母親にとっても
「しんどさ」を減らす、本当の支援になります。
「どっちか」ではなく「安心して関われる母」に変わっていくステップとは
- 「グレーゾーンと言われた」
- 「ADHDとASDの両方を指摘された」
そんなふうに診断や言葉だけが先に進んでいって、
「この子自身の姿」が見えづらくなっていた時期があった。
支援に取り組んでいるのに、
いつまでも「合っていない感覚」が残っているとあなたは感じていた。
- ADHDの特性に合わせて環境を整えた
- 声のかけ方も工夫した
でも、
なぜか伝わらない。
むしろ、
不安定になっていくことさえあった。
そのたびに、
「また間違えたのかもしれない」と、
自分を責める思考が止まらなくなっていった。
けれど今ならわかります。
「ADHDなのかASDなのか」を判断することが、
目的じゃなかったのだと。
必要なのは、
「この子に何が起きているか」に目を向けること。
そして、
- 「どんなときに落ち着けていたか」
- 「どんな関わりが混乱を生んでいたか」
を、ひとつずつ見ていくことでした。
ADHDとASDの「どちらか」に当てはめようとするのではなく、
その両方の視点を持ちながら、
安心して関われる母に変わっていくことが本当の支援につながっていきます。
この3週間のサポートでは、
「診断名に振り回される日々」から少し距離を取って、
母自身の視点を整えながら、
「この子と一緒にいられる安心感」を取り戻すプロセスを歩んでいきます。
診断名で正しさを求めなくていい。
「どっちか」を決めるために悩むのではなく、
「どちらがあっても関われる関係」を育てていくために、ここから変わっていける
──そんな視点が、あなたにもきっと見えてくるはずです。
無料LINE診断|今のあなたに必要なサポートは?
『何から始めればいいかわからない…』そんなあなたへ。
LINEで「数字」を入力するだけで、今のあなたに合ったサポート商品を診断できます。」
今すぐLINEに【 4 】と入力してください。
ADHDとASDの「違い」に悩んできたあなたにぴったりのプログラム内容が届きます。
「ADHDだけじゃなかった」と気づいた母親に必要だった、「視点の整え直し」
- 「ADHDと診断されたのに、どうしてこんなにしっくりこなかったんだろう」
- 「支援を受け始めても、家庭ではまったく噛み合わないまま」
そんなふうに、
あなたは理由のない孤独を抱えていた時間がありました。
- 冗談が通じない
- 予定変更で混乱する
- 触れられるのを嫌がる
ADHDだけでは説明できない反応が、
日常の中でいくつも積み重なっていった。
それでも
- 「診断が出たんだから」
- 「ADHDの対応をすれば」
と、必死に向き合ってきたんですよね。
そんなときに届けたいのが、
「ADHDと診断されたのに、それだけでは説明できなかった子どもの『違い』に悩んでいた母が、特性を見つめ直し、安心して関われるようになる──3週間集中再安心サポート」です。
このサポートは、
診断名を整理するためではなく、
母親自身の安心とまなざしを取り戻す3週間です。
STEP①|「違和感」の棚卸しと視点の言語化
最初の1週間は、
ずっと抱えてきたモヤモヤの正体を言葉にしていきます。
ADHDとASD、それぞれの特徴や重なり方を、
「うちの子」の感覚や反応に置き換えながら丁寧に整理します。
「何度も失敗してきた」ように見えていた関わりが、
実は
- 「伝え方のズレ」
- 「感覚の違い」
だったと気づける時間でもあります。
STEP②|「この子に届く関わり方」を実践するステップへ
2週目は、
実際に
- 「どの対応が届いていたか」
- 「逆に混乱を生んでいたか」
に目を向けながら、
ADHD的なアプローチにASDの視点も加えた関わり方を一緒に組み立てていきます。
たとえば、
- 見通しの提示
- 言葉の選び方
- 切り替えのタイミングなど
「この子のペース」に寄り添う工夫が増えてくると、反応にも少しずつ変化が現れます。
STEP③|「診断名」ではなく「関係性」を整え直す時間
最後の週では、
支援の正解を探すのではなく、
母子の関係そのものを見つめ直していきます。
- 「この子の受け取り方がわかってきた」
- 「怒らなくても通じる場面が増えた」
そう感じられるようになったとき、関わる側の安心感が根っこから変わっていきます。
「診断名に合った対応」ではなく、
「この子に合った距離感」を育てることが支援になるという実感が、
ゆっくり育っていきます。
- 伝わらなかった言葉が、少しずつ届くようになる。
- 拒否されていた声かけが、表情の変化に変わって返ってくる。
それは、
母親自身が安心を取り戻していくことでしか起こらない変化です。
「ADHDと診断されたのに、それだけでは説明できなかった子どもの『違い』に悩んでいた母が、特性を見つめ直し、安心して関われるようになる──3週間集中再安心サポート」は、
その第一歩を、あなたと一緒に歩むための場所です。
“ADHDとASDの違い”に悩む前に、知ってほしいこと
「ADHDと診断されたのに、どうしてこんなに伝わらないの?」
──そんな違和感を、ひとりで抱えてきたあなたへ。
この3週間が、「診断名では届かなかった部分」に気づき直し、安心して関われる関係を取り戻すきっかけになります。
ASD的な特性が見え始めた子どもと、
どう関わればいいのかわからなかった…。
でも、「ADHDの支援では足りなかった」と気づいたことこそが、関係の見直しの第一歩になります。
「ADHDと診断されたのに、それだけでは説明できなかった子どもの『違い』に悩んでいた母が、特性を見つめ直し、安心して関われるようになる──3週間集中再安心サポート」では、
母親自身の視点を整え、家庭の中でできる具体的な関わり直しを一緒に進めていきます。
まずは内容をゆっくり見てみてくださいね。
まとめ|「ADHDだけじゃない気がしていた」…その感覚を、大切にしていいんです
ADHDと診断されたとき、
「これで少し安心できる」と
思ったんです。
でも、
ADHDだけでない特性が見えるようになり、
日が経つにつれて、
その「安心」は揺らいでいきましたよね。
- ADHDの説明は理解していた。
- 支援にも協力的なつもりだった。
だけど、この子の反応は、どこか違う──
- 冗談が通じなかったり
- 予定変更で泣き出したり
- 音やにおいにも敏感だったり
「これってADHDの特徴だったっけ…?」と、
誰にも言えない違和感を、
あなたはずっとひとりで抱えてきました。
支援が足りていないわけじゃない。
でも、
どうしてもうまくいかない場面が増えてきている。
その「行き詰まり」の奥には、
ADHDとASDの違いに気づいたあなたの目があるんです。
── 整理しておきたい、あなたの中にあった感覚
この記事で分かったこと
- ADHDの支援は受けているのに、何かが伝わっていない気がしていた
- 「この子は多動というより、「ズレ」があるように感じていた」
- 診断名ではなく、「この子に合う関わり方」を知りたかった
- ASDという言葉を調べながらも、受け止めるのが怖かった
- 自分の感覚を信じてもいいのか、不安で夜中に何度もスマホを開いていた
ADHDと診断されて、ちゃんと理解してきたつもりだった。
でも、
- 伝わらない
- 噛み合わない
この子の反応に、いつの間にか戸惑うことが増えていたんですよね。
- 冗談が通じない
- 予定変更で取り乱す
一度決めた順番が狂うと、感情のスイッチが一気に入る──
「ADHDの特性とは聞いていたけれど、それだけじゃない」
そんな感覚を、ずっと抱えていました。
それでも、自分の育て方のせいだと責めてきた。
でも本当は、「関わり方が合っていなかっただけ」だったんです。
「ADHDと診断されたのに、それだけでは説明できなかった子どもの『違い』に悩んでいた母が、特性を見つめ直し、安心して関われるようになる──3週間集中再安心サポート」は、
その「わかりにくさ」を、母の目線で丁寧にほどいていくための3週間です。
- Week1では、これまでの「関わりのズレ」を「違和感」として棚卸しし、ADHDとASDの重なりや違いをやさしく整理します。
- Week2では、ASD的要素を含めた伝え方・切り替え方・見通しづくりなど、ADHDだけでは届かなかった対応を一緒に整えていきます。
- そしてWeek3では、「どう関われば伝わるか」ではなく、「どうすれば安心が伝わるか」へ。「理解される経験」を、少しずつ親子で積み重ねていく時間がはじまります。
癇癪やズレを「問題」と捉えるのではなく、
「この子には、こう見えていたんだ」と視点を整えていく中で、
お子さんの表情にも、反応にも、確かな変化が生まれていきます。
もう、自分を責めなくていいんです。
「わからなかった」ことを責めるより、
「わかろうとした」その気持ちを、これからの関係に変えていく。
その一歩を、ここからはじめていきましょう。
「この子に合う関わり方がわからない」と悩んできた私へ
- 「ADHDの診断は受けたのに、なんだか腑に落ちないままここまで来た」
- 「ASDかもしれない…と思い始めてから、怖くてひとりで調べてばかり──」
──そんなふうに、
「ADHDだけじゃ説明できない」と感じてきた母親が、
「安心してこの子を見つめ直せる私」へ整えていく3週間があります。
「ADHDと診断されたのに、それだけでは説明できなかった子どもの『違い』に悩んでいた母が、
特性を見つめ直し、安心して関われるようになる──3週間集中再安心サポート」は、
ADHDとASDの「重なり」や「境界」に戸惑う日々を経て、
今この子に必要な関係を再構築していくためのサポートです。
こんな方におすすめです
- ADHDの支援をしても噛み合わず、母子ともに疲れてしまっている
- ASDの可能性に気づいたが、どうしたらいいかわからない
- ADHDとASDの違いを整理できず、正解探しに迷子になっている
- 夫に相談できず、検索しては閉じる日々が続いている
- 「診断名」ではなく、「関係」を整えたいと願っている
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 2月2日(月)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと3名様限定』
※銀行振込限定・先着順
ネットバンキングのご利用で、今すぐ開始することが可能です。
▶ ADHDとASDの「違い」に悩んできた私が、安心して関われるようになる3週間へ
そして──
ADHDとASDの「違い」に気づけたからこそ、
「わたし自身のこれから」を整えたいと感じたあなたへ。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
「ADHDとASDの子を支える母」を超えて、
「私としての人生」を歩み直すための3週間です。
- ADHDやASDに振り回される毎日から、自分の軸を取り戻したい
- 「母親」という役割だけで生きることに、限界を感じている
- これからの人生を、自分の意思で選び取っていきたい
このプログラムでは、
「発達特性を支える母」の先にある、
「私の人生そのもの」を整えていきます。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
すでに診断済みの方も、そのまま詳細ページへ進めます。
あなたの心と体に合ったサポートを、今すぐ確認してみてください。








