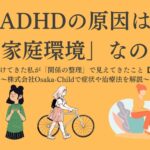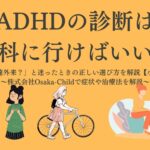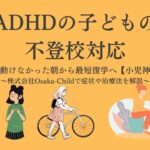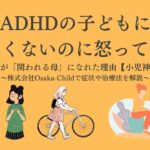朝から何度も叱って、
疲れ果てた夜。
寝顔を見るたびに、
「また怒りすぎた」と後悔ばかりが押し寄せてくる。
- 優しくしたいのに、余裕がない。
- この子を信じたいのに、責めてしまう。
──そんなふうに、
愛情とイライラのはざまで揺れ続ける日々を、
ずっと続けてきたはずです。
私もそうでした。
理屈ではわかっているのに、
気持ちが追いつかないことばかり。
何をどう変えればいいのかさえ、
もうわからなくなっていた時期がありました。
でも、
今になってようやく気づけたことがあります。
一番苦しかったのは、
「ちゃんと向き合いたいのにできなかった」自分を責め続けていたことだったということ。
本当はずっと、
関係を壊したくなんてなかったのです。
このページでは、
以下の5つの視点から、あなたの毎日に光を当てていきます:
この記事を読んでわかること
- ADHDの子どもの行動には「脳の特性」という土台がある
- 怒りを止められない背景には、親自身の疲労と孤立がある
- 自己嫌悪の正体は、「ちゃんと向き合いたい」気持ちの裏返し
- 自分の感情を整えることで、関係性そのものが変わっていく
- 「どう接するか」より、「どんな自分でいられるか」が土台になる
いろんな本を読んでも、
講座を受けても、
うまくいかないことばかりで、
ココロがついていかなかった。
それでも、
この子ともう一度、ちゃんとつながりたいと願ってきたあなたへ。
『なんでできないの?』と責めてしまう毎日。
怒りたくないのに、
また声を荒げてしまう──
そんなふうに、
子どもとの関係に限界を感じているあなたへ。
『なんでできないの?』と責める毎日から、『わかってあげられる私』へ──3週間集中再安心サポートは、
ただ叱らない方法を教えるのではなく、
あなた自身の「まなざし」を整えていく3週間のオンラインサポートです。
- 子どもの特性を正しく捉えなおす
- 感情の揺れに気づき、整える
- 「安心して関われる私」に立ち戻る
このプロセスを通して、
少しずつ、怒らずに関われる日が増えていきます。
そして気づけば、この子と笑い合える時間がちゃんと戻ってくるんです。
もう、ひとりで責め続けなくて大丈夫。
この3週間は、「母としてのあなた自身」を整える時間です。
監修者
株式会社Osaka-Child所属 児童精神科医
- 名前: 西山遥
- 出身地: 京都府
- 最終学歴: 京都大学医学部 精神科専攻
- 専門分野: 思春期精神医学、発達障害、小児うつ病
- 職歴: 大阪市立総合医療センター精神科(児童・思春期外来)勤務(12年)
専門分野について一言: 「『わからない』と感じる思春期のこころに、安心の手が届く社会を目指しています。」
監修者
株式会社Osaka-Child所属 臨床心理専攻大学教授
- 名前: 森本哲夫
- 出身地: 奈良県
- 最終学歴: 米国ハーバード大学心理学部 博士課程修了
- 専門分野: 臨床心理学、発達心理学
- 職歴: ハーバード大学研究員(5年)、大阪大学人間科学部教授
専門分野について一言: 「心の成長とは、自己理解の旅でもあります。その旅のお手伝いができれば幸いです。」
毎日が“これでいいのかな…”の連続だった私へ
朝の支度でバタバタ、
帰ってきたら忘れ物、
そして寝る前のひと悶着…
ADHDの子どもとの毎日は、休まる暇がない
──そんな日々に、ココロがすり減っていませんか?
- 気が散って話を聞いてくれない。
- じっとしていられず、すぐ立ち歩く。
- 感情が爆発して、止めようがない…。
どれも「わざと」じゃないって、頭ではわかってる。
でも、
- うまくいかない現実に、イライラしてしまう。
- 叱ってばかりの自分を責めて、泣きたくなる夜もある。
「『なんでできないの?』と責める毎日から、『わかってあげられる私』へ──《3週間集中再安心サポート》」は、
ADHDの「育てにくさ」に毎日向き合ってきたお母さんが
怒りや不安を手放し、
「この子らしさ」を受けとめていくための個別サポートです。
こんな方におすすめです
- 注意してもすぐ他のことに気が逸れてしまう
- じっとできず、席に座らせるだけで疲れてしまう
- ちょっとしたことで怒り、叩いたり叫んだりする
- 何をやっても変わらない気がして、自信をなくしている
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 2月5日(木)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと1名様限定』
※銀行振込限定・先着順
そして──
ADHDの子どもとの関わりに安心感が生まれてきた今、
ふと「自分の人生」のことを考える時間が増えてきたあなたへ。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
「母としての安心」を手にしたその先に、
「私としての人生」をもう一度デザインし直す3週間。
子どものことばかりに必死だった毎日から、
自分のココロを取り戻すための、次のステップです。
- 子どもの特性を受け入れられるようになってきた
- でも、自分の人生にはまだ満たされなさが残っている
- 「母としての役割」だけじゃない生き方を築いていきたい
このプログラムでは、
「子育てを通して得た安心」を土台に、
「私自身を主語にした生き方」へとつなげていきます。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
「ちゃんとしてるのに、苦しい」
「頑張ってるのに、うまくいかない」
——そんな違和感を抱えたまま、ずっと我慢していませんか?
LINEで3分セルフ診断ができます。
あなたの“今の感覚”の正体が、見えてきます。
「どうしてこの子だけ、言うことを聞けないの?」から始まる毎日

朝、準備が進まない。
- 着替えが途中で止まり、
- おもちゃを触っていたり、
- 兄弟にちょっかいを出したり。
やっと始めたと思ったら、
また別のことを始めてしまう…
そんな子どもの様子に、
あなたは何度「早くしなさい!」と声を上げてきたでしょうか。
そしてその後に、
罪悪感に押しつぶされそうになるんですよね。
- 「また怒っちゃった」
- 「本当はもっと優しくしたいのに」
──そんな思いを、ずっと繰り返してきたはずです。
まずは、
そうした「困った行動」の背景にある
「脳の仕組み」から見直していきましょう。
あなたが悪かったわけじゃないし、
あの子がわざとやってるわけでもありません。
困った行動には、「脳の仕組み」という背景がある
ADHD傾向の子どもは、
- 「集中を保つ」
- 「指示を最後まで覚える」
- 「気持ちを切り替える」など
がとても苦手です。
これらは性格ではなく、
脳の
- ワーキングメモリ
- 実行機能
といった領域が関わっています。
たとえば、
忘れ物が多いのは「やるべきことの優先順位を整理できない」こと
が背景にあります。
気がそれてしまうのは、
「目の前の刺激に反応しやすい神経特性」があるからです。
本人の意思でコントロールできるものではなく、
「そうなってしまう」脳の仕組みがあるということ。
だからこそ、
- 「何度言っても聞かない」
- 「ふざけてるの?」
と見えてしまう行動も、
根っこから見方が変わっていきます。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「叱っても直らないのは、私のせい?」
そんなふうに自分を責めてしまっていた方へ。
ADHDの本質を知れば、子どもとの関係が変わりはじめます。
-

-
参考子どものADHD(注意欠如・多動症)とは?原因、症状・40代母親ができる対策と対応
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 近年、子どもたちの中に「ADHD(注意欠如・多動症)」という言葉を耳にすることが増え ...
続きを見る
頭ではわかっていても、
毎日のやり取りの中では、
やっぱりイライラしてしまいますよね。
- 「またか」
- 「なんで今それ?」って
──冷静ではいられない瞬間、たくさんあったはずです。
そんなふうに感じてしまう自分も、
ちゃんと理解される必要があります。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
- 「何度言っても直らない…」
- 「落ち着きがなさすぎる…」
そんなふうに悩んでいる方へ。
ADHDの不注意・多動・衝動性は「努力不足」ではないという視点から、怒ってばかりの関係を見直せる記事をご用意しました。
👉 ADHDの不注意・多動・衝動性に困ったとき、「怒る以外の関わり方」を考える
-

-
参考ADHDの「不注意・多動・衝動性」は「努力ではできない」─怒られてばかりの子に必要な視点とは【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 怒りたくないのに、 また怒ってしまった。 食事中に立ち歩く 話を聞かない 準備がまっ ...
続きを見る
まずは、親の「イライラ」への理解から始めよう
- 何度注意しても通じない。
- どう伝えても響かない。
──そのもどかしさの蓄積が、イライラという形で爆発してしまう。
あなたはきっと、
子どもを変えたかったわけじゃないですよね。
ただ
- 「通じ合いたい」
- 「わかってほしい」
と願ってきた。
でもその願いが届かない日々に、
気づかぬうちに疲れ果ててしまっていたんですよね。
ポイント
だから、
まずは「怒ってしまう自分」にも理由があると知ってください。
怒りは、
理解されないつらさの裏返しです。
そこにフタをしないことが、
関係を変える第一歩になります。
子どもの行動に振り回される毎日だからこそ、
改めて
「ADHDとはどういう特性か」をシンプルに整理しておきましょう。
診断名ではなく、
「日常の中の行動」として捉えていく視点です。
ADHDとは?注意・多動・衝動の3つの軸で見る
無料LINE診断|今のあなたに必要なサポートは?
『何から始めればいいかわからない…』そんなあなたへ。
LINEで「数字」を入力するだけで、今のあなたに合ったサポート商品を診断できます。
今すぐLINEに【 4 】と入力してください。
「怒ってしまう私」から抜け出すヒントと、ぴったりの理由が届きます。
ADHDは、主に次の3つの特性で説明されます。
- 注意がそれやすい(集中が続かない)
- 多動的で落ち着きがない(体が動いてしまう)
- 衝動的に行動する(つい言っちゃう/やっちゃう)
ポイント
この3つのうち、
どれが目立つかは子どもによって違います。
そして、
年齢や場面によっても変化していきます。
たとえば、
- 幼児期は走り回る・騒ぐなどの多動が目立ちやすく、
- 学童期には忘れ物やうっかりミスといった「注意の抜け」
が気になるようになります。
重要なのは、
「本人にとって、それが『自然な反応』になっている」という視点です。
問題を正すのではなく、
背景を理解してあげることで、
あなたのまなざしも、少しずつ変わっていきます。
「ADHDかも…」と思ったとき、何から始めればいい?
うちの子だけ、なんだか違う
──そう感じはじめたきっかけは、毎日の小さな「ひっかかり」が重なっていく中にありました。
- まわりの子と同じように声をかけているのに、伝わっていないように見える。
- 何度言っても変わらなくて、どう接したらいいのかわからなくなっていく。
けれどそれを言葉にするのが怖くて、
- 「まだ大丈夫」
- 「気のせい」
と、自分に言い聞かせていた時期もありましたよね。
でも、本当は気づいていた。
この子には、
もしかすると何か「特性」がある
──そんな思いが頭をよぎったとき、
いちばん揺れていたのは
子どもの様子ではなく、
自分自身の気持ちでした。
- どうしたらいいのかわからない。
- 誰に相談すればいいのか、どこから始めればいいのかも整理がつかない。
そのまま何日も過ぎていったと思います。
だからこそ最初に必要なのは、
「診断を受けるかどうか」よりも前に、
- 「この子にとって、今何が起きているのか」
- 「自分は何に戸惑っていたのか」
を静かに見つめ直す時間です。
それが、「始めやすい一歩」になります。
ポイント
ADHDという言葉は、
診断名というより、
「今この子がどういう傾向をもっているか」を捉えるための道具です。
関わり方を変えるのではなく、見方を整理することから始まります。
「まず何をすればいいの?」
──そう悩んでいた方に向けて、こちらの記事でも整理しています。
▶ 【✅ 補助No.2|「もしかしてADHD?」と気づいたときに読む記事】
ADHDは「性格」ではない。「わざとじゃない」理由を知る
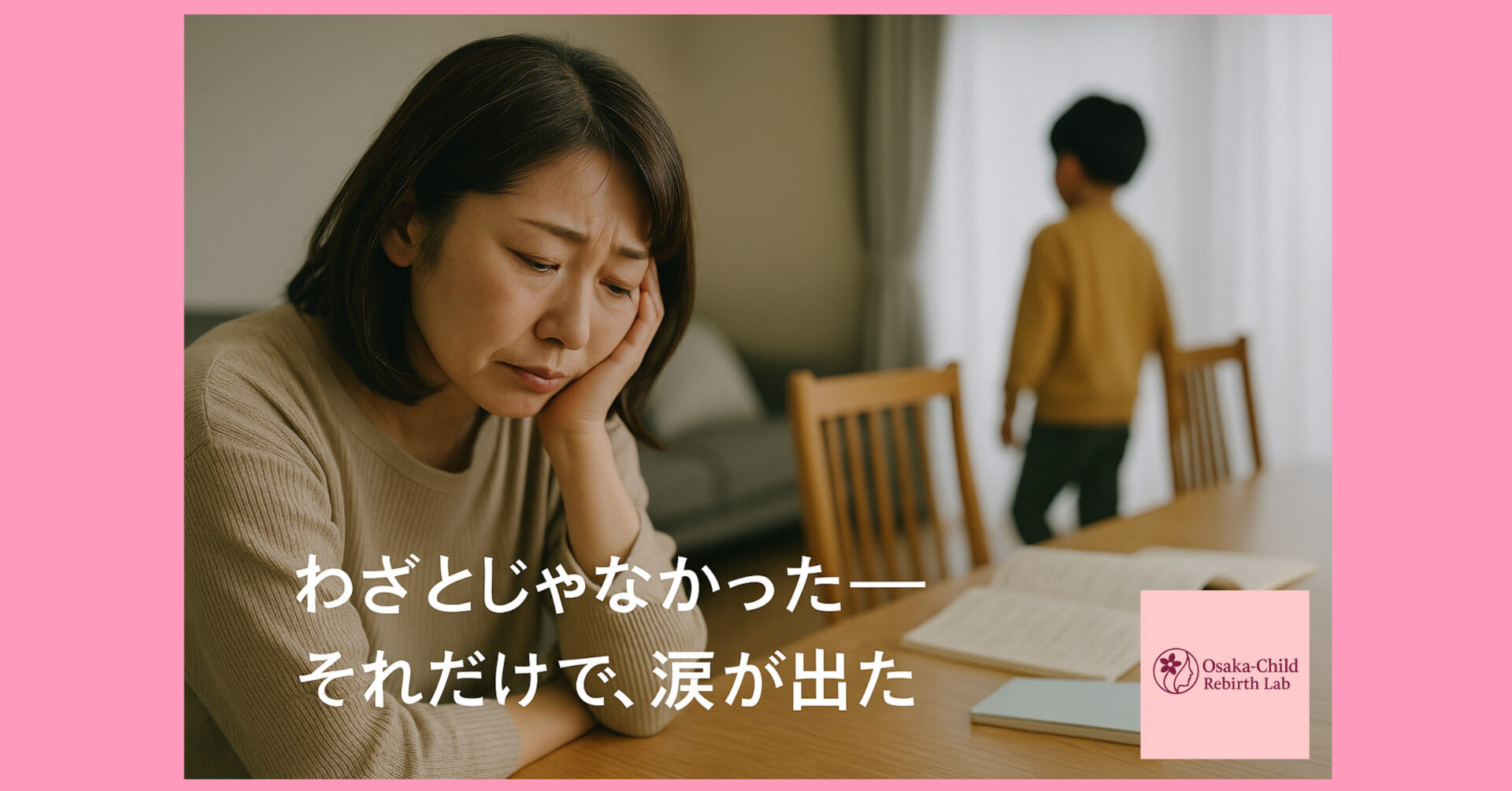
- 「ふざけてるだけなんじゃないの?」
- 「怠けてるだけじゃないの?」
──そんなふうに言われてきた言葉が、あなたの中でも抜けなくなっていませんか?
- 怒っても変わらない日々。
- 伝えたつもりでも伝わらない。
でもどこかで、
「この子は本当は悪くないんじゃないか」とも感じてきたはずです。
ここでは、
「性格の問題」だと誤解されがちなADHDの特性を、
もっと丁寧に、
もっと優しいまなざしで見直していきます。
何度叱っても直らないのは、本人の意思の問題じゃない
- 「昨日も注意したよね」
- 「さっき言ったばかりだよ」
- 「何回言えばわかるの?」
その言葉の奥には、
「この子は直す気がない」と感じてしまう
親のつらさがありますよね。
でも
ADHD傾向の子どもにとっては、
「聞いたことを保持して行動につなげる力」
そのものに弱さがあります。
つまり、「聞いていない」のではなく、
聞いたことを処理して動くまでのステップが抜け落ちやすいということ。
何度も叱ってしまうのは、
あなたが無関心だったからではなく、
「わかってほしい」と必死だったからのはずです。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「ちゃんと叱ってるのに、どうして直らないの?」
そんなふうに思い悩んできたあなたへ。
性格ではなく「脳の特性」だと知れば、見える世界が変わります。
-

-
参考ADHDと「性格の違い」を誤解していた私へ|怒っても直らない本当の理由【児童精神科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「どうして何度言っても直らないの?」 「わざとやってるんじゃないかと思ってしまう」 ...
続きを見る
さらに傷つくのは、
「育て方のせいだよ」と遠回しに言われるとき。
本当にそうなのか、
自分を疑いすぎてしまう瞬間があったはずです。
でも、ちゃんと知ってほしいことがあります。
「怠けてる」「だらしない」という誤解を手放す
たとえば、
- 宿題をやらない
- 支度が遅い
- 片づけができない
そういった行動が続くと、
「やる気がない」と見えてしまいますよね。
でもADHDの子は、
行動の手順を頭の中で整理して、
次に何をすればいいかを実行する力がとても弱いんです。
それは怠けているのではなく、
「どうすればいいかがわからないまま止まってしまう」という状態。
「だらしない」という言葉の裏には、
本人も困っているのに助け方がわからない構造があります。
おそらく、
あなたはそれにうすうす気づいていたはずです。
「この子、本当は悪気がないのに、なんで責められるんだろう」
──そんな気がして、苦しかったこともあったんじゃないでしょうか。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「うちの育て方が悪かったのかな…」
そんなふうに、自分を責めてしまっていた方へ。
ADHDの「本当の原因」を、最新の研究とともにお伝えします。
-

-
参考ADHDの原因は「家庭環境」なの?──育て方を責め続けてきた私が「関係の整理」で見えてきたこと【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 ADHDの子どもが 何度言っても忘れ物が治らなくて、 「ちゃんとしなさい」ってまた言 ...
続きを見る
それでも、
「どうしてこの子だけこんなに…」という気持ちが残るのは自然なこと。
そこで次は、
もう少し科学的な視点から、ADHDという特性を捉えてみましょう。
脳科学が教えてくれる、行動の理由と対処の方向性
ADHDは、
脳の前頭前野という「司令塔」の働きに特性がある
ことがわかっています。
このエリアは、
「今何をすべきかを判断し、順番に実行する」役割を担っています。
その働きが弱いと、
- 情報を記憶する
- 切り替える・抑える
といった一連の流れがスムーズにいきません。
- 「やらなきゃいけないのに、できない」
- 「止まりたいのに、止まれない」
ADHDの子どもたちは、
そんな「自分でもコントロールできない困難」と日々向き合っています。
つまりこれは、
あなたや子どものせいではなく、
特性として備わっているものなんです。
支援とは、
努力させることではなく、
仕組みの違いを理解し、
関わり方を変えていくこと──
その視点を持てるだけで、親子関係の空気はゆるんでいきます。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「もしかして、私もADHDなのかな…?」
そんな不安を抱えたことがある方へ。
実は「母親の特性」が子どもに影響しているケースもあるんです。
-

-
参考【早期対応】ADHDの原因が母親の遺伝の確率は約70%|隠れADHDが母親に存在
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 あなたの子供が少し落ち着きがない、あるいは注意が散漫していると感じることはありません ...
続きを見る
「がんばってない」のではなく、「できない」だけだった子どもへの理解
- 「なんでまた忘れてるの?」
- 「昨日も言ったよね?」
そんなふうに何度も言ってしまう自分が、
ずっと嫌でした。
- やる気がないわけじゃない。
- サボってるんでもない。
それくらい、
わかっているつもりだったんです。
でも毎日続く「できなさ」の前では、
余裕がなくなってしまう瞬間があって…。
それでもやっぱりココロのどこかで、
「この子、本当はがんばってるんじゃないか」って
思っていたあなたがいました。
- 何がわからないのか、
- どこで止まっているのか。
そこに目を向けるだけで、
子どもの表情は少し変わっていく。
「できない」には、理由があります。
だからこそ、
「がんばればできる」と言い続けるのではなく、
「どんなサポートがあれば前に進めるのか」を一緒に考えていくこと
が大切なんですよね。
「できない」だけだった
──そう思えたとき、あなたは責める気持ちよりも、
支えたい気持ちが自然とにじんくる体感がえられます。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「がんばらない子」じゃなかった。
実は「ADHDの特性でできなかった」と気づいたとき、見え方が変わります。
ADHDの子を怒ってばかりいた母親が、「支える関係」に変われた理由とは?
👉 ADHDの子を責めてきた私が、「できない理由」に気づけた話
-

-
参考ADHDの子どもは怠けてるんじゃない──怒ってばかりいた私が知った「できない理由」【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「なんでこんなに怒ってしまうんだろう」 毎晩そうやって反省して、 寝顔を見ながらため ...
続きを見る
症状の現れ方と「年齢による違い」を知っておく

子どもの「困った行動」が続いていると、
- 「うちの子だけ浮いてる」
- 「成長が遅れてる」
と感じることってありますよね。
でも、
それってほんとうに「遅れ」なのでしょうか?
もしかしたら、
「その年齢の子に特有の現れ方」というだけかもしれません。
ADHDは、
年齢や環境によって、
症状の出方や困りごとの「顔」がガラリと変わります。
ここからは、
幼児期〜思春期までのステップを一緒に見ていきながら、
あなたの子どもにとっての「今」を、
少しだけ違う角度から見つめてみましょう。
幼児期・小学生・中高生──どんな特徴がある?
たとえば
幼児期のADHD傾向では、
- 「落ち着きがない」
- 「話を聞けない」
- 「急に走り出す」
といった、
「身体的な多動」が目立ちます。
小学校に上がると、
じっと座って授業を聞く場面が増え、
今度は
- 「集中できない」
- 「忘れ物が多い」
- 「指示が通らない」
といった「注意の持続困難」が前に出てきます。
中学・高校になると、
外見的な多動は少なくなっていく一方で、
- 「物事の段取りが立てられない」
- 「時間感覚がズレている」など、
実行機能の弱さが課題になっていきます。
つまり、
年齢によって
「問題の見え方」が変わるという流れがあります。
だからこそ、
単に「性格がだらしない」と決めつけてしまうのは、すごくもったいない。
こうして見ると、
同じADHD傾向の子でも、
年齢によって困りごとの質がまったく違っていることがわかります。
だから、
「うちの子の今の姿」が、
どういう段階にあるのかを知っておくことがすごく大事なんですよね。
年齢によって困りごとの「顔」は変わる
発達って、
「一直線」じゃないですよね。
できることが増えても、
別のところでつまずいたり、
今まで平気だったことが急に苦手になったり──
その波のような揺れを、
あなたはずっとそばで見てきたのです。
ADHDの子は、
その揺れが特に大きい。
しかも、
「できるときはできるのに、なんで今日は無理?」ということが本当に多い。
でもそれは、
甘えてるからでも、
気分屋だからでもなくて、
脳のエネルギー配分にばらつきがあるという背景があります。
だから、
「昨日できたんだから、今日もできるはずでしょ」と責めることは、
本人にとっては
「無理してた自分を否定される」ような感覚になります。
あなたがその違いに気づいてあげられたら、
きっとこの子は救われます。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「この子の『困った行動』、いつまで続くの…?」
そんなふうに感じていた方へ。
ADHDの症状は、年齢とともに「現れ方」が変化します。
👉 乳幼児・小学生・思春期…年齢ごとのサインを見逃さないために
-

-
参考ADHDの年齢別特徴を知る|小学生から成人までの症状の変化と関わり方【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 朝、ADHDの子どもの忘れ物に追われて息が上がる。 準備はしたのに、また鍵と連絡袋が ...
続きを見る
ここまで「年齢による違い」を整理してきましたが、
実はそれよりもっと大事なのが、
「うちの子の場合はどうか?」という視点です。
ADHDはひとつの型じゃありません。
その子の「人生まるごと」を見ていく姿勢が、いちばんの理解なんです。
「うちの子の場合」で捉える視点が大切
「ADHDの子はこうです」と言われても、
「うちの子はちょっと違う…」と感じたこと、ありませんか?
それ、
あなたの感覚のほうが正しいんです。
診断名よりも大事なのは、
目の前の子どもが、どこで・どんなふうに困っているか。
そして、
それを毎日見ているのは、
誰でもない「あなた自身」です。
たとえば、
- 教室で静かにしていられるけど、家では癇癪を起こす。
- 学校では怒られないのに、家庭でだけ問題が起きる。
──そういうとき、
「家では甘えてるだけ」と言われることもあるけど、
実際は、
家だから安心して「抑えきれない困りごと」が出ているケースも多いです。
- 「この子にとっての安心」
- 「この子なりの頑張り」
それを知っているのは、
親であるあなたにしかできない観察です。
だからどうか、自信を失わないでください。
診断書やチェックリストじゃ測れない
「その子らしさ」を、
あなたはもう見つけてきたはずです。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「ADHDとASD、どう違うの?」
そんな疑問や迷いが生まれたとき、診断名の境界で悩む母親が安心して整理できる視点と、関わり方のヒントをまとめています。
👉 診断名だけでは見えなかった「違い」を、家庭での関わり方から見つめ直す
-

-
参考ADHDとASDの違いとは?──ADHDと診断された子どもに見え始めたASD傾向との重なり【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 何度言っても伝わらない。 「さっきも言ったよね?」が、口癖になっていた。 それなのに ...
続きを見る
年齢ごとに変わる関わり方──支援は「何歳からでも」始められる
「どうしてもっと早く気づけなかったんだろう」
そうやって、自分を責め続けてきましたよね。
でも
ADHDの子どもにとって、
「支援はいつからでも遅くない」という視点が、
何より大事なんですよね。
たとえ中学生であっても、
関わり方を見直すことで、
親子の関係が変わり始めます。
困っているのにうまく伝えられなかった子が、
「わかってもらえた」と感じた瞬間に、
ようやくココロを開いてくれる場面もあるんです。
ポイント
ADHDは、
年齢によって特性の現れ方が変わっていきます。
だからこそ、
「今のこの子」に合った関わり方が必要になります。
支援とは、
教え方を正すことではなく、
その子の発達段階と特性を踏まえて、一緒に考えていくことなんです。
年齢に関係なく、
関係性はいつでも立て直せます。
「今からできることがある」
──そう思えた瞬間から、支援はもう始まっていると言えます。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「支援するなら早いほうがいい?」
そんな不安を感じている方へ。
ADHDの支援は「何歳からでも」始められるという視点から、関わり方のヒントをお届けします。
👉 支援に出遅れた…と悩んでいた私が、「今からでも遅くない」と感じられた理由
-

-
参考ADHDの支援は何歳から始められる?|支援してこなかった私が「今からでも遅くない」と感じられた理由【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 怒りたくて怒ってるわけじゃない。 それなのに毎日、怒ってしまう。叱ってしまう。 何度 ...
続きを見る
幼児期から成人期までのADHDの特徴と症状
ADHDは、
年齢とともに「困りごとの出方」がはっきり変わります。
- 幼児期はADHDの多動・衝動が前面に出て、止まらない体と気持ちに寄り添う毎日になります。
- 小学生期はADHDの不注意が学習や忘れ物に直結します。
- 思春期〜成人期はADHDの疲れやすさと自己管理の難しさが中心になります。
年齢別の特徴を押さえると、関わり方は具体化します。
- 短い合図で切り替える
- 予定と手順を見える化する
- 課題は小さく分ける。
- 感情は先に落ち着けてから伝える。
必要に応じて外部支援も組み合わせます。
責めるより、仕組みで支える。
今日から整え方を変えれば、暮らしは少しずつ軽くなります。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「ADHDの困りごと、年齢で顔が変わってきた…」と感じた方へ。
幼児期から成人期までの変化をやさしく整理し、家庭と学校の関わり方を具体化した解説です(小児神経科医監修)。
👉 年齢で変わるADHDの特徴と関わり方を一度に整理(小児神経科医監修)
-

-
参考ADHDの年齢別特徴を知る|小学生から成人までの症状の変化と関わり方【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 朝、ADHDの子どもの忘れ物に追われて息が上がる。 準備はしたのに、また鍵と連絡袋が ...
続きを見る
「病院に行くべき?」と迷ったときに、大事にしてほしいこと

「やっぱり病院に行くべきなのかな…」
そう思いながらも、
なかなか一歩が踏み出せずにいるあなたへ。
- 「もし診断されたらどうなるの?」
- 「逆に診断されなかったら、今の困りごとはどうしたらいいの?」
──そんなふうに、
ぐるぐると考えすぎて疲れてしまうこと、ありますよね。
ここでは、そんなあなたが少しでも楽になれるように、
- 「受診する前に知っておきたいこと」
- 「病院の選び方」
そして「診断の本当の意味」について、
やさしく整理していきます。
「“私のせい”って、もう思いたくなかった」
「また忘れてる…」
「なんでじっとしてられないの?」
わかってる。わざとじゃないって。
- でも…もう限界だった。何度言っても忘れる
- 注意しても
- 席を立ち
- 急に大声を出す
ルールも守れず、すぐにかっとなる子どもに、
「ダメな母親」のレッテルを自分に貼りつけていた。
「怒ってばかりの毎日から、『この子らしさ』に寄り添える私へ──《3週間集中再安心サポート》」は、
ADHDの特性に悩む子育ての日々に、
「正解」ではなく「安心」を取り戻していく3週間の個別サポートです。
こんな方におすすめです
- 不注意・多動・衝動性のある子どもへの関わりに、疲れ切っている
- 「しつけが悪い」と周囲に思われている気がして、外出すら億劫
- 怒る→自己嫌悪の無限ループから抜け出せなくなっている
- 母親としての自信が持てず、誰にも本音を言えない
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 2月5日(木)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと1名様限定』
※銀行振込限定・先着順
▶ ADHDの「育てにくさ」に寄り添える私になる3週間を見る
そして──
ADHDの子どもに向き合いながらも、
「母としての安心」の先に、
「私自身の人生」も取り戻したいと願いはじめたあなたへ。
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
ADHD育児で後回しにしてきた「私自身の想い」に、
今こそ本気で向き合う3週間。
「母親として頑張る」だけの毎日を終わらせ、
これからは「私を大切にする人生」を始めませんか?
- 子ども中心の生活に、自分の感情や希望を押し込めてきた
- 「何のために生きているのか…」と感じる瞬間がある
- 「この子の母」だけじゃない、「私」としての人生を再設計したい
このプログラムでは、
ADHD育児を乗り越えてきた「あなたの本音」と向き合い、
人生を取り戻す準備を一緒に進めていきます。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
「医療に行く前」に知っておきたいこと
病院に行けば、
子どもの困りごとが全部解決する。
──そう信じたくなる気持ち、よくわかります。
でも、診断されたからといって、
すぐに状況が劇的に変わるとは限らないんですよね。
それよりもずっと大切なのは、
子どもの日常の困りごとに、どう寄り添っていけるかなんです。
たとえば、
- 「じっとしていられない」
- 「忘れ物が多い」など
の行動があっても、
その子らしいペースで安心して暮らせているなら、
今すぐ医療に結びつける必要はないこともあります。
でももし、
- あなた自身が「もう限界…」と感じていたり、
- 学校や家庭の中で疲れきっているようなら、
それはすでに
「支援が必要なサイン」だと受け止めてあげてください。
- 「ちゃんと育ててあげられてない気がして、つらい」
- 「怒りたくないのに、毎日怒ってばかり」
──そんな思いを抱えてここまで頑張ってきたはずです。
「医療に行くかどうか」は正解があることじゃないからこそ、
どんな判断をするにも、
あなたの心に安心の土台が必要です。
ここからは、
実際に病院を選ぶときの目安についてもお伝えしていきますね。
受診するならどんな病院?何科?
「どの病院に行けばいいのか、まったくわからない」
──そんな戸惑いを抱えているお母さんはとても多いです。
ADHDの診断や支援に関しては、
以下のような診療科が対象になります:
- 小児神経科・児童精神科(専門性が高い)
- 小児科(医師によって対応に差あり)
- 心療内科・精神科(中学生以降の場合)
ただ、
現状ではどの病院も予約が取りづらかったり、
初診まで数ヶ月待ちというケースも少なくありません。
でもそれだけ、
「見てほしい」と願う親子がたくさんいるという証拠でもあるんです。
診断を前提にするのではなく、
- 「今、困っていることを整理したい」
- 「第三者の視点を聞いてみたい」
そんな気持ちで医療につながることも、立派な一歩です。
診断名よりも、
あなたの「困ってるんです」と伝える勇気が、
何より尊いことだと私は思います。
病院に行くことがゴールではなく、
「この子と向き合いながら、一緒に歩いていける環境を整える」ことこそが、
本当の目的です。
次は、
「そもそも診断って何のためにあるの?」という大事なテーマについてお話ししますね。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「ADHDの診断、どの科に行けばいいかわからない…」
そんな迷いを解消するために、小児科・発達外来・小児神経科・精神科の違いと選び方を医師監修で詳しく解説しました。
-

-
参考ADHDの診断は何科に行けばいい?──「小児科?発達外来?」と迷ったときの正しい選び方を解説【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 わが子のADHDらしさに気づいてから、 毎日が小さな引っかかりの連続になってしまう。 ...
続きを見る
診断がゴールじゃない。支援の第一歩として
診断って、
「ラベルを貼ること」ではありません。
それは、
子どもが少しでも生きやすくなるための「通過点」のようなものです。
たとえば、診断がついたことで…
- 学校での合理的配慮が受けられる
- 福祉サービスの対象になる
- 家族や周囲の理解が得られやすくなる
──そんなプラスの変化が起こることもあります。
でも反対に、
- 「診断されたから」
- 「ADHDだから」
と、周囲がその子を「決めつける目」で見てしまうこともあるんですよね。
だからこそ、
いちばん大切なのは、
親であるあなたのまなざしです。
- 「この子は困ってる」
- 「こんなふうに頑張ってきた」
──そんな実感があるからこそ、今ここにいるのです。
診断がついても、つかなくても、
「この子の味方でいよう」と思っているその気持ちが、
もうすでに支援なんです。
診断がなくても支援はできる?「迷っている」母親への視点
「まだ診断されていないから、何も始められない」
──そうやって、ずっと足踏みしてきました。
ADHDのような特性って、
診断の有無ではなく、
「日常でどれだけ困っているか」
が大事なんですよね。
- 家では忘れ物が多くて何度も声をかけて
- 学校では注意されてばかり
そんな日々が続いていたら、
もうその時点で「支援が必要な状態」だった
のです。
それでも、
「診断されないとダメ」と思い込んでいたから、
誰にも言えずにいました。
でもある日、
支援センターで「お母さんもつらいですよね」と言われて、
涙が止まりませんでした。
この子のことだけじゃない。
あなたはこの記事で、
私自身が安心できる場所が必要だったんだって、
ようやく気づけたんです。
迷っているその気持ちごと、
相談していい。
診断がなくても、
関われる人はちゃんといます。
まずは
「困っていることがある」と伝えるだけで、
支援の扉は少しずつ開いていきます。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「診断が必要なのか、ずっと迷っている」
そんなあなたへ。
病院に行く前に知っておきたい、「家庭でできる関わり方」をまとめました。
👉 ADHDと診断される前でもできる、「安心して関わる」ための第一歩とは?
-

-
参考ADHD 診断を受けるべきか迷ったとき──「まだ病院に行けていない母」が知っておきたい関わり方【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「また怒ってしまった」 そう感じる夜が、何度もありましたよね。 わが子の忘れ物やミス ...
続きを見る
診断は何科へ行けばいい?発達外来・精神科の違い
- 「発達外来ってどこにあるの?」
- 「精神科って、大げさじゃない?」
そんなふうに、
医療機関の名前を見ただけで、
ココロが引いてしまうこともありますよね。
ADHDの相談先としてよく出てくるのが、
- 「小児神経科」
- 「児童精神科」
- 「発達外来」
といった専門機関です。
だけど、
いきなり専門病院に行くのが不安なときは、
まず
小児科や保健センターに相談するのでも大丈夫です。
「いきなり診断」ではなく、
「今の困りごとを整理したい」
──その気持ちを出発点にしていいんですよね。
実際、
あるお子さまが最初にかかったのは、
町の小さな小児科でした。
そこから紹介状をもらって、
ようやく専門医につながることができた。
だから、
「何科を選ぶか」よりも、
「今の気持ちを受け止めてもらえる場所かどうか」
が大切だったと、あとから気づきます。
「この子、どう関わればいいんだろう」
そう感じたときが、
最初の受診タイミング。
どこに相談するか悩んだときは、
「ここなら話せそう」と感じた場所から始めていいんです。
「診断したほうがいいのかな」と考えるたび、
胸の奥が締め付けられる。
- ADHDを「名前」だけで終わらせたくないし、
- 誤解のまま前に進むのも避けたい。
次のセクションでは、
受診の前にココロと情報を整える方法と、
ADHDの改善につながる病院選びの視点をお伝えします。
【✅ 補助No.18】
ADHD診断で活用できるカウンセリングの効果と進め方
子どものADHDの診断を考えるだけで、
体もココロも固くなってしまう日がありますよね。
そんなときこそ、
カウンセリングを「診断準備の場」として使えます。
カウンセリングでは、
ADHDの困りごとを日常の言葉で整理し、
強みと課題を分けて書き出します。
- 家や学校での出来事
- 時間帯
- きっかけ
- うまくいった工夫など
を簡単に記録するだけで、
ADHDの経過が一枚の地図になります。
ポイント
この地図を医師に見せることで、
診断の精度が上がるだけでなく、
ADHDの環境調整や支援策が具体化します。
診断の有無だけを目的にせず、
「これからの暮らしを軽くする」ために、
専門家と一緒に歩みを整えていきましょう。
記録と気持ちの整理ができたら、
次は安心して続けられる病院選びです。
診断を受けたあと、生活を改善できるかどうかは、
受診先の選び方で大きく変わります。
診断のための病院選び──改善につながる選び方のポイント
ADHDの診断は、
受けて終わりではなく、
その後の関わりと環境づくりにつなげることが大切です。
だからこそ、
病院選びは
「通いやすさ」だけで決めないことがポイントになります。
ポイント
選ぶときは、
ADHDに詳しい
- 小児神経科
- 児童精神科
- 発達外来
を軸にします。
そして、次の点を事前に確認します。
- ADHDの評価方法が明確で、家庭や学校への具体的提案があるか
- フォローの頻度や、学校・自治体支援との連携があるか
- 薬以外の支援(環境調整・スキルトレーニング)も提案してくれるか
予約の取りやすさや待機期間、
レポートの内容も生活を左右します。
家に合う提案をしてくれる医療との出会いが、
ADHDの子どもとのココロが安定した暮らしを確実に前に進めます。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「診断は受けたのに、次の一歩が見えない…」
そんなときは、ADHDの診断後に「フォローが続く」病院の選び方と受診準備を、母親目線でわかりやすく整理しています。
👉 ADHD診断後の病院選び|フォローが途切れない相談先と受診準備のチェック
-

-
参考ADHD診断を受けたのにフォローなし…9歳からの病院選びで後悔しないために【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 ADHDと診断されたあの日(6歳)から、 あなたは毎日の子どもの小さなできないことが ...
続きを見る
学校・家庭でどう支える?「関わり方」の実践知

ADHDのことを知っても、
実際の生活の中で「どう関わるか」となると、
迷いが出てきますよね。
怒らないようにしようと思っても、
毎朝のバタバタで爆発してしまったり、
先生と連携しようとしても、
「ちゃんと育ててください」と言われたような気がして、
深く傷ついてしまった経験があるはずです。
ここでは、
- 「学校との関係」
- 「家庭での対応」
- 「この子に合った工夫」
の3つに分けて、
実践的な「関わり方の視点」を整理していきます。
うまくやろうとしなくて大丈夫。
「つながりなおしたい」という気持ちさえあれば、
きっと道は見えてきます。
学校との関係をこじらせないためにできること
学校とのやりとりに、
しんどさを感じているお母さんはとても多いです。
先生からの何気ない言葉に、
「私の育て方が悪いって言われた気がする」
──そんなふうに、ココロがざわついてしまった経験があるはずです。
でも、
先生もまた「どう対応すればいいのか」がわからないまま、
「問題行動」だけを見てしまっているケースが多いんです。
そこで大切になるのが、
情報共有です。
たとえば…
- 朝の準備が苦手な理由
- 集団の中で気が散りやすい場面
- 叱られた後にパニックになる理由
こういった背景を、
できるだけ「責めずに、短く、事実として」伝える
ことで、
先生も「そういう特性があるんですね」と
理解しやすくなります。
連絡帳でも、
短いメモでもいいんです。
あなたのまなざしが伝われば、
少しずつ信頼の糸が結ばれていきます。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「学校に行けないのは、ADHDのせい?」
そんなふうに感じているあなたへ。
不登校の背景にある「困りごと」と、親としてできる関わり方を具体的に解説しています。
-

-
参考ADHDの子どもの不登校対応|声をかけても動けなかった朝から最短復学へ【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 朝、「学校行こう」と声をかけても、 ADHDのわが子は布団の中で固まったまま。 時間 ...
続きを見る
家庭でできる支援と、やってはいけない対応
家の中では、
どうしても「できて当然」という目線になりがちです。
- 「また忘れたの?」
- 「何回言えばいいの?」
そんな言葉を、
あなたも何度も口にしてきましたよね。
でも、
ADHDの子どもたちは、
「わかっていても、できない」という
困りごとを抱えています。
これは意志の弱さではなく、
脳の働き方の違いです。
だからこそ、
「できないなら教えればいい」ではなく、
「できるように環境を整える」という視点が必要になります。
たとえば…
- 毎日の忘れ物 → 玄関に「持ち物ボード」を設置する
- 宿題ができない → 時間を区切って一緒に始める
- 癇癪がひどい → 気持ちが落ち着く「安心スペース」をつくる
そして何より大切なのは、
「怒らなくても伝わる関わり方」を探し続けること。
その努力を、あなたはずっとしてきたはずです。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「もしかして、ADHDが原因で学校に行けないの…?」
そんな不安を抱えているあなたへ。
不登校の背景にある「発達特性」と、親としてできる具体的な関わり方を丁寧に解説しています。
「この子に合ったやり方」を見つける視点
マニュアルや専門家のアドバイスが、
どうしても「現実の子育て」には当てはまらないと感じること、
ありませんか?
ADHDの子どもたちは、
いわゆる「普通の方法」が通用しにくいことが多いです。
でもそれは、
「この子のやり方が間違っている」のではなくて、
「この子に合ったやり方をまだ見つけられていないだけ」です。
たとえば…
- 音に反応しやすい → キッチンタイマーで動くきっかけをつくる
- 順序だてが苦手 → やることリストを絵にして見える化する
- 感覚過敏がある → 洋服のタグや素材を変えてみる
その子にとっての「ちょうどよさ」を見つける工夫は、
親子の関係そのものを優しくしてくれます。
うまくいかない日もあるけど、
試行錯誤を繰り返してきたあなたなら、
きっとこの子に合う道を見つけていけます。
“叱る前にできること”を一緒に整えていきませんか?
何度言っても直らない。叱っても伝わらない。
そんな日々に疲れきってしまったあなたへ。
「どう関わればいいのか分からない」と感じるのは、あなたが悪いわけではありません。
家庭の中で、できることから変えていく──
それだけで、親子の関係は少しずつほぐれていきます。
このサポートは、叱るよりも「理解する」土台を一緒に育てていくための3週間です。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「ADHDの子に、つい怒ってばかり…」
そんな関わり方を変えたいと感じた方へ。
「怒らない関係」のつくり方を、家庭での具体的な工夫とともに紹介しています。
👉 「安心して向き合える関係」に変わっていくためにできること
-

-
参考ADHD 怒らない関わり方がわからなかった──怒ってばかりいた私が見つけた「安心の関係」のつくり方【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「毎日、怒ってばかりいる」 そんな自分に落ち込みながらも、 どうしたらよかったのか、 ...
続きを見る
学校に行きづらくなった子どもへの「関わり直し」のヒント
毎朝、
「行きたくない」とうつむく子どもを見て、
どうしていいかわからなくなる日が続いていました。
- 無理に連れていくことが正しいのか
- それとも休ませるべきなのか
何を選んでも、
自分を責めてしまう感覚が消えなかったんですよね。
ポイント
ADHDの特性がある子は、
刺激の多い教室や集団行動のストレスを、
うまく言葉にできません。
でもそれを
「甘えてる」と見られてしまうと、
ますます追いつめられてしまう。
だからこそ、
まず大事なのは
「なぜ行けないのか」を、
一緒に整理していく視点なんですよね。
行けなくなった理由の中には、
- 「わかってもらえなかった悲しさ」
- 「失敗を繰り返す苦しさ」
が隠れています。
ただ学校に戻すことだけを目標にせず、
「安心できる関係を取り戻す」ことから始める。
その関わり直しが、
子どもの心をもう一度前に向かわせる力になってきます。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「学校に行きたくない」と言われて、どうしていいかわからなかった…
そんな経験がある方へ。
ADHDの子どもが抱えやすい「二次障害」と、家庭でできる関わり直しについて、専門家と一緒にやさしく整理しました。
👉 学校に行きたくない子への、ADHD的な背景と関わり方を知る
-

-
参考ADHDの「二次障害」が始まっていた──「もう学校に行きたくない」と言い出した子どもに、母としてできたこと【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 朝、布団から出られない。 小学校のときは何とか登校していたのに、 中学生になって「も ...
続きを見る
音やにおいに敏感な子どもと、どう向き合えばいい?
- 「音がイヤ」
- 「その服着たくない」
- 「教室がくさい」──
そう言われたとき、
- ただの「わがまま」なのか
- それとも何かあるのか
すごく迷ったことがありました。
ADHDの子どもには、
感覚過敏や感覚の調整がうまくできない特性
があることがあります。
ポイント
聴覚・嗅覚・触覚などの刺激に、
本人の意思とは関係なく反応してしまう状態です。
その困りごとは、
周囲から理解されにくく、
- 「わがまま」
- 「過保護」
と誤解されやすいんですよね。
でも、
ただでさえがんばっているこの子に、
さらに
「がまんしなさい」と伝えることが、
どれほどの負担になるか──
それに気づいてから、
「どこが苦しいのか」を一緒に見つけることを意識するができるようになります。
本人も言葉にできない感覚があるからこそ、
「感じすぎてしまう世界」に寄り添うまなざしが必要になります。
工夫の前に、
まず理解があるだけで、
子どもの呼吸は少し楽になっていくはずです。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「着替え・音・におい…こんなに気にするなんて、ADHDの特徴なの?」
そんな不安を感じた方に向けて、ADHDと感覚過敏がある子どもへの関わり方をやさしく整理した記事をご紹介します。
👉 ADHDで感覚過敏のある子どもと、安心して関わるためにできること
-

-
参考ADHDで感覚過敏もある子どもとどう向き合えばよかったのか──着替え・音・においに戸惑い続けた毎日【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 朝から 「この服イヤ!」 「くさい!」 って泣かれて、また今日も疲れた…。 ADHD ...
続きを見る
学校に行けない日が増えると、
胸の奥に重い石を抱えたような感覚になりますよね。
ポイント
ADHDのある子の不登校は、
行きたくない気持ちと行けない理由がいくつも重なって起こります。
次のセクションでは、
そのADHDの子どものココロの動きをとらえながら、
背景を整理しながら、家庭でできる支え方をお伝えします。
ADHDと不登校の関係──原因整理と家庭でできるサポート
ADHDの不登校は
「怠け」ではなく、
脳の特性と環境のズレが積み重なって始まります。
- 授業のスピードについていけない、
- 忘れ物や失敗が続く、
- 友だちとの衝突が増える
──そんな日々が続くと、
教室が安心できる場所ではなくなってしまうのです。
家庭でできるのは、
まず原因を分けて見える形にすること。
- 学習面のつまずきは方法や量を変える
- 人間関係の負担は関わり方や距離を調整する
- 疲れやすさはスケジュールの見直しで減らす
ADHDのある子は
「安心できる場」から少しずつ行動を広げると回復が早まります。
家を責められる場所ではなく、
帰ってこられる安全地帯にしておくことが、
次の一歩を踏み出す土台になります。
家庭で安心の土台が整ったら、
次は「どうやって戻すか」です。
ADHDの復学は早く戻すことより、安定して続けられることが大切です。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「ADHDの子どもが不登校になり、どう支えたらいいかわからない…」
そんな母親のために、「無理に登校させる」のではなく、家庭から安心を整えて最短復学へつなげる方法を整理しました。
不登校から最短復学につなげるためのADHD対応
ADHDのある子を
最短で復学につなげるには、
焦らず段階を踏むことがベストです。
ポイント
環境変化に弱い特性があるため、
急な復帰は再び不登校を招くリスクがあります。
有効なのは「段階的登校」です。
- まずは保健室や別室から始める
- 授業は得意科目や短時間から組む
- 成功体験を重ねて自信を回復させる
同時に、
学校と家庭でADHDに合った配慮を共有することが欠かせません。
- 担任や支援員と連携し、
- 子どもが安心できる条件を整えてから教室に戻す。
この積み重ねが、結果として最短の復学になります。
未来に向けて「また行けたね」と笑える日を、
家庭と学校が一緒につくっていきましょう。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「ADHDの子が不登校になり、朝の声かけで疲れ果ててしまう…」
そんな状況で悩む母親のために、「行けないのは怠けではなく特性」という視点から、家庭でできる安心の整え方と復学への流れをまとめています。
👉 ADHDの子どもの不登校を「家庭から整え、最短復学へつなげる視点」を読む
-

-
参考ADHDの子どもの不登校対応|声をかけても動けなかった朝から最短復学へ【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 朝、「学校行こう」と声をかけても、 ADHDのわが子は布団の中で固まったまま。 時間 ...
続きを見る
親も子も、疲れきってしまう前に。「一人で頑張らない」選択肢
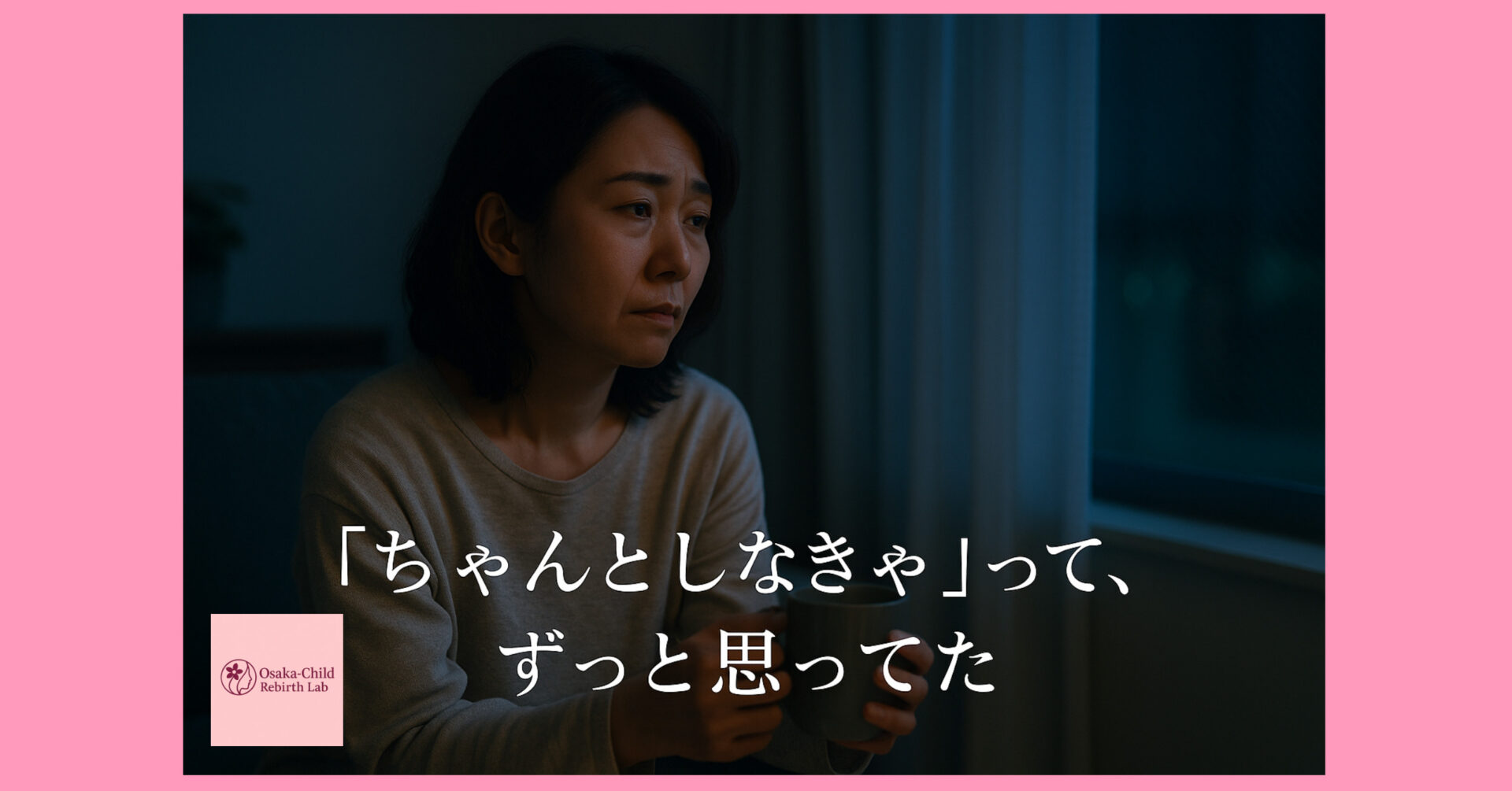
どれだけ知識を学んでも、
工夫しても、
「今日はもう無理…」と、
ココロが折れそうになる日ってありますよね。
- 怒りたくないのに怒ってしまったり、
- もう限界なのに、誰にも助けを求められなかったり。
そんな日々が積み重なれば、
子どものために頑張っているはずの自分が、
どんどん苦しくなってしまうのは当然なんです。
ここからは、
そんな「疲れた私」に目を向けていきましょう。
一人で頑張ることをやめた瞬間から、
親子の関係がゆるみはじめることもあります。
イライラ・不安・疲労感──母親が限界を感じる理由
無料診断|あなたの“心のパターン”を知る
「なぜか毎日イライラしてしまう…」
そんな方のために、LINEで「キーワード」を送るだけで診断できるサービスをご用意しました。
LINEに『ADHD』と入力して送信してください。
あなたのための視点と“安心できる関わり方”が届きます。
ADHDの子どもを育てる日常は、
「予測できないこと」の連続です。
- 明日はどうなるか分からない、
- 今は落ち着いていても次の瞬間どうなるか分からない。
この「張り詰めた感じ」が、
気づかないうちにココロを消耗させていきます。
- 朝の支度
- 学校との連絡
- 兄弟げんか
- 宿題
- 寝かしつけ…
どれも日常の一部だけれど、
全部に「対応力」を求められる毎日です。
- 「ちゃんとしなきゃ」
- 「なんとか乗り切らなきゃ」
そう思い続けてきたことで、
イライラや疲れが積もってしまった経験があるはずです。
それでも、
「ちゃんと母親をやれていない」と自分を責めてしまう。
その責任感が、
さらに苦しさを深くしている構造があります。
実はこれ、
ココロのエネルギーが底をついているサインであることが多いんです。
だからこそ、今こそ「がんばり方」を見直すタイミング。
完璧じゃなくてもいい。
「全部を一人で背負わなくていい」という発想が、
親子の関係を楽にしてくれることもあります。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「毎日、なんだかしんどそう…」
そんなADHD傾向のある子の様子が気になっていたら、「疲れやすさ」の原因と、家庭でできる関わり方から見つめてみませんか。
👉 ADHDの子の「しんどそう」の理由と、できることを整理する
-

-
参考ADHDの子が「疲れやすい」のはなぜ?──「毎日しんどそう…」と悩む母が知っておきたい原因と関わり方【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「また朝から怒ってしまった」 そうやって落ち込む日が、 あなたはどれくらい続いたでし ...
続きを見る
「実は自分もADHD傾向かも」と思ったら
子どもの行動に向き合う中で、
「これ、自分にも当てはまる気がする」
そんなふうに感じたことはありませんか?
- 忘れっぽい
- 集中力が続かない
- 気持ちの切り替えがうまくいかない。
そんな「自分の困りごと」を、
これまでずっと我慢してきた方も多いはずです。
「私って、ただダメな人間なのかな」
そうやって自分を責め続けてきた背景があります。
でも実際には、
ADHD的な特性を持ちながら、
ずっと努力して生きてきた。
それに気づいたとき、
「だからしんどかったんだ」と深く腑に落ちることがあります。
“私にも必要だった安心”を、今から取り戻せる
「子どもにイライラするのは、私のせい…?」
そう思い詰めてきたあなたへ。
あなたが「安心して関われる母」に変わっていくことで、
この子も、自分らしく育っていけます。
『なんでできないの?』と責める毎日から、
『わかってあげられる私』へ──
このサポートは、あなた自身のココロのゆとりも一緒に育てていく3週間です。
大人になって初めて、
自分自身の「扱いづらさ」に名前がつくことは、
回復の第一歩でもあるんです。
子どもの支援と同じくらい、
自分自身をゆるめていく視点も、
これからは大切になっていきます。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「もしかして私にもADHDの特性があるのかも…?」
そんな気づきや違和感を覚えた方へ。
子どもとの関わりの中で、自分自身の特性と向き合う母親の視点から描いた記事です。
👉 子どもへのイライラの裏にあった、「大人の私」のADHD気質
-

-
参考発達障害・ADHDが「大人の私にもあるかも」──子どもに怒るたび、よぎっていた違和感【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「どうしてこんなに怒ってしまうんだろう」 「自分の子どもなのに、感情が抑えられないこ ...
続きを見る
「ちゃんとしなきゃ」の毎日から、自分をゆるめていく
- 「この子のために、もっとちゃんとしなきゃ」
- 「母親なんだから、私が頑張らなきゃ」
そう思い続けてきたことで、
「本当の自分」をどこかに置き去りにしてきた方も多いです。
でも、
いつも完璧な母親でいようとすると、
ココロもカラダも、どこかで折れてしまうんですよね。
大切なのは、
「疲れてる」とちゃんと認めてあげること。
- 弱音を吐いてもいい
- 頼ってもいい
- 泣いてもいい
「ちゃんとしなきゃ」よりも、
「今日はここまででよし」にしてあげる。
そんな小さなゆるみの積み重ねが、
子どもにも安心を届けてくれます。
そしてそのゆるみの中に、
「私も、もう一度やり直せるかもしれない」
そんな希望が、ふっと差し込んでくる瞬間が訪れることもあります。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「どうしてこんなに疲れやすいんだろう…」
そんな悩みを抱えている方へ。
発達障害特有の「見えにくい疲れ」の原因と、少しずつラクになるための実践的な対策をご紹介しています。
-

-
参考発達障害の方のココロやカラダが疲れやすい5つの原因とは|心身が軽くなる対策法
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 毎日の生活の中で、「なぜ私はこんなにも疲れやすいのだろう?」と感じることはありません ...
続きを見る
ADHDのきょうだいが感じやすい「孤立感」とは?
気づけば、
「ごめんね」と言うばかりになっていました。
- 静かにしてくれてありがとう
- ひとりで頑張ってくれてありがとう
でも、
そんな言葉すら、
ちゃんと伝えられていなかったのです。
ADHDのきょうだいがいる子どもは、
親の視線が自分に向いていない感覚を、
早い段階で察知してしまうことがあります。
- 「わがままを言ってはいけない」
- 「迷惑をかけないようにしなきゃ」──
そんなふうに、
「いい子」を続けてきた子どもほど、
ココロの中に寂しさを抱えやすくなるんですよね。
だけどそれは、
放っていたわけじゃない。
ただ毎日、
目の前の困りごとに追われすぎて、
気づく余裕がなかっただけなんです。
もし、
「この子のこと、見えてなかったかも」と思ったとしたら、
そこからやり直せます。
「ありがとう」よりも
「気づけなくてごめんね」。
そのひとことから、
きょうだいとの関係は、少しずつほぐれていきます。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「次男の笑顔が減ってきた気がする…」
そんな不安を感じた方へ。
ADHDのある兄弟とそうでない兄弟の孤立感に早く気づき、両方の子に安心を届けるための関わり方を具体的にまとめています。
-

-
参考ADHDの兄弟に起きやすい孤立感──母親が知るべきサインと関わり方【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 長男のADHDに合わせて 朝から夜まで走り抜ける。 支度 連絡帳 宿題 明日の準備 ...
続きを見る
子どもとのやりとりがうまくいかない日が続くと、
- 「性格が合わないだけなのかな」と自分を責めたり、
- 子どものせいにしてしまいそうになる
ことがありますよね。
ADHDのある子の場合、その違和感には理由があります。
次のセクションは、
そのADHDの脳とココロの動きの正体と暮らしを軽くするヒントをお伝えします。
ADHDと「性格の違い」を誤解していた私が知った本当の理由
ADHDのある子との衝突を
「性格の不一致」だと受け止めていた時期は、
あなたは毎日が消耗戦でした。
実際には、
ADHDの脳の特性が行動や反応の背景にあります。
忘れ物が多いのはだらしなさではなく、
ワーキングメモリの容量の問題。
反発や言い返しは
衝動の制御が難しいために起こります。
この背景を知ると、
叱るしかなかった場面に別の選択肢が見えてきます。
- 行動の前に短い合図を入れる
- 選択肢を減らして迷いを減らす
- できた瞬間を逃さず言葉にする
ADHDを理解すると、
親子関係は「性格が合わない関係」から
「特性に合った関わり」へ変わります。
疲れを減らしながら、
一緒に笑える時間を増やすことができます。
ADHDの特性を理解すると、
どうしてこんなにも疲れやすいのかも見えてきます。
次のキャプションは、
ADHDを含む発達障害のある人が日常で消耗してしまう理由と、
その改善のヒントを整理します。
発達障害の人が疲れやすい5つの原因と生活改善のヒント
ADHDや自閉スペクトラム症など、
発達障害のある人は
日常の中で多くのエネルギーを消費しています。
その疲れやすさには理由があります。
- 感覚過敏による刺激の過多
- 注意を切り替えるときの負荷
- 社会的やりとりでの緊張
- 自己管理や時間管理への継続的努力
- 小さな失敗の積み重ねによる精神的消耗
改善のためには
- 「減らす」
- 「区切る」
- 「任せる」
を意識します。
- 刺激を避ける環境を整える、
- タスクを小さく分ける、
- 得意な人や道具に任せる
──こうした工夫がADHDのある暮らしの負担を減らします。
疲れを減らすことで、
親も子も安心して日々を過ごせる時間が増えていきます。
ADHDの原因とその背景を整理したいとき
「私のせいなのかな」
──そう問い続けてきた時間が、
ココロの中に静かに積もっていました。
- 妊娠中の生活
- 怒ってしまった日のこと
思い出すたびに、
どこかで「この子に影響してしまったのでは?」と
感じてきましたよね。
ポイント
でも実際のところ、
ADHDには「これが原因」と言い切れるものはありません。
- 妊娠中の体調
- 脳の発達
- 遺伝的傾向
- 家庭での関わり方など
複数の要因が重なって現れると言われています。
ここでは、
「何が悪かったのか」ではなく、
「どんな背景があるのか」に目を向けて、
自分を責めてきた気持ちごと、
少しずつほどいていけるような視点をお届けします。
妊娠中の影響はある?──不安を整理する知識
ADHDと聞いたとき、
真っ先に浮かんだのは「妊娠中のこと」です。
- 仕事のストレス
- 栄養の偏り
- 薬
- 睡眠不足──。
何かひとつでも心当たりがあると、
「私のせい」と思い込んでしまいますよね。
でも実際には、
ADHDの発症を
「妊娠中の行動だけ」で説明することはできない
という見方が医学的に言えます。
医学的にも、
胎児期の環境は多くの影響を受けますが、
それだけで発達特性が決まるわけではない
のです。
だからこそ、
「あのときのことを悔やんでいる自分」がいたら、
それだけ真剣に、この子と向き合ってきた証なんですよね。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「妊娠中のストレスや体調不良が、この子のADHDの原因だったのかも…」
そんな自責の思いを抱えながら、二人目をためらっている方に向けた安心の視点整理コンテンツをご用意しています。
👉 「妊娠中の影響かも」と悩んだあなたへ──自責から「安心して向き合える母」に変わっていくために
-

-
参考ADHDの原因は妊娠中の過ごし方?──二人目を望むたびココロの奥で引っかかっていたこと【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 何度言っても、またすぐに忘れてしまう。 感情のスイッチが入ると、手がつけられない。 ...
続きを見る
親からの遺伝の可能性を知っておく
「この子、自分にそっくりだな」
──そう感じた瞬間、
胸がつまるような感覚になったのではないですか?
- 忘れっぽさ
- 衝動的な言動
- 集中力の波
もしや自分も…と気づいたとき、
「やっぱり遺伝させてしまったのかな」と感じてしまうこともあるはずです。
確かに、
ADHDは遺伝的な影響を受けやすい特性とされています。
でもそれは、
「あなたのせい」ということではありません。
似ているからこそ、気づいてあげられる関係がある
ということでもあるんですよね。
「私も同じだった」と感じたことで、
この子の
- 「わかりづらさ」
- 「苦しさ」
に、より深く寄り添えるようになったと感じることができます。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「この子のADHD、もしかして私のせい?」
そんなふうに自分を責めてしまう母親のために、「遺伝」にまつわる不安をやさしく整理する記事をご用意しています。
👉 ADHDと遺伝の関係に悩んだとき、ココロが軽くなる読みもの
-

-
参考ADHDの原因が遺伝だと聞いて「やっぱり私のせい?」と感じたときに読む話【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 最近、 わが子のADHDの特徴が強くなってきた気がして、 不安が増していた。 宿題の ...
続きを見る
育て方や家庭環境が影響しているの?
「もっとちゃんと関わっていたら、こうはならなかったのかな」
そうやって、
ずっと自分の育て方を責め続けてきましたよね。
たしかに、
ADHDの子どもは
家庭の中で不安を感じたり
叱責が続いたりすると
特性が強く出やすくなる傾向があります。
でもそれは、
「育て方が原因でADHDになった」という意味ではありません。
ADHDは脳の神経機能の特性であり、
愛情の有無やしつけの方法で「作られるもの」ではない
のです。
うまく関われなかった日があったとしても、
それは「ダメだった証拠」ではなく、
余裕がなかっただけ。
そう気づいたとき、親子の関係は少しずつほどけていきます。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「育て方のせい?」と悩んできたあなたへ。
「ADHDと家庭環境の関係」を、責める気持ちをほどきながら整理できる内容です。
👉 「私のせいかも…」と思い詰めていた母親が、関係を整えるきっかけを見つけた話
-

-
参考ADHDの原因は「家庭環境」なの?──育て方を責め続けてきた私が「関係の整理」で見えてきたこと【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 ADHDの子どもが 何度言っても忘れ物が治らなくて、 「ちゃんとしなさい」ってまた言 ...
続きを見る
子どもの様子を見ながら
「これって私にも似ている…」と感じる瞬間がありますよね。
ADHDの診断や特徴を知るほど、
自分の過去や日常と重なる部分が見えてくることがあります。
次のセクションでは、
母親からの遺伝がADHDにどのくらい影響するのか、
そして気づかれにくい「隠れADHD」についてお話しします。
母親の遺伝がADHDに影響する確率と隠れADHDの存在
ADHDは遺伝的要素の影響が大きく、
親のどちらかにADHDの特性がある場合、
子どもも受け継ぐ確率が高まります。
特に母親がADHDの場合、
- 家事や時間の使い方、
- 感情のやり取りのパターン
も似やすく、家庭全体のリズムに影響します。
一方で、
自分がADHDだと気づかないまま大人になっている
「隠れADHD」もたくさんいます。
忘れやすさや段取りの苦手さを
- 「性格」
- 「忙しさ」
で片づけてきた結果、
子育ての中で初めて自分の特性に向き合う人もいます。
この背景を知ることで、
自分を責めるよりも
「親子でADHDを理解し、暮らしを整える」方向に力を使えるようになります。
ADHDは遺伝しても、
関わり方と環境の工夫で日常は大きく変えられます。
今からでも親子一緒に、
安心できる時間を増やしていくことは十分に可能です。
「『なんでできないの?』と責める毎日から『わかってあげられる私』へ」

「怒りたくないのに、怒ってしまう」
何度そう思ってきたか、わからないですよね。
叱ったあと、
部屋の隅で小さくなっている子どもの背中を見て、
自分のほうが傷ついた気がして…
そのたびに後悔ばかりが積み重なっていく。
でも、
それはあなたが「母親として失敗している」からじゃありません。
誰よりも、
この子とちゃんと向き合おうとしてきた証拠です。
ここでは、
「もう限界かも…」と感じてしまったあなたに、
「わかり合える関係」を取り戻すための小さな一歩を一緒に探していきます。
「母としての限界」を感じたあなたへ
毎日気を張って、
怒らないように言い方を工夫して、
それでも反応されずにまたイライラしてしまう。
夜になると、
「今日もダメだった」って、
自分を責めながら眠りについていたりしませんか。
このループ、
もう何年も続いてる──
そんな気がして、
ココロが折れそうになるんですよね。
でもね、
それって
あなたがずっと「がんばり続けてきた証」です。
限界を感じて当然の状態だったはずです。
怒るのをやめたいのに止められないのは、
感情の問題じゃなく、
「関係性の疲弊」があるからなんです。
あなたが悪いんじゃない。
責めるたびに傷ついていた、
その気持ちをずっとひとりで抱えてきたんです。
関連記事|さらに詳しく知りたい方へ
「ADHDの子に、どう関わればいいのかわからない…」
そんな戸惑いや自己嫌悪に苦しんできた方へ。
「怒らない子育て」ではなく、「安心して関われる関係」を取り戻すためのヒントをまとめた体験ストーリーです。
👉 叱ってばかりいた私が、「関われる母」に変わっていくまでの3週間
-

-
参考ADHDの子どもに怒りたくないのに怒ってしまう──そんな私が「関われる母」になれた理由【小児神経科医監修】
子育て・夫婦・わたし自身——悩みに寄り添う5つのサポート ※ 気になる画像をクリックすると詳細ページに移動します。 「また怒ってしまった」 子どもが寝たあと、 何度もそうつぶやいてきました。 ADHD ...
続きを見る
この子との毎日に、もう一度「信じられる関係」を
- 言い返される
- 無視される
- 癇癪を起こされる──
何気ないやりとりで、ココロがズタズタになる日々。
- 「なんでこんなことになるの?」
- 「私の育て方が悪かったの?」
ずっと、そう問い続けてきたはずです。
でも本当は、もう一度、この子を信じたいって願ってきたんですよね。
あなたの中には、
- 「この子とちゃんと向き合っていきたい」
- 「また笑い合える関係を築きたい」
そんな願いが、今もずっと息をしてるはずです。
関係は壊れていません。
ただ、「安心して関われる形」を失っていただけ。
信じたくて、でも不安で──
そうやって揺れながらも、
ずっとそばにいてくれたあなたの存在は、
この子にとっての「土台」になっているはずです。
3週間で「安心して関われる母」へ──サポートプログラムのご案内
- 試行錯誤を繰り返しても、
- 本やネットを読み漁っても、
どうしても変わらなかったのは、
「やり方」の問題ではなく、
「関係の安心感」が足りていなかったからです。
子どもを理解したいのに、
- 余裕がなくて責めてしまう。
- 信じたいのに、不安が邪魔をする。
──それでも、もう一度「つながり直したい」と願っているあなたへ。
「怒ってしまう私」を卒業して、「安心して関われる母」になるために
まずは、あなた自身が安心できる場所をつくること。
そこからすべてが変わっていきます。
- 「なんでこんなに怒ってばかりなんだろう」
- 「ちゃんと育てなきゃ」
と思うほど、
子どものADHD特性に振り回されて、
気がつけばまた声を荒げている。
そんな毎日に、疲れ切っていませんか?
『なんでできないの?』と責める毎日から、
『わかってあげられる私』へ──3週間集中再安心サポートは、
診断や支援機関よりも先に、
「母親自身の安心」を整えることを重視した、
家庭向けの心理サポートです。
このサポートでは、
- ADHDの特性を正しく理解し、
- 「怒らずに伝わる関わり方」を身につけ、
- 母親自身が「責めない自分」を取り戻す
という3つのステップを、
週ごとにゆっくり丁寧に進めていきます。
すると、「ちゃんとさせなきゃ」から、
「この子なりの歩みに寄り添えばいいんだ」へと、
自然に関わり方が変わっていきます。
不安で張りつめていた毎日に、
すこしずつ「余白」が戻ってくるはずです。
子どもの変化を願うなら、
まずはお母さんのココロを安心で満たすこと。
『なんでできないの?』と責める毎日から、
『わかってあげられる私』へ──この3週間は、そのための再出発の時間です。
『わかってあげたいのに、怒ってしまう…』そんなあなたへ
- 「もう怒りたくない」
- 「でも、どうすればいいかわからない」
そんな葛藤の中でがんばってきたあなたへ。
「この子らしさ」にちゃんと寄り添える関係を、3週間で取り戻す。
このサポートは、母としての自信と安心を“自分の中に取り戻す”時間です。
- ADHD・発達グレーの子の特性に合わせた「関わり方」の再構築
- 母としての怒り・疲れ・不安を軽くする感情ケア
- 「この子ともう一度、わかり合いたい」あなたの願いを支える3週間
あなたが変わると、関係も変わります。
安心して向き合える毎日を、ここから始めてみませんか?
まとめ|「この子を信じたい」気持ちだけは、あなたの中で消えてなかったはずです
- 怒らないって決めたのに、
- またイライラしてしまった。
- 責めるつもりなんてなかったのに、言いすぎてしまった
そんな日々を何度も繰り返してきて、
自分を嫌いになってしまいそうな夜もあったはずです。
でも、
だからこそ気づいてほしいんです。
あなたはずっと、
「この子と向き合おうとしてきた」ということに。
- どう関わればよかったのか、
- 何が正解だったのか、
ずっと探し続けてきたんですよね。
うまく言えないけど、
その根底にはいつも、
「この子を信じたい」という気持ちが生きていました。
それが、
あなたが母として「あきらめてこなかった」証です。
この記事でお伝えした、大切な5つの視点を振り返ります。
見出し(全角15文字)
- ADHDの特性は「性格」ではなく、脳の発達と関係している
- 怒ってしまうのは、関係が壊れたからではなく、「疲弊」が続いていただけ
- 叱ったあとに苦しくなるのは、「ちゃんと向き合いたい」という願いがあるから
- 自分を責めるより、「安心して向き合える関係」を育てることが大切
- 母であるあなたの「ココロの土台」を整えることで、関係の再構築が始まる
ここから、何を変えていけるか。
「『なんでできないの?』と責める毎日から、
『わかってあげられる私』へ──3週間集中再安心サポート」は、
「叱っても変わらない」子どものADHD特性を理解し、
怒りに支配されない関わり方を身につけるための心理サポートです。
この3週間であなたは、
「ちゃんとしなきゃ」という思い込みを手放しながら、
わかってあげたい気持ちが届く「接し方」を、
少しずつ取り戻していきます。
同時に、
お母さん自身のココロのケアも丁寧に進めていきます。
「また怒ってしまった」と責めるココロに、
「安心」の居場所を作ること。
それが、「『なんでできないの?』と責める毎日から、
『わかってあげられる私』へ──3週間集中再安心サポート」の本当のスタートです。
完璧じゃなくていい。
ここから、「安心して関われる母」として、
この子との毎日をもう一度始めていきませんか。
「子育てが、こんなに孤独になるなんて思わなかった」
「叱れば直ると思ってた」
でも、何度言っても変わらなくて──
私の関わり方が悪いの?
そんなふうに自分を責め続けてきた日々。
わかってあげたいのに、つい怒ってしまう。
その苦しさは、
「関わり方の知識がなかっただけ」。
「怒ってばかりの毎日から、“この子らしさ”に寄り添える私へ──3週間集中再安心サポート」は、
発達障害・グレーゾーンの特性理解と、
「お母さん自身のケア」からはじめる3週間。
もう責めなくていい。
怒りの奥にある「わかってほしい」が、ちゃんと届く関わり方を一緒に見つけていきます。
こんな方におすすめです
- 何度叱っても子どもの行動が変わらず疲れている
- 育てにくさに戸惑い、自分の限界を感じている
- 発達障害の可能性は気になるが、診断には踏み出せない
- 「どう関わればいいのか」誰にも聞けず悩んでいる
✅ 【銀行振込限定・特典付き】で受付中
🔸 本日 2月5日(木)23:59まで ご入金分まで
🔸 『あと1名様限定』
※銀行振込限定・先着順
ネットバンキングのご利用で、今すぐ開始することが可能です。
そして──
ADHDの子どもに向き合い続けてきたその時間、
あなたは「自分の人生」をどこかに置いてきていませんか?
《人生再統合プログラム(50万円)》は、
母として、精一杯やってきたあなたが、
「自分の時間・感情・夢」を取り戻すための3週間。
- 子ども優先の毎日に、ふと虚しさを感じてしまう
- 自分のことを後回しにしすぎて、ココロがカサカサになっている
- 「私はこの先、何がしたいんだろう…」と立ち止まる瞬間が増えてきた
今こそ、「母親」という役割の奥にある、
あなた自身の人生を取り戻すときです。
※《3週間集中再安心サポート》修了者限定
すでに診断済みの方も、そのまま詳細ページへ進めます。
あなたの心と体に合ったサポートを、今すぐ確認してみてください。